解説記事2021年02月01日 巻頭特集 令和3年度税制改正~コロナ禍後を見据えた企業活動の変革等に向けて~(2021年2月1日号・№868)
巻頭特集
令和3年度税制改正
~コロナ禍後を見据えた企業活動の変革等に向けて~
一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部 秋本潤一郞
令和3年度税制改正では、新型コロナウイルス感染症の下での経済活動を下支えする措置の他に、研究開発税制の改組・延長、デジタルトランスフォーメーション(DX)税制、カーボンニュートラル(CN)税制をはじめとしたコロナ禍後を見据えた税制措置が講じられる。本稿では、企業活動の変革を見据えた税制措置を主に取り上げる。なお、内容については、今後の法案の策定・審議により、変更が生じうる。併せて、全ては筆者個人の見解であり、所属組織を代表したものではないことにご留意いただきたい。
1 研究開発税制の改組・延長
(1)改正の背景
コロナ禍の下で、法人税額そのものが減少することが見込まれる中にあっても、将来のイノベーションの創出に向けて、企業が引き続き研究開発を行うインセンティブを維持・強化し、Society 5.0を実現することが重要課題である。
これを受けて、総額型については、一定の要件の下で法人税額の控除上限を25%から30%に引き上げるとともに、税額控除率についても研究開発投資の維持・強化に向けた見直しが行われた。また、クラウドを通じてサービスを提供するソフトウェアに関する研究開発投資を税額控除の対象に加える等、経済のデジタル化への対応を進める他、オープンイノベーション(OI)型の運用改善等も図られた。
以下では、研究開発税制を構成する3つの制度、すなわち、①試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)、②中小企業技術基盤強化税制、③特別試験研究に係る税額控除制度(OI型)における改正内容を解説する。
(2)総額型
今回改正では、まず控除上限(現行法人税額の25%)について要件付きで引き上げが行われた。すなわち、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、次の2つの要件を同時に満たす事業年度(研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限の特例を受ける事業年度を除く。)について、図表1の通り、法人税額の控除上限が25%から30%に引き上げられる。
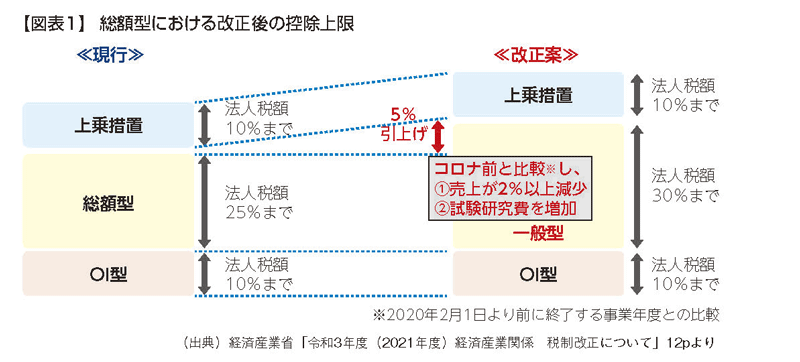
要件1 基準年度比売上金額減少割合(当期の売上金額が令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の売上金額に満たない場合のその満たない部分の金額のその最後に終了した事業年度の売上金額に対する割合)が2%以上
要件2 試験研究費の額が基準年度試験研究費の額(令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の試験研究費の額)を超過
この要件設定の背景としては、コロナ禍直前の事業年度に比べて売上高が減少したものの、研究開発投資に依然として積極的に取り組む企業を後押ししようとする政策的な意図があると見られる。
なお、試験研究費割合(所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額(当期の売上金額及び当期の開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の合計額をその各事業年度の数+1で除して計算した金額)に対する割合を指す。)が10%を超える場合における総額型の控除上限の上乗せ特例及び税額控除率の上乗せ特例措置について、令和4年度末まで2年間の延長が行われた。
次に、試験研究費を維持・拡大するインセンティブを強める観点から、控除率カーブ(増減試験研究費割合に基づき、控除率を決定する算式)について、図表2の通り見直しを行った上で、適用期限が令和4年度末まで2年間延長される。
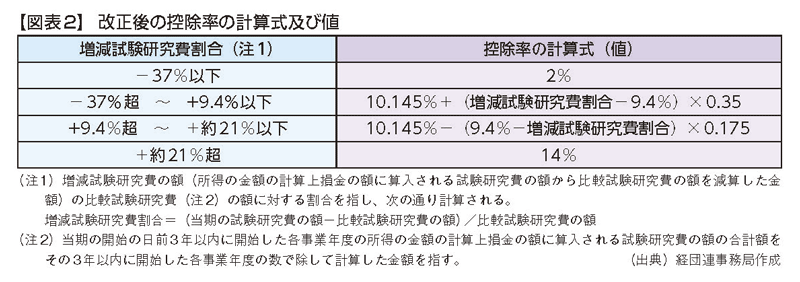
ここから分かる通り、控除率の上限は14%(原則は10%)で維持される一方で、その下限は現行の6%から2%(増減試験研究費割合が▲37%以下の場合)にまで引き下げられる。改正に係る議論の過程では、控除率の下限を0%にまで引き下げる案も浮上したが、本来事業年度に応じて変動の大きな試験研究費の性質に鑑みれば、かえって研究開発投資に対するディスインセンティブとなりかねないとの懸念からこの水準で決着した。
更に、増減試験研究費割合が0%の場合の控除率である8.5%は維持される。これに加えて、増減試験研究費割合が8%の点を境として、控除率カーブの傾きが0.175から0.3に変化していたが、改正により同割合が9.4%の点を屈折点として、傾きが0.35に変化する。新たな屈折点である9.4%は、第6次科学技術基本計画(対象年度は令和3年度.7年度で現在策定中)における民間試験研究費の目標と整合的な形で決定されたとみられる。この改正により、増減試験研究費割合が8%.12.9%の場合には控除率は現行よりも低下する一方で、同割合が12.9%超の場合には控除率が上昇することとなる。新旧の控除率カーブは、図表3の通りとなる。
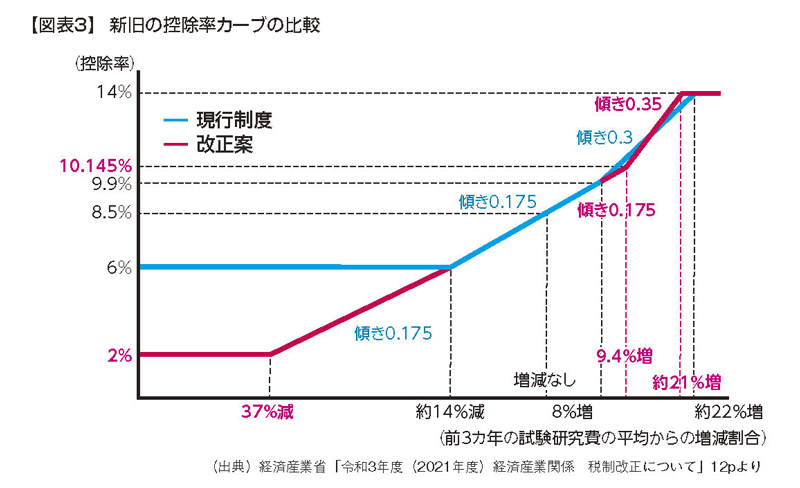
(3)中小企業技術基盤強化税制
本税制では、中小企業者(適用除外事業者を除く。)又は農業協同組合等は、上記総額型に代えて適用する場合に、その事業年度の所得に対する調整前法人税額の25%を上限として、試験研究費の額の12%相当額の税額控除が認められる。今回改正により、総額型といわば平仄を合わせる形で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準年度(令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度)比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ試験研究費の額が基準試験年度試験研究費の額を超える場合に、その事業年度の控除上限が5%引き上げられる。
なお、令和3年3月31日までの間、増減試験研究費割合が8%を超える場合は、税額控除割合を最大17%とし、税額控除の上限を10%上乗せする時限措置がある。今回改正により、①控除率カーブの屈折点を増減試験研究費割合が9.4%にした上で、控除率カーブの傾きを0.3から0.35とする見直し(上限は17%で変わらず)、②増減試験研究費割合が9.4%超の場合に税額控除上限に10%上乗せを行う措置に見直した上で、適用期限が令和4年度末まで延長される。加えて、試験研究費割合が10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費割合が10%を超える場合(増減試験研究費割合が9.4%超の場合の控除上限上乗せが適用される場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例(法人税額の10%上乗せ)の適用期限も令和4年度末まで2年間延長される。
これらは、図表4及び5の通り表される。
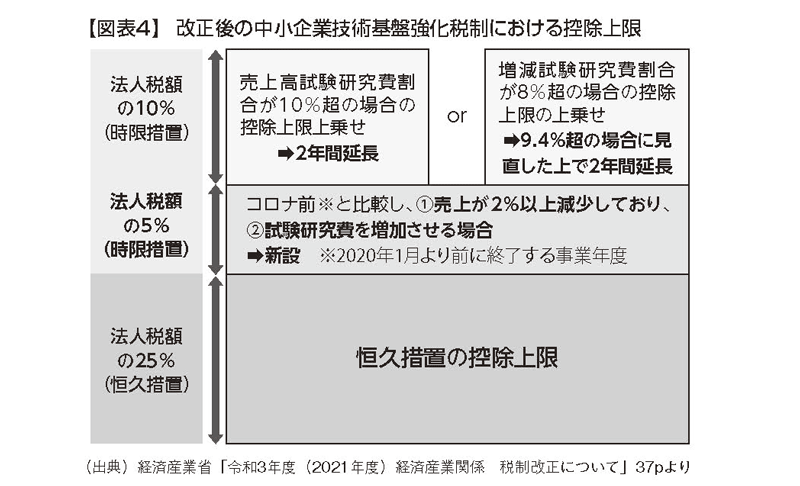
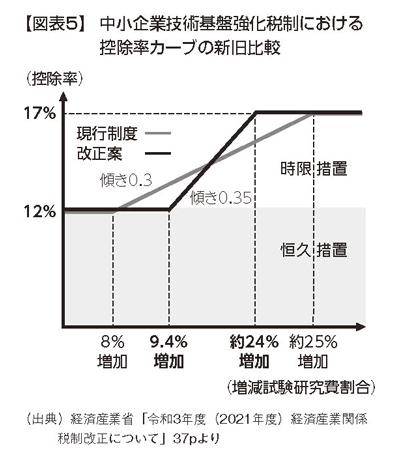
(4)特別試験研究に係る税額控除制度(オープンイノベーション(OI)型)
過度な監査手続きを回避することで過大な費用負担を排除する観点から、特別試験研究費税額控除制度ガイドライン(以下、ガイドライン)を改訂し、監査の方法を具体化することとなった。その際、人件費、原材料費及び経費、減価償却費それぞれを確認するためにどのような書類が必要かを明記する等の改訂が行われる見通しである。
また、相手方の確認手続きの合理化も行われる。現行制度では、共同研究の相手方の確認手続きと税理士・会計士等の第三者による監査とが一部重複しているため、まず企業が税理士等の第三者による監査を受け、共同研究の相手方は監査で作成された報告書を基に確認するという手続きを明確化するようにガイドラインが改訂される。以下がそのイメージとなる(図表6参照)。
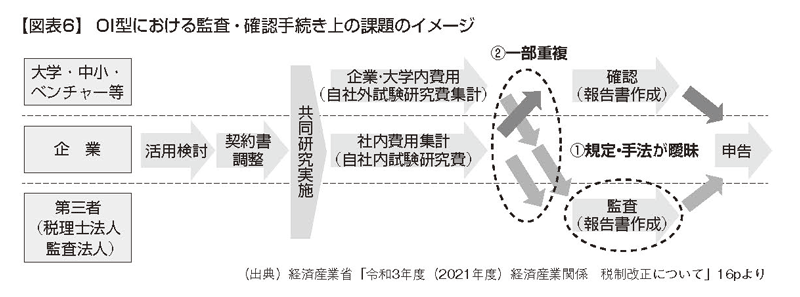
併せて、OI型の対象となる特別試験研究費の額に、国立研究開発法人の外部化法人との共同研究及び国立研究開発法人の外部化法人への委託研究に要する費用の額を加えて、その税額控除率を20%から25%に引き上げる。また、大企業と大学等との共同研究・委託研究について、契約時の試験研究費の総見込額が50万円超のものに限定される他、中小企業者等への委託研究について、「単なる外注」を対象から除外する見直しが行われる。
(5)試験研究費の対象の見直し(自社利用ソフトウェアに係る試験研究費の研究開発税制対象化等)
現行制度上は、自社利用ソフトウェアは、将来の収益獲得等が見込まれる場合には、資産計上しなければならず、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費の損金算入は認められていない(法基通7-3-15の3(2))。他方で、デジタル化の進展の下で、クラウド環境を通じて、ユーザーにサービス提供を行うビジネスモデルの普及に伴い、クラウドを通じてサービス提供を行うソフトウェアに関する研究開発費(現行制度では自社利用ソフトウェアに係る研究開発費と整理)についても、研究開発税制の対象とすることが改正時の大きな焦点となった。
結果として、試験研究費のうち、研究開発費として損金経理をした金額で非試験研究用資産(棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものを指す。)の取得価額に含まれるものを研究開発税制の対象とすることとなった。すなわち、非試験研究用資産の取得時に会計上の損金経理を行うのに合わせて税額控除も可能となる見直しである。これにより、クラウドを通じてサービス提供を行うソフトウェアに係る研究開発費についても、ソフトウェアの取得時にその取得価額に含まれるものが税額控除対象試験研究費に算入されることとなる。
なお、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費の支出時の即時損金算入は実現しなかった。減価償却に係る法人税法本則等の改正が必須となることがネックとなったとみられる。このため、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費が税務上は資産計上される取り扱いは変わらない。つまり、会計上は費用計上(「損金経理」)していたとしても、税務上は「固定資産」としての取り扱いは継続、ただし、その取得価額に含まれるものは研究開発税制の対象にすることを意味する。非試験研究用資産に係る税制上の取扱いの変更は大まかに以下の図表7の通り整理される。
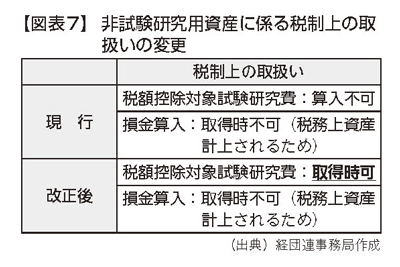
また、今回の見直しでは、固定資産に加え、上記の通り、事業供用の時に試験研究の用に供さない棚卸資産、繰延資産についても、見直しが行われる。現行では棚卸資産に含まれる試験研究費については売上原価計上時に、繰延資産についてはその減価償却費が税額控除対象となるが、いずれもその取得価額に損金経理した研究開発費が含まれる場合には、その取得価額が取得時に税額控除の対象となる。この結果、売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損が研究開発税制の対象となる試験研究費から除外されることとなった。併せて、取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産について、研究開発税制と特別償却等に関する制度との選択適用となる。こうした改正の背景には、研究開発税制は、既に行われた研究開発投資に事後的に税額控除を行うのではなく、あくまで将来の研究開発投資に対して、その実施時に税額控除という支援を与えることをより鮮明にしたいという政策意図があると見られる。
その一方で、研究開発用資産について、取得価額ではなく、その減価償却費を税額控除の対象に含めるという現行の取り扱いは維持される。関係企業の未償却残高が巨額であることを背景に改正は見送られた模様である。
また、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲の適正化を図る観点から、リバースエンジニアリング(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に該当しないもの)については、国際的な動向を踏まえ、対象から除外される。
なお、開発中の技術がその開発する者の業務改善に資するものであっても、その技術に係る試験研究が工学又は自然科学に関する試験研究(例えば、製造業の企業がAIによるプラントの自動運転を実現するために行うアルゴリズム等の研究開発等が該当。)に該当する時は、その試験研究に要する費用は研究開発税制の対象となること等が明確化される。
2 改正産業競争力強化法の下での3つの税制措置
コロナ禍の下での企業活動の落ち込みを回復軌道に戻し、再び諸外国との競争に勝ち筋を見出していくことが目下最大の課題である。その際のキーワードとなるのが、「事業構造の転換」、「デジタルトランスフォーメーション」、「カーボンニュートラル」である。以下では、改正産業競争力強化法(2021年1月執筆時点では本通常国会に提出予定)上のスキームにおいて講じられた3つの税制措置に焦点を当てて、その政策的な意図を含めて解説したい。
(1)業績のV字回復と事業構造の転換に向けた、欠損金の繰越控除制度の特例措置
① 特例措置創設の背景
コロナ禍の影響下にある期間に発生する巨額の欠損金を巡って、現行の繰越控除制度について、控除上限と繰越可能期間の緩和を求める声が令和3年度税制改正に関する議論の当初段階から強まっていた。
当該制度の下では、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入される。その控除上限について、大企業(中小法人等以外の法人)の各事業年度(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除く。)の場合は、その繰越控除前の所得の金額に100分の50を乗じた金額となる。なお、繰越欠損金がその事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度に生じたものから順次損金算入される。
しかしながら、平成23、27、28年度改正において、法人税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大の一環として、繰越期間が延長される一方で、控除上限が段階的に引き下げられてきた経緯がある。このため、控除上限の引き上げには、業績悪化に直面する企業の経営回復への側面支援という役割に加えて、いわゆる「内部留保」の積み増しにつながらない観点を踏まえつつ、将来に向けた事業再構築等の取り組みを後押しする役割が強く求められるようになった。その一方で、繰越可能期間の延長については、業種・業態によってはコロナ禍による業績下押し圧力がいつまで継続するか不透明感が強いことに伴い、事業再構築等に前向きではない企業への支援が適当なのかといった懸念から、早期に検討の俎上から外れた。
② 特例措置の内容
上述の背景の下、コロナ禍の厳しい経営環境の中で、赤字企業であっても、ポストコロナに向けた経営改革に果敢に挑み、業績のV字回復を果たした企業に対して、繰越欠損金の控除上限の引き上げ措置が創設された。
具体的には、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行日から同日以後1年を経過する日までの間に同法の事業適応計画(仮称)の認定を受けることが必要となる。その際の事業適応とは、経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして一定の基準に該当するものに限定される。事業所管大臣による計画認定に際して、企業はポストコロナに向けた取組(事業の再構築等)や、取組を進める上で必要となる投資計画(単純な維持・更新投資は対象外。)や、ROAを5%ポイント以上引き上げる等の目標を記載することが求められる見通しである。併せて、以下のいずれにも該当する事業年度が適用事業年度と位置付けられる。
イ 基準事業年度(特例対象欠損金額が生じた事業年度のうち、その開始の日が最も早い事業年度後の事業年度で所得の金額が生じた最初の事業年度を指す。)開始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。
ロ 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。
ハ 令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。
上記の適用事業年度において、特例対象欠損金額(原則として令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度において生じた青色欠損金額を指す。)がある場合には、同欠損金額について、欠損金の繰越控除前の所得の金額(その所得の金額の50%を超える部分については、累積投資残額に達するまでの金額に限る。)の範囲内で損金算入可能となる。ここでは、累積投資残額は、事業適応計画に従って行った投資額から既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50%を超えて損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額を指す。この結果、特例対象欠損金額が発生した後、黒字転換してから最長で5事業年度、最大で100%繰越控除可能となる。なお、業種・業態によっては、コロナ禍の影響が令和2年度開始日前に顕著となったことを勘案し、発生した欠損金額とコロナ禍との間に一定の指標に基づき相関関係が認められる等の場合には、令和2年2月1日から同年3月31日にまで終了する事業年度及び翌事業年度、すなわち令和元年度及び令和2年度の2事業年度も対象となる。
上述の特例措置は、図表8のイメージとなる。
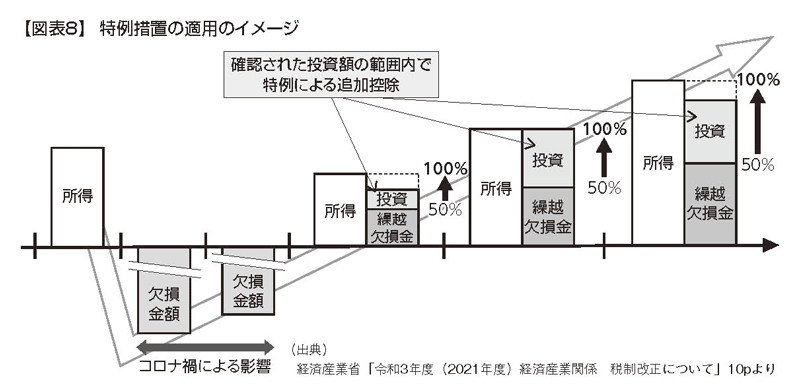
なお、事業適応計画(仮称)の申請から、控除の適用にいたるまでの手続きの流れは、図表9のような流れとなる。
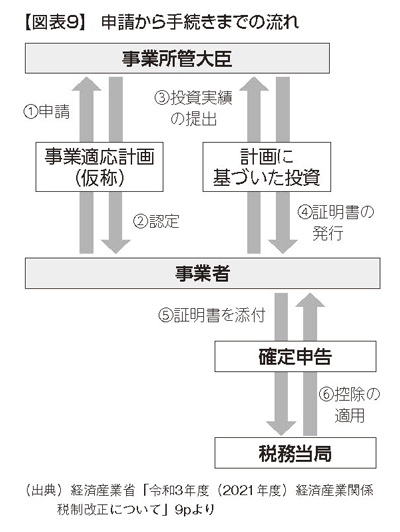
(2)デジタルトランスフォーメーション(DX)税制
デジタル技術を活用した企業変革を実現するためには、経営戦略・デジタル戦略の一体的な実施が不可欠である。このため、改正産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設し、部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(5%/3%)又は特別償却30%が令和4年度末を期限として新たに措置された。認定要件としては、他の法人等と「つながる」ことを企図してデータ連携・共有等に係る要件が設定される。なお、当該税制措置の対象となる投資額の下限は売上高比0.1%以上となり、投資額上限は300億円に設定されている(300億円を上回る投資は300億円まで)。加えて、税額の控除上限は、(3)と合わせて当期法人税額の20%までとされている。
上記をまとめると図表10の通りとなる。
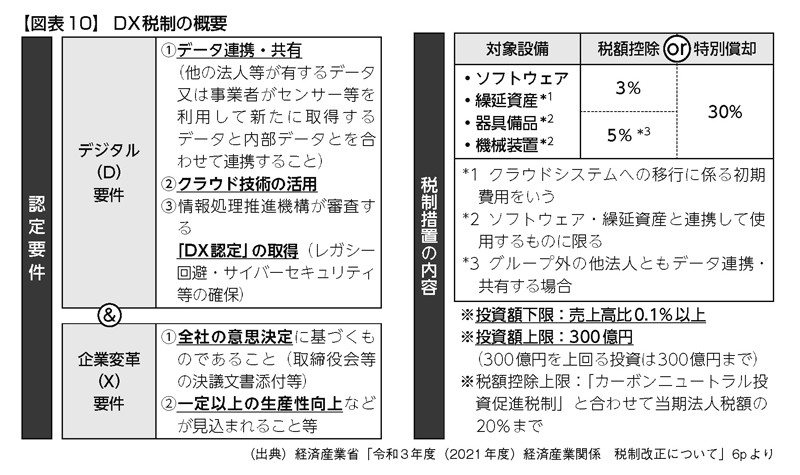
(3)カーボンニュートラル(CN)税制の新設
政府の掲げる、「2050年カーボンニュートラル」目標の実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠となる。このため、改正産業競争力強化法において、新たに計画認定制度を創設し、それに基づき、①大きな脱炭素化効果を持つ製品(化合物パワー半導体や燃料電池等)の生産設備、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除又は特別償却50%が令和5年度末を期限として新たに措置された。なお、措置対象となる投資額は500億円までとなることに加えて、控除税額は(2)のDX投資促進税制と合計で当期法人税額の20%までとなる。
上記をまとめると図表11の通りとなる。
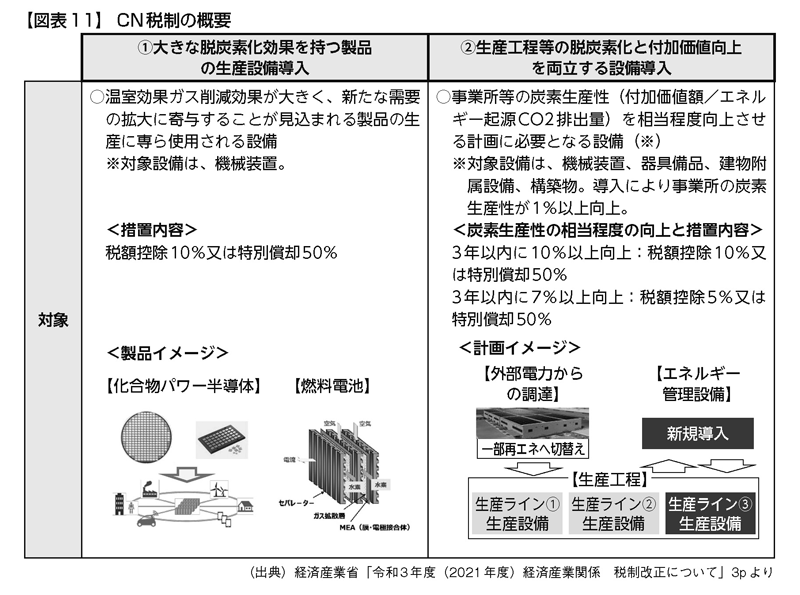
3 税務手続きの簡素化・デジタル化
コロナ禍を契機とした「新しい生活様式」の下での書面・押印・対面原則の抜本的な見直しの動きの中で、税務手続きデジタル化・簡素化にも大きな前進が見られた。
まず、押印規定について、国税・地方税ともに原則廃止が決定された。具体的には、国税について、税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについては、担保提供・物納手続関係や相続税・贈与税の特例に係る一部の例外書類を除き、令和3年4月1日以降廃止となる。また、地方税について、法令に根拠のない地方自治体独自の押印欄についても見直しが要請される。
次に、電子帳簿等保存制度についても、利用者である企業のニーズを踏まえた形で見直しが図られたことは画期的である。
1つ目に、電子帳簿保存制度について、現行では、真実性及び可視性の確保に係る諸要件を満たしつつ、計画的に事前承認を受けることが求められ、電子帳簿を導入したい企業にとっては高いハードルとなる。また、電子帳簿を利用していても、要件を充たさない場合は、電子データのまま保存することができず、紙を印刷して保存する必要がある。
今回の電子帳簿保存法の改正により、事前承認制度が廃止されることになり、国税関係帳簿書類についても、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次に掲げる要件に従って、それらの書類に係る電磁的記録の保存を行うことができるようになる。
イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備え付けを行うこと(説明書等の備え付け)
ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書等を備え付け、ディスプレイ画面等に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できること(モニター等の備え付け)
ハ 国税庁等の当該職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに応じること(ダウンロード要件)
今回の見直しの下で、電子帳簿保存の要件として、現行制度における訂正等履歴要件・相互関連性要件・検索要件は必要とされず、上記イ、ロ、ハのみで十分となる。
なお、現行制度よりも「緩やかな」基準で電子帳簿保存を認める一方、訂正等履歴要件や相互関連性要件等の追加的な要件を満たす場合には、いわば「優良帳簿」として過少申告加算税を5%軽減するというインセンティブも設けられた。
現行制度からの改正点は、前頁の図表12の通りとなる。
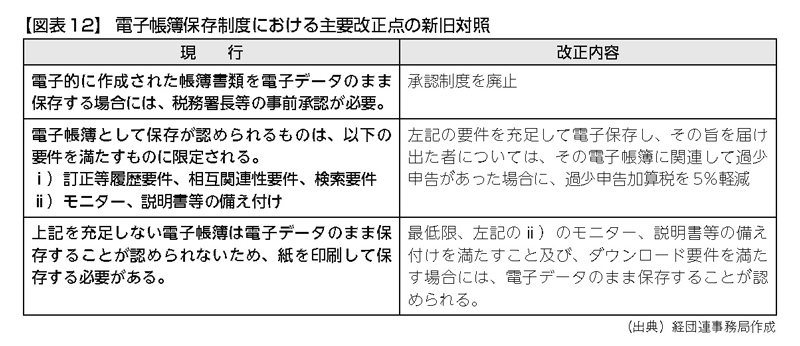
2つ目に、スキャナ保存制度については、現行の厳格な要件により制度を導入できない企業が多く存在することを受けて、事前規制型から事後の罰則強化型に移行する考えの下で、抜本的な改正が行われた。要件の緩和として、領収書等へのタイムスタンプ付与期間(現行3日以内)を記録事項の入力期間(最長約2か月以内)と同様とする他、適正事務処理要件(相互牽制、定期検査及び再発防止策の社内規則整備等)の廃止等が行われる。
現行制度からの改正点は、図表13の通りとなる。
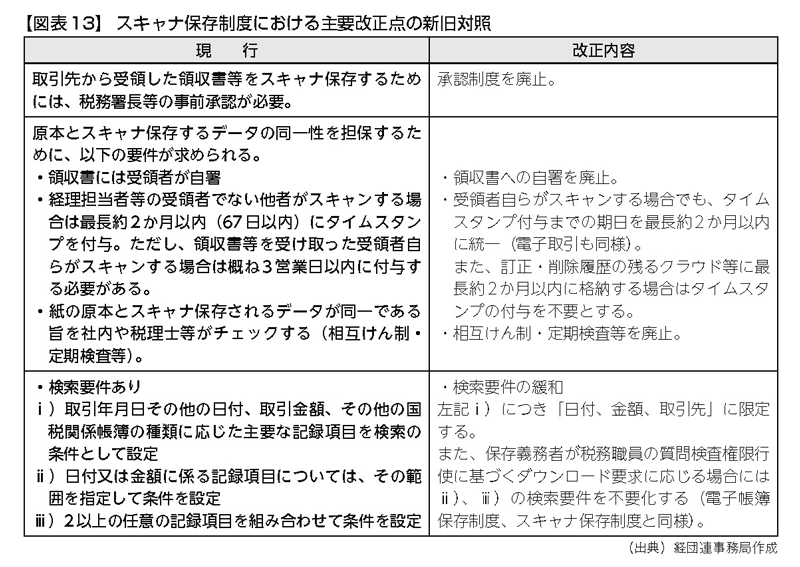
3つ目に、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度(電子取引データ保存制度)についても、検索要件の緩和等が行われる。すなわち、検索項目が①取引等の年月日、②取引金額、③取引先に限定される。これに加えて、判定期間における売上高が1,000万円以下である保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることとする場合は、検索要件の全てが不要となる。なお、ここでの判定期間とは、個人事業者について電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間を指し、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度を指す。
上述のスキャナ保存制度及び電子取引データ保存制度について、現行の要件が大幅に緩和される一方で、電子データに関連して改ざん等の不正が把握された際に罰則が強化される。具体的には、不正に関連して生じた申告漏れ等に課される重加算税の額は、通常課される重加算税の額に当該申告漏れ等に係る本税の10%に相当する金額を加算した額となる。
上記の図表14が制度の見直しの全体像である。
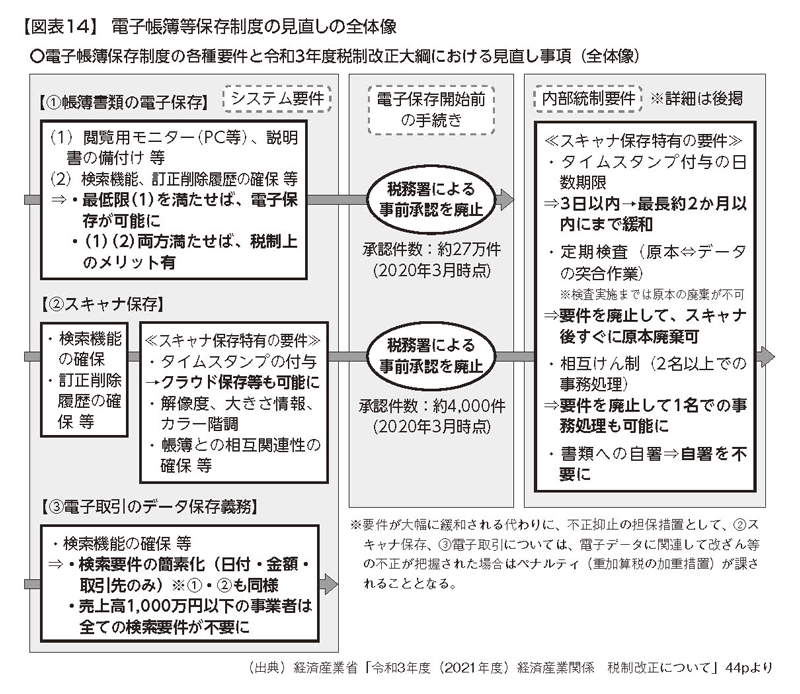
更に、地方税共通納税システムの対象税目の拡充も行われる。同システムは、eLTAXを活用して、納税者が全ての地方公共団体に対し、一度の手続きでまとめて電子納税を行うことを可能とする仕組みであり、令和元年10月より稼働している。全国に拠点を有する企業の利便性は高く、今回改正により、地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を追加し、eLTAXを通じて電子的に納付を行うことができるようになる。適用は、令和5年度以後の課税分となる。具体的な制度設計自体は、今後の課題であるものの、地方税共同機構「令和2年度 地方税における電子化の推進に関する検討会 とりまとめ」(令和2年11月)によれば、企業のニーズが高い固定資産税の「アップロード案」は、図表15のイメージとなると見られる。
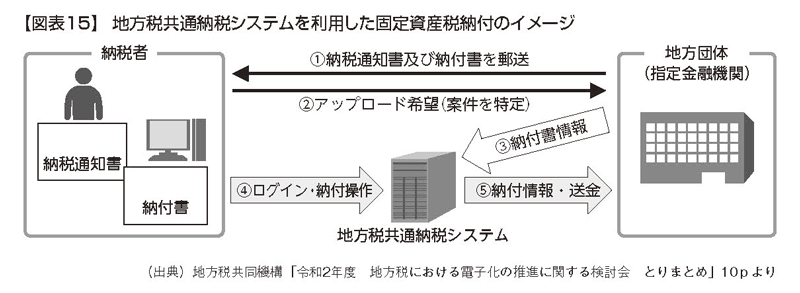
この他、個人住民税の特別徴収税額通知の電子化や、租税条約の届出書等の提出手続きの電子化も行われる。
4 自社株式等を対価とするM&Aを行う際の対象会社株主の株式譲渡損益の課税繰延制度の創設
(1)制度創設の背景
日本企業の収益性の向上の観点から、迅速かつ大規模なM&Aの必要性が高まっている。その際に、買収会社の手元資金や借入可能額を上回る大規模な事業再編を行いつつ、M&A以外の資金需要(設備投資・人材投資等)にも対応する上で、自社株式を対価とするM&Aが有用な手段となりえる。その際の被買収会社の株主に対する譲渡損益課税の繰延の可否が大きな課題とされてきた。
既に産業競争力強化法(平成30年5月23日公布、同年7月9日施行)の下で、自社株式対価M&Aの実施に際し、所定の要件を満たすことを条件に会社法、税法の特例措置が設けられている。上述の譲渡損益課税の繰延に関しては、「特別事業再編計画」(産業競争力強化法第25条)を作成し、主務大臣の認定を受けることを条件に令和3年3月31日までの時限措置として認められている。しかしながら、特別事業再編計画(図表16参照)については主務大臣の認定に加えて、認定要件も厳しく、機動性の求められるM&Aの実状にマッチせず、特例措置の適用が広がらないことが課題とされてきた。
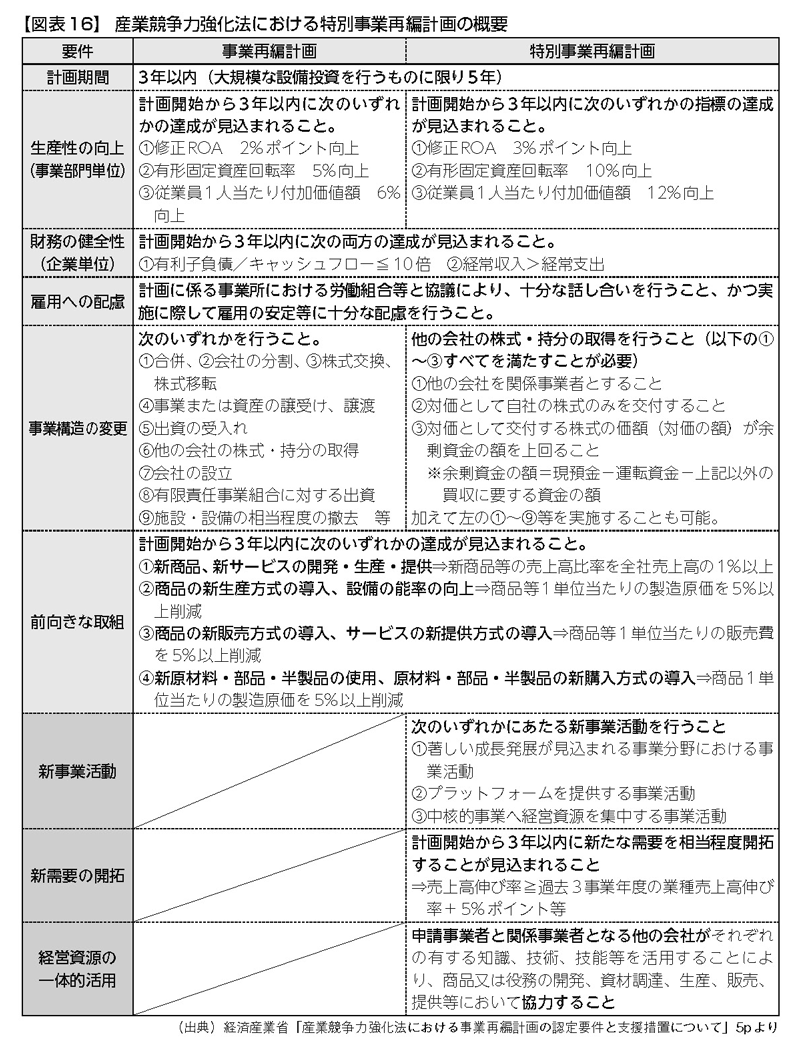
そこで、会社法の一部を改正する法律(令和元年12月11日公布)において、自社株式等(株式に加えて株式以外の金銭等を交付可能(会社法774条の3①五))を対価とするM&Aを規定化した「株式交付制度」を利用する場合の税制措置の創設に注目が集まった。当該制度は、「株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第774条の3第2項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること」とされている(会社法第2条32の2、令和3年3月1日施行)。ただし、既に子会社となっている株式会社の株式を追加で取得する場合や、外国会社の買収は対象外である。
令和2年度与党税制改正大綱では、「株式交付制度」を活用した場合の被買収会社の株主の株式譲渡損益の課税繰延の可否については結論が得られず、「会社法制の見直しを踏まえ、組織再編税制等も含めた理論的な整理を行ったうえで、必要な税制措置について検討する。」という取り扱いとなった。その背景として、現行の組織再編税制において、自社株式対価M&Aの被買収会社の株主の譲渡損益の課税繰延を整合的に説明することが困難であったと見られる。すなわち、現行の組織再編税制の代表的な類型である合併や株式交換は、強制的な株式譲渡が行われ、株主の投資が継続している場合に株主の譲渡損益の課税が繰り延べられると整理されている一方で、株式交付はあくまで任意取引であって譲渡の強制性がないことから、現行の組織再編税制の整理には当てはまらないと解釈される。これに加えて、M&Aに際し、自社株式と現金を混合することの是非も、現行の組織再編税制との関係で課題となった模様である。
(2)措置の内容
法人が、会社法の株式交付制度により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社(買収会社を指す。)の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を譲渡した時点ではなく売却時まで繰り延べる租税特別措置が恒久的に設けられる(所得税についても同様)。本措置の下では、産業競争力強化法の特別事業再編計画の事前認定は不要となり、より実効性のある制度となる。ただし、上述の通り株式交付制度の利用を前提としているため、既存子会社の株式の買い増しや、外国会社の買収の場合には本措置は適用されず、課税の繰延は行われないことに留意が必要である。図表17がそのイメージとなる。
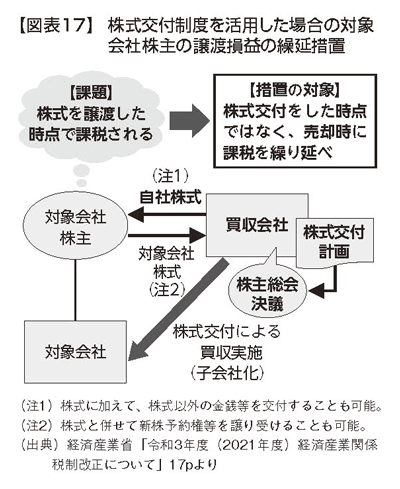
当該措置は、対価として交付を受けた資産の価額のうち、買収会社の株式の価額が80%以上である場合に限定され(対価となる現金等は、政策的な観点も踏まえ、総額の20%以下となることが決定。)、買収会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には、買収会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上を繰り延べることとする。
5 その他の主要改正項目
(1)自動車関係諸税
以下では、乗用自動車に係る税制に限定して、主要な見直し事項を解説する。令和3年度税制改正の議論では、コロナ禍という未曽有の状況下での家計の自動車需要の下支えに加えて、地球環境への負荷の小さい自動車の普及促進という課題への対応が焦点となった。主な改正事項は、次の2点である。
1点目に、自動車重量税に係るエコカー減税について、新しい2030年度燃費基準への切り替えを促す観点を踏まえつつ、減免税対象割合が現行水準とほぼ同様となるように、前頁の図表18の改正が行われる。
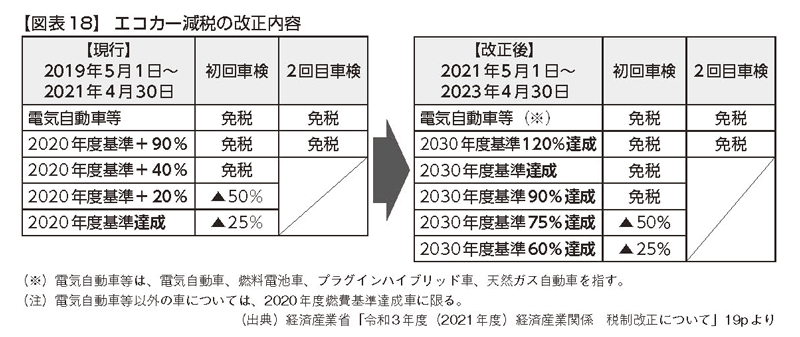
2点目に、自家乗用車に係る自動車税・軽自動車税の環境性能割についても、新燃費基準への切り替えを図りつつ課税の軽減対象割合が現行と同様の約7割となる基準を維持する形で改正が行われる。また、非課税対象割合が現行水準と同じ約5割となる基準も維持される。
更に、コロナ禍への対応の一環である、環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)は、既に令和3年3月末まで延長されているが、令和3年12月末までの9か月間の再延長が行われる。
この他、クリーンディーゼル車に係るエコカー減税、環境性能割については、燃費性能に応じた減税措置に変更される等の見直しが行われる。
(2)土地に係る固定資産税等の負担軽減
次回の固定資産税評価替えのベースとなる令和2年1月1日の公示地価とコロナ禍を受けた実勢価格が乖離する中、令和3年度限りの措置として、商業地等、住宅用地、農地の区別なく、地価上昇により税額の上昇が見込まれる全ての土地について、令和3年度の課税標準額を令和2年度の額と同額にする措置が講じられた。また、地価下落により税額が減少する土地は、そのまま減額となる。現行の負担調整措置の仕組みは継続となる。今回はコロナ禍を受けての異例の措置となったが、令和4年度の負担水準のあり方に関する議論には注視が必要である。
(3)住宅ローン減税
コロナ禍における家計の住宅購入を下支えする観点から、現行の控除期間13年間の特例の適用期限を1年間延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、合計所得金額1,000万円以下の者については面積要件を現行の50平米以上から40平米以上へと引き下げる。なお、会計検査院は、超低金利環境が続く一方で、控除率が借入残高に対して1%に設定されていることで「逆ざや」が生じることを問題視しており、令和4年度税制改正では控除額や控除率のあり方の見直しに向けた議論が行われる見通しである。
6 令和4年度以降の税制改正に向けて
デジタルトランスフォーメーションの社会実装及び「2050年カーボンニュートラル」の達成という文脈において、各種税制措置が検討されることとなるだろう。前者については、既にDX税制(第2章で解説)が新設されたところだが、当該税制措置の活用状況等を踏まえつつ、更なる企業間のデータ連携や、事業変革をキーワードとした、有効な税制措置が検討の俎上に上ることが予想される。併せて、令和3年度末で適用期限を迎える、次の税制措置に係る検討にも注目が必要である。1つ目は、Society 5.0の実現の社会基盤となる5G(第5世代移動通信システム)投資促進税制である。当該税制措置は、「安全・安心な5G情報通信インフラの早期かつ集中的な整備を行うため」に令和2年度税制改正において新設された経緯があることを踏まえれば、関係インフラの整備状況に照らして、改廃も含めた見直しの方向性が注目される。2つ目は、オープンイノベーション促進税制である。当該税制は、企業とスタートアップ企業間のオープンイノベーションに係るインセンティブを提供している。更なるオープンイノベーションの裾野の拡大・深化に資する税制措置のあり方についても議論が行われることとなるだろう。
後者、すなわちカーボンニュートラルの推進という観点では、令和3年度税制改正で、CN税制(第2章で解説)という大きな「アメ」が新設された以上、令和4年度以降は「ムチ」に関連した措置に対する議論が俎上に上ることは避けがたいだろう。例えば、経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(令和2年12月25日)における一節を以下に引用する。
市場メカニズムを用いる経済的手法(カーボンプライシング等)は、産業の競争力強化やイノベーション、投資促進につながるよう、成長戦略に資するものについて、既存制度の強化や対象の拡充、更には新たな制度を含め、躊躇なく取り組む。検討に当たっては、環境省、経済産業省が連携して取り組むこととしており、成長戦略の趣旨に則った制度を設計しうるか、国際的な動向や我が国の事情、産業の国際競争力への影響等を踏まえた専門的・技術的な議論が必要である。
上記の「カーボンプライシング等」には、二酸化炭素の排出量取引(クレジット取引)はもちろんのこと、炭素税や国境調整措置も含まれる。同戦略では、炭素税に関しては、「企業の現預金を活用した投資を促すという今回の成長戦略の趣旨との関係や、排出抑制効果などの課題が存在している」と課題への言及に留まっている。他方で、国際的な議論の動向に目を転じると、欧州を中心に脱炭素社会の実現という大目標に向けた、国際調整措置をはじめとした「手法」についても注目が集まっている模様である。わが国経済界は、既にイノベーションを通じた脱炭素社会の早期実現に向けて、「チャレンジ・ゼロ」等の主体的な取り組みを進めているところであるが、国際的な議論の潮流を踏まえつつ、税制上の対応のあり方についても、今後の議論に注意を払うことが必要であろう。
なお、「2050年カーボンニュートラル」目標を巡っては、自動車関係諸税のあり方も焦点となりうる。令和3年度与党税制改正大綱の検討事項では、「『2050年カーボンニュートラル』目標の実現に積極的に貢献するものとするとともに、(中略)、受益と負担の関係も含め、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う」と記載されている。
現行のエコカー減税等の税制措置は、主に「燃費」、すなわち1リットルの燃料に対し、何キロメートル走行可能かを国際基準と比較し、減税幅等を区分している。今後の自動車関係政策の動向を慎重に見定める必要があるものの、仮に電気自動車への全面的な移行が中長期的に図られる場合に、現行の自動車関係諸税の枠組みのあり方に関する議論の推移を十分に注視する必要があろう。
この他、地方法人税関係では、全面小売自由化され、2022年に導管部門が法的分離するガス供給業において、現行の枠組みへの付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税の導入の是非が大きな焦点となるだろう。
なお、国際課税分野では、経済の電子化に係る課税上の課題への対応として、OECDのBEPS包摂的枠組において、第1の柱(利益配分)、第2の柱(ミニマム課税)について制度の青写真が昨年10月に公表された。既に同青写真へのパブリックコメントと公開市中協議が終えられたところであるが、依然として残る技術的課題や、各国経済界等から指摘された制度そのものの簡素化が積み残しの宿題となっている。今後は、2021年央の国際合意に向けた議論の進展に注目が集まるが、わが国としてはそれ以降の国内制度の見直しが大きな山場となるだろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















