解説記事2019年09月16日 最新判決研究 土地の相続税評価における「特別の事情」の存否(鑑定額と相続後売却価額の正否)(2019年9月16日号・№803)
最新判決研究
土地の相続税評価における「特別の事情」の存否(鑑定額と相続後売却価額の正否)
東京地裁平成30年10月30日判決(平成29年(行ウ)第482号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X1、X2及びX3(原告、以下「Xら」という。)は、Xらの父甲が平成24年2月17日死亡したことにより甲を相続(以下「本件相続」という。)した(甲の相続人には、Xらのほか訴外A及びBがいた。Xらと一括して以下「本件相続人ら」という。)。本件相続人らは、平成24年11月24日、本件相続につき遺産分割協議をし、本件相続に係る各相続税(以下「本件各相続税」という。)について、期限内申告及び修正申告(申告による取得財産価額の合計は9億2632万円余)をした。
これに対し、所轄税務署長は、平成27年2月24日、本件各相続税について、取得財産の価額を11億2203万円余とする各更正(以下「本件各更正」という。)及びそれに係る過少申告加算税の賦課決定をした。Xらは、本件各更正等を不服とし、前審手続を経て、国(被告)に対し、本件各更正等の取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)本件相続人らは、本件相続により、本件土地1(仮換地4,703㎡)、本件土地2(同6,605㎡)、本件土地3(同925㎡)、本件土地4(同7,507㎡)及び本件土地5(同3,293㎡)(以下「本件各土地」という。その位置関係は、別図のとおりである。)を取得した。
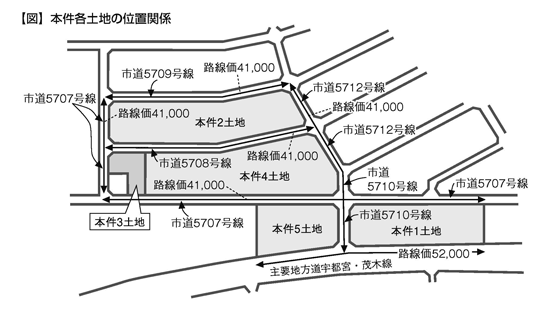
本件各土地の「従前地」の各土地は、宇都宮都市計画事業の土地区画整理事業(以下「本件区画整理事業」という。)の施行地内に所在していたが、従前地については、本件土地区画整理事業の施行者である独立行政法人都市再生機構が、遅くとも平成20年10月までに、「仮換地」の街区及び画地の場所の土地に仮換地の指定を行った。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、Xらが本件各土地を相続により取得した時における本件各土地の時価である。具体的には、当該時価を財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)によって評価することができるか、評価通達を適用上「特別の事情」が認められるか、にある。
2 国の主張
(1)相続税法22条に定める「時価」は、課税実務においては、評価通達の定める画一的な評価方法によって評価されている。これは、あらかじめ定められた評価方法によりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地から見て合理的であるという理由に基づくものである。そうすると、特に租税平等主義という観点からして、評価通達に定められた評価方法が合理的なものである限り、これが形式的に全ての納税者に適用されることによって租税負担の実質的な公平をも実現することができるものと解されるから、特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ評価通達に定める評価方法以外の方法によって評価を行うことは、納税者間の実質的な租税負担の公平を欠くことになるため、許されないというべきである。
(2)本件各土地を評価するに当たっては、評価通達14に定める路線価について個別評価をしたものであるところ、これは、土地区画整理事業の施行地区内にある宅地については、その土地区画整理事業の進行具合により評価する対象の宅地が異なるなど、個別的な対応を要することが多いことから、関東信越国税局においては、財産評価基準書上、一定の土地区画整理事業の施行地区内については「個別評価」と表示した上で、当該地区内に所在する土地について、評定を担当する税務署長が路線価及び倍率(以下「路線価等」という。)を個別に評定することとしているものであることに鑑みれば、個別評価地区内の路線価等は、時価を算出する上で適正なものであるといえる。
(3)関東信越国税局長が定めた本件各土地が面する各路線について個別評価した平成24年分の各路線価及び評価通達14-2に定める地区区分は、別図「本件各土地の位置関係」及び平成24年分個別評価回答書記載のとおりである。そして、本件相続の開始日における本件各土地の現況は雑種地であるところ、評価通達に基づき、価額を評価するに当たっては、その指定を受けた仮換地について、当該仮換地は既に市街地を形成している市街化区域に存することから、宅地比準方式によって、路線価方式により評価することとなる(評価通達24-2、82)。
その結果、本件各土地の評価額は、次のとおりとなる。
本件土地1 2億4962万円余
本件土地2 2億5581万円余
本件土地3 3657万円余
本件土地4 2億8333万円余
本件土地5 1億6980万円余
(4)Xらが主張する鑑定評価書における鑑定評価額は、本件各近隣土地の個別的要因を踏まえて、当該土地そのものの価額を求めたものであるから、不合理である。また、本件各土地の実際の売却価額については、本件相続開始から約9か月後(本件土地2)又は、約2年9か月後(本件土地4)であるが、時点修正を行うことなく単純に価額を比較したものであるから、合理的とは認められない。
3 Xらの主張
(1)相続税法上の土地評価においては、納税者間の公平や徴税の便宜のため、可能な限り、全国一律の統一的な評価基準を尊重すべきことには合理性があるが、地方税法における固定資産評価の方法等を相続税法上の土地評価の方法にそのままあてはめるのは無理がある。以上のことからすると、相続税評価に当たって、評価通達適用において、例外を認めるべき要件である「特別な事情」の該当性の判断においては、固定資産税評価ほどの厳格性が求められるわけではない。
(2)Xらは、本件各土地について、有限会社A不動産鑑定(A不動産鑑定士)に鑑定を依頼し、その鑑定に係る不動産鑑定評価書(以下「A鑑定書」という。)に係る評価額に基づき本件再修正申告書を提出している。また、本件近隣各土地について国有財産の売却が行われているところ、本件各近隣土地に係る鑑定評価額(本件近隣土地Aについては、平成22年2月1日時点、本件近隣土地BないしDについては、平成22年9月1日時点)は、1平方メートル当たり、おおむね、3万0900円から3万9000円の範囲に収まっており、A鑑定書とも整合的である。
一方で、本件各土地に係る処分行政庁の評価額は、おおむね、1平方メートル当たり3万7700円から5万3000円の範囲であり、本件各近隣土地の鑑定評価額と比較して著しく齟齬があり高額に過ぎる。
処分行政庁による本件各土地の評価過程は、各標準地の評価額を誤って高額にしてしまうと、個別路線価の評価額も高額となってしまうところ、標準地甲及び標準地乙の鑑定評価額は、1平方メートル当たり、それぞれ、4万4700円及び6万円であり、標準地乙と本件近隣土地Aは同街区にあるにもかかわらず、本件近隣土地Aの鑑定評価額である1平方メートル当たり3万7000円とは著しい差異があり、処分行政庁の個別路線価の評価額が誤っていることを推認させる。
(3)Xらは、本件相続の開始後に本件土地2の一部を売却したが、最も高い申込金額ですら1㎡当たり2万9385円であり、処分行政庁の評価額である1㎡当たり3万8727円を大きく下回っている。また、Xらは、平成26年11月8日、本件土地4を売却したが、1㎡当たりの金額は3万0249円であり、処分行政庁の評価額である1㎡当たり3万7741円を大きく下回っている。このことからしても、処分行政庁の評価額は過大である。
(4)A鑑定書は、本件土地1及び本件土地5につき、面積規模が大であることを理由に、それぞれ、30%及び25%の減額をしている。また、本件近隣土地A及び近隣土地Bの国有財産の売却に係る鑑定においても、面積が大であることによる減価(面大減価)が行われている。面積が大であることを理由とする減価は不動産鑑定において通常見られる合理的な処理である。
(5)以上のとおり、本件では、評価通達による評価方法を画一的に適用することによって、当該財産の「時価」を超える評価額となり、適正な時価を求めることができない結果となるから、財産評価通達による評価額が過大であるか、評価通達を当てはめる過程で所用の補正をするべきところこれをしていないなど、評価通達に規定する評価方法によるべきでない「特別な事情」が認められる。
三、判決要旨
請求棄却。
(1)相続税法22条は、同法3章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により算定する旨を定めるところ、この「時価」とは、相続開始時における当該財産の客観的交換価値をいうものと解される。
この点、相続税法は、特定の財産を除き、財産の評価方法について定めを置いていないが、これは、財産が多種多様であり、「時価」の評価が必ずしも容易なことではなく、評価に関与する者次第で個人差があり得るため、納税者間の公平の確保、納税者及び課税庁双方の便宜、経費の節減等の観点から、評価に関する全国一律の統一的な評価の方法を定めることを予定し、これにより財産の評価がされることを当然の前提とする趣旨であると解される。
上記相続税法の趣旨からすれば、評価対象の財産に適用される通達に規定する評価方法が適正な「時価」を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり、かつ、当該財産の相続税の課税価格がその評価方法に従って決定された場合には、相続財産の価額は、同通達に規定する評価方法を画一的に適用することによって、当該財産の「時価」を超える評価額となり、適正な時価を求めることができない結果となるなど、同通達に規定する評価方法によるべきではない特別な事情がない限り、同通達に規定する評価方法によって評価するのが相当であり、同通達に規定する評価方法に従い算定された評価額をもって「時価」であると事実上推認することができるものというべきである。
(2)評価通達において、市街地的形態を形成する地域にある宅地について、その評価を路線価方式によって行うものとする点については、路線価が、売買実例価格、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として、1年間の地価変動に対応するなどの評価上の安全性を考慮して公示価格の80%程度の水準を目処として定められていることに加え、路線価を基として、同通達15から20-5までの規定による一定の加算又は減算を行って評価するものと定められており、これらの評価の基準、根拠や計算の過程等に照らせば、かかる路線価方式については、一般的に合理的なものと認めるのが相当である。
また、土地区画整理事業の施行地区内にある宅地について、関東信越国税局においては、評価通達14に定める路線価について個別評価を行っているところ、土地区画整理事業の施行地区内にある宅地については、当該事業の進行具合により評価する対象となる宅地が異なるなど、個別的な対応をすることが多いため、個別評価を行う地区以外の路線価等の評定と同様に、①標準地を選定し、②不動産鑑定士等から当該標準地に係る不動産鑑定評価又は意見の提出を受け、③当該標準地の仲値(買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合における価格)を把握し、④当該標準地の仲値を基に、⑤路線価の案をあらかじめ評定し、納税義務者から相続税又は贈与税の申告に当たり、個別評価地区内の土地について個別評価申出書が提出された場合には、あらかじめ評定した路線価の案を基に、必要に応じて現地調査及び隣接地域とのバランスの検討等を行い、個別評価を回答するとされているのであり、個別評価における路線価の評定手順もそれ以外の路線価に係る評定手順とほとんど同様であることからすれば、土地区画整理事業施行中である宅地の評価方法として上記個別評価は合理的なものであると認めるのが相当である。したがって、本件土地の評価方法は合理的なものと認めるのが相当である。
(3)本件各土地につき、評価通達の定める評価方法により評価すると、前記国の主張のとおりとなる。
この点、Xらは、前記評価通達に基づく価額は、A鑑定書に係る評価額及び本件各近隣土地に係る鑑定内容に比較して高額であり、前記の「特別の事情」に該当すると主張する。
しかし、そもそも、前記で説示した納税者間の公平の確保、納税者及び課税庁双方の便宜、経費の節減等などの相続税法22条の趣旨からすれば、納税者が鑑定意見書等に基づいて財産の時価を算出した場合、仮に当該鑑定意見書等による評価方法が一般に是認できるもので、それにより算出された価格が財産の客観的な交換価値として評価し得るものであったとしても、当該算出価格が評価通達の定める評価方法に従って決定した評価額を下回っているだけでは、評価通達の定める評価方法に従って決定した価額が当然に時価を超えるものとして違法になることはないといえる。この点、Xらは、前記で説示した「特別の事情」につき、評価通達の定める評価方法によって本件各土地に係る評価額がA鑑定書及び本件各近隣土地に係る鑑定内容に比して高額であると述べるにすぎず、評価通達を正しく適用したとしても本件各土地の時価を適切に算定することができないことを基礎づける事情について何ら具体的に主張立証してない。
その点を措くとしても、A鑑定書においては、本件土地2ないし4の取引事例比較法を検討するに当たって、「地価調査価格を規準とした価格」の基準地として、「周辺の宅地化が比較的進んでいる地域」である宅地見込地を採用しているが、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての統一的規準とされる国土交通省が定める不動産鑑定評価基準でいう「見込地」とは、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域をいうところ、本件土地2ないし4はいずれも「一般住宅地区」にあるのであるから、上記基準値から本件土地2ないし4の価額を求めるに当たり、種別の差異に基づく補正が必要となると考えられる。この点、Xらは、「周辺の利用状態-17」として調整されていると主張するが、A鑑定書では、いかなる理由に基づいて上記割合の減算をしたのかについて合理的な説明がされていない。
また、A鑑定書では、本件土地1及び本件土地5につき、「規模大」であるとして、本件土地1につき30パーセント、本件土地5につき25パーセントの減価をしているが、土地評価に係る地域要因及び個別的要因の比較等について比準方法を示すものとして国土交通省が策定する「土地価格規準表」においては、画地条件に係る地積の過大による減価について、「対象地がその存する地域の標準的な画地との比較において広大地と判定される画地であっても、一体利用することが市場の需給関係等を勘案して合理的と認められる場合は、地積過大により減価を行う必要がないことに留意すべき」とされており、地積過大であることから当然に減算すべきとはされていないことからすれば、本件土地1及び本件土地5の評価においても、地積過大であることを理由に減算するのであれば、いかなる理由に基づいて上記割合の減算したのかについて合理的な説明がされるべきであるところ、A鑑定書では何ら説明がされていない。
以上のとおり、A鑑定書については上記問題点を指摘することができるから、A鑑定書における評価額が本件各土地の時価であるとはいえず、A鑑定書における評価額をもって、本件各土地について、評価通達に規定する評価方法によるべきではない「特別の事情」があるとは認められない。
また、本件各近隣土地の鑑定評価書における鑑定評価額は、本件各近隣土地そのものの価額を求めたものであるから、標準地乙の鑑定評価額と本件各近隣土地の鑑定評価額との間に差異があるとしても、その価格差のみをもって、本件土地について評価通達に規定する評価方法によるべきではない「特別の事情」があるとは認められない。
(4)Xらは、本件相続の開始後に、本件土地2の一部及び本件土地4を売却したが、いずれも1㎡当たりの金額が評価通達による評価額を大きく下回っていると主張する。
しかし、本件土地2の売買はX1及びX3がXらに係る本件各相続税を支払うことを理由としてなされたものであり、契約当事者の個別的な事情を踏まえて合意されたものであるといえるし、本件土地2の一部の売買契約が締結されたのは平成24年11月29日であり、本件土地4の売買契約が締結されたのは、平成26年11月8日であって、本件相続の開始日である平成24年2月17日から約9か月後又は約2年8か月後であるから、上記各売却価格を根拠に、本件土地2及び本件土地4の時価を求めることはできず、上記各売却価格をもって、本件各土地について評価通達に規定する評価方法によるべきではない「特別の事情」があるとは認められない。
(5)Xらは、本件土地1及び本件土地5について、評価通達に基づく価額は、地積過大による減価を行っておらず、平成29年度税制改正大綱によって、「地積規模の大きな宅地の評価」として面積規模の大きな土地が当然に減額されることなどを踏まえると、通達に規定する評価方法によるべきではない「特別の事情」があると主張する。
しかし、評価通達では、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法4条12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地(潰れ地)の負担が必要と認められるもの(ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものを除く。)に該当する場合には、路線価方式に代えて、広大地補正率による算定を行うこととされ(評価通達24-4)、加えて、仮に上記広大地に該当しないとしても、奥行価格補正(評価通達15)等により減算を受ける場合があるなど、一定の場合には減価を行うこととされているのであるから、評価通達による評価方法には合理性があるというべきである。そして、前記で説示したとおり、地積過大であるとしても、当然に減価をすべきではなく、広大地として一体利用することが市場の需給関係等に勘案して合理的と認められる場合は、減価を行う必要がないところ、本件土地1及び本件土地5について、評価通達を正しく適用したとしても同土地の時価を適切に算定することができないことを基礎付ける事情を認めることはできず、評価通達に規定する評価方法によるべきではない「特別の事情」があるとは認められない。
四、解説
はじめに
本件は、相続税における土地の「時価」の評価方法が争われたものである。相続財産の中で土地の占める割合は依然として高く(注1)、その価額の評価額が相続税の負担に大きな影響を及ぼしている。また、土地の相続税課税のあり方は、土地政策全体にも大きな影響を及ぼすこととなり、特に、土地の評価額と地価公示法上の公示価格との関係(バランス)が大きな問題とされた。その結果、平成4年以降、土地の相続税評価額は、公示価格水準の8割を目途に設定されている(注2)。個々の土地の価額については、市場価格が確立されているわけではないので、実務では、評価通達が定める評価方法に依存することになる。
しかし、評価通達が定める評価方法は、課税の公平、実務上の便宜性等を考慮して、画一的な評価方法を採用しているので、個々の土地の価額の評価方法として常に適合するとも限らない。そのため、後述するように、評価通達自体が同通達が定める評価額以外の「時価」の存在を許容しており(同通達6)、裁判例においても、「特別の事情」が存した場合には、評価通達が定める評価額以外の評価額を認めている。
本件においても、上記の「特別の事情」の存否について、不動産鑑定士による鑑定評価額と本件各土地の一部を本件相続後に売却した際の売却価額がいずれも評価通達が定める評価額(課税価格)を下回るということで、Xらがその存在を主張して争ったものである。このように、評価通達の適用上「特別の事情」の存否を争う事例は最近散見されるところであるが、本件においても、その存否について検討することとする。特に、本件においては、当該相続財産を実際に売却した場合の売却価額を同財産の相続時の「時価」との関係が問題となるものと考えられる。
1 評価通達の一般的合理性と「特別の事情」
(1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。かくして、「時価」の意義・解釈が問題となるが、それは、法の解釈論ということで、本来であれば、学説・判例に委ねられることになる。しかし、実際には、行政庁の命令手段である評価通達の定めを学説・判例が後追いしている感じがする。
すなわち、評価通達1(2)は、「時価」の意義について、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定めている。この通達にいう「……通常成立すると認められる価額」については、客観的交換価値又は客観的交換価額を意味するということで、「時価」の意義として、学説・判例もこれを支持し(注3)、所得税法又は法人税法における「価額」とも共通するものと解されている。
しかし、上記通達が「時価」の意義を客観的交換価値であるということを示すのみでは、通達の機能である職務命令として「時価」解釈の統一を図ることは困難であり(実務上の混乱を招き)、ひいては、課税の公平も期し難くなる。
(2)そこで、上記通達は、その後段において、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定め、同通達2以下において具体的な評価方法(評価額)を定め、国税庁部内の評価の統一を図ることとしている。そして、評価通達は、土地については、土地を宅地等に10区分し(評基通7)、その区分ごとに評価単位を定め(評基通7-2)、本件で問題となる宅地については、市街地的形態を形成する地域にあるものについては路線価方式によることとし、それ以外の宅地については倍率方式によって評価することとしている(評基通11)。また、本件で問題となる路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、所定の画地調整を行って評価する方式をいう(評基通13)。この場合、「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定し、路線に接する宅地で所定の要件を満たすものについて、「売買実例価額、公示価格(〈略〉)、不動産鑑定士等による鑑定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱による鑑定評価した価額をいう。以下同じ。)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。」(評基通14)と定められている。
また、本件各土地は、仮換地の面積が925㎡から7507㎡に及ぶという相当大きな地積を有するところ、そのような広大な宅地に関し、本件相続開始当時の評価通達では、「広大地」に該当するものについて、最高65%の評価減を認めており(同通達24-4)、当該取扱いが平成29年に廃止されたことに伴い、「地積規模の大きな宅地の評価」(評基通20-2)を定め、所要の評価減を定めている。
(3)以上のような土地就中宅地に係る評価通達が定める評価方法については、既に多くの裁判例において合理性が容認され、本判決も、それに追随している。そうなると、他に特別の事情がない限り本判決も判示するように、評価通達に定める評価額が当該財産の「時価」として容認されることになる。
しかしながら、評価通達が定める評価額は、前述したように、課税の統一を図るために画一的に定めたものであるから、宅地であれば、当該宅地の個別事情によっては画一的な評価額では適合しない場合も考えられる。例えば、土地の代表的な評価方法である路線価方式の路線価は、その年の1月1日現在で設定され、その1年間にわたって適用されるが、その1年間に地価が著しい下落をすれば、いかに公示価格水準の8割で評価されていても、年末に相続が発生した場合には、当該路線価による評価額が当該相続により取得した土地の「時価」を上回ることもあり得る(注4)。
そこで、評価通達6は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。この通達の運用においては、「著しく不適当」という実体要件と「国税庁長官の指示」という形式要件が適切に充足されることが重要である(注5)。このような評価通達6が適用されると、同じ(類似)財産の相続税評価額(「時価」評価)が複数(二本立て)存することになるが、このような複数評価は、相続税評価に係る個別通達及び評価通達においても明文規定が設けられている(注6)。
(4)前述のような同じ(類似)財産について複数評価が生じることについては、裁判例においても、評価通達が定める評価方法について一般的合理性を容認しながらも、当該財産の取得等において「特別の事情」が存在していれば、評価通達が定める評価額以外の価額を相続税法上の「時価」として容認しているところである。
この「特別の事情」を初めて容認したのが、東京高裁昭和56年1月28日判決(税資116号51頁)(注7)である。この判決の事案では、市街化区域内農地の売買契約中に相続が発生した場合(当該農地の路線価方式による評価額約2018万円、売買価額約4539万円)に、当該相続人が当該農地の評価額で申告したことに対し、税務署長が当該農地は売却済であるとして売買価額で課税処分を行ったところ、一審の東京地裁昭和53年9月27日判決(税資102号551頁)は、当該農地の所有権が留保されているから当該課税処分は違法であるとして取り消した。これに対し、前掲東京高裁判決は、当該農地の所有権が被相続人に留保されていても、当該農地については評価通達が定める評価額によらない「特別の事情」が認められるとし、当該農地の「時価」は当該売買価額になる旨判示し、原判決を取り消した。上告審の最高裁昭和61年12月5日第二小法廷判決(訟務月報33巻8号2154頁)は、結論において、原判決を維持している。
このように、裁判において「特別の事情」を認めて評価通達によらない価額を「時価」と認めたことは、前掲東京高裁判決当時は画期的なことであったが、その後多くの裁判例において「特別の事情」の存否が争われてきた。本判決も、その一例であるが、各事案における「特別の事情」の個別性が強いだけに、当該「特別の事情」の存否について慎重な検討が必要である。
2 鑑定評価額と「特別の事情」
(1)我が国の公的土地評価の中核となっているのが、地価公示法に基づく地価公示制度である。すなわち、同法は、標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地取引価格に対し指標を与えること等を目的とし(同法1)、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を基にして、正常な価格たる公示価格を公示する(同法2①)。この場合、「正常な価格」とは、「土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(〈略〉)において通常成立すると認められる価格」(同法2②)をいうので、前記1で述べた税法上の「時価」又は「価額」を意味する客観的交換価値の概念と共通する。
また、不動産鑑定士は、公示区域内への土地について鑑定評価を行う場合には、前述の公示価格を規準としなければならない(地価公示法8)。このように、不動産鑑定士による鑑定評価は、公示価格とリンクした権威あるものであるが故に、前述したように、路線価を設定する場合にも、不動産鑑定士による鑑定評価額が重要な判定要素となっている。
(2)以上のように、土地の評価においては、不動産鑑定士の鑑定評価は、本件のように、評価通達に基づく評価額が当該納税者にとって納得できない場合(特別の事情があると認められる場合)によく利用され、その正否が法廷で争われることになる。本来、公示価格又は評価通達上の評価額も不動産鑑定士の鑑定評価が基になっていることを考えると、それらに反した不動産鑑定士による鑑定評価は矛盾することになる。しかし、公示価格であれ、評価通達上の評価額であれ、それぞれ標準地に係る標準的な価格が基になっているので、実際の取引(相続)に係る個別事情が全て考慮されているわけではないので、当該個別事情を考慮した鑑定評価額が正当化されることもあり得るはずである。
もっとも、従前においてみられる事例では、法廷に証拠として出された不動産鑑定士による評価額は、当該不動産鑑定士が当該納税者の依頼によって(報酬を得て)鑑定評価を行うこともあってか、ともすれば客観性を失い当該納税者の利益を配慮した鑑定評価が行われている事例も見受けられる。また、裁判官においても、証拠として出された鑑定評価額よりも、評価通達に基づく評価額の一般に合理性を安易に強調し過ぎている傾向も見受けられる。いずれにせよ、不動産鑑定士による評価額をもって当該事案における「特別の事情」を立証するためには、前述のような壁があることを認識しておく必要がある。
3 当該土地の実際の売買価格と「特別の事情」
(1)前述した評価通達上の評価額であれ、当該評価額の規範となる公示価格であれ、それぞれ標準地について標準的な価格が設定されたものであって、実際に相続等によって取得した土地の「時価」である「通常取引される価額」であるとは限らない。そのため、評価通達上の評価額と当該取得財産の売買価額との間に著しい乖離があった場合もあり得るということもあって、前述した評価通達6の定めがあり、また、裁判例においても「特別の事情」の存否が問題となるところである。
現に、前記1で述べた東京高裁昭和56年1月28日判決の事案では、売買契約中に相続によって取得した土地につき、売買価額約4539万円、評価通達上の評価額約2018万円であるところ、上記判決は、売買契約中であるという「特別の事情」を認め、当該売買価額を「時価」と認めている。このように、当該取得財産の「時価」について売買価額を優先する裁判例は、相続開始直前に取得している場合に多い(注8)。もっとも、そのような事例に類似する場合であっても、評価通達上の評価額を「時価」とすべきとする裁判例もある(注9)。更に、課税時期直前に取得した土地等の「時価」につき、当該取得価額を基にして評価すべきとする取扱い通達も存する(注10)。
(2)前述の各事例は、相続等により取得した財産につき、評価通達上の評価額よりも当該財産の売買価額が高額であった場合であるか、逆に、売買価額が低額であった場合にも問題となる。そして、本件でもそうであるが、低額になる方が納税者にとって一層深刻であるといえる。この点については、バブル経済崩壊後地価が暴落した際、国税庁は、1月1日現在で設定した路線価が年後半の相続等の事案に対応できないことを認識し、路線価方式による評価額以外の評価額を容認したことがある(注11)。
しかしながら、相続等によって取得した土地等を取得後に評価通達上の評価額を下回った価額で売却した場合に、当該売却価額をもって「時価」とすることができるか否かについては、過去の事例をみてもそれを是としない傾向にあるようである。この場合には、当該相続人等が恣意的に安価で売却することも考えられるであろうし、そうでなくても、当該売却の個別事情、課税時期後の期間の長さ等からみて、当該売却価額が当該相続時等の「時価」を表わすものであるか否か疑義が生じるものと考えられる。結局、本件でもそうであるが、それぞれの個別事情を総合勘案して判断せざるを得ないものと考えられる。
4 本件各土地に係る「特別の事情」
(1)本件は、Xらが本件相続によって取得した本件各土地の「時価」につき、評価通達上の評価額によるべきか、評価通達適用上「特別の事情」を認めるべきか、が争われたものである。本件各土地は、宇都宮市の土地区画整理事業の施行地区内にあり、本件相続開始時には既に仮換地の指定が行われていたが、5区画の平均面積が4~5000㎡に及ぶという広大なものである。よって、このような個別事情を有する本件各土地の価額について、評価通達の定めによって評価することに合理性があるのか、あるいは「特別の事情」を認めて別の評価方法が妥当であるのか、その場合にも、具体的にいずれの評価方法(価額)が妥当するのかが問題となる。
かくして、本判決は、まず、「相続税法の趣旨からすれば、評価対象の財産に適用される通達に規定する評価方法が適正な「時価」を算定する方法として一般的な合理性を有する」、「同通達に規定する評価方法によるべきではない特別な事情がない限り、同通達に規定する評価方法によって評価するのが相当であ」る等を判示し、評価通達に定める市街地的形態を形成する宅地について適用される路線価方式の合理性を容認した。
また、本件各土地が本件区画整理事業にあるという個別事情に関し、本判決は、路線価の設定者が当該個別事情に配慮し、「①標準地を選定し、②不動産鑑定士等から当該標準地に係る不動産鑑定評価又は意見の提出を受け、③当該標準地の仲値(買い進みや売り急ぎがなかったものとした場合における価格)を把握し、④当該標準地の仲値を基に、⑤路線価の案をあらかじめ評定し、納税義務者から相続税又は贈与税の申告に当たり、個別評価地区内の土地について個別評価申出書が提出された場合には、あらかじめ評定した路線価の案を基に、必要に応じて現地調査及び隣接地域とのバランスの検討等を行い、個別評価をするとされている」と判示し、土地区画整理事業施行中である宅地の評価方法として上記個別評価は合理的である旨判示した。
次いで、本判決は、Xらが証拠として提出したA鑑定書の鑑定評価額については、前述のように、本件土地2ないし本件土地4はいずれも鑑定評価の対象として土地の種別が異なるとし、本件土地1及び本件土地5につき「規模大」を理由に25%又は30%の減価をしているが、当該減価に合理的理由はない旨判示した。また、本判決は、Xらが、本件相続開始後に本件土地2の一部及び本件土地4を売却した際の売却価額が評価通達上の評価額を大幅に下回っている旨主張したことに対しては、それらは相続税納付のための売り急ぎという個別的事情があり、かつ、本件相続開始後約9か月又は約2年8か月後に売却されているから当該各土地の「時価」を求めることができない旨判示した(以上の各判示により本件における「特別の事情」を否定した。)。
(2)以上のように、本判決は、本件各土地が本件区画整理事業の対象となっていること、本件各土地が平均数千㎡に及ぶという大規模な宅地であるという特殊事情を有しているところ、それらを考慮した関東信越国税局の路線価設定に不合理はないと判示し、本件土地1及び本件土地5に係る売却価額も当該合理性を覆す根拠にはならない旨判示した。しかし、そのような判示には、いささか路線価方式の合理性に肩を入れ過ぎている感じは見受けられる。
けだし、本件各土地のような大規模な宅地が面する路線価の設定において、同じ規模の標準地が採用されてそれについて具体的にどのような評価がされたのか(あるいは、標準地の面積が小さければどのような調整が行われたのか)について、国の主張や本判決の認定において読み取れないし、Xらの主張においてもそれらの問題が具体的に指摘されていない。
また、相続等によって取得した土地(財産)の直近の売却価額については、それが相続税法上の「時価」を具現したものであることについて相当の説得力を有するはずである。しかし、その売却が相続等の直近ではなく、相当の期間を経た後の期間、本件における約9か月後又は約2年8か月後という期間がどのような意味を有するかについてもっと慎重に検討されるべきである。因みに、法人税基本通達4-1-5は、非上場株式の価額の評価について直前6月間の適正な売買価額を第一順位に採用しているところ、大分地裁平成13年9月25日判決(税資251号順号8982)(注12)は、非上場株式の売買は少ないものであるから1年1月又は2年5月前のものでも参考にすべき売買実例になる旨判示しているが、国も控訴していない。また、評価通達185かっこ書は、取引相場のない株式の価額(時価)を純資産価額方式で評価する場合に課税時期3年以内に取得した土地等及び家屋等の価額(時価)については、当該取得価額(売買価額)を参考にすべきことを定めている。
このような評価通達の取扱いや大分地裁判決の考え方によれば、課税時期後3年間という期間は参考とすべき売買実例の射程に入るはずである。そうであれば、本件においても、本件各土地の売買実例について、売り急ぎの実態や相続開始後9か月又は2年8か月の間に近隣の地価動向がどうなっていたかについて、もっと慎重な検討がなされて然るべきであると考えられる(それは、Xらの主張にも緻密さを欠いていることを意味する)。
5 本判決の意義と問題点
以上のように、本件は、土地区画整理事業の施行地にあり、かつ、大規模な面積を有する本件各土地の「時価」の評価につき、評価通達の適用上「特別の事情」が存するか否かが争われたものである。本判決は、他の裁判例と同様に、評価通達が定める評価方法(評価額)の一般的合理性と、本件各土地に係る路線価方式による評価額の合理性を容認し、Xらが主張する鑑定評価額と相続開始後の実際の売却価額が評価通達上の評価額を大幅に下回るという事実についても、「特別の事情」に当たらないと判断した。
このように、土地等の評価について、評価通達適用上の「特別の事情」の存否については、課税又は争訟段階において、国(課税庁)又は納税者側から主張されることになる。この場合、納税者側からの主張は比較的少ないので、本判決は、その一事例として参考になる。また、本判決については、前述したように、評価通達上の評価方法についての一般的合理性が強調されるが故に、本件各土地の特殊事情や実際の売却価額の重要性がやや看過ごされているように考えられる。
(注1)相続財産に占める土地の割合は、昭和63年には69.3%であったが、平成28年には38.0%となっているものの、いずれも他の財産に比して、断突に多い(日本租税研究協会「税制参考資料集 令和元年5月」279頁)。
(注2)品川芳宣「財産(資産)評価の実務研究 第5回」季刊資産承継2018年秋号198頁等参照。
(注3)金子宏「租税法 第23版」(弘文堂 平成31年)714頁、最高裁平成22年7月16日第二小法廷判決(判例時報2097号28頁)、東京高裁平成27年12月17日判決(同2282号22頁)、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等参照。
(注4)東京地裁平成9年9月30日判決(税資228号829頁)、東京高裁平成11年8月30日判決(同244号400頁)等参照。
(注5)詳細については、品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)122頁、同「財産(資産)評価の実務研究 第3回」季刊資産承継2018年春号(No.3)201頁等参照。
(注6)負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について(平成元年直評5等)、評価通達169(2)、同189なお書等参照。
(注7)品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)806頁参照。
(注8)東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、東京高裁平成5年1月26日判決(税資194号75頁)、東京地裁平成5年2月16日判決(同194号375頁)、東京高裁平成5年12月21日判決(同199号1302頁)等参照。
(注9)東京地裁平成17年10月12日判決(税資255号順号10156)等参照。
(注10)前出(注6)の個別通達、評価通達185かっこ書等参照。
(注11)前出(注4)各判決等参照。
(注12)前出(注7)246頁参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















