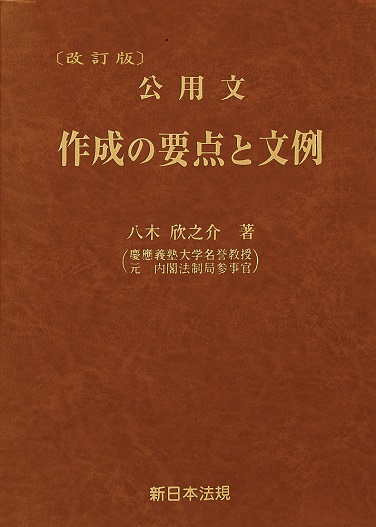解説記事2019年10月28日 未公開判決事例紹介 土地購入に係る税務相談をめぐる税理士賠償責任事件(2019年10月28日号・№809)
未公開判決事例紹介
土地購入に係る税務相談をめぐる税理士賠償責任事件
試算内容の誤りを確認すればOK
今号8頁で紹介した東京地裁判決の全文について、仮名処理した上で紹介する。
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、1730万4770円及びこれに対する平成29年6月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、税理士である被告に対し、節税目的による土地及び建物の一括購入に係る税務相談をしたところ、被告が国税通達等を看過し、売買契約書の代金額の記載方法について原告に適切な助言をしなかったため、期待していた節税効果を得ることができなかったと主張して、債務不履行に基づく損害賠償請求として、課税負担額増加分等1730万4770円及びこれに対する平成29年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者等
ア 原告(昭和18年生)は、平成8年まで○○信託銀行株式会社の○○支店長を務めた後、株式会社○○百貨店の取締役を務めたという職歴を有する者である。
有限会社I(以下「I」という。)は、不動産の賃貸、管理及び売買等を目的とする平成7年4月5日成立の会社であり、原告がその代表取締役を務めている(乙27)。
イ 被告(昭和29年生)は、昭和62年に税理士登録をした税理士であり、かつて税理士事務所であるY会計事務所を開設していた者である。
(2)原告は、平成25年4月23日、株式会社B(以下「B」という。)から、別紙物件目録1記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同目録記載2の建物(以下「本件建物」といい、本件土地と併せて「本件不動産」という。)を代金総額2億3000万円(内訳:本件土地1億6778万0465円、本件建物5925万6700円、消費税等296万2835円)で買い受けた(以下「本件売買契約」という。)。本件売買契約の締結に当たって作成された売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)には、本件不動産の代金額の上記内訳が記載されていた。(甲10)
(3)被告は、平成25年以降、原告の所得税の確定申告書を作成し、K税務署に対し、原告の確定申告を行った。被告は、同確定申告書に、本件建物の簿価を1億円と記載していた。
(4)K税務署は、平成28年6月7日、原告の税務調査を行い、原告に対し、本件建物の簿価は本件売買契約書に記載された代金額である5925万6700円とすべきであると指摘した。原告は、K税務署に対し、本件建物の簿価を5925万6700円として、平成25年以降の修正申告を行った。
(5)資産税課情報第25号平成12年8月29日国税庁資産税課「建物と土地を一括で取得している場合の『建物の取得価額』について」によれば、譲渡所得の計算における建物の減価償却費相当額の計算に当たり、建物と土地を一括で取得している場合には、その取得価額を「建物の取得価額」と「土地の取得価額」に区分する必要があるところ、取得時の契約において建物と土地の価額が区分されている場合には、原則として、その契約による価額を各々の取得価額として区分することとされている(甲8)。
2 争点及び当事者の主張
本件の争点は、①被告は、本件売買契約書の代金額の記載方法について原告に対して助言をすべき善管注意義務に違反したか、②上記①の善管注意義務違反によって原告に生じた損害である。
(1)争点①(被告は、本件売買契約書の代金額の記載方法について原告に対して助言をすべき善管注意義務に違反したか)について
ア 原告の主張
(ア)包括的な委任契約の締結及び具体的な相談
原告は、被告との間で、原告、原告の妻及びIの平成10年分以降の税務申告業務及び節税対策のコンサルティング業務を包括的に被告に委任する旨の委任契約(以下「本件委任契約」という。)を締結していた。
原告は、平成24年11月頃、被告に対し、本件不動産を購入する予定であることを前提に、本件建物の減価償却費相当額の試算並びに原告、その親族及びI(以下、まとめて「原告ら」という。)の所得税、住民税等の税率の試算額の提出を求めた。また、原告は、同年12月3日、被告から、本件不動産の所在及び代金総額並びに被告が試算した本件不動産の代金額の内訳、本件建物の減価償却費相当額及び税負担比較等が記載された書面を交付され、本件建物の賃料収入が加算された場合の税率の変動について指導を受け、被告に対し、本件不動産の購入に係る税務対策について具体的に相談した。さらに、原告は、平成25年3月16日、被告に対し、本件不動産の代金額の内訳、本件建物の減価償却費相当額及び税負担比較等を自ら試算して記載した資料(乙7。以下「本件資料」という。)を交付し、原告による上記試算に誤りがないか確認を求めた。
以上のとおり、原告は、本件委任契約に基づき、被告に対し、本件不動産の購入に係る税務対策について具体的な相談を行った。
(イ)被告の善管注意義務違反
被告は、本件委任契約及び前記(ア)の具体的な相談に基づき、税理士として、本件売買契約書の代金額の記載方法について原告に対して助言をすべき善管注意義務を負っていた。具体的には、土地及び建物を一括購入した場合の建物の減価償却費相当額は売買契約書に記載された建物の取得価額を基準として認定されることを把握した上で、原告に対し、本件売買契約書における代金額の記載方法いかんによって税務署による本件建物の減価償却費相当額の認定額が左右されることを説明し、必要に応じて本件売買契約書等を確認した上で、本件売買契約書の代金額の記載方法について適切な助言をすべき義務があったものである。
しかし、被告は、原告に対し、本件売買契約書の代金額の記載方法について助言をせず、かえって、本件不動産の代金総額から本件土地の公示価格又は路線価を差し引いた金額を建物簿価として設定して確定申告を行えばよいという誤った助言をして、上記義務に違反した。
イ 被告の主張
(ア)本件委任契約の締結及び具体的な相談の不存在
被告が原告との間で本件委任契約を締結したことはない。被告が原告から受任した業務の内容は、Iの会計処理及び申告業務並びに原告及びその家族の確定申告や贈与税の申告作業にとどまる。
また、原告は、平成24年12月3日、被告に対し、初めて本件不動産の購入を検討していることを告げただけであり、購入に向けた具体的な相談はしていないし、平成25年3月16日には、被告に対し、自らの試算に基づいて作成した本件資料を交付して、一方的に本件不動産の購入計画を話していたことがあったものの、本件不動産の購入に係る税務対策について具体的に被告に相談し、助言を依頼したなどということはなかった。
(イ)善管注意義務違反の不存在
したがって、被告が、税理士として、本件委任契約及び上記相談に基づき、本件売買契約書の代金額の記載方法について原告に助言をすべき善管注意義務を負ったということはなく、同義務に違反したこともない。また、被告が原告に対して原告が主張するような誤った助言をしたこともない。
(2)争点②(①の善管注意義務違反によって原告に生じた損害)について
ア 原告の主張
(ア)原告は、本件売買契約書の代金額の記載方法について被告から適切な助言を受けていれば、本件売買契約書に本件建物の代金額として1億円と記載し、本件建物の取得価額が1億円であることを前提として平成25年以降の所得税の確定申告を行うことができたところ、被告の前記(1)ア(イ)の善管注意義務違反によって、本件建物の取得価額が5925万6700円(本件売買契約書に記載された本件建物の代金額)であることを前提として修正申告を行うことを余儀なくされ、所得税及び住民税の負担が増加する損害を受けた。原告は、本件売買契約を締結した頃、複数の不動産業者から本件不動産以外の物件の紹介を受けていたから、原告において本件建物の代金額を1億円とすることに固執した結果としてBとの交渉が決裂し、本件不動産の購入を断念するに至ったとしても、他の不動産業者から不動産を購入することによって節税の目的を達成することが可能であった。
(イ)本件建物の残存耐用年数は18年であり、原告が定額法による税務申告をしていることを前提とすると、本件建物の減価償却率は0.056である。平成22年以降、原告の所得税率は、20%であった平成25年を除いて33%を下回ったことがなく、また、住民税は6%を、県民税は4.025%をそれぞれ下回ったことがない。これらを前提とすると、原告は、以下のとおり課税負担額が増加したことになり、これが被告の善管注意義務違反によって原告が受けた損害額である。
a 平成25年 45万6704円
(計算式)(1億円-5925万6700円)×0.056×(所得税20%+住民税6%+県民税4.025%)×8か月/12か月
b 平成26年 114万1382円
(計算式)(1億円-5925万6700円)×0.056×(所得税40%+住民税6%+県民税4.025%)
c 平成27年から平成42年まで 1570万6704円
(計算式)(1億円-5925万6700円)×0.056×(所得税33%+住民税6%+県民税4.025%)×16年分
d 合計 1730万4770円
イ 被告の主張
仮に被告に本件委任契約及び具体的な相談に基づく善管注意義務違反があるとしても、これと原告が主張するような前記アの損害との間の因果関係はない。
被告が、原告に対し、本件売買契約書に本件建物の代金額として1億円と記載するよう助言をしたとしても、Bが本件建物の代金額を1億円とすることに応じる可能性は低い。そして、Bが本件建物の代金額を1億円とすることに応じなかった結果、原告が本件不動産の購入を断念した場合に、原告が本件不動産と同等の価値の不動産を購入した蓋然性があったことは立証されていない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実並びに証拠(甲28、乙21、原告本人、被告本人及び後掲のもの。ただし、以下の認定に反する部分は除く。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、同認定を左右するに足りる証拠はない。
(1)本件売買契約締結に向けた交渉より前の事実関係
ア 原告は、○○信託銀行株式会社の○○支店長を務めていたときに、同支店と取引のあった税理士事務所に所属していた被告と知り合った。原告は、平成7年にIを設立したが、これは、法人を設立して同法人に資産の一定程度を移すという、被告から助言された節税対策を実行したものであった。その後、原告は、平成10年頃から、上記税理士事務所から独立していた被告に対し、原告らの税務申告を依頼するようになった(甲1、3、5)。同税務申告業務に対する報酬は、全てIから支出されており、その金額は、申告件数に応じて年間25万円から60万円程度であった(乙6)。
イ 被告は、前記アのとおり原告らの税務申告業務を行うようになって以降、原告に対し、Iの原告及びその妻に対する役員報酬や貸付金の利息の定め方等について助言をした。また、被告は、原告個人の相続税等の対策として、金融機関から借入れをして収益不動産を購入する方法があることを紹介した上で、特に既に不動産所得があった原告の場合、土地及び建物が一体で相応の減価償却を期待できる物件が適しており、その際の減価償却費相当額の基準となる建物簿価については、土地及び建物一体の価額から公示価格又は路線価に基づいて算出した土地の価額を差し引いて算出すればよいが、土地の価額を路線価に近付けすぎると税務申告上問題となることがあり得ることなどを助言した。
ウ 被告は、原告と協議の上、平成16年12月14日、不動産の賃貸、管理及び売買等を目的とする会社である有限会社Lを設立し、同社の取締役に就任した。同社は、平成18年、原告を宅地建物取引主任者として宅地建物取引業免許の申請を行い、その免許を取得した(乙4の1・2、28)。
原告及び被告は、この頃には、互いのことを共同の事業パートナーとして位置付けるに至っており、原告は、被告の承諾の下、Y会計事務所の「特別顧問」という肩書で相続関係の処理等の種々の業務に携わるようになっていた(甲29、乙5)。
エ(ア)原告は、平成19年3月18日、Cから、別紙物件目録2記載1(1)の土地及び同目録記載1(2)の建物を代金総額3150万円で買い受けた。同売買契約の締結に当たって作成された売買契約書には、上記の土地及び建物の代金の内訳が記載されていなかった。(甲4)
(イ)原告は、平成21年1月29日、R社から、別紙物件目録2記載2(1)の土地及び同目録記載2(2)の建物を代金総額1億8200万円で買い受けた。同売買契約の締結に当たって作成された売買契約書には、上記の土地及び建物の代金の内訳が記載されていなかった。(甲6)
(2)本件売買契約締結に向けた交渉時の原告及び被告の動き
ア 原告は、平成24年12月3日、Y会計事務所を訪問し、被告と面談した。その際、原告において本件不動産を購入することを検討していることが話題となった。なお、被告作成の業務日誌の同日の欄には、「I」「X来所 Nに新規不動産購入(T倉庫ワイン置場用ビル)予定 相談」と記載されている(乙2)。
イ 原告は、平成25年3月16日、Y会計事務所を訪問し、被告と面談した。その際の話題の中心は、原告の紹介により第三者から依頼された業務に係る報酬に関することであったが、原告は、その話題の後、被告に対し、自らの試算に基づいて作成した本件資料を交付し、その内容を説明した。
2 争点①(被告は、本件売買契約書の代金額の記載方法について原告に対して助言をすべき善管注意義務に違反したか)について
(1)本件委任契約締結の有無
ア 本件委任契約の明示的な締結について
原告が本件委任契約の内容として主張する節税対策のコンサルティング業務とは、要するに、原告の節税対策について被告が具体的な提案、助言をすることを意味するものと解されるが、原告と被告の間において、原告がそのような業務を包括的に被告に委任するという本件委任契約が明示的に締結されたことを認めるに足りる証拠はない。
イ 本件委任契約の黙示的な締結について
被告は、認定事実(1)アないしウのとおり、平成10年頃以降、原告らの税務申告業務を継続的に行っていただけでなく、原告からの相談に応じて税務対策としての様々な助言を行っており、また、原告が認定事実(1)エのとおり別紙物件目録2記載の各土地建物を購入したのは、被告による上記の助言を参考にしたものであったと認められる。しかし、認定事実(1)ウのとおり、原告及び被告は単なる顧客と税理士との関係にとどまらず、原告においてはY会計事務所の特別顧問の肩書で相続関係の処理などの業務に携わり、一方で被告においては原告の宅地建物取引主任者の資格を利用して有限会社Lを経営するなど、共同の事業パートナーという関係にあったことや、上記の税務相談及びそれに対する助言に関しても、原被告間で具体的に委任の事務の範囲やそれに対する報酬額の取決めがされておらず、実際に原告らが被告の助言の対価としての報酬を支払った形跡もないことに照らすと、上記の税務相談及びそれに対する助言の事実によっては、原告と被告との間で本件委任契約が黙示的に締結されたと認めることはできず、そのほか、同事実を認めるに足りる証拠はない。
ウ 被告の原告に対する善管注意義務の内容
原告と被告との間で本件委任契約が締結されたと認められないことは、前記ア及びイのとおりであるから、この点に関する原告の主張は理由がない。そうすると、被告は、原告に対し、原告から税務相談を受ける都度締結される個別の委任契約に基づき、同相談の具体的内容に応じ、税理士として的確な助言をするという内容の善管注意義務を負担していたにとどまるというべきである。以下、原告は、被告には上記のような個別の委任契約に基づく善管注意義務違反があったとも主張しているものとして、検討を進める。
(2)被告の善管注意義務違反の有無について
ア 原告は、①平成24年12月3日以前に、被告に対し、本件不動産を購入する予定であることを前提に、本件建物の減価償却費相当額の試算及び原告らの所得税、住民税等の税率の試算額の提出を求め、同日、被告から、本件不動産の所在及び代金総額並びに被告が試算した本件不動産の代金額の内訳、本件建物の減価償却費相当額及び税負担比較等が記載された書面を交付され、②平成25年3月16日、被告に対し、自らの試算に基づいて作成した本件資料を交付し、原告による本件不動産の所得税の試算に誤りがないか確認を求めたと主張し、上記①で被告から交付された書面として甲24を提出する。
イ 甲24は、上部に手書きで「12/3 X様来所」と記載され(以下「手書き部分」という。)、その下に活字で、原告が本件不動産を取得する予定であり、代金額は総額2億3000万円であること、原告が本件不動産を取得することによる年間減価償却費相当額の計算式や取得前後における租税負担額の比較等の記載があるほか、本件不動産の代金額の「内訳は、土地130,000,000円、建物100,000,000円を予定している。」と記載されている(以下「活字部分」という。)ところ、原告は、手書き部分及び活字部分ともその作成者は被告であると主張し、被告はこれを争っている。なお、甲24には手書き部分とは違う筆跡による「18百万円未満に抑える必要有り」、「○○○地24百万→12百万へ減額」などという手書きの記載もあるが、これらは原告が自書したものである。
ウ そこで検討するに、甲24の活字部分については、「限界税率」という専門的な用語が用いられ、所得金額に応じた税率が詳細に記述されている上、原告がその隣に「18百万円未満に抑える必要有り」、「○○○地24百万→12百万へ減額」と自書しているところ、これらは被告から活字部分を示されて説明を受けたことを踏まえてその内容を書き留めたものと考えるのが自然である一方、被告自身、「この文書が、私の作成したものであると断言はできません。」と陳述し(乙21)、本人尋問においても「手書き部分を除いた印刷部分、これはあなたが作成したものですか。」との問いに「よくわかりません。」と供述するにとどまっている上、書式についても「私が作成する手控えによく似ています。」とも供述していることによれば、被告が作成したものと認めるのが相当である。また、甲24の手書き部分も、当該部分のみが被告以外の者によって偽造されたとは考えにくいところである。
しかし、甲24の作成者に関する前記認定を前提としても、活字部分中の原告及びその妻の氏名の記載には敬称が付されていない上、被告において原告に交付することを予定している書面に「12/3 X様来所」と鉛筆書きでわざわざ記載する合理的理由も見いだし難いことからすると、甲24は、顧客である原告に説明資料として交付することを予定して作成された書面ではなく、元々は被告の手控えであったと認めるのが相当である。また、甲24の活字部分には、想定される賃料額や経過年数等の情報の記載もあるところ、証拠(原告本人)によれば、原告がM社から本件不動産の物件概要書(甲7)の交付を受けたのは平成24年12月13日であり、原告自身も、本件訴訟の当初の段階では、同月5日の時点では売主において本件不動産を売却することができるかどうかすら不確実で、同月3日の時点では「具体化していない物件購入についての具体的相談は行いようがなく、行っていない。」とまで主張していたこと(平成30年1月15日付け原告第2準備書面)からすると、甲24は、平成24年12月3日の時点で完成していたものではなく、同日以降、被告が原告からの相談や情報の提供を受けて、その都度、その内容を補充したり更新したりするなどし、いずれかの時点で原告に交付されたものと認めるのが相当である。
エ そして、前提事実(1)ア及び認定事実(1)のとおり、原告が長年信託銀行に勤務し、会社役員を経て、本件売買契約当時はY会計事務所の特別顧問の肩書で活動していた上、自身の節税対策についても強い関心を抱き、本件不動産の購入前にも、節税対策のために金融機関から借入れを行い、土地及び建物を一体として購入するなどしていたことからすれば、原告は、これらの経験を通じて税務に関する知識を相当程度深めるに至っており、確定申告において賃料収入から差し引かれる建物の減価償却費相当額の算定方法についても承知していたものと認められ、また、本件不動産の購入に当たっても、本件不動産の代金総額の内訳、本件建物の減価償却費相当額及び税負担比較等を改めて試算した本件資料を作成するなどしていたことからすると、原告は、本件不動産の購入に係る税額の計算をする程度の能力は十分に備えていたものと認められる。他方で、被告は、当初から本件売買契約自体には関与せず、また、独自に本件不動産について調査したものではないことからすると、甲24の活字部分については、被告において原告から聴き取った内容をそのまま記載したものと認めるのが相当である。
この点につき、原告は、本件不動産の代金額の内訳を土地1億3000万円、建物1億円としたのは被告である旨供述するが、甲24が元々は被告の手控えとして作成されたものであることは前記認定のとおりであるから、活字部分中の「内訳は、土地130,000,000円、建物100,000,000円を予定している。」という箇所は、被告において、原告がそのように予定しているという話を聴き取って記載したものと考えるのが自然であるし、原告の経歴やそれまで節税対策として平成19年及び平成21年に別紙物件目録2記載の各土地建物を購入した経験等に照らして、原告は基本的な節税対策の仕組みについては理解していたと認められること、代金額が総額2億3000万円とされている点も、売主が当初は2億8000万円での売却を希望していたこと(甲7)からすると、原告の購入希望額にすぎず、そうした状況で被告において物件の情報もない中で土地と建物の価格の内訳を策定するとは考えにくいから、代金額の内訳については、原告において土地1億3000万円、建物1億円としたものと考えるのが合理的である。したがって、原告の上記供述は採用することができない。
オ 以上によれば、甲24の記載によっては、原告が被告に対して本件建物の減価償却費相当額の試算及び原告らの所得税、住民税等の税率の試算額の提出を求めたとは認められないというべきであり、そのほか、原告が被告にそのような依頼をしたと認めるに足りる証拠はない。
そうすると、原告は、被告に対し、本件不動産を購入するに当たって自ら試算した内容の確認を求めたにとどまり、本件全証拠によっても、それを超えて、本件不動産の購入に伴う具体的な税額計算を依頼したり、税務上のアドバイスを求めたりした事実は認められないというべきである。そして、こうした相談内容を前提とすると、被告においては、原告の試算した内容に誤りがないかを確認すれば足り、本件売買契約書における代金額の記載方法いかんによって税務署による本件建物の減価償却費相当額の認定額が左右されることを説明し、必要に応じて本件売買契約書等を確認した上で、本件売買契約書の代金額の記載方法について適切な助言をすべき義務を負っていたと解することはできない。また、本件全証拠によっても、被告が、原告に対し、本件売買契約書における代金額の記載方法いかんにかかわらず、本件不動産の代金総額から本件土地の公示価格又は路線価を差し引いた金額を建物簿価として設定して確定申告を行えばよいという誤った助言をしたという事実は認められない。
よって、被告に善管注意義務違反は認められない。
カ なお、本件においては、原告が被告に対して相談をしていた平成25年3月16日の時点では、本件不動産の代金額の内訳を土地1億3000万円、建物1億円とすることが試算の前提となっていたことは当事者間に争いがなく、被告は本件不動産の代金額の内訳についてそれ以上の情報を与えられなかったものである。そして、減価償却費相当額の算定の基礎となる「建物の取得価額」が契約金額を指すというのは、文理上も自然な解釈というべきところ、原告において実際には代金5925万6700円で本件建物を購入しながら、減価償却費相当額の算定に当たっては「建物の取得価額」を実際の代金額とは異なる1億円として申告をしても差し支えないとの考え方に立ち、試算の前提となっていた1億円とは異なる代金額で本件建物を購入してしまうことまで被告が想定して、本件売買契約書における代金額の記載方法いかんによって税務署による本件建物の減価償却費相当額の認定額が左右されることを説明する義務を負うと解することは到底できないというべきであり、原告の主張はその意味でも当を得ないものである。
第4 結論
以上のとおりであって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから、主文のとおり判決する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.