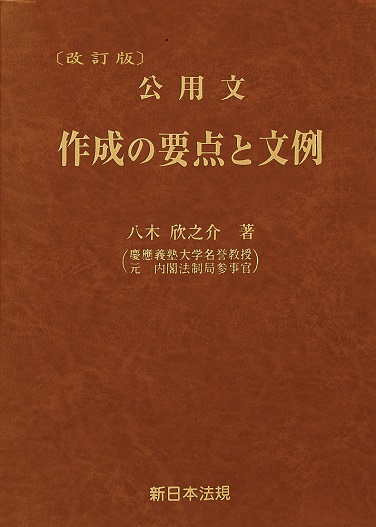解説記事2021年03月22日 ニュース特集 最高裁、資本の払戻しにおけるプロラタ計算は違法(2021年3月22日号・№875)
ニュース特集
国の上告棄却で、政令改正等が行われる可能性も
最高裁、資本の払戻しにおけるプロラタ計算は違法
資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当に係る税務上の取扱いを巡り争われていた事件で、最高裁判所(第一小法廷・深山卓也裁判長)は令和3年3月11日、国の上告を棄却した。
本件を巡っては、「その全額が資本の払戻しに該当する」とした一審と、資本剰余金を原資とする部分は「資本の払戻し」に、利益剰余金を原資とする部分は「剰余金の配当」に該当するとした控訴審の解釈が分かれていたことから、最高裁の判断に関心が集まっていた。
最高裁は、一審判決と同様に「その全体が法人税法24条1項3号(現行4号)に規定する資本の払戻しに該当する」とし、この点については国の主張を認めたものの、同じく一審判決で示され国を敗訴へと導いた、資本の払戻しにおける株式対応部分とみなし配当部分のプロラタ計算を定めた法人税法施行令23条1項3号(現行4号)の規定を違法・無効とするとの判断も支持。判断の理由は控訴審と異なるものの、一・二審に続き、納税者に軍配を上げた。
最高裁で法人税法施行令の規定が違法・無効と判断されたことが今後の実務に与える影響、また、本判決により政令改正等が行われることになるのか、注目される。
控訴審の解釈は否定、資本・利益双方原資の配当「全体が資本の払戻し」
被上告人X社は、外国子会社(米国デラウェアLLC)から、資本剰余金1億ドル(以下「資本配当」)と利益剰余金5億4,400万ドル(以下「利益配当」)をそれぞれ原資とする配当を受けたが、それぞれ別個の決議に基づき行われた独立した別個の配当として、資本配当は資本の払戻し(法法24①三)に、利益配当は剰余金の配当(法法23①一)に該当することを前提に、利益配当約410億円を益金不算入、資本配当については約129億円を損金(関係会社株式評価損)に算入して法人税の連結確定申告を行った。これに対し、処分行政庁は、各決議日や効力発生日が同日であることなどから、その全額が資本の払戻しに該当するとして、利益配当の益金不算入額を約327億円、資本配当に係る有価証券譲渡損を約41億円とする法人税の更正処分を行った。これを不服としたX社は提訴した。
一審、国の主張認めるも処分は違法
一審である東京地裁は、本件配当の全額が資本の払戻しに該当するとの判断を示し、この点については国の主張を認めた。しかし、資本の払戻しにおける「株式又は出資に対応する部分の金額」と「みなし配当の金額」のプロラタ計算による算定方法を定めた法人税法施行令23条1項3号について、払戻し法人の利益積立金額がマイナスの場合に利益剰余金を原資とする部分が「株式又は出資に対応する部分の金額」として扱われることとなる点を問題視。これは、本来であれば二重課税防止の観点からみなし配当として益金不算入となるべき部分が有価証券の譲渡に係る対価の額に算入されることとなり、法人税の課税対象になってしまうためだ(図表4及び5参照)。結論として東京地裁は、当該施行令は「減少した資本剰余金の額を超える『払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等』が算出される結果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」という判断を下して課税処分を取り消し、納税者が勝訴した(東京地裁平成29年12月6日判決。本誌730号40頁)。
「資本の払戻し」の新たな解釈示した控訴審
国は一審判決を不服として控訴したが、二審の東京高裁は、「資本の払戻し」の解釈について、「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る)」(法法24①三)とは、「資本剰余金の額の減少によって行う剰余金の配当」すなわち、「資本剰余金を原資とする配当」をいうものとの解釈を示し、「資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資として配当が行われた場合には、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるような例外を除き、原則として、資本剰余金を原資とする配当は法人税法24条1項3号の資本の払戻しに、利益剰余金を原資とする配当には同法23条1項1号の剰余金の配当に当たる」との新たな考え方を示し、より納税者の主張に近い判断を下した(東京高裁令和元年5月29日判決。本誌796号4頁)。ただ、この判断を巡っては「立法趣旨と異なる」などの意見もあり、議論を呼んでいた。
最高裁、「控訴審の解釈は誤り」
控訴審の上記判断に対し、最高裁は、法人税法の解釈を誤った違法があると判断した。最高裁は、「平成18年改正後の法人税法においては、23条1項1号と24条1項3号の適用の区別につき、会社財産の払戻しの手続の違いではなく、その原資の会社法上の違いによることとされた」とした上で、「そして、会社法における剰余金の配当をその原資により区分すると、①利益剰余金のみを原資とするもの、②資本剰余金のみを原資とするもの及び③利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とするものという3類型が存在するところ、法人税法24条1項3号は、資本の払戻しについて「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)……」と規定しており、これは、同法23条1項1号の規定する「剰余金の配当(……資本剰余金の額の減少に伴うもの……を除く。)」と対になったものであるから、このような両規定の文理等に照らせば、同法は、資本剰余金の額が減少する②及び③については24条1項3号の資本の払戻しに該当する旨を、それ以外の①については23条1項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞれ規定したものと解される」との解釈を示し、「利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は、その全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する」と、一審判決と同様の結論を下した。
利益積立金がマイナスの場合、プロラタ計算を定めた施行令は違法
上記のとおり本件配当の全体が資本の払戻しに該当するという国の主張は一審同様に認められたものの、最高裁は、同じく一審判決で示され国を敗訴へと導いた、資本の払戻しにおける株式対応部分とみなし配当部分のプロラタ計算による算定方法を定めた法人税法施行令23条1項3号は違法・無効とするとの判断も支持し、国の上告は棄却された。
最高裁は、法人税法の資本部分と利益部分とをしゅん別するという基本的な考え方や、みなし配当の規定の趣旨なども踏まえた上で、「法人税法24条1項3号は、利益剰余金を原資とする部分を資本部分の払戻しとして扱うことは予定していないものと解される」と指摘。一審と同様に、配当を行う子会社の配当直前の利益積立金額がマイナスである場合、つまり、簿価純資産価額が直前資本金額より少額である場合に、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出され、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当において、利益剰余金を原資とする部分が資本部分の払戻しとして扱われることとなる点を問題とした。その上で、法人税法施行令23条1項3号の規定について、「減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである」と結論づけた。
本件を巡っては、資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当について一審と控訴審の判断が分かれたことから、最高裁がどのような判断を下すのか関心を集めていたが、今後は本判決で示された最高裁の判断に従って実務が行われていくことになろう。また、最高裁で法人税法施行令の規定が違法・無効と判断されたことにより、政令改正等が行われることになるのか、注目される。

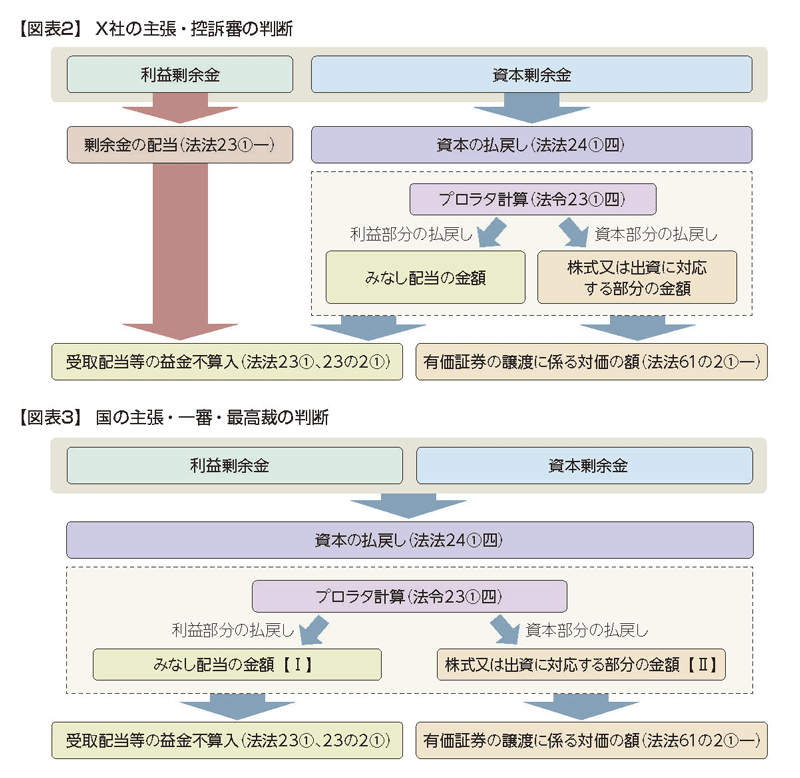
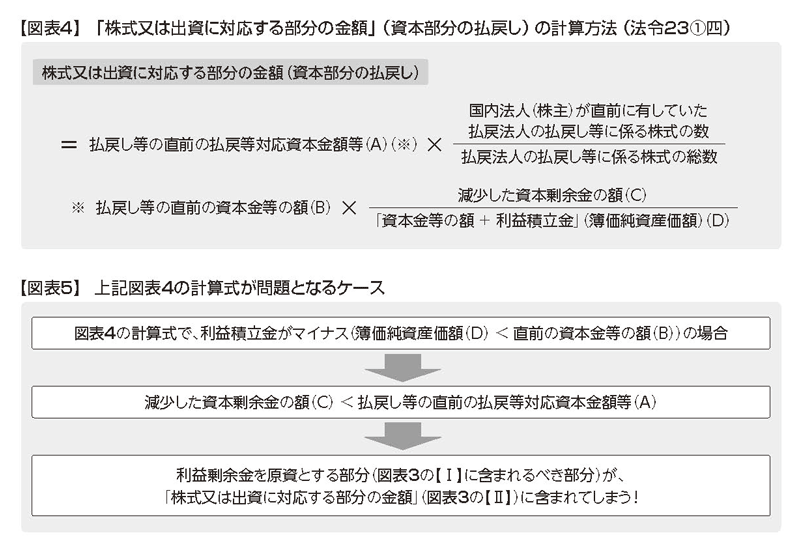
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.