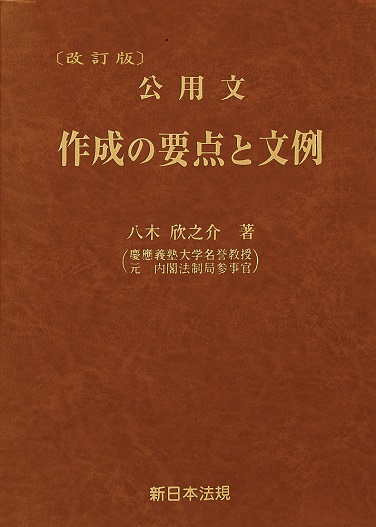解説記事2019年11月18日 税理士のための相続法講座 相続法改正(7)―遺留分③(2019年11月18日号・№811)
税理士のための相続法講座
第52回
相続法改正(7)-遺留分③
弁護士 間瀬まゆ子
1 はじめに
相続法改正について第7回目となる今回のテーマは、前回・前々回に続いて遺留分です。
① 遺留分減殺請求権(改正後は遺留分侵害額請求権)から生じる権利を金銭債権化
② 受遺者等の請求により裁判所が金銭債務の支払いにつき相当の期限を許与する制度の新設
③ 遺留分算定の基礎財産に加える相続人に対する生前贈与を10年以内にされたものに限定
今回は、上記の③、すなわち、相続法改正により、遺留分算定の基礎財産に加える相続人に対する生前贈与が10年以内にされたものに限定されることになった点について解説していきます。
2 改正の趣旨
改正前の民法でも、生前贈与について、「相続開始前の1年前にしたものに限り」その価額を算入することとされていました(ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は算入されると規定されていました。)。しかし、判例は、特別受益としての贈与は、特段の事情のない限り、相続開始前1年間に限らず、また、損害を加えることの認識の有無を問わず、算入されるとしていました(最三小判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)。つまり、相続人への贈与は、たとえ何十年前のものでも、遺留分侵害額を計算する際に加算されてしまうのです。
しかし、そのような解釈によると、相続人への生前贈与を知り得ない第三者たる受遺者らに不測の損害を与える場合がありました。
Aが亡くなった。相続人は子BとCの2人。Aが相続開始時に有していた財産は3000万円の自宅のみだが、Aはそれを第三者Dに遺贈する内容の遺言を残していた。BがDに対し遺留分減殺請求をしたが、その話し合いの中で、Aが20年前にCに対して9000万円を贈与していたことが判明した。
この場合、旧法の下では、遺留分侵害額は以下のとおりに計算していくこととされていました。
遺留分の算定の基礎となる財産の額=3000万円+9000万円=1億2000万円
Bの遺留分侵害額=1億2000万円×1/2×1/2=3000万円
Cの遺留分侵害額=1億2000万円×1/2×1/2-9000万円=△6000万円
Bの最終的な取得額=3000万円
Cの最終的な取得額=9000万円(減殺なし)
Dの最終的な取得額=0円(全て減殺)
遺留分減殺の順序は、遺贈が生前贈与に優先します。したがって、上記のとおり、DがBに対して3000万円全額を負担することになってしまうのです。Dからすれば、知るはずもない20年前のCへの贈与で受贈財産全てを減殺されてしまうわけですから、確かに気の毒といえます。
そこで、新法では、受遺者等の保護を図るため、相続人に対する生前贈与については、相続開始10年前にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に含めるとの新たな規定を設けることとしました(新民法1043条3項)。ただし、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」は無限定で遡ることになります(その立証責任は遺留分権利者側が負担します。)。
※なお、受贈者が相続人以外の者である場合には、従前どおり相続開始1年前にされた贈与に限定されます。
※「遺留分権利者に損害を加えることを知って」いたとはどのような場合かと質問を受けることがあります。この点、第三者への1年より前の贈与については、改正前から「遺留分権利者を害することを知って」いたかが問題となる場合があり、この点に関する判例も出ていますので、これが参考になります。この点、判例では、贈与財産の全財産に対する割合だけでなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与か否かによるとされています。つまり、贈与の時点が古く、贈与者が若く、健康であるほど悪意は認定されにくく、また贈与者が会社のオーナー等で贈与後も収入が入ることが長く見込まれるようなときは悪意があったとは言われにくいことになると思われます。
このように10年という期間制限が設けられた結果、上記の事例で、Cに対する生前贈与分は、遺留分を算定するための財産の価額に加算されないことになりました。よって、Bの遺留分侵害額は、3000万円×1/2×1/2の750万円となり、この金額の限りでDに請求できることになります。
3 新法における遺留分の基本的な算定式
ここで、上記の改正点も踏まえて、改正後の遺留分の基本的な算定式を確認しておきます。
遺留分を算定するための財産の価額
=被相続人が相続開始時において有した(積極)財産の価額+相続人に対する特別受益の価額(原則10年以内)+第三者に対する生前贈与の価額(原則1年以内)-被相続人の債務の全額
遺留分額
=遺留分を算定するための財産の価額×民法1042条に定める割合(1/2または1/3)×遺留分権利者の法定相続分の割合
遺留分侵害額
=遺留分額-遺留分権利者が受けた特別受益の価額-遺産分割の対象財産がある場合には具体的相続分(※)に応じて遺産を取得した場合の当該遺産の価額(ただし、寄与分による修正は考慮しない)+被相続人に債務がある場合にはその債務のうち遺留分権利者が承継する債務の額
※本稿では詳しく触れませんが、未分割の場合に法定相続分で計算するか具体的相続分で計算するか、旧法のもとでは解釈上の争いがありました。この点、新法では具体的相続分とすることが明示され、解釈が統一されました。ただし、具体的相続分とした場合、遺産分割調停と遺留分侵害額請求訴訟が並行するような場合に、具体的相続分の価額が統一されないという問題が依然として残ります。
ただ、文字の羅列ではイメージが掴みづらいと思いますので、以下、具体例に基づいて確認していきます。
Eが亡くなった。相続人は、子のFとGの2人。Eの遺産は自宅マンション(3000万円)、土地(4000万円)と自社株(9000万円)のみ(債務はなかったものとする。)。Eは遺言を残しており、その遺言には、マンションと自社株は後継者たるFに、土地は遠戚のHにそれぞれ遺贈すると記載されていた。また、Eは、相続開始の11年前に、FとGに対しそれぞれ金融資産4000万円を生前贈与していた。
相続開始後、GがFに対し遺留分侵害額請求をした。その際、GはEの介護をしていたので300万円相当の寄与分があると主張した。
遺留分の算定の基礎となる財産の額
=3000万円+4000万円+9000万円
=1億6000万円
FとGへの生前贈与は相続開始10年より前になされているため、前述のとおり、ここでは加算しません。
Gの遺留分額
=1億6000万円×民法1042条に定める割合1/2×Gの法定相続分1/2
=4000万円
本件とは関係ありませんが、直系尊属のみが相続人の場合、民法1042条に定める割合は1/3となります。専門家でも誤解の多いところであるため、念のため触れておきます。
Gの遺留分侵害額
=遺留分額4000万円-特別受益額4000万円
=0円
遺留分の算定の基礎となる財産の額を算定する際には、11年前の特別受益の額は加算しませんでした。しかし、遺留分権利者の遺留分侵害額を算定する際には、年数の制限なく、全ての特別受益財産が遺留分額から控除されます(ここも10年に限定するという議論もあったようですが、受遺者である第三者の保護というのが元々の改正の趣旨であったことから見送られたようです。)。そのため、Gの遺留分侵害額を計算するにあたって、Gに贈与された4000万円が引かれることになります。さらに、遺留分においては、寄与分が考慮されないため(家庭裁判所の審判事項であること、被相続人の意思によるものでないこと等が理由としてあげられます。)、Gの主張する寄与分が存在するか否かに関わらず、300万円が加算されることもありません。
Fへの贈与は考慮されない一方、Gからすると、自らが受けた贈与分は遺留分から引かれ、寄与分も一切認められないわけですから不満が残りそうですが、残念ながら新法によった場合、Gの遺留分侵害額はゼロとなり、Gの請求は認められないこととなります。
逆に言うと、後継者と思われるFから見れば、旧法に比べ、有利な立場になったとも言えそうです。10年という長い期間の経過が必要ではありますが、早めに対策をとっておけば、いざというときに遺留分を請求されづらくなることも考えられるのです。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.