解説記事2021年04月26日 判例評釈 最高裁令和3年3月11日判決の解説−納税者訴訟代理人としての経験から−(2021年4月26日号・№880)
判例評釈
最高裁令和3年3月11日判決の解説−納税者訴訟代理人としての経験から−
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 平川雄士
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 石井裕樹
1. はじめに
最高裁判所は、令和3年3月11日、いわゆる資本の払戻しにおけるプロラタ計算に係る法人税法施行令(以下「施行令」という)23条1項3号の規定は、一定の限度において「法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである」との判断を示し、国の上告を棄却する納税者勝訴の判決を下した(最高裁令和3年3月11日第一小法廷判決(脚注1)。以下「本判決」という)。
筆者らは、本件の納税者訴訟代理人を務め、一審(東京地判平成29年12月6日(脚注2))及び控訴審(東京高判令和元年5月29日(脚注3))に続き、最高裁でも納税者勝訴判決を得た。
司法権の最終審が、租税法分野における施行令(政令)という行政命令を違法無効と判断し、納税者勝訴の判決を下すことは、先例もない極めて異例のことといえる。本判決は、租税法分野における法の支配を文字どおり貫徹したものということができる。
本稿では、筆者らの納税者訴訟代理人としての経験を踏まえて、本判決の解説を試みる(脚注4)。
本稿は、筆者らの個人的見解であり、納税者又は筆者らの所属する組織の見解ではない。また、紙幅の関係上、資本等取引や資本の払戻しの税務上の取扱いの基礎的な点については解説を割愛している。
2. 事案の概要
内国法人である納税者は、デラウェア州法上のLLCであり納税者が持分の100%を継続保有する外国子会社(以下「本件外国子会社」という)から、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度において、それぞれ別個の決議に基づき行われた、①現地会社法上の資本剰余金を原資とする1億ドルの剰余金の配当(以下「本件資本配当」という)及び②現地会社法上の利益剰余金を原資とする5億4,400万ドルの剰余金の配当(以下「本件利益配当」といい、本件資本配当と本件利益配当を併せて以下「本件配当」という)をそれぞれ受けた。
納税者は、①本件資本配当は法人税法(以下「法」という)24条1項3号にいう資本の払戻し(「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」)に該当し、②本件利益配当は法23条1項1号にいう利益配当(「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うもの……を除く。)」)に該当するとして確定申告した。
課税庁は、本件配当の全額が法24条1項3号にいう資本の払戻しに該当するなどとして法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という)をした。そこで、納税者は、本件更正処分の取消しを求めて訴えを提起した。
本件の特徴として、本件外国子会社の本件配当の直前の純資産の部の計数について、現地会社法上の利益剰余金の額はプラスであったが(脚注5)、我が国の税務上の利益積立金額はマイナスであった(簿価純資産価額(施行令23条1項3号イに定義される)が資本金等の額を下回っていた)という点があった(脚注6)。このため、本件資本配当が本件利益配当に先だって行われたとした場合(納税者の確定申告での立場)又は本件利益配当が本件資本配当に先だって行われたとした場合のいずれの場合であっても、税務上の取扱いとしては、①本件資本配当のうちにみなし配当(利益部分の分配)の額となる部分はなく、その全額が法61条の2第1項にいう有価証券の譲渡に係る対価(資本部分の払戻し)の額として取り扱われ、また、②本件利益配当はその全額が利益配当(利益部分の分配)の額として取り扱われることとなる。すなわち、本件利益配当と本件資本配当が別個独立した配当とされ順次行われるのであれば、その先後を問わず、納税者の主張する課税関係となる。他方、本件利益配当と本件資本配当が一つの配当(本件配当)と取り扱われた場合には、本件外国子会社の利益積立金額がマイナスであるとの事実関係の下で、施行令23条1項3号の規定をそのまま適用して計算すれば、国の主張する課税関係となるという事案であった。
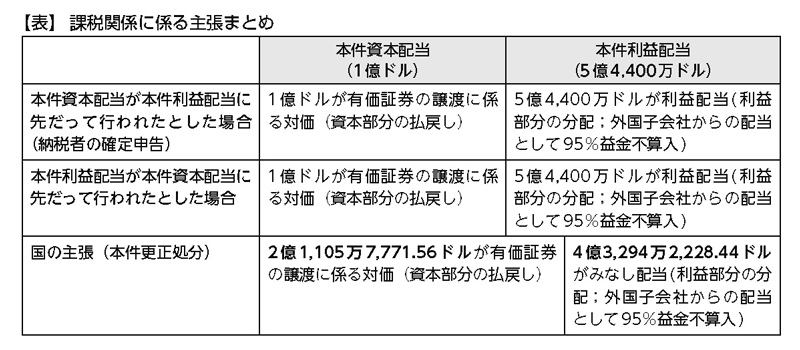
3. 本判決の争点
上告審では、以下の3点が争点となった。
争点①:法24条1項3号の適用上、本件利益配当と本件資本配当が別個独立の剰余金の配当として取り扱われるか(納税者の主張)、それとも併せて1つの剰余金の配当(本件配当)として取り扱われるか(国の主張)。
争点②:争点①が国の主張のとおりに判断されると仮定して、法24条1項3号の解釈上、「資本剰余金の額の減少に伴うもの」に資本剰余金と利益剰余金のいずれを先に減少したものとして計算するかで課税関係に差異が生ずる場合に限って利益剰余金を原資とする部分も含まれるか(納税者の主張)、それとも課税関係に上記差異が生ずるか否かにかかわらず利益剰余金を原資とする部分も含まれるか(国の主張)。
争点③:争点①及び争点②が国の主張のとおりに判断されると仮定して、剰余金の配当直前の利益積立金額がマイナスの場合は、法24条1項3号の剰余金の配当のうち利益剰余金を原資とする部分の一部が、利益部分の分配ではなく資本部分の払戻しとして課税上取り扱われることになるが、施行令23条1項3号の定めは、かかる課税関係となる限りにおいて、法24条1項3号の委任の範囲を超え違法か(納税者の主張)、それとも委任の範囲内であり適法か(国の主張)。
本件更正処分が適法(国の勝訴)となるためには、争点①から③の全てにおいて国の主張が認められることが必要であり、争点①から③のいずれか1つでも納税者の主張が認められれば、本件更正処分が違法(納税者の勝訴)となるという関係にあった。
4. 本判決の判示
本判決は争点②及び争点③のみについて判断を示しており、争点①については明示的な判断は示していない。以下では、各争点の重要性の順に従い、争点③、争点②、争点①の順に解説する。
(1)争点③(施行令23条1項3号の法適合性)について
この争点③においては、施行令は措いて法律自体の立法趣旨を正しく把握し立証(脚注7)することが何よりも重要となる。納税者は、法24条1項3号の立法時の整理が、(i)同号の適用上、剰余金の配当のうち利益剰余金を原資とする部分については、その全額を利益部分の分配(すなわちみなし配当)の額として取り扱うことを想定しており、(ii)かかる取扱いは税務上の利益積立金額がマイナスである場合も同様に妥当し、同号の剰余金の配当のうち利益剰余金を原資とする部分については、課税上もいわば将来における利益を現時点で払い戻すものとして、なおその全額を課税上も利益部分の分配の額として取り扱うことを予定していたと主張した(脚注8)。そして、施行令23条1項3号は、利益剰余金を原資とする部分の一部(本件でいえば、1億1,105万7,771.56ドル)につき、資本部分の払戻しの額として取り扱うことになるが、これは法が全く予定しないことであって、同号はそのような結果となる限りにおいて法の委任の範囲を超え違法無効であると主張した。
本判決は、納税者の上記主張を容れ、法23条1項1号及び24条1項3号の仕組みに照らせば、「法人税法24条1項3号は、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の場合には、そのうち利益剰余金を原資とする部分については、その全額を利益部分の分配として扱う一方で、資本剰余金を原資とする部分については、利益部分の分配と資本部分の払戻しとに分けることを想定した規定であり、利益剰余金を原資とする部分を資本部分の払戻しとして扱うことは予定していないものと解される。」と述べ、結論として「株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令23条1項3号の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。」と判示した。
この争点③について納税者の主張が認められた点が本判決の画期的な点であるが、やはり立法時の整理を一審から証拠力の高い証拠に基づき重厚に論証したことが効を奏したと考えられる。具体的には、上記(i)の主張につき、平成18年度税制改正についての立案担当者による解説(脚注9)その他権威のある諸文献を証拠とするとともに、(ii)の主張につき、やはり立案担当者による解説(脚注10)において、法24条1項3号について「将来利益の払戻しはありうる」が「将来資本の払戻しはありえない」ことが立法の「基本」とされていることや、法23条1項1号の利益配当については利益積立金額がマイナスであってもなお全額が利益部分の分配とされている旨を述べた文献等を証拠とし、その上で、各証拠と適確に結びつけて、法律自体の解釈につき、文理と趣旨という基本中の基本から、納税者の主張を逐一論証した。
(2)争点②(法24条1項3号の解釈)について
争点③において施行令の違法無効という(大胆な)判断が得られない場合に備えて、法令自体の解釈論として納税者の主張を正当化するためには、争点②の主張をするほかないという関係にあった。この点では金子宏名誉教授も納税者の主張と同旨を述べているところであり(脚注11)、争点②の主張も相応の根拠のある主張であると思われたため、納税者は一審でこの主張を展開した。しかし、立法趣旨を直截に示すといえる立案担当者の解説にて「資本剰余金と利益剰余金の双方を同時に減少して剰余金の配当を行った場合には、全体が資本の払戻しとなる」との納税者の主張(及び金子説)に反する解説がされている(脚注12)ところであり、また一審でも争点②に係る納税者の主張は排斥されたことから、控訴審では納税者は争点②に係る主張は行わず、争点①及び争点③に係る主張に焦点を当てる方針を採用した。しかし、控訴審判決は、一審における納税者の争点②に係る主張を拾い上げた上で、これを主たる理由として納税者の主張を認容したことから、ある意味これ幸いと国の上告受理申立て理由で取り上げられ、上告審でもこの点が争点化した。しかして、本判決は、「利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は、その全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するものというべきである。」と判断し、争点②の控訴審判決の判断を否定した。
上記の次第で、納税者は上告審で争点②の主張を主戦場としたわけではなかった。最高裁としても、この争点②に係る控訴審判決の判示は是正する必要があるということで、法令の解釈に関する重要な事項(民訴法318条1項)があると認め、不受理ではなく受理した上で、結論は(上記争点③のため)変わらない(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法325条2項)はない)ので上告棄却の判決をしたものと考えられる(脚注13)。
(3)争点①(本件利益配当と本件資本配当が別個独立の剰余金の配当か否か)について
納税者は、法24条1項3号の「資本剰余金の額の減少に伴うもの」との文言における「もの」は「剰余金の配当」を意味するところ、かかる「剰余金の配当」とは会社法等の私法からの借用概念であり、私法上1つの決議に基づく1つの剰余金の配当を意味すると解釈すべきと主張した上で、本件資本配当と本件利益配当は同日の株主総会で決議されてはいるものの、別個独立の決議書に基づき決議されている以上は、私法上ひいては法24条1項3号の適用上、別個独立の剰余金の配当として順次行われたものとして取り扱われるべきであると主張した。また、納税者は、諸般の事情を考慮すれば「配当の全体について私法上も一体のものと評価するのが相当」とする国の主張に対しては、借用概念論を無視し、明文の租税回避行為の否認規定(法132条1項等)によらない私法上の法形式の引き直しにほかならず、違法であると反論した(脚注14)。
争点①は一審から主要な争点となっていたものの、一審判決はこの争点①に触れずに争点③によって請求認容の結論を導いた。一方で、控訴審判決は争点②を主たる根拠として納税者の主張を認めたが、それにとどまらず、その余は「判断することを要しないと解されるが」「念のため」という枕詞を置いた上で、争点①に係る納税者の主張を容れ、本件資本配当と本件利益配当は、私法上ひいては法24条1項3号の適用上、別個独立の剰余金の配当であると判断した。
さて、本判決は、冒頭の事実摘示において、「資本剰余金及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当(以下『本件配当』という。)」と表記し、あくまでも1つの剰余金の配当(本件配当)の原資のみが異なる旨を摘示するとともに、6の段落でも「本件配当の全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するとした」本件更正処分の事実認定を前提とする説示をしており、本件利益配当と本件資本配当は原資を異にするものの1つの配当(本件配当)であるとの判断を示したようにも読める。しかし、争点①も国の上告受理申立て理由の1つであり、かつこの点は受理決定で排除されていない(本判決冒頭にも「排除されたものを除く」との記載はない)から、争点①も上告審の審判対象となっているはずのものである。その上で、本判決は、争点②及び争点③については判断を明示しておきながら、7の段落に「その余の点について判断するまでもなく」との説示を加えている。これらに鑑みれば、結局、本判決は、争点①について(上告受理申立ては受理したものの)判断を示さなかったと読むのが正しいように考えられる。すなわち、上記の本件利益配当と本件資本配当は原資を異にするものの1つの配当(本件配当)であるとの判断を示したかのように読める判示部分は、仮に本件更正処分の事実認定に立って(すなわち争点①に係る国の主張を認めたと仮定して)判断したとしても、争点③で納税者の主張を容れる以上は上告棄却という結論は変わらないことを前提に、争点③を判断するためのいわば仮定の前提事実を摘示したにすぎないものと考えられる(その意味では、本判決の判断は一審判決とほぼ同じであるといえる。)。もっとも、争点①を理由として結論を下すほうがある意味「楽」と思われるにもかかわらず、最高裁が上記のような立場を取ったことの理由は明らかではない(脚注15)。
5. 本判決の意義と勝因
本判決と同様の判断を結果的に示したことになる一審判決については、実務家により「衝撃」(脚注16)、「珍しい」(脚注17)などと形容されていたところである(脚注18)。裁判所としても、租税法の政令の法逸脱による違法無効を理由に納税者を勝訴させることは、諸々の波及的効果も大きく、躊躇を感じるであろうことは実務家の共通認識であったといえよう。当時は、一審判決は偶々の特異な地裁レベルの判断にすぎず、上訴審で取り消されるだろうと感じた向きが多かったのではないか。実際、租税法の政令の法逸脱が主張され、その主張が排斥された事例こそ多数あるものの(脚注19)、納税者の主張が認められかつ納税者の勝訴が確定した先例は見当たらない(脚注20)。
しかしながら、本件では一審、控訴審及び上告審を通じ一貫して納税者が勝訴している。振り返って勝訴の要因を検討すると、紙幅の制約で抽象的に表現するほかないのであるが、法律自体の立法趣旨の徹底した調査と証拠とする各種文献の特定といった基礎的な作業を愚直に実践した上で、法律の関連規定の文理と趣旨という基本中の基本から、証拠を具体的に引用して丁寧かつ論理立った主張立証を行ったところにあろう(「お作法」どおりのことである)。加えて、本件利益配当と本件資本配当のいずれが先に行われたかで課税関係が異なるという先後関係の問題に対処するということが法24条1項3号の立法趣旨である(脚注21)にもかかわらず、本件更正処分によれば、本件利益配当と本件資本配当のいずれが先に行われたとしても決して生じ得ない課税関係が生じることになり(上記【課税関係に係る主張まとめ】参照)、これは背理に他ならないという結論の不当性を端的に指摘したことも勝因の1つといえよう。
得てして、最高裁判例というものは、あくまでも事後的に判決書だけ読めば、その判断にしかなり得ないだろうという納得感を感じさせるものである。実際、条例が地方税法に反し違法無効と判断した神奈川県臨時特例企業税事件(最判平成25年3月21日)や告示の一部が地方税法の委任の範囲を超え違法無効と判断したふるさと納税事件(最判令和2年6月30日)といった先行する判例も併せてみれば、本判決は当然の判断であろうと事後的には評価されるのであろう。しかしながら、判決前つまり訴訟係属中の状態の訴訟代理人の立場に身を置いてみるならば、上記で述べた実務界の認識等の状況がある中で、本件において、納税者側で、政令の違法無効という主張につき最高裁を説得して勝ち切るということが、決してハードルの低いことではなかったことは、ご理解いただけるのではないだろうか。
本判決は、今後も政令の規定の文言に起因する租税争訟において、納税者側で先例として援用されていくことになると思われる。納税者が政令の法逸脱による違法無効を主張する(脚注22)上で鍵となる点は、政令の規定によれば単に社会通念上ないしは実態として不合理な結論となるということを超えて、法律自体が、文理及び立法趣旨に照らし、政令の規定に基づく結論を予定又は容認していないとまでいえるのか、そのような立法趣旨を示す証拠はあるのかという点といえよう。この意味において、本判決が出たからといって、納税者側において生兵法というべき援用の仕方にとどまるのでは、実を挙げることはなかなか難しいのではないか。
6. おわりに
以上のとおり、本判決は、争点③についての判断をもって、租税法分野において、司法による行政命令の統制を現実のものとし、もって法の支配を貫徹したものである。その法の支配に則り、違法無効とされた施行令の部分については、行政当局において何らかの是正対応がとられることが期待される。本稿脱稿時点では未だ公式の発表には接していないが、その行く末を見守るとともに、本判決について、租税法学及び実務の両面からの議論が深まることを期待したい。
脚注
1 裁判所ウェブサイト登載
2 資料版商事法務427号104頁
3 前掲注2・90頁
4 納税者訴訟代理人自身が担当した判例等を解説した先例として、山田二郎=大塚一郎編集代表「租税法判例実務解説」(信山社)がある。
5 本件配当の直前に孫会社から本件配当相当額の6億4,400万ドルの利益配当を受けていたことによる。なお、この額は本件外国子会社の税務上の利益積立金額には反映されていない。
6 この状況の現地会社法上の特殊性を指摘する向きも多いが、我が国の会社法においても、前期末においてその他利益剰余金及び利益積立金額がいずれもマイナスである株式会社が、当期の利益を臨時決算により取り込んでプラスとなったその他利益剰余金を原資として剰余金の配当を行う場合には、同じ状況が生じ得るのであり、指摘は当たらない(納税者はこの旨も主張していた。)。
7 法令解釈は事実ではなく裁判所の職責であるので技術的には立証の対象ではないが、租税訴訟においては法令解釈に係る主張を支える証拠が納税者のみならず国からも提出されるのが実務上一般である(ここにいう立証とはそのような意味である)。
8 上告受理申立て手続においては、相手方(納税者)は、申立人(国)の上告受理申立て理由書に対する反論の書面を提出する必要はないものの、納税者は、自主的にかかる反論の書面を提出していた(納税者側では実務上むしろ通常の対応であると思われる。もっとも材料は控訴審までに主張立証された事柄である)。なお、仮に受理決定の上で口頭弁論が開かれる場合は、答弁書を提出する必要が生じる。
9 佐々木浩ほか「平成18年版改正税法のすべて」256頁〜262頁
10 佐々木浩ほか「平成19年版改正税法のすべて」362頁
11 金子宏「租税法(第23版)」225頁
12 佐々木・前掲注9・256頁
13 武藤貴明「最高裁判所における民事上告審の手続について」判タ1399号70頁参照。
14 控訴審判決はこの主張を容れた判示をしているところである。
15 推測の域に留まらざるを得ないが、本件利益配当と本件資本配当が私法上別個独立の配当であるとしても、その別個独立の配当が(瞬時の時間差ではなく)同時に行われたとみる余地も否定はできないとすれば、その場合には同じ問題が生じ得るということを慮ったのかもしれない。
16 佐藤修二「法人税法施行令を違法・無効とした判決の衝撃」税務弘報66巻9号139頁
17 小島義博ほか「判批」TAX LAW NEWSLETTER2018年7月号5頁
18 代表的な租税法学者による評釈として、谷口勢津夫「判批」ジュリ1531号188頁
19 東京地判令和3年3月16日、東京地判令和2年12月1日、大阪高判平成29年3月17日、東京高判平成27年2月25日、東京高判平成22年11月17日等。
20 東京高判平成7年11月28日は、法律による委任が白紙委任であったこと(つまりは政省令への委任方法)を理由として施行令及び施行規則が無効とされた事例であり、政令が法律による委任の範囲内であったか否かが争われた事例というわけではない。
21 長井伸仁「大規模法人に対する審理上の留意事項」租税研究738号99頁〜100頁
22 佐藤英明「租税法律による命令への委任の司法統制のあり方」フィナンシャル・レビュー129号25頁を一般的に参照。
平川雄士 (へがわ ゆうし)
長島・大野・常松法律事務所パートナー。1997年東京大学法学部卒業、1999年弁護士登録、2004年Harvard Law School卒業、2005年ニューヨーク州弁護士登録、2007年〜2017年上智大学法科大学院実務家教授・准教授。IFA(国際租税協会)本部Supervisory Boardメンバー、同日本支部理事・運営委員。公益社団法人日本租税研究協会等における講演・執筆多数。Chambers Asia-Pacific (Band 1),Best Lawyersの2022 Lawyer of the Year - Tax Law - Tokyo等に選出。租税アドバイスおよび租税争訟を主に取り扱い、近時も複数の著名案件での勝訴実績を有する。
石井裕樹 (いしい ひろき)
長島・大野・常松法律事務所アソシエイト。2015年東京大学法学部卒業、2015年東京大学法科大学院(司法試験合格により)退学。著書に『SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価 投資スキームの実際例と実務上の問題点 第7版』(共著、清文社)、『コシダカによる本邦初の適格株式分配を利用したスピンオフ上場の解説』(共著、旬刊商事法務(No.2227))など、多数。租税アドバイスおよび租税争訟を主に取り扱い、複数の税務争訟に主体的に関与している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















