解説記事2021年05月03日 判例評釈 外れ馬券訴訟をめぐる最近の動向−東京高裁令和2年11月4日判決の検討−(2021年5月3日号・№881)
判例評釈
外れ馬券訴訟をめぐる最近の動向
−東京高裁令和2年11月4日判決の検討−
岩田合同法律事務所 弁護士・東京大学客員教授 佐藤修二
岩田合同法律事務所 弁護士 野口大資
東京高等裁判所は、近時、馬券の払戻金の所得区分について、納税者の主張を認めて雑所得に該当するとした第一審判決(東京地判令和元年10月30日裁判所ウェブサイト掲載。以下「原判決」という。)を取り消し、課税当局の主張を認めて一時所得に該当するとの判決を下した(東京高判令和2年11月4日公刊物未登載。以下「本判決」という。)。
いわゆる外れ馬券訴訟としては、最判平成27年3月10日刑集69巻2号434頁(以下「平成27年最判」という。)および最判平成29年12月15日民集71巻10号2235頁(以下「平成29年最判」という。)が著名である。二つの最高裁判決はいずれも、馬券の払戻金が雑所得に該当し、外れ馬券の購入金額も必要経費に該当すると判断した。筆者らのうち佐藤は、かつて、これらの最高裁判決について一文をものした経緯から(脚注1)、編集部より、本判決について執筆をすることのお勧めをいただいた。そこで、本稿では、最高裁の二つの判決との比較の観点を交えて、本判決について検討してみることにしたい。
1. 事案の概要
本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)を得ていた納税者(原告)が、平成24年分から平成26年分までの所得税について、本件競馬所得を一時所得として確定申告した後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき事由がない旨の通知処分を受けたことから、かかる通知処分の取消しを求める事案である。
2. 争 点
本件の争点は、本件競馬所得の所得区分が一時所得か雑所得かであり、具体的には、本件競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に該当するか否かが争われた。
3. 判決の概要
原判決は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当であるという、平成27年最判および平成29年最判が提示した判断基準の下、本件競馬所得が雑所得に該当すると判断した。
具体的には、原判決は、原告が、平成22年以降の5年間のうち4年間で、年間を通して利益を上げており、その金額は約516万円から約1376万円に及ぶこと、平成24年に約790万円の損失が生じているものの、同年の回収率(馬券の合計購入金額に対する合計払戻金額の比率)は、中央競馬(日本中央競馬会が行う競馬)の平成24事業年度の払戻し率(馬券の発売金額に対する払戻金額の割合。約75%)を相当程度超える86.4%を維持していること等を踏まえ、原告は回収率が総体として100%を超えることが期待し得る独自のノウハウに基づき馬券を選別して購入を続けていたということができ、原告の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったと判断したものである。
これに対し、本判決は、判断基準については原判決と同様の立場に立ちつつも、本件への当てはめとしては、本件競馬所得は、一時所得に該当すると判断した。
本判決は、平成24年の約790万円の損失について、1年間というある程度長期間で集計してもなお多額の損失を計上するということは、年間を通じての収支で利益が得られるように馬券の選別が行われる仕組みに大いに疑問を抱かせるものであり、偶然性の影響が減殺されていないことを推認させるといった理由を挙げて、納税者において回収率が総体として100%を超えることが期待し得る独自のノウハウを有していたとは認められないとして、客観的にみて営利を目的とするものであったとはいえないと結論付けている。
4. 検 討
本判決は、平成27年最判および平成29年最判と同じ判断基準を用いており、法律論のレベルでは、最高裁の考え方と軌を一にしたものであるといえる。しかし、具体的な事件の解決としては、これらの最高裁判決とは異なり、結論として一時所得に該当するとした。雑所得ではなく一時所得であると判断したポイントはどこにあるのであろうか。試みに、平成29年最判の調査官解説で用いられた表(脚注2)を参考に、本判決と、平成27年最判および平成29年最判とを対比してみると、次頁の表のとおりである。
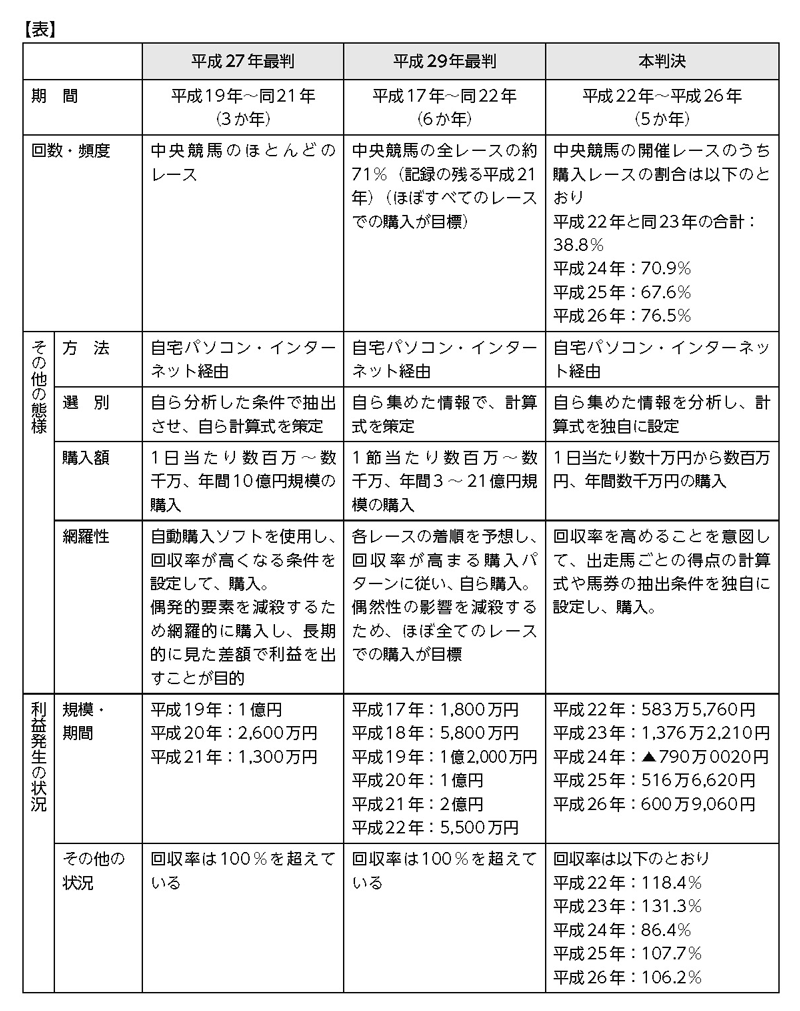
本件の事案と平成27年最判や平成29年最判の事案との差異としては、平成24年の回収率が100%に満たず、損失を発生させている点や、馬券を購入する回数・頻度が低い点が挙げられる。
所得税法34条1項にいう営利目的とは、馬券を購入する者が主観的に利益を上げる目的を有していただけでは足りず、客観的に見て利益が上がると期待し得る馬券購入態様であることをも要すると解される(脚注3)。本判決は、平成24年に損失が生じており、その額も平成22年、平成25年および平成26年の利益の額を上回ることを指摘した上、このように1年間というある程度長期間で集計してもなお多額の損失が生じたという経緯をもって、納税者の購入態様では偶然性の影響が減殺されていないことを推認させる一事情であるとしている。これは、馬券の払戻金を得ることがそもそも偶然性を有することを踏まえ、客観的に見て利益が上がると期待し得る馬券購入態様であるといえるためには、偶然性の影響を減殺しているといえるかどうかを重視するものであろう。実際、平成27年最判および平成29年最判においても、馬券購入者がほぼすべてのレースについて購入していること(ないしは、その意思があること)を認定しており、これは、偶然性を減殺するためにはできるだけ多くのレースについて購入する必要があることを前提としたものと思われる。偶然性の影響を減殺する購入態様であるかという点は、平成27年最判および平成29年最判と共通する重要な視点であるといえよう。
この点について、納税者は、年ごとに回収率100%という基準を満たすかどうかではなく、購入期間総体として観察すれば足りると主張していた。これは、平成29年最判では、客観的に見て営利を目的とするものであったということを認定するに当たり、「回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきた」と評価し、また、平成29年最判を受けて改正された所得税法基本通達34.1も、「回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らか」であることを雑所得該当性の考慮要素の一つとしていること(強調はいずれも筆者らによる。)に依拠したものと推察される。しかし、本判決は、かかる主張を認めなかった。この点、考え方は分かれるところかもしれないが、結果的に対象期間総体の回収率が100%を超えていたとしても、たまたまいずれかの年に多額の利益を上げただけであれば、そのような購入態様に営利性が認められるのは不自然であるから、本判決の判断に違和感はない。期間総体として100%を超えていることをもって、直ちに営利性が認められるものではなかろう。
もっとも、本判決は、平成24年の損失理由によってはこの損失の事実を除外して評価することも考えられるが、本件では、原因が不明であるため、損失の事実を除外しての評価をすることもできない、と指摘している。このような指摘に照らすと、本判決の考え方によっても、回収率が100%に至らなかったことにつき合理的な説明がなされ、損失が特別な事情によるものと評価される場合であれば、対象期間中のすべての年において回収率100%を超えていないとしても、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として認められる可能性も残る。
なお、本件では、平成27年最判および平成29年最判と比較すると、購入額が少額であるという点に特徴があり、国は、雑所得と認めない根拠として、この点を主張していた。しかし、原判決は、本件の納税者の購入額は、一般的な競馬愛好家と変わらないほどの額にとどまるものではない、と指摘して、平成27年最判および平成29年最判の事案との購入額の差異を重視しなかった。本判決も、この点については、原判決の判断を踏襲している。思うに、偶然性の影響の減殺のためにはそれなりに多くのレースについて購入する必要があると考えられることに照らせば、購入額は、必然的にある程度の多額になるはずであり(本件での購入額も、一般的な感覚からすれば、多額と言えるのではないだろうか)、ある程度多額であることを前提とすれば、その中での多少の購入額の多寡は重要ではないと思われ、本判決の立場が妥当であろう。
5. 結びに代えて
今回、原判決および本判決に触れる機会をいただいて感じられたことは、馬券払戻金の課税関係について、法解釈のレベルでは、平成27年最判および平成29年最判によって示された判断基準が定着する一方で、その判断基準の具体的当てはめについては、なお判断が分かれ得る現状にあるようだ、ということである。法解釈論のレベルでルールが帰一しつつあることは好ましいものの、結論について裁判所によって判断が分かれることは、課税関係の安定性や社会全体のコストという面から見ると、問題があるのかもしれない。もっとも、この点について、裁判所には、責任はない。それは、司法判断というものは、ルールに事実を適用して結論を導き出すという本質を有するから(いわゆる法的三段論法)、ルールが帰一したとしても、事実関係が異なれば結論は当然に異なるという宿命を有するためである。その意味では、馬券払戻金について、少なくとも一定の場合には一時所得として課税する(=少なくとも一定の場合には外れ馬券購入費の経費計上を認めない)というルールを採用する限り、その一定の場合が何であるのかについて、ケース・バイ・ケースで司法判断が分かれることは、防ぎようがないのである。もし、馬券払戻金の課税関係を現在よりも安定したものにしようとすれば、立法による解決が必要なのであろう。筆者らは、個別事案の解決を旨とする法曹実務家であり、制度論に長けた者ではないが、本件は、そのようなことを思わせる事案ではあった。
脚注
1 佐藤修二「外れ馬券訴訟の総括−求められる税務と法務の『コラボ』」税務弘報2018年6月号65頁以下。
2 三宅知三郎「判解」法曹時報71巻5号196頁。
3 三宅・前掲(注2)195頁。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年東京大学法学部卒業。2000年弁護士登録。2005年ハーバード・ロースクール卒業(LL. M.,Tax Concentration)。2005年〜06年Davis Polk & Wardwell LLP 勤務。2011年〜14年、東京国税不服審判所国税審判官。2019年〜東京大学法科大学院客員教授。
【主な著作】
『税理士のための会社法ハンドブック〔2021年版〕』(編著、第一法規、2021)、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)、『実務に活かす! 税務リーガルマインド』(日本加除出版、2016)など。
野口大資(のぐち だいすけ)
2016年大阪大学法学部卒業。2018年東京大学法科大学院修了。2019年弁護士登録。株主総会対応その他会社法に関する相談業務、租税訴訟その他の争訟案件等、幅広い業務に従事している。
【主な著作】
『税理士のための会社法ハンドブック〔2021年版〕』(共著、第一法規、2021)、「会社法改正を踏まえた株主総会対応の留意点<上>」資料版商事法務442号(共著、2021)、「外国籍パートナーシップ持分のクロス・ボーダー現物出資と課税−塩野義製薬事件東京地裁判決の検討−」T&Amaster837号(共著、2020)など。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















