解説記事2019年12月02日 解説 デジタル課税「Pillar2:税源浸食対抗税制-グローバル・ミニマム・タックスと税源浸食支払否認規定」のポイントと理論・実務上の問題点(2019年12月2日号・№813)
解説
デジタル課税「Pillar2:税源浸食対抗税制-グローバル・ミニマム・タックスと税源浸食支払否認規定」のポイントと理論・実務上の問題点
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 南 繁樹
第1 本稿の目的
2019年11月8日に、OECDから、経済のデジタル化に伴う税制上の課題への対応策として、「第2の柱(Pillar 2)に関する提案-税源浸食対抗税制」(Global Anti-Base Erosion Proposal(“GloBE”))が公表された(以下、「公開協議文書」という。)。本稿は、公開協議文書の概要を説明し、その問題点を指摘するものである。なお、Pillar 1に関する統合提案に関しては、本誌810号4頁以下「デジタル課税『Pillar 1:多国籍企業の利益の配分』のポイントと理論・実務上の問題点」を参照されたい(脚注1)。
OECD提案のうちPillar 2は、多国籍企業グループによる、低税率国に子会社を設置して課税ベース(所得・利益)を低税率国に移転させ、グローバルベースでの税負担を軽減する手法を防ぐことを目的とする。端的にいえば、タックス・ヘイブンに移転された所得に対して課税することで、タックス・ヘイブンの存在意義を消滅ないし低下させることが目的である。具体的な対策として、第1に、全世界、国又は事業体単位で最低税率を設定し、国外所得に対する実効税率が最低税率以下である場合に多国籍企業グループに合算して追加課税を行う方法が提案されている(ミニマム・タックス)。具体的な最低税率は、まだ明らかにされていない(最終的にはアイルランドの法人税率である12.5%になると予想する見解がある(脚注2)。)。第2に、高税率国から低税率国に課税所得を移転するような支払に関し、個別的に損金算入否認や源泉税課税を行うことにより、支払国において課税を行う方法が提案されている(税源浸食支払否認規定)。
公開協議文書は、多国籍企業グループ一般を対象とし、その範囲を限定していない。したがって、その対象は、GAFAを典型とするいわゆるデジタル企業に限られているわけではなく、また、Pillar 1のAmount Aのように「消費者向けビジネス(“consumer-facing businesses”)」に限られているわけでもない。したがって、Pillar 2は、世界的に事業を展開する企業一般に適用がある可能性があることに留意する必要がある。最終的な合意は、Pillar 1と同様に、2020年末が予定されている。
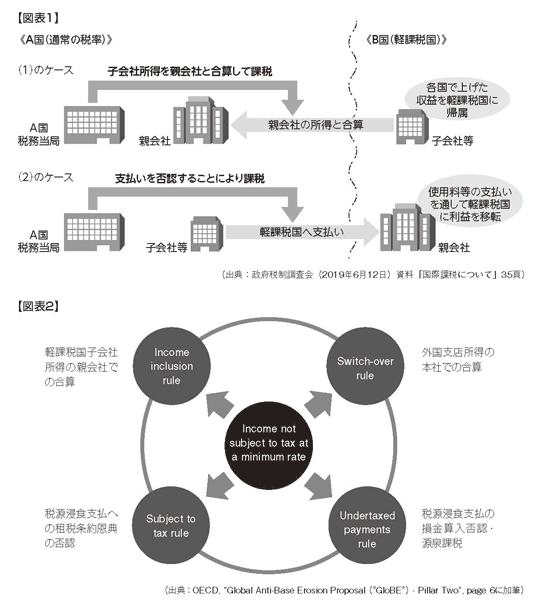
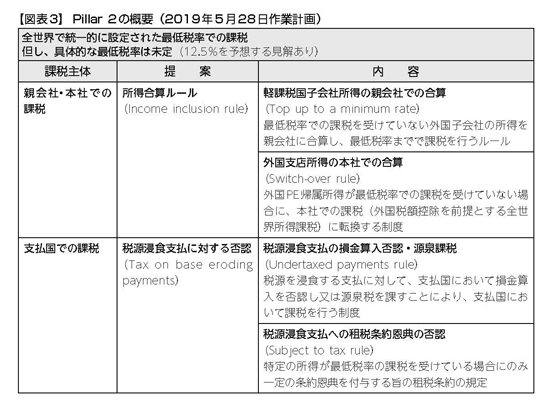
第2 Pillar 2に関する背景
1 BEPSにおける税源浸食への対抗策
なぜ、いま税源浸食に対する対抗策が提案されているのか。もとより、“BEPS”とは、「税源の浸食と(そのための)利益移転」(Base Erosion and Profit Shifting)を意味するものであり、BEPS プロジェクトの全体が税源浸食に対する対抗策であったともいえるから、BEPS 行動1~15までで完結していたはずではないかとの疑問が生じる。
BEPSプロジェクトを振り返ると、2012年にOECD租税委員会がBEPSプロジェクトを立ち上げ、2015年10月にBEPS最終報告書が公表された。その中には、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)に関する行動3、ハイブリッド・ミスマッチに関する行動2、支払利子の損金算入に関する行動4、さらに、移転価格税制に関する行動8~10が含まれており、税源浸食に対する対抗策は出尽くしていたはずである(脚注3)。これに対し、行動1は「電子経済に係る課税上の課題への対処」を取り上げていたが、2015年の行動1最終報告書では結論が先送りになり、「デジタル経済」への対処が宿題として残されていた。ところが、その後、欧州各国がデジタルビジネスに対する課税(Digital Service Tax, DST)を定める単独立法措置の動きを強めたため、米国もOECDにおける合意形成に傾き、2019年1月ポリシーノートにおいて、Pillar 1として新たなnexusとそれに基づいて利益を配分するルールを策定すべきことが提案され、同年5月作業計画(Programme of Work。以下「作業計画」という。)を経て、同年10月9日公表「第一の柱に関する統合的な提案」(Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One)に至っている。
2 米国税制改革-GILTI及びBEAT
では、なぜデジタル経済に関する報告書であらためて税源浸食が問題になるのか。作業計画は、経済のデジタル化は、(移転が容易な)無形資産の重要性を高め、税源浸食の可能性をより高めることを指摘し、デジタル経済への対処と税源浸食への対処は相互に関連し、相互に強化する効果を有することから、両者を同時に検討すべきであると述べている(パラ5~8)。もっとも、2019年1月のポリシーノートは「経済のデジタル化による課税上の課題は、残されたBEPSの課題に関するより広い視座の一部を占めている」と述べるとともに、「米国税制改革のような最近の進展を反映している」とも述べていた(“These proposals recognise that in part the tax challenges of the digitalisation of the economy form part of the larger landscape relating to remaining BEPS challenges and further reflect more recent developments such as US tax reform.”)(ポリシーノート2頁)。また、本年6月8日に開催された福岡でのG20のIssue Note にも、Income inclusion rule とUndertaxed payment ruleについて「米国のGILTI及びBEAT税制と共通点を見出す人もいるかもしれない(“Some may find similarities between the first and second options and US GILTI and BEAT regimes, respectively”.)」と記載されている(同3頁)。このことからすると、Pillar 2は、米国税制改革によって導入されたタックス・ヘイブン子会社に対するミニマム・タックス(GILTI)(脚注4)や税源浸食支払に関するミニマム・タックス(BEAT)(脚注5)に触発されたのではないかと思われる(脚注6)。その意味で、経済のデジタル化による税源浸食の可能性が背景にあるとはいえ、Pillar 2の具体案においては、対象をデジタル企業やデジタルに関連する事業に限定しているわけではなく、広く多国籍企業一般を対象としているように思われる(この点は、Pillar 1におけるAmount Bと同様である。)(脚注7)。
3 2019年5月作業計画(Programme of Work)
作業計画において、第二の柱(税源浸食対策税制)として提案されていたのは、以下の2つである(パラ56)。
①「所得合算ルール」(an income inclusion rule)
国際的に最低限の税率を定め、子会社の実効税率が当該最低税率を下回る場合に、当該子会社の所得を親会社に合算して課税する制度
②「税源浸食支払に対する否認」(a tax on base eroding payments)
税源を浸食する支払に対して、支払国において損金算入を否認し又は源泉税等の税を課すことにより、実質的に支払国において課税を行う制度
4 公開協議文書の位置付け
Pillar 2に関しては、所得合算ルールはタックス・ヘイブン対策税制(CFC税制)と制度設計としては類似しており(作業計画パラ59も、所得合算ルールはCFC税制を補完するものである旨を述べている。)、税源浸食支払の否認もハイブリッド・ミスマッチに関するリンキングルールと類似する。したがって、Pillar 1が従来の国際課税の大原則(PEなければ課税なし)に変更を加えるものであったのに比較すれば、従来の制度(少なくとも、BEPS行動計画)の延長線上にあるといえる。このため、制度の概要は作業計画において記載されているところで概ね尽きているともいえ、公開協議文書において斬新な提案が盛り込まれているということはない。
公開協議文書では、専ら「所得合算ルール」(Income Inclusion Rule)における軽課税国子会社所得の親会社での合算(Top up to a minimum rate)の具体的な制度設計について論じられており、外国支店所得の本社での合算(Switch-over rule)、税源浸食支払の損金算入否認・源泉課税(Undertaxed payments rule)、税源浸食支払への租税条約恩典の否認(Subject to tax rule)の具体的な制度設計については論じられていない。但し、実効税率の具体的な測定方法に関しては、公開協議文書の内容が、他の3者に共通する部分があるかもしれない。
第3 今後の日程
Pillar 2については、2019年12月9日に公聴会が予定されている。これらを踏まえ、Pillar 1及びPillar 2について、2020年1月までに概要(outline)について合意し、2020年末までに最終合意に到達することが想定されている。既にPillar 1「多国籍企業の利益の配分」に関する統合案については、本年11月21・22日に公聴会が開催された(なお、それに先立ち提出されたコメントはOECDのウェブサイトで公開されている。)。
第4 Pillar 2公開協議文書の要点
1 Pillar 2の構成
Pillar 2の提案には4つのルールが含まれているが、公開協議文書は「所得合算ルール」(Income Inclusion Rule)のみを取り上げている。したがって、他の3つのルールの詳細は明らかになっていない。公開協議文書は、所得合算ルールに関し、いかに実効税率を計算するかについて、①どのように課税ベースを算定するか、②高税率で課税された所得と低税率で課税された所得の通算(ブレンディング)をどのような範囲で認めるか、③適用除外ないし対象範囲を画する基準をいかに設定するかの3点を中心に論じている。
2 最低税率
作業計画は、適用される最低税率に関し、固定税率を定めるものとする(作業計画パラ64)。この点において、各国の法人所得税率までの課税を行うタックス・ヘイブン税制とは異なる(脚注8)。具体的な最低税率がどのような値になるかが最大の問題であるが、公開協議文書によれば、その数値は、主要な制度要素が完全に確定してから議論されるとされている(パラ9)。上述のとおり、アイルランドの法人税率12.5%が目安になるであろうが、米国のGILTIの税率(10.5%)やBEATの税率(最終的に12.5%)も意識されることになろうか(脚注9)。
3 課税ベースの算定
(1)統一的な課税ベースの重要性
実効税率は、「実効税率=税金÷課税所得」によって求められる。この実効税率の算定における分母となる課税所得の計算について、各国の課税制度に従う場合、透明性のある結果をもたらさないと述べられている(パラ14)。
(2)財務会計データの使用
そこで、公開協議文書は、「課税所得」に関し、財務会計上の規則によって計算された会計上の利益を出発点とし、調整を加えた数値を使用する旨を述べる(パラ16)。分子は、実際の納税義務または会計上発生した税金費用であるとする(パラ16)。
具体的な財務会計データに関し、公開協議文書は、最上位親会社の連結財務諸表作成に使用される会計基準を使用すべきことを示唆する(パラ21)。その際の会計基準として、IFRSのほか、米国GAAPや日本GAAPが例示されている(パラ22)。非上場企業について許容される会計基準の範囲は検討課題とされている(パラ23)。
(3)財務会計データから税務データへの調整
多国籍企業を統一的なミニマム・タックスの対象とするためには、課税ベースの統一が必要になる。そのために調整を行うべき旨が指摘されている(パラ24、25)。
(a)永久差異
財務会計と税務との間に永久差異が生じる場合として、以下のような場合が指摘されている(パラ26~30)。
① 外国法人からの配当金や法人株式の売却益の益金不算入・非課税措置
② 買収された企業の保有する資産の取得価額(会計上、買収時に公正価額で再評価するにもかかわらず、税法上は買収前の取得価額を引き継ぐ場合)
③ 政策的な非課税所得・損金算入の否認(政府債の利子や補助金の非課税措置、交際費・賄賂・罰金の損金算入否認)
(b)一時差異
財務会計と税務との間に一時差異が生じる場合として、減価償却方法の相違、引当金の損金算入・繰越欠損金の取扱い、割賦販売の取扱い、利益の分配に係る税金に関する繰延税金負債が例示されている。一時差異に関しては、下記の3つのアプローチが考えられるとされている(パラ33~44)。
① 超過税金支払と租税属性の繰越(Carry-forward)
さらに、以下の3つの方法に細分化される(パラ34)。
(i)子会社が最低税率を上回って支払を行った場合に、超過分を、翌年以降の最低税率を下回る年度に支払ったものとみなす制度
(ii)子会社が最低税率を下回ったために親会社が支払った税金について、子会社の税金支払が最低税率を超過する場合に親会社の税金から控除する制度
(iii)子会社の営業損失を子会社の財務会計上の利益を減少させる制度
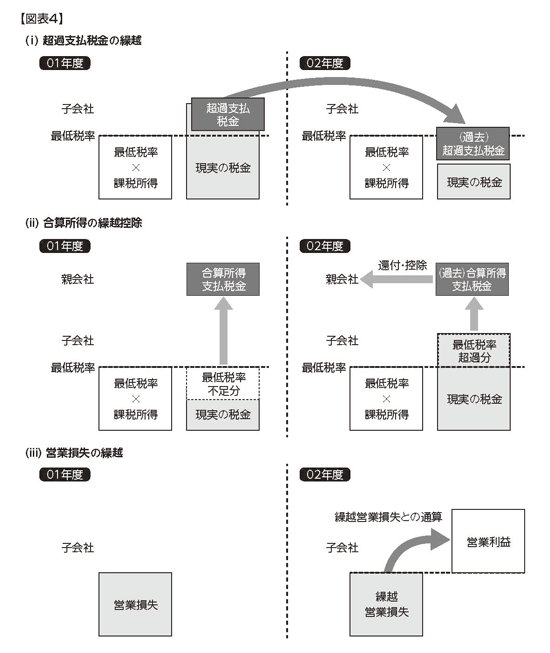
② 税効果会計
税効果会計は、一時差異による実効税率計算の変動を排除している。IFRSなどの会計基準は既に税効果会計を適用しているので、税効果会計に基づいて実効税率計算をすることは、多国籍企業のコンプライアンス負担を軽減させるとしている(パラ43)。
③ 複数年度平均
複数年間の支払税金総額と総所得に基づいて年間実効税率を計算する方法も、簡便との利点を有する方法として挙げられている(パラ44)。
いずれを採用すべきかについて、公開協議文書は結論を出していない。
4 ブレンディング(重課税所得と軽課税所得の通算)
(1)ブレンディングの単位
公開協議文書においては、納税者が同一のグループ内または同一国・地域内の異なる事業体間において、高税率で課税される所得(重課税所得)と低税率で課税される所得(軽課税所得)を通算することをブレンディング(Blending)と称し、どの範囲でブレンディングを認めるかについて詳細に論じている(パラ53~72)。公開協議文書においては、以下の3つが挙げられている(パラ55)。
① 全世界グループでの合算(A worldwide blending approach)
② 国・地域単位での合算(A jurisdictional blending approach)
③ 事業体単位での合算(An entity blending approach)
全世界グループでの合算においても、国外所得を合算するとされているので(パラ55a)、本国分は含まれない。
一般的には、ブレンディングの範囲が広いほど、軽課税所得と重課税所得を通算する可能性が高まり、ミニマム・タックスに抵触する可能性が低下する。ミニマム・タックスの目的からすれば、最低税率を下回る課税を確実に把握する点において、国・地域単位での合算がより適合的である。公開協議文書は、全世界グループでのブレンディングに関し、コンプライアンスコストは低いとしつつ、「(底辺への)課税競争に対する最低限(floor)を設けるという意味では効果が相対的に薄い」(less effective in creating a floor for tax competition)と述べ、全世界グループでの合算に対する賛否を明確にしていない(パラ56)。反対に、事業体単位での合算も、各国税制の下での連結納税やグループ税制の範囲でのブレンディングには肯定的な記載がなされており(パラ58)、それが認められる場合には、国・地域単位での合算との差異は小さい。
いずれの単位を採用するかについては、国・地域単位での合算に対する支持が多いとの報道もなされている。これに対し、低税率国は、ミニマム・タックスのインパクトを小さくすることを望むであろうから、全世界グループでの合算を支持する傾向が強いと思われる(脚注10)。
(2)ブレンディングの個別問題
公開協議文書は、ブレンディングに関し、様々な側面からの問題を論じている。
(a)ブレンディングと期間変動(ボラティリティ)の平準化
公開協議文書は、財務会計と税制の違いによる一時差異に関し、全世界グループ単位でのブレンディングによって緩和される旨を指摘している(パラ60~61)。
(b)連結財務諸表の利用
ミニマム・タックスの計算のために会計上の連結財務諸表を使用することを前提として、国・地域又は事業体単位でブレンディングされた実効税率を基準として最低税率との比較を行うとすれば、分母となる利益の計算において、連結財務諸表から、国・地域単位又は法人単位にまで分解しなければならない。また、その場合には、分子となる税金についても、単に国・地域又は法人に課された税金を使用すればよいとは限らず、連結財務諸表に計上された全世界グループ単位の税金に、調整を加えたうえで、さらに国・地域又は事業体単位に分解する必要が生じる(パラ62)。
(c)支店と本店との通算
本店と支店との間において所得を配分するルールを定める必要があることが指摘されており、税法上の規定に基づく課税所得の配分と同じルールに従うことが示唆されている(パラ63)。
(d)透明(パススルー)な事業体の取扱い
課税上透明として扱われるパートナーシップ等の事業体について、所得を配分するルールに合意する必要があると述べられている(パラ65)。これらの事業体は、所得を構成員に配分するため、事業体が組織された国・地域と構成員が居住者となる国・地域が異なる場合、所得を前者から後者に移転する効果が生じうる。このため、いずれのブレンディング方法においても、事業体の透明性が構成員の課税に及ぼす影響を認識するメカニズムが必要であると指摘されている(パラ65)。
(e)CFC税制により他国で課される税金の控除
全世界グループ単位の合算においては、各国のCFC税制(タックス・ヘイブン税制)において親会社国以外の国で課税が生じた場合にも、その税金は課された税金であるとして、分子の計算に考慮することができる。これに対し、国・地域単位又は事業体単位で合算する場合、たとえば、A国の法人甲に関し、B国のCFC税制においてB国の法人乙に対して課された税金は、あくまでもB国の税金であるので、A国又は法人甲の実効税率は過小評価、B国又は法人乙の実効税率は過大評価されることになる。そこで、この場合、CFC税制に基づいてB国法人乙に課された税金を、所得が発生したものとして扱われるA国又は法人甲において支払われたとみなすとの提案がなされている(パラ70)。
(f)配当その他の分配
グループ全体の連結財務諸表を基礎として利益を計算する場合、グループ法人間の配当は、自動的に消去される。これに対し、国・地域又は事業体単位でのブレンディングを行う場合、会計上は利益に含まれ、税法上は利益に含まれないことがあるので(脚注11)、調整が必要になる(パラ71)。
国・地域又は事業体単位でのブレンディングを行う場合、配当は分母となる利益から除外することができる。その場合は、配当支払に関する源泉税を分子から除外すると、源泉税を考慮できなくなってしまうので、配当を支払った事業体の利益に対する課税として取り扱うこととともに、受領者に対する課税として取り扱うことも検討されている(パラ72)。
5 適用除外(カーブアウト)
Pillar 2の制度の適用範囲について、基準値(threshold)、一般的適用除外(exclusion)及び個別的適用除外(carve-out)をどのように設定するかが検討されている。
(1)個別的適用除外
カーブアウトとして、以下の3つが検討対象とされている(パラ74)。
(a)実質基準による適用除外
BEPS行動5(有害な税慣行への対抗策)の基準に適合した体制及び同様の実質的な観点からの適用除外。これは、優遇税制やルーリングに関し、実質的な活動を行っている限りにおいて便益を与えることを許容するとの考え方であり、それをPillar 2にも採用するか否かが検討の対象とされている。但し、作業計画においても、このようなカーブアウトを設けることはPillar 2提案の政策目的と実効性を損なうと指摘されていた(2.1,3a.)。
この考え方は、わが国タックスヘイブン税制において、経済活動基準において事業実体を有するか否かを判定し、それが充足する限り、会社単位での合算課税の対象とならないのと同様の考慮に基づくものと思われる(脚注12)。
(b)有形資産に対する利益率(A return on tangible assets)に基づく適用除外
作業計画にも、公開協議文書にも理由は記載されていないが、上記利益率が高い場合、有形資産に対する依存度が高いため、無形資産の移転による税源浸食のおそれが小さいことを理由とするものと思われる。
(c)一定の基準値を下回る関連者取引を行うにすぎない関連法人に対する適用除外
(2)一般的適用除外
作業計画及び公開協議文書において、より一般的な観点からの適用場外として、下記の観点からの適用除外が検討対象とされている(パラ75)。
(a)売上高その他の規模に基づく適用除外
(b)利益又は関連者間取引が少額である取引又は法人に関する適用除外
(c)特定のセクター・業種に関する適用除外
上記(a)と(b)は、実際的な観点から採用の見込みがあると思われる。但し、Pillar 1と異なり、具体的な数値には言及されていない。
(c)の特定セクター・業種に関する適用除外についても、具体的なセクター・業種には言及されていない。
(3)検 討
公開協議文書は、上記の個別的・一般的な適用除外の様々な選択肢について逐一検討を加えている(パラ76~84)。事実と状況に基づく個別的な適用除外は納税者に不確実性を与え、税務当局による執行を困難にすると指摘し、消極的に評価している(パラ81)。他方で、客観的な基準に基づく適用除外も、それを立証する文書化が必要である場合、コンプライアンスコストをもたらすと指摘されている。特定のセクター・業種に関しては、Pillar 1においては具体的な言及があったが(採掘業、金融業等)、Pillar 2に関しては特定のセクター・業種への言及はない。
第5 今後のポイント
デジタル課税の文脈でPillar 2が提案されたことには唐突感もあるが、上述のとおり、米国でミニマム・タックスが実現された事実は大きく、私見ながら、Pillar 2の実現可能性は低いとはいえないのではなかろうか。
具体的な制度に関し、実務上、最大の問題は具体的な最低税率がいくつになるかであるが、12.5%ないし15%が想定されつつ、最後まで決まらないであろう。
ブレンディングの範囲については、先進国はミニマム・タックスの範囲が広がる国・地域単位を志向し、途上国は全世界グループベースを望むであろう。これに対し、納税者の観点からは、①そもそもミニマム・タックスに抵触する可能性と、②コンプライアンス・コスト(事務負担)の2点が問題になろう。全世界グループ単位であるとしても、本国分は含まれないとみられるので(パラ55)、日本で約30%の法人課税に服しているからといって、ミニマム・タックスへの抵触の可能性がないとは必ずしもいえない。まして、国・地域や事業体単位であれば、該当するケースは十分に考えられる。また、全世界グループ単位でも、国・地域単位でも、実効税率計算のために、相殺消去されていた勘定科目を復活させ、新たに調整計算を行わなければならない場合が生じ、事務負担が生じる。
Pillar 2の影響がどこまで及ぶかは、税率とブレンディングの範囲の組み合わせ次第であり、未知数である。Pillar 2はコンセプトとしてはタックス・ヘイブン税制に類似するとはいえ、現地国で実際に生産・販売活動を行っていても、それを理由とする適用除外が認められないとすれば、企業によってはその影響は大きい。東南アジアや東欧等に現地工場を有している日本企業は多数あり、投資優遇税制の恩恵を受けている場合も少なくないと思われる。それらに対してPillar 2の適用を受ける場合には、追加課税の額は大きなものとなる可能性があり、投資採算性の見直しが必要となる場合があるかもしれない。
特定セクター・業種による適用除外については、税源浸食の当否に関し業態が影響するとは考えにくいように思われる(脚注13)。
以上から、特に注目を要するポイントは、以下のようになろう。
・具体的な最低税率
・ブレンディング(最低税率を測定する単位)
・課税ベース(財務上の数値か、連結財務諸表からどのような調整を行うのか)
・複数年の調整(繰越、税効果会計、複数年平均)
・基準値(売上高)
・個別的適用除外(実質基準の採用の有無)
・一般的適用除外(特定セクター・業種)
コンプライアンスの問題として、従来の会計・税務の複数の帳簿管理に加え、さらに、ミニマム・タックス用の別のアカウントを作成することが必要になるとすれば、作業負担は増大するものと思われる。
脚注
1 本稿の執筆に際し、キヤノン株式会社理事・経理本部税務担当上席菖蒲静夫氏および東レ株式会社税務室長栗原正明氏から貴重な示唆をいただいた。記して感謝する。もちろん、本稿にありうべき誤りはすべて筆者のみの責任に属する。
2 米国共和党の税制政策に影響力を有すると言われているグリーンバーグ・ジョージタウン大学教授の発言(2019年10月29日日本経済新聞朝刊)。なお、公開協議文書の付録Aの「例」では15%の最低税率が使用されている。
3 わが国においても、2015年税制改正による損金算入外国子会社配当の益金算入(法人税法23条の2第2項1号)、2017年税制改正によるタックス・ヘイブン税制の抜本的改正(租税特別措置法66条の6)、2019年税制改正による過大支払利子税制の厳格化(同法66条の5の2第1項)及び移転価格税制における価格調整措置の導入(同法66条の4第8項)等、BEPS最終報告書に沿った税制改正が行われた。
4 米国外軽課税無形資産所得(Global Intangible Low-Taxed Income)に対する合算課税制度。外国子会社(Controlled Foreign Corporations, CFC)が認識する課税所得を、配当の有無にかかわらず、毎期米国株主側で合算課税するという制度。
5 税源浸食濫用対策税制(Base Erosion and Anti-Abuse Tax)。外国関連者に支払う費用項目を損金不算入として課税所得を再計算し、これにBEAT適用税率を乗じ、その結果算定されるBEAT修正法人税が通常の法人税を上回る場合に超過額をBEATミニマム・タックスとして課す制度。
6 政府税制調査会(2019年6月12日)における岡村忠生京都大学教授及び安居孝啓財務省主税局国際租税総括官発言参照。なお、岡直樹「BEPSポリシーノートから読み解くデジタル課税国際合意の方向性」は、英国の新型IP税(2019年4月6日に発効したOffshore Receipts tax)も、Pillar 2に影響していることを指摘する。
7 但し、セクター・業種による適用除外は今後の検討課題とされている。
8 租税特別措置法66条の6第1項参照。
9 BEATの税率は2018年1月1日以後の課税年度について5%、その後10%に引き上げられ、2016年1月1日以後に開始する課税年度において12.5%に引き上げられる。
10 2019年11月9日朝日新聞朝刊
11 法人税法23条及び23条の2参照。
12 外国関係会社が当該所在地国に所在することの経済的合理性があるか否かについて、事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準/所在地国基準によって判定される(租税特別措置法66条の6第2項3号)。
13 Pillar 2が、タックス・ヘイブン国のオフショア金融センターとしての役割をいかに評価しているのかは、必ずしも明らかではない。
南 繁樹 (みなみ しげき)
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士、東京弁護士会:1997年登録(49期)
E-mail:shigeki_minami@noandt.com
1994年東京大学法学部卒業。1997年東京弁護士会登録。2003年New York University School of Law卒業(会社法・租税法LL.M)。東京大学法学部非常勤講師(法と経済学)、神戸大学法科大学院客員教授、上智大学法科大学院非常勤講師、LEC会計大学院客員教授(いずれも租税法)。2017年~2018年IFA(国際租税協会)Asia-Pacific Chair。経済産業研究所「これからの法人に対する課税の方向性」プロジェクトメンバー。専門はM&A及び税務。税務の経験分野は、移転価格税制、国際的組織再編、租税条約、源泉所得税、法人税全般、金融商品、相続税等の全般に及ぶ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















