解説記事2021年09月20日 ニュース特集 令4改正・経産省重要要望事項の行方(2021年9月20日号・№898)
ニュース特集
D課税法制化、投資簿価修正・買収プレミアム問題、子会社配当の源泉徴収
令4改正・経産省重要要望事項の行方
令和4年度税制改正に向け、今年も各府省庁からの税制改正要望が出揃ったが、その中で企業の高い関心を集めているのが、経済産業省が要望している、OECDが7月に公表したデジタル課税に関するステートメントを受けたデジタル課税・第2の柱(ミニマム課税)の法制化に伴う外国子会社合算税制(CFC税制)の簡素化と、令和4年4月1日から施行されるグループ通算制度における投資簿価修正の見直しだ。このうち投資簿価修正の見直しは、通算子法人を買収した際の買収プレミアム相当額が当該通算子法人の離脱時に株式の譲渡原価に算入されないという仕組みの見直しを求めるものであり、現行の仕組みのままでは機動的な事業再編の足かせになりかねないとの懸念に基づいている。この投資簿価修正の取扱いは一般紙でも取り上げられるほど企業の間では問題化している。
ただ、本誌の取材によると、いずれの要望事項も令和4年度税制改正での実現に向けたハードルは高い。本稿では、改正に向けての課題、改正議論の行方など、本誌でしか読めない独自情報をお伝えする。
一方、経済産業省及び金融庁が共同で要望しているものの、いずれの省庁においても重点課題としてクローズアップされていないため見落としがちだが、令和4年度税制改正に向け、完全子法人株式等に係る配当の源泉徴収の不要化が要望されている。この要望は会計検査院の指摘を受けたもので、益金不算入とされる完全子法人株式等に係る配当を源泉徴収するという、いわば“法人税の前払い”をやめるよう求めるもの。こちらは改正実現に向け特段の障害は見当たらない。改正により生じる実務への影響について解説する。
デジタル課税・第2の柱導入に伴うCFC税制の簡素化
ステートメントの「2022年法制化」を「2022年“度”法制化」と解釈
右記の通り、経済産業省の令和4年度税制改正要望では、外国子会社合算税制(以下、CFC税制)の簡素化に言及している。その背景にあるのが、デジタル課税・第2の柱(以下、ミニマム課税)の国内法制化だ。
〇経済のデジタル化等に対応した新たな国際課税制度への対応(抜粋)
2021年10月の最終合意やその先の国内法化に当たっては、諸外国の動向も踏まえて、実体ある経済活動を行う企業に対する控除措置や既存の類似措置(外国子会社合算税制)の簡素化等を通じて、日本企業に過度な負担を課さないように配慮しつつ、国内外の企業間の公平な競争環境を整備し、日本企業の国際競争力の維持及び向上につながるものとする。
経済産業省が8月19日に公表した「デジタル経済下における国際課税研究会中間報告書」(以下、中間報告書)では、紙幅を割いてミニマム課税とCFC税制の関係について説明している(図表1、2参照)。具体的には、第2の柱とCFC税制には重なり合う部分があると指摘した上で、「CFC税制については、租税回避目的以外には事業活動上の経済合理性が乏しい行為に限定して例外的に適用する方向で、最低税率課税とCFC税制の役割分担を明確化することが考えられる」とある(中間報告書15頁「(2)最低税率課税の導入を見据えたCFC税制の簡素化の方向性」参照)。中間報告書について報じた一般紙では、外資系企業に対する課税強化を示唆する部分に着目した記事が目立ったが、日本企業からすれば、このCFC税制部分こそが核心部分と言える。
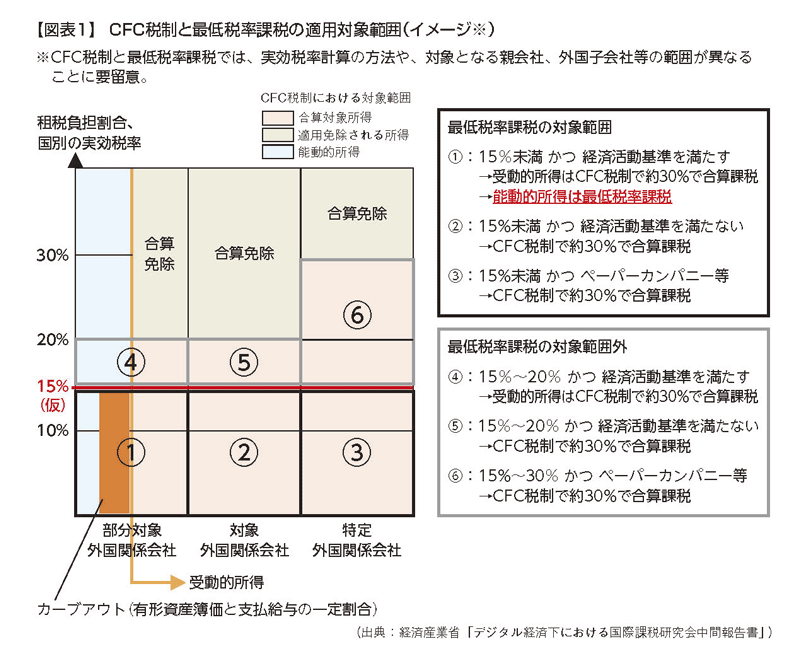
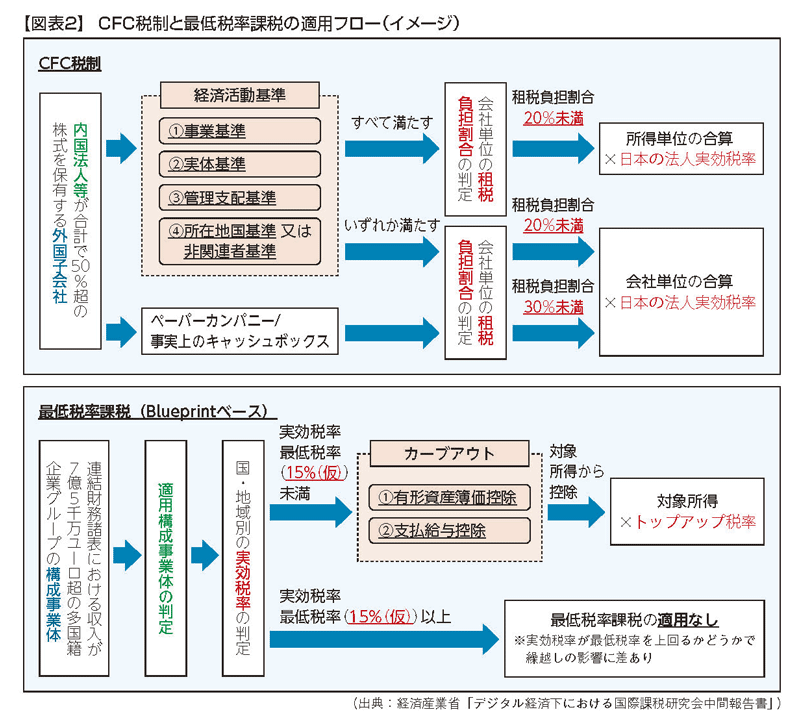
中間報告書の内容を踏まえると、CFC税制の簡素化に向けた議論は、同税制とミニマム課税の重複部分にフォーカスしたものとなろう。ミニマム課税の国内法制化を令和4年度税制改正で実現するのは事実上困難と言える。
OECDが7月に公表したデジタル課税に関するステートメントには、ミニマム課税に係る施行のタイミングについて、「2022年の法制化(brought into law)」との記述がある。これを文字通り解釈すれば、令和4年度税制改正で導入を決め、2022年前半の通常国会で成立させる必要がある。しかし、予定通り10月に最終合意に達したとしても、そこから短期間で国内法制化を仕上げるのは無理との指摘が企業側から聞かれたところだ(本誌891号10頁参照)。
日本の財務省もこのスケジュールがタイトであることは理解していると思われ、国内法制化の本命は令和5年度税制改正との認識が既に広まりつつある。「2022年の法制化」を明記するステートメントとの整合性の問題については、日本では法人税を暦年ベースではなく4月から開始する「事業年度ベース」で考えるのが通常であるため、「ステートメントにおける2022年とは、2022年“度”と解することも可能ではないか」との意見が聞かれる。これによれば、令和5年度税制改正で導入を決め(2022年12月頃)、翌年の通常国会で3月末に法案を可決・成立させれば(2023年3月頃)、「2022年(度)の法制化」というステートメントの要求は満たすことができるという解釈が成り立つことになる。
令和4年度改正では大綱に「簡素化」との文言が入るかに注目
とはいえ、令和4年度税制改正では何も議論しないということにはならない。
法制化が令和5年度税制改正ということになれば、今年の年末にかけた議論の焦点は、令和4年度与党税制改正大綱でCFC税制について何をどこまで書き込むのか、ということになる。振り返れば、BEPS行動3(CFC税制の効率化)を踏まえた平成29年度改正においても、その前年の平成28年度与党税制改正大綱でCFC税制の改正の方向性(あるいは論点)が打ち出されたことが議論のスタートとなった。企業サイドとしては、令和4年度与党税制改正大綱でミニマム課税に言及するのであれば、CFC税制について「簡素化」との文言を何とか盛り込みたいところだろう。
企業は租税負担割合30%基準の見直し、パテントボックス制度創設に期待
とりわけ、平成29年度改正で導入された租税負担割合30%基準の見直しへの期待が高まっている。当該割合が28%や29%などの米国子会社等が、「租税回避目的」で設立されているとはとても言い難いからだ。
また、中間報告書では、米国におけるFDIIや欧州におけるパテントボックス制度にも触れつつ、「我が国に無形資産を保持、集積することが必ずしも経済合理的ではないという現実を深刻に受け止め、我が国における具体的な取組について検討を深めていくことは急務である」としている。ミニマム課税(ムチ)の導入は不可避としても、日本企業に対する別途の支援措置(アメ)が必要ということだ。企業からは、パテントボックス等について検討することを示唆するこの部分への注目が集まっている。研究開発を行うこと自体への支援が研究開発税制、研究開発の成果物たる知的財産権の商業化に対する支援がパテントボックス等とすると、後者の創設を主張すると前者の縮減という議論にもなりやすく、なかなか正面から取り上げられて来なかったテーマと言える。本誌取材によると、パテントボックス等がこの年末に議論されることはない見込みだが、採用の可否はともかく、将来的には検討の俎上の載ることは十分に考えられよう。
グループ通算制度における投資簿価修正の見直し
分割との整合性に課題、簿価を簿価純資産価額と揃えることにも合理性
グループ通算制度では、離脱する通算子法人の株式の帳簿価額を当該通算子法人の離脱直前の簿価純資産価額と一致させることになる。この新しい投資簿価修正制度によれば、当該通算子法人を当初買収した際の買収プレミアム相当分が当該通算子法人の離脱時に株式の譲渡原価に算入されず、連結納税や単体納税と比べ、譲渡益の過大計上又は譲渡損の過少計上につながる恐れがある。この点について企業からは、令和2年度税制改正でグループ通算制度導入された頃より「円滑な事業再編が阻害されるのではないか」との懸念が表明されてきた(本誌833号4頁参照)。
その一方で、令和4年4月1日からのグループ通算制度の施行を約半年後に控え、既に新しい投資簿価修正制度に向け準備を進めている企業もある。仮に令和4年度税制改正でこの新しい投資簿価修正制度について何らかの修正が行われたとしても、その詳細が政省令レベルで判明するのは施行の直前となり、かえって実務に混乱が生じるのではないかとの指摘も聞かれる。また、通算子法人の離脱時の株式の帳簿価額を簿価純資産価額と一致させないとして、具体的にどのような制度設計とするのか、なかなか妙案が見つからないという事情もある。投資簿価修正に関する元々の改正の趣旨が「租税回避の防止」「制度の簡素化」「組織再編税制との整合性確保」の3つとされる中、そのすべてに対応する制度を別途構築するのは直ちには困難ということだ。
こうした中、令和4年度税制改正に係る経済産業省要望には下記の内容が盛り込まれた。
企業の生産性を向上させる事業再編を円滑化する観点から、グループ通算制度における、グループ通算子法人のグループ離脱時の取り扱い等について、制度の施行状況や組織再編税制との整合性等を踏まえ、中期的に必要な検討を行う。
これは投資簿価修正を念頭に置いた要望であることが本誌取材により確認されている。ただし、本要望は、償却資産に係る固定資産税、事業所税、地方法人課税といった、すぐには実現しない中長期課題との並びで記載されている。この記載場所の意味するところは、課題として認識されてはいるものの、令和4年度税制改正ですぐに実現するものではない、ということを意味する可能性が高い。さらに言えば、令和5年度税制改正以降での実現が保証されているわけでもない。
また、経済産業省の要望からは、組織再編税制との整合性がポイントとなっていることも読み取れる。グループからの離脱を分割との比較で考えれば、離脱通算子法人の株式の帳簿価額を当該通算子法人の簿価純資産価額と揃えるということには一定の合理性があるとも言える。単純に買収プレミアムについて面倒を見るべき(離脱時に譲渡原価に加算すべき)という主張では通らないということであろう。
企業からは早速、まずは検討課題に載ったことを評価する声も上がっている。改正実現までの道のりは険しいと考えられるが、議論自体は続くことになろう。
完全子法人株式等に係る配当の源泉徴収の不要化
会計検査院の指摘受け、金融庁と経産省が共同で要望
上記のとおり、ミニマム課税導入に伴うCFC税制の簡素化、グループ通算制度における投資簿価修正の見直しについては令和4年度税制改正での実現は困難な状況にある一方、改正が実現する可能性が高いのが、完全子法人株式等に係る配当の源泉徴収の不要化だ。
金融庁及び経済産業省は、「完全子法人株式等及び関連法人株式等の配当に係る源泉徴収を不適用とする」ことを共同要望している。いずれの省庁も重点課題としてクローズアップしていないため見落としがちだが、実務に影響が生じる可能性があるので留意したい。
この要望は会計検査院の指摘を受けたもの。会計検査院は令和元年度決算検査報告の中で、「全額に法人税が課されていない完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等に対して源泉徴収を行っているため、(所得税額控除の結果)還付金及び還付加算金並びにこれらに係る税務署の還付事務が生ずる」と指摘した上で、「財務省において、源泉徴収義務者による源泉徴収事務の便宜を考慮した上で、配当等に係る源泉徴収制度の在り方について、引き続き、様々な観点から効率性、有効性等を高める検討を行っていくことが肝要」と指摘した。還付加算金は888法人に対し3年間合計で3億6,563億円発生していたという(会計検査院・令和元年度決算検査報告「完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等について」参照)。
企業側からすれば、これはもっともな指摘と言える。特に完全子法人株式等に係る配当は全額益金不算入であることから、そもそも源泉徴収で「法人税の前払い」をする意味はない。源泉徴収の分、キャッシュが一時的に流出しているに等しく、非効率とされる。
この問題については、持株会社形態をとり、配当金収入が多い損害保険会社が継続して改善を求めてきたが、改正の影響は国内にグループ会社を有する産業界全体に及び、金融業界にとどまらない。そこで、金融庁が税制改正要望において主導的な役割を果たしつつ、経済産業省が名を連ねる構造となっている。
令和4年度税制改正で「納税環境整備」の一項目として整備へ
実務的な影響としては、配当する側から見ると、源泉徴収の有無の判定にあたり、その配当が完全子法人株式等に係るものであるか、あるいは関連法人株式等に係るものであるかを配当時点で正確に判定することが必要となる。もっとも、前者については100%グループ内の配当であることから、判定に迷うことは基本的に考えにくく、後者についても、33%超の株式を有する株主の特定に困るということは、そう多くないと考えられる。
財務省・国税庁としては、会計検査院の指摘に何らかの対応をする必要があるとみられ、関係業界等も含めた検討の結果、思わぬ技術的な制約が出てこなければ、基本的には順調に議論が進む可能性が高いだろう。また、還付加算金目当てで現行制度の維持を望む企業は少数に留まるであろうし、そもそも表立ってそのような主張ができるはずもないことから、改正に向けた障害は今のところ見当たらない。令和4年度税制改正における「納税環境整備」の一項目として注目しておく必要がある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















