解説記事2021年10月04日 ニュース特集 相続税関係における最新の重加算税取消裁決(2021年10月4日号・№900)
ニュース特集
審判所が重加算税を取り消したポイントとは
相続税関係における最新の重加算税取消裁決
重加算税が課されるには、無申告又は過少申告であったこと自体が隠ぺい又は仮装に該当するだけでは足りず、それとは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせて無申告又は過少申告であることを要することになる。しかし、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為の存在が常に必要になるわけではない。納税者が、当初から無申告又は過少申告であることを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかった又は過少申告をした場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解されている。本特集では、相続税関係における最新の裁決事例から重加算税が取り消されたケースを4件取り上げ、取り消された理由を中心に紹介することとする。
納税者や税理士の証言内容の裏付けが必要
最初に紹介する裁決事例は、被相続人の死亡により取得した共済金の申告漏れが重加算税の賦課要件を満たすかどうか争われたものである(関裁(諸)令2第13号、図1参照)。
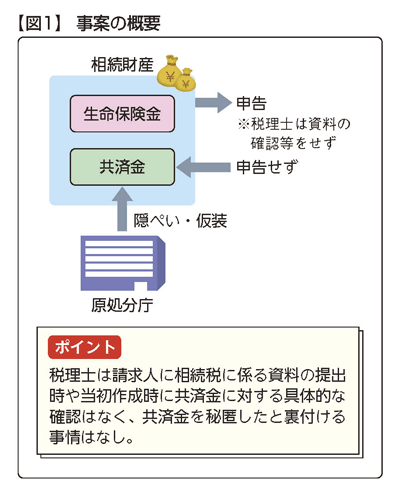
税理士に共済金の存在を秘匿したと主張
請求人は、被相続人から共済金を相続税の納税資金に使うよう言われていたため相続税の申告すべき財産ではないと誤解していたほか、納税資金に充てるために共済金に係る資料を区別して管理していたことから提出が漏れてしまったにすぎないと主張。税理士についても生命保険金が係争外死亡保険金以外にないかを問う質問をしなかったとした。
一方、原処分庁は、係争外死亡保険金は申告しており、共済金は係争外死亡保険金に比べて極めて高額であることなどからすると、請求人が共済金について安易に誤解することは考え難いとした。また、請求人は税理士から相続税に係る資料の提出を求められた際に係争外死亡保険金に係る資料のみを提出し、生命保険金は1つしかないと説明したほか、共済金が振り込まれてから相続税の納付を行う過程で共済金を意識する機会があったにもかかわらず、税理士にその存在を一切伝えなかったことを考慮すれば、請求人は共済金を除外する意図をもって税理士に対して殊更にその存在を秘匿したものといえるなどと主張した。
共済金の存在を秘匿したとまでは認定せず
審判所は、まず当初申告書の提出時において請求人が共済金について相続税の申告すべき財産であることを認識していたことは認められるとした。しかし、相続税に係る資料の提出時や当初申告書の作成時に、税理士が請求人に対して具体的にどのような確認等をしたのかが明らかではなく、むしろ審判所の調査によれば税理士は追加提出を依頼すべき資料等があるかを検討しておらず、請求人に対する具体的な確認等もしていなかったことが認められると指摘。審判所は、請求人が税理士に対して殊更に共済金の存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情は存在しないことなどに照らせば、請求人が当初から過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合に該当することまでは認められないとし、重加算税の賦課要件を満たすとはいえないとの判断を示した。
今回の裁決事例は、重加算税を賦課する場合の判定には請求人や税理士の証言の一部だけではなく、その証言内容の裏付けが必要になることを示唆するものといえよう。
銀行担当者の納税資金との説明を誤った可能性を否定できず
次に紹介する裁決事例は1件目と同様、請求人が納税資金との認識により相続税の期限内申告において死亡保険金を申告せず、その後に修正申告したところ、当該死亡保険金を申告しなかったことは隠ぺいに基づくものであるとして重加算税を賦課されたものである(東裁(諸)令2第65号、図2参照)。
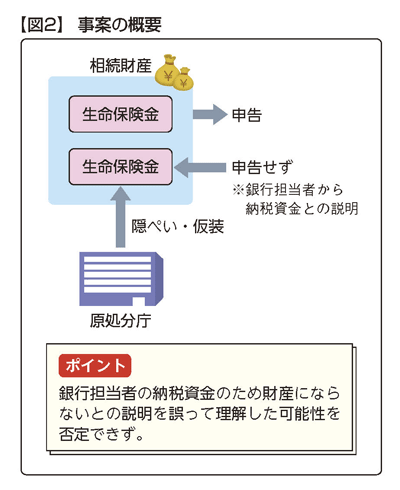
別の生命保険金は申告済み
請求人は、死亡保険金を申告しなかったのは、銀行支店の担当者から当該保険金は相続税の納税のための資金であり、振り込まれても請求人のものではない旨の説明を受けており、相続のトラブルが生じた場合にも相続税の対象とはならずに相続税の納税に充てることができる保険金であって請求人に帰属しない財産であるから申告の対象に含める必要はないものと理解していたなどと主張。一方、原処分庁は、①別の生命保険金は申告に含めていること、②本件保険金に係る支払調書には税務の申告に利用されたい旨の記載があること、③税理士が請求人に対して送信した電子メールには生命保険金の支払の有無を問い合わせる内容の記載があること、④銀行支店の担当者が、本件保険金が相続税の対象になることを保険契約締結時に請求人に説明したことからすれば、本件保険金が相続税の課税対象であることを十分に理解していたものと認められると主張した。
生命保険金の存在を税理士に伝えなくても
審判所は、請求人は本件保険契約について、銀行支店の担当者から納税のための生命保険契約であり(保険契約に係る保険料が一時払いであり、その支払額と基本保険金額が同額(1億円)であって、本件保険契約は被相続人名義の預金を相続開始後に相続人名義の預金へと移すことができることに意義がある契約であると説明)、すべて税金を納めるためのものであるから「〇〇さんの財産にはならない」との話があった旨述べていることからすれば、同担当者から保険契約について説明がされる中で、被相続人と同じ姓の請求人の財産にはならず、みなし相続財産として相続税の課税の対象となることはないと誤って理解してしまうなどした可能性も直ちに否定できないと指摘。その上で税務に関する知識や経験が豊富とはいえない請求人において、本件保険金は別途の生命保険金とは異なり、請求人の財産ではなく、相続税の課税の対象とはならないものと誤解し、かかる誤解に基づいて保険契約について税理士に伝えなかった可能性も否定できないというべきであるとした。
審判所は、請求人は相続税に関する調査の初日に保険金の入金事績が記録された請求人口座に係る通帳を調査担当職員に提示するなどしており、殊更に保険金の入金の事実を調査担当職員に対して隠そうとはしていない請求人の態度は誤解があった可能性を高める事実ともいえ、保険金の存在について税理士に伝えなかったことをもって、請求人が当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとまではいえないとの判断を示した。
死亡保険金の存在を失念した可能性は否定できず
3件目に紹介する裁決事例も生命保険金の申告漏れである。請求人が調査を受けて相続税の修正申告をしたところ、原処分庁が、請求人が被相続人の死亡により受領した生命保険金2口のうち1口を課税価格に含めずに申告したことは隠ぺい又は仮装に当たるとして重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が原処分の一部の取消しを求めたものである(東裁(諸)令2第61号、図3参照)。
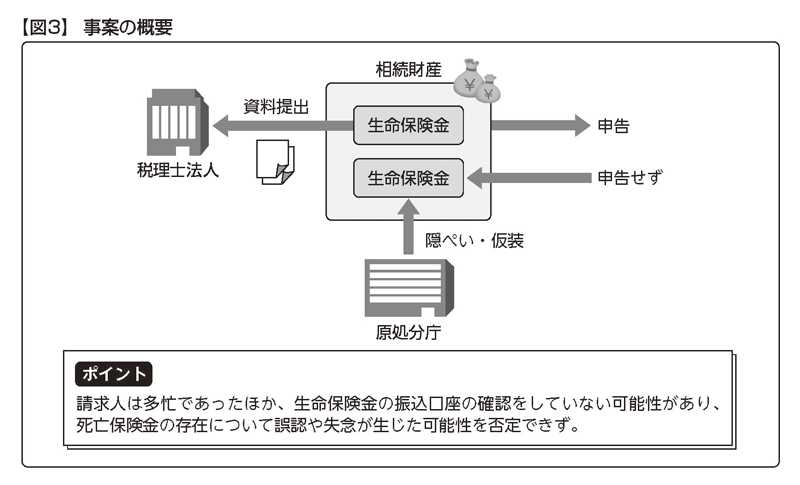
税理士に死亡保険金の資料を交付せず
請求人(大学教授)は、日頃から仕事や個人的な情報のデータをパソコンに保存しており、死亡保険金の支払通知書のデータについてもパソコンに保存はしていたものの、死亡保険金の存在については記憶から抜け落ちており、また、死亡保険金の請求手続は行っているが、多忙な仕事の傍らで行っていたものであり、重要性を認識せずその存在を失念していたなどと主張。一方、原処分庁は、請求人は申告書の作成を依頼した税理士法人に対して申告書の作成に必要な書類を交付した際に、死亡保険金に係る資料を交付せず、また、保険担当者から死亡保険金の存在を知らされた日から申告書提出日までの間、幾度となく税理士に対し説明する機会があったにもかかわらず説明をしなかったなどと主張した。
審判所は、①請求人は被相続人の死亡後、保険担当者からの指摘を受けるまでは、死亡保険金に係る生命保険契約が締結されていた事実すら知らず、当初は申告済保険金のみであると誤認していた、②各保険金の支払請求手続をした時期は、請求人が学年末試験や入試業務への対応、ヨーロッパ出張や複数の国内学会への参加をしていた時期に重なっていること、③死亡保険金の支払請求を送付したことにより死亡保険金が預金口座に振り込まれているが、通帳の残高の確認を請求人自身がしていない可能性がある上、申告済保険金と異なってやや簡易な方法で通知がされていることも考慮すると、死亡保険金の存在について請求人が主張するような誤認や失念が生じた可能性がないとはいえないとした。
また、審判所は、税理士とのやり取りの経過をみても申告済保険金以外の生命保険金の有無が殊更に問題とされているような事情は認められず、通帳及び支払通知書は破棄されることもなく保管され、実地調査の初日にこれらの資料が特段の支障なく調査担当職員に提示された事実に照らしても、死亡保険金の申告漏れに関し、請求人が当初から相続税の課税財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたということはできないと指摘。審判所は、請求人に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為があったとは認められないとの判断を示し、過少申告加算税相当額を超える部分の金額については取り消すこととされた。
夫の財産を妻の名義で預金がなされることは普通
最後に紹介するのは、請求人ら(妻及び子供2人)が被相続人(夫(父))の預け金を相続税の当初申告において相続財産として申告しなかったことが隠ぺい又は仮装行為に該当するか争われた事案である(仙裁(諸)令2第15号、図4参照)。
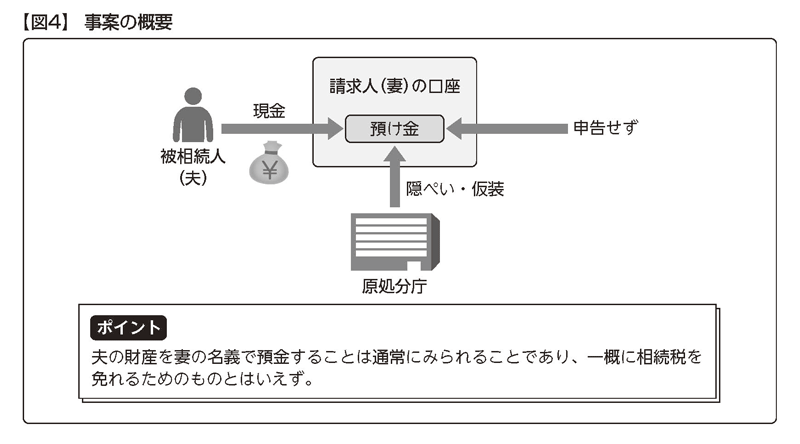
被相続人から勧められて口座開設
請求人は、本件現金は請求人に帰属するものであり、相続開始日には被相続人の遺産として存在しないのであるから相続人らが当初申告において預け金を相続財産として申告しなかったのは当然であると主張。一方、原処分庁は、請求人は被相続人から請求人の方が長生きするから請求人(妻)の名前で預金口座を作れと言われて口座を開設したことからすると、本件現金が被相続人に帰属するものであることを認識していたなどと主張した。
預け金は相続財産と認定も
審判所は、まず預け金が相続財産になるか否かについて検討。仮に現金の原資が被相続人に帰属する財産であった場合、特別な事情がない限り、現金が請求人によって口座に入金された時点で被相続人は請求人に対し、現金相当額の金銭債権(返還請求権)を取得し、また、当該金銭債権は、相続の開始により相続財産を構成することになるとした。本件について審判所は、被相続人及び請求人の貯蓄能力などからみて現金の原資は被相続人の財産であり、相続財産を構成すると認められるとした。
その上で審判所は、必ずしも民法が採用する夫婦別産意識の強いとはいえない夫婦関係においては様々な理由から例えば夫の財産を妻の名義で預金がなされることは通常にみられることであり、これについて一概に将来の相続税を免れるための事実の歪曲と評価することはできないと指摘。相続の開始時期も予想できない時点で請求人名義による口座開設について、直ちに隠ぺい又は仮装行為とは認め難いとの判断を示した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















