解説記事2019年12月16日 税理士のための相続法講座 相続法改正(8)―特別の寄与①(2019年12月16日号・№815)
税理士のための相続法講座
第53回 相続法改正(8)―特別の寄与①
弁護士 間瀬まゆ子
1 特別の寄与
今回のテーマは特別の寄与の制度(民法1050条)です。これは、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対する金銭の支払の請求を認めるものです。
以下、具体例に基づいて、この特別寄与の制度の趣旨を説明していきます。
Aが亡くなった。Aの相続人は次男Cと三男D。長男Bは、Aが亡くなる前年に亡くなっており、子供もいなかった。CとDは遠方におり、Bも多忙であったため、専らBの妻EがAの介護を引き受けてきた。
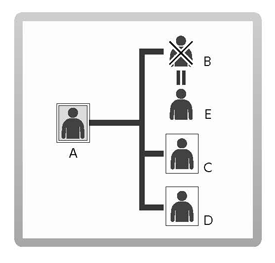
従前、長男の妻が介護を行ったような場合、妻を長男の履行補助者と解して、長男の寄与分として妻の貢献を相続の中で反映させる実務上の運用が行われていました。
つまり、上記の事例でも、Bが相続人であれば、Bの寄与分があったと認定してEの貢献を反映させるという解決策がありえたということです。しかし、Bが亡くなっているのでこのような策は採りえません。そうなると、Aの介護を全く行わなかったCやDが財産を取得することができる一方、EはどんなにAの介護に尽くしていたとしても、Aの相続に際して何らの分配を受けられないことになってしまいます。これは明らかに実質的な公平に反します。
※なお、BとEに子があれば、Bの代襲相続人としての相続分を決めるにあたり、Eの貢献を反映させる余地があります。ただ、その場合でも、EをBの履行補助者と解することはできても、子から見て母であるEを当然に子の履行補助者と見ることは一般に難しいため、Bの死亡後にEが行った療養看護については、子の相続分に反映できない可能性があります。
このような問題意識から、介護等の貢献に報いて実質的な公平を図るため、相続開始後、相続人でない親族に、相続人らに対して金銭(特別寄与料)の請求をすることができる権利を与えることとしたのです。
ただ、せっかくこのような制度ができても、実際に認められるケースが限定されたり、認められたとしても請求する親族の期待を裏切る程度の金額となったりするようなケースも出てくるのではないかと懸念しています。というのも、特別寄与料の制度は、相続人の寄与分と共通する部分が多いのですが、以前にも触れたとおり、寄与分については現状の実務におけるハードルは高いものとなっており、その寄与分に係る解釈・運用が特別寄与料についても相当程度援用されることが見込まれるからです。詳細については、次項以下で触れます。
2 特別の寄与の要件
特別寄与料の請求が認められるための要件は以下のとおりです(片岡武・菅野眞一「改正相続法と家庭裁判所の実務」163ページ以下参照)。
① 被相続人の親族であり、相続人でないこと
② 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと
③ 被相続人の財産の維持又は増加
④ ②と③の因果関係
⑤ 特別の寄与
まず①についてですが、請求権者は相続人以外の被相続人の親族です。内縁の配偶者、友人や近隣住民がどんなに介護に尽くしたとしても、特別寄与料をもらうことはできません(相続人が全くいないケースであれば、特別縁故者(民法958条の3)として若干の給付を受けられる可能性はあります。)。また、相続放棄、相続欠格や廃除によって相続権を失った者は、「相続人以外の親族」にあたりそうですが、特別寄与料の請求権者からは除かれます。すなわち、相続放棄をした相続人が特別寄与料だけもらうということはできないのです。
そして、上記のような「被相続人の親族」にあたるかの判断の基準時は相続開始時です。この点については、以下の具体例に基づいて確認していきます。
Fの次男Gの妻Hは、自宅で暮らすことを希望するFの意向を受け、自宅でのFの介護を一手に引き受け、Fに献身的に尽くした。Fも、そんなHに対する感謝の言葉を口にしていた。
(1)Gの浮気が発覚し、HはGと離婚することとなった。その後にFが亡くなった。
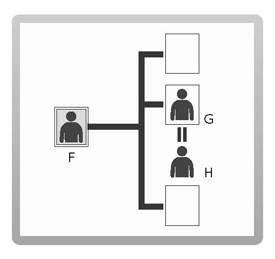
この事例で、Hは、Fの相続開始時においては、Fの親族ではなくなっています。したがって、特別寄与料の請求はできません。
Hに何らかの財産を取得させるためには、Fの生前に、遺言や死因贈与をしておくか、あるいは、生前贈与でHに財産を渡しておくほかありません。あるいは、FとHとの間に準委任契約(民法656条、643条)等があったとして、Hに一定の給付を受ける権利が認められる場合もあるかもしれませんが、そのハードルは低くありません(仮に認められたとしても金額は大きくないことが見込まれ、法的手段をとること自体を断念する場合も多いでしょう。)。
次に、②の要件を確認します。特別寄与料の制度は、寄与分の制度に通じるところが多いですが、寄与分と異なり、対象となる行為は、療養看護その他の労務の提供に限定されています。したがって、寄与分に関して一般に言われる、療養看護型、家業従事型のほか、労務の提供と評価し得れば、財産管理型の寄与行為についても特別寄与料が認められる可能性がありますが、一方で、金銭等出資型(被相続人に財産を給付していた)や扶養型(被相続人を扶養していた)は特別寄与料の対象には含まれません(ただ、相続人との間に貸借関係があったと認定し得るような事実関係があれば、金銭等の返還請求が認められる余地はあります。)。
更に、療養看護等の寄与行為は、無償またはそれに近い状態でなされることが必要です。被相続人から遺贈を受けた場合や、被相続人の資産・収入で生活していた場合にはこの無償性が否定されることがあります。
(2)Fの介護のため、GとHは元いた社宅を出て、F所有のアパートの一室に住むことにした。家賃は支払っていなかった。
上記の事例でHは、Fの資産を無償で利用することで利益を受けています。そのため、無償性の要件を欠き、Hの特別寄与料の請求が認められないことになりそうに思えます。
しかし、何らかの利益を得ていれば一律無償性が否定されるわけでもないのが実務です。転居した経緯や介護の負担の大きさ等の事情を考慮し、無償性はあったとして特別寄与料の請求自体は認め、ただ、後述する裁量割合により減額するという裁判官の判断がなされる場合もあります。
この辺りは、あらゆる場面を想定した通達が存在する税務の世界に慣れている税理士からすると、不可解な部分かもしれません。ただ、後述のとおり、特別寄与料について当事者間で話がまとまらない場合に最終的な判断を下すのは裁判所であり、各案件の結論はそれぞれの裁判官の裁量により決定されるため、どのような場合に認められるのかを類型化することは困難なのです。
次回に続きます。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















