解説記事2022年03月07日 ニュース特集 確定申告期に確認したい所得税・消費税Q&A(2022年3月7日号・№921)
ニュース特集
遺留分侵害額請求、暗号資産、補償金、住宅ローン控除etc.
確定申告期に確認したい所得税・消費税Q&A
本特集では、令和3年分確定申告に伴い東京国税局が確認している所得税・消費税の審理事例(Q&A)を紹介する。所得税関係では、遺留分侵害額請求や暗号資産に係る課税関係、構外再築工法に基づき支払われる補償金の取扱い、新型コロナ税特法と住宅ローン控除の関係などが取り上げられている。また、消費税関係では、新型コロナの影響と納税義務の免除の特例について確認されている。
所得税編
所得の帰属
1.遺留分侵害額請求を行った場合の課税関係(民法改正)
Q
納税者Xは、母Y(令和2年2月1日死亡)の唯一の法定相続人である。Yは、法定相続人ではないZに賃貸用建物(本件不動産)を含むYの全財産を包括遺贈する公正証書(平成16年9月1日付)を作成していたため、XはZを相手方として令和3年8月1日に地方裁判所に対して遺留分侵害額請求を行ったところ、令和3年8月31日、XとZの間で、ZがXに対して遺留分侵害額を支払う旨の遺産分割に関する合意書を交わすに至った。
この場合、Xは本件不動産から生ずる不動産所得を申告する必要があるか。
A
Xは、本件不動産から生じる不動産所得を申告する必要はない。
(解説)
遺留分減殺請求(旧民法1031)については、民法の改正(令和元年7月1日から施行され、同日以後に開始する相続について適用)により、遺贈及び生前贈与を減殺する制度(物件の請求)から、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する制度(金銭債権の請求)とする遺留分侵害額請求(民法1046①)に改正された。
また、相続財産から生ずる果実について、改正前は受贈者に果実の返還義務が課されていた(旧民法1036、改正後削除)が、改正後は、遺留分侵害額請求の算定の基となる遺留分の額は相続開始後の財産価額等とされている(民法1043①)ため、果実は遺留分侵害額請求の対象には含まれないことになった。
改正前においては、旧民法の規定及び平成17年9月8日最高裁判決等を踏まえ、遺産である賃貸不動産は、遺留分減殺請求後は包括受遺者及び相続人の共有に属し、また、その賃貸不動産から生じる賃料は賃貸不動産とは別個の財産として確定的に取得するものであるから、遺留分減殺請求から合意までの賃料については共有割合により按分して不動産所得として課税することとされていた。しかし、改正後は、上記のとおり物権の請求から金銭債権の請求に変わったことから、賃貸不動産について共有状態は生じず、また、果実である不動産賃料について遺留分侵害額請求の対象とはされない。
設例の場合、本件賃貸不動産は、相続開始時以降、包括受遺者Zが単独で所有するものとなり、遺留分侵害額請求後においても、XとZとの共有に属することはないから、Xに不動産所得が生じることはない。
所得区分
2.暗号資産取引を行った者に交付される景品の所得区分
Q
X社は金融商品取引業を営む内国法人であるところ、同社は暗号資産の証拠金取引を行う顧客向けに、以下のとおり、キャンペーンを実施した。
・ある一定期間内に一定数量以上の暗号資産の証拠金取引を行った顧客全員に対して、景品として、暗号資産(50リップル)を交付する。
上記景品について、交付を受けた顧客における課税関係はどのようになるか。
A
雑所得に該当する。
(解説)
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務の提供又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものは、一時所得とされている(所法34①)。
設問のキャンペーンにより交付される景品は、利子所得から譲渡所得のいずれの所得にも該当しない。しかしながら、景品の交付は、暗号資産の一定以上の取引という行為に密接に関連してなされているものと認められる。そうすると、当該景品は、対価性を有していることから、一時所得には該当しない。
したがって、設問のキャンペーンの景品は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれの所得にも該当しない所得であることから、雑所得として取り扱われることになる(所法35①)。
収入金額
3.起業地に係る関連移転の補償として「構外再築工法」に基づき支払を受ける補償金についての所得税法44条の適用について
Q
Xは、自己の所有する土地について、Z県による土地収用を受けたことに伴い、残地(収用されない部分の土地)上にある車庫(本件車庫)の移転に係る費用について、Z県が定める公共用地の取得に伴う損失補償基準(本件基準)等に基づき「構外再築工法(注)」により算定された補償金(本件補償金)の支払いを受け、本件車庫を同「構外再築工法」により移転させた。
なお、本件基準は、事業に必要な土地等の取得等に伴う損失の補償の基準を定め、もって事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的として定められたものであるところ、本件基準によれば、本件補償金は、Xの請求に基づき、Z県が、「起業地内の建物(本件建物)を移転させることにより、Xにとって『移転した本件建物』も『残留する本件車庫』も従前の利用目的に供することが著しく困難である」と判断し、本件基準に基づき、通常妥当と認められる移転工法のうちの一つである構外再築工法を採用した場合の移転料として以下の(1)ないし(3)の金額の合計額が支払われたものである。
(1)本件車庫の現在価額から発生材価額を差し引いた額
(2)運用益損失額(車庫の推定再建築費と本件車庫の現在価額との差額に係る本件車庫の耐用年数満了時までの運用益に相当する額)
(3)本件車庫の取壊し工事費
この場合に、本件補償金につき所得税法44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定は適用されるか。
(注)構外再築工法とは、残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築する工法をいう。
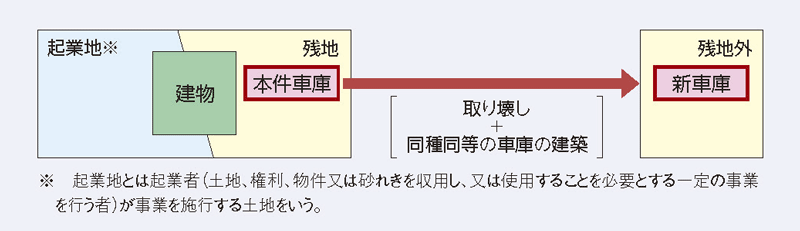
A
本件補償金には、以下の解説①ないし③の部分について所得税法44条の規定が適用される。
(解説)
本件車庫は、収用対象の土地上に存するものではなく、残地上に存するものであることから、行政目的の観点からすれば、本件車庫は移転せずとも行政目的の遂行が可能であると解することもできる。そうすると、本件補償金は、所得税法44条の適用の余地がないようにもみえる。
しかしながら、本件補償金は、Xの請求に基づき、Z県が、「本件建物を移転させることにより、Xにとって『移転した本件建物』も『残留する本件車庫』も従前の利用目的に供することが著しく困難である」と判断し、本件基準に基づき、通常妥当と認められる移転工法のうちの一つである構外再築工法を採用した場合の移転料として算出した金額が支払われたものである。そうすると、本件補償金は、本件基準の目的である事業の円滑な遂行のために必要と判断されて支払われたものと認められることから、所得税法44条に規定する「行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転」等の費用に充てるための補助金であると認められる。
この点について、最高裁平成22年3月30日第三小法廷判決(民集233号327頁)は、再築工法による移転を前提に公共用地の取得に伴う損失補償基準細則の定めに準ずる方法で算定された建物の移転料の交付を受けた者が、その交付の目的に従って、従前の建物を取り壊し、代替建物を建築して取得した場合には、当該移転料のうち、〔1〕従前の建物の現在価額から発生材価額を差し引いた金額に相当する部分は、その全額について、〔2〕運用益損失額に相当する部分は、代替建物の建築に実際に要した費用の額が従前の建物の現在価額を超える場合において、その超える金額に係る従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する部分について、〔3〕取壊し工事費に相当する部分は、実際に従前の建物の取壊し工事の費用に充てられた部分について、それぞれの交付の目的に従って移転等の費用に充てられたものとして、所得税法44条の適用を受けると解するのが相当である旨判示している。
上記最高裁判決に基づき、設問の事例において、所得税法44条が適用される範囲を検討すると、本件補償金のうち、①本件車庫の現在価額から発生材価額を差し引いた金額に相当する部分、②本件車庫の再構築に実際要した費用の額が本件車庫の現在価額を超える場合において、その超える金額に係る本件車庫の耐用年数満了時までの運用益に相当する部分及び③本件車庫の取壊し工事費に実際に充てられた部分が、同条に規定する「交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたもの」と認められ、同条が適用されることとなる。
損益通算
4.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(令和3年以降)
Q
X(居住者)は、米国カリフォルニア州に所在する中古建物2棟(それぞれの中古建物について、「国外中古建物A」「国外中古建物B」という)及び米国アリゾナ州に所在する1筆の土地(国外不動産C)を所有し、それぞれ貸付けを行い、不動産所得を得ている。
Xの令和3年分の不動産所得の内容は次のとおりである。
【国外中古建物A】
収入1,000万円
減価償却費200万円(耐用年数については、簡便法により算出している)
その他経費900万円
損失額100万円
【国外中古建物B】
収入200万円
減価償却費300万円(耐用年数については、簡便法により算出している)
その他経費500万円
損失額600万円
【国外不動産C】
収入1,100万円
必要経費600万円
所得金額500万円
本設例において、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を適用する場合、どのように国外不動産所得の損失の金額(損益通算不可となる部分の損失の金額)を計算すればよいか。
また、将来において国外中古建物A又は国外中古建物Bを譲渡した場合に、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費から控除する「償却費の額の累積額」から控除することとされている令和3年分の「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額」は、国外中古建物A及び国外中古建物Bそれぞれについて、いくらになるか。
A
以下の解説のとおりに計算する。
(解説)
1 「国外不動産所得の損失の金額」の意義
令和2年度税制改正で、個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該「国外不動産所得の損失の金額」に相当する金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、「生じなかったものとみなす」こととされている(措法41の4の3①)。
ここでいう「国外不動産所得の損失の金額」とは、個人の不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸付けによる損失の金額のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として一定の計算をした金額をいう(措法41の4の3②二)。
上記一定の計算をした金額とは、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した国外中古建物ごとの償却費の額のうち、次の(1)及び(2)の合計額とすることとし(措令26の6の3①)、2以上の国外中古建物を有する場合には、建物1棟ごとに計算することとされている(措令26の6の3③一)。
(1)当該償却費の額が当該国外中古建物の貸付けによる損失の金額を超える場合には、当該損失の金額
(2)当該償却費の額が当該国外中古建物の貸付けによる損失の金額以下である場合には、当該損失の金額のうち当該償却費の額に相当する金額
2 国外不動産等の貸付けによる不動産所得がある場合の調整
その年分の不動産所得の金額のうちに国外中古建物以外の国外にある不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下これらをまとめて「国外不動産等」という)の貸付けによる不動産所得の金額がある場合においては、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を上記1で計算した合計額から控除するものとされている(措法41の4の3②二、措令26の6の3②)。
(1)当該国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額
(2)以下のイの金額からロの金額を控除した金額
イ 国外中古建物のうち、その償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該国外中古建物の貸付けによる損失の金額以下であるものについて、その損失の金額の合計額
ロ 国外中古建物のうち、その償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該国外中古建物の貸付けによる損失の金額以下であるものについて、その償却費の額の合計額
3 本設例における国外不動産所得の損失の金額の計算
上記1及び2から、本設例における国外不動産所得の損失の金額は図のとおり計算され、同額が損益通算不可となる部分の損失の金額となる。
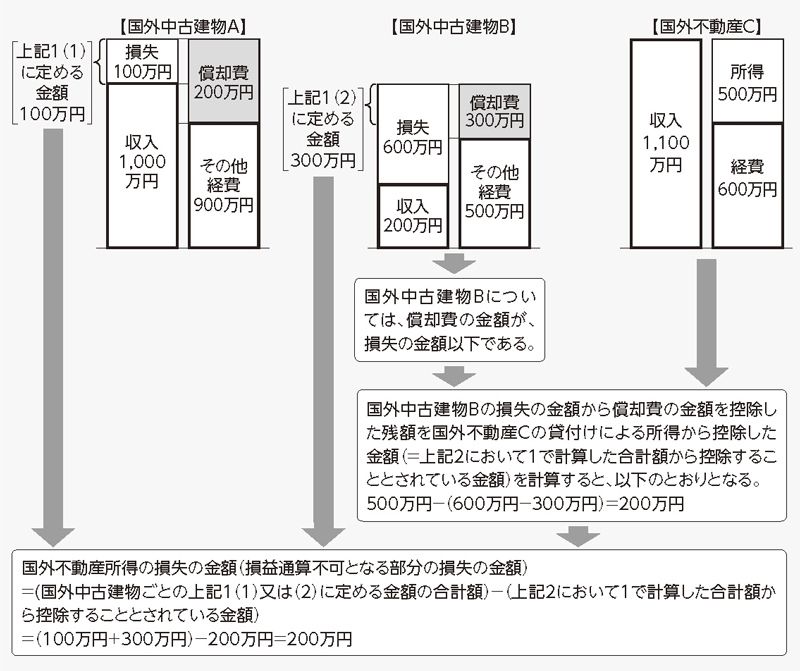
4 国外中古建物を譲渡した際の取得費の計算について
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費から控除することとされている「償却費の額の累積額(所法38②一)」からは、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除することとされている(措法41の4の3③)。
ここで、その年分の国外不動産所得の損失の金額に相当する金額の計算につき上記2の調整があった場合において、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡したときにおける、その年分の当該国外中古建物についての「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額」は、その年分の国外不動産所得の損失の金額に相当する金額に、その年分の上記1に掲げる(1)又は(2)の場合の区分に応じてそれぞれ定められた金額の占める割合を乗じて計算した金額とされている(措令26の6の3④)。
したがって、将来において国外中古建物A又は国外中古建物Bを譲渡した場合に、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費から控除する「償却費の額の累積額」から控除することとされている令和3年分の「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額」は、それぞれ以下の表のとおりに計算される。
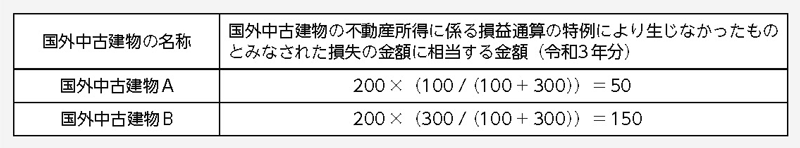
税額控除
5.住宅借入金等特別控除の控除期間の特例に係る入居期限の特例と6か月以内入居要件
Q
Xは、令和2年6月中に、居住用家屋の新築を目的とする工事請負契約(消費税率10%)をZ社との間で締結し、同年12月中に、Z社からこの家屋(本件家屋)の引渡しを受けたが、新型コロナウイルス感染症の影響により外出を自粛していたことなどにより、翌年7月になってようやく本件家屋に入居した。
この場合、Xは、住宅借入金等特別控除の控除期間の特例(13年間適用)を受けることができるか。
A
Xは、そもそも住宅借入金等特別控除を受けることができない。
(解説)
個人が、居住用家屋の新築をした場合において、その家屋をその新築の日から6月以内に居住の用に供したことなど、一定の要件を満たすときは、当該居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間について、住宅借入金等特別控除を受けることができる(措法41①)。
また、居住用家屋の新築に係る消費税率が10%であり、かつ、当該居住用家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間(※)に居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の控除期間を居住年以後13年間とする控除期間の特例が設けられている(措法41⑬)。
この控除期間の特例については、新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年12月31日までの間に居住の用に供することができなかった場合であっても、その家屋の新築に係る契約が同年9月30日までに締結されており、その家屋を令和3年12月31日までに租税特別措置法41条1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、適用を受けることができるとする入居期限の特例が設けられている(新型コロナ税特法6④)。
しかしながら、当該入居期限の特例をもって、住宅借入金等特別控除の「家屋をその新築の日から6か月以内に居住の用に供したこと」としている要件が排除されることはない(上記下線部分)ところ、Xは、本件家屋をその新築の日(引渡しを受けた日)から6月以内に居住の用に供していないため、そもそも住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
※ 新型コロナ税特法の改正により、一定の建物の取得等については居住の用に供した期間が異なるが、本設例は「6月以内の居住」の要件に係る留意事項を示すものであることから当該改正の説明は省略している。
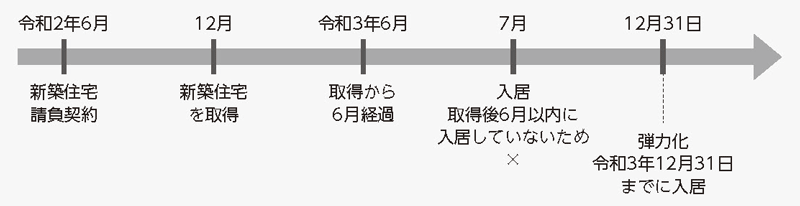
6.土地を先行取得した場合の新型コロナ税特法の適用関係
Q
Xは、令和元年10月1日、居住用家屋(本件家屋)を新築するための土地(本件土地)を借入金により取得し、令和2年12月中に、翌年の令和3年8月末に完成・引渡しの予定で本件家屋の新築を目的とする工事請負契約を締結したところ、新型コロナウイルス感染症の影響により、工事が遅延し、その完成・引渡しが同年10月末となった。
Xは、本件家屋を取得してから6か月以内に入居し、本件土地及び本件家屋の取得のための借入金についてはいずれも本件家屋に抵当権が設定されているが、本件土地に係る借入金についても住宅借入金等特別控除(措法41)の適用を受けることができるか。
A
Xは、本件家屋の新築の日前2年以内に本件家屋の敷地の用に供する土地を取得したことにならないことから、当該土地に係る借入金について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
(解説)
土地を先行取得した場合において、その土地に係る借入金について住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、「居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得すること」が要件の一つとされている(措令26⑧六)。
また、租税特別措置法41条1項にいう「新築の日」とは、その者がその家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱うこととされている(措通41−5)。
新型コロナ税特法では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、例えば、中古住宅を取得した後、その中古住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合で当該住宅の取得の日から6か月以内に入居できなかったときは、所定の要件を満たすことによりその住宅ローン控除の適用が受けられるなど、その適用の弾力化が図られている(新型コロナ税特法6①②)。
しかしながら、土地の先行取得のケースにおいて、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、土地の先行取得が家屋の新築の日前2年以内にならなかった場合については、住宅ローン控除の適用要件の弾力化は図られていない。したがって、Xは、本件土地に係る借入金について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
7.住宅借入金等特別控除の入居期限要件に係る特例(増改築等工事を行った場合)
Q
Xは、令和2年3月1日、中古住宅をYから取得したものの、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響等を受け、増改築工事の契約日、増改築工事が終了した日及び入居の日は以下のとおりとなった。
ⅰ 増改築等の工事に係る契約日......................令和2年7月20日
ⅱ 上記ⅰの工事が終わり引き渡しを受けた日.............令和2年11月30日
ⅲ Xが上記ⅱの住宅に入居した日.....................令和3年6月30日
この場合に、Xは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるか。
A
Xは、増改築等の工事が終了した日の6月以内に入居していないことから、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
(解説)
中古住宅を取得後に入居することなく増改築等工事を行った場合、新型コロナウイルス感染症等の影響によって工事が遅延したことなどにより、当該住宅を取得した日から6月以内に入居できなかったときでも、次の全ての要件を満たす場合には住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる(新型コロナ税特法6①②、新型コロナ税特令4①)。
① 個人が取得した既存住宅につきその居住の用に供する前に行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増改築等に係る契約が当該既存住宅の取得をした日から5月を経過する日又は令和2年6月30日のいずれか遅い日までに締結されていること
② 当該既存住宅を上記①の増改築等の工事が終了した日から6月以内に居住の用に供していること
③ 当該既存住宅を令和3年12月31日までに居住の用に供していること
設問の場合、上記①及び③は満たすものの、上記②を満たさないことから、Xは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
なお、中古住宅を取得後に耐震改修をした場合も同様の取扱いとなる(新型コロナ税特法6③、新型コロナ税特令4②)。
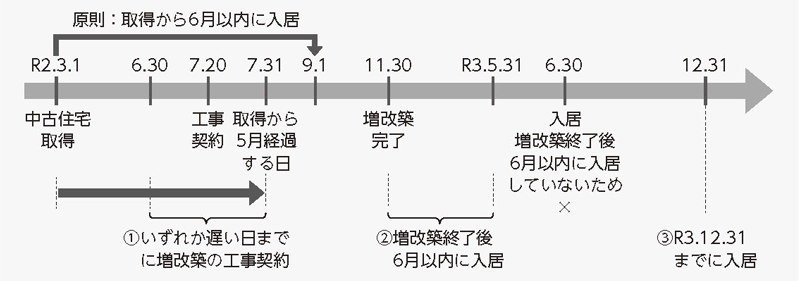
8.住宅借入金等特別控除の面積要件の特例に係る所得要件
Q
Xは、令和3年2月に、居住用家屋の新築を目的とする工事請負契約(消費税率10%)をZ社との間で締結し、同年7月中に、Z社からこの家屋(本件家屋)の引渡しを受け、同年10月中に本件家屋に入居した。
なお、本件家屋の登記簿に表示されている床面積は43㎡であった。
また、Xの令和3年分における所得の状況等は以下のとおりであった。
ⅰ 事業所得の金額......................................1,200万円
ⅱ 令和3年分に繰り越された令和2年分の純損失の金額.............300万円
この場合に、Xは、住宅借入金等特別控除の控除期間の特例(13年間適用)を受けることができるか。
A
Xは、住宅借入金等特別控除の控除期間の特例(13年間適用)を受けることができるが、令和3年分においては、住宅借入金等特別控除を受けることができない。
(解説)
令和3年度税制改正により、新型コロナ税特法における住宅借入金等特別控除のさらなる特例として、居住用家屋を令和2年12月31日までの間に居住の用に供することができなかった場合であっても、住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした場合や、特例居住用家屋の新築取得等で特例特別特例取得に該当するものをした場合に、当該新築取得等した家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の控除期間を居住年以後13年間とする控除期間の特例(措法41⑬)の適用を受けることができることとされている(新型コロナ税特法6の2①④)。
ここで、特例居住用家屋とは、居住の用に供する家屋で床面積が40㎡以上50㎡未満であるものをいい(新型コロナ税特法6の2④、新型コロナ税特令4の2②)、特例特別特例取得とは、家屋の新築の場合には、その新築の対価に係る消費税率が10%であり、かつ、その家屋の新築に係る契約が令和2年10月1日から令和3年9月30日までに締結されているものをいう(新型コロナ税特法6の2⑩、新型コロナ税特令4の2⑭)。
Xの住宅の取得は、特例居住用家屋を特例特別特例取得したものであるが、特例居住用家屋を特例特別特例取得した場合の特例は、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されないこととされている(新型コロナ税特法6の2④)ところ、合計所得金額とは、純損失の繰越控除(所法70)の適用がある場合であっても、当該繰越控除を適用する前の総所得金額等の合計額をいう(所法2①三十イ(2))。そうすると、Xの令和3年分の合計所得金額は1,200万円であり、1,000万円を超えるため、令和3年分において、Xは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないことになる。
なお、令和4年分から令和15年分までの各年分のうち、Xの合計所得金額が1,000万円以下である年分については、住宅借入金等特別控除の適用があることに留意する。
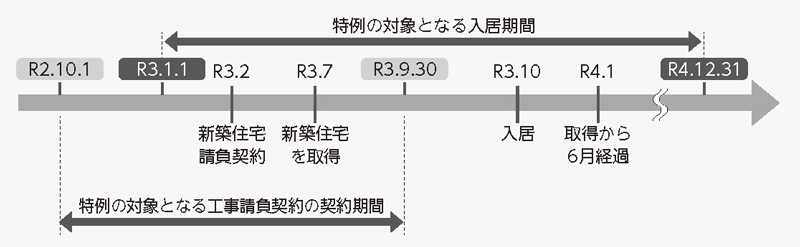
国外財産調書
9.国外財産調書による加算税の軽減措置の適用範囲
Q
Xは、内国法人Zの代表取締役を務める日本の居住者であるところ、Zは米国に所在するマンション(本件マンション)の貸付事業を営んでいる。
Xは、Zの行った本件マンションの貸付事業から生ずる所得は、実質的にはX自身の不動産所得に該当するとして、本件マンションの減価償却費等による損失の金額と他の所得との損益通算をして算出した総所得金額を記載した令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を、令和3年3月13日に提出した。その後、Xは税務調査において、Zの行った不動産貸付事業から生ずる所得はXの不動産所得には該当しない旨の指摘を受け、当該指摘に基づいて、令和3年8月14日に、修正申告書(本件修正申告書)を提出した。
なお、Xは、令和2年12月31日分国外財産調書を令和3年3月14日に提出しており、当該国外財産調書には本件マンションに関する事項が記載されていた。
本件修正申告書に基づいて課されるべき過少申告加算税について、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外送金等調書法)6条1項《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》に規定する加算税の軽減措置は適用されるか。
A
本件修正申告書の提出に基づいて課されるべき過少申告加算税について、国外送金等調書法6条1項に基づく加算税の軽減措置は適用されない。
(解説)
国外送金等調書法6条1項は、国外財産に関して生ずる一定の所得に対する所得税に関し修正申告書の提出があり、国税通則法65条《過少申告加算税》の規定の適用がある場合において、提出期限内に提出された国外財産調書にその修正申告の基因となる国外財産について国外送金等調書法5条1項の規定による記載があるときは、国税通則法65条の規定による過少申告加算税の額から一定の金額を控除する旨規定している。ここにいう「記載」とは、国外送金等調書法施行規則12条1項によると、国外送金等調書法5条1項本文の規定に該当する者の有する国外財産の種類等とされている。そうすると、国外送金等調書法6条1項の規定の適用上、「国外財産」とは同項中の修正申告書等を提出すべき個人が有する「国外財産」に限られ、当該個人以外の者が有する「国外財産」はこれに当たらない。
本設例において、Xが提出した修正申告書は、Zが有する国外不動産の貸付けから生ずる所得を誤ってXの所得として申告したことに基因するものであるから、本件マンションに関する事項が、Xの提出した国外財産調書に記載されていたとしても、当該修正申告書に基づいて課されるべき加算税について、国外送金等調書法6条1項に基づく軽減措置は適用されない。
消費税編
10.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による消費税の納税義務の免除の特例
Q
個人事業者Xは、令和元年7月1日に新たに事業を開始するとともに、令和元年分の課税期間を適用開始課税期間とする「消費税課税事業者選択届出書」を提出している。
令和3年3月1日に、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年10月分の事業としての収入金額が著しく減少したとして、令和2年分の課税期間に係る「新型コロナ税特法第10条第3項の規定に基づく消費税課税事業者選択不適用届出に係る特例承認申請書」及び「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出し、当該特例承認申請書につき税務署長の承認を受けた。
その後、Xが令和3年分の課税期間につき次のように各手続を行った場合、それぞれ令和3年分の課税期間に係る納税義務はどのようになるか。
なお、Xの各課税期間に係る基準期間における課税売上高は1,000万円以下であり、各課税期間において消費税法9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》、10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》及び12条の4《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例》の規定の適用はない。
(1)令和2年分の課税期間を特定課税期間とする令和3年分の課税期間に係る「新型コロナ税特法第10条第1項の規定に基づく消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」及び「消費税課税事業者選択届出書」を令和3年3月31日に提出した場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月分の事業としての収入金額が著しく減少したとして、令和3年分の課税期間に係る「新型コロナ税特法第10条第1項の規定に基づく消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」及び「消費税課税事業者選択届出書」を令和4年3月31日に提出した場合
A
いずれの場合も、Xの令和3年分の課税期間に係る納税義務は免除されない。
(解説)
(1)の手続を行った場合
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に事業としての収入の著しい減少があった事業者(特例対象事業者)が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき課税事業者の選択の適用を受けることについて税務署長の承認を受けたときは、「消費税課税事業者選択届出書」をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日に提出したものとみなされる(新型コロナ税特法10①、新型コロナ税特令7、新型コロナ税特法消関係通2)。
なお、その承認を受けようとする場合には、特定課税期間の末日の翌日から2月(個人事業者の12月31日の属する課税期間である場合には、3月)を経過する日までに「新型コロナ税特法第10条第1項の規定に基づく消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」を提出しなければならないこととされている(新型コロナ税特法10⑦一)。
そうすると、Xは、特定課税期間である令和2年分の課税期間の末日の翌日から3月を経過する日である令和3年3月31日に「新型コロナ税特法第10条第1項の規定に基づく消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請書」及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出しており、また、令和3年分の課税期間は、特定課税期間以後の課税期間に該当することから、当該申請書につき税務署長の承認を受けることを前提として、同日に提出された「消費税課税事業者選択届出書」は、令和3年1月1日の初日の前日に提出したものとみなされる。
したがって、Xの令和3年分の課税期間に係る納税義務は免除されない。
(2)の手続を行った場合
Xは、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月分(令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間)の事業としての収入金額が著しく減少しているため、令和2年分の課税期間のみならず、令和3年分の課税期間についても特定課税期間となる。
そうすると、Xは、特定課税期間である令和3年分の課税期間の末日の翌日から3月を経過する日である令和4年3月31日に「新型コロナ税特法第10条第1項の規定に基づく消費税課税事業者選択届に係る特例承認申請書」及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出していることから、当該特例承認申請書につき税務署長の承認を受けることを前提として、同日に提出された「消費税課税事業者選択届出書」は、令和3年1月1日の初日の前日に提出したものとみなされる。
したがって、Xの令和3年分の課税期間に係る納税義務は免除されない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















