解説記事2022年03月07日 最新判決研究 関係会社間の非上場株式の譲受けと受贈益の認定(2022年3月7日号・№921)
最新判決研究
関係会社間の非上場株式の譲受けと受贈益の認定
東京地裁令和3年10月29日判決(令和2年(行ウ)第394号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告)は、平成18年8月に設立されたインターネット等を利用したマーケティング業務等を目的とする株式会社(平成27年11月に商号変更、変更前を「I社」という。)であるが、平成27年11月11日付で、平成27年2月18日に設立された有価証券の保有等を目的とするK社を吸収合併した。K社の設立当時の発行済株式総数は、200株であり、Xの代表取締役Eがその全部を保有していたが、平成27年2月21日に、その全部がT及びS(以下「Tら」という。)に100株ずつ譲渡された。K社は、平成27年3月30日付で、Xの発行済株式の全部437株(以下「本件株式」という。)を保有していたH社から本件株式を対価12億1000万円(以下「本件対価の額」という。)を譲り受けた(以下「本件株式譲受け」という。)。H社は、英領ヴァージン諸島に設立された外国法人であり、その発行済株式全部がTらに2分の1ずつ保有されていた。そして、Xは、平成28年1月24日、平成27年2月18日から同年10月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)分法人税について上記の事実に基づき確定申告した。
なお、K社、H社、X及びTらとA社(平成14年10月設立、スマートフォン等のモバイルコンテンツの企画、開発等を目的。平成25年7月ジャスダック市場に上場)との間で、平成27年3月2日付けの基本合意書(以下「本件基本合意書」という。)を作成し、本件合併後に、A社がXを吸収合併することが約され、その際の本件株式の価額が25億2538万円余と評価されていた。
以上の一連の取引(以下「本件スキーム」という。)等を図解すると、別図のとおりとなる。
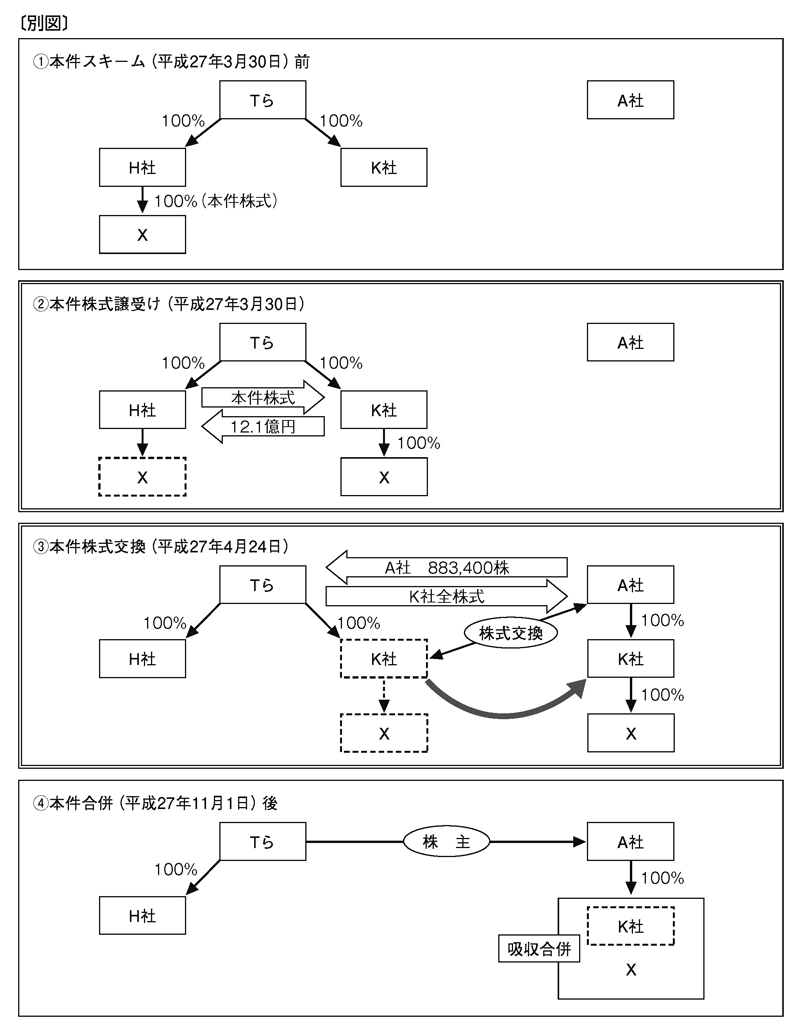
(2)これに対し、処分行政庁は、平成30年7月27日付でXに対し、K社の平成27年2月18日から同年10月31日までの事業年度(以下「本件K事業年度」という。)分法人税について、本件株式の価額25億2538万円余として、本件対価の額との差額につき、受贈益を認定し、更正及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服として、国(被告)に対し、前審判手続を経て、その取消しを求めて、本訴を提起した。
二、争点と当事者の主張
1 争 点
(1)本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額を受贈益の額として益金の額に算入すべきか。
(2)本件更正の理由附記に不備があるか。
なお、本稿においては、(2)の争点については、詳述を省略する。
2 国の主張
(1)法人税法22条2項は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のもの」に関わる収益の額を益金の額に算入すべきことを規定している。そして、適正な価額よりも低い対価をもってする資産の譲受け(低額譲受け)の場合であっても、譲受けの時点において、当該資産の適正な価額に相当する経済的価値の実現が認められることは、無償による資産の譲受けの場合と同様である。
(2)本件においては、第三者算定機関の本件株式の評価は、36億円を上回るとされていたものであり、この評価が不合理であるとする理由も見当たらないことに加えて、本件各合意当事者において、本件株式の価額が25億2538万円余(本件対価の額12億1000万円+A社株式88万3400株に1489円を乗じた金額である13億1538万2600円)と評価されていたことからすれば、本件株式の適正な価額は、少なくとも25億2538万円余を下回るものではなく、同金額を本件株式の適正な価額とみることに合理性があった。
(3)Xは、本件スキームにおける本件株式譲受けと本件株式交換とは一体の取引であって、各取引において本件株式の時価相当額25億2538万円余で取引されているのであるから、各取引において各当事者が贈与をしたり、贈与を受けたりすることはないと主張するようである。
しかしながら、本件株式譲受けと本件株式交換は、取引の当事者、取引の対象となる資産及び取引形態が異なる別々の取引である。仮に、本件株式譲受けと本件株式交換が本件スキームに基づいて一体の取引として行われたとしても、これらの各取引を一体として、各当事者の所得金額を計算すべきとする法的根拠はなく、Xの主張は法的根拠を欠いた独自の見解にすぎない。
3 Xの主張
(1)本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額13億1538万円余は、本件K事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるべき事実がないにもかかわらず、処分行政庁は、本件更正等を行い、本件K事業年度の法人税額につき所得金額を13億0248万円余とし、過少申告加算税の額を4617万円余等と算定したものである。したがって、本件更正等には、重大な事実誤認があるからいずれも違法である。
(2)すなわち、本件基本合意書の1条に本件株式譲受け及び本件株式交換を順次実施し、もってK社をA社の完全子会社及びXをK社の完全子会社とするとあることから分かるとおり、本件株式譲受けと本件株式交換は、本件スキームの中で一体的に行われているのであって、別個独立に行われているわけではない。
TらとA社は、TらがH社を通じて保有していた本件株式を手放す対価について、本件株式の適正な価額を本件株式譲受けによって交付される現金12億1000万円と本件株式交換によって交付されるA社の株式88万3400株の本件株式譲受日の時価相当額との合計額とすると合意して本件株式譲受けと本件株式交換を行っている。このため、本件株式譲受けだけを根拠に、K社がH社に対し、現金12億1000万円に加えてA社の株式88万3400株の本件株式譲受日の時価相当額である13億1538万円余を支払わなければならない(当該金額をK社からH社に支払わなければ、当該金額がH社からK社への贈与となる。)などということはあり得ず、本件株式譲受けによってK社がH社から13億1538万円余の贈与を受けたとする本件更正の事実認定は誤っている。
(3)国の法人税法22条2項の解釈は誤っている。受贈益の額は、資産の対価と適正な価額との差額のうちの「実質的に贈与を受けたと認められる金額」に限られると解される。このことは、①同項の立案過程から、資産の低額譲受けの場合、常に資産の対価と適正な価額との差額の全額が収益の額となる受贈益の額とされるのではなく、その差額のうち贈与を受けたと認められる金額があるときに限り、その金額が受贈益の額とされると解されていたことを確認することができ、②資産の低額譲渡等における寄附金の額について定めた法人税法37条8項は、資産の対価と適正な価額との差額のうち、「実質的に贈与をしたと認められる金額」のみが寄附金の額となると規定し、③同様に、資産の低額譲受け等における受贈益の額について定めた同法25条の2第3項も、資産の対価と適正な価額との差額のうち「実質的に贈与(中略)を受けたと認められる金額」のみが受贈益の額となるとされていることから裏付けられている。
(4)そして、資産の低額譲受けの場合に、法人税法22条2項の収益の額として益金の額に算入される受贈益の額となる資産の対価と適正な価額との差額のうち、「実質的に贈与を受けたと認められる金額」は、「全契約内容」に従って判断されるべきである。本件においては、本件スキーム及びそれに関する本件基本合意書並びにこれに基づく本件株式譲渡契約、本件株式交換契約及び本件合併契約の「全契約内容」に従って「実質的に贈与を受けたと認められる金額」のみを受贈益の額として益金の額に算入しなければならない。本件株式譲渡契約は本件スキームの一部であり、これに基づく本件株式譲受けは、本件スキーム上、その後に連なる本件株式交換及び本件合併と切り離して考えてはならないものである。そして、本件株式譲渡契約の内容はもとより、本件基本合意書、本件株式交換契約及び本件合併契約の内容まで子細に確認してみても、これらの契約の当事者間で贈与をしたり贈与を受けたりすることがあると解することはできない。
三、判決要旨
請求棄却。
(1)法人税法22条2項の趣旨は、法人が資産を無償で譲り受ける場合には、譲受時における資産の適正な価額(時価)に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものと解される。
そして、譲受時における適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲受けの場合にも、当該資産には譲受時における適正な価額に相当する経済的価値が認められるところ、たまたまそのうちの一部のみについて対価が現実に支出されたからといって対価の額と適正な価額との差額部分の収益が認識され得ないものとすれば、無償譲受けの場合との間の公平を欠くことになるから、その趣旨からして、この場合に益金の額に算入すべき収益の額は、当該資産の譲受けの対価の額と同資産の譲受時における適正な価額との差額であると解される(資産の低額譲渡につき最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決・民集49巻10号3121頁参照)。
(2)本件更正は、平成27年3月30日付けで本件株式譲渡契約に基づき、H社からK社に対してされた本件株式譲受けに係る本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額を受贈益の額と認定して、法人税法22条2項に基づき本件事業年度の益金の額に算入したものであるところ、本件株式の適正な価額が25億2538万円余であることについては当事者間に争いがなく、また、前記前提事実によれば、本件株式譲渡契約に係る本件株式の対価は12億1000万円(本件対価の額)と認められる。
上記のとおり本件対価の額は本件株式の適正な価額を下回る金額であることからすると、本件株式譲受けは、資産の低額譲受けに当たるものであるから、この場合に益金の額に算入すべき受贈益の額は、前記説示したところによれば、当該資産の譲受けの対価の額と当該資産の譲受時における適正な価額との差額であるというべきである。
そうすると、本件株式譲受けに係る受贈益の額は、本件対価の額である12億1000万円と本件株式の適正な価額である25億2538万円余との差額である13億1538万円余であるというべきであるから、これを本件株式譲受けに係る受贈益の額と認定して益金の額に算入するのが相当である。
(3)これに対し、Xは、受贈益の額は、資産の対価と適正な価額との差額のうちの「実質的に贈与を受けたと認められる金額」に限られる旨主張する。
しかしながら、前記説示したとおり、法人税法22条2項によれば、資産の低額譲受けの場合にも、当該資産には譲受時における適正な価額に相当する経済的価値が認められるため、当該資産の譲受けの対価の額と譲受時における資産の適正な価額との差額に相当する収益があると認識すべきであるものと解されることからすれば、これを「実質的に贈与を受けたと認められる金額」に限定して解釈すべき理由はないというべきである。
この点についてXは、法人税法22条2項の立案過程から、資産の低額譲受けの場合、常に資産の対価と適正な価額との差額の全額が受贈益の額とされるのではなく、その差額のうち贈与を受けたと認められる金額があるときに限り、その金額が受贈益の額とされるということを確認することができる旨主張する。
しかしながら、昭和40年度税制改正によって制定された現行の法人税法22条2項について、その法案の国会への提出前の立案過程において、昭和38年B案42条として、著しく低い価格の対価により資産を譲渡した場合に、当該資産の時価と当該対価の額の差額に相当する金額のうちに贈与をしたものと認められる部分の金額があるときは、当該贈与をしたものと認められる部分の金額を益金の額に算入する旨の規定が検討されたことが認められるが、同案は、飽くまで立案過程での一案にとどまり、実際には同案で検討された文言が現行法人税法22条2項に反映されなかったのであるから、これをもって同項の解釈の根拠とすることはできない。
また、Xは、法人税法37条8項が、内国法人が資産の譲渡等をした場合において、その譲渡等の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれるものとする旨を規定していることをもって、資産の低額譲受けの場合にも同法22条2項の解釈として受贈益の額となるのが、資産の対価と適正な価額との差額のうちの「実質的に贈与を受けたと認められる金額」に限られる旨主張をする。
しかしながら、法人税法にいう寄附金の額の認定に関し、同法37条7項は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産の贈与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与時における価額によるものとするが、このうち広告宣伝費及び見本品の費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費等とされるべきものを除くと規定しており、贈与をした側においては、金銭その他の資産の贈与であっても上記の交際費等とされるべきものは寄附金の額には含まれないのに対し、同法22条2項の収益の額は、前記のとおり資産の譲受時の適正な価額をもって認識されるべきものであるから、贈与を受けた側においては、贈与をした側の費目が寄附金であっても交際費等であっても、収益の額となることに何ら変わりがないものとされている。
そうすると、法人税法における寄附金の額の認定の問題と、同法22条2項に基づく収益の額の認定の問題は、基本的に別個のものというべきであるから、同法37条8項を根拠とするXの上記主張は採用することができない。
さらに、Xは、法人税法25条の2第3項は、資産の対価とその適正な価額との差額のうち「実質的に贈与(中略)を受けたと認められる金額」のみが受贈益の額となると規定していることをもって、資産の低額譲受けの場合にも、同法22条2項の解釈として受贈益の額となるのが資産の対価と適正な価額の差額のうちの「実質的に贈与(中略)を受けたと認められる金額」に限られる旨主張をする。
しかしながら、法人税法25条の2第3項は、飽くまで内国法人が他の内国法人との間に完全支配関係がある場合に限定して、同条1項において益金不算入とされる受贈益についてその額を定めている規定であり、同条3項は、同法22条2項にいう「別段の定め」に該当するものである。
そして、前記前提事実によれば、本件株式譲渡の時点において、H社とK社とは完全支配関係にはなかったと認められるのであるから、本件において法人税法25条の2第3項が適用される余地はないというべきであるし、同項が同法22条2項にいう「別段の定め」に該当する以上、このような特則の規定から遡って益金算入に関する一般的規定である同項を解釈する根拠とするのは妥当ではない。
なお、証拠によれば、K社は、本件株式を取得するに当たり、本件対価の額と同額の12億1000万円を借り入れていることが認められ、本件株式以外には資産がなく、その時点でのK社の純資産額は資本金と同額の1000万円であったことが認められる。そして、前記前提事実のとおり、本件株式譲受後にされた本件株式交換契約において、A社の株式88万3400株(本件株式譲受日における時価相当額13億1538万円余)がK社の全株式との交換の対価としてK社の株主であるTらに対し交付されていることが認められるが、上記のとおりK社の純資産額は1000万円しかなかったのであるから、A社の株式88万3400株がTらへの本件株式交換の対価とされたことは、本件株式譲受けにおいて、K社が本件対価の額12億1000万円と本件株式の適正な価額25億2538万円余との差額13億1538万円余も含めてH社から実質的に贈与を受けたことを示しているというべきである。
そうすると、仮に、受贈益の額は、資産の対価と適正な価額との差額のうちの「実質的に贈与を受けたと認められる金額」に限られると解する余地があるとしても、上記事実関係からすれば、本件株式譲受けにより、K社は本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額13億1538万円余を「実質的に贈与を受けたと認められる」から、Xの前記主張はこの点からも採用することができない。
(4)次に、Xは、受贈益の額となる資産の対価と適正な価額との差額のうち「実質的に贈与を受けたと認められる金額」は、「全契約内容」に従って判断されるべきであるとし、本件スキームに係る「全契約内容」に照らして本件株式譲受けに当てはめる限り、本件株式交換がされたから「実質的に贈与を受けたと認められる金額」がどこにもなく、したがって、本件株式譲受けにおいて、K社には受贈益の額はない旨主張をする。
Xの主張は、判然としない部分があるが、本件における法人税法22条2項の収益の額の認定に当たっては、本件スキームに係る全契約内容に照らし、本件株式譲受けに係る対価には、本件対価の額である12億1000万円に限られず、その後行われた本件株式交換契約に基づきTらに交付されたA社の株式88万3400株(本件株式譲受日における時価相当額13億1538万円余)も含まれると主張するものと解される。しかしながら、法人税法22条2項の収益の額として、資産の対価と適正な価額との差額のうち「実質的に贈与を受けたと認められる金額」のみが受贈益の額となるものではないことは前記説示のとおりである。
また、法人税法22条2項の収益の額の認定に当たり、契約内容全体に照らして解釈すべきであるとしても、法人税の取扱いにおいては、資産の販売等に係る収益の額の認定は、同一の相手方又はこれとの間に支配関係等がある者との間で締結した複数の契約について、一定の場合に結合したものを一つの契約とみなし収益を認定する場合もあるが、このような場合を除き、個々の契約ごとに計上するのが原則であると解される。
前記前提事実によれば、本件株式譲渡契約と本件株式交換契約は、本件スキームの一環として行われたものであると認めることができるが、これらの契約が締結された時点では、本件各合意当事者は、いまだ支配関係にあるものではなかったと認められる。また、前記前提事実によれば、本件株式譲渡契約は、H社とK社を当事者として本件株式を本件対価の額で譲渡するものであったのに対し、本件株式交換契約は、K社とA社を当事者として、K社の全株式とA社88万3400株とを交換するものであり、かつ、本件株式交換契約の対価であるA社の株式の交付を受けたのはTらであったことが認められるところ、これによれば両契約は、取引の当事者、取引対象とする資産及び取引態様を異にする別個の取引であったといわざるを得ない。
そうすると、法人税法22条2項の収益の額の認定に当たり、契約内容全体に照らして解釈すべきであるとしても、本件株式譲渡契約に係る対価として、本件対価の額のほかに、別個の契約である本件株式交換契約に係る対価であるA社の株式88万3400株を、本件株式譲受けの対価と認めることはできない。
(5)以上によれば、本件株式譲受けに係る受贈益の額には、本件対価の額である12億1000万円と本件株式の適正な価額である25億2538万円余との差額である13億1538万円余であるというべきであるから、これを本件株式譲受けに係る受贈益の額として益金の額に算入するのが相当である。
四、解説
はじめに
現行の法人税法は、昭和40年に全文改正された条文を基にしている。全文改正された当時の法人税法は、単体課税を原則とし、法人間のいかなる取引も、その段階で損益を認識していた。その代表的な規定が、法人税法22条2項に定める無償取引において収益を認識する規定である。すなわち、法人間で資産の無償譲渡が行われると、当該資産のその時の「価額」によって、譲渡法人には、当該「価額」による収益の額と寄附金という損失の額が認識され、譲受け法人には、当該「価額」による受贈益(収益の額)が認識された。そして、資産の低額取引については、当該対価による有償取引と当該対価と当該資産の「価額」との差額が無償取引に当たると解され、当該無償取引部分について、前述のような収益の額が認識された。
ところが、平成13年に組織再編成税制が導入され、平成14年に連結納税制度が導入され、そして、平成22年にいわゆるグループ法人課税制度が導入されると、前述の単一法人課税制度と所定のグループ法人間の無償取引から収益等を認識しないというグループ法人課税制度等が混在することとなり、法人税法の条項とその解釈を極めて複雑なものとした。
本件は、当事者からすれば、本件スキーム全体において損益を認識すれば足りるものと考えたことであろうが、処分行政庁が、関係法人間の個々の取引について、損益を認識して、低額譲渡(低額譲受け)に当たるとし、当該資産(本件株式)の対価の額と「価額」との差額について、譲受け法人(K社)に対し受贈益を認識した上で、K社を吸収合併したXに対し課税処分(本件更正)を行ったものである。このような課税処分については、前述した法人税法が全文改正された当時の考え方からすれば、至極当然であるかのように考えられるが、前述のような法人税制の変遷により、グループ課税制度等が導入された現行法の下では、考えさせられるところがある。
以下、関係条項を確認した上で、本件更正の当否を検討することとする。
1 無償取引と収益認識
(1)法人税法5条は、「内国法人に対しては、各事業年度(〈略〉)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。」と定めている。この場合、「所得」とは何かということと、そのことと本稿で問題になっている「無償取引から収益が生じる」ことの関係を明らかにする必要がある。一般に、各税法上の用語には、借用概念と固有概念がある。借用概念は、他の法分野で用いられている用語であり、他の法分野から借用しているという意味で借用概念と呼ぶ。例えば、所得税法上の「住所」、「配偶者」等がある。そして、借用概念の解釈については、他の法分野と別意に解すべきことが租税法規の明文又はその趣旨から明らかな場合は別にして、他の法分野におけると同じ意味に解することが、法的安定性の見地から望ましいと解されている(注1)。
他方、固有概念は、他の法分野では用いられておらず、租税法が独自に用いている概念である。そして、固有概念は、社会生活上又は経済生活上の行為や事実を他の法分野の規定に通ずることなしに、租税法規に取り込んでいるから、その意味内容は、法規の趣旨・目的に照らして租税法独自の見地から決めるべきであると解されている(注2)。この固有概念の代表的なものとして、「所得」がある。
その所得の概念も、一律ではなく、消費型所得概念と取得型所得概念に区分され、法人税の課税対象となる取得型所得概念も、制限的所得概念と包括的所得概念に区分される。制限的所得概念は、利子、配当、地代、利潤、給与等、反覆的・継続的に生ずる利得のみを所得として観念し、一時的・偶発的・恩恵的利得を所得の範囲から除外する考え方である。これに対し、包括的所得概念は、人の担税力を増加させる経済的利得はすべてが所得を構成すると観念する(注3)。我が国の所得税法及び法人税法は、包括的所得概念によっている。
(2)そして、法人税法は、「内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。」(法法21)と定め、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、各事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」(法法22①)と定めている。この「益金」については、昭和25年制定の旧法人税基本通達が、「総益金とは……純資産増加の原因となるべき一切の事実をいう。」(同通達51)と定め、包括的所得概念と同義である純資産増加説を宣明していたが、昭和44年5月の新法人税基本通達の制定に際し、法令の解釈上疑義がなく、条理上明らかであるということで削除された(注4)。
そして、法人税法22条2項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と定めている。この収益が生じる取引のうち、解釈上、最も問題となるのが、「無償による資産の譲渡」及び「無償による役務の提供」である。
本件で問題になる「無償による資産の譲渡」から収益が生じることについては、一般的には、「無償による譲渡の場合には、現実的には収益が生じないが、一旦収益が実現し、しかる後にそれが贈与されたものと考えるべきである。」と解されている(いわゆる二段階説)。ともあれ、「無償による資産の譲渡」から収益が生じることについては、当該資産の所有期間中に生じた評価益相当額(キャピタル・ゲイン)が、その譲渡(処分)によって実現したと認識され、収益が生じたものと解される(注5)。なお、資産の低額譲渡については、当該譲渡の対価と当該資産の「価額」と差額が「無償による資産の譲渡」となる。
(3)上記のように、「無償による資産の譲渡」から収益が認識し得るとしても、当該法人において当該収益が留保されているわけではないので、当該収益が流出したものと観念される。その流出項目が、役員給与(退職給与)であったり、寄附金として認識される。この場合、寄附金の額については、法人税法37条7項が、「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(〈略〉)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益その供与の時における価額によるものとする。」と定めている。
そして、法人税法37条8項は、次のように定めている。
「内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。」
次いで、上記の資産の譲渡を受けた側又は寄附金を受けた側には、「無償による資産の譲受け」があったことになり、受贈益として収益が認識されることになる。
以上が、法人税法が収益の認識について定めた基本原則である。
2 収益認識の特例(別段の定め)
(1)昭和40年に全文改正された法人税法においては、前述した法人税法22条2項の規定が収益認識の原則とされ、それと異なる別段の定めは極めて限られていた。しかし、冒頭でも述べたように、平成10年代以降の法人税法22条2項の特則である別段の定めが非常に多くなり、法人税法上の所得計算の構造自体が複雑なものになってきている。その一つが、収益認識についての重複的な規定である。例えば、法人税法22条の2は、企業会計との調整のために設けられた規定であると言われるが、その1項で、「内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(〈略〉)に係る収益の額は、〈略〉その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。」と定めているが、このような定めは、法人税法22条2項の下で通達等によって解釈されていたことであるが、わざわざ法定することに疑問がある。
また、法人税法61条の2は、「内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(〈略〉)又は譲渡損失額〈略〉は、〈略〉その譲渡に係る契約をした日(〈略〉)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。」と定めているが、これも、法人税法22条2項と重複しているものと考えられる。
そして、法人税法62条1項は、「内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」と定めているが、これも、法人税法22条2項の規定から解釈できることであると考えられる。
(2)上記のような規定の要否はともかくとして、法人税法22条2項の規定とは異なって、資産の移転等があっても、その時点では収益を認識しない別段の定め(特例)が多く設けられている。例えば、法人税法25条の2第1項は、「内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(〈略〉)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(〈略〉)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。」と定めている。また、連結納税に関しては、連結納税の開始に伴う所定資産の時価評価損益を当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入するとし(法法61の11①)、連結納税への加入の際にも同様な規定が設けられている(法法61の12)。他方、いわゆるグループ法人税制の下では、完全支配関係がある法人の間の取引の損益については、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産等以外の譲渡損益調整資産の譲渡損益に限り、その譲渡した事業年度の損益の額に算入することとしている(法法61の13)。
次に、上記のような所定の資産の譲渡損失の繰延べを最初に定めた(従来からある圧縮記帳制度を除く。)いわゆる組織再編成税制の下では、前述したように、合併等の組織再編成時に、原則として、譲渡損益を認識することを宣明した上で、所定の適格要件を充足した合併、分割、現物出資、現物分配、及び株式交付に係る資産移転について帳簿価額の引継ぎ(損益を認識しないこと)を定めている(法法62の2、62の4、62の5、62の6)。
以上のように、法人税法22条2項に定める収益認識の原則規定については、数多くの別段の定め(特則)が定められており、法人税の最近の実務では、そのような別段の定めをいかに活用するかということに関心が集中している。
3 本件株式譲受けと受贈益
(1)本件においては、Xによって平成27年11月に吸収合併されたK社が、同年3月、Xの発行済株式の全部(本件株式)を保有していたH社から、当該株式(本件株式)を12億1000万円(本件対価の額)で譲り受けた(本件株式譲受け)というものである。このような吸収合併、本件株式譲受け等は、K社、H社、X及びTらとA社との間で、最終的には、K社及びXをA社に吸収合併させるという一連の企業再編の合意(本件基本合意書)の下に行われたものであるが、その際の関係者間の本件株式の価額は25億2538万円余であると評価されていた。
かくして、Xは、上記事実に基づき、本件事業年度分法人税の確定申告したのであるが、処分行政庁が、K社が譲受けた本件株式の価額が25億2538万円余であったから、本件対価の額と差額が受贈益に該当する旨の更正(本件更正)等をしたため、本訴を提起した。本訴においては、専ら本件株式の価額が幾許であるかが争われたが、Xは、本件株式譲受け、本件株式交換等は本件スキームの中で一体的に行われたものであり、別個独立に行われたものではないから、本件対価の額も正当なものである旨主張し、国は、本件株式譲受けについて法人税法22条2項を適用すれば本件株式の価額は少なくとも25億2538万円余と評価され、本件対価の額と差額が受贈益として認識される旨主張した。
(2)本判決は、まず、前述したように、法人税法22条2項の趣旨につき、「法人が資産を無償で譲り受ける場合には、譲受時における資産の適正な価額(時価)に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものと解される。」と判示し、次いで、「本件株式譲受けは、資産の低額譲受けに当たるものであるから、この場合に益金の額に算入すべき受贈益の額は、前記説示したところによれば、当該資産の譲受けの対価の額と当該資産の譲受時における適正な価額との差額であるというべきである。」と判示した。
また、Xが、法人税法22条2項の立法時(昭和40年)の立案資料、法人税法37条8項が実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額を寄附金としていること、法人税法25条の2第3項が「実質的に贈与を受けたと認められる金額」について受贈益の額となるとしていること、本件株式譲受けは本件スキームの一環として行われたこと等を理由に、「受贈益の額は、資産の対価と適正な価額との差額のうちの「実質的に贈与を受けたと認められる金額」に限られる」旨主張したのであるが、本判決は、次のように判示し、いずれも理由がない旨退けている。すなわち、本判決は、昭和40年の立法当時の資料については、Xが主張するような案は採用されなかったこと、法人税法22条2項と同37条8項とは別規定であること、法人税法25条の2第3項は完全支配関係を前提としていること、本件スキームにおけるそれぞれの契約は別個独立の取引であること等を理由にしている。
(3)以上のように、本判決は、K社の本件株式譲受けにつき、法人税法22条2項の立法趣旨等を全面に出し、本件株式の価額と本件対価の額の差額について受贈益を認定し得ると判示し、Xが種々の理由から本件株式譲受けが実質的な贈与でない旨主張したのに対し、それらの理由を全て排斥した。このような判断については、前記1で述べた法人税法22条2項の立法趣旨等と前記2で述べた同項による収益認識の例外が所定の要件に充足しなければならないこと等に照らし首肯し得ると考えられる。
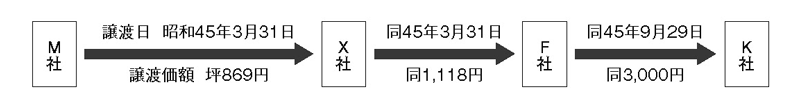
しかしながら、資産の無償又は低額取引から機械的に収益を認識し、受贈益を認識し得るかについては、従前の裁判例等に照らし、考えさせられるところもある。例えば、上記のようなM社、X社及びF社のグループ会社間で約定を結び各社の財政状況等を考慮した上で、土地ころがしを行い、最終的にはグループ会社外のK社に当該土地をその時価(坪3000円)で譲渡した場合に、所轄税務署長が、X社に対し、当該時価と譲受け、譲渡の対価の額の差額につき、受贈益と損失(寄附金)を認定した課税処分の適否が争われた事例がある(注6)(上掲参照)。
一審の大阪地裁昭和58年2月8日判決(税資129号172頁)は、法人税法22条2項及び同法37条8項を機械的に適用して、当該課税処分を適法と認めた。これに対し、大阪高裁昭和59年6月29日判決(行裁例集35巻6号822頁)は、この事案のように、Xが契約で指定された譲渡価額よりも高額(時価)で譲渡できる利益、権利、地位を有しなかったときは、時価で譲渡しなかったからといって、譲渡益(寄附金)課税はできない旨判示して、当該課税処分を取り消した。そして、この判決は、国も上告せず確定している。
他方、本件においては、K社の低額による本件株式譲受けも、関係会社間の約定に基づいて定められた価額によって行われたものであるから、その点では、前掲大阪高裁判決のような考え方を適用できないこともないと考えられる。また、前記2で述べたように、近年の法人税法は、グループ会社間等における取引について所定の条件の下に損益を認識しない(繰り延べる)条項を多く定めているので、それらとのバランスも考えさせられるところがある。
4 本判決の意義と問題点
以上のように、本件は、関係者及び関係会社間の一連の企業再編の取引(本件スキーム)の中で、K社がH社から本件株式を時価よりも低額で譲受け(本件株式譲受け)たことに対し、法人税法22条2項に基づく受贈益課税(本件更正)が行われ、当該処分の適否が争われたものである。本判決は、結局、法人税法22条2項の趣旨を厳格(忠実)に解し、本件更正を適法と認めた。このような判断は、組織再編成税制やグループ法人税制が導入されるまでは、法人税法22条2項の規定の下で、至極当然に受容されたものと考えられ、Xの方も訴訟を起すまでもなかったかも知れない。
しかし、上記各税制が導入されて以降、法人税法22条2項の規定の例外規定が多く設けられ、関係会社間等の取引について損益を認識しないケースが増加してきた。そのため、本件のような関係会社間等の取引についても、法人税法22条2項の例外として損益を認識すべきではないのではないかという考え方があっても不思議ではない。それに釘をさしたという点で、本判決の意義がある。しかし、本判決にも、前述のような問題があることを認識すべきである。
(注1)金子宏「租税法 第23版」(弘文堂 平成31年)127頁等参照。
(注2)前出(注1)129頁等参照。
(注3)前出(注1)195頁等参照。
(注4)詳細については、品川芳宣「課税所得と企業利益」(税務研究会出版局 昭和57年)4頁参照。
(注5)前出(注4)16頁等参照。
(注6)品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)360頁参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















