解説記事2022年05月16日 ニュース特集 D課税・第2の柱 コメンタリのポイントと法制化に向けた課題(2022年5月16日号・№930)
ニュース特集
赤字でも税額発生の仕組み、少数持分構成事業体ルール、CFC税制簡素化…etc.
D課税・第2の柱 コメンタリのポイントと法制化に向けた課題
OECDは昨年12月20日、デジタル課税・第2の柱「最低税率制度(ミニマム課税)」についてモデル・ルールを公表したが(本誌914号)、モデル・ルールを理解する上で欠かせないのが、モデル・ルールを解説した「コメンタリ」や図解や計算例等を用いた「事例集」だ。
本誌は、3月14日にOECDより公表されたコメンタリや事例集を解読した。そこで本特集では、モデル・ルール公表時に本誌が指摘していたGloBE所得がない(法域全体で赤字)場合にもトップアップ税額が生じる可能性や、企業から「通常のETR/トップアップ税額の計算と何が違うのかが分かりにくい」との声が上がっていた少数持分構成事業体ルールといったコメンタリの内容を解説しつつ、2022年法制化・2023年施行に向けた課題として、最低税率制度と類似するCFC税制の見直しの方向性について、独自取材に基づきレポートする。
赤字でもトップアップ税額が発生するメカニズム
永久差異対応部分については第1事業年度からトップアップ課税を強制
昨年12月に公表されたデジタル課税・第2の柱「最低税率制度(ミニマム課税)」のモデル・ルールの中で企業から懸念の声が上がったのが、モデル・ルール4.1.5だ。ここには、「ネットGloBE所得がない法域の事業年度において、当該法域の調整対象税額(注:ETRの分子)がゼロ未満かつ予定対象税額(注:ある法域におけるGloBE所得又は損失に最低税率(15%)を乗じた金額に相当する金額)に満たない場合には、その法域の構成事業体は、その法域に係る現行事業年度について、これら金額の差額に相当する金額の追加的な現行年度トップアップ税額を有するものとする」旨の記述があり、GloBE所得がない、すなわち法域全体で赤字の場合にもトップアップ税額が生じることが示唆されている。
これに対し企業からは、このメカニズムがモデル・ルールの要旨(executive summary)で謳われている「所得についてミニマム税を支払う」「利益に対するトップアップ課税」に反しているのではないかとの不満の声が聞かれたが、コメンタリとともに3月14日に公表された事例集に掲載された計算例により、GloBE所得がない場合でもトップアップ税額が生じることが明確となった(Example 4.1.5−1)。以下、数字を入れた事例で見てみよう。
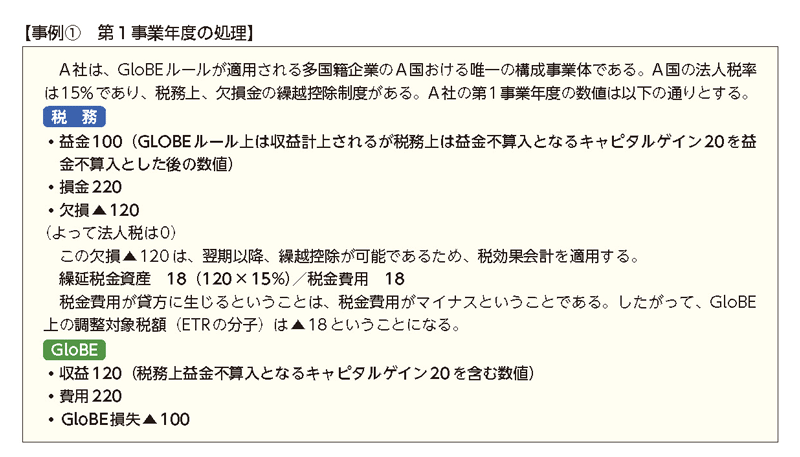
上記の通り予定対象税額とはGloBE損失に最低税率を乗じた金額であるため、事例①においては、「▲100×15%=▲15」となる。また、調整対象税額は上記の通り▲18である。A国における調整対象税額(▲18)はゼロ未満であり、かつ、予定対象税額(▲15)に満たないことから、調整対象税額(▲18)と予定対象税額(▲15)の差額(3)が、現行年度トップアップ税額ということになる。GloBE損失▲100でも3のトップアップ税額が生じるということだ。
この3という数字は、益金不算入となるキャピタルゲイン20にA国の法定税率=最低税率15%を乗じたものに等しい。欠損金▲120のうち▲20が永久差異であるキャピタルゲインの益金不算入額からなると見なすならば、この永久差異に係る繰延税金資産(20×15%=3)については、本来GloBEルールが対応すべき時間差異(一時差異)に対応するものではない。それにもかかわらず、何ら対応策を講じなければ、欠損金が繰越控除される翌期以降においては、繰延税金資産が取り崩される際に、永久差異に対応する部分も含めて調整対象税額を増やすことになるため(繰延税金資産を取り崩す際には、その由来に関係なく、「税金費用××/繰延税金資産××」という仕訳となり、税金費用(=調整対象税額)が増えることになる)、ETRを不当に嵩上げしてしまうということを懸念したわけだ。英国政府が議論を主導したと見られる。そこで、欠損金の計上に係る繰延税金資産の計上及び取り崩し自体には手を付けず、早めに第1事業年度で手を打ち、永久差異対応部分についてはトップアップ課税を強制するということである。なお、最初から永久差異部分を除外して欠損金に係る繰延税金資産を計上するという趣旨の案も検討された模様だが、関連する数値の管理が煩雑になるとの理由により採用されなかったことがコメンタリで説明されている(第4章パラ20)。
事例集では、第2事業年度の処理についても触れている。ここでは、税務上とGloBE上の数値が等しいと仮定されている(事例②参照)。
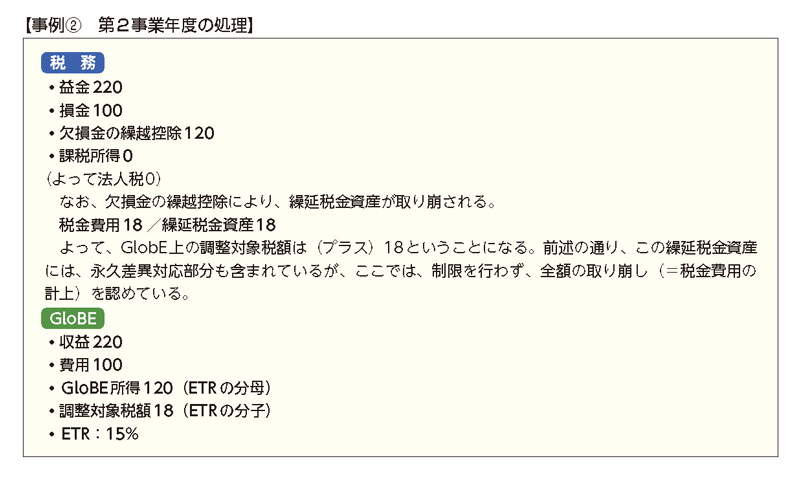
このように、欠損金が繰越控除される前に永久差異対応部分についてトップアップ課税を強制することで、ETRの分子嵩上げによる“IIR免れ”は不可能となる。
少数持分構成事業体ルール
少数持分グループとその他グループの所得・税額はブレンディングせず
最低税率制度では、通常の租税負担割合(ETR)/トップアップ税額の計算とは異なる特別ルールが整備されている。その1つが少数持分構成事業体ルールだ。
少数持分構成事業体に関する記述はモデル・ルールにおいても見られたところ(第5条6項)。それによると、「少数持分サブグループ」についてはあたかも別個の多国籍企業グループであるかのように租税負担割合(ETR)/トップアップ税額の計算等を行うとされている。定義規定においても一定の用語解説はなされていたが、企業からは「通常のETR/トップアップ税額の計算と何が違うのかが分かりにくい」との声が上がっていた。しかも、この少数持分構成事業体ルールについて、コメンタリとともに公表された事例集には図表等の掲載はない。そこで本誌オリジナルの資本関係図を用いながら、少数持分構成事業体ルールについて解説する。少数持分構成事業体ルールを理解する上では、次頁図のような資本関係図を想定するとよいだろう。
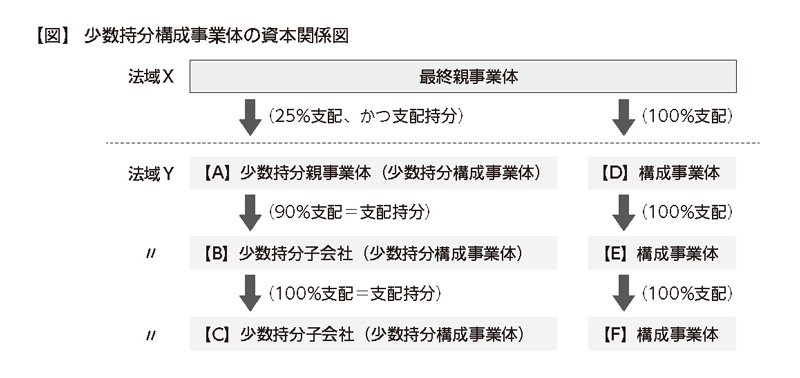
法域X所在の最終親会社が法域Yに所在する【A】の株式を25%有しており、かつ、支配持分を有している。そして、【A】は【B】の、【B】は【C】の支配持分を有している。この支配持分(Controlling Interest)とは、連結財務諸表において連結子会社として連結するだけの所有持分を意味する(モデル・ルール10.1の定義規定参照)。最終親事業体の【A】に対する株式保有割合は25%に留まるが、その他の影響力を行使することにより【A】を事実上支配し、財務諸表において連結している状況を指すと想定される。このほか、最終親事業体は、別系統で法域Yに構成事業体【D】【E】【F】を有する。
法域Yには構成事業体が6社あるが、【A】〜【C】のETR/トップアップ税額計算と、【D】〜【F】のETR/トップアップ税額計算は別個に行う。つまり、【A】〜【C】グループと【D】〜【F】グループの所得・税額は「ブレンディング」しない。【A】〜【C】系列は、最終親事業体による「支配」はあるものの、持分割合が低いため、いわばトップアップ税額の帰属計算上の“血のつながり”が薄く、【A】の他の75%の株主グループへの影響を考慮したということであろう。
支配持分を有していても「少数持分親事業体」に該当しないケースも
続いて定義を見ていこう。
まず少数持分構成事業体とは、最終親事業体による直接・間接の株式持分が30%以下である構成事業体をいう。上図では【A】【B】【C】が該当する。
次に少数持分サブグループとは、少数持分親事業体及びその少数持分子会社をいう。これも【A】【B】【C】が該当する。少数持分親事業体とは、他の少数持分構成事業体に対し直接・間接に支配持分を有する少数持分構成事業体をいう。ただし、当該少数持分構成事業体が別の少数持分構成事業体から支配持分を直接・間接に保有される場合は除かれる。この結果、【A】は少数持分親事業体に該当するが、【B】は【A】によって支配持分を保有されているため、少数持分親事業体に該当しないことになる。
最後に少数持分子会社とは、少数持分親事業体から支配持分を直接・間接に保有される少数持分構成事業体をいう。
なお、仮に上図を少し修正し、【A】を通じた【D】に対する支配持分の保有があり、かつ、最終親事業体が【D】の株式を60%保有しているとする。この場合、【D】は【A】を通じ支配持分を保有されるが、最終親事業体による持分が30%を超えるため少数持分構成事業体に該当せず、少数持分子会社ともならない(コメンタリ第5章パラ102)。
国内法制化に向けた課題
12月決算子会社の合算時期を3月決算子会社に合わせるよう求める声
令和4年度与党税制改正大綱には、デジタル課税について、「わが国企業等への過度な負担とならないように既存制度との関係などにも配慮しつつ、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する」との記述が盛り込まれている(与党大綱12頁参照)。ここでいう「既存制度」が外国子会社合算税制(CFC税制)を意味しているのは間違いない。最低税率制度は文字通り租税負担割合が最低税率15%に満たない法域の子会社について、15%に達するまで親会社所在地国でトップアップ課税を行うものであり、軽課税国の子会社の所得を親会社所在地国で合算課税するCFC税制と類似しているからだ。
与党大綱でいう「過度な負担」とは、企業側からすると過剰合算の解消と事務負担の軽減ということになるが、税制当局からすると事務負担の軽減だけと解釈することも可能である。CFC税制において仮に過剰合算が生じていたとしても、CFC合算税額は最低税率制度の租税負担割合の分子に加算できるため(その分、租税負担割合が上昇し、最低税率制度が発動しにくくなる)、CFC税制と最低税率制度において二重課税が生じるわけではないからだ。過剰合算は、必ずしも最低税率制度の導入と同時に解消する必要はなく、平時の税制改正で(時間をかけて)処理すれば足りるということになる。すなわち、最低税率制度と同時に対応すべきは事務負担の軽減であり、令和5年度税制改正におけるCFC税制の議論では、まず土俵(=検討のスコープ)をどのように設定するかが問われることになる。
ペーパーカンパニー等に係る全部合算の廃止にはハードルも
事務負担の軽減という観点から企業のニーズが高いのは、平成29年度税制改正で導入された、租税負担割合20%〜30%のレンジの特定外国関係会社(ペーパーカンパニー、キャッシュボックス)に係る全部合算の廃止だ。企業によっては、特定外国関係会社でないことの証明に時間ばかりかかり、結果として合算税額が生じていないケースも多い。この要望が実現すれば、判定対象の外国関係会社が相当減るというメリットがある。とはいえ、企業全体で見た場合には、このレンジで一定の合算税額が生じているのも事実であるため、税制当局がこの改正要望を素直に受け入れる可能性は高くない。
こうした中で急浮上しているのが、合算時期の見直し案だ。現状、合算対象所得は「(外国関係会社の)事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の事業年度」において益金算入することとされている(措法66の6①)。このため、3月決算法人である日本の親会社にあっては、中国等に多い12月決算の子会社の所得を、直後に到来する自らの3月期の法人税申告に急いで取り込まなければならず、合算所得金額を含め、各種係数を見込み計上せざるを得ないなど、綱渡りの実務を強いられている。これが3月決算の子会社であれば、余裕をもって親会社の次の期において合算ができる。12月決算であるか3月決算であるかで、これほど取扱いが異なるのは不合理であるとして、企業側では、12月決算の子会社であっても3月決算の子会社と同様の合算時期にしてはどうかとの意見が強まっている。
ただし、この論点はCFC税制のみで完結せず、親会社において合算税額が生じた場合に、その合算税額を最低税率制度における租税負担割合の計算上、子会社のどの事業年度において分子に加算するのかという論点とも関係する。今後、一体的な検討が進むだろう。
プッシュダウンは「当該子会社の受動的所得×トップアップ税率」が限度に
また、このCFC合算税額の分子への加算(プッシュ・ダウンと呼ばれる)には制限が行われ(モデル・ルール4.3.3)、計算例も公表されている(事例集4.3.3−1)。簡潔に言えば、子会社の受動的所得に係るCFC税額として親会社法域から子会社法域にプッシュダウンできる金額は、当該子会社の受動的所得にトップアップ税率(最低税率15%−その子会社法域の租税負担割合)を乗じた金額が限度となる。この受動的所得とは、(a)配当又は配当同等物、(b)利子又は利子同等物、(c)賃借料、(d)使用料、(e)年金、(f)上記(a)〜(e)の所得を生み出す資産に係るネット・ゲインとされており(モデル・ルール定義規定)、機械的に該当有無を判定し、これら所得が能動的な活動に由来するかどうかという実質判断は行わない(コメンタリ第10章パラ87)。また、例えば配当、利子など日本のCFC税制における部分合算所得の範囲とは重なる部分もあれば、日本のCFC税制には存在する異常所得がGloBEにはないなど、重ならない部分もある。
企業サイドからは、簡素化の観点から、CFC税制における部分合算の範囲をGloBEの定義に統一してはどうかとの声も聞かれるが、コメンタリでは、「包摂的枠組がGloBEルールにおいて合意した受動的所得の定義は特別目的の定義であり、CFC税制の下で課税に服すべき適切な所得の範囲について見解を示したものと解釈されるべきではない」と予防線を張る解説がなされている(コメンタリ第10章パラ87)。CFC税制の設計は各国による裁量が認められており、包摂的枠組による合意に拘束されるものではないという課税当局の意思が透けて見える。
企業からは、「子会社が日本のCFC税制上、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当する結果、部分合算ではなく会社単位の全部合算となる場合には、そもそも当該子会社については現状、部分対象所得を切り分けて把握していない。GloBEルールにおいてはどのように取り扱うのか」との疑問の声が聞かれるが、全部合算の場合にもGloBEルールでいう「受動的所得」を切り分けた上でプッシュダウン計算を行う必要がある方向。例えば全部合算所得100のうち30がGloBEでいう受動的所得、残りの70が受動的所得以外の所得(能動的な事業所得)だとすると、30についてはプッシュダウン制限が生じ、残りの70についてはプッシュダウン制限が生じない。全部合算所得100がすべて受動的所得から成る場合には、全額がプッシュダウン制限の対象となる。このような作業は企業にとって追加的な負担となろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















