解説記事2022年05月23日 税務マエストロ 令和4年4月19日最高裁判決後の総則6項適用について(2022年5月23日号・№931)
税務マエストロ
令和4年4月19日最高裁判決後の総則6項適用について
#273
税理士 梶野研二
略歴
国税庁 課税部 資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所 裁判所調査官、国税不服審判所本部 国税審判官、東京国税局 課税第一部資産評価官、玉川税務署長などを経て、平成25年6月 税理士登録。現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。○主な著書 「ケース別 相続土地の評価減」、「非公開株式評価実務マニュアル」(新日本法規)、「判例・裁決にみる非公開株式評価の実務」(共著)(新日本法規)、「株式・公社債評価の実務」、「土地評価の実務」(共著)(大蔵財務協会)
今回のテーマ
財産評価基本通達第1章総則第6項(脚注1)の適用を巡っては、これまで、その適用基準が不明瞭である、あるいは特定の納税者に対して恰も狙い撃ちをするかのような課税処分を行うことは平等原則に反するなどと言われてきました。令和4年4月19日最高裁判所第三小法廷判決(以下「令和4年最高裁判決」といいます。)は、同項を適用した課税処分の取消しを求める納税者の主張を排斥しました。この判決において、最高裁判所は、総則6項の適用と租税法における平等原則との関係についての考え方を述べており、今後の評価実務に与える影響は大きいと思われます。
そこで、本稿では、令和4年最高裁判決の考え方を整理し、総則6項を巡る実務への影響について説明することとします。
マエストロの解説
第1 総則6項とは
相続税法第22条は、「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」と定めており、相続税及び贈与税の課税上、財産の評価は時価によることとし、その時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解されています。
しかしながら、財産の客観的交換価値は必ずしも一義的に確定されるものではなく、これを個別に評価すると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等によって異なった評価額が生ずることが避けられず、また、それでは課税当局の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることから、課税実務においては、評価通達によって各種財産の評価方法に共通する原則や各種財産の評価単位ごとの評価方法が定められており、原則としてこの評価通達に定められた画一的な評価方法によって財産の評価が行われています。このような取扱いは、当該財産の評価に適用される評価通達の定めが適正な時価を算定する方法として合理性を有するものである限り、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減といった観点からみて相当であり、また、租税法の基本原則の一つである租税平等主義に照らせば、特定の納税者あるいは特定の財産についてのみ、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によってその価額を評価することは、原則として許されないものと考えられています。
しかしながら、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないなど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者の全ての財産の価額の評価に用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような場合についてまで、評価通達の定めによって評価することは適当ではありません。そこで、評価通達は総則第6項に「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定め、他の合理的な方法によって評価することを認めています。
なお、総則6項は、評価通達の定めによって評価した価額(以下「通達評価額」といいます。)が相続税法第22条に定める本来の時価(本稿では、便宜的に「実勢価額」といいます。)を上回る場合においても適用され、この場合には、評価通達の定める評価方法ではなく、不動産鑑定評価による不動産鑑定評価額など他の合理的な方法により評価した価額を基に相続税の課税が行われますが、本稿では、令和4年最高裁判決を踏まえ、通達評価額が、実勢価額を著しく下回る場合に評価通達の定めによらずに評価した価額で相続税等の課税が行われるケースについて説明することとします。
第2 令和4年最高裁判決
令和4年最高裁判決の概要と同判決の意義は以下のとおりです。
1 事実関係
被相続人Aは、平成24年6月17日に94歳で死亡し、上告人ら共同相続人がAの財産を相続により取得しました。Aの相続財産中には、甲不動産及び乙不動産(甲不動産と乙不動産を併せて「本件各不動産」といいます。)が含まれていたところ、これらについては、Aの遺言に従って上告人らのうちの1名が取得しました。なお、当該上告人は、平成25年3月7日付けで、乙不動産を5億1,500万円で第三者に売却しました。
(1)本件各不動産の取得の経緯等は次のとおりです。
① Aは、平成21年1月30日付けでB信託銀行から6億3,000万円を借り入れた上、同日付けで甲不動産を代金8億3,700万円で購入した。
② Aは、平成21年12月21日付けで共同相続人らのうちの1名から4,700万円を借り入れ、同月25日付けでB信託銀行から3億7,800万円を借り入れた上、同日付けで乙不動産を代金5億5,000万円で購入した。
③ A及び上告人らは、上記①及び②の各不動産の購入及びその購入資金の借入れを、A及びAが経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、本件各不動産の購入及びそのための借入れが近い将来発生することが予想されるAからの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて企画して実行したものである。
(2)申告及び課税処分等は次のとおりです。
① 上告人らは、本件相続につき、評価通達の定める方法により、甲不動産の価額を合計2億4万1,474円、乙不動産の価額を合計1億3,366万4,767円と評価して、平成25年3月11日に相続税の期限内申告書を提出した。この申告書においては、課税価格の合計額は2,826万1,000円とされ、基礎控除額を控除した結果、相続税の総額は0円とされていた。
なお、上記(1)の①及び②の購入及び借入れがなかったとすれば、Aの相続開始に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を超えるものであった。
② 国税庁長官は、C国税局長からの上申を受け、平成28年3月10日付けで、同国税局長に対し、本件各不動産の価額につき、総則6項により、評価通達の定める方法によらずに他の合理的な方法によって評価することとの指示をした。

③ D税務署長は、上記指示に従い、平成28年4月27日付けで、上告人らに対し、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準により本件相続の開始時における本件各不動産の正常価格として算定した鑑定評価額に基づき、甲不動産の価額が7億5,400万円、乙不動産の価額が5億1,900万円であることを前提とする更正処分(相続税の課税価格の合計額を8億8,874万9,000円、相続税の総額を2億4,049万8,600円とするもの)及び過少申告加算税賦課決定処分を行った。
2 原審判決の概要
原審判決(脚注2)は、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないなど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情がある場合には、他の合理的な方法によって評価することが許されるものと解すべきであるとの一般論を述べたうえで、本件各不動産の通達評価額と不動産鑑定評価額の間に著しい開差があること、本件各不動産が相続財産に含まれることとなった経緯やその結果相続税が課されないこととなったこと等の事実関係の下では、評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められることから他の合理的な方法によって評価することが許されると判断し、不動産鑑定士による本件各不動産の鑑定評価額は本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるからこれを基礎とする更正処分は適法であるとの判決を下しました。
3 最高裁の判断
最高裁判所第三小法廷は、相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法によらず鑑定評価額に基づき評価した価額によって行った課税処分は、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものではなく適法であるとして、同処分の取消しを求める納税者の上告を棄却しました。
(1)相続等により取得した財産の価額
相続税法第22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとしているが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が通達評価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。そうであるところ、本件各更正処分に係る課税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各通達評価額を上回るからといって、相続税法第22条に違反するものということはできない。
(2)租税法における平等原則
他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ通達評価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
(3)本件への当てはめ
これを本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。もっとも、本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2,826万1,000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。
4 令和4年最高裁判決の意義
(1)これまでの総則6項の考え方
総則6項の適用については、評価通達を画一的に適用することが合理的でない特別の事情がある場合には、課税当局は、評価通達によらない評価をすることができるとの判例の考え方(脚注3)を前提に、通達評価額が不動産鑑定評価等による評価額など客観的交換価値と認められる価額を大幅に下回るときには、この特別の事情があるものとして、同項が適用できるとする考え方が一つの理解でした(脚注4)。もちろん課税時期直前の多額の借入れや銀行融資を受ける際の稟議書に節税効果が謳われていることなども特別の事情の認定をする際に考慮されますが、これらの点は、いわば特別の事情を認定する際の補強材料に過ぎないと整理することができます(脚注5)。相続税法第22条の法令解釈通達である評価通達の中の一規定に過ぎない総則6項は、評価対象財産について相続税法第22条に定める時価を適正に評価するために設けられたものであり、評価対象財産の取得の経緯や目的は時価の評価とは別の問題として扱うべきであるとの考え方によるものです(脚注6 7)。
一方、総則6項の適用が認められるための「評価通達を画一的に適用することが合理的でない特別の事情」については、通達評価額と実勢価額との間の著しい開差に加え、納税者による租税回避行為など何らかの行為が必要だとする考え方もありました(脚注8 9)。
(2)令和4年最高裁判決の考え方
イ 令和4年最高裁判決は、相続税法第22条の解釈としての時価の問題と、租税法全体を支配する基本原則の一つである租税平等主義の問題は別次元の問題であることを示した点に意味があるといえます。
すなわち、令和4年最高裁判決は、まず、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、相続税法第22条に違反するものではなく、そのことは課税処分に係る財産の価額が通達評価額を上回るか否かによって左右されないと述べています。そのうえで、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ通達評価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、租税の一般原則である平等原則に違反して違法となるが、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を通達評価額を上回る価額によるものとすることは平等原則に違反するものではないと解されると判断しました。すなわち、令和4年最高裁判決は、①時価の判断(第1ステップ)と②平等原則違反を排斥するだけの合理的な事由の有無の認定(第2ステップ)の二段構えの判断が必要であるとしたものであり、これまで総則6項の適用要件として不明確だった租税回避行為等の納税者の行為の有無が、②の事由を認定するための事実関係の一つと整理したものと考えられます。
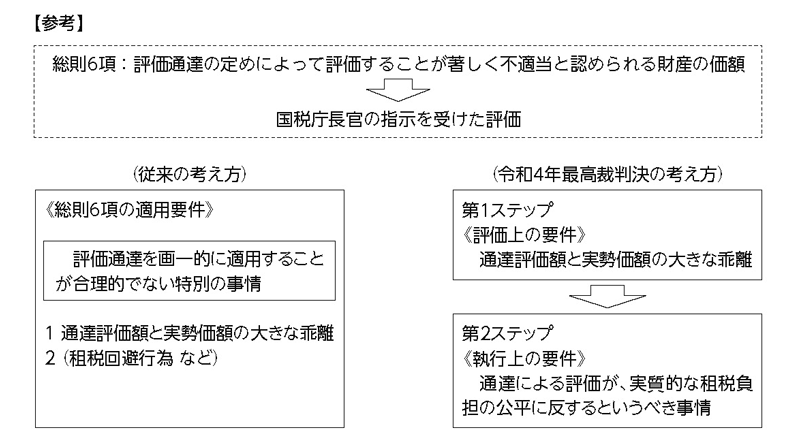
ロ 評価通達は相続税法第22条の法令解釈通達であり、「(相続税等の課税における財産の)価額は、……この通達の定めによって評価した価額による。」(評基通1(2))と規定しているものの、通達評価額が同条にいう時価から著しく乖離する結果となるときには、課税当局としては、通達の定めにかかわらず、同条に規定する時価により課税処分をしなければならないと考えられます。これは租税法の一般原則である租税法定主義から派生する合法性の原則(脚注10)から導かれるものであり、評価通達に総則6項の定めがあろうとなかろうと、課税当局としては、相続税法22条の時価による課税をしなければならないわけです。
しかしながら、合法性の原則が租税法における一般原則の一つということであれば、また平等原則も重要な租税法の一般原則の一つです。令和4年最高裁判決は、相反する合法性の原則の要請と平等原則の要請とのはざまに陥ったときには、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」の有無により、いずれの原則を優先させるかを判断すべきであるとしたものといえます。総則6項が、通達評価額とは異なる価額により課税を行う場合に、国税庁長官への上申を求め、その判断を仰ぐこととしているのは、時価評価の妥当性の審査に加え、まさにこの判断を慎重に行うためであるということができます(脚注11)。
(3)令和4年最高裁判決の射程
総則6項が適用される財産は、不動産に限定されるものではなく、これまで取引相場のない株式等についても同項が適用されてきました。令和4年最高裁判決の考え方は、不動産以外の財産についても当てはまると考えられます。
なお、総則6項の適用場面に類似する問題として、財産の種類が問題となることがあります。例えば、売買契約中の土地について売主に相続が開始した場合に、相続税の課税財産となるのは土地ではなく残代金請求権であると考えて、債権の金額により相続税の課税価格を計算することとなります(脚注12)。また、相続税の負担の軽減を図る目的のみで一時的に取得し、その目的を達成すると出資額に見合う金銭を回収することを予定して発行される株式について、課税庁側は、法律上の形式は別として、その経済的実質は預け金と同様であり、およそ評価通達が配当還元方式によって評価することを予定している株式とはかけ離れた性質を有する財産であることは明らかであるところ、評価通達は、このような性質を有すると認められる財産の具体的な評価方法を定めていないとして、総則5項に基づき、本件株式と経済的性質の類似していると認められる同通達204《貸付金債権の評価》の定めに準じて、本件株式の価額を評価することとなると主張しています(脚注13)。これらのケースは、総則6項からのアプローチと総則5項(脚注14)からのアプローチのいずれもが考えられるところです。総則5項の適用については令和4年最高裁判決の直接の射程ではありませんが、同項が適用されるこれらの事例においてはその適用が納税者に与える影響は総則6項の適用場面と類似しており、この場合についても租税法共通の原則である平等原則が適用されると考えられます。
第3 令和4年最高裁判決を受けた今後の実務
1 総則6項適用基準についての展望
令和4年最高裁判決に先立って最高裁判所で弁論が開かれたことから、総則6項の適用に当たっての何らかの基準が示されるのではないかとの憶測もありましたが、結局、大方の期待に反して具体的な基準が示されることはありませんでした。そのため、依然として、総則6項の適用基準があいまいであるとの指摘が続くと思われますが、仮に、今後、税務当局が何らかの基準を示すことはあるとすれば、どのような基準が考えられるのでしょうか。
(1)課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等の評価方法の改正
例えば、課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等については、通常の取引価額に相当する金額により評価することとする通達改正が考えられます。評価通達185かっこ書きにおいて、取引相場のない株式を純資産価額方式で評価をする場合に、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地等及び家屋等の価額は課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価をすることとされています。この取扱いは、昭和63年12月の租税特別措置法改正により設けられた「相続開始前3年以内に取得した土地等又は建物等について、相続税の課税価格に算入すべき金額は、その土地等又は建物等の取得価額を基にする」との特例措置(平成8年改正前の租税特別措置法第69条の4)と同時期に定められたものであるところ(脚注15)、同特例措置は平成8年の税制改正で廃止されたことから(脚注16)、評価通達185かっこ書きも削除すべきではないかとの意見がありましたが、国税庁では、この取扱いを廃止しませんでした。この扱いを廃止すれば、相続開始直前に被相続人が不動産を購入することにより相続税の課税価格を圧縮するのと同様の手法により取引相場のない株式の評価額を意図的に引き下げる事例が横行することとなるのではないかとの懸念をぬぐいきれなかったためだと思われます。廃止された租税特別措置法の定めが「取得価額」による課税だったのに対し、評価通達185かっこ書きは「通常の取引価額」を基にした評価であって、両者は全く異なったものですが、制定の経緯からいまだに廃止の要望は強いものと思われます(脚注17)。こうした状況下で、課税当局が、被相続人が相続開始前3年以内に取得した土地等及び家屋等について通常の取引価額に相当する金額により評価することとする扱いを制定することは、かなり難しいのではないかと思われます。
(2)マンションの評価の創設
平成27年10月27日の政府税制調査会の場においてタワーマンション等を利用した節税策について委員からの指摘があり、国税庁は、「タワーマンションを利用した節税策について、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、従来から財産評価基本通達6項を活用してきたところであるが、今後も、適正な課税の観点から同項の運用を行いたい」との対応方針を明らかにしました(脚注18)。評価通達においては、建物(自用家屋の場合)の評価は、原則として固定資産税評価額の1.0倍で評価することとしているところであり、タワーマンションに係る固定資産税評価額についての見直しが図られたことから、相続税における評価についても若干の適正化が図られることとなりましたが、根本的な見直しは見送られました。令和4年最高裁判決に係る事例も、マンションとその敷地の評価が問題となっていました(脚注19)。一般に、マンションの価額は、そのマンションの敷地の持分の価値やその建築価額などにも大きく影響されますが、そればかりではなく、交通利便性、建物の床面積、築年数、内装や設備、眺望、セキュリティ、管理業者の提供するサービスの内容、マンション販売業者のブランドなどにも大きく影響されると考えられます。マンションの評価方法については抜本的な改正が必要だと考えられますが、技術的な困難さを伴うことから、近いうちに新たな評価方法が示される可能性は低いと思われます。
(3)開差率
通達評価額と実勢価額との間の開差率(実勢価額/通達評価額)に着目し、この開差率が一定の率(例えば、3.0倍)を超えた場合に、通達評価額ではなく実勢価額をもって評価するとする扱いも考えられます(ただし、開差が一定の金額以下のものは除外すべきでしょう。)。しかしながら、実勢価額の確認には、納税者及び課税当局の双方にとって多大なコストがかかり、また、納税者が算定した実勢価額と課税当局が算定した実勢価額とが異なることとなることは想像に難くありません(脚注20)。さらに数値基準を設けられた場合、その数値をクリアさえすれば通達評価額が認められるとなれば、そこに新たな不公平が生じることになりかねません。新たに設けられた基準をクリアしたとしても、実質的な租税負担の公平に反すると認められるケースが出現すれば、当局としては総則6項を適用せざるを得ないと考えられます。このような点から、一定の開差率を総則6項の適用基準とすることにより同項の適用基準の明確化を図ることは難しいと考えられます。
2 当面の不動産に係る総則6項適用対策
総則6項適用の一般的な基準を示すべきであるとの実務家サイドの要望は強いものの、上記1のとおり近いうちに何らかの基準が示される可能性は低いと思われます。したがって、当面は個別の事案ごとに、令和4年最高裁判決の考え方に沿って、①通達による評価額が時価を著しく下回るかどうか(第1ステップ)、②評価通達によらない評価が平等原則に反することにならないかどうか(第2ステップ)の判断がされることとなると考えられます。すなわち、今後、不動産の評価額について総則6項の適否が問題となるケースにおいては、①対象財産の時価の評価(通達評価額の妥当性、他の合理的な評価方法の有無、他の評価方法により評価した価額の妥当性など)についての検討が行われ、その結果、相続税法22条にいう時価の評価の観点から、評価通達の定めによらずに評価することが相当であるとの結論に達したならば、次のステップとして、②通達の定めによらずに対象財産の評価を行い、相続税等の課税を行うことが平等原則に反しないこと、すなわち評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき「事情」の有無についての検討という2段構えでの検討が必要になると思われます。
(1)通達による評価額と時価の乖離
まず、納税者としては、相続開始前において保有する不動産(特に相続開始直前に取得したもの)の実勢価額及び通達評価額並びにそれらの開差(開差率及び開差額)について正しく認識することが必要となります。相続開始前に購入した不動産の取得価額が、例えば、地価事情の変動や買進みがあったことなどから実勢価額に比して高額の契約に至ったというような事情がある場合には、その点を明らかにしておくことは有用でしょう。
また、税務調査時に、課税当局が不動産鑑定を行うことも考えられますが、その鑑定評価額が適正なものであるかどうかの検証が必要となります。
(2)実質的な租税負担の公平に反するというべき「事情」
評価通達に定める画一的な評価を行わないことに合理的な理由がない限り総則6項の適用は平等原則に違反することとなりますから、総則6項を適用するためには、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき「事情」が必要になります。
令和4年最高裁判決の事例は、「租税負担の軽減を意図してこれを行ったもの」であり、この事例において評価通達の定めるところによる画一的な評価を行うことは同様の不動産の購入やその購入源資である借入れのような行為をせず、又はすることができない他の納税者と上告人らとの間に看過しがたい不均衡が生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するものであると認められることから、このことは評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情に当たるというものでした。
この「事情」の有無についての判断の際の着目点として次の点が挙げられます。
① 多額の借入れによる不動産の購入
まずは、多額の借入金により不動産を取得するケースです。金融機関の主導で行われることが多いと思われますが、通常では融資を受けられないような多額の借入れを、形式的な事業計画のみで、高齢の被相続人に、短期間の審査で貸し付けるているケースが特に問題となります。令和4年最高裁判決は、「本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることができない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ」と述べているところですが、誰でもが同様の多額の借入れをすることができるわけではなく、このような借入れをすることができるのは、一部の者に限られており、この点が「事情」の有無の判断に大きく影響しているといえます。
なお、被相続人の手持ちの現預金を元手に不動産を購入する場合でも、相続税の圧縮という点では同じですが、借入金により不動産を購入した場合には、借入金額とその不動産の評価額との差額が生じることにより、他の財産の価額を減少させることとなり、その差額が著しく極端な場合には相続税が課税されないような結果となることもあり得ますが、手持ちの現預金により不動産を購入する場合には、少なくとも、不動産の評価額相当額は相続税の課税対象金額として維持されますので、借入金で不動産を購入する場合とは異なるといえます。したがって、同じ不動産の購入であっても、借入金で不動産を購入するケースの方が、より「事情」の認定を受けやすいと考えられます。
② 課税時期前(相続開始直前)の不動産購入
次に、総則6項の適用が問題となるケースとしては、相続開始直前に不動産を購入しているケースです。それも偶々不動産を購入したところその直後に予期せぬ相続開始を迎えたというようなケースではなく、相続開始が遠くないと思われるほど被相続人が高齢であったり、不治の病で余命を宣告された直後に、不動産の購入を画策するケースです(脚注21)。
③ 被相続人が高齢である場合
不動産を購入した時点で、高齢であって、購入した不動産を利用することがおよそ想定できない、又はその利用が困難なケースも注意が必要です。令和4年最高裁判決に係る事件では、借入金の返済期間が被相続人の余命年数を大幅に上回っていることが指摘されていますが、借入金の返済を含む事業全体が相続人等に引き継がれていくことを前提としているならば借入金の返済期間それ自体は重要な判断要素ではなく、むしろ高齢化により判断能力が劣っている状態で相続人等が主導して不要不急の不動産を取得したと認められるケースが指摘を受けやすいと考えられます。
④ 事業計画等の欠如
購入した不動産について、具体的な利用計画がないケース、借入金の元利返済額及びその不動産の維持管理費を勘案すると保有することによって採算がとれず、相続開始後、速やかに売却することを想定していると考えられるケース、相続税の圧縮以外に取得・保有する理由がないケースは、総則6項の適用されるリスクが高いといえます。逆にいえば、利用目的、採算性、実際の維持管理の方法(誰が、どのように行うか、費用の負担に耐えられるかなど)、購入者に万が一の事態が生じた場合の対応などしっかりした計画を策定したうえで取得するのであれば、総則6項適用のリスクは小さくなるといえるでしょう。
⑤ 相続開始後の売却
特に、相続開始直前に購入した不動産を相続税の申告書の提出期限内又は相続税の申告書の提出直後に売却した場合には、総則6項適用のリスクが高いといえるでしょう。相続開始後に売却した場合でも、被相続人が従来より保有している不動産であったり、売却の理由が相続税の納税資金捻出のためなどであれば「事情」とはなりにくいでしょう。
なお、あらかじめ相続開始後に売却することを企図して購入した不動産を相続開始後に売却した場合、その不動産は、評価通達第2章(土地及び土地の上に存する権利)及び第3章(家屋及び家屋の上に存する権利)に定める財産ではなく、棚卸資産に準ずる資産であるとして、評価通達4−2に準じ同133を準用して課税時期における販売価額を基に課税価格を計算して課税処分が行われることもあり得ると考えられます(脚注22)。
⑥ 租税回避行為
上記①から⑤に該当する場合で、不動産の取得・保有により相続税の大幅な圧縮が図られているケースについては、総則6項が適用されるリスクが非常に高いといえます。金融機関や関与税理士等のアドバイスにより不動産を取得している場合において、被相続人あるいは相続人等関係者の手元資料や金融機関等の社内文書に相続税の負担軽減の目的であることが明記されているときには、課税当局の「事情」の認定の有力な根拠となり得ます。ただし、総則6項の適用は、不動産の購入・保有という行為が、租税回避又は相続税等の負担の軽減を目的として行われたものに限られるわけではないと考えられます。つまり、租税回避又は相続税等の負担の軽減目的は、総則6項適用における重要な要素の一つではありますが、必要条件でも十分条件でもないといえますので、仮に、相続開始直前の不動産の購入が租税回避目的であることが明らかではないとしても、そのことのみをもって総則6項適用のリスクがなくなるとはいえないでしょう。
⑦ 著しい開差
令和4年最高裁判決は、「本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。」と述べています。同判決からは、一般的には、通達評価額と実勢価額との間に大きな開差があるだけでは、「事情」とはならないといえるでしょう。しかしながら、同判決で述べているのはあくまでも「本件不動産」の評価額についての判断にすぎません。その開差が極めて大きく、平等原則の要請と合法性の原則の要請との比較衡量の結果、その著しい開差それ自体が「事情」に当たるとして総則6項が適用される余地もあると思われれます。
上記に掲げた点は、相互に関連しており、そのうちのいくつかに該当すれば、総則6項が適用されるリスクが高くなるといえます。また、該当項目が一つであってもその程度が著しい場合には、総則6項が適用されるリスクがあるといえます。納税者としては、上記に掲げた点のうちの一つでも該当すれば、総則6項適用のリスクが高いことを十分に認識する必要があります。
相続開始前に不動産を取得することにより相続税の節税を図ること自体は、何ら咎められることではないと考えられますが、それが社会通念を踏み越えた結果、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるとされる場合に総則6項の適用が問題になるわけです。
相続税の課税対象と見込まれる者は、生前から、万が一の時にはどのくらいの税負担が生じることとなるのか、あらかじめ試算をし、それを踏まえて、無理のない形で不動産取得などの節税策を検討していくことが重要です。中長期的な観点での不動産投資を計画し、不動産の購入・保有に税負担の軽減以外の合理的な目的があることを明確に主張できることが総則6項の適用を回避する有効な対策であるといえます。
おわりに
令和4年最高裁判決により、「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」が存する場合には、評価通達の定めによらない評価方法により課税処分を行ったとしても平等原則に違反することはないとされたことから、課税当局にとって、当該事情の存在の主張立証が必要になるとの点では総則6項適用のハードルが高くなったといえますが、一方で、その主張・立証が可能と判断されれば、同項の適用に踏み切ることとなると考えられることから、今後、総則6項が適用されるケースは増加することはあっても減少することはないように思われます。
これまでみてきたように近いうちに納税者が期待するような総則6項発動の客観的な基準が示されることは困難だと思われます。納税者としては、上記「当面の不動産に係る総則6項適用対策」に掲げたポイントに十分留意する必要があります。
最後に、総則6項の運用に関する事務運営指針(脚注23)に従い、一元的に国税庁において、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」の有無について適正な判断を行うことを期待するとともに、納税者の予測可能性を高めるために、総則6項を適用することとした事案及び総則6項を適用しないとした事案について、①評価通達の定めにより評価した価額と当局が認定した価額及び②実質的な租税負担の公平に反するというべき「事情」の有無についての判断の結果について、個別の納税者の情報を伏したうえで、公表されることが望まれるところです(脚注24 25)。
脚注
1 昭和39年4月25日直資56ほか「相続税財産評価に関する基本通達」として制定され、地価税法の制定を機に、平成3年12月18日に「財産評価基本通達」と改題されたが、総則6項については、通達制定当時から改正はされていない。本稿では、同通達を「評価通達」といい、同通達第1章総則第6項を「総則6項」という。
2 令和元年8月27日東京地裁判決(税務訴訟資料269号13304順号)、令和2年6月24日東京高裁判決(金融・商事判例1600号36頁)。
3 平成4年3月11日東京地裁判決(判例時報1416号73頁)、平成9年6月23日大津地裁判決(訟務月報44巻9号1678頁)、平成16年3月2日東京地裁判決(訟務月報51巻10号2647頁)など。
4 例えば、「本件通達に定められた評価方法を画一的に適用することによって、明らかに当該財産の客観的交換価値とは乖離した結果を導くこととなり、そのため、実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び本件通達の趣旨に反することとなるなど、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方式によることが許されると解すべきである。」(平成17年11月10日東京地裁判決(税務訴訟資料10199順号))。
5 令和4年最高裁判決に係る事件の第一審判決(令和元年8月27日東京地裁判決)では、「本件通達評価額が本件鑑定評価額と大きくかい離しており、これによって課税額に大きな差が生じていること自体が、……特別の事情の存在をうかがわせるものであるということができる。」と述べ、「そもそも処分行政庁が本件各更正処分を行ったのは、本件不動産につき評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるという理由によるものであって、本件被相続人及び原告らに相続税対策の意図があることを理由として不利益な処分を課したものではない。」としている。
6 野村資産承継研究所品川芳宣理事長は、「(総則6項の)実体的要件たる「著しく不適当」とは、評価通達が相続税法22条に規定する「時価」を解釈・適用するために存在しているのであるから、当該財産の通達上の評価額と客観的交換価値との開差が客観的にみて著しく不適当と認められる場合、すなわち、財産の客観的価値に関する事項に限定すべきであって、租税回避を企画したか否かというような主観的要素は本来判断の要素とすべきではないと考えられる。」と述べている(季刊資産承継2018年春号No.3「第3回 財産(資産)評価の実務研究」203頁)。
7 税務大学校研究部加藤浩教授は、「個々の評価対象財産に存在する諸々の事情(事実)に関して、これを考慮した上での当該財産の客観的交換価値を算定し、これと当該財産を評価通達に当てはめそのまま評価した場合の評価額とを比較したところ、両者に乖離が生じると認められる場合に、評価通達によらない「特別の事情」があると認められ、その結果、評価通達以外の合理的な評価方法により評価することになるものと考えることができる。」と述べている(税務大学校論叢第94号「相続税法64条と財産評価基本通達6項との関係について」平成30年6月167頁)。
8 課税当局の研修資料によると、「特別の事情」の有無の判断に当たっては、次の点などに着目しつつ、様々な事実関係を総合考慮することに留意するとし、①評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること、②評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること、③評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること、④上記③の著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していることを掲げている(東京国税局課税第一部資産課税課・資産評価官 平成28年7月作成「資産税審理研修資料」(TAINS 評価事例708302))。
9 渡邉定義税理士は、総則6項の適用における予測可能性を論ずる脈絡で、「「適用3要件」である①評基通による評価の合理性の欠如(著しい乖離)②他の合理的な評価方法の存在③乖離が生じるに至る納税者の行為−−の存在と読み取ることができる。中でも、その乖離が生じるに至る納税者の行為の存在は、評基通6項適用の重要な点だと考えられる。」と述べている(2022年11月15日付「税理士会」1406号11頁「論壇」)。
10 合法性の原則とは、「課税要件が充足されている限り、租税行政庁には租税の減免の自由はなく、また租税を徴収しない自由もなく、法律で定められたとおりの税額を徴収しなければならない」との原則をいう(金子宏著「租税法第24版」86頁)。
11 平成14年6月28日課評1−13ほか「「財産評価基本通達第5項((評価方法の定めのない財産の評価))及び第6項((この通達の定めにより難い場合の評価))の運用について」の一部改正について(事務運営指針)」(TAINS:H140628課評1−13)には、この場合の事務処理要領が定められている。
12 昭和61年12月5日最高裁第二小法廷判決(訟務月報33巻8号2149頁)、平成11年10月29日名古屋地裁判決(税務訴訟資料245号151頁)。
13 平成9年7月4日裁決(裁決事例集No.54 451頁)。
14 財産評価基本通達第1章総則第5項(本稿では「総則5項」という。)は、「この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する。」と定めている。
15 平成2年8月直評12ほかによる改正。
16 平成7年10月17日大阪地裁判決(行政事件裁判例集46巻10・11号942頁)は、地価の下落が急激かつ著しい状況下において、租税特別措置法第69条の4の規定を適用することにより、相続により取得した不動産の価値以上のものを相続税として負担しなければならなくなったケースについて、このような事案についてまで無制限に同条を適用することは憲法違反(財産権の侵害)の疑いが極めて強いとして、同条を適用した課税を取り消した。この判決が契機となって平成8年に同条は廃止された。
17 令和3年6月23日「令和4年度税制改正に関する建議書」(日本税理士会連合会)18頁、令和3年6月「令和4年度税制改正意見書」(日本公認会計士協会)35頁など。
18 平成27年11月2日付週刊税のしるべ。
19 令和4年最高裁判決に係る事件と同時期に総則6項の適用の是非を争点として訴訟提起された事件も相続開始前のマンションの取得に関するものである(令和2年11月12日東京地裁判決、令和3年4月27日東京高裁判決)。
20 平成9年9月30日東京地裁判決(訟務月報47巻6号1636頁)、平成18年11月17日大阪地裁判決(税務訴訟資料256号10575順号)など。
21 相続開始前に貸付用不動産を購入することにより金融資産を不動産に変換し、金融資産で保有する場合に比し、相続税評価額が圧縮され、かつ、小規模宅地等の特例も適用できるという節税策が雑誌などで盛んに紹介されている等(平成30年版改正税法のすべて(大蔵財務協会)641頁)の実態を踏まえ、平成30年税制改正において、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、原則として貸付事業用宅地等に該当しないこととされたところである(措法69の4③四)。
22 評価通達4−2は「土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、……、第6章((動産))第2節((たな卸商品等))の定めに準じて評価する。」と定めている。このような課税は、総則6項というよりは、総則5項((評価方法の定めのない財産の評価))を適用するものともいえる。
23 前掲平成14年6月28日課評1−13ほか事務運営指針。
24 納税者は、公表裁決や訴訟となった事例以外の事例を参照することはできないが、争訟に至らなかった事例も存すると思われる。
25 前掲日本公認会計士協会の税制改正意見書では、総則6項の適用に係る納税者の予測可能性確保のため、同項にいう「著しく不適当」な場合の例を明確に示すことや、更に詳細な規定を財産評価基本通達に設けることといった施策を講じることを求めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















