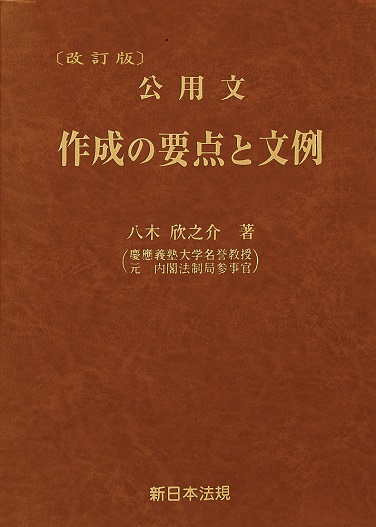解説記事2022年05月23日 未公開判決事例紹介 タックスヘイブン税制巡りメガバンクが逆転勝訴(2022年5月23日号・№931)
未公開判決事例紹介
タックスヘイブン税制巡りメガバンクが逆転勝訴
子SPCの純利益から配当等を受け得る支配力なし
本誌923号40頁で紹介した法人税更正処分等取消請求控訴事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する(東京地裁の判決は本誌922号25頁参照)。
○メガバンクがケイマンに置いたSPC(特別目的会社)に係るタックス・ヘイブン対策税制(CFC税制)の適用の可否が争われた事件。具体的には、メガバンクの益金の額に算入されるべき「課税対象金額」を算定するための「請求権勘案保有株式等割合」が争われたもの。一審で納税者側が敗訴していたが、東京高裁は令和4年3月10日、メガバンクが各子SPCの当期純利益から剰余金の配当等を受け得る支配力は存在せずCFC税制を適用すべきでないとして、原判決を取り消した(令和3年(行コ)第96号)。
主 文
1 原判決を取り消す。
2 処分行政庁が控訴人に対し平成29年11月7日付けでした平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税に係る更正処分(ただし、令和元年7月29日付け減額更正による一部減額後のもの)のうち所得の金額4935億1557万9742円を超える部分及び納付すべき法人税額628億8628万7000円を超える部分並びに上記更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、同日付け変更決定による一部減額後のもの)をいずれも取り消す。
3 処分行政庁が控訴人に対し平成29年11月7日付けでした平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る更正処分(ただし、令和元年7月29日付け減額更正による一部減額後のもの)のうち課税標準法人税額1177億8873万3000円を超える部分及び納付すべき地方法人税額38億2783万9600円を超える部分並びに上記更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、同日付け変更決定による一部減額後のもの)をいずれも取り消す。
4 本件訴えのうち処分行政庁が控訴人に対し令和3年4月26日付けでした法人税及び地方法人税に係る各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消しを求める部分を却下する。
5 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 主文1項ないし3項と同旨(2項及び3項については、当審において、原判決「事実及び理由」第1の1及び2の請求から上記のとおりに請求を拡張した。)
2 処分行政庁が控訴人に対し令和3年4月26日付けでした控訴人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す(当審における追加請求)。
3 処分行政庁が控訴人に対し令和3年4月26日付けでした控訴人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す(当審における追加請求)。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件事案の要旨は、原判決3頁22行目の「本件各処分」を「本件各更正処分」と改め、同23行目末尾に行を改めて以下のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
「原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。控訴人は、上記申告額を超えない部分の取消しを求めて令和3年1月27日付けで処分行政庁に対し、各更正の請求(以下「本件各更正の請求」という。)を行ったが、処分行政庁から本件各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)を受けたため、前記「第1 控訴の趣旨」のとおり、当審において、本件各通知処分の取消しを求める訴えを追加し、また、本件各更正処分の取消請求を拡張した。」
2 関係法令の定め、前提事実、争点及び当事者の主張の要旨
(1)関係法令の定め、前提事実、争点及び当事者の主張の要旨は、以下のとおり補正し、後記(2)に控訴人の当審における追加請求及び拡張請求に係る主張を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の2ないし4に記載のとおりであるから、これを引用する。
ア 4頁2行目の「第1項は、」の次に「同項各号に掲げる」を加える。
イ 5頁4行目の「よるものと」の次に、「され、内国法人が同法66条の6第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものと」を加える。
ウ 6頁15行目の「適用対象留保金額(」の次に「その未処分所得の金額から留保したものとして所定の調整を加えた金額。」を加え、同16行目の「における」を「において、計算方法が変更された上で定められた」と、同17行目の「という。」を「ということがある。ただし、単なる名称の変更ではなく、計算方法が変更されているため、後記「第3 当裁判所の判断」においては、両者を区別して記載する。」と、同24行目の「における」を「において、計算方法が変更された上で定められた」と、同25行目の「という。」を「ということがある。ただし、単なる名称の変更ではなく、計算方法が変更されているため、後記「第3 当裁判所の判断」においては、両者を区別して記載する。」とそれぞれ改める。
エ 9頁20行目の「保有」から同22行目の「本件各子SPCは、」までを「保有しており、本件各子SPCは、」と改め、同25行目の「関係法令(1)」の次に「ア、」を加える。
オ 13頁10行目末尾に行を改めて以下のとおり加える。
「上記の持株SPCに対する□□□□(SPC②)優先出資証券に係る配当可能金額152億9600万円は、期末時点における確定未払の配当額76億4800万円のみならず、期中において配当実施済みの76億4800万円をも合算した額(措置法施行令39条の16第2項1号の「その総額」もこれを前提として算定)であり、事業年度終了の時に請求権の内容等が異なる株式等を発行している場合に該当するとしてされた上記算定方法が処分行政庁によって問題とされたことはない(控訴人令和3年9月3日付け求釈明事項に対する回答書11頁、被控訴人の当審準備書面(1)11頁)。」
カ 14頁2行目末尾に行を改めて以下のとおり加える。
「上記の持株SPCに対する△△△△(SPC①)優先出資証券に係る配当可能金額16億7300万円は、期末時点における確定未払の配当額8億3650万円のみならず、期中において配当実施済みの8億3650万円をも合算した額(措置法施行令39条の16第2項1号の「その総額」もこれを前提として算定)であり、事業年度終了の時に請求権の内容等が異なる株式等を発行している場合に該当するとしてされた上記算定方法が処分行政庁によって問題とされたことはない(控訴人令和3年9月3日付け求釈明事項に対する回答書12頁、被控訴人の当審準備書面(1)11頁)。」
キ 17頁15行目末尾に行を改めて以下のとおり加える。
「キ 控訴人は、原審段階では、本件各更正処分のうち、本件修正申告における申告額を超える部分の取消しを求めていたところ、上記申告額を超えない部分の取消しを求めるため、令和3年1月27日付けで処分行政庁に対し、本件各子SPCに係る課税対象金額の益金算入額が0円であるという本件訴訟における控訴人の主張と同様の理由により、当審における拡張後の本件各更正処分の取消請求と同内容の更正の請求(本件各更正の請求)を行った。これに対して、処分行政庁は、控訴人に対し、同年4月26日付けで本件訴訟における被控訴人の主張と同様の理由により、上記更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)を行った。控訴人は、同年5月31日付けで国税不服審判所長に対し、本件各通知処分の取消しを求める審査請求を行った。(以上につき、甲19ないし22)
控訴人は、当審において、本件各通知処分の取消しを求める訴えを追加し(同年9月10日付け訴えの変更申立書(5))、また、本件各更正処分の取消請求を拡張した(同年11月2日付け訴えの変更申立書(6)。顕著な事実)。」
ク 17頁23行目の別紙4についての補正
(ア)43頁17行目末尾に行を改めて以下のとおり加える。
「平成17年税制改正は、期末に配当されずに内部留保された利益に対して期末に請求権を有する株主について、適切に課税を行うためにされた改正であるから、特定外国子会社等が期末に請求権の内容が異なる株式等を発行していない場合には、内国法人は、期末における持株割合という支配力に応じて課税を受けることが相当であり、控訴人の上記主張は理由がない。」
(イ)47頁7行目末尾に行を改めて以下のとおり加える。
「そして、同号括弧書の「当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権に基づき受けることができる……剰余金の配当等……の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額」における「剰余金の配当等」について、当該事業年度における適用対象金額と合理的に関連性のある剰余金の配当等によるべきであり、本件においては、当該事業年度中に具体的に配当請求権の確定した(実際に支払われた)剰余金の配当等の金額によるべきである。すなわち、課税対象金額の「計算の適正化」の観点から、「内国法人が特定外国子会社等から実際に受領できる配当等の金額に相当する金額」(甲9・302頁)をベースに課税対象金額を計算する以上、当該内国法人が実際に受領することができなかった期中の配当も踏まえて請求権勘案保有株式等の計算を行うべきである。また、そもそも「剰余金の配当等……の額」は、ストック(事業年度終了の時における残高)ではなく、フロー(ある事業年度に生じた金額)の概念であるから、事業年度終了の時という一時点で捉えるべきものではなく、一定期間で把握されるべきものである。さらに、タックス・へイブン対策税制は、当該各事業年度の課税対象金額の合算を問題とするものであるから、少なくとも課税対象金額(適用対象金額)の基礎となった当期の利益(又はそれが留保された剰余金)から配当が行われているという関連性が必要であるといえる。
したがって、本件資金調達スキームのように、本件各子SPC事業年度において、本件各子SPCが獲得した当期の利益(=適用対象金額)がその事業年度中に全てその優先出資者である本件持株SPCに配当されている場合、請求権勘案保有株式等は、当該事業年度中に具体的な請求権の確定した利益の配当に基づき算定すべきである。
これを本件についてみると、本件各子SPC事業年度中の平成27年6月30日に本件持株SPCの優先出資証券の償還が行われているから、同事業年度中において、「当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」に該当するといえる。同事業年度中に具体的な請求権が確定し、実施された配当は全て優先出資者である本件持株SPCに対して支払われ、控訴人に対して支払われていない。したがって、同事業年度終了の時における本件各子SPCの発行済株式等のうち控訴人の請求権勘案保有株式等の占める割合(本件保有株式等割合)は0%となり、課税対象金額は0円と算出される。」
(2)控訴人の当審における追加請求(本件各通知処分の取消請求)及び拡張請求(本件各更正処分の取消しの拡張請求)について
ア 控訴人
(ア)追加及び拡張前の請求と争点が同じであるため、請求の追加及び拡張前の主張(引用に係る原判決「事実及び理由」第2の4の「争点及び当事者の主張の要旨」(補正後のもの)における控訴人の主張)と同じである。
(イ)以上によれば、控訴人の本件事業年度の法人税に係る所得金額は、被控訴人が主張する5019億9836万9849円から本件各子SPCに係る課税対象金額の益金算入額84億8279万0107円を除外した4935億1557万9742円であり、これを前提とすると、納付すべき法人税額は、628億8628万7000円であり、控訴人の本件事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額は、1177億8873万3000円であり、納付すべき地方法人税額は、38億2783万9600円である。本件各更正処分のうち上記額を超える部分及び本件各通知処分はいずれも取り消されるべきである。
イ 被控訴人
(ア)本件各通知処分の取消請求について
本件各通知処分の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものであるから、却下されるべきである。増額更正処分である本件各更正処分の取消請求(拡張後のもの)において、本件更正の請求に係る税額等を超える部分の取消しを求めることが可能であるから、本件各通知処分の取消しを求める利益はない。
(イ)本件各更正処分の取消しの拡張請求について
追加及び拡張前の請求と争点が同じであるため、請求の追加及び拡張前の主張(引用に係る原判決「事実及び理由」第2の4の「争点及び当事者の主張の要旨」(補正後のもの)における被控訴人の主張)と同じである。
第3 当裁判所の判断
1 本件各通知処分の取消しの訴えについて
引用に係る原判決「事実及び理由」第2の3の「前提事実」(補正後のもの。以下「前提事実」という。)(5)の課税の経緯等を踏まえると、増額更正処分である本件各更正処分の取消請求(拡張後のもの)において、本件各更正の請求に係る税額等を超える部分の取消しを求めることが可能であるというべきである。そうすると、重ねて本件各通知処分の取消しを求める利益はなく、それらの取消しを求める訴えは不適法であるから、却下すべきである。
以下、その余の請求について判断する。
2 認定事実
(1)前提事実(1)エのとおり、本件各子SPCは、控訴人に係る特定外国子会社等に該当する。
(2)本件資金調達スキームの仕組み及び本件各子SPC事業年度における配当、本件優先出資証券の償還等の状況等
前提事実(1)ないし(3)、(4)イ及びウ並びに証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 本件優先出資証券は、いずれも平成20年12月29日に発行されたものであるが、当時、同年9月頃に生じたいわゆるリーマンショックによる全世界的な株価の下落を背景として、控訴人を含む大手邦銀において、自己資本が毀損し、銀行法上求められる自己資本比率を充足しないおそれが生じていた。このため、控訴人を含む大手邦銀において、平成20年の秋頃から平成21年3月期の年度末にかけて、自己資本の増強を目的として、本件資金調達スキームと同種の優先出資証券による資金調達が積極的に行われ、金融庁にも認められた手法として、金融界の実務に定着してきた(甲16)。
イ 本件資金調達スキームにおける資金の流れは、一定の条件の下で、控訴人が本件劣後ローンに基づいて本件各子SPCに利息を支払い、本件各子SPCが、受領した利息のおおむね全額を本件優先出資証券の配当として持株SPCに支払い、その後、持株SPCが、受領した配当の全額を持株SPC優先出資証券の配当として投資家に支払うというものであり、持株SPC、本件各子SPCのいずれのレベルにおいても、各SPCの運営に必要な最小限度の費用分を除いて、利益が留保される事態が生じない建付になっており、控訴人が保有する本件各子SPCの株式について配当が支払われることは、仕組み上想定されていなかった(控訴人は、資本を供給する側ではなく、調達する側であるため、資本供給の対価たる配当を受けることは想定されていない。)。
ウ 本件各子SPC事業年度の当期純利益の額(適用対象金額は同額である。)は、SPC②が76億4673万8142円、SPC①が8億3605万1965円であったが、期中の平成27年6月30日に本件優先出資証券に係る配当として、持株SPCに対して、SPC②が76億4800万円、SPC①が8億3650万円と上記各当期純利益の額を上回る金額を支払うとともに本件優先出資証券が償還され、同事業年度終了の時(平成27年12月3日)において、本件各子SPCが発行する株式等は控訴人が保有する普通株式のみとなった。そして、本件各子SPCは、それぞれ同年12月3日に清算する旨の株主総会決議を行い、平成28年3月4日に解散した(前提事実(4)イ及びウ)。
エ 本件資金調達スキームと同様のスキームで資金調達を行った控訴人以外の大手邦銀において、優先株式(出資)の償還後において、普通株主(出資者)である大手邦銀側がタックス・ヘイブン対策税制による合算課税を受けた事例があることはうかがえない。
3 タックス・へイブン対策税制の趣旨等
(1)措置法66条の6第1項は、内国法人が、法人の所得等に対する租税の負担がないか又は極端に低い国若しくは地域(タックス・へイブン)に子会社を設立して経済活動を行い、当該子会社に所得を留保することにより、我が国における租税の負担を回避しようとする事例が生ずるようになったことから、このような事例に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的として、一定の要件を満たす外国子会社を特定外国子会社等と規定し、その課税対象留保金額を内国法人の所得の計算上益金の額に算入することとしたものである(最高裁平成17年(行ヒ)第89号同19年9月28日第二小法廷判決・民集61巻6号2486頁参照。甲6、13、乙5、37)。
(2)昭和53年度の税制改正により導入されたタックス・へイブン対策税制につき、導入後間もない時期に大蔵省(当時)の関係者らによって執筆された文献では、「本税制においては、軽課税国の子会社等の留保所得のうち株主の持分に応じて計算される課税対象留保金額は「収益の額とみなして」(株主が内国法人の場合)……合算課税されることとされている。これは、株主たる内国法人……に係る課税対象留保金額が、通常であれば当該内国法人……に対する利益の配当又は剰余金の分配として交付されるべき性質のものであり、株主は子会社等にそうさせるだけの支配力をもっているにもかかわらず、子会社等が配当を全くあるいはわずかしか行わず、留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得る、という考え方の表れといえよう。」(乙5・93頁)、「本税制は、子会社等の法人格を否定することなく、その留保所得が実質的に帰属する者である我が国株主に課税しようとするものであり、そのための課税要件を明確かつ具体的に定めている。別個の法人格を有する外国法人の所得を株主の所得に算入するような措置は極めて異例なものといえるが、しかし、タックス・へイブンの利用という事態に対しては課税の実質的公平を確保するために本税制のような所得計算についての本則の特例を設けることにより株主に対する措置を講ずることが妥当と考えられたのである。」(乙5・93頁)、「今回の立法は、我が国の企業が、いわゆるタックス・ヘイブンに子会社を設け、その子会社に所得を留保して我が国の課税を回避することに対処するものといえる。タックス・へイブンに子会社を設けてもその子会社が所得をタックス・へイブンに留保しないでこれを株主たる我が国の居住者又は内国法人に配当すれば、その配当について我が国で課税が行われるので我が国における租税回避は生じないこととなる。」(乙37)とされている。
(3)ア 引用に係る原判決「事実及び理由」第2の2の「関係法令の定め」(補正後のもの。以下「関係法令の定め」という。)(1)ア及びオ並びに(3)のとおり、平成17年税制改正前においては、措置法上、特定外国子会社等が請求権の内容の異なる複数の種類の株式を発行している場合であっても、それが請求権のない株式等である場合を除き、そのような株式等の種類ごとの請求権の内容は、課税対象留保金額の算定において考慮されないものとされていたのに対し、平成17年税制改正後においては、課税対象留保金額の算定において当該特定外国子会社等が発行する株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算することが定められ(措置法66条の6第1項)、措置法施行令上、内国法人が直接に有する外国法人の株式等につき、当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、内国法人が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額に占める割合を乗じるなどして請求権勘案保有株式等を計算する旨が定められた(措置法施行令39条の16第2項1号)。
イ 上記の平成17年税制改正の趣旨については、財務省関係者の解説によれば、課税対象留保金額の計算の適正化の表題の下で「今回の改正では、課税対象留保金額について、特定外国子会社等が請求権が異なる株式等を発行している場合には、内国法人が特定外国子会社等から実際に受領できる配当等の金額に相当する金額を基に計算することとされました。」(甲9・302頁)とか、子会社の留保所得のうち、内国法人の所得に合算される金額の計算につき、従来は持株割合に応じて合算していたところ、利益持分割合に応じて合算する旨を図示し、具体例としては、持株割合は50%であるが、利益持分割合を90%とするような種類の株式を発行する例があり、これに対抗するため、仮に持株割合より利益持分割合の方が多い場合には、利益持分割合に応じて合算をするということで、租税回避行為の防止という観点から手当をした(乙6)などと説明されている。
(4)タックス・へイブン税制は、平成21年法律第13号による措置法の改正及び平成21年政令第108号による措置法施行令の改正(以下、併せて「平成21年税制改正」という。)により改正されているところ、平成21年税制改正前は、特定外国子会社等が内国法人に支払った剰余金の配当等の額は、その内国法人において益金の額に算入されることから、二重課税を避けるため、特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算上控除されていた(平成21年税制改正前の措置法66条の6第1項、同措置法施行令39条の16第1項。乙38)。
ところが、平成21年税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度が導入されたことに伴い、内国法人が一定の外国子会社から受ける剰余金の配当等は益金不算入となり、適用対象金額等の計算において配当に対する課税との調整を行う必要がなくなったため、特定外国子会社等が支払う剰余金の配当等の額は、適用対象金額等の計算上控除しないことになった。このような内容の変更に伴い、定義も「適用対象留保金額」から「適用対象金額」に変更された(平成21年税制改正後の措置法66条の6第1項、2項2号。甲11・88頁以下、甲14、乙38)。
(5)以上のとおり、タックス・へイブン税制は、タックス・ヘイブンに設立した外国子会社の所得から剰余金の配当等を受け得る支配力を有している内国法人が剰余金の配当等を受けずに外国子会社に留保所得を蓄積しているところに租税回避があるとみて、留保所得のうち内国法人の持分に応じて計算される金額を内国法人の所得に合算して課税することとしたものである。別個の法人格を有する外国子会社の所得を内国法人の所得に算入するという極めて異例なものであるが、内国法人が外国子会社の留保所得から剰余金の配当等を受け得る支配力を有する点(留保所得が実質的に内国法人に帰属するという評価も可能)がこのような課税の合理性を基礎付け、正当化するものと解される(上記(2))。そして、平成17年税制改正は、持株割合によって上記の支配力を把握するだけでは、外国子会社が剰余金の配当等の経済的な利益の給付を請求する権利の内容が異なる株式等を発行し持株割合と異なる割合で剰余金等の配当を行う場合には租税回避を十分に阻止できないなどの問題があったことから、上記の経済的な利益の給付を請求する権利の内容も勘案し、その権利に基づき受けることができる剰余金の配当等の額の割合(以下「利益持分割合」という。)によって上記の支配力を適正に把握できるようにしたものと解される(上記(3))。
なお、平成21年税制改正により、特定外国子会社等が支払う一定の剰余金の配当等は適用対象金額の計算上控除しないこととなったが、外国子会社配当益金不算入制度が導入されたことに伴い、配当に対する課税との調整を行う必要がなくなったことによるものであり、上記のタックス・へイブン対策税制の制度の基本的な趣旨や合理性、正当性の根拠について変更をもたらすような改正ではない(上記(4))。
4 措置法施行令39条の16第2項1号の「外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」の判断時期
(1)措置法施行令39条の16第1項は、タックス・ヘイブン対策税制において内国法人の収益の額とみなされる課税対象金額は、適用対象金額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合(請求権勘案保有株式等割合)を乗じて計算した金額とする旨定めていること(関係法令の定め(1)エ。このように各事業年度終了時の株式等によって請求権勘案保有株式等割合を計算する旨は、平成17年税制改正前から同様に定められている。)に加え、措置法施行令39条の20第1項は、外国法人が外国関係会社に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が法66条の6第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものと定めていること(関係法令の定め(1)イ。このように上記各判定は各事業年度終了時の現況による旨は、平成17年税制改正前から同様に定められている。)を併せ考慮すると、措置法施行令39条の16第2項1号(平成21年税制改正前措置法施行令39条の16第3項1号)が剰余金の配当等の割合から請求権勘案保有株式等を計算すべき場合として定める「外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」に該当するか否かの判定は、特定外国子会社等の事業年度終了の時の状況によると解するのが同規定の文理解釈として自然である。
そして、平成17年税制改正は、外国子会社の留保所得(すなわち、ある時点で剰余金の配当等がされずに外国子会社に蓄積されている所得)に対する支配力を、剰余金の配当等の割合(利益持分割合)によって把握しようとしたものであるところ(前記3(5))、剰余金の配当等を受け得る支配力を判断する時点を外国子会社の事業年度終了の時と設定するのであれば、同じ時を基準として「外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」には利益持分割合で、そうでない場合には持株割合で支配力を判断するのが合理的である。
そうすると、上記文理解釈の結果は、利益持分割合によって請求権勘案保有株式等を定めるべき場合があることを新たに定めた平成17年税制改正の制度趣旨にも合致するものということができる。
(2)これに対し、控訴人は、措置法施行令39条の16第2項1号括弧書の「当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」とは、事業年度終了の時に限定せず、事業年度のいずれかの時点でそうであれば足りると解釈した上、事業年度全体の剰余金の配当等の額の割合によって請求権勘案保有株式等を計算すべきであると主張する(事業年度終了の時に請求権の内容が異なる株式等が発行されていた本件各子SPC事業年度の前年度については、事業年度全体の剰余金の配当等の額の割合によって請求権勘案保有株式等を計算するという計算方法が処分行政庁によって問題とされたことはなかったが(前提事実(4)ア)、控訴人は、このような計算方法を事業年度のいずれかの時点で請求権の内容が異なる株式等が発行されていた本件各子SPC事業年度にも用いることができる旨主張している。)。なるほど、このような解釈によれば、本件各子SPCの本件各子SPC事業年度の当期純利益(適用対象金額)に対する控訴人の支配力(利益持分割合)に即した課税対象金額を算定できることになる。
しかしながら、①上記(1)のとおり、条文の文理解釈のみならず、利益持分割合によって請求権勘案保有株式等を定めるべき場合があることを新たに定めた平成17年税制改正の制度趣旨に照らしても、「外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」とは、特定外国子会社等の事業年度終了時の状況のことを指すと解されること、②控訴人が主張する上記解釈を措置法施行令39条の16第2項1号の一般的な解釈として採用した場合、例えば、事業年度の途中まで優先出資証券と普通株式が発行されていた外国子会社について、その両者を有していた内国法人Aと普通株式のみを有していた内国法人Bがおり、その優先出資証券に基づいて期中に内国法人Aに優先的に多額の配当がされた後に優先出資証券が償還され、事業年度終了の時には、内国法人Aと内国法人Bが普通株式のみを保有していたという事例において、内国法人Aは期末の持株割合ではなく、これより多い事業年度全体を通じた剰余金の配当等の額の割合による合算課税を受けることになるが、このような結論については、納税者の経済生活における法的安定性や予測可能性を害するおそれがあり、租税法律主義の観点から問題があることからすれば、控訴人が主張する上記解釈を措置法施行令39条の16第2項1号の一般的な解釈として採用することはできず、同号の解釈は、上記(1)の文理解釈によるほかないというべきである。
5 措置法施行令39条の16第1項、2項の規定の適用の是非
(1)措置法施行令39条の16第2項1号所定の「外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合」に該当するかどうかの判定は、特定外国子会社等の事業年度終了の時の状況によるとの解釈(前記4(1))によれば、本件各子SPC事業年度の終了時においてSPC②が発行していた株式は、控訴人が保有する普通株式6410万株のみであったから、SPC②の請求権勘案保有株式等割合は100%となり、SPC①についても同時点において発行していた株式は、控訴人が保有する普通株式1210万株のみであったから、SPC①の請求権勘案保有株式等割合も100%となる。処分行政庁は、これを前提に、措置法施行令39条の16第1項、2項の規定を形式的に適用して、本件各子SPCの適用対象金額の全額が課税対象金額として控訴人の本件事業年度の所得の金額の計算上益金に算入されることなどを理由として、本件各処分を行ったものである。
(2)しかしながら、前記2で認定したとおり、本件資金調達スキームが利用された経緯、目的、仕組みからして、控訴人が本件各子SPCの当期純利益から剰余金の配当等を受け得ること、言い換えれば、その当期純利益に対して支配力を有すると評価されるような処理はもともと想定されておらず、現に本件各子SPC事業年度においても、上記の仕組みに従って、本件各子SPCの当期純利益を上回る金額が期中に持株SPCに配当されており、事業年度全体を通じてみても、また、期末時点についてみても、控訴人が上記当期純利益(適用対象金額は同額である。)に対して支配力を有していたとは認められない。そうすると、本件資金調達スキームにおける本件各子SPC事業年度の処理において、内国法人(控訴人)が外国子会社(本件各子SPC)の利益から剰余金の配当等を受け得る支配力を有するというタックス・へイブン対策税制の合算課税の合理性を基礎付け、正当化する事情は見いだせないし、また、上記処理に租税回避の目的があることも、客観的に租税回避の事態が生じていると評価すべき事情も認められない。それにもかかわらず、処分行政庁は、前記4(1)の解釈を前提として措置法施行令39条の16第1項、2項の規定を形式的に適用し、本件各子SPC事業年度終了の時には控訴人が本件各子SPCの全株式を保有していたことから、持株割合による請求権勘案保有株式等割合が100%であったとして、控訴人が支配力を有していなかった本件各子SPCの同事業年度の当期純利益から算出された適用対象金額(当期純利益と同額)の全額を本件各子SPCとは別法人である控訴人の所得に合算したものであって、このような扱いは、措置法66条の6の趣旨ないしタックス・へイブン対策税制の基本的な制度趣旨や理念に反するものであり、正当化できないというほかない。
そして、前記2の事実関係によれば、本件各子SPC事業年度の本件各子SPCの適用対象金額(当期純利益)に対する控訴人の支配力は存在しないから、その適用対象金額のうちに、控訴人の有する株式等の数に対応するものとして剰余金の配当等の経済的な利益の給付を請求する権利の内容を勘案して控訴人の益金に算入するのが相当な金額(課税対象金額)は存在しないと解するのが、タックス・へイブン対策税制の基本的な制度及び理念、そして、これを踏まえた措置法66条の6の趣旨に照らして相当であり、これに反する限度で措置法施行令39条の16第1項、2項を本件に適用することはできないというべきである。
なお、上記判断は、本件の具体的事案において、措置法66条の6の趣旨等に照らし、措置法施行令39条の16第1項、2項2号が定める課税対象金額の計算に関する部分を文理解釈どおりに形式的に適用することはできないとするにとどまるものであり、措置法66条の6第1項の適用要件及び同条3項の適用除外要件に租税回避の目的や実態の有無という新たな要件を付加するものではない。
6 以上によれば、控訴人の本件事業年度の法人税に係る所得金額は、被控訴人が主張する5019億9836万9849円から本件各子SPCに係る課税対象金額の益金算入額84億8279万0107円を除外した4935億1557万9742円であり、これを前提とすると、納付すべき法人税額は、628億8628万7000円であり、控訴人の本件事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額は、1177億8873万3000円であり、納付すべき地方法人税額は、38億2783万9600円である(弁論の全趣旨)。そうすると、本件各更正処分のうち上記額を超える部分及び本件各賦課決定処分はいずれも違法である。
第4 よって、控訴人の請求中、本件各更正処分の取消請求(拡張後のもの)及び本件各賦課決定処分の取消請求については、いずれも理由があるから認容すべきであるところ、これら(ただし、本件各更正処分については当審における拡張前の請求)を棄却した原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、原判決を取り消した上、控訴人の上記各請求をいずれも認容することとし、本件各通知処分の取消しを求める部分は、不適法であるから却下することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 鹿子木 康
裁判官 頼 晋一
裁判官藤澤孝彦は、転補のため、署名押印することができない。
裁判長裁判官 鹿子木 康
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.