解説記事2022年06月13日 SCOPE ロイヤルティに係る移転価格課税巡り納税者再び勝訴(2022年6月13日号・№934)
処分の大部分を取り消した原判決維持
ロイヤルティに係る移転価格課税巡り納税者再び勝訴
セラミックス製品の製造等を行うN社が海外子会社との間で行ったロイヤルティ取引に対する移転価格課税の適法性を巡り争われていた事件で、東京高裁は令和4年3月10日、課税処分の大部分を取り消した原判決を支持し、国の控訴を棄却した。
残余利益の分割要因として「重要な無形資産以外の利益発生要因についても考慮すべき」とした一審の判断が控訴審でも支持された形となった。本件と同様の取引に係る平成23−27年分の処分についても東京地裁で係争中だが、同様の判断が下されることになりそうだ。
高裁も残余利益の分割要因に重要な無形資産以外の要因も考慮すべきと判示
本事案で課税処分の対象となったのは、N社が、自動車の排ガス浄化用部品の製造を行う海外子会社(本件国外関連者)から、特許及びノウハウ等の使用許諾の対価として受け取るロイヤルティに係る取引である。国は、N社が受け取るロイヤルティの額が独立企業間価格に満たないとして移転価格税制を適用した(国の算定方法について図表参照)。
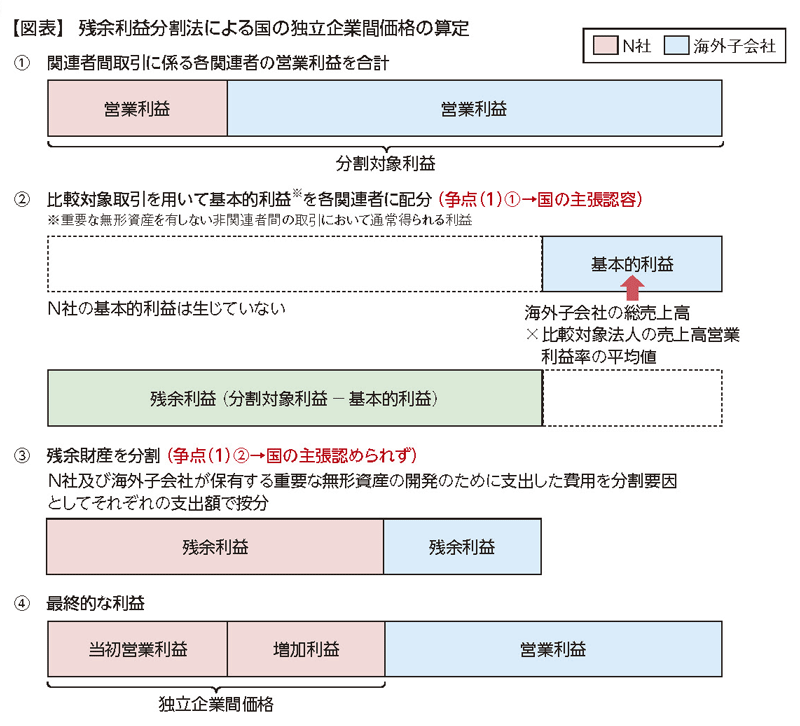
一審の東京地裁は、(1)国の基本的利益の算定は相当であるとしたものの、(2)残余利益の分割については、重要な無形資産の開発に係る原告及び本件国外関連者の各支出額のほかに、本件国外関連者に係る超過減価償却費を分割要因に加えて配分するのが相当であるとして、原告の主張を一部認め、課税処分の大部分を取り消した(本誌879号参照)。
国はこれを不服として控訴し、N社も主張が認められなかった部分について附帯控訴を行ったが、双方ともに補充主張はすべて排斥され、原判決が維持された。
国は、「残余利益の分割要因は基本的に『重要な無形資産』のみによるべきで、重要な無形資産とは全く無関係な別個の要因を分割要因と認めるには、『重要な無形資産』に匹敵する適度の価値(重要性)を備え、超過利益獲得に寄与する(相関関係のある)ものと認められる必要がある」と主張したが、これに対し東京高裁は、租税特別措置法施行令39条の12第8項1号及び措置法通達66の4(4)−2の規定、OECD移転価格ガイドラインを挙げ、そのような考え方をうかがわせる条項や記載はないとした。
その上で、「確かに、平成23年改正前の措置法通達66の4(4)−5の規定から、残余利益分割法における分割要因は『重要な無形資産』に限られるかのような解釈もみられたが、同通達は、これらの者が分割対象利益の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因(分割要因)に応じて計算するという措置法施行令39条の12第8項1号の規定を具体化するものとして定められた通達にすぎない上、(中略)残余利益分割法を定める法令の解釈として、「重要な無形資産」以外にも分割対象利益の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因があると認められる場合であってもこれを考慮しなくてよいとする趣旨であるなどと解することはできない」との考えを示した。
また、国は、「本件国外関連者の設備投資による売上高等の増大は、比較対象法人との比較による基本的利益の算定において考慮済みであるから、かかる事情を残余利益の分割要因として考慮すべきではない」などとも主張したが、東京高裁は「本件国外関連者による本件製品の生産については、市場条件や競争状況、設備投資の規模や資本集約度の高さ、規模の利益の発生等、比較対象法人には当てはまらない要因が存在し、これに基づいて利益が発生したという事情が認められ、しかも、それらの要因が重要な無形資産と重なり合い、相互に影響しながら一体となって超過利益(残余利益)が発生したと認められることなどから、これらの事情は、比較対象法人との比較による基本的利益の算定において考慮済みであるなどとはいえず、残余利益(超過利益)の分配において適切に考慮されるべき」などとして、国の主張を斥けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















