解説記事2022年07月25日 ニュース特集 令4改正通達踏まえた財産債務調書の記載変更点(2022年7月25日号・№940)
ニュース特集
富裕層の財産把握のため高まる重要度、記載簡略化で提出促す狙いか
令4改正通達踏まえた財産債務調書の記載変更点
近年、課税当局は「重点管理富裕層プロジェクトチーム」(富裕層PT)を設けるなどして、富裕層に対する課税の適正化に取り組んでいる。富裕層が所有する国内外の財産・債務の情報収集を行う方法として、財産債務調書制度及び国外財産調書制度があるが、周知のとおり、令和4年度税制改正ではこれらの制度の見直しが行われている。
この改正を受け国税庁は7月5日、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の改正通達(以下、「調書通達」)、及び改正内容のポイントを示した「財産債務調書制度等の見直しについて」を公表した。本特集では、令和4年改正の内容を押さえつつ、今回の通達の改正等で詳細が明らかになった部分を、「財産債務調書制度FAQ(令和3年12月)」(以下「QA」)の内容等も踏まえながら詳しくお伝えする。
提出義務者の拡大の一方で提出期限は延長も、宥恕規定は厳格化
まず、令和4年改正の内容をおさらいしておこう(表1参照)。
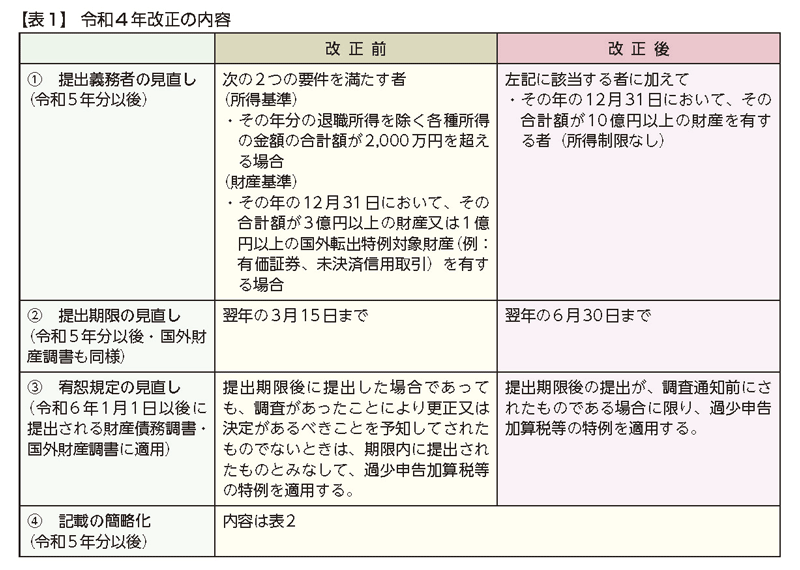
改正前は、所得2,000万円以下の者は、仮に高額の資産を保有していたとしても財産債務調書の提出義務がなく、課税庁による資産の異動状況等の把握が十分でないという課題があった。そこで、令和5年分以後は、提出義務者に所得要件を設けずに、財産の価額の合計額が10億円以上の者を提出義務者に加えることとされた。
なお、海外で保有する資産の合計額が12月31日時点で5,000万円を超える場合は、別途、国外財産調書も提出しなければならない。
また、改正前の提出期限(3月15日)までに、保有財産の詳細を正確に算出・記載することは必ずしも容易でないことから、提出期限を6月30日まで延長することとされた。同様に事務負担軽減の観点から、記載事項の運用上の簡略化も改正事項に盛り込まれた。
記載事項の簡略化については、税制改正大綱では、記載を省略することができる「家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(改正前:100万円未満)に引き上げる旨のみが明らかにされていたが、7月5日に公表された改正後の調書通達では、簡略化できる財産・内容の詳細が明らかになった(表2参照)。
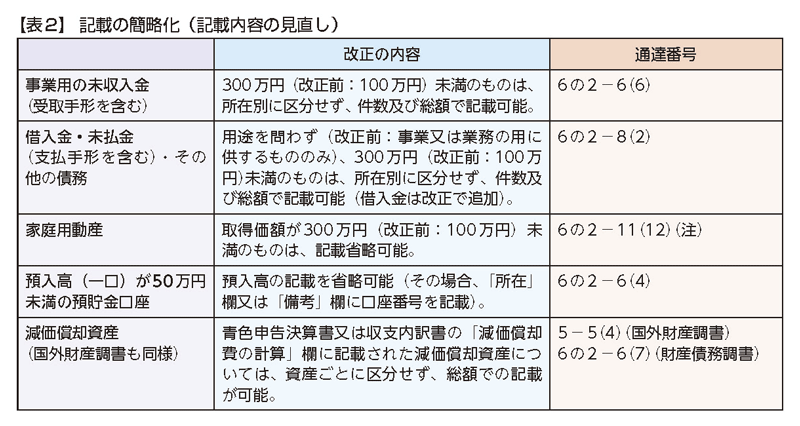
そのほか、提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置も見直された。
周知のとおり、財産債務調書等を提出期限内に提出した場合は、調書記載の財産・債務に関して所得税等の申告漏れがあっても、過少申告加算税又は無申告加算税が5%軽減され、また、調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された調書に記載すべき財産・債務の記載がない場合に、その財産・債務に関して所得税等の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。
改正前は、提出期限後に財産債務調書等を提出した場合であっても、税務調査によって更正または決定があることを予知していない場合は期限内に提出したことになり、過少申告加算税・無申告加算税が軽減されることとなっていたが、令和6年1月1日以後は、この宥恕規定が適用されるのは、税務調査の通知がある前に財産債務調書等を提出した場合に限られることとなる。
財産の価額は見積価額、財産評価通達価額のいずれでもOK
財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」とされているが、時価に準ずるものとして「見積価額」によることも可能とされている。
時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格などとされている。また、見積価額とは、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいうとされている(調書通達6の2−10)。調書通達6の2−11では、財産の区分ごとの見積価額が例示されている。
また、財産債務調書には、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額を記載することもできる(QA23)。
上記以外で記載上注意すべき事項として、QAの中でも重要性が高いものを紹介する。
まず、その年の12月31日において保有する財産の価額の合計額の判定に当たっては、含み損のあるデリバティブ取引や信用取引等に係る権利の価額を含めて判定する必要がある(QA3)。
また、事業用の財産債務とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供している財産債務をいい、一般用の財産債務とは、当該事業又は業務の用に供する以外の財産債務をいうが、記載すべき財産債務の用途が「一般用」及び「事業用」の兼用である場合には、一般用部分と事業用部分とを区分することなく、財産債務調書に記載することができる(QA6、調書通達6の2−6、6の2−8)。
さらに、土地付き建物など、2以上の財産の区分からなる財産で、それぞれの財産の区分に分けて財産の価額を算定することが困難な場合には、一体のものとしてその財産の価額を算定し、いずれかの財産の区分にまとめて記載することができる。ただし、備考欄にその旨を記載しなければならない(QA7、調書通達6の2−4)。
そのほか、財産的価値のある暗号資産を12月31日において保有している場合は、財産債務調書への記載が必要になる(国外送金等調書法6の2①本文)。暗号資産は、財産の区分のうち、「その他の財産」に該当するため、財産債務調書には、暗号資産の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別に記載する。暗号資産の所在は、その財産を有する者の住所又は居所となり、暗号資産を預けている暗号資産取引所の所在が国内か国外であるかは、財産債務調書への記載の要否に影響はない(QA10)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























