解説記事2022年08月22日 巻頭特集 総則6項判決の歴史的意義と評価通達のあり方(2022年8月22日号・№943)
巻頭特集
対談
総則6項判決の歴史的意義と評価通達のあり方
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
公認会計士・税理士 緑川正博
6億9,787万円の相続財産の相続税額をゼロにしたことで総則6項の適用を受けた事案の最高裁判決は納税者側の敗訴に終わったが、最高裁が弁論の機会を設け、平等原則に言及した上で総則6項の適用を適法としたことは税務の専門家の間でも大きな話題を呼んだ。しかし、実は今回の最高裁判決が、36年前に最高裁が自ら示した判断を修正するものであることを知る者は少ない。
この案件に当時法務省の課長補佐として携わり、控訴を断念していた国税当局を翻意させた人物が、品川芳宣 筑波大学名誉教授だ。総則6項を巡る初の判決である東京高裁昭和56年1月28日判決、その上訴審の最高裁昭和61年12月5日判決から総則6項を巡る問題にすべて対応してきたという点では唯一の国税OBである品川教授は、今回の判決に至るまで最高裁が同種事例をことごとく不受理としてきた長い期間を「40年戦争」と表現する。
現在は税理士法人大手町トラストの代表社員として約50名の税理士を率いる実務家兼経営者ともなった品川芳宣 筑波大学名誉教授と、かつて平成2年に話題を呼んだ株価通達について品川教授と対談するなど企業税務に関する実務家の緑川正博公認会計士に、本最高裁判決への評価、財産評価基本通達への考え方などについて語っていただいた。(対談本文中敬称略)
本件だけが最高裁まで争われた理由
緑川:財産評価基本通達(以下、評価通達)総則6項に関する最高裁判決(最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決)が出て以来、様々な評釈や意見が出されています。その中には、今回の最高裁判決について「平等原則を無視している」とか「租税法律主義における予測可能性を無視している」といった批判も見受けられますし、現在の評価通達を「悪」とするものもあります。
品川:そうですね。今回の最高裁判決は過去の経緯を知らないと理解できない部分もあるので致し方ないのかもしれませんが、少なからず的外れな論評も見られるように感じます。たまたま、総則6項に関して事の発端からすべて対応してきたのは歴史的に私しかいないため、この最高裁判決は感慨深いものがあります。
緑川:その辺りのお話は後ほどじっくりお聞きするとして、まず私が疑問に思ったのは、アドバイザーの問題です。平等原則を主張するなら、どうして「他では認められているのに何故本件だけは認められないんだ」という主張を他の事例を個別、具体的に示した上でしなかったのかということです。通常、本件でタックスプランニングを提案した信託銀行は、「他でも同様の提案をしているが問題になっていない」と説明しているのではないかと思います。また、信託銀行であれば多くの事例を持っているので、課税処分を受けなかった事例を具体的に示すことができたはずです。こうした点を踏まえると、本件は果たして争われる事案だったのかという疑問が湧いてきます。

品川:原告側の主張に少し書いてありますね。他の事案でもよくやっていて認められているのだから、本件だけ課税処分を受けるのは平等原則に反するのではないかという主張は若干しています。確かにもう少し事例を出すというやり方はあるかもしれませんが、信託銀行としては、自分達が被告になっているわけではありませんので、できればあまり関わりたくなかった、少なくとも訴訟では表に出たがらなかったのではないでしょうか。自分達が提案をしたとしても、訴訟になったらあとは弁護士に任せ、自分達が率先してこういうことを勧めたということを表沙汰にしたくなかったのではないかと思います。

本件における税理士の立ち位置
緑川:逃げですね。信託銀行の勧めに乗った納税者にも問題があったとは思うのですが、当然、税理士がついていたはずですよね。このケースで相続税をゼロにすれば否認されるリスクがあることは明らかなわけですから、その点は当然指摘するべきだったと思いますが。
品川:信託銀行には必ず顧問税理士がいるはずであり、逆に言えば顧問税理士こそこの提案の実際の立役者になっていたのではないかと思います。私の今の仕事は納税者の代理人ですけれども、否認されるリスクがあるかどうかということはしょっちゅう問題になりますし、リスクはきちんと説明しています。ただ、リスクを負うか負わないかを最後に判断するのは納税者であり、「最後はお客様のご判断ですよ」ということは言いますね。
緑川:不動産というのは扱う金額が大きいだけに、必然的に税務リスクも大きくなります。また、今回のような事案には銀行、弁護士、税理士と多くの人が絡み報酬も多額になります。こうした中で、誰かが調整役をやるべきでしょうか。
品川:結局は申告納税制度ですから、最終的にはお客さんの判断、納税者の判断ということになるのではないでしょうか。
緑川:でも納税者は税務に関しては素人ですよ。
品川:実際には税務代理人である税理士ですね。我々は税務代理契約を締結して代理人として申告したり、税務調査に対応したり、何らかの節税方法があった場合にはリスクを説明して、あとはお客さんがどう判断されるかということです。
緑川:タックスプランニングを実行してしまった後に先生のところに話が来た場合にはどうするんですか。
品川:申告期限前であれば、売買契約を破棄するということもできます。実際、そういうアドバイスをすることはありますね。
緑川:しかし、本件はそうはなりませんでした。
品川:とにかく相続税がゼロになればよいということで押し通そうとしたということでしょうね。税理士法1条には、税理士の使命として「納税義務の適正な実現を図る」と書いてありますが、適正な納税義務とは何かということについて、当時主税局の立法担当者も「適正な納税義務には適法な節税をすることも含む」という説明はしています。では適法な節税とは何かということになると、租税回避との境が非常に見え難くなります。税理士として、お客様に「こうやったら税金が安くなりますよ」と言うことが卑しいことなのか高尚なことなのか、そこは非常に難しいところですね(笑)。
緑川:単に評価通達に起因する評価上の乖離を利用することが節税とは思いませんが。企業継続においては税というのは基本的に重要コストですから、それをどう軽減するのかということについてプランニングするのは大切だと思いますが、個人が6億円を超える財産の相続税を評価ギャップを利用してゼロにすることがプランニングだとは思わないですね。現金をリスク資産に変え、リスクがあるということですぐに売却しただけですから。
品川:そこが通達では「著しく不適当」という表現になるし、今回の最高裁判決では「特別な事情」について「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」という表現になるわけです。いずれにせよ、通達評価額と取引価格に乖離があるというのは周知の事実です。今回はたまたま最高裁まで争われることになりましたが、この種の節税案件は日常茶飯事的に行われているというのが実態だと思いますね。
40年前の判断を修正した最高裁判決
緑川:同種事案が他にも多数あると思われる中で本件だけが何故最高裁まで争われたのでしょうか。
品川:この点については、私が法務省の課長補佐時代、今から45〜6年前に手掛けた事案について話さなければなりませんね。その事案こそが、総則6項の適用を受けて最高裁まで行った初めての事案です。被相続人が死亡した2週間後に引き渡しされることになっていた売買途上にある土地について、国税当局は既に売却されたものとして売買価額で課税したのに対して、東京地裁は亡くなった時点では引き渡しが済んでいないからまだ「土地」であるとして、路線価で評価しました。この時の売買価額が約4,500万で、路線価による評価額は2,000万位だったのですが、東京地裁は申告の内容を認めて課税処分を取り消しました(東京地裁昭和53年9月27日判決)。国税庁は「これはもう仕方がない。控訴はしない」と言っていたのですが、私は法務省の課長補佐として課長に対して「本件のように売買が確定して代金が確実に入ってくるケースでは、裁判上『特別な事情』を認めて、通達評価額ではなくて、本来の客観的交換価値で課税すればよいのではないか」と進言しました。
緑川:確かにその物件の売買価格、すなわち客観的交換価値が明らかになっているわけですからね。
品川:ただ、その時にも平等原則が問題となったのです。国税庁も、通達が路線価等の評価額を「時価」と言っているにもかかわらず、いたずらに総則6項を適用して評価を二分割にすることは平等原則に反するとの考えでした。当時の租税法学者も、そのような解説をしていました。本件では、東京高裁(昭和56年1月28日判決)は私が書いた準備書面を認めたのですが、敗訴した納税者側が上告したのです。最高裁(昭和61年12月5日判決)は、平等原則に反するといった批判に配慮して「特別の事情」があるから課税処分は正しいとした高裁の判断には触れないまま、高裁判決を維持しました(本誌936号21頁参照)。最高裁は、本件は「相続財産」が違うという整理をしました。要するに、単なる土地ではなくて、土地が債権に化体していると言ったのです。したがって、債権として評価をすればよいので、売買価額と同じ金額になると。高裁判決については、結論は正しいけれども理由が違うと整理しました。それ以降、最高裁はこの種の案件については一切受理しないようになりました。要するに判断を示さなかったのです。
緑川:平等原則が問題となったにもかかわらず、これを財産の種類の問題にすり替え、それ以来、最高裁は6項に関する平等原則の問題については判断を示さずに来たということですね。
品川:そうです。「逃げていた」とも言えるかもしれません。
緑川:しかし、今回は平等原則の問題を初めて正面から受け止めました。これは何故でしょうか。
品川:地裁、高裁による6項の適用に関して「裁判上の特別事情」を容認して「平等原則に反しない」とする判決の蓄積を踏まえて、裁判所はこの辺で最高裁としてのお墨付きを出してもよいのではと考えたのではないでしょうか。本件で最高裁が弁論を開くということで、原審の判断がひっくり返るのではないか、納税者が勝つのではないかという観測記事がたくさん流れましたが、勝ち負けはともかく、最高裁が弁論を開くということは、たとえ結論は原審の判断と同じでも、最高裁として新たな考えを示すということであり、私も関心を持っていました。最高裁は、「特別の事情の問題」について「著しく課税の公平に反する事情がある場合」というような言い方で対応してきたわけです。今回、最高裁として総則6項を適用した課税処分を裁判上適法と認めることの論拠を明確にしたという点では非常に画期的な判決と言えます。これは、昭和61年の最高裁判決では避けていた結論を、いうなれば“40年戦争”を経て、最高裁が判断を下したということです。
緑川:相続財産の種類の問題ではなくて、評価の問題として捉えたということですね。
品川:そうです。特に本件のように、不動産を相続直前に取得するようなケースには、今回のような対応をとらざるを得なかったということでしょうね。
緑川:もう逃げられなくなったと。
品川:最高裁は、通達違反の課税処分は「一般論としては」平等原則に反するのだけれども、合理的な理由があればそうはならないと言っています。そして、「合理的な理由」というのは、「実質的な租税負担の公平に反するという事情があるかどうか」ということで、本件については、本来であれば6億円を超える相続財産があったにもかかわらず不動産を購入することによって相続税がゼロになったというような事情があれば、それは「実質的な租税負担の公平に反するという事情」であると言っています。つまり、「平等原則」の適用から除外される「合理的な理由」に当たるという論法で、原審の判断を維持したわけです。
本件の根本には旧措置法69条の4
緑川:結局、本件の問題点は、相続人が借金を不動産所得で返済していくという、不動産業をきちんとやっていくという長期的な計画がなかったということに尽きるのではないでしょうか。本気で不動産業をやるのであれば、何で問題にするんだと言えるだけの事実を積み重ね、採算を明確にしておけばよかったのではないかと思ってしまいます。
だから、最初にアドバイザーの問題を指摘したのです。
品川:実際、不動産業をやる気がないから、購入した不動産のうちの1つはすぐに売却していますしね(前記図表参照)。本件最高裁判決でも、通達評価額との乖離を利用した取引があり、その取引の結果税負担が減少したということで、「税負担の減少と取引の間に相当因果関係がある」という言い方になりました。極端なことを言えば、10年前に不動産を買って結果的に相続税が安くなったとしても、「相当因果関係がある」と言い難いでしょう。結局、相当因果関係があるかどうかは例えば1年とか2年とか、期間的な問題もあるんだろうと思います。その期間をどのように認めるかはまた議論があるところでしょう。本件では、最高裁が総則6項の適用要件を示さなかったことに対し不満の声が聞かれましたが、裁判官にとっても、総則6項適用の適用要件を明らかにするというのは非常に難しいことです。通達評価額と取引価額に乖離があるのは当然であり、通達評価額が取引価額を上回ることもあります。問題となるのは、乖離を利用する取引があり、取引の結果、税負担に相当額の差が生じ、その相当額の乖離とその取引との間に相当因果関係がある、といった要件を満たしている場合です。ですから、取引がなければ問題にならないんですよ。
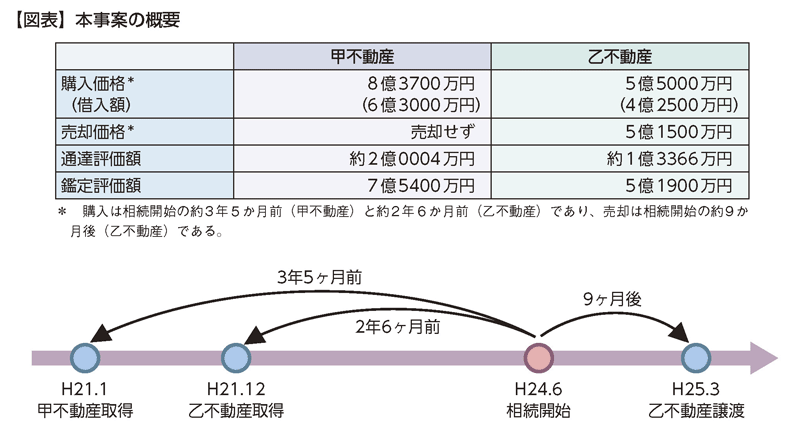
緑川:本件で言えば「借金して不動産を購入する」という取引ですね。
品川:そうです。かつて負担付贈与通達(下記参照)を出した際にもよく言われたのは、例えば、10億の土地の評価額が6億円だとすると、その土地を単純贈与すれば6億で済むんですよ。それを6億円の負担を付け、あるいは6億円で売ったことにして4億の差額を“ピンハネ”しようとするから、あのような通達を出したのです。
負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について(抜粋)
| 土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。 |
緑川:本件は自己資金でやったらよかったのではないでしょうか。単純贈与と一緒で。
品川:いえ、本件の根本には旧措置法69条の4がありますので。10億円の貯金があったら10億円に課税されるけれども、当時は土地を買えば1億円になるということで、じゃあ父親が亡くなりそうなので早く土地を買おうということになる。旧措置法69条の4ではそれに対して全部蓋をしたんです。
緑川:蓋をした後に本来は手当が必要であったにもかかわらず、してないということですね。
品川:負担付贈与通達の決裁段階で、当時の長官が、こんな通達を出せるのであれば、措置法69条の4だって通達でやればよかったと言っていましたが、負担付贈与通達がまだ生きてるように、通達でやれば済むんですよ。負担付贈与通達を出した時に私が東京税理士会に説明に行ったところ、ある税理士から「なぜ69条の4のように法律に書かないのか、なぜ通達でやるのか」という質問を受けました。そこで、「財産評価基本通達はあくまでも評価の通達であるため“通常取引される価額で評価する”と書いてあるのであって、取得価額で評価するとは一言も書いてない。ただし、それが通常取引される価額に相当する場合は、買った値段でもよいということを言ってるだけだ」と回答しました。そして、逆に私から、「措置法69条の4では、あくまで取得価額と言っているので、1億円で買った土地が5千万円に値下がりしても1億で課税するのに対し、通達では5千万円に値下がりしたら5千万円で評価して課税することになる。どちらがよろしいですか?」と聞いたところ、その税理士曰く、「土地が値下がりするはずがないだろう」と。それが当時の税理士の一般的な感覚でした。
緑川:それからあっという間に土地が暴落しましたが。
納税者、課税庁ともにメリットを享受する評価通達を否定する意味はない
品川:相続税を少なくするには、別に銀行から借金をしなくても色々なやり方があるわけですから、本件も相続開始近くになって銀行から借金したことだけの問題ではなくて、要するに通達評価額との開差をどういうふうにどこまで利用したらセーフなのかアウトなのかという、ある意味永遠の課題なんです。したがって、冒頭で緑川先生からご指摘があったように、評価基準制度(評価通達)を否定したって仕方がないんですよ。
緑川:確かに国税当局は通達、言わばマニュアル通り課税すればいいし、マニュアル通りにしてくれるから納税者・実務家も楽なんですよ。その評価基準制度を「悪」だというのは理解できませんね。
品川:そういうことです。納税者や実務家、そして課税庁も評価基準制度の利益を享受しているのです。だから制度自体は否定できないし、どこかに弊害が生じた場合には、お互い知恵を出し合うことが重要だと思いますね。
緑川:壊さないように努力すべきでしょうね、お互いが。マニュアルは、当然に100点満点とはいかないですから。
品川:はい、お互いが制度をうまく活用するということです。
緑川:とはいえ、今回の最高裁判決によって、今後総則6項適用事案が増えるのでしょうね。
品川:増えるでしょうね。実際、これまでは評価通達185のカッコ書きに「課税時期前3年以内」と書いてあるから、会社が買った不動産に対して「3年過ぎたから大丈夫だろう」と思っていたところ、最近は調査官が今回の最高裁判決のことを出してくるケースが増えているようです。国税当局が強気になるのは間違いありません。
緑川:それに対して税理士がどれだけキチンと対応できるかということがこれからの課題になりそうですね。キチンとした理論武装の第一人者として実務家になった品川先生と久しぶりに対談できて楽しかったです。本日はありがとうございました。
財産評価基本通達185(純資産価額)
| 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、 以下略 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























