解説記事2022年09月05日 SCOPE CFC税制とソフトバンク税制ダブル適用に二重課税の懸念(2022年9月5日号・№945)
法令上何らかの調整措置を設けるべきとの声
CFC税制とソフトバンク税制ダブル適用に二重課税の懸念
外国子会社合算税制(CFC税制)と子会社株式簿価減額特例(いわゆるソフトバンク税制)が両方適用された場合、二重課税が生じるのではないかとの疑問が実務家の間で生じている。この疑問を受けて本誌が課税当局に見解を取材したところ、「行政機関である課税当局として、その状況を二重課税とみるのかどうかについてはコメントできない」との回答であったが、企業や実務家からは、納税者の担税力に即しているとは言い難い課税が生じ得る以上、法令に何らかの調整措置を設けるべきではないかとの声が挙がっている。
両税制ダブル適用でキャッシュ増加額の約2倍が課税対象に
周知の通り、CFC税制は、措置法66条の6に定める対象外国関係会社等の「課税対象金額」を、内国法人の収益の額とみなして益金の額に算入する制度である。そして、内国法人が外国法人から受ける配当等の額がある場合には、措置法66条の8の規定により、その額のうち「特定課税対象金額」(課税対象金額を基礎として計算)に達するまでの金額は、益金の額に算入しないこととされる。この取扱いは、法人税法23条の2に定める外国子会社からの配当の場合、同条第1項を読み替える形で、配当金の全額を益金不算入とする仕組みとなっている(措置法66条の8第2項)。一方、ソフトバンク税制について定める法人税法施行令119条の3第10項は、適用除外要件に該当する場合を除き、外国子会社配当益金不算入を含む「益金不算入規定」により益金の額に算入されない金額に相当する金額を、株式の簿価から減算すると定めている。CFC税制が適用された外国法人からの配当であってもソフトバンク税制の対象となり得ることは、法人税基本通達2−3−22の2からも明らかだ。同通達では、措置法66条の8第2項の適用を受けた場合でも、ソフトバンク税制の対象となるのは、100%ではなく読み替え前の95%分である旨明記している。
こうした中、実務家の間では、CFC税制が適用された外国子会社からの配当にソフトバンク税制まで適用されてしまうと、二重課税が生じるのではないかという疑問が生じている。例えば、簡便的な数値と仮定を用いた【表】ケース1の場合、CFC税制とソフトバンク税制のダブル適用により合計で1,950が課税対象とされることになるが、一連の取引を通じたキャッシュの増加は1,000に過ぎない。両税制のいずれかのみが適用されるのであれば、キャッシュの増加額と課税対象額が同額となるが(【表】ケース2及び3参照)、両税制が適用されると、課税対象額がキャッシュの増加額の約2倍となり、この点が二重課税ではないかと問題視されている。
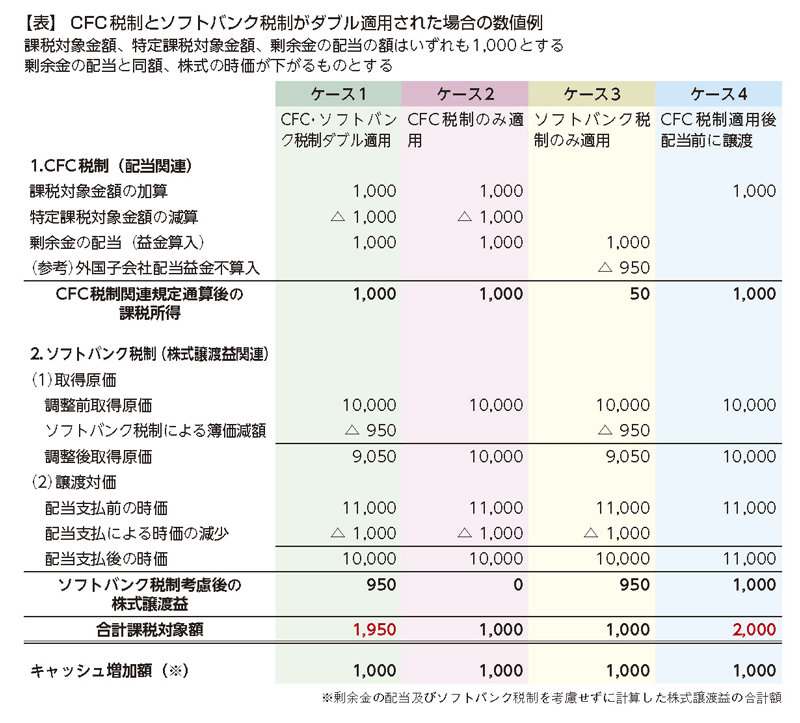
課税当局は状況承知しつつもコメント控える
そこで本誌が課税当局に対し二重課税が生じるのではないかとの疑問を投げかけてみたところ、「そのような状態になっている(調整する規定がない)ということは承知しているが、課税当局はあくまで法を執行する行政機関であるため、それを二重課税とみるのかどうか、また、法令上どのように措置すべきなのかということについてはコメントできない」との回答であった。また、CFC税制が適用された子会社株式を配当金の分配を受ける前に譲渡した場合も、理論上、キャッシュの増加額の2倍が課税対象となることから(【表】ケース4参照)、課税当局は、両税制が適用された場合に限った話ではないと認識しているようだが、この問題についても、同様に「コメントできない」とのことであった。
CFC税制とソフトバンク税制が両方とも適用されると、上記のような意味で二重課税が生じることになるが、納税者の担税力に即しているとは言い難い課税が生じ得ることから、企業や実務家からは、法令上何らかの調整措置を設けるべきではないかとの意見が挙がっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























