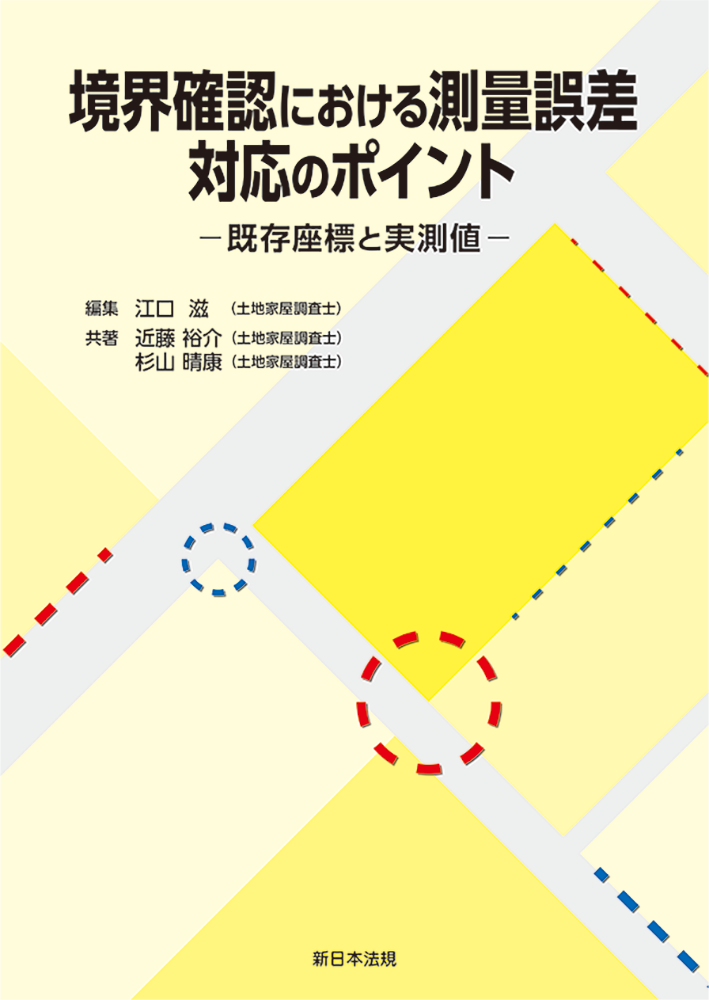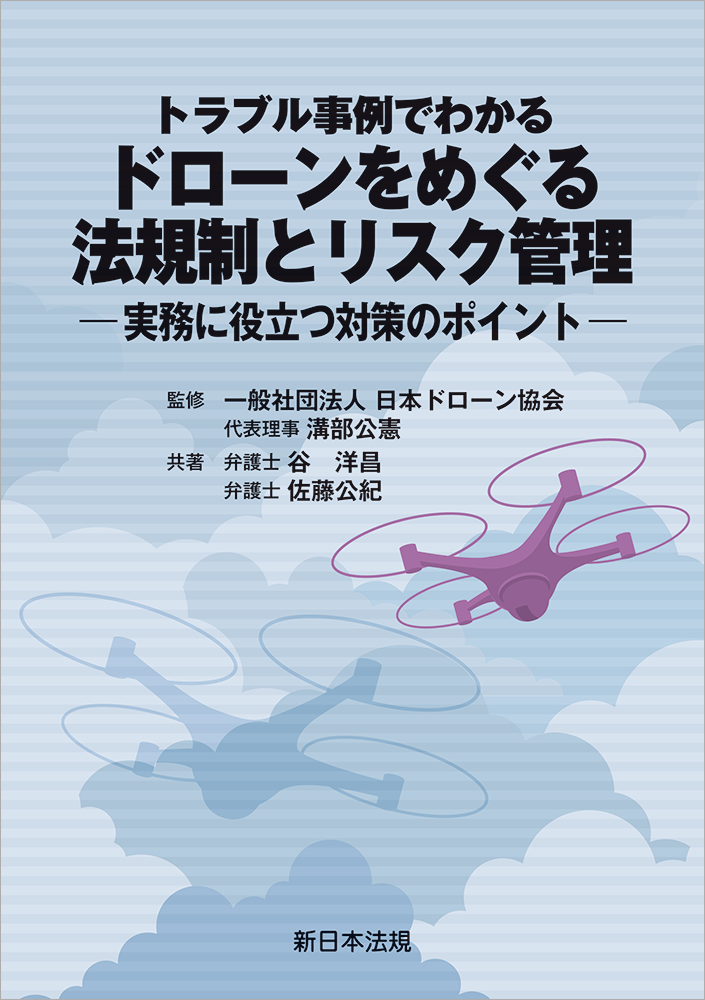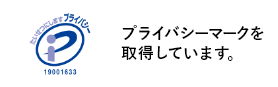解説記事2022年09月12日 未公開判決事例紹介 滞納借主からの債務免除で貸金業者に第二次納税義務(2022年9月12日号・№946)
未公開判決事例紹介
滞納借主からの債務免除で貸金業者に第二次納税義務
第二次納税義務を負わせない特段の事情なし
本誌932号40頁及び945号9頁で紹介した第二次納税義務納付告知処分取消請求事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する。
○借主から過払金返還債務の免除を受けた元貸金業者(原告)が、借主の滞納国税について第二次納税義務を有するか否かが争われた事件。東京地裁民事51部(岡田幸人裁判長)は令和4年5月17日、納付告知処分の取消しを求めた原告の請求を棄却した(令和2年(行ウ)第370号)。東京地裁は、本件債務免除には、「実質的にみて、当該無償譲渡等の処分により第三者に帰属することとなった経済的利益がなお滞納者に帰属しているものとして当該第三者に対して納税義務を課すことがかえって公平を失することとなるような特段の事情は認められない」との判断を下した。
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
I税務署長が平成31年1月16日付けで原告に対してした納税者Bの滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は、貸金業者であった原告が、訴外B(以下「本件滞納者」という。)との間で3つの基本契約に基づき金銭の貸付けと弁済を繰り返す継続的取引(以下「本件各取引」という。)を行い、その後、本件滞納者と本件各取引に係る和解契約(以下「本件和解契約」という。)を締結して過払金返還債務等の一部の免除を受けたところ、I税務署長(処分行政庁)から、本件滞納者は源泉所得税を滞納しており、本件和解契約に基づく本件滞納者による上記債務の免除は国税徴収法(令和3年法律第11号による改正前のもの。以下「徴収法」という。)39条所定の「債務の免除」に該当し、原告は上記滞納国税に係る第二次納税義務を負うとして、徴収法32条1項に基づく納付告知(以下「本件告知処分」という。)を受けたことから、被告を相手に、本件告知処分の取消しを求める事案である。
2 関係法令の定め
(1)滞納者(納税者でその納付すべき国税をその納付の期限までに納付しないものをいう〔徴収法2条9号〕。以下同じ。)の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(これらを併せて以下「無償譲渡等の処分」という。)に起因すると認められるときは、無償譲渡等の処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、無償譲渡等の処分により受けた利益が現に存する限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う(徴収法39条)。
(2)徴収法39条に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法2条5号に規定する法人(地方公共団体その他の公共法人〔法人税法別表第一〕をいう。)以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする(国税徴収法施行令14条1項)。
3 前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記証拠〔書証は特記しない限り枝番を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告(甲7、弁論の全趣旨)
原告は、貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」である。以下では、同改正の前後を問わず「貸金業法」という。)3条1項所定の登録を受けた貸金業者(貸金業法2条2項)であったが、平成21年6月27日以降は一切の融資業務を終了し、平成28年8月、貸金業法所定の登録を更新しなかった(なお、原告の商号は、平成10年12月1日に「□□□□株式会社」から「□□□□ファイナンス株式会社」に変更された後、平成15年1月1日に「A株式会社」に変更され、更に平成20年11月28日に組織変更に伴い現商号に変更されている。)。
(2)原告と本件滞納者との間の本件各取引(甲1〜3、弁論の全趣旨)
ア 原告と本件滞納者は、平成12年8月11日付けで、「極度額借入契約書」(甲1)を取り交わして金銭消費貸借に係る基本契約(以下「本件基本契約1」という。)を締結し、以後同年9月12日から平成15年9月16日までの間、本件基本契約1に基づき、原告による金銭の貸付けと本件滞納者による返済を繰り返す一連の取引(以下「本件取引1」と総称する。)をした。
イ 原告と本件滞納者は、平成15年10月3日付けで、「極度額借入契約書」(甲2)を取り交わして金銭消費貸借に係る基本契約(以下「本件基本契約2」という。)を締結し、以後同日から平成18年5月17日までの間、本件基本契約2に基づき、原告による金銭の貸付けと本件滞納者による返済を繰り返す一連の取引(以下「本件取引2」と総称する。)をした。
ウ 原告と本件滞納者は、平成18年6月7日付けで、「施行規則第16条3項に基づく17条1項書面の写し」と題する書面(甲3)を取り交わして金銭消費貸借に係る基本契約(以下「本件基本契約3」といい、本件基本契約1及び2と併せて「本件各基本契約」という。)を締結し、以後同月8日から平成22年11月15日(以下「本件最終返済日」といい、本件基本契約1に基づく最初の借入日である平成12年9月12日から本件最終返済日までを「本件取引期間」という。)までの間、本件基本契約3に基づき、原告による金銭の貸付けと本件滞納者による返済を繰り返す一連の取引(以下「本件取引3」と総称する。)をした。
エ 本件各取引における本件各基本契約に基づく原告による貸付け及び本件滞納者による返済の状況は、別紙2「利息制限法に基づく法定金利計算書」の「年月日」、「借入」及び「返済」の各欄(ただし、本件取引期間に係る部分に限る。)記載のとおり(「借入」欄の記載は原告による貸付額を、「返済」欄の記載は本件滞納者による返済額をそれぞれ意味する。)である。
(3)本件各基本契約の契約内容等(甲1〜3、31、32)
ア 本件各基本契約において定められた借入利率及び遅延利率は、本件基本契約1につきいずれも29.20%、本件基本契約2につきいずれも29.20%、本件基本契約3につきそれぞれ12.88%及び13.88%である(いずれも年365日の日割計算)。また、本件各基本契約における約定返済日はいずれも毎月15日であり、返済金は、いずれも、未払利息、遅延損害金、利息、元金の順に充当するものとされている。
イ 本件基本契約1においては、借主は、契約に基づく債務の支払を1回又は一部でも怠る等の事由が発生し、原告が必要と認める場合は通知・催告がなくとも原告に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、残元金に未払利息・遅延損害金・利息を付して直ちに支払うものとする旨の条項(以下「本件期限の利益喪失条項1」という。)が定められている。
本件基本契約2においては、借主は、契約に基づく債務の支払を1回又は一部でも怠る等の事由が発生した場合には、原告からの通知・催告がなくとも原告に対する一切の債務について期限の利益を失い、残元金に未払利息・遅延損害金・利息を付して直ちに支払わなければならない旨の条項が定められている。
本件基本契約3においては、借主は、いずれかの返済期日において返済金額の一部又は全部の支払を怠った場合には、原告からの通知・催告がなくとも原告に対する一切の債務について期限の利益を失い、残元金に未払利息、遅延損害金及び利息を付して直ちに支払うものとするが、借主が上記条項に基づき期限の利益を喪失した場合であっても、借主が、その後、当該返済金額中の未払金及び遅延損害金(ただし、未払利息及び遅延損害金については、利息制限法所定の利率を超えない範囲で支払えば足りるものとする。)を支払った場合には、当該支払日の翌日から、再度、期限の利益が付与されるものとする旨の条項が定められている。
(4)本件和解契約の締結等(甲4、弁論の全趣旨)
ア 原告は、本件滞納者との間で、平成29年1月24日付けで「和解書兼確認書」(甲4。以下「本件和解契約書」という。)を取り交わし、本件各取引に係る和解契約(本件和解契約)を締結した。
本件和解契約書には、①本件滞納者は、本件各取引から過払金が発生しているものと認識の上、平成28年12月21日、原告との間で過払金等の有無やその返還に関する相談をしたところ、原告からは法律の専門家へ相談することや本件滞納者自身で訴訟提起することもできる旨の助言を受けたが、本件滞納者は弁護士を代理人とせずに解決することを決するに至ったこと、②原告と本件滞納者は、原告が本件滞納者に本件の解決金として20万円(以下「本件解決金」という。)を支払うことにより、当事者間に現存する全ての争いや主張を互譲し、清算することを選択し、和解に至ったこと(以上4項)、③原告は平成29年2月8日限り、本件解決金を本件滞納者が指定する口座に振り込んで支払うこと(7項)、④本件滞納者は、原告が本件解決金を遅滞なく支払ったときは、原告に対するその余の請求を放棄すること(9項。この条項に基づく債務の免除を以下「本件債務免除」という。)などが記載されている。
イ 原告は、平成29年1月27日(以下「本件解決金支払日」という。)、本件滞納者に対し、本件和解契約に基づき本件解決金を支払った。
(5)本件滞納者の滞納状況等
ア 本件滞納者は、平成31年1月16日(以下「本件処分日」という。)当時、法定納期限を経過した平成16年度の源泉所得税を滞納しており、被告は、本件処分日時点で、本件滞納者に対し、別紙3租税債権目録記載のとおりの国税債権(総額249万0900円。以下「本件滞納国税」という。)を有していた。なお、本件滞納国税に係る法定納期限のうち、最も遅いものは平成16年6月10日である。(乙1)
イ 本件滞納者は、本件和解契約の締結後、本件処分日までの間において、本件滞納国税の総額を徴収するに足りる財産を取得したことはなく、本件処分日の現況においても、かかる財産を有していなかった(乙8、弁論の全趣旨)。
(6)本件告知処分(甲6、弁論の全趣旨)
本件滞納国税に係る納税地を所轄するI税務署長は、本件処分日付けで、原告に対し、原告は91万6080円の限度で本件滞納国税に係る第二次納税義務を負う旨を納付通知書(甲6)により告知した(本件告知処分)。
なお、上記納付通知書には、処分理由として、本件各取引を利息制限法所定の法定利率に引き直して計算をすると、本件最終返済日(平成22年11月15日)の時点で、84万1934円の過払金及び1万3507円の利息(以下、過払金とこれに対する民法704条所定の利息〔以下「過払利息」という。〕を併せて「過払金等」といい、過払金等に係る返還又は支払請求権及び返還又は支払債務をそれぞれ「過払金債権」及び「過払金債務」という。)が発生しているところ、本件滞納者は、原告との間で本件和解契約を締結することにより、上記過払金にこれに対する本件和解契約締結日(平成29年1月24日)までの過払利息27万4146円を加算した合計111万6080円から本件解決金20万円を差し引いた91万6080円について債務免除を行ったと認められるので、原告は、徴収法39条の規定により、上記債務の免除によって受けた利益が現に存する額を限度として本件滞納国税について第二次納税義務を負うこととなる旨が記載されている。
(7)本件訴訟に至る経緯
ア 原告は、平成31年2月5日、本件告知処分に係る第二次納税義務者として納付すべき91万6080円を納付した(争いがない)。
イ 原告は、平成31年4月12日、本件告知処分の全部の取消しを求める審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、令和2年4月1日、同審査請求を棄却する旨の裁決をした(甲7)。
ウ 原告は、令和2年9月18日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
4 争点
本件の争点は、本件告知処分の適法性であるところ、具体的には、①本件債務免除の額(本件解決金支払日時点で原告が本件滞納者に負担していた過払金債務〔以下「本件過払金債務」といい、これに対応する債権を「本件過払金債権」という。〕の額)及び②本件債務免除が徴収法39条所定の「債務の免除」に該当するか、という2点である。なお、上記①に関しては、 本件各取引は、「事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」(最高裁平成18年(受)第2268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号28頁)に当たることから、利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)所定の制限利率による引き直し計算は、本件各取引全部を通じて一体として行うべきものであること及び
本件各取引は、「事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」(最高裁平成18年(受)第2268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号28頁)に当たることから、利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)所定の制限利率による引き直し計算は、本件各取引全部を通じて一体として行うべきものであること及び 原告が過払金の受領につき悪意の受益者であることは当事者間に争いがなく(第1回口頭弁論調書参照)、本件滞納者が本件取引1及び2において約定返済日を徒過して返済した場合における遅延損害金の発生の有無及びその範囲のみが争われている。
原告が過払金の受領につき悪意の受益者であることは当事者間に争いがなく(第1回口頭弁論調書参照)、本件滞納者が本件取引1及び2において約定返済日を徒過して返済した場合における遅延損害金の発生の有無及びその範囲のみが争われている。
5 当事者の主張
争点についての当事者の主張の要旨は、別紙4記載のとおりである。なお、同別紙において定義した略称は本文においても用いることがある。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(本件債務免除の額〔本件過払金債務の額〕)について
(1)本件各取引における期限の利益の喪失の有無
ア 前記前提事実(2)エ、(3)アによれば、本件各基本契約については、いずれも返済日が毎月15日とされていたところ、本件滞納者は、①本件取引1については、平成12年10月15日の約定返済日に返済しなかったことにより初めて遅滞に陥り、同日から5日遅れた同月20日に約定の分割金を支払ったが、その後も約定返済日から数日遅れて約定の分割金を支払うことが複数回あったこと、②本件取引2については、平成15年11月15日の約定返済日に返済しなかったことにより初めて遅滞に陥り、同日から2日遅れた同月17日の約定の分割金を支払ったが、その後も約定返済日から数日遅れて約定の分割金を支払うことが複数回あったこと、③本件取引3については、平成18年6月15日の約定返済日に返済しなかったことにより初めて遅滞に陥り、同日から1日遅れた同月16日に約定分割金を支払ったが、その後も約定返済日から数日遅れて約定の分割金を支払うことが複数回あったこと、以上のとおり認められる。
そして、本件各基本契約においては、本件滞納者が契約に基づく債務の支払を1回又は一部でも怠る等の事由が発生した場合には、原告からの通知・催告がなくとも原告に対する一切の債務について期限の利益を失うことが合意されていたから(前提事実(3)イ)、本件滞納者は、上記各約定返済日に分割金の支払を懈怠したことにより、当該約定返済日の経過をもってその期限の利益を失ったものと認められる。
イ この点、被告は、原告は本件滞納者が期限の利益を喪失していないものとして扱っていたから、本件滞納者は本件各取引において期限の利益を喪失していなかった旨主張する。
しかしながら、上記のとおり、本件各基本契約においては、本件滞納者は債務の支払を怠る事実の発生により当然に本件各基本契約に基づく期限の利益を失うこととされていたのであり、このことは、原告において本件滞納者が期限の利益を喪失していないものとして扱っていたか否かによって左右されるものではない。したがって、被告の上記主張は採用することができない。
ウ 被告は、本件基本契約1については、原告が必要と認めた場合のみ、本件滞納者の期限の利益を喪失させることができるものとなっているところ、原告は「必要と認める場合」に該当しないとして、本件滞納者の期限の利益を喪失させなかったものと認められる旨主張する。
しかしながら、本件期限の利益喪失条項1においては、本件基本契約1に基づく債務の支払を1回又は一部でも怠る等の事由が発生した場合には、本件滞納者は原告による通知・催告がなくとも当然に期限の利益を失うものとされていたものである(前提事実(3)イ)。そして、本件期限の利益喪失条項1には、原告が「必要と認める場合」は当然の期限の利益を失う旨の定めがあるところ、原告による通知・催告がないにもかかわらず原告の意向のみによって期限の利益の喪失の有無が左右されるとすれば、借主である顧客にとって期限の利益の喪失の有無や自身が原告に対して負担している債務の内容を把握することができないこととなり、借主が極めて不安定な立場に置かれることとなる。しかしながら、本件期限の利益喪失条項1が、借主をそのような不安定な立場に置くことを想定しているものとは解し難いのであって、本件期限の利益喪失条項1における上記文言は、本件基本契約1に基づく債務の支払の1回又は一部の遅滞によって当然に期限の利益を失うことを前提としつつ、この場合においても原告が期限の利益の喪失を宥恕し、本件滞納者に期限の利益を再度付与することがあり得ることを注意的に規定したものと解するのが相当である。
したがって、本件取引1についても、本件滞納者が平成12年10月15日の約定返済日に分割金の支払を懈怠したことにより、同日の経過によってその期限の利益を喪失したものと認めるのが相当であり、この点についての被告の主張を採用することはできない。
(2)期限の利益の再度付与の有無について
ア 上記(1)のとおり、本件滞納者は、本件各取引のいずれについても、約定返済日に約定の分割金の支払を懈怠したことにより期限の利益を喪失したものであるが、その後も本件各基本契約に基づく分割金の返済を繰り返すとともに、原告から新たな貸付けを受けていたものである(前提事実(2)エ)。
この点、本件取引3については、本件基本契約3において、借主(本件滞納者)がいずれかの返済期日において返済金額の一部又は全部の支払を怠った場合であっても、借主がその後当該返済金額中の未払金及び遅延損害金を支払った場合には、当該支払日の翌日から再度期限の利益が付与されるものとする旨の定めがあることから(前提事実(3)イ)、本件滞納者は、約定返済日に分割金の支払を懈怠することにより期限の利益を喪失した場合であっても、その後に約定の分割金を支払った際に期限の利益を再度付与されていたものと認められる。
イ 他方、本件基本契約1及び2については、本件基本契約3とは異なり、期限の利益の再度付与に関する規定は置かれていない(前提事実(3)イ)。
もっとも、前記前提事実、乙5の1・答17及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件取引1及び2において、本件滞納者が約定の返済期日に分割金の支払を解怠して期限の利益を喪失した後も、元利金の一括弁済や遅延損害金の支払を求めたことはなく、本件滞納者からの分割金の支払を受領し続けるとともに、新たな貸付けを繰り返していたことが認められる。
また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額等を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならないものとされているから(貸金業法18条1項4号)、貸金業者であった原告も、本件各取引において本件滞納者から分割金の支払を受けた際には、その都度、直ちに、貸金業法18条1項所定の書面に相当する書面として、受領金額及びその充当内容等を記載した書面(以下「領収書兼利用明細書」という。)を本件滞納者に交付していたものと認められる(乙5の1・答14参照)。
しかるところ、原告が、本件滞納者との間の取引(本件各取引)について貸金業法19条所定の帳簿として作成している貸付元帳(本件貸付元帳。乙20)には、本件取引1及び2について、本件滞納者が約定の返済日に分割金の支払を懈怠した場合であっても、その後に分割金の支払があったときは、当該支払のあった日を処理日として、「遅延日数」及び「遅延利息」の欄はいずれも「0」と表示されて「通常日数」及び「通常利息」のみが計上されるとともに、当該分割金が通常利息及び貸付元金に充当された旨や次回期日が翌月15日である旨が記載されており、原告は、本件滞納者が約定返済日に分割金の支払を懈怠した場合であっても、後に約定の分割金を支払った場合には、少なくとも当該支払時以降、本件滞納者が期限の利益を喪失していないものとして取り扱っていたものと認められる。このような本件貸付元帳の記載内容及び原告における取扱いに照らせば、本件取引1及び2において、本件滞納者が約定の返済日に遅れて分割金を支払った際に原告が本件滞納者に交付した領収書兼利用明細書にも、遅延損害金が発生していることは記載されていない一方、当該分割金が利息及び貸付元金に充当された旨が記載されていたものと推認することができる。そして、原告がこのような記載内容の領収書兼利用明細書を本件滞納者に交付する行為は、本件基本契約1及び2において返済金はいずれも未払利息、遅延損害金、利息、元金の順に充当するものとされていること(前提事実(3)ア)も併せ考慮すると、本件取引1及び2において、遅延損害金が発生していない、すなわち、本件滞納者が期限の利益を喪失していないとの原告の認識を外部(本件滞納者)に表示するものであるということができる。
ウ 上記イの諸事情、殊に、本件滞納者が約定の返済日に分割金の支払を懈怠した後も原告は元利金の一括弁済や遅延損害金の支払を求めなかったのみならず、本件滞納者がその後に分割金の支払をする際に、遅延損害金の発生が記載されておらず、当該分割金が利息、及び貸付元金に充当された旨記載された領収書兼利用明細書を本件滞納者に交付していたものと推認されることに照らせば、本件取引1及び2において、本件滞納者が約定の返済日に分割金の支払を懈怠して期限の利益を喪失した場合であっても、本件滞納者がその後に約定の分割金を支払った時点で、期限の利益を再度付与する旨の原告の本件滞納者に対する黙示の意思表示があったものと認めるのが相当であり、これに反する原告の主張は採用することができない。
(3)小括
ア 上記(1)、(2)によれば、本件各取引のいずれについても、本件滞納者は、約定の返済日に分割金の支払を懈怠したことにより期限の利益を一旦喪失した場合であっても、その後約定の分割金を支払った時点で期限の利益を再度付与されているものと認められるから、本件各取引について利息制限法所定の制限利率による引き直し計算をするに当たっては、約定の返済日から支払が遅延した期間についてのみ遅延損害金が発生したものとして遅延利率(利息制限法4条1項所定の利率。ただし、約定の遅延利率がこれを下回る場合には、当該利率。)を用い、その余の期間については、通常利率(利息制限法1条所定の利率。ただし、約定の利率がこれを下回る場合には、当該利率。)を用いて計算するのが相当である。
イ 上記アの方法に従って本件各取引について引き直し計算をすると、本件滞納者が平成29年1月27日(本件解決金支払日)時点において原告に対して有していた本件過払金債権の額は、別紙2のとおり、128万6782円(同日時点における過払金96万8478円に、同月24日時点における過払利息累計額31万7906円及び同月25日から同月27日までの過払利息398円を加えた額)となる。
ウ そして、本件和解契約は、原告が本件滞納者に本件解決金20万円を平成29年2月8日までに支払うことを停止条件として、本件滞納者が原告に対して有するその余の請求権を放棄することを内容とするものであるところ(前提事実(4)ア)、原告は、平成29年1月27日(本件解決金支払日)に本件解決金を本件滞納者に支払っているから(前提事実(4)イ)、原告は、同日、本件滞納者から、上記イの128万6782円から本件解決金20万円を控除した、108万6782円の過払金債務の免除を受けたものと認められる(本件債務免除)。
2 争点②(本件債務免除が徴収法39条所定の「債務の免除」に該当するか)について
(1)認定事実
前記前提事実に加え、証拠(甲5、乙2、3、4、5の1)及び弁論の全趣旨によれば、本件和解契約の締結に至る経緯等として、次の各事実が認められる。
ア 本件滞納者が本件最終返済日に原告に分割金を支払ったのを最後に原告と本件滞納者との間で取引はなく、同日時点で100万円近い過払金等が生じていたものの、以後、過払金債権の存否等を含め、原告と本件滞納者との間で本件各取引についての交渉や協議等は行われなかった。
イ I税務署長は、平成28年12月13日、原告に対し、本件照会書を送付し、徴収法141条に基づき、原告と本件滞納者との間の取引について照会した。
ウ 原告は、本店に送付された本件照会書を実際の対応業務を行っている大阪市所在のリーガルサービスセンターに転送し、同センターは、平成28年12月20日、これを受け付けた。
エ 原告は、平成28年12月21日、本件滞納者に架電し、本件各取引につき過払金が生じている可能性があることを伝えた上で、支払を希望する過払金の額を尋ねたところ、本件滞納者は20万円の支払を受ける内容での和解を希望する旨述べた。
オ 原告は、平成28年12月22日から平成29年1月4日までの間、複数回にわたり本件滞納者に架電を試みたが、本件滞納者と直接話をすることができなかった。
カ 原告は、平成29年1月6日、本件滞納者に架電し、本件滞納者の希望どおり解決金20万円を支払う内容で和解契約を締結し、解決金の支払期限を同年2月8日とすることを伝えた。
キ 原告は、平成29年1月16日、本件滞納者に宛てて、本件滞納者において記入すべき部分を空欄とした本件和解契約書を発送した。なお、原告は、本件和解契約書に原告と本件滞納者との間の本件各取引の内容について記載した取引明細書を添付して本件滞納者に送付したものの、本件和解契約書にはその時点において本件各取引から生じている過払金等の額は記載されておらず、上記エ及びカの電話での話合いの際にも、原告が本件滞納者に本件各取引から生じている過払金等の額を伝えたことはない。
ク 原告は、平成29年1月16日付けで、本件照会書に対するI税務署長宛ての回答書を作成し、同回答書は、同月18日、I税務署に到着した。なお、同回答書に添付された取引明細書は平成28年12月20日付けのものである。
ケ 本件滞納者は、上記キの本件和解契約書の本件滞納者記載欄に署名押印等した上で原告に宛てて返送し、原告は、平成29年1月24日、これを受領した。
コ 原告は、平成29年1月27日、本件解決金(20万円)を本件滞納者の銀行口座に振り込む方法により支払った。
(2)判断の枠組み
ア 徴収法の定める第二次納税義務制度は、主たる納税義務が申告又は決定若しくは更正等により具体的に確定したことを前提として、その確定した税額につき本来の納税義務者の財産に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合において、形式的には第三者に財産が帰属していても、実質的には滞納者にその財産が帰属していると認めても公平を失しないようなときは、形式的な権利の帰属自体を否認することなく、その形式的に権利が帰属している者に対して補充的に納税義務を負担させることにより、租税徴収と課税の公平の確保を図ることをその趣旨とするものである(最高裁昭和48年(行ツ)第112号同50年8月27日第二小法廷判決・民集29巻7号1226頁参照)。
イ そして、徴収法39条は、滞納者が行った無償譲渡等の処分の相手方を第二次納税義務者としているところ、これは、滞納者が行う無償譲渡等の処分が、租税債務の引当てとなる滞納者の積極財産を減少させるものであるとともに、その相手方に一方的に経済的利益を生じさせるものであることに鑑み、このような無償譲渡等の相手方については、それだけで、通常であれば本来の納税義務者である滞納者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しないような特別な関係にあるといえることから、これらの者に第二次納税義務を課すこととしたものと解される(最高裁平成16年(行ヒ)第275号同18年1月19日第一小法廷判決・民集60巻1号65頁参照)。このような同条の趣旨からすれば、同条にいう「債務の免除」は、民法519条所定の債務の免除に限られるものではなく、契約による債務の免除等、滞納者がその意思によりその有する債権を対価なく消滅させる行為を広く含むものと解すべきである。
ウ 他方、上記アにおいて説示した第二次納税義務の趣旨に照らせば、形式的には徴収法39条所定の無償譲渡等の処分に該当する行為であっても、当該無償譲渡等の処分により第三者に帰属することとなった経済的利益がなお滞納者に帰属しているものとして当該第三者に対して納税義務を課すことが、その実質に照らし、かえって公平を失することとなるような特段の事情がある場合には、徴収法39条所定の無償譲渡等の処分には該当しないものというべきである。これを債務の免除についていえば、形式的には債務の免除に該当する場合であっても、当該債務の免除に至る経緯やその内容等に照らし、当該債務の免除が、実質的には何らかの給付その他の経済的利益の移転との対価関係を有するものと認められる場合や、当該免除された債務に係る債権が、客観的にみてその実質において無価値であると認められる場合等が、このような特段の事情のある場合に当たるものと解される。他方、当該債務の免除が、当該滞納者又はその相手方である当該第三者にとって単に経営上又は経済的に合理的であるというのみでは、上記説示したところに照らし、上記特段の事情があるということはできないものというべきである。
(3)検討
ア 上記の見地からみると、本件債務免除は、本件和解契約に基づき、原告が本件滞納者に所定の期限までに本件解決金(20万円)を支払うことを停止条件として、本件滞納者が原告に対して有するその余の債権を放棄し、これにより原告が当該債権に係る債務の免除を受けるというものであるから、契約による債務の免除として、その外形から、徴収法39条1項所定の「債務の免除」に該当することは明らかである。
イ しかるところ、前記(1)において認定した本件和解契約及びこれに基づく本件債務免除に至る経緯に照らし、本件債務免除が、実質的に対価性を有するものであるとは認められない(本件滞納者が本件債務免除によって原告から何らかの対価的利益を受けたものと認めるに足りる証拠はなく、むしろ、乙5の1・答31によれば、本件滞納者は、本件和解契約後に本件過払金債権の概算額を処分行政庁の職員から知らされてもったいないと思ったが、過払金があることを知らなかったし、しょうがなかった旨述べていたことが認められる。)し、本件和解契約締結日ないし本件解決金支払日の時点において、本件債務免除に係る債権(本件過払金債権のうち、本件解決金相当額を控除したもの。)が、客観的にみて実質において無価値であったことを認めるに足りる証拠もなく、他に、実質的にみて、本件債務免除により消滅した上記債権に係る経済的利益がなお本件滞納者に帰属しているものとして、本件債務免除の相手方である原告に対して納税義務を課すことがかえって公平を失することとなるような特段の事情が存するものとも認められない。
ウ 以上によれば、本件債務免除は、徴収法39条所定の「債務の免除」に該当するものと認められる。
(4)原告の主張について
ア 原告は、原告においては福井地裁判決を重く受け止め、顧客の過払金に関する問い合わせがあった場合には速やかに顧客にコンタクトをとり、過払問題についての認識を確認し、顧客と原告との間の取引において過払金が発生している可能性があることを伝え、顧客の希望を聴取し、できる限り早期に和解による解決を目指すように業務手続を変えたものであり、本件においても、このような業務手続に従って本件和解契約を締結したものであるから、本件和解契約の締結には「合理的な理由」がある旨主張する。
しかしながら、福井地裁判決は、既に貸金業者と借主との間の金銭消費貸借が具体的に問題となり、過払金の発生それ自体を否定する具体的根拠のない状況の下、それを容易に知り得る貸金業者が、なお返済請求をし、返済金の受領をしてきたことについて、社会通念に照らして著しく相当性を欠くものとして不法行為責任を認めたものにすぎず、本件のように、貸金業者と借主との間の取引が終了した後交渉のないまま長期間が経過している場合において、第三者から当該借主との間の取引について照会を受けた貸金業者が、直ちに当該借主との間で過払金に係る和解契約を締結すべきものとする規範までがここから導かれるものとは到底いうことができず、原告が、福井地裁判決の趣旨を尊重して本件和解契約を締結したものとはにわかには認め難い。
むしろ、前記認定事実によれば、原告は、平成22年11月15日に本件滞納者から分割金の支払を受けたのを最後に、本件滞納者とは交渉がなかったところ、平成28年12月にI税務署長から本件滞納者との間の取引についての照会を受けるや、直ちに本件滞納者に連絡を取り、その時点で生じていた具体的な過払金等の額を伝えることなく和解契約を締結することを持ち掛け、本件滞納者との協議が整った後、本件和解契約書を本件滞納者に発送するのと同時にI税務署長に対して上記照会に対する回答書を送付して本件滞納者との間の取引内容を開示し、その後、本件滞納者からその署名押印のある本件和解契約書の返送を受けた後、速やかに本件解決金を本件滞納者に支払い、これにより、本件解決金の額を大きく上回る110万円近い過払金債務の免除を受けたことが認められ、このような経緯に照らせば、原告は、本件滞納者の本件滞納国税に係る滞納処分として、本件過払金債権が差し押さえられ(徴収法47条1項、62条1項参照)、その全額が取り立てられること(徴収法67条1項参照)を回避する目的で、本件滞納者との間で本件債務免除に係る条項を含む本件和解契約を締結するに至ったことがうかがわれるところであり、原告の上記主張はその前提を欠くものというべきである。
また、上記の点をおいても、福井地裁判決は、借主において貸金業者に対する過払金債権を放棄し、その債務を免除することを求めるものではないから、仮に、本件和解契約の締結に至る経緯において福井地裁判決の存在及びその内容が考慮されていたとしても、これにより本件債務免除自体に合理的な理由があるということになるものではない。
そもそも、前記(2)ウのとおり、形式的には徴収法39条の無償譲渡等の処分に該当する行為につき、同条所定の無償譲渡等の処分該当性を否定すべき特段の事情があると認められるか否かについては、実質的にみて、当該無償譲渡等の処分により第三者に帰属することとなった経済的利益がなお滞納者に帰属しているものとして当該第三者に対して納税義務を課すことがかえって公平を失するものといえるか否かという観点から検討すべきところ、本件債務免除については、これが実質的には原告から本件滞納者に対する何らかの経済的利益の移転と対価関係を有するものとは認められないし、免除に係る本件過払金債権が客観的にみて実質において無価値であるとも認められず、上記の観点に照らして上記特段の事情があるとは認められないことは前記(3)イのとおりである。したがって、仮に、本件和解契約を締結し、本件債務免除を受けることが、原告の経営上ないし経済的な観点からみて必要性及び合理性を有するものであるとしても、そのことによって、上記特段の事情があるものとして徴収法39条所定の「債務の免除」該当性が否定されることとなるものではないから、この点についての原告の主張は採用することができない。
イ 原告は、引き直し計算について「正解」がなかった当時の裁判例の状況に鑑みれば、原告が本件和解契約を締結したことには「合理的な理由」が認められる旨主張するが、これも、本件和解契約の締結が原告にとって経済的合理性を有することをいうにとどまり、上記アにおいて説示したところに照らし、上記の点が前記(2)ウの特段の事情を基礎付けるものということはできないから、原告の上記主張は採用することができない。
ウ 原告は、本件和解契約の締結は本件滞納者にとっても「合理的な理由」があった旨主張するが、原告が指摘する本件滞納者側の事情も、本件和解契約の締結が本件滞納者にとって経済的に合理的なものであることを示すものにすぎず、上記アにおいて説示したところに照らし、前記(2)ウの特段の事情を基礎付けるものとはいえない。また、原告が過払金債権の正味の現在価値として主張するところも、原告が過払金返還請求を受けた事案全体における平均的な過払金等の支払割合を指摘するものにとどまり、本件和解契約締結ないし本件解決金支払日の時点において本件過払金債権自体が客観的にみて実質において無価値であったことを裏付けるものではなく、上記の点をもって前記(2)ウの特段の事情があるということもできないから、原告の上記主張は採用することができない。
エ 原告は、過払金債務は、企業会計上偶発債務とされ、法人税法上も「債務の確定しないもの」として損金計上できないものとされており、このような過払金債務に係る「合理的な理由」のある和解については、会計処理の一貫性や法人税法との整合性等の観点から、徴収法39条の「債務の免除」の射程外とすべきである旨を主張する。
しかしながら、本件過払金債権及びこれに対応する本件過払金債務は、客観的には、本件和解契約の締結ないし本件解決金の支払の時点においてその金額が一義的に定まるものとして存在していたことは、争点①において説示したとおりであり、このことは、本件過払金債務の企業会計上及び法人税法上の取扱いによって左右されるものではない。そうである以上、本件過払金債権は、これに対応して原告が負う本件過払金債務が、企業会計上偶発債務とされるものか否かや、法人税法上債務確定基準を満たさないものとして損金の額に算入することができないものかどうかにかかわらず、被告が本件滞納者に対して有する租税債権(本件滞納国税)の引当てとなるべき本件滞納者の積極財産を構成し、本件滞納国税に係る滞納処分としてこれが差し押さえられた場合には、原告は、その全額の取立てに応じざるを得ないものであるし(徴収法67条1項)、この場合には、原告の主張によっても、本件過払金債務は会計上確定債務として認識されることとなるとともに、法人税法上も債務確定基準を満たすこととなるものと解されるから、仮に、本件過払金債務が、本件和解契約の締結前においては、企業会計上偶発債務として引当金のみが計上されるべきものであり、法人税法上も「債務の確定しないもの」として損金の額に算入することができないものであったとしても、これを免除することが徴収法39条所定の「債務の免除」に該当するものとして第二次納税義務の基礎とすることが、会計処理の一貫性や課税上の公平性・一貫性を欠くものとして不合理であるということはできない。
したがって、この点についての原告の主張は採用することができない。
3 本件告知処分の適法性について
(1)徴収法39条によれば、同条所定の第二次納税義務が成立するためには、①滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること、②滞納者がその財産につき、無償譲渡等の処分をしたこと、③無償譲渡等の処分が、当該国税の法定納期限の1年前の日以後にされたものであること、④徴収不足が、無償譲渡等の処分に基因すること、⑤無償譲渡等の処分により受けた利益が現存することの各要件を充足することを要するものと解される。
(2)そこで検討すると、本件滞納者は、本件処分日の現況において、本件滞納国税の総額を徴収するに足りる財産を有していなかったから(前提事実(5)イ)、同日時点において上記(1)①の要件を満たしていたものと認められ(上記(1)①の要件の意義につき、最高裁平成26年(行ヒ)第71号同27年11月6日第二小法廷判決・民集69巻7号1796頁参照)、争点①及び②において認定説示したところによれば、本件滞納者は、本件和解契約により、原告に対する本件過払金債権128万6782円から本件解決金を控除した108万6782円の債権を放棄し、当該債権に係る原告の債務を免除したものであり、これが徴収法39条の「債務の免除」に該当するものと認められるから、上記(1)②の要件も満たすものと認められる。また、本件和解契約に基づき上記債務の免除がされたのは、当該債務免除に係る停止条件(本件解決金の支払)が成就した日である本件解決金支払日であるところ、本件滞納国税に係る法定納期限のうち、最も遅いものは平成16年6月10日であるから(前提事実(5)ア)、上記(1)③の要件も満たす上、本件滞納者は、本件和解契約の締結後、本件処分日までの間において、本件滞納国税の全額を徴収することができる財産を取得していないこと(前提事実(5)イ)からすると、被告は滞納処分により本件過払金債権の全額を差し押さえることによってしか本件滞納国税を徴収することができなかったところ、本件債務免除によってそれが不可能となったものいえるから、上記(1)④の要件も満たすものと認められる。さらに、争点①及び②において説示したところによれば、原告は、本件解決金支払日において、本件債務免除により108万6782円の利益を受けたものと認められるところ、この利益がその後消滅したこともうかがわれないから、上記利益は本件処分日においても現に存するものと認められ、上記(1)⑤の要件も満たすものと認められる。
(3)上記(2)によれば、原告は、本件処分日において、本件滞納者の本件滞納国税につき108万6782円の限度で徴収法39条に基づく第二次納税義務を負っていたものと認められるところ、本件告知処分によりその納付を告知した税額はこれを下回っているから、本件告知処分は適法である。
4 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
裁判長裁判官 岡田幸人
裁判官 溝渕章展
裁判官釜村健太は、異動のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 岡田幸人
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -