解説記事2022年10月03日 第2特集 暦年課税は廃止せず、相続時精算課税の見直しが課題(2022年10月3日号・№948)
第2特集
相続税・贈与税の見直しに着手、年内に報告書を取りまとめへ
暦年課税は廃止せず、相続時精算課税の見直しが課題
政府税制調査会(会長:中里実東京大学名誉教授)は9月16日、資産移転の時期に中立的な税制の構築に向けた相続税・贈与税のあり方に関して、「相続税・贈与税に関する専門家会合」(座長:増井良啓東京大学大学院法学政治学研究科教授)を設置し、議論をスタートすることを明らかにした。中里会長は暦年課税の廃止は行わず、当面の課題として利用状況が低迷している相続時精算課税制度の利便性向上への見直しなどを挙げた。また、現行の相続税の課税方式について、法定相続分課税方式から諸外国のような遺産課税方式や、遺産取得課税方式への移行といった見直しは中期的な検討課題であるとしている。専門家会合では、早ければ11月上旬にも報告書を取りまとめる予定。時間が限られるなか、今回は、相続税・贈与税の抜本的な見直しまでには至らないようだ。
2年前の総会では暦年課税を廃止すべきとの意見が相次ぐも
資産移転の時期に中立的な税制の構築に向けた相続税・贈与税のあり方については、政府税制調査会が令和元年9月26日に取りまとめた「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」において、「資産課税が適切な再分配機能を果たしていくべく、そのあり方を不断に検討していく必要がある。」と明記されたことを受け、令和2年11月13日開催の政府税制調査会の総会において専門家会合を設置することが決められていた。
当時の総会では、被相続人の高齢化が進んだことにより老老相続が増加しており、相続による若年世代への資産移転が進みにくい状況にあることや、富裕層による節税策として連年贈与が増加している状況などについて説明が行われており、これを踏まえ、資産の移転の時期に関係なく、納税義務者にとって生前贈与と相続を通じた資産の総額に係る税負担が一定になるようにする仕組みを構築すべきとの観点から検討が行われている。
委員からは暦年課税を廃止し、相続時精算課税に一本化すべきなどの意見が多く、いずれ近いうちに暦年課税が廃止されるのではないかとの報道が専門誌や経済誌だけでなく、一般誌にも広く伝えられることになった。
一連の報道を受け、中里会長は専門家会合を設置するに当たり、9月16日の総会で、「近々暦年課税が廃止されるのではないか」あるいは「110万円の基礎控除が使えなくなるのではないか」との懸念に対し、「そのような議論は行わない」と明言し、理論的・実務的な視点を踏まえた検討を行うとしている。
少額申告や贈与財産が下落した場合などが適用のネック
今回の見直しの検討課題となる一番手は相続時精算課税制度の利便性の向上だ。日本の場合、米国やドイツ、フランスなどと異なり、贈与税は相続税とは別体系であり、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択制となっている。暦年課税については、生前贈与と相続で税負担が大きく異なっており、資産移転の時期に中立的ではないとされている。一方、「相続時精算課税」の場合は、選択後は生前贈与と相続税で税負担は一定であり、資産移転の時期に中立的であるとされている。
しかし、平成30年分のデータではあるが、申告件数は暦年課税の37.4万件に対して相続時精算課税は4.3万件と低調にとどまっている。申告件数が低調にとどまる理由としては、暦年課税とは異なり、110万円以下の少額の贈与であっても申告しなければならないことや、贈与財産の価額が贈与者の相続開始時までに下落した場合であっても、贈与時の価額で相続税を課税することとされているため、贈与財産の価額が下落したときは相続時精算課税制度を選択したことで不利益が生ずることなどがネックとなっているようだ。今後、これらの問題点などについて検討されることが想定される。
教育資金等の一括贈与非課税措置も検討課題
富裕層を優遇し、格差の是正に逆行する制度であるとの批判の声がある「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」や「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についても見直しの検討課題となる公算が高い。令和3年度税制改正においても、これらの非課税措置については廃止すべきとの意見が与党の税制調査会で強く聞かれたものの、最終的には適用要件を厳しくした上で2年間延長されることになった。適用期限は令和5年3月31日であることから、内閣府や文部科学省などが適用期限の延長を求めているが、制度の存廃を含め令和5年度税制改正でも大きな論点になりそうだ。
法定相続分課税方式の見直しは中期的な検討課題に
資産移転の時期に中立的な税制の最終的な形は相続税・贈与税の一体化ということになろう。この場合、贈与者は税負担を意識して財産の移転のタイミングを計る必要がなく、その一方で税率の格差を狙った意図的な税負担の回避も防止することができる。
例えば、米国やドイツ、フランスでは、贈与税・遺産税(相続税)の税率表が共通となっており、相続・贈与に係る税負担の中立性が確保される制度を設けているとされている(図表参照)。米国の場合は贈与税と遺産税は統合されており、一生涯の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税するという遺産課税方式を採用。ドイツやフランスも贈与税と相続税は統合されており、一定期間の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税する遺産取得課税方式が採用されている。これらの方式は、生前贈与と相続で税負担は一定とされているため、資産移転の時期に中立的であるとされている。一方、日本の場合は、相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって計算し、それを各人の取得財産額に応じ按分して税額を計算する方式である「法定相続分課税方式」が採用されている。贈与税は相続税とは別体系であり、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択制となっている。前述したとおり、暦年課税は、資産移転の時期に中立的ではないとされている。
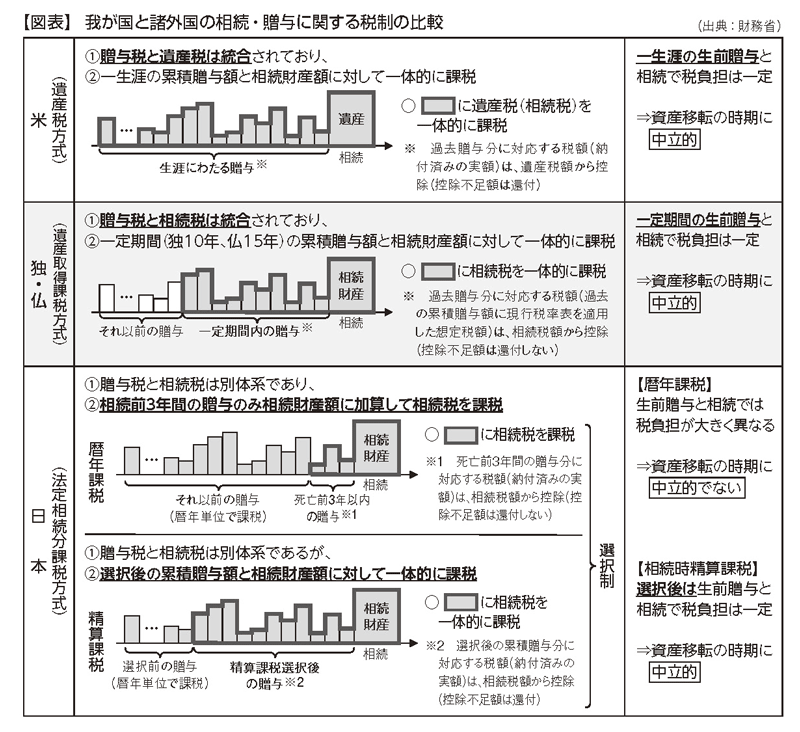
このため、最終的には「暦年課税」の廃止を含めた「法定相続分課税方式」の見直しが焦点となるが、中里会長は、現行の法定相続分課税方式から諸外国のような遺産課税方式や、遺産取得課税方式への移行といった大規模な見直しの議論は中期的な検討課題であり、今回の専門家会合では検討課題としないことを明らかにしている。
生前贈与財産の加算制度の対象期間延長は?
このように今回の専門家会合では、暦年課税の廃止は検討されないものの、最も気になるのは暦年課税における生前贈与財産の加算制度の見直しがあるかどうかだ。現行の加算の対象期間は「3年」とされており、加算の対象期間を「5年」「7年」などに延長することになれば、現行制度よりも「資産移転の時期の選択に中立的な税制」に近づくことになる。今後の議論が注目される点である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























