解説記事2022年10月31日 ニュース特集 Q&Aで読み解く上場会社等監査人登録制度(2022年10月31日号・№952)
ニュース特集
個人も含めすべての監査人にガバナンス・コードが必須
Q&Aで読み解く上場会社等監査人登録制度
上場会社の監査を登録制とすることなどを盛り込んだ改正公認会計士法が令和5年4月1日から施行される。金融庁は10月21日、改正法に係る政令・内閣府令案等を公表(11月21日まで意見募集)。上場会社等監査人に登録するための要件や登録の拒否要件などが明らかとなった。登録を受けるためには、形式的な要件のほか、人的体制や品質管理体制の整備などが求められる。具体的には、上場会社の監査経験を持つ公認会計士の確保や、業務の品質の管理に係る選任の部門の設置などが求められる。また、登録後は、監査事務所の品質管理システムの整備状況や監査法人のガバナンス・コードの適用状況などを開示する必要がある。これらの要件などは監査法人だけではなく、上場会社の監査を行う共同監査事務所などにも適用される。今後、中小規模の監査事務所も含め、早急な体制整備が求められることになる。
本特集では、上場会社等監査人登録制度を説明するとともに、政令・内閣府令案等及び日本公認会計士協会が公表した「公認会計士法改正に関連する協会制度変更要綱案」(11月4日まで意見募集)に基づきその概要をQ&A形式で解説する。
大手監査法人から中小規模監査法人への交代が増加傾向
Q
上場会社の監査を行うには、法律上登録が義務付けられることになりますが、その背景について教えてください。
A
現行、上場会社の監査を行う監査事務所に対する規律については、2007年より「上場会社監査事務所登録制度」が導入されている。ただ法的な根拠があるわけではなく、あくまでも日本公認会計士協会の自主規制の1つとして、財務諸表監査の信頼性が図られている。
しかし、昨今では大手監査法人の上場会社数は減少傾向にあり、2021年は124社、2022年には140社が大手監査法人から準大手監査法人や中小規模監査事務所(中小監査法人、共同事務所、個人事務所)に交代している。このような状況の中、監査手続きの複雑化や改訂品質管理基準の適用など、監査の品質確保のための整備が求められており、上場会社の監査を担う監査法人の登録制度を法定化することで監査リスクに対応できる体制を整える狙いがある。
会社法上の監査などは登録せずに可能
Q
会社法上の監査なども登録しなければ監査を行うことができませんか。
A
監査を行う上で登録が必要となるのは、金融商品取引法上の財務計算に関する書類及び内部統制報告書に係る監査証明に限定されている。このため、会社法上の監査など、その他の監査については、登録を行わなくとも実施することができる。
登録申請は従来と同じく会計士協会
Q
新しく導入される「上場会社等監査人登録制度」と現行制度の違いについて教えてください。
A
現行、日本公認会計士協会が行っている上場会社監査事務所登録制度は、あくまでも自主規制の1つだが、新たな「上場会社等監査人登録制度」は公認会計士法で規定されたものとなる。
登録要件や登録の取消し要件などは公認会計士法に規定されることになるが、登録を受けようとする場合には、従来と同じく、日本公認会計士協会に登録申請を行うことになる。同協会は、登録拒否事由に基づき申請者の適格性を確認することになる。適格性が確認された場合には、日本公認会計士協会が設置する上場会社等監査人名簿に登録する運びとなる。
登録判断は「品質管理委員会」から「上場会社等監査人登録審査会」に変更
Q
自主規制の下では、登録の判断は日本公認会計士協会の品質管理委員会が行っていますが、何か変更になる点はありますか。
A
現行制度では、日本公認会計士協会の品質管理委員会が品質管理レビューに係る審査、上場会社監査事務所の登録の双方を実施しているが、今後、登録の審査・登録の取消しの判断に関しては新たに協会内に設置される「上場会社等監査人登録審査会」が行うことになる。この点が従来の制度と大きく異なる。
審査会長は日本公認会計士協会の会長が就任する。構成員の数は未定となっているが、客観性を確保するため少なくとも外部の学識経験者などの非会員の数を会員よりも多くする方針だ。現行制度では非会員よりも会員の方が多くなっている。なお、議事については個別案件になるため、現行と同じく非公開とする方向になっている。
名簿も法定化
Q
上場会社等監査人名簿が法定化されるとのことですが、現行の準登録事務所名簿や抹消リストは廃止されるのですか。
A
現行制度では、品質管理委員会は上場会社監査事務所名簿、準登録事務所名簿、抹消リストを備えることとされている。法定化後は、「上場会社等監査人名簿」のみ日本公認会計士協会に備え、現行制度の名簿は廃止することとしている。ただし、各名簿等で開示を行ってきた品質管理レビューの実施状況や、登録を取り消された場合の理由等については新制度移行後も同協会のホームページで公表する予定としている。
登録の拒否要件、社員数の「5人」は今後見直しも
Q
法令上、上場会社等監査人名簿への登録が拒否される要件について教えてください。
A
登録の拒否要件については、例えば、以下のとおりとなっている(改正法34条の34の6)。監査法人の場合には、公認会計士である社員の数が5人以上とされている。常勤か非常勤かについては問われていない。また、この社員数に関しては、制度導入後、日本公認会計士協会の中小規模監査法人等に対する支援などを踏まえ、今後見直されることが想定されている。
・上場会社等監査人登録を取り消されてから3年を経過しないとき |
登録する上での一番のハードルは人的体制と品質管理体制の整備
Q
登録の拒否要件にある「上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるもの」とはどのような体制をいうのでしょうか。
A
登録を受ける上では、この体制整備が要件で最も難しいものとなる。内閣府令では、大きく人的体制と品質管理体制の2つに分けられ、どちらも整備する必要がある(改正規則87条)。
3年以上の上場会社の監査経験がある社員が必要
Q
具体的に人的体制及び品質管理体制にはどのような要件があるのでしょうか。
A
人的体制では、まず、上場会社等の財務書類に係る監査業務に十分な知識及び経験を有している公認会計士を確保していることが必要であるとされている。公認会計士の登録を受けた後、3年以上監査証明業務の経験が必要とされる。監査経験が上場会社等の監査証明業務に限られている点、注意が必要だ。また、監査法人に関しては、社員の過半数を確保する必要がある。
2番目は日本公認会計士協会の調査に協力したことがある者でないことや、監査証明業務の運営の状況に重大な不備があるとして同協会の認定を受けた者でないことなどとされている。これは、上場会社監査事務所名簿から登録が抹消された監査事務所の会員が、新たに監査事務所を設立して再度登録事務所名簿に登録申請して監査業務を行っていた事例があり、これを法令上登録拒否事由としたものである。
また、品質管理体制では、業務の品質の管理に係る選任の部門の設置、業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人の場合は社員に限る)の選任が必要とされている。特に中小規模の監査事務所にとってはハードルの高い要件となっている。
個人の監査事務所等も人的体制や品質管理体制が必要
Q
個人の監査事務所の場合も、品質管理部門がないなどの登録の拒否要件に該当すれば、登録が認められないことになるのでしょうか。
A
個人の監査事務所についても前述した登録の拒否要件に該当すれば、登録は認められないことになる。例えば、業務の品質の管理に係る選任の部門の設置は個人の監査事務所にとってはかなり厳しい要件といえる。改正公認会計士法の施行から1年6か月は経過措置により、改正後の要件をクリアしていなくても監査を行うことができるが、それまでに体制の整備などを行う必要がある(今号11頁参照)。監査法人になるなど、規模を拡大することも視野に入れる必要があろう。
登録の拒否要件に該当しているか否かは協会のレビューで判断
Q
上場会社等監査人名簿への登録の審査に関しては、現行と同じ品質管理レビューが行われますか。
A
上場会社等監査人名簿への登録の審査は、前述したとおり、日本公認会計士協会が行うことになり、登録の拒否要件に該当するか否かを判断する。判断に当たっては、上場会社等の監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制を確認することを目的とした「適格性の確認のためのレビュー」により行うこととしている。
なお、登録申請者が、①「適格性の確認のためのレビュー」を正当な理由なく拒否した場合、又は②「適格性の確認のためのレビュー」を実施した結果、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が見受けられた場合で、辞退勧告措置が講じられた場合には、法令に定められた体制整備義務に違反するものとして、上場会社等監査人名簿への登録は拒否されることになる。
登録拒否等に不服がある場合は行政不服審査法に基づく審査請求の対象
Q
登録が拒否された場合、これまでと同じく不服申立てはできますか。
A
現行制度では、日本公認会計士協会の品質管理委員会が上場会社監査事務所名簿への登録を認めない決定などを行った場合には、その会員は同協会の適正手続等審査会に対し、審査申立てを行うことができるとされている。
しかし、改正後は、登録の拒否又は登録の取消しを受け不服がある場合には、同協会の適正手続等審査会ではなく、行政不服審査法に基づき審査請求を国に行うことになる。
共同事務所での監査、補助者も含めて5人以上が必要
Q
共同事務所が登録を行った場合、監査を行う場合に要件はありますか。
A
数的には少ないものの、個人の公認会計士が他の公認会計士と共同で上場会社の監査を行っているケースがあるが、改正後も登録を受けることにより上場会社の監査を行うことができる。具体的には登録を受けた監査法人と共同で監査を行う場合、又は他の登録を受けた公認会計士と共同で行う場合となっており(改正法34条の34の13)、後者の場合は使用する補助者の公認会計士と合わせて5人以上が要件となっている。
情報開示義務、監査法人のガバナンス・コードの適用は必須
Q
登録を受けた監査法人又は公認会計士(登録上場会社等監査人)については、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制など、情報開示義務が課せられているとのことですが(改正法34条の34の14)、具体的にはどのような内容となっていますか。
A
登録上場会社等監査人は、例えば、年度(3月末)又は会計年度中の一定の日(基準日)における業務の品質の管理の状況を適切に評価するとともに、①基準日、②業務の品質の管理の目的、③基準日における業務の品質の管理の状況、④業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由、⑤④の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とする者であった場合には、業務の品質の管理の状況等を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容を公表することとされている(改正規則案93条)。
また、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材確保の状況などを公表しなければならないとされている(改正規則案95条)。加えて、「組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の適用状況について公表することとされている(改正規則案96条)。
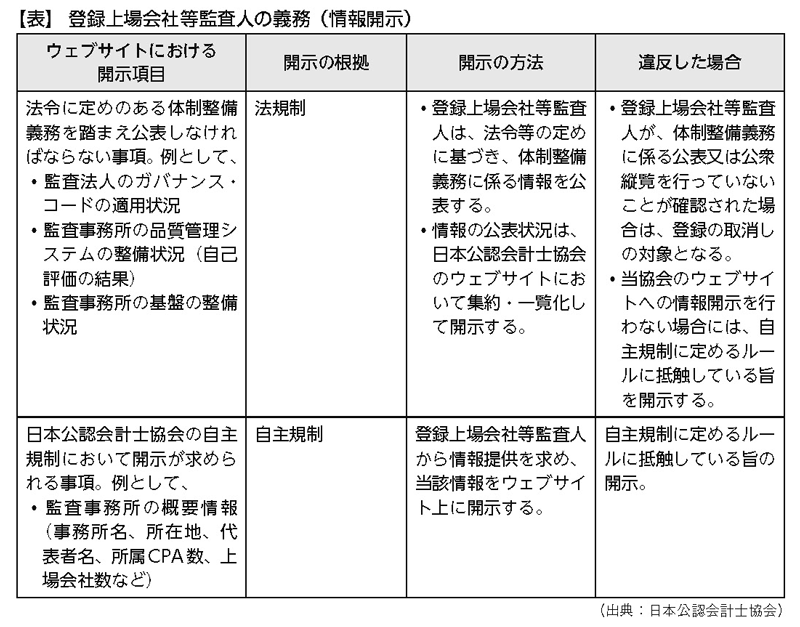
共同監査事務所もガバナンス・コートの適用が必要
Q
共同監査事務所であっても監査法人のガバナンス・コードを適用することが求められるのでしょうか。
A
登録上場会社等監査人であれば、共同監査事務所であっても監査法人のガバナンス・コードの適用が義務付けられる。
金融庁は10月24日に、「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」を開催。中小監査法人等にも適用できるよう監査法人のガバナンス・コードの改訂に着手した。現行のコードは大手監査法人を念頭に策定されたため、コードの受け入れを表明しているのは、9つの大手・準大手監査法人以外は9つの中小監査法人にとどまっている。ただし、改訂の方向性としては、中小監査法人等に限定した新たなコードを策定することはせず、「上場会社監査を担う監査法人」を想定し、あるべき組織的運営となるような見直しを行うとしている。
3年に1度の品質管理レビュー
Q
登録上場会社等監査人の義務について教えてください。日本公認会計士協会の品質管理レビューはどうなりますか。
A
日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人に対して、品質管理レビューを受けることを義務化する。上場会社に限らず、監査を行っている場合には通常レビューを原則として3年に一度実施する。また、改正公認会計士法では、監査を一切行っていない場合であっても登録上場会社等監査人となることが可能となっているため、この場合には「適格性の確認のためのレビュー」を登録申請時などに行うとしている。
また、監査法人のガバナンス・コードの適用状況や監査事務所の品質管理システムの整備状況、監査事務所の基盤の整備状況については改正法上開示義務が課せられているが、各事務所のほか、日本公認会計士協会のホームページにも集約・一覧化して公表することが求められている。
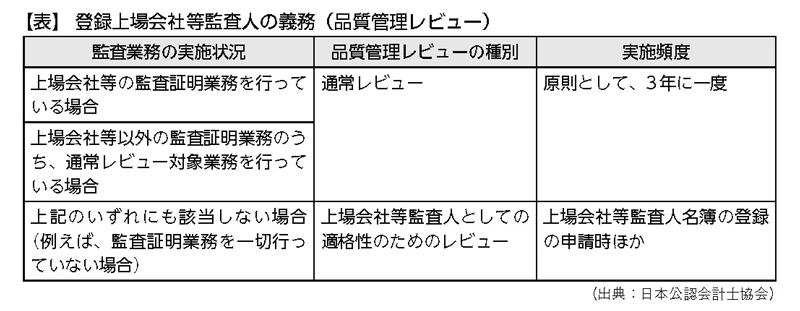
登録の取消し、法令違反などで会計士協会が判断
Q
登録上場会社等監査人となった場合、どのようなケースで登録の取消しが行われますか。
A
登録上場会社等監査人の登録の取消しの判断については、法令に定められた登録の取消し要件(改正法34条の34の9)に該当するかどうかを日本公認会計士協会の上場会社等監査人登録審査会が行うことになる。
例えば、不正の手段により登録した場合のほか、登録の拒否要件に該当した場合や、業務管理体制の整備義務(改正法34条の34の14)に違反した場合などが該当する。なお、登録の審査時の拒否とは異なり、登録の取消しは「できる」規定となっている。
施行から1年6か月は現行制度による経過措置あり
Q
改正公認会計士法の施行日までに登録要件を満たす必要がありますか。
A
改正公認会計士法については、令和5年4月1日から施行することが明らかにされている。ただし、改正により各監査法人等は人的体制や品質管理体制などの整備が必要となるため、現在、上場会社の監査を行っている場合には経過措置が設けられている。
具体的には、施行日から起算して2週間以内に日本公認会計士協会に届出(下表参照)を行うことにより、1年6か月の間はこれまでどおり監査を行うことができる。登録要件を満たしていない場合にはこの1年6か月の間に体制整備などを行う必要がある。中小規模の監査事務所や共同監査事務所の場合には規模の拡大を含め、早急に体制を整備する必要に迫られることになりそうだ。
なお、経過措置後も上場会社の監査を行う場合には、改めて上場会社等監査人名簿への登録申請が必要となるので留意したい。
・施行日から起算して2週間以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を日本公認会計士協会に届け出なければならない。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















