解説記事2022年11月21日 SCOPE 外貨建インボイス、売手換算税額使用は請求書等積上計算のみ(2022年11月21日号・№955)
帳簿積上計算・割戻計算は買手換算で
外貨建インボイス、売手換算税額使用は請求書等積上計算のみ
インボイス制度に関するQ&Aの問56で、消費税の課税対象である外貨建の請求書には売手が円換算した消費税額の記載が必要である旨解説がされている。この円換算後の消費税額の買手側での取扱いについて本誌が課税当局に取材したところ、買手が仕入税額控除について請求書等積上げ計算を行う場合は売手による円換算後の消費税額に拘束されるが、帳簿積上げ計算及び割戻し計算による場合は、従来通り、買手が自社で採用する外貨換算の方法によって計算した消費税額を使用して差し支えないことが確認された。
仕入税額控除で税額自体を積み上げるか税込額から計算するかで扱いに差異
米ドル等の外貨建であっても、日本国内で完結する取引であれば消費税が課されるのが原則であり、消費税を含めた外貨建の請求書を発行することは珍しくない。国税庁が公表しているインボイス制度に関するQ&Aの問56では、そのような場合におけるインボイス制度上の取扱いが解説されており、外貨取引であっても、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」については、円換算した金額を記載する必要があるとされている。この場合の円換算は、消費税法基本通達(以下「消基通」)10−1−7を参照し、法人税(所得税)の例により行う。Q&Aは、請求書を発行する側の売手による外貨換算について解説したものだが、買手側も自社の法人税の例によって換算するということは、消基通10−1−7の逐条解説(平成30年版)に「外貨建て課税仕入れに係る支払対価の額についても、所得税又は法人税の例によることになり」との記載がある点等から読み取ることができる。すなわち、外貨換算は“各社”の法人税の例によるため、買手側の企業が売手側と全く同じ換算方法を採用しているとは限らず、例えば消基通10−1−7で参照している法人税基本通達13の2−1−2においても、継続適用を条件として、TTM以外にTTBやTTS、あるいはこれらの前月末レートや平均レートなどの使用が認められている。買手はこれらの取扱いをベースに、自社が採用する方法によって円換算した金額で仕入税額控除の計算を行うというのが、従来から行われている一般的な実務となっている。このような背景から、実務家の間では「このQ&Aは、外貨建の請求書に売手側の法人税の例によって円換算した消費税額の記載がある場合、買手側の仕入税額控除計算上、当該円換算された金額に拘束されるという意味なのか」との疑問の声が聞かれる。
この点について本誌が課税当局に取材したところ、外貨建請求書に記載された売手側による円換算後の消費税額は、買手が仕入税額控除について請求書等積上げ計算を行う場合、その記載金額に拘束される一方、帳簿積上げ計算及び割戻し計算による場合には、買手が自社で採用している外貨換算のルールに基づき円換算をした税込金額をベースに計算して差し支えないことが確認された。つまり、拘束されるのは請求書等積上げ計算を行う場合のみ、ということだ。
仕入税額控除において控除すべき「課税仕入れに係る消費税額」は、消費税法施行令46条1項に規定される請求書等積上げ計算では「適格請求書に記載されている消費税額等」、すなわち税額自体を使用するのに対して、同条2項の帳簿積上げ計算及び3項の割戻し計算では、要約すれば「課税仕入れに係る支払対価の額」を110(又は108)で除してそれに消費税率を乗じた金額をもって課税仕入れに係る消費税額として取り扱うこととされている。「課税仕入れに係る支払対価の額」は、110で除すという点以外にも、消費税法30条8項1号二で「消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(略)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む」と規定されているため、税込金額であることは明らかだ。そのうえで、前述消基通10−1−7に関する逐条解説で「外貨建て課税仕入れに係る支払対価の額についても、所得税又は法人税の例によることになり」と解説されていることを踏まえると、帳簿積上げ計算及び割戻し計算の場合は、買手側の法人税の例によって換算した円建ての税込金額から計算される金額をベースに仕入税額控除の計算を行う、ということになる。その一方で、請求書等積上げ計算の場合は請求書に記載された消費税額自体を積み上げることになるが、Q&Aで消費税額は円換算した金額を記載する必要があると解説されていることを踏まえると、“円建て”で記載された消費税額を積み上げることを前提としている、ということになろう。
以上の取扱いをまとめると表の通りとなる。結局、帳簿積上げ計算又は割戻し計算を採用する場合は外貨建請求書に記載された円換算額は関係なく、従来通り自社で採用している換算ルールによって計算した金額を使用すればよいということになる。しかし、請求書等積上げ計算を行う場合には売手側円換算による消費税額を用いることになり、採用する方法によって取扱いが異なる点、注意が必要だ。
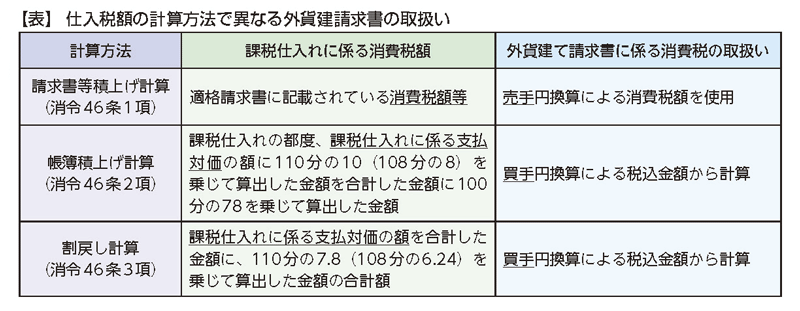
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























