解説記事2022年12月12日 ニュース特集 インボイス制度に負担軽減措置導入(2022年12月12日号・№958)
ニュース特集
一定の中小事業者、1万円未満ならインボイスなしで仕入税額控除可
インボイス制度に負担軽減措置導入
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されるが、与党税制協議会は、小規模事業者等に対するインボイス制度の負担軽減措置などを決めた(本誌957号5頁参照)。令和5年度税制改正大綱に盛り込む。基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(適格請求書)の保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とするとともに、インボイス制度移行に伴う事務負担の軽減を図るため、1万円未満の少額な値引きなどについては、返還インボイス(適格返還請求書)の交付を不要とする措置を講じる。また、免税事業者が課税事業者を選択した場合には、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとした。
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が対象で6年間の経過措置
令和5年10月1日からインボイス制度が導入される。インボイス制度では、課税事業者が消費税を一般課税で申告する際、インボイスの保存がなければ、仕入税額控除が認められなくなる。軽減税率制度の実施により、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が必要であり、このような取引についてもインボイスの保存が必要となるため、中小事業者等にとっては過度な事務負担が生じることになると指摘されている。
帳簿のみで可
このため、令和5年度税制改正では、中小事業者等に対する事務負担の軽減を図る観点から、基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、6年間、1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする措置を講じる。全事業者の90.7%が対象になるとされている。金額については、「3万円未満」とすべきとの意見も強かったが、企業の課税仕入れのうち、1万円未満の取引が82%を占めていることから、最終的に「1万円未満」で決着した。
なお、基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間の課税売上高が5,000万円以下である場合は、特例の対象とすることとされている。
1万円未満の少額な値引き等は返還インボイス不要
インボイス制度移行に伴う事務負担の軽減も行われる。具体的には少額な返還インボイスの交付義務の見直しだ。
現行、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った場合には売手と買手の税率と税額の一致を図るため、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった書類(返還インボイス)の交付義務が課せられることになっている。しかし、多くの事業者からは、例えば、決済の際に、買手側の都合で差し引かれた振込手数料相当額やその他の経費を、売手が「売上値引き」として処理する場合に新たな事務負担になるとの懸念の声が寄せられていた。
このため、事業者の事務負担を軽減することを目的に、1万円未満の少額な値引きなどについては、返還インボイスの交付を不要とする措置を講じることとしている(図表1参照)。事業者にとっては朗報となる改正といえそうだ。
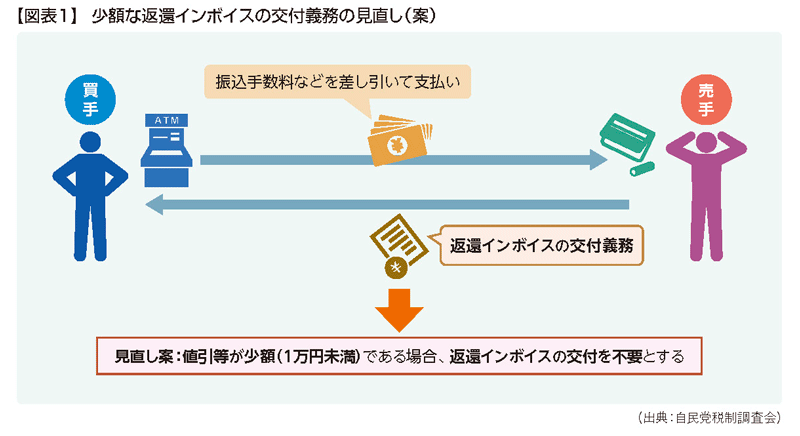
課税事業者を選択した場合の3年間、納税額を売上税額の2割に軽減
免税事業者が課税事業者を選択した場合には、取引先の求めに応じてインボイスを交付することができるが、これまでとは異なり、消費税の申告義務が生じることになる。また、請求書様式や会計システムの見直しなどの対応も必要になる。
このため、免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとしている。簡易課税を選択した場合に比べても事務負担や税負担が大幅に軽減されることになる(図表2参照)。
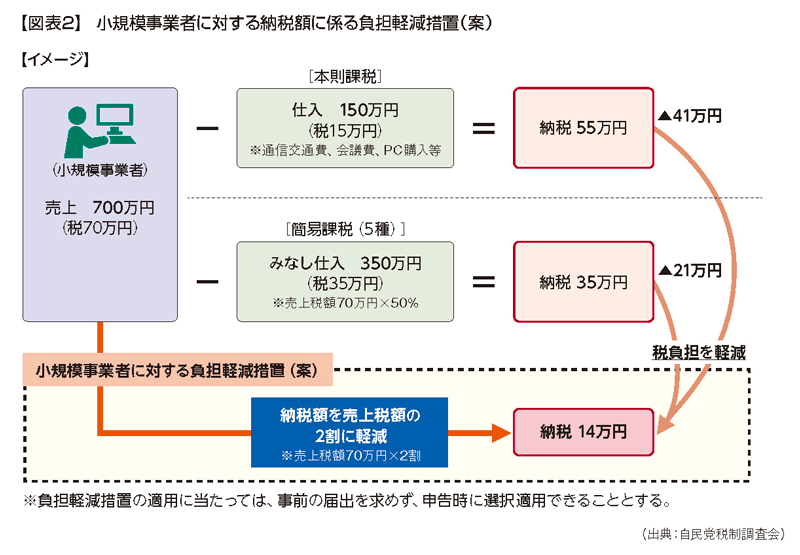
激変緩和措置については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の者を対象とし、インボイス制度の開始(令和5年10月1日)から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることとする。また、適用に当たっては事前の届出は求めず、申告時に選択適用できるとしている。
なお、激変緩和措置は3年間の措置となっているが、与党税制協議会では、3年後についても急激に納税額が上がらないような措置を講じるべきなどの意見が出されている。3年後も何らかの対応がとられる可能性がありそうだ。
経過措置の当面の間の維持は実現せず
そのほか、免税事業者との取引への影響を緩和するため、インボイス制度導入後3年間は、免税事業者からの仕入れに係る消費税の8割相当額(その後の3年間は5割相当額)の仕入税額控除を可能とする経過措置が設けられている。この点、経過措置を当分の間維持すべきとの要望があったものの、今回の改正では実現しなかった。
登録希望日から登録する場合には15日前に
負担軽減措置ではないが、インボイス制度の登録手続の見直しも行われる(図表3参照)。インボイス制度については、令和5年10月1日から開始されるが、それ以降に登録する事業者も少なからずいることだろう。事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う際において、課税期間の初日から登録を受ける場合については、現行では1か月前までに申請書を提出する必要があるが、これを課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すればよいこととする。登録を取り消す場合の届出書の提出期限についても同様の見直しが行われる。
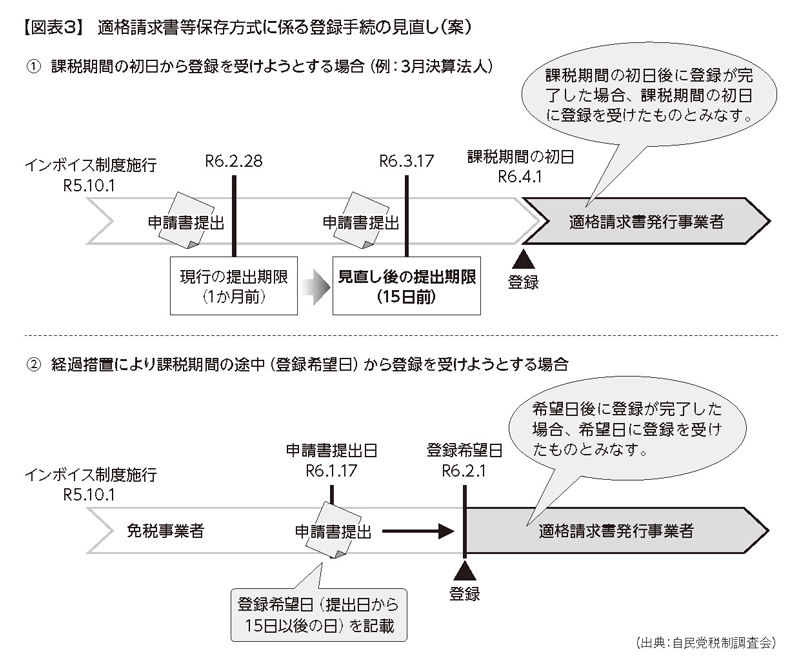
また、免税事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においては免税事業者自らのタイミングで登録を受けることができる経過措置を受けることができる。この点、登録希望日から登録を受けようとする免税事業者については、申請書に登録希望日を記載することを可能とする。この場合、提出日から15日以後の日を記載することとしている。
登録申請書を提出してから登録番号が通知されるまでには一定の期間が必要とされており、現在、登録申請書を提出してから登録通知までの期間は、e-Taxの場合で約3週間、書面の場合で約1か月半となっている(11月24日時点)。このため、実際に登録が完了した日が、課税期間の初日後又は登録希望日後であっても、課税期間の初日又は登録希望日に登録を受けたものとみなすことができるようにする。
ただし、この場合であっても、登録の通知が来るまではインボイスを交付することはできない。改めて相手先に課税期間の初日又は登録希望日に登録した旨を連絡する必要があるので留意したい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























