解説記事2022年12月12日 SCOPE 地裁、韓国からの保全共助要請に基づく保全差押処分は適法(2022年12月12日号・№958)
第二次納税義務者・ケイマン法人の債権差押え
地裁、韓国からの保全共助要請に基づく保全差押処分は適法
日本の国税庁が韓国の国税庁から保全共助要請を受けて行った保全共助実施決定処分及び第二次納税義務者の債権の保全差押処分の取消しを求めて争われていた事案で、東京地裁民事3部(市原義孝裁判長)は令和4年11月30日、納税者の請求を棄却した。
東京地裁は、本件保全共助対象外国租税は税務行政執行共助条約発効前ではあるものの、要訴追故意事案に係る租税であるため保全共助の対象となるなどとして、本件各処分は適法であるとの判断を下した。
要訴追故意事案に係る租税は税務行政執行共助条約発効前でも保全共助対象に
税金の滞納者の資産が国外にある場合に、各国の税務当局が財産の所在する国の税務当局に要請してその滞納税金を取り立ててもらう仕組みとして、税務行政執行共助条約に基づく徴収共助要請がある。
本事案の概要は図のとおり。韓国、日本及び香港で海運業に携わっているK氏は、租税ほ脱で有罪が確定し、韓国国税庁は、K氏が代表を務めていたケイマン法人をK氏の滞納所得税等の一部についての第二次納税義務者に指定した。そして、そのうちの有罪確定ほ脱租税に係る部分について、日本の国税庁に保全共助の要請をした。
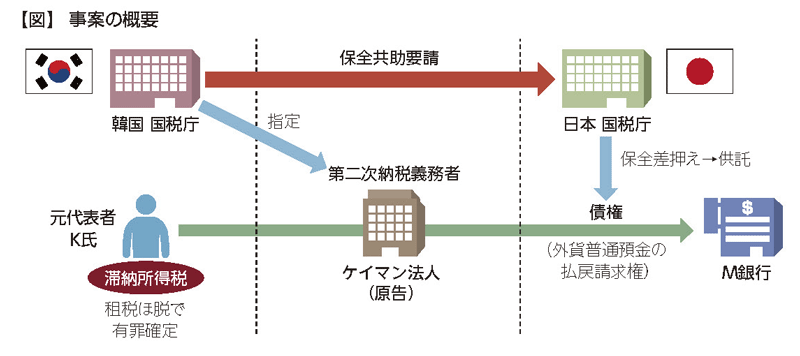
東京国税局長は、本件保全共助要請を受け、保全共助の実施を決定し、ケイマン法人(原告)がM銀行に対して有する外貨普通預金の払戻請求権を差し押さえた上で、その取立てを行い、取り立てた金銭を供託した。
これに対しケイマン法人は、本件保全共助実施決定処分及び保全差押処分の取消しを求めて訴訟を提起した。
保全共助対象外国租税の存否は要請国に提訴
本件の一つ目の争点は、「本件保全共助対象外国租税は、我が国において税務行政執行共助条約の適用のある課税期間に課される租税であるといえるか」。
日本において共助対象外国租税となり得る租税は、原則として、日本について税務行政執行共助条約が効力を生じた年の翌年1月1日(平成26年1月1日)以後に開始する課税期間に課される租税とされている。東京地裁は、本件保全共助対象外国租税は、平成19年の課税期間に係るものであるが、要請国の刑事法に基づいて訴追されるべき故意による行為に係る租税事件(要訴追故意事案)の対象とされた租税であれば、例外的に、上記より前に開始する課税期間に課される租税であっても共助対象とすることができることから、要訴追故意事案に係る租税に該当する本件保全共助対象外国租税は、「我が国において税務行政執行共助条約の適用のある課税期間に課される租税であるといえる」との判断を下した。
2つ目の争点は、「本件保全共助対象外国租税の不存在を理由として、本件各処分は違法となるか」。この点について東京地裁は、「実特法11条13項は、共助対象者は、実特法上の処分についての不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従っているかどうかを主張することができない旨を定めている」と指摘。また、「税務行政執行共助条約23条2項は、この条約に基づき要請国が採った措置、特に、徴収の分野に関連して、共助対象外国租税債権の存在若しくは額(中略)についての争訟の手続は、要請国の適当な機関にのみ提起することができる旨を定めているから、原告は、これらの措置について不服がある場合には、要請国である韓国の適当な機関に争訟の手続を提起すべきであって、我が国において、これらの措置についての争訟の手続を提起することはできない」と判示した。
そのほか原告は、要請国である韓国の税務当局との間での情報交換をする義務の不履行があった、本件各公示送達は適法な送達ではなかったなどとも主張したが、いずれの主張も斥けられている。
裁決と異なり「訴えの利益あり」と判断
なお、本件訴えのうち、本件保全差押処分の取消しを求める部分については、訴えの利益がないとして裁決では却下されていたが、これについて東京地裁は、「関係規定の構造に照らせば、所轄国税局長等としては、当該保全共助対象外国租税について徴収共助の実施決定がされるまで、同取立てに係る金銭を保管のために供託しなければならないのであって、共助対象者としても、その間は、供託原因である当該保全差押処分を取り消す旨の確定判決を得ることにより、当該供託の効果を覆滅させるとともに、取消判決の拘束力を通じて、当該供託に係る金銭の返還を受けることができるというべきである。そのため、保全共助の共助対象者としては、保全共助として行われた債権の保全差押処分に基づく債権の取立て及び供託がされた後であっても、少なくとも、徴収共助の実施決定がされるまでの間は、当該供託に係る金銭の返還を受けることができる余地が残されており、この点につき、法律上の利益を有するものと解される」として、裁決とは異なる判断を示している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























