解説記事2023年01月09日 ニュース特集 令和5年度法人税制改正のポイント(2023年1月9日号・№961)
ニュース特集
改正の背景・趣旨を踏まえ大綱を“深読み”
令和5年度法人税制改正のポイント
令和5年度税制改正は、防衛費財源を確保するため法人税が約30年前の法人臨時特別税導入以来の純然たる増税になることが確定したという点で税制改正史に残ることとなった。法人税に対する付加税の税率は「4〜4.5%」とされ、法人実効税率は、付加税4%の場合は30.64%、付加税4.5%の場合は30.75%となる。一方、中小企業に配慮し、当該付加税には500万円の税額控除が付されており、課税所得2,400万円までは追加負担が生じない。
また、令和5年度税制改正では「スタートアップ」がキーワードの一つとなった。同年度改正では、持分を一部残すスピンオフ(パーシャルスピンオフ)税制が1年限りの租税特別措置として実現することになったが、本措置は「スタートアップ政策」の一環として位置付けられており、本措置の適用を受けるために認定を受けることが求められる「産業競争力強化法の事業再編計画」は、主としてスタートアップの切り出し等に資する計画を意図していることが本誌取材により判明している。昨年度改正されたばかりのオープンイノベーション促進税制の対象となる「特定株式」には、ニューマネーをもたらす新規発行株式ではなく、オーナー等の有する既存の株式が追加されている(マジョリティ(過半数)を取得することが要件)。
研究開発税制の一般型では、「控除率」のカーブの傾斜を強めるのみにとどまらず、(税額)控除上限に到達した企業等へのインセンティブ強化措置として、増減試験研究費割合に応じて控除上限が変動する措置が盛り込まれた点、注目される。
国際課税分野では、デジタル課税第2の柱(ミニマム課税)を令和5年度税制改正で法制化した上で、準備期間を考慮し、令和6年4月1日以降開始事業年度から適用することとするとともに、ミニマム課税の国内法制化に連動して企業の事務負担軽減の観点からCFC税制を見直し、特定外国関係会社に係る30%基準を1割引き下げ27%とする。なお、国内ミニマム課税(QDMTT)と軽課税所得ルール(UTPR)は令和6年度税制改正以降に先送りとされた。
このほか、長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例については、法人税の申告時に事後的に譲渡資産と買換資産の紐づけを行っているのではないかとの税務当局の問題意識の中、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(四半期)の末日の翌日以後2月以内に取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届出書を税務署に届け出ることを求めることとされた。
本特集では、改正の背景・趣旨を踏まえつつ、令和5年度法人税制改正のポイントを解説する。
法人税増税
「税額控除後、かつ、外税控除前や所得税額控除前」の税額がベースに
令和5年度税制改正大綱の公表(12月16日)は例年よりも6日ほど遅くなったが、その最大の原因となったのが、防衛力強化のための防衛費増加に伴う増税議論だ。
令和9年度において現状より約4兆円多く必要となる防衛費の財源は歳出改革等のみでは補い切れず、1兆円強の増税が不可欠となる。そこで、どの税目を増税するのかということが問題となったが、社会保障財源である消費税はその対象とはなりえず、所得税についても、12月8日の政府与党政策懇談会後の会見で岸田総理が「現下の家計を取り巻く状況に配慮し、個人の所得税の負担が増加するような措置は行わない」と述べたことから、その選択肢は自ずと限られた。
結論として、法人税の増税は、東日本大震災を受けて導入された復興特別法人税と同じく、法人税額に一定割合を乗じて税額を算出する付加税方式となった。具体的には、法人税額に対し「4〜4.5%」の付加税が課される。付加税の課税ベースとなる法人税額は、復興特別法人税を参考にすれば、「措置法上の税額控除後」かつ「外税控除前や所得税額控除前」のものとなるのではないかとみられる。
また、中小企業に配慮する観点から税額控除が設けられる。その金額を巡っては議論が紛糾した。当初は「所得1,000万円相当の税額控除」、税額に換算すると170万円(≒軽減税率対象所得800万円×軽減税率特例15%+200万円×法人税率23.2%)との案が出ていたが、湾岸戦争時の法人臨時特別税における「300万円」よりも低いことに中小企業団体が反発、最終的には所得約2,400万円、税額換算500万円(800万円×15%+1,600万円×23.2%=491.2、切り上げて500万円)とすることで決着した。
増税内容は法律に記載せず、会計上は税効果への影響なし
施行は「令和6年以降の適切な時期」とされ、詳細設計は今後の議論に委ねられており、令和5年度税制改正法案には盛り込まれないことから、会計上も税効果への影響は生じない。
法人実効税率は、付加税4%の場合は30.64%、付加税4.5%の場合は30.75%となる。現状が29.74%のため1%弱のアップとなる。東日本大震災時の復興特別法人税(平成24年度、25年度)は、平成23年度税制改正における「法人税率引下げ+課税ベース拡大」によるネット減税分をいわば吐き出す範囲でのプラス・マイナス・ゼロの改正だったが、今回は純然たる増税となる。純然たる増税は、(増減収のカウントの仕方にもよるが)30年前の湾岸戦争時の法人臨時特別税導入以来となる。
賃上げ税制や投資減税、研究開発税制等の税額控除つきの租税特別措置をフルに活用できれば、付加税の発射台を低くすることができるため、構造的に、投資や賃上げに前向きな企業は、追加的な税負担を抑えられる仕組みとなっている。ただし、当然のことながら、付加税を相殺できるほどのものではない。
増税は最速で令和6年度税制改正となる。この際に一緒に議論することになるのが、令和5年度末で適用期限を迎える賃上げ税制やカーボンニュートラル投資促進税制だ。その際には、このような租税特別措置を、新設を含め、どれだけ拡充できるかが焦点となろう。
スピンオフ税制
認定期間「1年」は延長の可能性 組織再編税制との整合性は令和6年度改正で議論へ
自民党税調のいわゆるマルバツ審議で当初は「×」が付された「一部持分を残すスピンオフ(パーシャルスピンオフ)税制」(図1参照)だが、最終的には令和5年度税制改正大綱に改正項目として盛り込まれている。
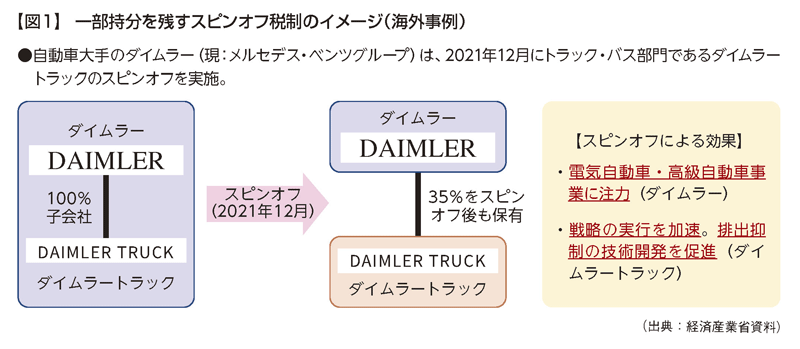
大綱の該当部分を抜粋すると、以下の通りとなっている。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が同法の特定剰余金配当として行う現物分配で完全子法人の株式が移転するものは、株式分配に該当することとし、その現物分配のうち次の要件に該当するものは、適格株式分配に該当することとする(所得税についても同様とする。)。
(1)その法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみを交付するものであること。
(2)その現物分配の直後にその法人が有する完全子法人の株式の数が発行済株式の総数の20%未満となること。
(3)完全子法人の従業者のおおむね90%以上がその業務に引き続き従事することが見込まれていること。
(4)適格株式分配と同様の非支配要件、主要事業継続要件及び特定役員継続要件を満たすこと。
(5)その認定に係る関係事業者又は外国関係法人の特定役員に対して新株予約権が付与され、又は付与される見込みがあること等の要件を満たすこと。
大綱の内容を理解する上では、本措置が「スタートアップ政策」の一環として位置づけられていることに留意する必要がある。昨年8月末の経済産業省要望の段階では、スピンオフ税制の拡充は「Ⅰ.スタートアップ・エコシステムの抜本強化」ではなく、「Ⅱ.カーボンニュートラルへの対応とイノベーション促進のための取組」の一項目として取り上げられていたが、11月に新しい資本主義実現会議で取りまとめられた「スタートアップ育成5か年計画」では、スピンオフ税制の拡充はスタートアップ政策の中に位置付けられた。その後、自民党税調で審議された経済産業部会要望においても、スピンオフ税制は、いつの間にか「Ⅰ.スタートアップ・エコシステムの抜本強化」策の一つに数えられている。
企業からは、大綱でいう「産業競争力強化法の事業再編計画」とはどのようなものなのか、早速疑問の声が挙がっているが、上記のような経緯を踏まえれば、主としてスタートアップの切り出し等に資する計画を意図していると考えるべきだろう。
また、認定期間が1年間しかないことについて「短すぎる」との指摘があるが、これは産業競争力強化法自体が、令和3年改正法の附則において、3年後すなわち「令和6年」における見直しの対象となっていることが影響しており、見直しの結果、認定期間が延長される可能性はある。
なお、認定を令和6年3月末までに受ければ、スピンオフ自体は令和6年4月以降であっても構わないと解される。
従業者の事業への継続従事要件もスタートアップを意識、要件追加の可能性も
また、追加的な株式分配を行うことによって持分を最終的にゼロにする等の要件は設定されていない。大綱(3)により従業者の事業への継続従事要件(90%以上)が入ったのは、(不採算事業の切り出しということでもないため)スピンオフされたスタートアップにおいて、退職者が続出するとは通常考えられないためであろう。あとは、大綱(4)により粛々と適格判定を行うことになる。
(5)の趣旨やその詳細については、今後の明確化が待たれるところだ。「新株予約権が付与され、又は付与される見込みがあること等」における「等」についても、何らかの追加の要件が設定される可能性は否定できないだろう。
オープンイノベーション促進税制
既存オーナー等からの株式買取りによる経営権取得を念頭
昨年度税制改正でも見直されたオープンイノベーション促進税制(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)について、同特例の対象となる特定株式に「発行法人以外の者から購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるもの」が追加される。「発行法人以外の者から購入により取得した」との要件からは、今回特例の対象に追加された特定株式は、法人が発行した新株ではなく、既存株式を対象にしていることが分かる。要するに、既存のオーナー等から株式を過半数買い取り、経営権を取得することを求めている。
対象となる株式の取得価額は「5億円以上」で「200億円」が上限となる。また、株式を取得した場合、5年間の継続保有と事業活動の継続が求められる。今回の改正の対象となる既存株式については、原則として、株式の取得から5年(昨年度改正では新株の取得については3年とされた)を経過した場合、当該株式に係る特別勘定を取り崩して益金算入することが求められる点、注意が必要である。
株式取得から5年以内のいずれかの事業年度において売上高が「1.7倍かつ33億円以上」となったこと等の要件を満たせば、益金算入を免れることになる。要するに「5年以内に会社を大きくせよ」ということだ。ただし、益金算入を免れた場合でも、特定株式について剰余金の配当を受けた場合には、その25%相当額の特別勘定の金額を取り崩して益金算入することが求められる。
研究開発税制
増減試験研究費割合0%における控除率8.5%は変わらず
一般型研究開発税制では、インセンティブ強化の観点から控除率のカーブの傾斜が現状より急角度にされる。ただし、増減試験研究費割合0%における控除率8.5%は維持された。
具体的には、控除率の最低保証率を2%から「1%」に縮減した上で、税額控除率を以下の算式の通りとする。これを図示すれば図2の通りとなる。
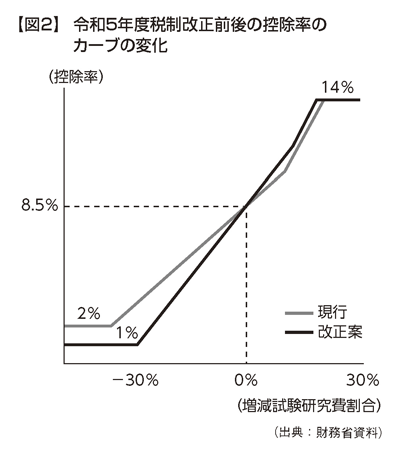
(イ)増減試験研究費割合が12%超の場合
11.5%+(増減試験研究費割合−12%)×0.375
(ロ)増減試験研究費割合が12%以下の場合
11.5%−(12%−増減試験研究費割合)×0.25
また、税額控除の上限についてもメリハリをつける。具体的には、令和3年度税制改正が導入されたコロナ特例(売上が2%減少していても、試験研究費が増加している場合には、法人税額の控除上限を5%上乗せする措置)を令和4年度末の期限をもって廃止した上で、下記の通り増減試験研究費割合の増減に応じて上下する仕組みとする。控除上限は最大で30%、最小で20%となる。これを図示すれば図3の通りとなる。増減試験研究費割合が「−12%まで」「−4%〜+4%まで」「+12%以上」では控除上限が一定となる“踊り場”を設ける。
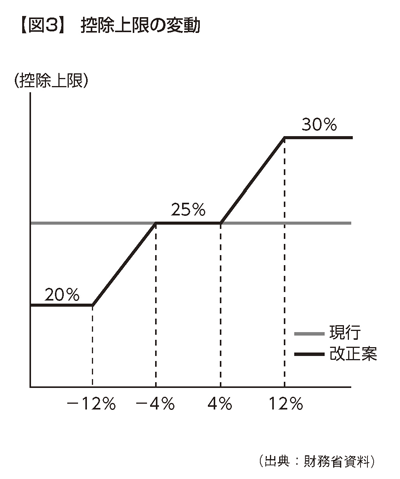
増減試験研究費割合が4%を超える部分
1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする)を加算
増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る部分
1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする)を減算
ミニマム課税
他国が軽課税所得ルール早期導入なら、12月決算法人等にUTPR発動の恐れは
国際課税については、デジタル課税第2の柱、多国籍企業グループに対する所得合算ルール(IIR)の令和5年度改正での法制化が打ち出された。ただし、準備期間も考慮し、令和6年4月1日以降開始事業年度から適用する。
この制度の対象となる「特定多国籍企業グループ等」は基本的には連結グループ全体の売上高が日本円で約1,000億円(7億5,000万ユーロ相当額)以上の企業グループである。各法域・国ごとの「国別実効税率」が「基準税率」(15%)を下回っている場合に、15%に達するまでの金額を「当期国別国際最低課税額」とし、これをその法域・国に所在するグループ会社の「個別計算所得金額」で按分して「会社等別国際最低課税額」を計算し、その金額のうち最終親会社に帰属する持ち分割合に応じた金額を合計したものが、課税ベースである「国際最低課税額」となる。これに対して1,000分の907の税率で法人税が課税され、法人税額の907分の93の税率で地方法人税が課税される。法域・国別のグループ計算を行った上で個社に配分し、さらに最終親会社において合算するという複雑な制度となっている。令和6年1月1日以降開始する事業年度から適用されるのではないかとの観測もあったが、通常の税制改正通り4月施行となる。税制当局は、他国が軽課税所得ルール(UTPR)を早期に導入した場合でも、12月決算法人等が親会社所在地国(すなわち日本)で「IIR未導入」との理由により不当にUTPRが発動されないよう、国際交渉の場でも情報発信していく構えを見せている。
国内ミニマム課税(QDMTT)とUTPRは、第2の柱の詳細がOECDで完全に固まっていないこともあり、令和6年度税制改正以降に先送りとなった。
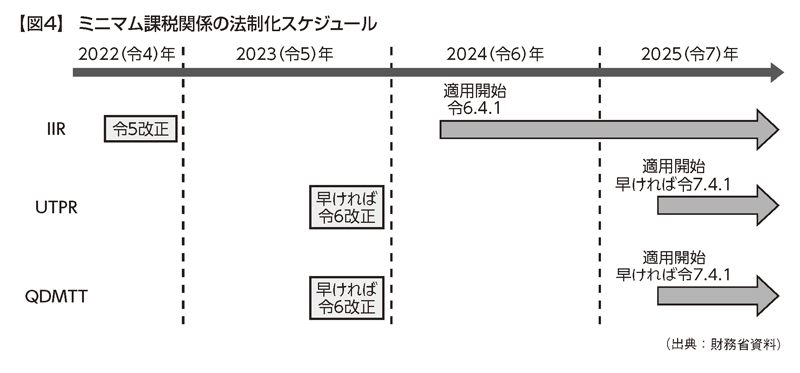
CFC税制の簡素化
税引前利益額に着目するアプローチは頓挫
ミニマム課税の国内法制化に連動して、CFC税制の簡素化が行われる。この点について、経済産業省は昨年8月末の税制改正要望で以下の要望を行っていた。
……企業の事務負担を軽減する。見直しを行う場合には、判定の対象となる外国関係会社の絞り込み、経済活動基準の見直し、最低税率課税制度の実務の利活用、外国子会社合算税制における手続き期間の見直しなどについて見直しの検討対象とする。
このうち、企業側からの要望の声が最も大きかったのが、「判定の対象となる外国関係会社の絞り込み」だ。当初は、外国関係会社の会計上の税引前利益額に着目して、一定金額以下(例えば1億円や数千万円以下)の場合には判定の対象から除外する案も検討された模様だが、サンプル的に我が国の多国籍企業の実態調査を行う中で、税引前利益額が僅少であっても看過できない規模の課税対象金額が生じていることが明らかとなった。税制当局としては、事務負担軽減の結果、現行制度に比べ課税漏れが生じてしまう事態は容認できないところだろう。こうして、税引前利益額に着目するアプローチは頓挫したという経緯がある。
増租税負担割合の計算は残るも、事務負担軽減軽減に向け確かな一歩
結局、30%基準を1割引き下げることとなったわけだが、「27%以上」であることを証明するため、企業としては引き続き外国関係会社の租税負担割合を計算する必要があるという意味において、厳密には「判定の対象からの除外」がされたとは言えず、簡素化の効果は限定的にならざるを得ない。
ただし、日本企業全体で見てみると、27.30%のレンジには、それなりの数の外国関係会社が存在することから、税務調査の対象や申告時に添付対象となる外国関係会社はそれだけ減ることになる。もっとも、外国関係会社が多い米国の場合、27%以上かどうかが微妙で、租税負担割合の計算(特に州税の計算)を詳細に行わざるを得ない恐れがあり、その効果は限定的かもしれないが、この改正はCFC税制の簡素化に向け確かな一歩と言えるだろう。
経済活動基準、手続期間の見直し等見送り、関係書類は添付要件から保存要件に
経産省要望のうち、経済活動基準の見直しについては、結局のところ「事務負担の軽減」とのカテゴリーに留まらない“質的な改正”が必要との判断により、令和5年度改正議論には乗らなかった。
与党大綱(8頁〜)における「外国子会社合算税制について可能な範囲で見直しを行うとともに、令和6年度税制改正以降に見込まれる更なる「第2の柱」の法制化を踏まえて、必要な見直しを検討する。」との記載は、以上の内容をサマライズしている。企業にとっては、改正に向け一縷の希望が行間からにじみ出ている。
なお、今回の改正では、事務負担軽減の一環として、租税回避リスクが少ない部分対象外国関係会社(租税負担割合20%未満であるが、経済活動基準は満たしている外国関係会社)について、部分適用対象金額がないことなどを条件に(つまり合算金額がないことを前提に)、これまで関係書類に課されていた添付要件が「保存要件」に改められた。こちらも事務負担軽減の効果は限定的であるが、税制当局が譲歩した格好だ。
R6年1月1日事業年度開始の特定外国関係会社がR7年3月期の合算免除の対象も
このほか、今回の改正が「内国法人の令和6年4月1日以後に開始する事業年度について適用する」とされている点、注目される。
CFC税制が大幅に見直された平成29年度税制改正は、「外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用する」とされていた。今回の改正の適用時期は、第2の柱の施行時期とCFC税制の簡素化のタイミングを一致させただけということもできるが、例えば租税負担割合が28%である特定外国関係会社について、いつから合算免除になるかというと、令和6年1月1日に事業年度が開始する特定外国関係会社も、令和7年3月期の内国法人の法人税申告において合算免除できるとの見方も可能だ。施行日の趣旨については、税制当局が今後どのように説明をするのか注目しておく必要がある。
事業用資産の買換え特例
申告時の“事後的紐づけ”に、税務当局が問題意識
周知の通り、買換え特例とは、長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について一定の課税の繰延べを認めるもの(措法65の7①四)。同特例の創設は昭和44年度税制改正と非常に古く、減税額も令和2年度で約718億円(国交省の推計)と租税特別措置の中でも比較的規模が大きいことから、適用期限切れの度に縮減の議論に晒されてきた。
近年では、平成27年度改正で、一律80%だった繰延率が縮減され、買換えの類型に応じて3段階に分類された。具体的には、地方活性化の観点から、都市部から郊外への買換えは繰延率80%が維持される一方、郊外から首都圏(東京23区除く)への買換えについては75%、郊外から東京23区への買換えについては70%へと繰延率が縮減されている。
こうした中、令和5年度税制改正では、制度のさらなる規律強化が行われる。改正のポイントとしては、「東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換え」の課税の繰延べ割合を90%(現行:80%)に引き上げる一方、「同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換え」の課税の繰延べ割合を60%(現行:70%)に引き下げる点だ。いずれも、都市部への一極集中を回避するための改正と言える。
また、買換え特例を巡っては、税務当局内に、企業は実際の買換えのタイミングではなく、法人税の申告時に事後的に譲渡資産と買換資産の紐づけを行っているのではないかとの問題意識がある。例えばある事業年度において甲社が資産A及びBを譲渡し、資産C及びDを取得したとする。甲社にとって、Aを譲渡したからCを取得した、あるいは、Bを譲渡したからDを取得したという事業上の因果関係はないが、買換え特例の適用を受けるため、法人税の申告時にAからCへの買換え、BからDへの買換えを行った旨を別表十三(五)に記入した場合、税務当局からすれば、甲社は申告時にAとC、BとDを紐づけているに等しい。
このような行為が常態化すれば、買換え特例の政策効果(買換えの喚起による事業再構築等の推進)は十分に発揮されないことになる。そこで令和5年度税制改正では、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産を交換した場合の課税の特例を除き、①譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(四半期)の末日の翌日以後2月以内に本特例の適用を受ける旨、適用を受けようとする措置の別、②取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等、を記載した届出書を所轄税務署長に届け出ることを適用要件に加える。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















