解説記事2023年03月06日 解説 令和4年最判を踏まえた非上場株式の評価に対する総則6項適用の可否(中央出版HD事件をもとに)(2023年3月6日号・№969)
解説
令和4年最判を踏まえた非上場株式の評価に対する総則6項適用の可否(中央出版HD事件をもとに)
森・濱田松本法律事務所 税理士 間所光洋
森・濱田松本法律事務所 弁護士 安部慶彦
1 はじめに
昨年8月、非上場株式の評価に対して課税庁が財産評価基本通達6(以下「総則6項」という。)を適用し、課税処分を行った事案が、東京地裁に提訴された(本誌959号参照)(以下「本件」という。)。本件は、2022年4月19日最高裁判決(最判令和4年4月19日判タ1499号65頁)(以下「本最判」という。)以降、はじめて裁判所で総則6項の適用が争われる事案となるため、今後の総則6項に関する実務(とりわけ非上場株式の評価における実務)に大きな影響を与える可能性がある。
以下では、本件の事実関係について簡単に触れたうえで、今後想定される争点について検討する。なお、本件は2022年8月2日の提訴後、2022年10月25日に第1回口頭弁論が、2023年1月11日にウェブ期日が行われたばかりであり、本稿執筆時点(2023年1月末)において、当事者による書面としても訴状、答弁書、及び被告側の第1準備書面が提出されているのみである。そのため、本稿において検討した論点が、今後、実際に論点となるとは限らない点に留意されたい。
2 本件の事実関係
本件の当事者は、2014年に死亡したAの子または孫であるX、Y、Z及びWの4名である(以下「Xら」という。)。なお、本件当事者の親族関係は次頁図のとおりである。
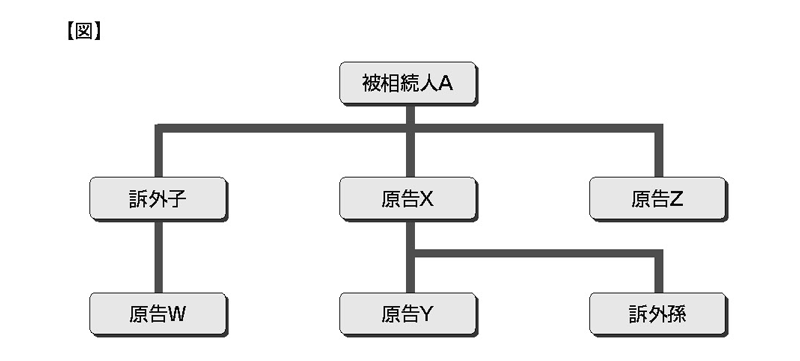
Aは、2014年6月に検査入院をして以降、入退院を繰り返していたところ、同年12月、中央出版HDの子会社から7,300,000,000円を借り入れ(以下「本件借入れ」という。)、翌日、そのほぼ全額を充当する形で、中央出版HDが自己株式として保有していた中央出版HD株式95,780,328株を、1株あたり76円、総額7,279,304,928円で中央出版HDから取得した(以下「本件取得」という。)。その後、Aは、本件取得から9日後(以下「本件相続開始日」という。)に、70歳で死亡した。
Aは相続直前において、中央出版HD株式376,170,184株(うち普通株式335,428,416株、A種株式40,741,768株)を保有しており、Aからの相続(以下「本件相続」という。)により、Xが352,630,184株(普通株式311,888,416株、A種類株式40,741,768株)を、Yが23,540,000株(全て普通株式)をそれぞれ取得した。
Xらは、中央出版HD株式の相続税法上の時価を財産評価基本通達(以下「財基通」という。)に従って1株あたり18円と評価したうえで相続税の確定申告を行った(以下「本件確定申告」という。)(脚注1)。これに対して課税庁は、2018年6月15日付で、総則6項を根拠に、中央出版HD株式の価値を、第三者(D社)による鑑定(以下「本件鑑定①」という。)に基づき1株あたり55円として計算して更正処分を行った(以下「本件更正処分」という。)。本件更正処分の理由は、大要、以下のようなものであった。
・Xらは本件申告において、中央出版HDの株式352,630,184株の価額を、財基通に基づき、347,343,312円(1株あたり18円)としているが、以下の事実から、総則6項に定める「特別の事情」があると認められる。
・中央出版HDが2013年5月に株式移転により設立された際、Aは248,128,710株を取得したが、当該取得の際の中央出版HDの株式の価額を1株あたり67円としていること
・Aは、2013年8月に、中央出版HDの株式24,000,000株を、1株あたり67円で、中央出版HDの関係会社であるB社に譲渡していること
・Aは、2014年12月、中央出版HDから、同社が保有する自己株式95,780,328株を、1株あたり76円で取得していること
・Xは、2016年4月、C銀行から、中央出版HDの子会社の定期預金を担保として65億円を借り入れるとともに、当該子会社との間で質権設定契約を締結し、当該子会社による担保の提供に係る担保として、Xが保有する中央出版HDの株式85,526,316株(普通株式44,784,548株、種類株式40,741,768株)に質権を設定しているところ、当該質権に係る価額として65億円(1株あたり76円)が設定されていること(脚注2)
・中央出版HDは、直前期末において、中央出版HDを中心とするグループ全体で合計約480億円の現金預貯金を保有しているが、中央出版HDの株式の評価について、財基通を形式的に当てはめて評価すると、グループ内の一部の子会社について類似業種比準方式が適用される結果、これらの現金預貯金は中央出版HDグループの評価額に適正に反映されないこととなる。
・D社(大手アドバイザリー会社)が課税庁の依頼に基づき作成した株式価値算定報告書(本件鑑定①)においては、1株あたり55円として評価している。
そこで、Xらがこれを不服として再調査請求をしたところ、改めて第三者(D社)による鑑定(以下「本件鑑定②」という。)が行われた結果、課税庁は、2019年5月7日付で、中央出版HD株式鑑定評価額である46.48円として計算し、本件更正処分を一部取り消す旨の再調査決定をした。
Xらは本件更正処分(再調査決定により一部が取り消された後のもの)を不服として、2019年6月11日、本件更正処分の全部の取消しを求めて名古屋国税不服審判所に審査請求を行ったが、2022年3月25日付で、Xらの審査請求を全部棄却する旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)(脚注3)。
3 本件裁決の概要等
(1)「特別の事情」に関する判断
本裁決は、結論として、総則6項に定める「特別の事情」があるとして納税者の審査請求を棄却した。
その理由付けのうち「特別の事情」に関する部分は、大要、以下のとおりである。なお本稿では紙幅の関係もあり、本件裁決の内容に関する評釈は行わない。
① 乖離について
類似業種比準方式を大会社に適用するのが一般に合理的であるのは、大会社の株式が、必ずしも常に会社の総資産価値の割合相当額で取引されるわけではないからである。しかし、本件で問題となるのは、大会社である中央出版HD子会社(以下「本件子会社」という。)の株式を財産として所有する中央出版HDの純資産価額であるところ、中央出版HD株式について、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、本件子会社の発行する株式(以下「本件子会社株式」という。)についても純資産の価値を反映させた価額を基に取引が成立することは、極めて自然で合理的である。
そうすると、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合、本件相続開始日において、本件子会社株式を類似業種比準方式により評価した1株当たりの時価よりも高い水準の価額が成立するのが通常と推認するのが自然で合理的であり、逆に、類似業種比準方式により評価した価額が通常成立すると認めることは困難である。
② 本件借入れ・本件取得について
本件借入れ・本件取得により相続財産に含まれる価額は55億円を超える圧縮が生じている。たしかに、本件取得の直前における本件会社の株式の価額を財基通に従って算定すると1株あたり12円と認められることから、本件取得によって約17億円の相続財産の増加にも寄与しているものの、これを考慮しても、結果として相続税に係る課税価格を38億円分圧縮させている。
こうした本件借入れ・本件取得は、70歳という高齢に達したAが、自身の病状に関する告知を受け、入退院を繰り返していた時期に行われたものであり、Xらも、こうした本件借入れ・本件取得を遺留分対策で行なったものと主張していることから、本件借入れ・本件取得は、少なくとも本件相続が近い将来発生することを見越して行われたものであることが明らかである。
③ 結論
以上からすると、財基通の評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、かえって、相続発生を見越して本件借入れ・本件取得に相当するような行為を行わなかった納税者との間での実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであるといえることから、他の合理的な評価方法により、中央出版HD株式の適正な時価を評価すべき特別の事情があると認められる。
(2)中央出版HD株式の「時価」に関する判断
本件鑑定②の評価方法についてみると、DCF法、類似会社比準法及び修正簿価純資産法による各評価額を算定しているところ、これらは、日本公認会計士協会による企業価値評価ガイドライン(以下「本件ガイドライン」という。)が挙げる手法であり、本件ガイドラインにおいて実務上一般的とされている評価方法に則ったものである。また、本件鑑定②が前提とした事実に誤りがあるとは認められず、推論の過程にも本件ガイドラインに照らして不合理な点は見当たらない。
加えて、修正簿価純資産法により算定した評価額は、A、B社、及びXが時価純資産価額法により算定し取引に用いた1株67円及び76円より相当低い水準となっており、これをDCF法及び類似会社比準法による各評価額との総合評価によって、最終的な評価額はさらに低い水準に抑えられている。
以上の諸事情を総合すると、本件鑑定②における評価額は、合理的な評価方法により控えめに算定されたものであり、本件相続開始日において、本件相続株式について、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に、これを上回る価額が成立する可能性はあるとしても、これを下回る価額が通常成立すると認めることは困難であるから、時価を上回るものではないと認められる。
(3)本件借入れ・本件取得による相続財産の「圧縮」とその仕組み
本件借入れ・本件取得による相続財産の圧縮は、主に、本件借入れにより取得した73億円の金銭が本件取得により中央出版HD株式に変わっているところ、本件取得においては所得税法上の評価額である1株当たり76円で評価しているのに対して、本件相続に際しては相続税法上の評価額である1株あたり18円で評価していることによるものと考えられる。
そして、所得税法上の評価額と相続税法上の評価額との差額は、中央出版HD子会社のうち財基通上は大会社にあたるものが、所得税法上の評価においては小会社に該当するものとして扱われ、その結果、類似業種比準方式を採用することができる割合が50%とされていること(残りの50%は純資産価額方式が採用される。)に起因していると考えられる(所基通59−6(2))。
なおXらは、本件確定申告において、本件借入れに係るAの債務73億円の全額を控除している。
4 本最判の概要等
(1)本最判の概要
まず、本件について具体的な検討を行う前に、本最判の内容を簡単に紹介する。
本最判は、金融機関からの借入れを行ったうえで、被相続人の相続直前に相続税の負担を軽減させる目的をもって取得された収益不動産の相続税法上の評価について、総則6項の適用が争われた事例である。本最判は、総則6項の適用に関して、論点を①相続税法22条の「時価」と②平等原則とに分類し、大要、以下のとおり判示した(引用部分中の下線部・括弧内筆者)。
① 相続税法22条について
相続税法22条の「時価」とは「当該財産の客観的な交換価値」をいい、評価通達は「上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達であって、国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たら」ない(判事事項①)。
「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条[相続税法22条]に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されない」。
② 平等原則について
「評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである」。
「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である」(判事事項②)。
本件各不動産について「本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離がある」ことをもって、上記の「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」があるということはできない。もっとも、(i)本件各不動産の購入及びその購入資金の借入れが行われなければ「本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきであ」り、(ii)被相続人及び納税者は、収益不動産の購入と、購入のための金融機関からの借入れ(以下「本件購入・借入れ」という。)が「近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえ」、「本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきである」(判事事項③)。
(2)課税庁における総則6項の判断基準(脚注4)
① 課税庁における従前の判断基準
総則6項は、「財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められること」を「実体要件」として定めている。本最判に至るまでの過去の裁判例・裁決例の多くで、この「実体要件」について、「……例外的に、評価通達による評価方法によらないことが正当と是認される特別の事情がある場合」と判示されており、「著しく不適当」と「特別の事情」は実質的に同義のものとして解されていた。総則6項の適用が争われた事案は、そのいずれもが事例判断とされており、過去の裁判例・裁決例から一般的意義を抽出することは困難であった。
もっとも、本最判の前に税大論叢80号に掲載された論文では、「特別の事情」が認められた事案からその判断基準とされた要素を抽出し、以下の4つの判断基準をもとに総合的に「特別の事情」の有無を判断する見解が示されていた(脚注5)。
(i)評価通達による評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること(評価通達による評価の合理性の欠如)
(ii)他の合理的な時価の評価方法が存在すること(合理的な評価方法の存在)
(iii)評価通達による評価方法に従った価額と他の合理的な時価の評価方法による価額の間に著しい乖離が存在すること(著しい価額の乖離の存在)
(iv)納税者の行為が存在し、当該行為と(iii)の「価額の間に著しい乖離が存在すること」との間に関連があること(納税者の行為の存在)
上記の判断基準は、著者の個人的見解とはいえ、課税庁の担当者が過去の裁判例等から導き出したものであるため、実務において、総則6項の適用可能性を検討するに際して、これらの判断基準が参考にされることが多かったと思われる。
② 本最判を受けた総則6項の判断基準
上記(1)で示した本最判の判示内容を受けて、国税庁が総則6項の判断基準の一部を変更する、あるいは変更したとする報道が見受けられる。これらの報道の内容について、課税庁から公表された情報はなく、正確性についての担保もないことから、本稿では新たな基準に関して検討することは控えることとする。ただし、変更後においても従来の判断基準(iii)と同様に、「著しい乖離」の存在が要求されているようであるが、これは、本最判における判示事項との関係において問題となり得ることから、従来の判断基準(iii)を前提に、「著しい乖離」に関してのみ以下で簡潔に検討する。
この「著しい乖離」を巡って、本最判は、乖離があることを認定しつつも、そのことをもって「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」であるということができないと判示している。また、最高裁判所調査官が本最判を解説した記事(以下「解説記事」という。)においても、「実質的な租税負担の公平という観点からは、同様のかい離は類似の不動産にも広く存在し得る以上、これを相続する潜在的な他の納税者と同じく通達評価額によったとしても租税負担の均衡が害されることはな」(脚注6)いとしている。こうした点からすると、「著しい乖離」は平等原則に関する検討を行うにあたっては考慮要素とはならず、もはや総則6項の判断基準に入る余地がないようにも思われる。
もっとも、従来の判断基準(iii)を含む総則6項の判断基準は、あくまでも課税庁内部で総則6項の適用可否を判断する際に依拠する内部基準に過ぎない。そして、課税庁の判断として、そもそも是正が必要となるような著しい乖離が存在しない事案については、総則6項の適用を想定していないものと考えられる。
本最判及び解説記事を踏まえると、「著しい乖離」の存在を要求する判断基準は、裁判実務上は総則6項の判断基準(平等原則違反の考慮要素)にはなり得えないものと考えられるが、課税庁が本最判後も引き続き「著しい乖離」を判断基準に挙げているのであれば、課税実務上は「著しい乖離」が依然として重要な検討事項の一つになると思われる。
5 想定される論点
(1)本最判の判示事項が本件に及ぶか(本最判の射程)
本最判は、上記のとおり、相続直前に、借入れを伴う収益不動産の取得を行った場合において、当該収益不動産の通達評価額に対して総則6項が適用された事例である。そのため、本件のように非上場株式(中央出版HD株式)の通達評価額に対して総則6項が適用された場合においても、本最判の枠組みが当然に当てはまるとは限らない。実際、一般論として、収益不動産については比較的時価算定がしやすいことに加え、本最判の事例においても、収益不動産を相続発生の直前に取得し、そのうち一部についてはすぐに第三者に譲渡しているなど、当該収益不動産の時価に関する基準が明確であったのに対して、本件は純然たる第三者間取引が想定されない非上場株式に関する事案であり、本最判の前提とする事実関係とは異なっているとも言い得る。
この点に関し、被告(国)は、本最判の射程が本件にも及ぶ前提で主張を行っている。実際、本最判の解説記事(脚注7)においては、本最判の判示事項のうち、相続税法22条に規定する「時価」の問題と平等原則の問題との区別に関する判断枠組みや、平等原則に違反しない場合についての法理判断は相続財産一般に妥当するとされており、また本最判の事案に即した判示についても、事例判断ではあるが、その考え方は不動産以外の相続財産が問題となる事案においても参考になるとされている。
本最判の射程に関しては、私見としても、結論として、本件のような非上場株式の評価に関する事案においても射程が及び、又は参考になると考える。まず相続税法22条の「時価」に関する判示(判事事項①)は、相続税法22条の文言解釈であり、相続財産に限定はないことから、当然に本件にも及ぶと考えられる。また相続税法22条における「時価」と平等原則に関する切り分けの問題についても、その理由付けの根拠は、租税法上の一般原則としての平等原則と、課税庁が財基通に従った画一的な評価を行っているという事実(公知の事実)であり、これは非上場株式の評価に関しても当てはまるものである(判事事項②)。そして、本最判の事例判断(「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反すると言うべき事情」に関する具体的な検討部分等)についても、収益不動産と非上場株式との間の差異を考慮に入れる前提であれば、一定の行為を行ったことにより相続税の負担が著しく軽減されていること、被相続人と納税者が租税負担の軽減をも意図して一定の行為をしたこと等の事情が考慮要素となり得る点について、当然、非上場株式の評価に関する事案であっても参考になるものと考えられる(判事事項③)。なお、これらの「事情」については課税庁側が主張立証責任を負うものと考えられる(脚注8)。
そこで以下では、本最判の射程(判断枠組み)が本件にも及ぶことを前提に、想定される論点をさらに検討する。
(2)相続税法22条における「時価」とアドバイザリー会社が算定した「時価」について
ア 相続税法22条の「時価」の考え方
本最判では、相続税法22条に規定する「時価」とは「当該財産の客観的な交換価値」をいうものと判示しており、もし本件において、課税庁による評価額(すなわちアドバイザリー会社の評価額である46.48円)が「時価」=「中央出版HD株式の客観的な交換価値」を上回っている場合には、本件更正処分は相続税法22条に違反することとなる。
しかしながら、例えば上場会社株式のように、ある時点における客観的な交換価値を一義的に決定できる財産や、タワーマンションのように、比較的「取引相場」を観念しやすい財産とは異なり、中央出版HD株式のような、通常、第三者間での取引が想定されない財産については、「取引相場」を観念することは難しく、そもそも「客観的な交換価値」を確定することが可能であるのか、可能であるとしてそれは具体的にいくらであるのかが問題となり得ると考えられる。
この点、本最判は「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条[相続税法22条]に違反するものではな」いと判示している。そのため、理論上は、被告(国)としては問題となっている財産の「時価」そのものを主張立証できなくとも、「時価」より低い価格であると立証すれば足りる可能性がある。本最判をこのように理解すると、本件において、被告(国)としては、アドバイザリー会社による評価額が相続税法22条の「時価」より低い価格であることを主張立証すれば足りることとなり、具体的に相続税法22条の「時価」がいくらであるのかを主張立証する必要はないこととなる(脚注9)。
以上の点に関しては、本最判の前になされたものではあるものの、本件裁決の判断(上記3(3))も参考になる。本件裁決は、アドバイザリー会社の評価額について、「合理的な評価方法により控えめに算定されたものであり、本件相続開始日において、本件相続株式について、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に、これを上回る価額が成立する可能性はあるとしても、これを下回る価額が通常成立すると認めることは困難であるから、時価を上回るものではないと認められる」としており、これは上記と同様の理解に立つものであると考えられる。
なお、本件裁決でも明示されている点であるが、A及びXによる一連の取引(上記2参照)における評価額(1株あたり67円または76円)が、相続税法22条の「時価」、すなわち「客観的な交換価値」とみられているものではない点には留意が必要である。すなわち、AとXとは親族であり、かつ、中央出版HDは同族会社(法人税法2条10号)であることから、これらの取引において用いられた評価額をもって、直ちに相続税法22条における「時価」とすることはできない。したがって、例えば本件鑑定②における評価額が67円より低いことをもって、相続税法22条に違反しない、という立論は直ちには成立しないこととなる。
以上を前提に、本件を離れて一般論として検討すると、本最判以前から、課税庁としても、非上場株式の評価としては「固い」評価、すなわち、確実に相続税法22条の「時価」を下回ると言い得る評価をもって課税処分に及んでいたものと考えられ、本最判の枠組みを踏まえれば、こうした傾向は今後も続くものと思われる。そうすると、納税者として相続税法22条違反を争うためには、課税庁側が主張する「固い」評価が「客観的な交換価値」を上回っていることを主張する必要があることとなるが、評価の前提となる事実に誤りがあったり、評価過程に大きな過誤がある等の事情がない限り、こうした主張のハードルは比較的高いものになると考えられる。
本件においては、被告(国)側がどのようにして、本件鑑定②の評価額が「時価」よりも低いものと主張立証するのか、原告(納税者)側がどのような反論を行うかが注目される。
イ 非上場株式の評価実務と時価
上記アのとおり、相続税法22条違反を争う場合、原告(納税者)としては被告(国)側が主張する鑑定評価額(本件では本件鑑定②の評価額)が「客観的な交換価値」を上回っていると主張する必要がある。そうすると、原告(納税者)としては、(a) 「時価」がいくらであるか特定せず、鑑定評価額の算定に誤りがあることをもって「客観的な交換価値」を上回っていると主張するか、(b) 「時価」を特定し、鑑定評価額がこれを上回っていると主張することが考えられる。このうち(b)については、比較的近接した時点で第三者間取引があればそれを主張することとなるが、こうした取引がなければ、原告(納税者)として別の鑑定評価を取得し、これが「時価」であると主張することとなる。しかしながら、この場合、原告(納税者)側の鑑定評価額と、被告(国)側の鑑定評価額の信用性が争点となる結果、最終的に各鑑定評価額の算定手法の適切性等について主張立証が行われることとなり、これは(a)の場合と大きく変わらないこととなる。
したがって、被告(国)側が鑑定評価を取得している場合で相続税法22条違反が争われるときには、基本的に、鑑定評価額の評価方法の妥当性が争点になるケースがほとんどであると思われる。
実際、本件裁決においても、アドバイザリー会社の評価方法(本件鑑定②)の妥当性について争点となっている。現時点で本件鑑定②にかかる鑑定書そのものは証拠として提出されていないものの、裁判所においても、鑑定書における個別の事項について争われる可能性は十分にある。
例えば、本件裁決においては、非公開株式における流動性プレミアム、種類株式の評価にあたっての議決権や優先配当権の価値、加重平均資本コストの計算、コントロールプレミアム等について多くの議論がなされている。そのため、これらの点について、本件で争点となり、裁判所が一定の判断を行えば、こうした非上場会社における(特に種類株式を利用した)資本政策に関し、一定の指針となり得ることが期待される。
(3)平等原則違反について①−租税負担の軽減の意図
本最判は「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に関して、被相続人と納税者が「近い将来発生することが予想される」被相続人からの相続における「租税負担の軽減をも意図して」不動産の購入と金融機関からの借入れを行ったことを考慮要素の1つとしている。本件でも、もし被相続人が「租税負担の軽減をも意図して」本件借入れ・本件取得を行っていた場合には、平等原則違反の検討にあたって考慮要素の1つとなり得るものと考えられる。
本件裁決においても、納税者が本件借入れ・本件取得の目的は遺留分対策であると主張したのに対して、遺留分対策であった以上、本件相続が近い将来発生することを見越して行われたものであるとしている。
しかしながら、上記本件裁決から明らかなように、被相続人と納税者において、被相続人において近い将来に相続が発生することを予想していたことしか判断しておらず、被相続人や納税者における租税負担の軽減の意図については一切触れられていない(脚注10)。
本最判の判示からは、租税負担の軽減の意図はあくまで「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」に関する1つの事情でしかないようにも読めるが、他方、租税負担の軽減の意図は一切なく、近い将来に相続が発生することを見越して一定の行為を行った結果、偶然、租税負担が軽減された場合にまで総則6項により課税がなされ得ると考えるのは、いささか課税範囲が広すぎるように思われる。少なくとも、本最判の事案から離れても、租税負担の軽減の意図を有していたか否かは、「実質的な租税負担の衡平に反するというべき事情」を判断するにあたって、特に重要な要素の1つであると考えられる。
したがって、本件においても、Xらにおいて、本件借入れ・本件取得が行われるに際し、租税負担の軽減の意図を有していたかどうかは、重要な論点となる可能性がある。
租税負担の軽減の意図に関する証拠として、本最判では金融機関作成の稟議書があり、当該稟議書からすれば納税者が租税負担の軽減の意図をもって金融機関からの借入れと収益不動産の取得を行ったことが明確であったが、本件では、被告(国)が、本件借入れ・本件取得の態様等から、専ら相続税対策のために行われたことが認められると主張するにとどまり、こうした主張を裏付ける証拠は今のところ提出されていない(脚注11)。そのため、被告(国)側が、本件においてどのように租税負担の軽減を意図していたことを立証するのか、注目される。
なお、単純に、相続直前に本件借入れ・本件取得を行ったことをもって、直ちに、租税負担の軽減の意図を推認するのはやや乱暴なように思われる。また、これに関連して、本最判の解説記事(脚注12)は「ここで問題となっているのは、時価にかかる事実の(平等な)認定であり、いわゆる租税回避行為の否認ではない[引用略]。本判決が、上記の判断に当たり、否認の根拠規定の有無や本件購入・借入れの経済合理性等を問題としていないのは、そのためであると考えられる」としている。また、本最判の解説記事(脚注13)においても「一定の行為がされた結果、通達評価額によると客観的に租税負担が著しく軽減されることを前提に、当該行為が租税負担の軽減をも意図して行われたものであることを指摘するものであり、主観的な意図のみによって合理的な理由を認める趣旨ではない(意図の強さが軽減の程度を補完するものでもない)と思われる。……軽減される相続税の額やその割合を総合的に考慮して、正に「著しい」といえる場合に限る趣旨と解される」としたうえで「明確なスキームの企画・実行と行ったことまで必須とするものではなく、かつ、他の意図・目的とも併存し得ることを前提としていると考えられる」としている。しかしながら、租税回避行為の否認ではないことは、直ちに経済的合理性等を問題としないことには繋がらず、本最判以外の事例においては、平等原則違反を検討するにあたり、本最判が考慮要素としなかった経済合理性等が考慮要素となる可能性は十分に考えられる。また、仮に経済合理性を全く問題にしないのであれば、わずかでも租税負担の軽減を意図していれば、租税負担の軽減をも意図していたこととなる可能性があるが、このように考えてしまうと、結果的に相続税額が減少するような取引全てが、租税負担の軽減をも意図して行ったことにもなりかねず、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」の範囲があまりに広くなりすぎてしまうことが懸念される。
(4)平等原則違反について②−鑑定評価額を全ての相続株式に適用することの是非
本最判が「本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」(判示事項③)と判示していることからも明らかなとおり、平等原則に基づく判断枠組みの検討にあたっては、一定の行為をしない(することのできない)納税者との平等を、その本質としている。
本件においては、本件株式のうち本件借入れ・本件取得に関連する95,780,328株だけでなく、Xらが本件相続において取得した全株式に対して、アドバイザリー会社の評価額である1株46.48円を用い、本件更正処分を行っているが、そもそも本件借入れ・本件取得がなかったとしても、もともとAが保有していた280,389,856株については、財基通上の評価(本件借入れ・本件取得の前であれば1株12円、その後であれば1株18円)に基づいて相続税が支払われていたはずである。
そうすると、現時点で原告からこうした主張はなされていないものの、上記のような平等原則に基づく判断枠組みの本質を前提にすれば、本件借入れ・本件取得と関連しない株式についてまで、アドバイザリー会社の評価額である1株46.48円に基づいた評価を行い、本件更正処分を行うのは、平等原則の枠組みにおいて許容され得ないようにも思われる。すなわち、本件借入れ・本件取得に関連する95,780,328株については1株当たり46.48円で評価した金額と、それ以前からAが保有していた280,389,856株については1株あたり12円(仮に、本件借入れ・本件取得が既存株式に対して与える影響についても実質的な租税負担に関する検討で考慮すべきであれば18円)で評価した金額の合計額である7,816,547,917円(9,498,887,053円)を超える部分については、実質的な租税負担の公平に反しておらず、課税処分は違法とされる可能性も十分に考えられる。
なお、上記の整理においては、同じ中央出版HD株式に対して複数の評価額を用いているが、これはあくまで平等原則の観点からの課税の限度額を計算するためのものであって、一物二価を前提に時価の算定を行ったものではない点に留意を要する。
脚注
1 なお、Xらは更正の請求や修正申告を行っているが、本稿では割愛する。
2 質権に関する詳細は現時点において必ずしも明らかではない。
3 審査請求はX、Y、Z及びWがそれぞれ個別に行っているため、裁決としては4個存在しているが、基本的にその内容は同一であることから、以下ではXに対する裁決を「本件裁決」としている。
4 総則6項の「適用要件」として論じられることもあるが、財基通はあくまで通達に過ぎず法規性はないうえ、その通達に基づいて課税庁が課税処分を行うかどうかの基準でしかないため、本稿では「判断基準」としている。また下記「実体要件」についても同様の趣旨から鉤括弧付きとしている。
5 山田重將「財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について −裁判例における「特別の事情」の検討を中心に」
6 山本拓「判解」ジュリスト1581号95頁 なお、こうしたかい離は本来、評価通達の見直し等によって解消すべきものであり、またかい離を課税庁側が主張しても、それは主張自体失当であるとされている。
7 山本拓「判解」ジュリスト1581号96頁
8 山本拓「判解」ジュリスト1581号95頁
9 なお、本最判においては、その原審において、課税庁の主張する鑑定評価額が、問題となった不動産の客観的な交換価値としての時価であると認定されている。こうした時価に関する事実認定に関しては、事実審において、課税庁の主張額の根拠とされる鑑定等の合理性、信用性を吟味して判断すべきとされており、事実審(下級審)において「時価」を特定する前提に立っているようにも読める(山本拓「判解」ジュリスト1581号94頁参照)。
10 本裁決は本最判が出される前になされたものであるため、このような判断もやむを得ないものと考えられる。
11 被告(国)は、第1準備書面において、被相続人が過去に海外生命保険等を利用した相続税対策プランを実行するなど、かねてから自己の相続税対策に強い関心を持っていたと認められること、被相続人が本件借入れ・本件取得以外にも、遺言の書換え、名義株式の書換え等の様々な行為を行っており、近い将来に被相続人に相続が発生することを予想して各行為を行っていたと認められること、本件借入れ・本件取得は、近い将来発生する被相続人の相続に間に合うように迅速性が重視される一方で、法的な手続きや契約書作成等の事務作業が無視ないし軽視されていたこと、本件借入れの資金は、その実行後に、大半がこれを拠出した関係会社に還流していたことなどから、本件借入れ・本件取得は専ら相続税対策が目的であると認められ、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえると主張している。
12 山本拓「判解」ジュリスト1581号96頁
13 山本拓「判解」ジュリスト1581号96頁
間所光洋 まどころ こうよう
森・濱田松本法律事務所 パートナー。成蹊大学法学部卒業。法人税から所得税まで幅広い税務を取り扱っている。特に事業承継・相続税対策のプランニングを得意としている。事業承継については、株価算定や組織再編のストラクチャー策定から実行支援まで数多くの実績を有する。
安部慶彦 あべ よしひこ
森・濱田松本法律事務所 シニア・アソシエイト。早稲田大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。事業承継を取り巻く法務・税務を幅広く取り扱い、特に信託、遺言等を利用した紛争予防の観点からの相続対策や、相続税を見据えたオーダーメイドのプランニングを得意としている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















