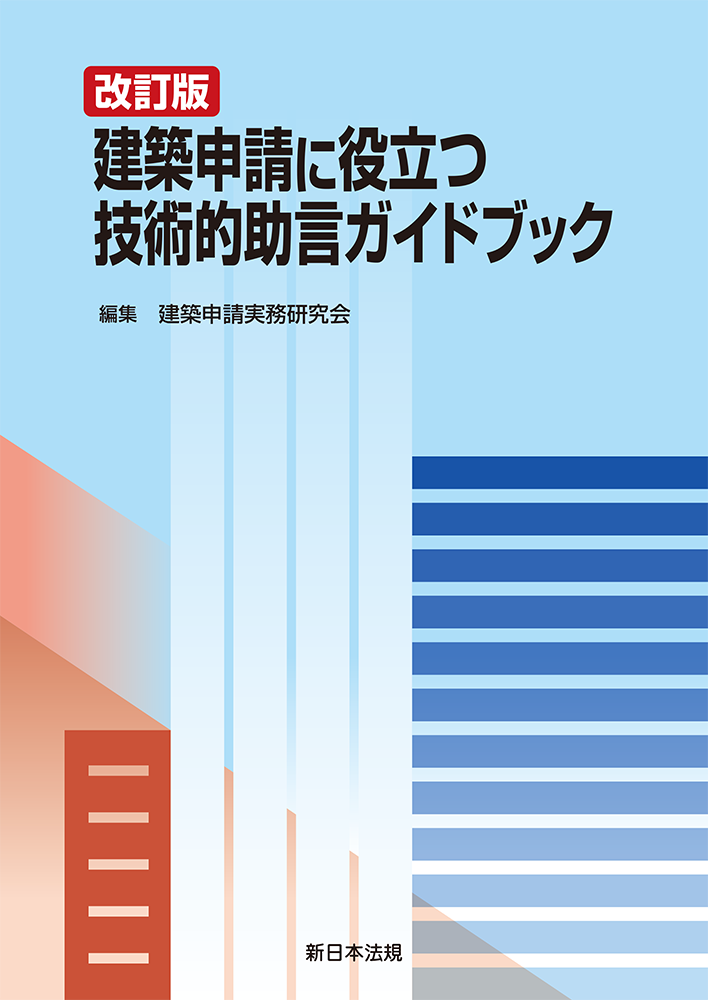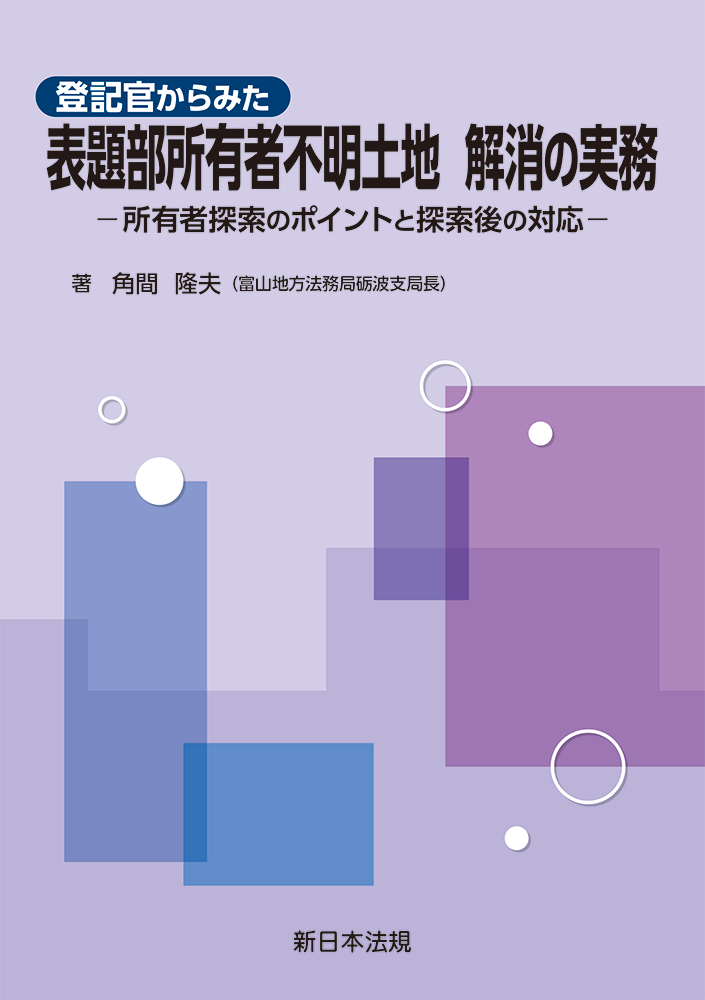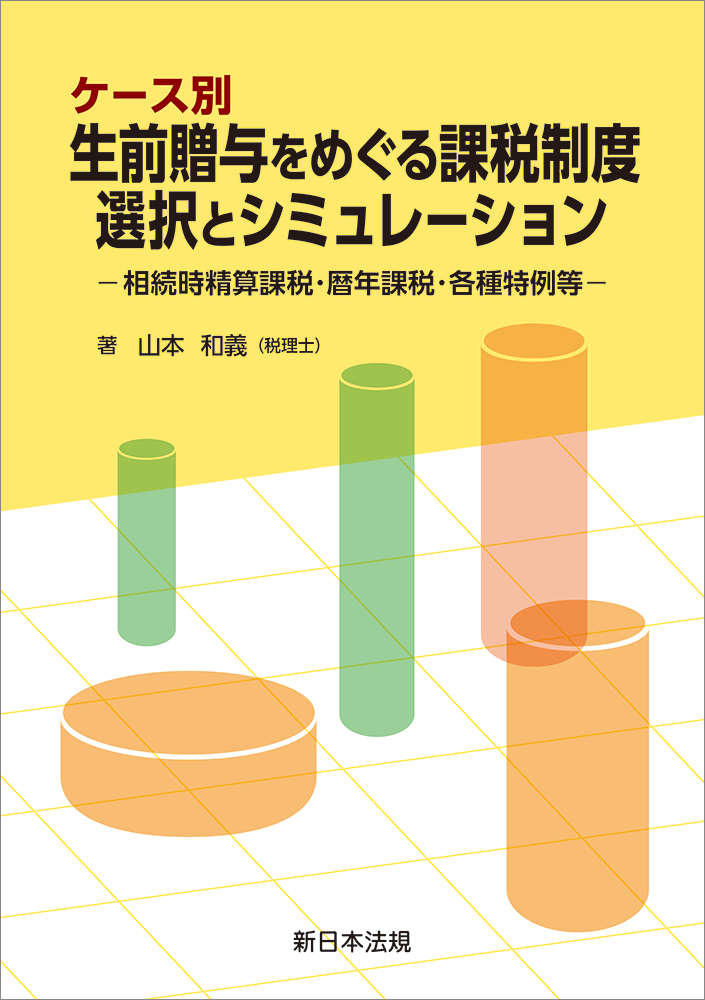解説記事2020年01月13日 ニュース特集 質問応答記録書作成上の重要ポイントが判明(2020年1月13日号・№818)
ニュース特集
記載事項の優先順位、不利益事実の即座録取etc.
質問応答記録書作成上の重要ポイントが判明
本誌ではこれまで「質問応答記録書作成マニュアルの中身とは?」(No.751)、「当局、質問応答記録書で臨場感・迫真性を追求」(No.798)を取り上げてきたが、今般、新たに質問応答記録書作成上の重要事項が判明した。今号の特集では、質問応答記録書に記載すべき事項の優先順位、回答者の答述が変遷した場合・納税者側が不利益事実を自認した場合の対応など、課税当局の資料の内容をQ&A形式で紹介する。
質問応答記録書作成の基本的な手順
1 事前準備
Q1
当局が質問応答記録書作成の準備段階で重視していることは?
A
質問応答記録書は、課税が適法であること、言い換えれば、課税要件事実が存在することを立証するために作成することから、質問応答記録書の作成に当たっては、入念な事前準備が必要であり、具体的には、調査対象事案における「課税要件事実」の分析が必要不可欠としています。なお、事前準備においては、質問応答記録書に記載すべき事項に優先順位を付け、「ここだけは質問応答記録書で証拠化しておく」というポイントを明らかにしておくことも重要とされています。
Q2
事前準備の具体的な事例は記載されていますか。
A
過少申告がなされた事案において重加算税を賦課するケースが例示されています。
その中で、重加算税を賦課するためには、原則的に①過少申告加算税の賦課要件に該当すること、②「納税者」による隠蔽又は仮装行為が存在すること、③当該隠蔽又は仮装行為に基づく過少申告があることの3つの事実が必要であり、③の要件から必然的に導き出される帰結として、②の隠蔽又は仮装行為は、過少申告行為よりも前に存在しなければならないと指摘しています。その上で、納税者による帳簿の破棄という「隠蔽」に該当する行為が存在したとしても、これが過少申告行為より前に行われていない場合には、原則としては、重加算税は賦課できないこととなり(図1参照)、このような場合には、過少申告後の隠蔽又は仮装行為を根拠として重加算税の賦課を認めた判例を分析し、これと調査中の事案を比較するなどして、重加算税の賦課が可能か否かについて慎重な検討が必要になるとしています。
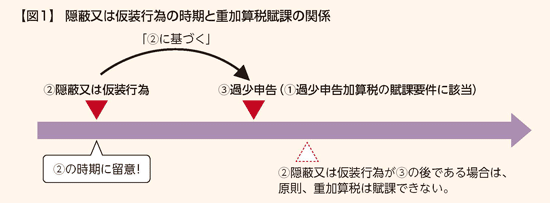
Q3
隠蔽又は仮装行為の時期に注目しているのですね?
A
Q2のとおり、隠蔽又は仮装行為の時期によって、重加算税賦課の可否に関して検討すべき事項が異なることから、質問応答記録書の作成に当たっては、帳簿の破棄という「隠蔽」行為の存在だけではなく、その行為の時期にも留意すべきとしています。
また、質問応答記録書の作成に当たっては、調査対象事案で立証しなければならない課税要件事実を入念に分析し、どのような事実を記載しなければならないのかを十分に整理する必要があり、そのように整理した質問応答記録書に記載すべき事項について箇条書形式の項目メモを作成するなどの方法も有用としています。
Q4
箇条書形式の「項目メモ」とはどのようなものですか。
A
架空外注費事案に係る「項目メモ」の作成例(表1参照)では、質問応答記録書に記載する項目を、(A)必ず証拠化したい項目、(B)できれば証拠化したい項目、(C)余裕があれば証拠化したい項目に区分しています。また、質問応答記録書に記載すべき項目について優先順位を付ける際には、(1)その項目が課税要件事実の存在を立証するために直接必要な事実か否か(2)各項目を立証する他の証拠があるかを意識することが重要としています。
なお、この事例での法人税及び重加算税との関係で立証すべき課税要件事実として、以下が掲げられています。
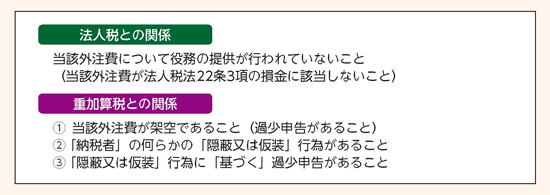
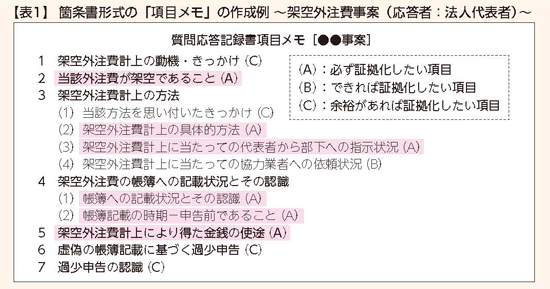
Q5
「項目メモ」の優先順位の理由は示されていますか。
A
Q4中の①~③は、課税要件事実の立証に直接必要な事実であり、これらを立証する明らかな客観的証拠があることも想定し難いことから、質問応答記録書により証拠保全する必要性が高く、優先順位は「A」になるとしています(表2参照)。
なお、②の課税要件事実の立証に関して、過少申告の意図は重加算税賦課の要件とされておらず、過少申告の意図が不要であるとしても、「隠蔽又は仮装」行為自体は故意に行われる必要があることから、これらの項目を明らかにするに当たっては、この点も意識することが重要とされています。
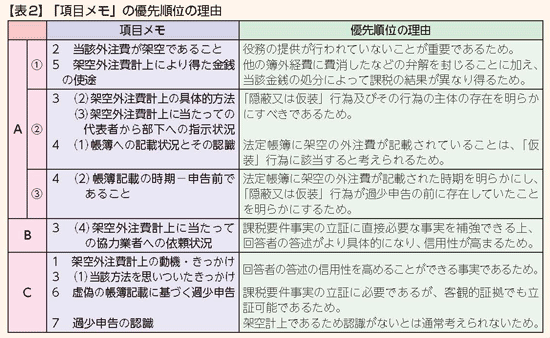
2 質問応答記録書の作成
Q6
質問応答記録書の作成で留意事項とされているのは?
A
まず「事実の要素を明確にすること」を挙げています。「事実の要素」とは、①誰が、②いつ、③どこで、④誰と、⑤何を、⑥なぜ、⑦どのようにしたかなど、「事実認定」を行う上で確定すべき事項を指し、「事実認定」とは、これらの「事実の要素」を信用性の高い証拠によって確定する作業とされます。「事実の要素」を可能な限り明らかにする主な理由は、①課税要件事実の存否を明らかにする、②具体的な答述を得て質問応答記録書の信用性を高めることの2点とされています。また、事実の要素の中で特に重要と考えられるのは、「主体(誰が)」と「日時(いつ)」であり、質問応答記録書に日時を記載する場合には、回答者がどの程度の根拠をもってその日時を答述しているのかを意識する必要があるとしています。
Q7
その他、留意事項として何が挙げられていますか。
A
「評価」ではなく「具体的事実」を記載するとしています。質問応答記録書を作成する目的である課税要件事実の立証のためには、「隠蔽又は仮装」行為の内容となる「具体的事実」を明らかにする必要があるというものです。「評価」の言葉とは、その言葉だけを聞いても具体的な情景が浮かばない表現をいい、例えば、売上除外、架空経費、破棄、隠蔽、隠匿、改ざん、虚偽記載、通謀、合意、管理、取引、指示などとされます。「評価」を表す言葉についてどの程度「評価」の内容となる具体的事実を明らかにしなければならないかは、課税要件や争点、更には、回答者の答述以外の証拠の有無などによって異なってくるとされています(表3参照)。
【表3】具体的事実の記載例
| 良い文例(具体的事実) |
| 私は、平成25年1月から、毎日、現金で受け取った売上げのうち3万円を、事業用のお金の入金や経費に使っている当座預金口座に入金せず、毎日の売上げを記録している売上帳にも記録せず、現金のまま自宅に持ち帰って、寝室に置いている金庫に入れて保管し、遊興費に使っていました。 |
| 私は、平成25年頃から、息子名義の預金通帳、キャッシュカード、届出印を夫の寝室にある金庫に入れており、私が知る限り、この金庫の暗証番号を知っているのは夫と私だけで、この息子名義の預金に現金を入出金するには夫の許可が必要でした。 |
| 社長に「捨てておきなさい」といわれたので捨てました。 |
Q8
回答者の答述の変遷、不利益事実の自認への対応は?
A
質問調査を行う中で、回答者の答述が変遷した場合には、回答者から答述を変遷させた理由を聴取し、これを質問応答記録書に記載して証拠化することを原則としています。特に、当初は不正行為を否定し、正確に申告した旨述べていた回答者がこれを撤回して不正行為を認めるに至った場合には、①これまでの質問調査で虚偽を述べていたこと、②そのような虚偽を述べていた理由、③不正行為を正直に話そうと思った理由を具体的に聴取して質問応答記録書に記載し、証拠化しておくことが必要不可欠としています。
また、調査の中で、納税者側が課税要件事実の立証につながる不利益事実又はその一部を自認した場合には、即座に(当日中に)これを質問応答記録書に録取し、証拠化することが重要としています。
Q9
質問調査で証拠物を示し、説明を求める目的は何ですか。
A
質問応答記録書を作成する際に、入手している重要な「証拠物」を納税者等の回答者に示し、その証拠に関する説明をさせた上で、それを質問応答記録書に記載して証拠化することにより、①その答述に「証拠物」という裏付けを付与すること、②客観的な事実と齟齬する答述を質問応答記録書に記載するという事態を防止すること、③得られた答述の具体性を増すことができるとしています。
また、納税者が売上げなどを記載したとうかがわれるメモのような、その証拠物のみでは一定の事実の立証をすることが困難な場合には、メモの記載内容から不正計算に関係することは予想できても、具体的に何を意味するのか分からないため、記載された内容一つ一つの意味を問い、メモを書いた本人しか知らない意味を詳細に聴き取るとしています。
質問応答記録書作成における重要事項
Q10
答述の証拠化で作成する質問応答記録書と調査報告書の違いは?
A
質問応答記録書は、その記載内容について、答述したとおり誤りがない旨の回答者による確認を経た上で、その確認作業の証として回答者による署名・押印(指印)を受けるものであるのに対し、調査報告書は、回答者の答述内容を調査担当者が記載したに過ぎず、その記載内容について、回答者の確認を何ら経ないものとされます。
訴訟等において、回答者から「そのような答述はしていない。」などと主張された際に、質問応答記録書の場合には署名・押印(指印)の存在を理由に的確な反論が可能となるのに対し、調査報告書の場合には的確な反論が困難になる(言った言わないの水掛け論となる)ことから、回答者の署名・押印(指印)のある質問応答記録書は、それがない調査報告書よりも証明力(信用性)が格段に高い証拠とされています。
Q11
署名押印のない質問応答記録書の位置付けは?
A
質問応答記録書は、最終的に回答者に内容を確認させて署名・押印(指印)を得ることを前提にして作成されるものであり、署名・押印(指印)のない質問応答記録書であっても、回答者による内容確認を経ることになるため、回答者の署名・押印(指印)を得ないことを前提に作成される調査報告書とは、この点において違いがあるとしています。
また、質問応答記録書に署名・押印(指印)がない場合でも、その奥書に記載内容に誤りがない旨及び記載内容に誤りがないにもかかわらず、署名・押印(指印)を拒否した具体的理由が記載されている場合には、回答者が質問応答記録書に記載された内容の答述を行った蓋然性が高いと判断される可能性が高まるとしています(図2参照)。
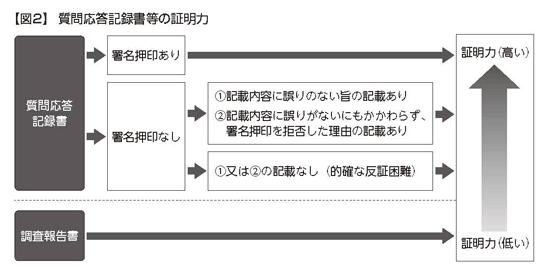
Q12
当局が質問応答記録書の作成を断念するケースはありますか。
A
回答者が質問応答記録書への署名・押印(指印)に難色を示している場合であっても、質問応答記録書を作成した上、署名・押印(指印)をするよう説得すべきであり、回答者が署名・押印(指印)しなければ証明力は調査報告書と同じであるなどと即断し、質問応答記録書の作成を早々に断念することがあってはならないとしています。
他方、例えば、回答者や関与税理士が、質問応答記録書を作成してもその内容確認には応じない旨明言しているなどの場合にまで質問応答記録書の作成を強行することは、回答者の意向を無視して質問調査を行っていると受け取られかねないため、そのような場合には、回答者の答述内容を記載した調査報告書を作成することもやむを得ないとしています。
Q13
質問応答記録書の作成状況はどのように記録されますか。
A
質問応答記録書を作成した場合に、その旨を上司に報告するための調査報告書の作成に際しては、事後に回答者等から「長時間にわたる質問調査が行われ、回答者が疲弊したことに乗じて質問応答記録書に署名・押印(指印)の強要が行われた。」などといった弁解を封ずるため、質問調査を行った時間や休憩をとった時間などを記載し、証拠化しておくべきとしています。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -