解説記事2023年06月19日 ニュース特集 税理士等の実態確認、選定理由と聴取の意図(2023年6月19日号・№983)
ニュース特集
主宰会計法人との取引に着目
税理士等の実態確認、選定理由と聴取の意図
税理士法違反行為の未然防止等を目的とする税理士・税理士法人に対する実態確認のマニュアルが判明。税理士事務担当者(実態確認を実施)は、臨場前に「事前準備票」を作成し、着目ポイントを整理する。事前準備段階での検討事項には、税理士等情報せん、過去の調査事績等に加え、税理士等が主宰する会計法人の有無も含まれており、税理士事務担当者には主宰会計法人との取引がある場合の聴取事項も周知されている。また、臨場時は「実態確認メモ」を使用した聴取が行われ、実態確認の終了時には、「税理士等実態確認表・付表」が作成される。
本特集では、税務当局の資料に基づき実態確認の事前準備、臨場時の聴取事項、実態確認表の記載内容などを確認する。
署管内税理士等の5%(上限15件)を目安に
税理士、税理士法人(税理士等)に対する実態確認は、税理士業務の適正な運営を図る観点から、財務省設置法19条に基づき対象者の協力を得て行われる(受忍義務なし)。
実態確認の目的は、税理士法違反行為の未然防止、軽微な違反行為に対する注意喚起とされ、各種情報等があるものの税理士法違反行為が明らかでない場合など、業務執行状況等を個別に接触して確認する必要がある場合に実施される。実態確認の実施件数について、大阪国税局の令和4事務年度における計画件数をみると、自署管内に事務所登録のある税理士(社員税理士、所属税理士を除く)および税理士法人の合計の5%(上限15件)を目安とし、上期に計画件数のおおむね6割を実施するとしている。
情報せん、調査事績等から「事前準備票」を作成
税理士等の実態確認の流れは、事前準備→臨場(実態確認)→調査移行(重大な税理士法違反が認められた場合)となる。
事前準備では、「税理士等実態確認 事前準備票」が作成される。その際、税理士事務担当者は、①税理士名簿、②事務員名簿、関与先一覧、③税理士本人の申告書、決算書等、④税理士等情報せん、⑤過去の税理士調査事績等、⑥定例会等の出席状況、⑦研修の受講状況、⑧e-Taxの利用状況、⑨書面の添付状況(税理士法33条の2)、⑩地図、⑪現地確認(できれば)、⑫会計法人他、税理士の主宰法人の有無、⑬関与先の過去の調査事績、⑭HPの有無、比較広告の有無などを検討し、着目ポイントを絞り込んでいる。
なお、「事前準備票」には、税理士等に対する実態確認の選定理由も記載されている(表参照)。
【表】実態確認の選定理由
イ)懲戒処分により業務停止期間中の者・懲戒処分後業務を再開した者 |
聴取事項を列記した「実態確認メモ」を使用
通則法に基づく調査手続なし
前述のとおり、税理士等の実態確認は、財務省設置法19条に基づいて行われるものであり、国税通則法に基づく調査手続等はない。この点、税務当局は、事前連絡等において、「先生の業務内容等(日頃の業務)を確認させていただきたい」「事務員等に対する管理監督体制など確認させていただきたい」などと説明し、協力を得るとしている。
見取り図でPC設置状況を確認
臨場時(実態確認)には、概況聴取(経歴、開業の経緯、支部定例会出席状況)および「実態確認メモ」(聴取事項を列記)を使用した聴取が行われる。
具体的には、実態確認メモにより、①従業員、関与先の増減、②関与の程度、訪問状況、③担当者別一覧表、④給与支払状況、給与の決め方、⑤内部管理体制・就業規則の確認、⑥業務処理簿、⑦印鑑、ICカード、税理士証票の確認、⑧事務所見取り図の作成、⑨本人申告書作成方法、⑩犯罪収益移転防止法適用の有無が確認される。
そのほか、実態確認メモには、「使用人の源泉徴収」(税理士が会計法人を主宰している場合、使用人が従事する業務内容により給与負担を税理士たる個人と会計法人で分担すべき場合が生じる)、「税務相談」(税務相談には誰が応じているか。使用人が相談した場合の税理士への報告手段、方法の確認)等の聴取事項も記載されている。
主宰会計法人、2つの取引形態を念頭に聴取
また、臨場時には、税理士等と関連する会計法人の状況等も聴取される。事前準備段階で税理士等が主宰する会計法人の有無を確認するのは前述のとおり。
税理士事務担当者は、主宰する会計法人との取引がある場合、2つの形態(図参照)を念頭に関係書類等をチェックし、以下の事項を聴取する。
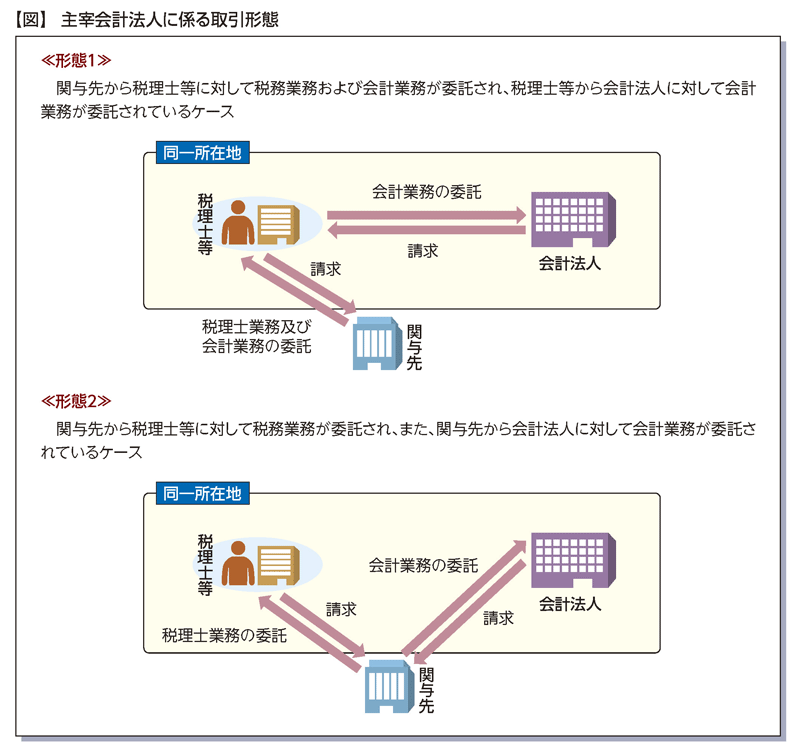
・会計法人の従業員等が税務書類の作成等を行っていないか(税理士等と会計法人の従業員の従事業務を聴取)
・会計法人が一括して業務を受託していないか(契約内容の確認)
・会計業務を行う税理士法人の社員税理士は、会計法人の無限責任社員または取締役に就任していないか(税理士法人および会計法人の定款を確認)
・税理士等の業務と会計法人の業務が区別されているか(それぞれの業務の流れおよび使用人の業務内容等を聴取)
・会計法人が直接関与先と接触していないか(委託業務の流れを聴取)≪形態1≫
・会計法人が一括して税務業務の委託分まで関与先に請求していないか(税理士と関与先、税理士等と会計法人の関与先への請求書および契約書を確認)≪形態2≫
主宰会計法人に委託の場合、確認表付表を作成
実態確認の終了時、税理士事務担当者は、実態確認メモ、業務処理簿、源泉徴収簿、日報・業務日誌、見取り図等から「税理士等実態確認表」を作成し、会計業務を主宰会計法人に委託している場合は、「税理士等実態確認表付表」を作成する。
なお、実態確認表に記載した内容以外で、後日に残すべき事項(税理士の人柄、情報せんの具体的な解明内容、指導事項の詳細、税理士主宰法人の状況等)は、「概況メモ」に記載される。
「税理士等実態確認表(税理士用)」、「税理士等実態確認表付表(会計法人用)」の記載要領(一部)については、下記を参照。
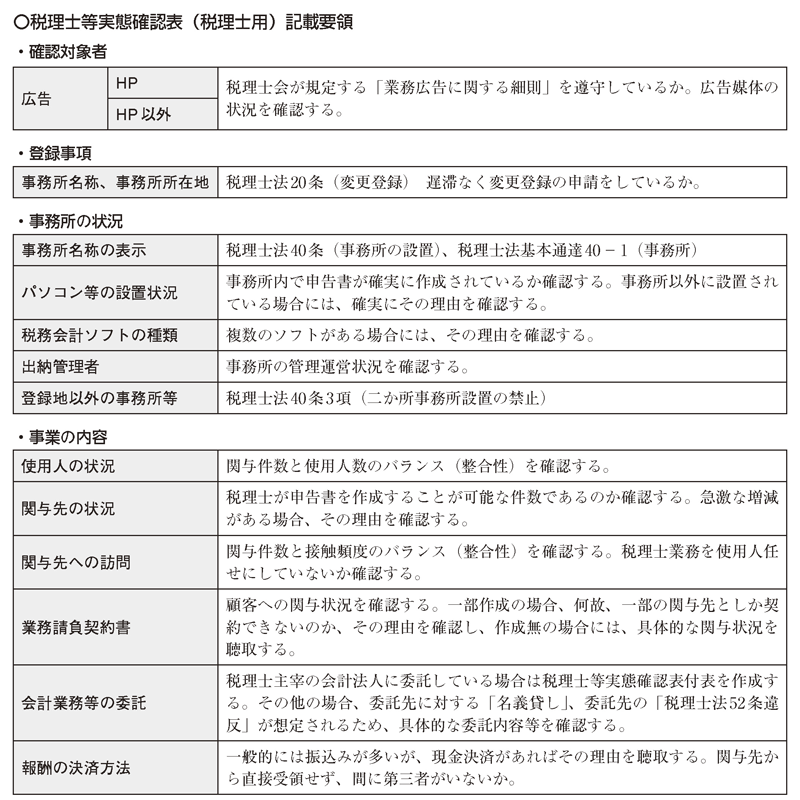
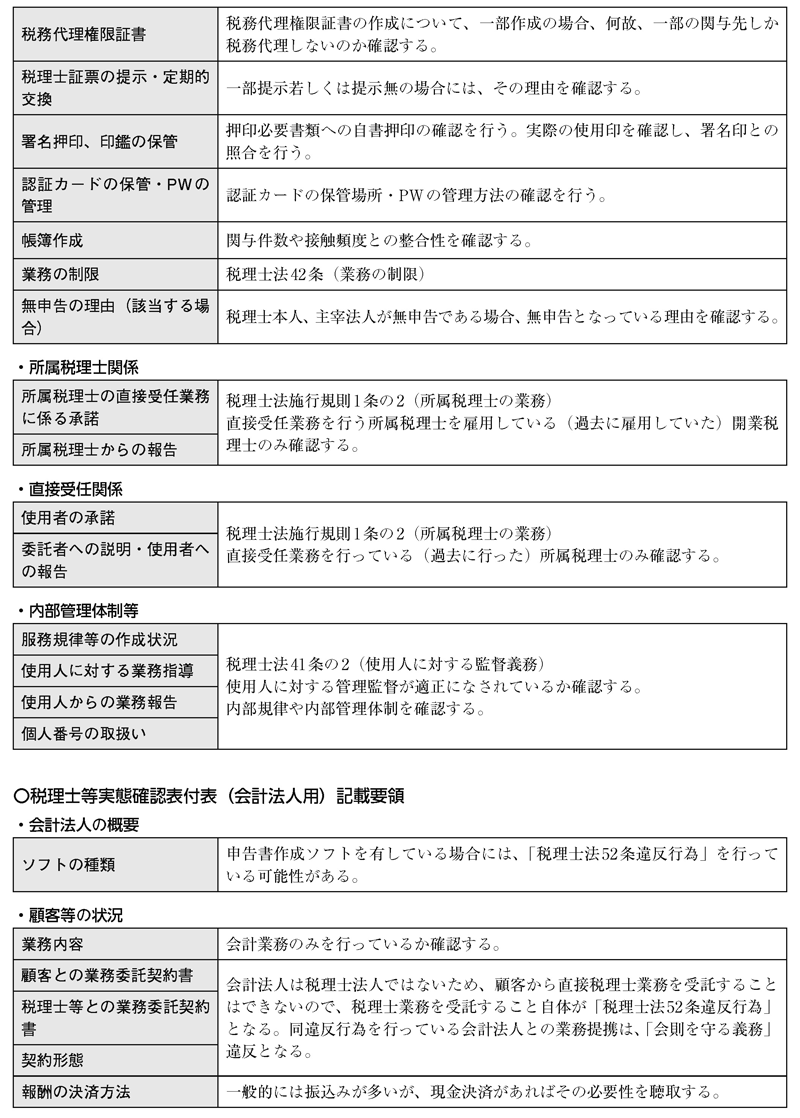
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























