解説記事2023年08月14日 巻頭特集 鼎談 信託型ストック・オプションに関する国税庁見解の法的検討(前編)(2023年8月14日号・№991) ~国税当局への照会制度の課題の検討を兼ねて~
巻頭特集
鼎談 信託型ストック・オプションに関する国税庁見解の法的検討(前編)
~国税当局への照会制度の課題の検討を兼ねて~
北海道大学大学院法学研究科教授 佐藤修二
弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士 木村浩之
JTC東京法律事務所 弁護士 川添文彬
本誌が今年2月初旬に「権利行使時に課税対象とされる」との課税当局の見解をスクープして以来(965(2023年2月6日)号「信託型SOスキーム権利行使時課税 従来の理解を覆すことに」参照)、本見解への驚きの声や真偽を問う声、導入企業がとるべき対応など様々な議論の渦中にあった信託型ストック・オプション(以下、SO)だが、国税庁が5月30日にQ&A、7月7日に改正通達を公表したことで、一時の喧騒は収まりつつある。むしろ、税制適格SO等の要件の解釈及び適用関係が明確化又は優遇されたことを好意的に捉える向きも少なくない。
その一方で、SOを専門とする法律家からは、そもそも税制適格SO等に関するルールと信託型SOの課税関係は別問題であるとして両者を切り離したうえで、信託型SOに対する国税庁見解を疑問視する声が聞かれる。
本鼎談では、企業法務・租税法務を専門とする弁護士を約20年間経験した後、現在は北海道大学大学院法学研究科で租税法の教鞭をとる佐藤修二教授を進行役として、国税庁勤務を経て現在は日本税法学会及び信託法学会に所属し、信託税制に精通する弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナーである木村浩之弁護士、SOをはじめとするインセンティブ報酬について会社法と租税法を統合したアドバイスに数多く従事してきたJTC東京法律事務所の川添文彬弁護士に、信託型SOに対する国税庁の見解に対する法的視点からの検証、法人課税信託との関係、今回話題となった国税当局への照会制度のあり方など、幅広いテーマについて語っていただいた。
※なお、本鼎談は、国税当局や裁判所が同じ見解を有するとは限らないことを前提としたうえで、令和5年7月31日時点までの公開情報のみに基づき、一定の前提事実の下で個人的な意見・見解を述べたものであり、個別企業に対する一切の法的助言を構成しないことに留意されたい。
はじめに
編集部:まず本誌の読者の皆さんに今回の企画の経緯を理解していただくため、佐藤先生から先生方の簡単なご紹介をお願いいたします。
佐藤:わかりました。まず、木村浩之先生は、2005年に国家公務員Ⅰ種試験(当時)を経て国税庁に入庁され、5年ほどのご勤務を経た後、弁護士に転身され、現在は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナーとして、国際租税法、エステート・プランニング等の実務に従事されています。これらのお仕事、特にエステート・プランニングとの関係から信託税制に造詣が深く、私が東京大学法科大学院で教鞭をとっていた時も、毎年、ゲストとして信託税制の話をしていただきました。また国税庁の立場についても、勤務経験に基づく肌感覚をお持ちなので、今回は、とりわけ信託税制や国税庁の立場についてお話を伺いたいと思います。
川添文彬先生は、大手法律事務所の一角を占めるアンダーソン・毛利・友常法律事務所で7年ほどのご勤務を経た後、2年半ほど前に独立してJTC東京法律事務所を設立されました。独立以前から、いわゆるインセンティブ報酬につき、会社法と租税法を統合したアドバイスに多く従事され、現在も、インセンティブ報酬を含むスタート・アップ企業の法務に広く携わっておられるほか、スマート・アワード・ブラザーズ株式会社のCEOとして、リーガル・テックも手掛けておられます。このようなご経歴から、信託型SOのことを伺うには正に最適の方であり、今回の企画の主役と言えます。
最後に、私、佐藤は、20年ほど企業法務・租税法務を専門とする弁護士を経験した後、昨年10月に大学教員に転身し、北海道大学大学院法学研究科で、租税法の授業を担当しております。ただ、株式報酬、信託税制のいずれも難解であり、今回は、木村先生、川添先生の専門的知見もお借りしたく、T&Amaster編集部にお願いのうえ、このような企画が実現したものです。
木村:今回はお招きいただきありがとうございます。佐藤先生にもご紹介いただきましたが、私は2005年に国税庁に入庁し、主に法人税の担当をしてまいりました。入庁後すぐの2006年度に商法改正(新会社法の制定)に伴う法人税法の改正、その翌年の2007年度に信託法改正に伴う信託税制の改正という二つの大きな税制改正を経験しました。今回の鼎談のテーマである信託型SOは信託税制の改正の際に創設された法人課税信託という仕組みが用いられたものであり、大変感慨深いものがあります。2010年に弁護士に転身した後は現在に至るまで、法人税にとどまらず、企業オーナーをはじめとした個人の所得税・相続税の問題などに幅広く対応しております。信託型SOに関しては、2019年に佐藤先生とご一緒した信託の研究会(その成果は2020年に『受益権複層化信託の法務と税務』として日本法令より出版)で信託事例を研究したことをきっかけに興味・関心を持つようになりました。今回はこうした経験を踏まえてお話をすることができればと思います。
川添:佐藤先生、ご紹介いただきありがとうございます。佐藤先生は私のロースクール時代に国税審判官のお仕事について伺わせていただいてからのご縁、木村先生は私の留学先であるライデン大学(オランダ)の先輩でして、今回はご一緒できて大変光栄です。私は、弁護士になった後、企業法務一般、税務アドバイス、税務訴訟案件を中心的に扱っており、留学から帰国した2018年頃から、大手法律事務所において、グローバルな案件を含め、株式報酬制度の導入支援案件に特に多く携わるようになりました。株式報酬制度の導入支援は、私の企業法務及び税務の経験を総合的に活かせる業務分野であったことや、企業の成長に貢献できる仕事であることに意義・やりがいを感じるようになりました。そのため、2021年1月に独立した後も、上場・未上場のスタートアップのクライアントを中心に、税制適格SO、有償SO及び株式報酬の導入支援に特に注力しながら、企業法務一般を扱っています。どうぞ宜しくお願いいたします。
信託型SOの概要
佐藤:早速ですが、信託型SOを巡る近時の課税問題につき概要を説明していただけますか?
川添:国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)」(個人課税課情報第7号他4課共同、最終改訂令和5年7月)(以下「国税庁Q&A」といいます。)問3に記載された前提事実が、実務上用いられている全ての信託型SOとの関係で正しい事実関係なのかどうかは分からないのですが、今回は国税庁見解の法的検討がテーマですので、国税庁Q&A問3【税制非適格ストックオプション(信託型)の課税関係】に記載された事実関係を前提といたします。
国税庁Q&A問3は、信託型SOにつき表の事実関係の下で、表の「課税関係(国税庁の見解)」の列に記載のとおり、役職員によるSOの権利行使時に給与所得として課税されるとしています(以下、この解釈を「国税庁見解」といいます。)。
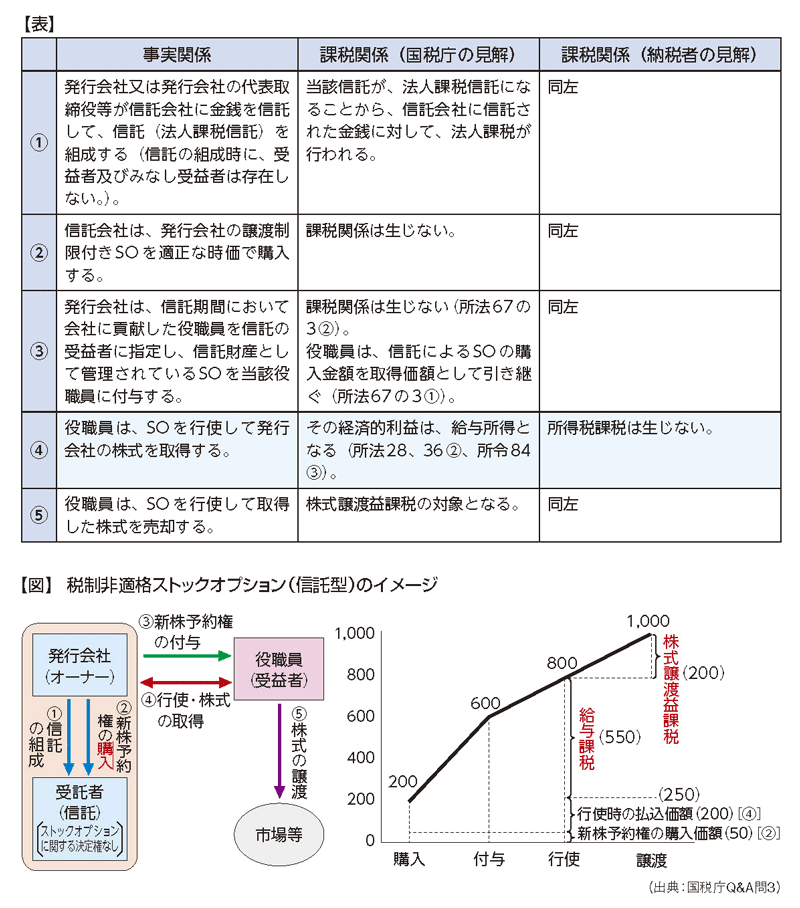
他方で、従前、表の④の時点(SOの権利行使時)においては、有償SOと同様に、役職員に所得税課税は生じないとの解釈が提唱されていました(以下、この解釈を「納税者見解」といいます。)(脚注1)。この点が国税庁見解と納税者見解の相違点になっています。
佐藤:概要をご説明いただき、ありがとうございました。信託型SOは、信託を用いたインセンティブ・プランである点に特徴があると思います。今、法人課税信託という用語が出てきましたが、法人課税信託という制度の概要や課税の考え方につき、信託税制に造詣の深い木村先生からご説明いただけないでしょうか。
木村:先ほど触れました2007年度の信託税制の改正では、信託の受益者が信託財産を所有するものとみなして受益者に課税することを原則としました。これを受益者課税の原則といいます。ところが、受益者課税の原則では不都合が生じる場面が想定されました。その1つが、信託型SOで採用されている受益者の存しない信託です。受益者が存在しないわけですから、受益者に課税することができません。そこで、受益者に課税するのではなく、その代替として信託を法人とみなして受託者に課税することとされました。これによると、信託に拠出された財産は法人に贈与されたものとして法人税の課税対象となる一方で、その後、受益者が生じた場合には、すでに課税済みの財産が受益者に引き継がれるものとして、特段の課税関係が生じないものとされました。この引継ぎに関する条文をみると、受益者の存しない信託の受益者となった者は受託者から信託財産の帳簿価額を引き継ぐこととされ(所得税法67条の3第1項)、受益者は受託者が信託財産を取得した日において帳簿価額に相当する金額で信託財産を取得したものとみなされます(同法施行令197条の3第2項第1文及び第2文)。そして、受益者はその引継ぎにより生じた収益の額を認識しないとされています(所得税法67条の3第2項)。
所得税法67条の3
居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2 前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
信託型SOの課税問題に対する全体的な見方
佐藤:信託型SOの課税関係を巡り、国税庁見解と納税者見解が異なっているとのことでしたが、実務家として本件についていかなる見方をされていらっしゃいますか?
木村:本件では国税庁は信託型SOが信託を利用することで税制適格SOの要件を回避したものであるとの見方をしているように感じています。しかしながら、税制適格SOは無償SOを前提としたものであり、信託型SOは有償SOを前提としたものですので、比較対象を誤っているのではないかと思います。すなわち、典型的な信託型SOは株価が低い時期に低い発行価額で有償SOを発行した上で、その付与のタイミングに柔軟性を持たせたものであると理解できます。これが実質的に無償SOの付与であって税制適格要件の回避であるというのですが、株価が低いうちに低い発行価額で発行されるものであっても実際に対価が支払われる以上、それは有償SOであって特段問題とされるべきものではないと思われます。
川添:一般的な見方と少し違うかもしれませんが、それを承知で私見を述べます。なお、私自身は、従前より、事後交付型のインセンティブ・プランとしては、未上場スタートアップでも米国と同様に事後交付型の株式報酬(Restricted Stock Unit。以下「RSU」といいます。)を利用する又は利用しやすくなるように税制を整備するのが良いと考えてきたこともあり(脚注2)、その観点からのバイアスがかかっているかもしれないことにはご容赦いただければと存じます。
そもそも日本の税制では、未上場スタートアップが、シンプルに、事後交付型の株式報酬(RSU)を採用しようとすると、役員に対する株式報酬につき損金の額に算入できず(法人税法34条1項2号ロ)(脚注3)、他方で役員は給与所得課税を受けるため、単純な現金報酬に比べて、税務上不利な扱いを受けることになると考えております。特に未上場スタートアップにおいて、事後交付型のインセンティブ・プランを採用したいとのニーズがあるにもかかわらず、それを実現するための経済活動を税制(法令)が阻害している、つまり通常あるべき課税関係よりも不利に扱ってきたことが根本的な問題と考えています。
信託型SOは、そのような不十分な税制(法令)の下で、役職員の貢献度に応じて付与対象者及び付与数・金額を後決めする、つまり事後交付型のインセンティブ・プランを採用するというニーズを満たすために利用されてきたものであると捉えています。信託型SOが、税制適格要件を回避して、給与所得を譲渡所得に転換する租税回避目的で用いられてきたという見方は、少なくとも信託型SOの利用者の意図や実体とは合っていないのではないでしょうか。
昨今の国税庁Q&A、通達の改正等により、税制適格SOの要件の解釈及び適用関係が明確化又は優遇されたため、信託型SOが権利行使時に給与所得課税されても、全体的には望ましかったと見る向きもあるようですが、立法論ではなく、法令の解釈論という観点から見ると、税制適格SOの要件(租税特別措置法29条の2)の解釈及び適用と、信託型SOについての国税庁見解が正しい法令(所得税法28条、36条2項、所得税法施行令84条3項)の解釈及び適用なのかは、全く別の問題ですので切り分けて考える必要があると思います。
そして、本鼎談のテーマである信託型SOについての国税庁見解に対する法的視点からの検証という点では、信託型SOの権利行使時の課税関係は、有償SOの権利行使時の課税関係と同じ課税関係になるのが正しい法令の解釈及び適用であるように思われ、国税庁見解は正しい法令の解釈及び適用とはいえないのではないかという疑問を持っております。
本来は、信託型SOの課税関係を法令の解釈に委ねるのではなく、米国等の主要諸外国のインセンティブ・プランに関する法制度・実務の全体像を十分に調査したうえで、未上場スタートアップを含めて事後交付型のインセンティブ・プランの理想的な在り方を議論・検討し、信託型SO、RSUを含めて、立法機関が正面から立法で明確に税制整備をすることが望ましいと考えております。
信託型SOに対する国税庁見解の法的検討
佐藤:ありがとうございます。全体像については概ね把握できましたので、本鼎談のテーマである国税庁見解に対する法的視点からの検証を行っていきたいと思います。
過去の最高裁判例との関係
佐藤:まず、過去のSOに関する最高裁判例を押さえると、最高裁は、米国親法人がその100%子会社である日本法人の代表取締役に付与したSOの行使時の所得分類につき、給与所得と一時所得のいずれであるかが争われた事案において、当該SOの権利行使益は給与所得になる旨を判示しています(最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁)。そして、国税庁Q&A問3において、「(注1)支配関係のある親会社等から労務の対価として付与されたストックオプションに係る経済的利益についても、給与所得に区分されます。」という記載があり、これは過去の最高裁判決を意識した記載であるとも読めます。
この記載からすると、国税庁としては、過去のSOの最高裁判決からすれば、信託型SOについても、SOの権利行使益が給与所得として課税されるはず、という見解なのかもしれません。過去のSOの最高裁判決と今回の信託型SOの課税問題との関係については、どのようにお考えでしょうか?
川添:ご指摘の「(注1)支配関係のある親会社等から労務の対価として付与されたストックオプションに係る経済的利益についても、給与所得に区分されます。」との記載は、令和5年7月の国税庁Q&Aのアップデートの際に追記されたと理解しており、ご指摘のとおり、過去の最高裁判決を意識した記載であると考えております。もっとも、およそ最高裁判決は事例判断であり、ご指摘の最高裁判決は、重要な点において事実関係が異なる事案、つまり同種の事案とはいえない事案においてまで、SOの行使時に権利行使益が給与所得として課税されるとの解釈を判示したものではないと考えています。
そして、当該最高裁判決の事案と信託型SOの取引では、新株予約権の時価発行の有無及び信託契約の有無等の重要な点において事案が異なることに加えて、当該最高裁判決の扱うSOの権利行使時の所得分類の問題(注:給与所得か、一時所得か)と、信託型SOに対する課税の扱う課税時期の問題(注:SO行使時に所得税課税されるかどうか)が次元の異なる問題であることからすれば、信託型SOの取引に対して、当該最高裁判決の射程は及ばない、つまり当該最高裁判決は、信託型SOにつき行使時給与所得課税になるとの国税庁見解の正当性を基礎付ける論拠にはならないと考えています。
所得分類の問題か、課税時期の問題か
佐藤:今、所得分類の問題と課税時期の問題が異なるとのご指摘がございましたが、信託型SOに対する課税は、所得分類の問題ではなく、課税時期の問題とお考えなのでしょうか?
川添:はい。納税者見解は、そもそもSOの権利行使時において役職員に所得税課税はなされないという見解であるのに対して、国税庁見解は、SOの権利行使時においては役職員に所得税課税がなされ、かつ、所得分類は給与所得として課税されるとの見解であると理解しています。したがって、納税者見解と国税庁見解の本質的な見解の相違点は、SOの権利行使時において所得税課税されるかどうか、つまり課税時期の問題だと考えています。SOの権利行使時において所得税課税されないのであれば、所得分類の問題は生じないと考えます。
木村:私からも補足しますと、所得分類が問題になるのは所得が生じたときであり、まずは所得が生じたといえるかというのが論理的な先決問題であると思います。そして、やや結論の先取りとなりますが、有償SOについて権利行使時に所得が生じないために所得税の課税がなされないのであれば、同じく有償SOである信託型SOについても権利行使時には所得が生じないために所得税の課税がなされないのではないかと思います。ただ、信託型SOが税制適格要件を回避した無償SOであるとみている国税庁としては、税制非適格SOと同様に権利行使時に所得が生じると言わざるを得ないのではないかと思います。
法令の適用関係
佐藤:ありがとうございます。仮に当該最高裁判決の射程が及ばないとしても、それだけでは国税庁の見解が適法ではないという結論は出ないと思いますが、法律上は何が問題になるでしょうか?
川添:国税庁Q&Aにおいて信託型SOのSO行使時に給与所得課税がなされることの根拠法令として掲げられているのは、所得税法28条、同法36条2項及び所得税法施行令84条3項ですので、国税庁見解が、これらの法令の正しい解釈及び適用かどうかが問題になると思います。
これらの法令の内容を見ると、所得税法28条は給与所得の意義及び範囲についての規定、所得税法36条2項は、同条1項の定める「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」を、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする規定です。そして、税務大学校から発刊されている所得税法施行令84条3項(当時は同施行令84条)の研究論文によれば、同項は、権利の行使の日の収入金額を定めていること等から、同項に該当する権利の課税時期が行使時であること及び課税価額を明確にするための規定である旨の考え方がなされているようです(脚注4)。これらを前提にして、信託型SOの課税問題を課税時期の問題と捉えるのであれば、直接的には、新株予約権の課税時期を定めた所得税法施行令84条3項が適用されるかどうかが問題になると考えられます。
所得税法36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
所得税法施行令84条3項
3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(省略)における当該権利に係る法第三十六条第二項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(省略)における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
(省略)
二 会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(省略)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。)当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
(省略)
佐藤:国税庁Q&Aが根拠法令とする所得税法36条2項と、所得税法施行令84条3項との関係はどのように考えればよいのでしょうか? 仮に、所得税法施行令84条3項が適用されなくても、所得税法36条2項を適用して国税庁見解が正当化される余地はありますか?
川添:国税庁Q&A問2【税制非適格ストックオプション(有償型)の課税関係】の有償SOの課税関係の説明の中で、国税庁は、有償SOにつき「当該ストックオプションの行使時の経済的利益(ストックオプションの値上がり益)については、所得税法上、認識しないこととされています(所法36②、所令109①一)。」としています。所得税法施行令109条1項1号は、同項3号と併せて読めば、所得税法施行令84条3項に該当しない新株予約権の行使により取得した株式についても適用される規定ですから、この国税庁の見解からすれば、所得税法施行令84条3項に該当しない新株予約権について、所得税法36条2項を適用して、権利確定時に所得税課税する余地があるとは考えられないように思います。
このことに加えて、今指摘した国税庁Q&A問2の記載からすると、国税庁は所得税法36条2項について収入認識時期(課税時期)を定めた規定と理解しているようであり、また、国税庁見解が、所得税法36条2項及び所得税法施行令84条3項を根拠法令として掲げていることからすれば、国税庁は、所得税法施行令84条3項の法的性質を所得税法36条2項の定める収入認識時期(課税時期)の内容を実施・具体化するために設けられた執行命令であると捉えているように見受けられます。そのような理解からしても、所得税法施行令84条3項の直接的な適用場面において、同条項が適用されないのに、所得税法36条2項を適用して新株予約権の権利行使時に所得税課税することは正当化できないと思います。
所得税法施行令84条3項2号の適用関係
佐藤:結論としては、所得税法施行令84条3項が適用されなければ、国税庁見解は正当化されないとお考えなのですね。それでは、その整理に基づき、本題となる所得税法施行令84条3項の適用の有無につき具体的に考えていきましょう。国税庁Q&A問3には次の記載があり、役職員の金銭等の負担がないことから、いわゆる「報酬」のように見えるので給与所得だ、というのは、素朴な感覚としては分かりやすいのかもしれません。法律上の整理としては、国税庁は、役職員の金銭等の負担がない点を捉えて、役職員が受領する新株予約権(SO)が「役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるもの」(所得税法施行令84条3項2号)に該当する、という見解なのでしょうか?
(注3)税制非適格ストック・オプション(信託型)については、<省略>
・実質的には、発行会社が役職員にストック・オプションを付与していること、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、『給与として課税される』こととなります。
川添:そうだと思います。所得税法施行令84条3項2号の立案担当者の解説によれば、新株予約権が、「役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるもの」(同号)に該当する場合というのは、役職員に対して役務提供に係る報酬債権を付与したうえで、当該報酬債権の払込みに代えて新株予約権が発行される場合が想定されていたようです(脚注5)。信託型SOはこの場合には該当しませんが、国税庁見解は、役職員が金銭等を負担していないという事実を捉えて、役職員が受領する新株予約権(SO)は、報酬らしいということで、「役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるもの」(同号)に該当すると考えているのではないかと思います。この国税庁の考え方自体は、国税庁見解が公表される前の2023年2月の予算委員会でなされた答弁からも推察されるところでした(脚注6)。
しかし、法令の解釈及び適用という観点から分析すると、租税法令上、「報酬」かどうかは新株予約権の権利行使時に所得税課税できるかどうかという課税時期の問題の判断基準ではないですし、また、信託型SOの新株予約権について、受益者となる役職員が金銭等を負担していないという点を捉えて、「役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるもの」(同号)に該当するというのは、私法上の法律関係からも、所得税法上の評価としても、形式的にも実質的にも、無理があるのではないかと思います。
第1に、租税法の規律する経済活動は第一次的には私法によって規律されているところ、租税法律主義(憲法84条)の目的である法的安定性を確保するため、一般的に、課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであると考えられており(脚注7)、その旨を判示した裁判例もございます(脚注8)。第2に、最高裁判例において、所得税の課税(収入)時期は、その収入の原因となる権利が確定した時点であると考えられており(権利確定主義)、かつ、その権利が確定する時期は、その権利の特質を考慮して決定されるものと考えられています(脚注9)。つまり、課税時期の問題は、原則として、権利が確定したかどうかという観点から判断すべき問題であり、ここでいう権利とは、私法上の権利のことと解されます。そして、信託型SOの課税問題が課税(収入)時期の問題であると整理したうえで、これらの判例・裁判例を踏まえるならば、信託型SOの新株予約権が、「役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるもの」(同号)に該当するかどうかも、私法上の法律関係を基礎として考えるべきだと思います。
このことを念頭に、信託型SOの取引の私法上の法律関係をみると、信託型SOの取引においては、私法上、SO(新株予約権)が発行会社から受託者に対してSOの適正な時価である金銭の払込みを受けたことの対価として発行される以上、発行会社が受益者を指定するという事実関係を前提としても、「発行会社から役職員に対して新株予約権が役務提供の対価として発行された」という私法上の法律関係は存在しません。そうだとすると、租税法上も、当該SO(新株予約権)は、「新株予約権(……役務の提供その他の行為による対価であることとされるもの)」(所得税法施行令84条3項2号)には該当しないと考えるのが自然な法令の解釈及び適用であると考えます。また、最高裁昭和53年2月24日判決を踏まえて、当該新株予約権の「権利の特質」を考慮すると、結局、当該新株予約権の内容は適正な時価である金銭の払込みを受けることの対価として発行される新株予約権(会社法236条1項2号)、つまり有償SOなのですから、有償SOと同じように、権利行使時には課税されないと考えるのが自然であるように思われます。
木村:まさにその通りで、国税庁は「実質的に」といいますが、法律上の観点からみると、発行会社は受託者にSOを発行するのであって役職員等に発行するものではなく、また、SOの発行時に適正な対価が支払われる以上、その後の行為が対価となるものではありません。そのような私法上の法律関係を法令上の根拠なくして二重にも無視するというのは、あまりに法形式を無視するものであって問題があるように思います。また、国税庁見解のようにSOの付与を受ける側の役職員等の立場からみて無償で取得したことが無償SOであることの根拠となるのであれば、有償SOを個人からの贈与によって取得した場合も同様と考えざるを得ませんが、そのような解釈には無理があるといえるでしょう。
法人課税信託との関係
佐藤:ありがとうございます。要するに、「報酬」かどうかは新株予約権の課税時期の問題の判断基準ではない、私法上の法律関係としては有償SOなので、課税関係も有償SOと同じように考えるのが正しい法令の解釈及び適用ではないかというわけですね。
ところで、先ほども申し上げましたが、信託型SOについては信託を用いたインセンティブ・プランである点に特徴があると思います。先ほど、法人課税信託につき木村先生にご説明いただきましたが、利用される信託が法人課税信託であることは、法令の解釈に影響するでしょうか?
所得税法施行令197条の3
2 法第六十七条の三第一項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合における同項の信託財産に属する資産については、前項に規定する該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する帳簿価額に相当する金額により取得したものとみなして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。この場合において、同条第一項の法人課税信託の同項に規定する受託法人が当該資産を取得した日を当該居住者の当該資産の取得の日とする。
木村:法人課税信託を用いるとしても、有償SOであるとの性質が変容するものではないでしょう。先ほどお話しした法人課税信託の仕組みでは、まずはSOの発行価額相当額の金銭の贈与を受けた受託者に法人税の課税がなされた上で、その金銭をもって受託者が発行価額の払込みをしてSOの発行を受けますので、これは有償で発行されるSO、すなわち有償SOです。その後、役職員等のうちに受益者となる者が生じた場合、その受益者は受託者がSOを取得した日(すなわちSOの発行日)においてSOを帳簿価額(すなわちSOの発行価額)に相当する金額で取得したものとみなされます。要するに、受益者が受託者の立場を引き継ぐものとされていますので、有償SOについて受益者となる役職員等が取得したものとみなされるSOはやはり有償SOであって無償SOではありません。なお、個人間で有償SOが贈与された場合も同様に、贈与を受けた者が贈与をした者の立場を引き継ぐものとされていますので(所得税法60条1項1号参照)、贈与後も有償SOであるとの性質が変容するものではないと解されます。
川添:私も、木村先生にご説明いただいた「受益者となった者は受託者が信託財産を取得した日において、法人課税信託に該当しないことになった日の直前の帳簿価額に相当する金額で信託財産を取得したものとみなされる」という所得税法の仕組み(所得税法67条の3第1項・所得税法施行令197条の3第2項)からすると、国税庁Q&A問3の前提事実の下での所得税法上の評価としては、受益者となる役職員がSOの発行日においてSOを発行価額と同額で取得したという評価になると思います。国税庁見解のように、役職員が金銭等を負担していないという事実を捉えて、役職員が無償で新株予約権の発行を受けたのと同じように評価することは、この所得税法の仕組み、法令の定めに反する評価であり、形式的にも実質的にも、所得税法上の評価として無理があると言わざるを得ないように思います。佐藤先生のご質問との関係では、信託型SOの信託が法人課税信託であることは、納税者の見解をサポートするものであると考えます。
佐藤:ありがとうございます。結局、私法上の法律関係、所得税法上の評価のいずれの観点からも、役職員が受領する新株予約権(SO)は、「役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるもの」(所得税法施行令84条3項2号)に該当せず、同号に該当しない以上、役職員のSOの権利行使時に所得税課税することはできないのではないかということですね。国税庁見解の「実質的には、……役職員に金銭等の負担がないことなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価に当た」るという評価について、所得税法の仕組みからすれば、所得税法上の評価としては形式的にも実質的にも無理があるのではないかというご指摘は興味深いですね。
信託の濫用か、包括的否認規定(所得税法157条)の適否
佐藤:少し視点は変わりますが、木村先生に冒頭でご指摘いただいたとおり、国税庁としては、税制適格SOの要件(租税特別措置法29条の2)を満たさずに、税制適格SOと同じような課税関係になるという点を問題視したのかもしれません。この点を捉えて、国税庁のQ&Aとは別の理由付け、例えば信託の濫用であると主張する、又は包括的否認規定(所得税法157条)を適用するなどして、国税庁見解の課税関係を導く余地はあるでしょうか?
川添:私も、信託型SOに関する各種報道をみて、木村先生からご指摘いただいたとおり、国税庁は信託型SOを税制適格SOの要件を満たさずに権利行使時の所得税課税を回避する租税回避と捉えているのではないかとの印象を持っております。信託型SOが節税のためだけのプランなのか、あるいは、節税ではない合理的な目的があるのかは裁判所の関心事にもなりうると思います。法律上は、外国税額控除制度の濫用であることを理由にその適用を否定した最高裁平成17年12月19日判決と同様に、信託という法形式や信託税制の濫用と評価されるかどうかや、もし国税当局が包括的否認規定(所得税157条)を適用するのであればその要件充足性などが問題になりうると思います。
しかし、冒頭の方で申し上げたとおり、信託型SOは、役職員に対して業績向上及び勤続維持のインセンティブを付与する、優秀な役職員を採用するというSO一般と同様の目的に加えて、事後交付型のインセンティブ・プランを採用するというニーズを満たすために、新株予約権を信託する仕組みであると理解しております。この目的は、新株予約権と信託を利用するための税目的以外の合理的な目的であると評価することが自然ではないかと思います。
また、信託型SOの制度導入に際して、新株予約権の行使時に所得税課税を受けないという税の考慮があったとしても、私人が税の考慮をしたうえで経済活動をすることは当然ですので、それだけで、直ちに濫用又は租税回避であると評価することは困難と思われます。
信託型SOが、今申し上げたような税目的以外の目的をもって導入されたとすると、そしてそれが信託型SO導入時の資料等から立証可能だとすると、信託契約や信託税制の濫用であるとまでは評価し難いように思います。また仮に国税当局が包括的否認規定を適用しても、ほぼ同様の理由で、「所得税の負担を不当に減少させる」(所得税法157条)とは言えず、包括的否認規定(同条)の要件を充足しないと思われます。従って、これらを理由として、国税庁見解の課税関係を導くことはできないのではないかと思います。
木村:川添先生のご意見に同感です。信託型SOはあくまでも有償SOであって、それが信託であるという理由で否認されるものではないと考えております。
委託者の属性は問題か
佐藤:国税庁Q&A問3は、「発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会社に金銭を信託して、信託(法人課税信託)を組成する(信託の組成時に、受益者及びみなし受益者は存在しない。)。」としており、委託者が発行会社又は代表取締役の場合のいずれをも対象としています。イメージ図をみると、「オーナー」という用語も出てきます。委託者が、発行会社か、代表取締役か、株主か、その他の第三者かによって、課税関係に違いは出てくるでしょうか?
川添:これまで申し上げた考え方からすると、委託者の属性によって左右されるような議論はなく、委託者の属性にかかわらず、国税庁見解は所得税法施行令84条3項2号の課税要件を満たさないのではないかと考えております。その意味で、委託者が誰かによって課税関係に違いは生じないと考えられるように思います。
ただし、委託者が発行会社の役員であり、受益者となる者でもある場合には、仮に法律を離れて生の事実関係だけをみるとしても、SOの時価発行対価の原資を拠出した当該役員が無償でSOを取得したとは評価し難しいようにも思われます。仮に国税庁の見解によっても、このような役員が行使するSOについてまで、権利行使時に給与所得課税がなされる理由はよく分からないように思われます。この点について、もし国税庁としても、信託の委託者としてSOの時価発行対価の原資を拠出した役員・受益者については、有償でSOを取得したと評価できるので、SOの権利行使時に給与所得課税はなされないと考えられるということでしたら、国税庁Q&Aを更に明確化することも考えられるのではないかと思います。
木村:私も基本的には同じ考えですが、委託者が発行会社以外の場合には、国税庁のいう発行会社による実質的な無償付与というのはさらに言いにくいのではないかという気はします。すなわち、委託者が発行会社であれば、その信託の定めによっては発行会社が実質的にSOを付与したという議論も(当該SOが有償SOであるか無償SOであるかという点は措くとして)あり得なくはないのですが、委託者が発行会社でなければ、実質的にも発行会社による付与というのは無理があるのではないかと思われます。
小 括
佐藤:木村先生、川添先生、詳細な議論をありがとうございました。
この問題は、会社法・信託法・租税法が交錯する難解なものであり、私もまだ考えが固まってはいないのですが、大筋で、先生方のご見解に違和感はありません。私は、弁護士であったころから、課税当局に伝統的に見られる「実質課税」の考え方、すなわち、法形式を脇に置いて経済的実態に基づいて課税する、という方向性については批判的でした。おそらくそれは、私に限らず、民事法の感覚を基盤として持っている法曹実務家は皆そうだろうと思います。しかし、ここ10年くらい、そのような「実質課税」は許されないとする裁判例が積み重なっていたので、「実質課税」の考え方は、なりをひそめたと思っていたのです。ところが、今回の国税庁見解は、信託という法形式を無視して、実態は給与であるとして課税するもののように思え、違和感を持っております。
(後編に続く)
脚注
1 松田良成・山田昌史「新株予約権と信託を組み合わせた新たなインセンティブ・プラン(下)時価発行新株予約権信託−」旬刊商事法務No.2043(2014年9月15日号)34頁以下(特に39~40頁)参照
2 川添文彬「オランダ留学で得た知見が租税実務にどう役立つか~ダブル・トリガー・RSUについての覚書を兼ねて~」税務弘報2022年5月号49~51頁
3 経済産業省産業組織課『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~(2023年3月時点版)』Q7
4 原正子「所得税法施行令第84条の考察−個人に係る新株予約権の課税関係を中心として−」税務大学校論叢69号136~137頁
5 青木孝徳ほか『改正税法のすべて』(大蔵財務協会、平成18年)152頁
6 川添文彬「信託型ストック・オプションの租税実務上の諸問題~国税庁の見解を踏まえた対応策の検討~」税務弘報2023年7月号96頁及び99頁
7 金子宏『租税法〔第二十四版〕』(弘文堂、2021年)129頁
8 例えば、東京高判平成22年5月27日判時2115号35頁
9 最判昭和49年3月8日民集28巻2号186頁、最判昭和53年2月24日民集32巻1号43頁
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年、東京大学法学部卒業。2000年、弁護士登録。2005年、ハーバード・ロースクール卒業(LL. M.,Tax Concentration)。2011年~14年、東京国税不服審判所国税審判官。2019年~22年、東京大学法科大学院客員教授。2022年~現在、北海道大学大学院法学研究科教授。
著書に、 『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、 2020)、『夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話』(共著、中央経済社、2020)など。
木村浩之 (きむら ひろゆき)
2005年東京大学法学部卒業、2005年~2009年国税庁(国家公務員一種)、2010年弁護士登録、2016年ライデン大学国際租税センター修了(国際租税法上級LL.M.)、2020年一橋大学法学研究科非常勤講師(担当科目:国際租税法)、現在弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士、日本税法学会理事。
著書に『新版 基礎から学ぶ相続法』(清文社、2022年)、『対話でわかる国際租税判例』(編著、中央経済社、2022年)、『中小企業のための予防法務ハンドブック』(共著、中央経済社、2021年)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(共著、日本加除出版、2020年)、『受益権複層化信託の法務と税務』(共著、日本法令、2020年)、『祖税条約入門 −条文の読み方から適用まで』(中央経済社、2017年)など。
川添文彬 (かわぞえ ふみあき)
弁護士。一橋大学法科大学院(2012年卒)、ライデン大学(ITC Leiden−国際租税法LL.M.)(2018年卒)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所(2014年~2020年)を経て、JTC東京法律事務所代表弁護士(2021年~)、早稲田大学法務教育研究センター講師(租税判例研究)(2021年~)及びスマート・アワード・ブラザーズ株式会社代表取締役CEO(2021年~)。
近時の論文として、「信託型ストック・オプションの租税実務上の諸問題~国税庁の見解を踏まえた対応策の検討~」税務弘報2023年7月号、「未上場スタートアップのストック・オプション及び株式報酬の租税実務上の諸問題~SO及びRSUの活用に向けての環境整備を中心に~」税経通信2023年8月号。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















