解説記事2023年10月23日 ニュース特集 監査法人社員の脱退時における持分割合の算定方法が判明(2023年10月23日号・№1000)
ニュース特集
脱退社員の損益で分配未了のものは加算せず
監査法人社員の脱退時における持分割合の算定方法が判明
無限責任監査法人(被告)の社員であった原告が同監査法人から脱退した際の持分の払戻しの金額が争われた注目すべき裁判で、東京地方裁判所(笹本哲朗裁判長)は令和5年3月30日、脱退時持分割合の算定方法を明らかにし、原告の請求を一部認容した(令和元年(ワ)第27152号)。具体的には、「脱退時の全社員の出資金額+脱退時の全社員に属する損益の額」を分母とし、「脱退時の脱退社員の出資金額+脱退時の脱退社員に属する損益の額」を分子とする比率によることと解するのが相当であるとした。そして、既脱退社員に属する損益で分配未了が存在する場合、当該損益は、既脱退社員に対して払戻し等がされる可能性も残っているため、これを脱退社員に帰属する損益に加算すべきではないとしている。
持分の払戻し額は「脱退時財産額×脱退時持分割合」で算出
本件は、被告である無限責任監査法人の社員であった原告が同監査法人を脱退した際の持分の金額が争われたもの。原告は、監査法人に対し、公認会計士法34条の22第1項において準用する会社法611条に基づき、持分の払戻しとして990万円余りの金額(既払払戻額500万円を除く)を求めた。
なお、原告が脱退した後の社員総会では、原告からの出資金及び持分の払戻請求について、出資した500万円の払戻しのみ行う旨が総社員の賛成により承認されるとともに、脱退社員への払い戻す出資持分について、社員の出資金額とする旨の定款変更が行われた。
主な争点としては、脱退時財産額の評価及び脱退時持分割合の算定方法となっており、当事者の主な主張は表1の通りとなっている。また、持分の払戻しの額については、原則として、脱退時財産額(脱退時における監査法人の財産の価額)に脱退時持分割合(脱退時における脱退社員の持分割合)を乗ずることにより算出すべきことは当事者間に争いはない。
【表1】主な争点と当事者の主張
| (争点)脱退時財産額の評価 | |
| 原告(元社員) | 被告(監査法人) |
| 社員の脱退に伴う持分の払戻しにおいて、法人の財産については、いわゆる帳簿価額によるものではなく、事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額でとらえる必要がある。したがって、脱退時財産額については、DCF方式を加味した価格又は時価純資産を参照すべきであり、後者については、社員脱退時の法人の純資産の時価評価を適切にとらえる必要がある。 本件において被告の脱退時財産は税効果会計を踏まえて評価すべきであるから、その純資産の時価評価としては、繰延税金資産を加味して簿価純資産を修正した価額とすべきである。 |
本件における脱退時財産額の評価については、DCF方式を採ることは適切ではなく、また、純資産法を採る場合には、税効果会計を踏まえて評価すべきとの原告の主張を争う。 税効果会計は、上場会社等以外の企業において、強制適用されておらず、被告において採用している事実もない。本件において被告における脱退時財産額の時価評価としては、簿価純資産と同額であり、これに税効果会計を仮定的に適用して繰延税金資産を考慮すべきではない。 |
| (争点)脱退時持分割合の算定方法 | |
| 原告(元社員) | 被告(監査法人) |
| 脱退時持分割合は、脱退する社員の脱退時における全社員の出資金額のうち、脱退社員の出資金額が占める比率(出資金比率)によるべきである。 | 脱退時持分割合を出資金比率により算定する場合、加入後直ちに脱退する社員を仮定すると、持分を超える額の貢献がないにもかかわらず高額の払戻しをする必要が生ずる場合があり、合理性を欠く。 |
脱退時における簿価純資産額をベースに評価
まず、脱退時財産額の評価について裁判所は、最高裁判決を引用し、監査法人の社員が法人から脱退した場合における払戻持分の計算の基礎となる法人財産の価額(脱退時財産額)の評価は、監査法人としての事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とすべきものと解するのが相当であるとし(最高裁昭和44年(オ)第551号同年12月11日第一小法廷判決・民集23巻12号2447頁参照)、そのための評価方法として、時価純資産法(修正簿価純資産法)を採ることには相当性があるとした。
ただし、本件については、監査法人の資産の中で、時価評価として帳簿価額を修正しなければならないものがあるとはうかがわれず、原告の脱退時における監査法人の簿価純資産額が、時価純資産額と異なるとか、被告の監査法人としての事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とした額と異なるとは認められないと指摘。本件では、原告の脱退時における簿価純資産額を原告の持分払戻の計算の基礎とすることが相当であるとした。
なお、原告は脱退時財産額の評価について、単なる簿価純資産額ではなく、税効果会計を適用した上で行うべきと主張するが、裁判所は、繰延税金資産の計上を前提とした監査法人の財産の価額の評価が、監査法人としての事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とした評価として適切なものということはできないと判断した。
会計士法、脱退社員の有する出資による分け前の払戻しを想定
次に脱退時持分割合の算定方法について裁判所は、公認会計士法は脱退に伴う持分の払戻しについて、脱退社員と監査法人との間の財産関係の清算という観点から、監査法人の純財産額に占める脱退社員の有する出資による分け前(過去に履行した出資の価額や自己に属している利益)の払戻しを想定しているものと解されるとし、監査法人の社員の出資金額及び社員に属する損益を基礎とした持分割合、すなわち、「脱退時の全社員の出資金額+脱退時の全社員に属する損益の額」を分母とし、「脱退時の脱退社員の出資金額+脱退時の脱退社員に属する損益の額」を分子とする比率(出資・帰属損益比率)によることと解するのが相当であるとした。そして、既脱退社員に属する損益で分配未了が存在する場合、当該損益は、既脱退社員に対して払戻し等がされる可能性も残っているため、これを脱退社員に帰属する損益に加算すべきではないとして、裁判所は、表2に掲げた算定方法を示した。
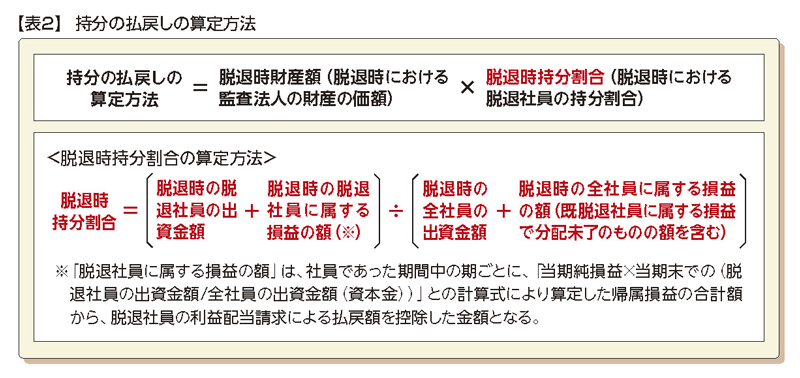
既脱退社員が多数の場合は現実的にあらず
なお、裁判所は、既脱退社員に属する損益で分配未了のものが存在する場合において、脱退社員の持分の払戻しの額を算定する方法としては、①脱退時財産額から既脱退社員に分配されるべき財産額を控除したものに、②脱退社員の脱退時に監査法人に現存する社員の出資金額及び同社員に属する損益を基礎とした持分割合、すなわち、「脱退時の全社員の出資金額+脱退時の全社員に属する損益の額」を分母とし、「脱退時の脱退社員の出資金額+脱退時の脱退社員に属する損益の額」を分子とする比率を乗ずる方法でも、合理的な結論を導くことが可能であるとも考えられるとしたが、①の算定においては、脱退社員の脱退時までに脱退した既脱退社員すべてに分配されるべき財産額の和を算出する必要があり、それには、既脱退社員の各脱退時における監査法人の財産額を計算する必要があるが、既脱退社員が多数に上る場合など、そのような計算を行うことが現実的ではない場合が想定され、合理性を欠くことから採用できないとしている。
そのほか、原告が主張する出資金比率による方法についても、監査法人の財産の状況によっては、脱退社員が過去に履行した出資の価額及び脱退社員に属する損益に相当する財産が払い戻されない事態が生ずることがあり得ることなどから採用できないとした。
持分の払戻額は662万2,731円
裁判所によれば、①被告の財産額(脱退時財産額)は8億7,350万4,806円、②原告の脱退時における全社員の出資金額は3億4,600万円であり、全社員の損益の額(既脱退社員に属する損益で分配未了のものの額を含む)は5億2,750万4,806円、③原告の脱退時における出資金額は500万円であり、原告に属する損益の額は162万2,731円であるとされ、これを前述の算定方法(表2)に従って計算すると、脱退時持分割合は662万2,731/8億7,350万4,806となり、結果、原告に対する持分の払戻額は662万2,731円になるとした。そして、被告が原告に持分払戻しとして既に支払っている500万円を除くと、被告が原告に対し支払うべき額は162万2,731円になるとの判断を示した(表3参照)。
【表3】本件における具体的な持分の払戻額
(前提) |
持分払戻請求権に付すべき遅延損害金の利率は商事法定利率年6分
裁判では、持分払戻請求権に付すべき遅延損害金の利率についても争点となっている。裁判所は、監査法人は他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をする業務を組織的に行うことを目的として、公認会計士法に基づき設立された法人であり(公認会計士法1条の3第3項、2条1項)、監査法人が行う財務書類の監査に関する業務は、請負の性質を有すると解される監査報告書の提出を主要な目的の一つとしていると指摘。監査法人の行う業務は営利を目的とするものというべきであるから、監査法人は商法上の商人に該当する(商法4条1項、502条5号)のが相当であるとの見解を示した。
その上で裁判所は、監査法人が社員から出資を受ける行為は、監査法人がその事業を営むためにする行為であり、附属的商行為(商法503条)に該当し、社員の監査法人に対する持分払戻請求権に付すべき遅延損害金の利率は、商事法定利率年6分であるとした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















