解説記事2023年10月30日 ニュース特集 小規模宅地、債務控除etc. 相続税の審理上の留意点(2023年10月30日号・№1001)
ニュース特集
資産税の質疑事例から紹介
小規模宅地、債務控除etc. 相続税の審理上の留意点
本特集では、東京国税局が審理担当者等に周知している相続税の質疑事例(審理上の留意点)を紹介する。「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出有無と小規模宅地特例の関係、相続時精算課税適用財産の価額に評価誤りがあった場合の取扱い、相続人でない者が支払った葬式費用等に係る債務控除の可否などが示されている。
1 修正申告により非上場株式等に係る相続税の納税猶予税額が増加した場合の過少申告加算税
Q
Yは、被相続人Xの相続に係る相続税の申告において、非上場株式等の相続税の納税猶予の特例を適用することとして、相続税の申告書を期限内に提出した。この申告に対する税務署の調査の結果、Yが取得した対象非上場株式等に評価誤りが確認されたことから、Yは修正申告書を提出した。
この場合、Yの修正申告においては、納税猶予税額が増加することにより申告期限までに納付すべき税額は生じないが、過少申告加算税を賦課しないこととなるのか。
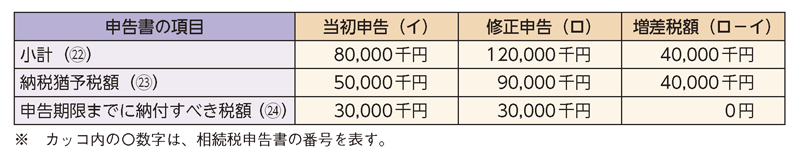
A
修正申告に基づいて増加する差引税額(40,000千円)を対象に、過少申告加算税を賦課する。
【理由】
1 修正申告等に係る相続税額の納税猶予
非上場株式等の相続税の納税猶予の特例は、原則として、期限内申告書に係る相続税額に限って適用されるものであるところ、修正申告または更正があった場合で、その修正申告または更正が期限内申告書の提出による対象非上場株式等(または特例対象非上場株式等)の評価誤りまたは税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告または更正があった場合における当該修正申告または更正により納付すべき相続税額(付帯税を除く)については、当初から対象非上場株式等(または特例対象非上場株式等)の相続税の納税猶予の特例の適用があることとして取り扱うこととされている(措通70の7−6、70の7の2−9、70の7の6−4)。
したがって、本事例においては、対象非上場株式等の評価誤りのみに基づいて修正申告がされた場合における納付すべき相続税額全額について、当初から対象非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例の適用があることとなるので、修正申告に伴い納付すべき相続税額は生じないこととなる。
2 修正申告等により納税猶予税額が増加した場合の過少申告加算税の対象となる税額
国税通則法(以下「通則法」という)第65条≪過少申告加算税≫第1項は、修正申告書の提出があったときは、その修正申告に基づき通則法第35条≪申告納税方式による国税等の納付≫第2項の規定により増加する納付すべき税額に過少申告加算税を賦課する旨規定している。
ところで、通則法第35条第2項第1号には、納付すべき税額は修正申告書に記載した通則法第19条≪修正申告≫第4項第3号に掲げる金額である旨記載されており、通則法第19条第4項第3号には、申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額である旨記載されている。
一方、租税特別措置法(以下「措法」という)第70条の7の2≪非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除≫第1項(または措法第70条の7の6≪非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例≫第1項)の規定は、その相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、措法第70条の7の2第2項第5号(または措法第70条の7の6第2項第8号)に記載のある納税猶予分の相続税額に相当する相続税について、納税を猶予する旨規定している。
したがって、本事例においては、納税を猶予する前の納付すべき相続税の額である小計(40,000千円)を対象に、過少申告加算税を賦課することとなる。
なお、措通70の7の2−9≪修正申告等に係る相続税額の納税猶予≫(または措通70の7の6−4≪修正申告等に係る相続税額の納税猶予≫。いずれも措通70の7−6≪修正申告等に係る贈与税額の納税猶予≫を準用)の定めにより、修正申告等に係る相続税額については、当初から非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用があることとして取り扱われることから、本事例の場合、延滞税は課されないこととなる。
2 「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の取扱い
Q
被相続人Xの相続人は、YおよびZの2名(以下「相続人ら」という)であり、相続人らの間で遺産分割協議が調わないことから、Xの相続(以下「本件相続」という)に係る相続税(以下「本件相続税」という)について、相続人らは、申告期限までに未分割であるとして申告書を各々が単独で税務署長に提出した。また、Yは、本件相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割が成立しなかったことから、所定の日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」(以下「承認申請書」という)を提出し税務署長の承認を受けているところ、Zは承認申請書を提出していない。
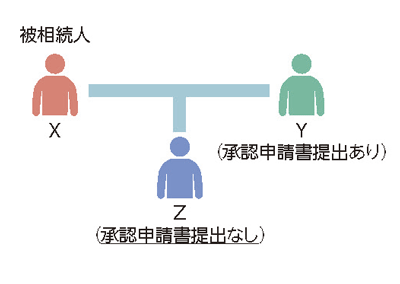
令和4年4月1日、租税特別措置法(以下「措法」という)第69条の4≪小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例≫(以下「小規模宅地の特例」という)を適用できる宅地(以下「特例対象宅地」という)をYとZでそれぞれ1/2ずつ相続することなどを内容とする調停が成立した。
今後、相続人らは、本件相続税につき、措法第69条の4第4項の規定に基づく更正の請求を予定しているところ、その課税価格の計算に当たり、特例対象宅地のうちYが取得した部分について、小規模宅地の特例の適用を受けることができるか、また、特例対象宅地のうちZが取得した部分について、小規模宅地の特例の適用を受けることができるか。
A
特例対象宅地のうちYが取得した部分については、小規模宅地の特例の適用を受けることができる。
特例対象宅地のうちZが取得した部分については、小規模宅地の特例の適用を受けることができない。
【理由】
措法第69条の4第4項は、相続または遺贈に係る相続税法(以下「相法」という)第27条≪相続税の申告書≫の規定による申告書の提出期限までに共同相続人または包括受遺者によって分割されていない宅地等については適用することができない。しかし、同項ただし書において、その分割されていない宅地等が申告期限から3年以内に分割された場合、また、3年を経過するまでの間に当該宅地等が分割されなかったことにつき、当該相続または遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内に分割された場合は、この限りではない旨規定されている(なお、措法第69条の4第4項ただし書には宥恕規定がない)。
そうすると、本事例の場合、承認申請書を提出している者(Y)と提出していない者(Z)の小規模宅地の特例の適用に当たり、Yの更正の請求において、特例対象宅地のうちZが取得した部分について小規模宅地の特例の適用を受けることができるか、また、Zの更正の請求において、特例対象宅地のうちYが取得した部分について小規模宅地の特例の適用を受けることができるか疑義が生じる。
この点、措法第69条の4第1項は、「財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして……選択をしたもの」の「相続税の課税価格に算入すべき価額」を減額するとし、また、相法第16条≪相続税の総額≫は、相続税の総額は「財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額」を基に計算することと規定している。
したがって、本事例については、Zが取得した部分には小規模宅地の特例を適用しない価額を、Yが取得した部分には小規模宅地の特例を適用した後の価額を、それぞれ算入した課税価格の合計額を基に相続税の総額を計算することとなる。
3 相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合の権利義務の承継
Q
下掲の相続関係図に基づく事案について、事実関係は以下のとおりである。
1.長男B(配偶者および子なし)は、平成16年に母Xからの贈与について相続時精算課税を適用していたところ、令和元年に死亡した。
2.長男Bの相続人は母Xのみであったところ、母Xは、相続放棄(民法938)をした。
3.母Xには、長男Bの他に子である長女C(令和3年に死亡し、長女Cには、子である孫Eおよび孫Fがいる)および二女Dがいる。
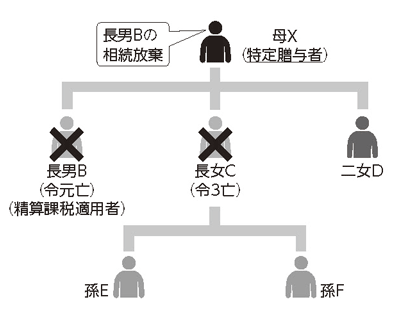
この場合、長男Bが相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務(以下「相続時精算課税の適用に伴う権利義務」という)を、誰がどのように承継するか。
A
長男Bの死亡により、長女Cおよび二女Dは相続時精算課税の適用に伴う権利義務の2分の1をそれぞれ承継する。また、長女Cの死亡により、孫Eおよび孫Fが相続時精算課税の適用に伴う権利義務の4分の1をそれぞれ承継する。
【理由】
1 権利義務の承継等
特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除く。以下「承継相続人」という)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継する(相法21の17①)。
この場合、承継相続人が2人以上いる場合の各相続人の承継割合は、民法第900条≪法定相続分≫から第902条≪遺言による相続分の指定≫まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)に規定する相続分(その特定贈与者がいないものとして計算した相続分)による(相法21の17③、相令5の5、通法5②)。
なお、承継相続人が特定贈与者のみである場合には、相続時精算課税の適用に伴う権利義務はその特定贈与者および民法第889条≪直系尊属及び兄弟姉妹の相続権≫の規定による後順位の相続人となる者には承継されず消滅することになる(相基通21の17−3)。
また、承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合には、その承継相続人の相続人(以下「再承継相続人」という)は、その承継相続人が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することとされている(相法21の17④)。
2 当てはめ
本事例において、まず、母Xは、長男Bの相続について、民法上の放棄(民法938)をしているため、母Xは最初から長男Bの相続人でなかったこととなる(民法939)ことから、上記1なお書きには該当せず、相続時精算課税の適用に伴う権利義務は長女Cと二女Dがそれぞれ2分の1を承継することとなる(相続時精算課税の適用に伴う権利義務は消滅しない)。
次に、長女C(承継相続人)については、相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継するも、母X(特定贈与者)より先に死亡していることから、再承継相続人である孫Eおよび孫Fがそれぞれ4分の1を承継することとなる。
4 相続税の課税価格に加算される相続時精算課税適用財産の価額(評価誤りが判明した場合)
Q
Xは、平成26年に父から土地(以下「本件土地」という)の贈与を受けたため、相続税法第21条の9≪相続時精算課税の選択≫(以下「相続時精算課税」という)の規定を適用して、贈与税の期限内申告を行った。その後、令和4年6月に父が死亡したことから、Xは、相続により取得した財産と相続時精算課税を適用して贈与を受けた本件土地を相続税の課税価格に算入して申告書を作成していたことろ、平成26年分の贈与税の申告書に記載した本件土地の評価額が誤っていることが判明した。
この場合、平成26年分の贈与税の更正・決定に係る除斥期間は既に経過しており、本件土地の評価額を是正することはできないことから、Xが父の相続に係る相続税の課税価格に算入する本件土地の価額は、贈与税の申告書に記載した価額となるのか。
A
相続税の課税価格に算入する本件土地の価額は、本件土地の評価誤りを是正した後の価額となる。
【理由】
相続税法第21条の15≪相続時精算課税に係る相続税額≫第1項は、特定贈与者から相続または遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者は、当該特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価額(以下「適用財産の価額」という)を相続税の課税価格に加算する旨規定している。
そうすると、贈与税の期限内申告書に記載された適用財産の価額に誤りがある場合、①贈与税の更正・決定の除斥期間内である場合には、更正または更正の請求(以下「更正等」という)により是正し、当該是正された後の当該財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となる。
一方、本事例にように、②贈与税の更正・決定の除斥期間が経過している場合には、更正等により適用財産の価額を是正することはできないところ、この場合であっても、贈与税の期限内申告書に記載された当該財産の価額ではなく、評価誤りを是正した後の当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなるのか疑義が生じる。
この点、相続税法基本通達は、相続税の課税価格に加算することとなる適用財産の価額は、贈与税の期限内申告書に記載された価額ではなく、当該贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される当該財産に係る贈与の時における価額である旨定めている(相基通21の15−1、21の15−2)。
したがって、本事例については、平成26年分の贈与税の更正・決定の除斥期間が経過しているため、贈与税の申告書に記載した適用財産の価額を是正することはできないものの、Xの父の相続税の課税価格に加算される適用財産の価額は、本件土地の評価誤りを是正した後の価額となる。
なお、この場合において、相続税の税額から控除される相続時精算課税に係る贈与税相当額は、平成26年分の贈与税の申告において課せられた贈与税相当額となる(相法21の15③)。
5 相続人でない者が支払った債務控除の取扱い
Q
被相続人Xは、生前、内縁の妻であるYに身の回りの世話をしてもらっていた。この度、Xが生前にYを受取人とする生命保険契約をしていたことが分かり、Yは、その保険金6,000万円を受け取ることとなった。
Yは、Xの葬儀に際して葬式費用300万円を負担し、また、Xの借入金100万円を返済した。
この場合、Yは、相続税の申告に当たり、支払った葬式費用および借入金の金額を控除することができるか。なお、被相続人Xには相続人等がおらず、同人が遺言書を作成していた事実もない。
A
Yが支払った葬式費用および借入金の額を債務控除することはできない。
【理由】
相続税法(以下「相法」という)第13条≪債務控除≫第1項は、「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3≪相続税の納税義務者≫第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から(中略)その者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。」旨規定しており、第2項は、「相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で(中略)その者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。」と規定している。
そうすると、被相続人の債務および葬式費用を取得した財産の価額から控除できるのは、①相続人および②包括受遺者で、かつ、無制限納税義務者に限られることとなる。
本事例に当てはめると、Yは、相法第3条≪相続又は遺贈により取得したものとみなす場合≫の規定により、生命保険金を「遺贈により取得したもの」とみなされるところ、Yは、「相続人」でも「包括受遺者」でもないことから、相法第13条第1項の規定には該当しない。
したがって、その支払った葬式費用および借入金を債務控除することはできない。
6 個人立幼稚園等の事業に係る債務
Q
個人立幼稚園の園長および設置者であったXの父(事業経営者)が令和4年に死亡したことから、Xは、当該幼稚園の新設置者として事業を承継した。Xは、個人立幼稚園の教育用財産を相続により承継取得するとともに、個人立幼稚園の事業に係る債務を承継した。
この場合、個人立幼稚園の事業に係る債務は、相続税の課税価格の計算上債務控除の対象となるか。なお、本事例は、個人立幼稚園の教育用財産を相続により取得した場合の相続税の非課税制度の適用要件(相令附則4)を充足しているものとする。
A
債務控除の対象とならない。
【理由】
相続税法第12条≪相続税の非課税財産≫第1項第3号は、公益を目的とする事業を行う一定の者が相続または遺贈により取得した財産(公益事業用財産)で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なものに限り相続税を課さない旨規定している。
ところで、相続税法第13条≪債務控除≫第3項は、公益事業用財産(相法12①三)の取得、維持または管理のために生じた債務の金額は、債務控除の対象とならない旨規定している。
したがって、本事例の個人立幼稚園の事業に係る債務は、相続税の課税価格の計算上債務控除の対象とならない。
なお、個人立幼稚園の事業に係る未納の所得税や住民税は、上記「公益事業用財産(相法12①三)の取得、維持または管理のために生じた債務」には該当しないため、債務控除の対象となる。
また、相続税法施行規則第13条≪相続税の申告書の記載事項≫第1項第8号は、相続税の申告書の法定記載事項として「相続税法第12条第1項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項」を規定しているところ、当該申告書に所定の記載欄はないため、申告があった際には、申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)や「教育用財産の明細書」等により、その内容を確認することとなる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















