解説記事2023年11月13日 ニュース特集 みずほ銀行事件、最高裁で国が逆転勝訴(2023年11月13日号・№1003)
ニュース特集
CFC税制適用巡り“過剰課税”を指摘するも、文理重視
みずほ銀行事件、最高裁で国が逆転勝訴
CFC税制の適用を巡り争われていたみずほ銀行事件について最高裁は令和5年11月6日、判決を言い渡した。控訴審では、「同行が各子SPCから剰余金の配当等を受け得る支配力は存在しない」として、CFC税制の適用を認めた一審判決が取り消され、みずほ銀行が逆転勝訴していたが、最高裁は更正処分等を適法と認め、一転、みずほ銀行側の完敗という結果に終わった。
最高裁は、「適用対象金額に乗ずべき請求権勘案保有株式等割合に係る基準時を特定外国子会社等の事業年度終了の時とする」と定めた本件規定(措令39条の16①)は、個別具体的な事情にかかわらず合理的であり、「本件各子SPCの利益は本件優先出資証券にのみ配当されたにもかかわらず、本件優先出資証券が同事業年度の途中で償還されたために、みずほ銀行の本件保有株式等割合が100%となり合算課税がされる」という本件の事実関係等の下であっても、本件規定を適用することが本件委任規定(措法66条の6①)の委任の範囲を逸脱するものとはいえないとの判断を下した。
控訴審「配当等を受け得る支配力なし」とCFC税制の適用を否認
みずほ銀行は特定外国子会社等に該当する各子SPCの発行済普通株式の全部を保有していたが、各子SPCの優先出資証券は、みずほFGの100%子会社であるケイマンSPCが全て保有していた。しかし、各子SPCは期中において優先出資証券の全部を当該ケイマンSPCに償還したため、各子SPCが事業年度終了日において発行する株式等は、みずほ銀行が100%保有する普通株式のみとなっていた(図参照)。
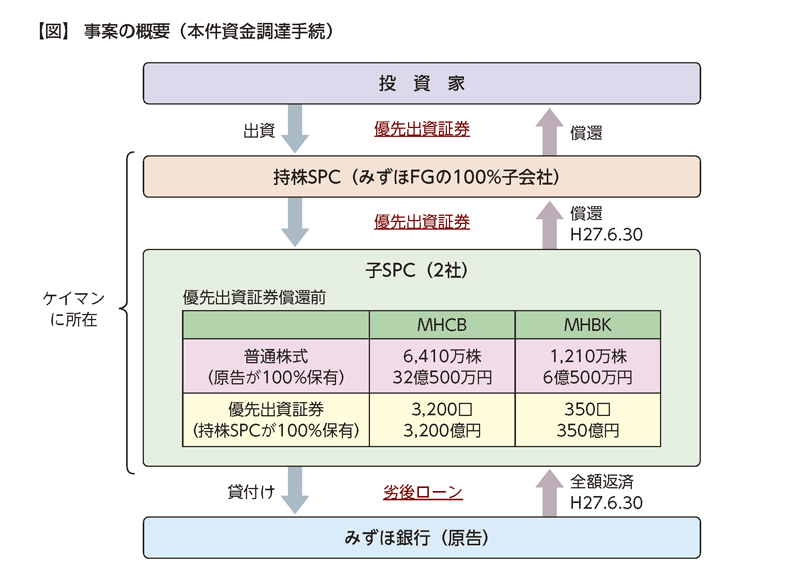
そのため処分行政庁は、事業年度終了時における「請求権勘案保有株式等割合」は100%であり、本件各子SPCの適用対象金額(各子SPCがみずほ銀行から受け取る劣後ローンの利息等)の全額が課税対象金額としてみずほ銀行の益金の額に算入されるべきとして、CFC税制を適用して各更正処分等を行った。
一審でみずほ銀行は、事業年度末における事業年度末の状況はたまたま生じた形式的な状況にすぎず、本件資金調達スキームはバーゼルⅡ規制に対応するための方法として邦銀で広く採用されていた方法であり、また、各子SPCの稼得した所得は全て優先出資証券について配当され、みずほ銀行には帰属しないことなどから、租税回避の実態を伴うものではないなどと主張していたが、東京地裁は、規定の文理から、当該割合を判断すべき時点は「当該外国子SPCの事業年度終了時」であり、当該割合は100%であるとして、みずほ銀行の請求を棄却していた。
これに対し東京高裁は、本件規定(措令39条の16①)を適用すれば本件株式保有割合は100%となるとしながらも、みずほ銀行が本件各子SPCから剰余金の配当等を受けることは想定されていなかったため、内国法人が外国子会社の利益から剰余金の配当等を受け得る支配力を有するという、いわゆるタックス・ヘイブン対策税制の下での合算課税の合理性を基礎付ける事情は見いだせない上、本件各子SPC事業年度における処理につき、租税回避の目的も、客観的に租税回避の事態が生じていると評価すべき事情も認められないとして、本件規定を本件に形式的に適用することは、本件委任規定(措法66条の6①)の趣旨及びタックス・ヘイブン対策税制の基本的な制度趣旨に反するから、その限度で本件規定を本件に適用することはできないとの判決を下していた。
“基準時”を設ける本件規定は個別具体的事情にかかわらず合理的
最高裁は、本件では、本件の事実関係等の下において本件規定を適用することが本件委任規定の委任の範囲を逸脱するか否かが問題となるとした上で、まず、本件規定の内容が一般に本件委任規定の趣旨に適合するか否かについて検討した。
そして、「本件委任規定において課税要件の明確性や課税執行面における安定性の確保が重視されており、事業年度終了の時という定め方は一義的に明確であること等を考慮すれば、個別具体的な事情にかかわらず上記のように基準時を設けることには合理性があり、そのような内容を定める本件規定が本件委任規定の目的を害するものともいえない」との考えを示した。
その上で、本件の事実関係等の下において本件規定を適用することが本件委任規定の委任の範囲を逸脱するか否かについて検討したところ、上記のとおり、個別具体的な事情にかかわらず基準時を設ける本件規定の内容が合理的である以上、「本件各子SPC事業年度における本件各子SPCの利益は本件優先出資証券にのみ配当されたにもかかわらず、本件優先出資証券が同事業年度の途中で償還されたために本件保有株式等割合が100%となり、みずほ銀行に対して合算課税がされる」という帰結をもって、直ちに本件委任規定の委任の範囲を逸脱することにはならないとした。
また、①特定外国子会社等の事業年度の途中にその株主構成が変動するのに伴い、剰余金の配当等がされる時と事業年度終了の時とで持株割合等に違いが生ずるような事態は当然に想定される、②内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等は、原則として、内国法人の所得金額の計算上、益金の額には算入されない以上、本件委任規定につき、特定外国子会社等において剰余金の配当等が留保されることにより内国法人が受ける剰余金の配当等への課税が繰り延べられることに対処しようとするものと解することはできないから、前記事実関係等の下において剰余金の配当等に係る個別具体的な状況を問題とすることなく本件規定を適用することによって、本件委任規定において予定されていないような事態が生ずるとはいえない、③前記事実関係等の下においては、本件各子SPCの事業年度を本件優先出資証券の償還日の前日までとするなどの方法を採り、本件各子SPCの適用対象金額が0円となるようにする余地もあったと考えられるから、本件規定を適用することによってみずほ銀行に回避し得ない不利益が生ずるなどともいえないと指摘し、前記事実関係等の下において本件規定を適用することは本件委任規定の委任の範囲を逸脱するものではないと結論づけた。
補足意見、“過剰課税”を認めるも回避可能と判断
最高裁判決には補足意見が付されているが、同意見は、本件規定には“過剰課税”が発生するという問題があること、なおかつ、本件においては現に“過剰課税”が発生していることを指摘しつつも、結論として、それでも判決を覆すには至らないとしている。
具体的には、当該外国法人がその事業年度終了時とは異なる日を基準日として剰余金の配当等を支払ったところ、これを受け取った当該外国法人の株主がその直後に到来する事業年度終了時には当該外国法人の株主ではない場合において、①上記基準日においては受取株主が特定親会社であるとすれば、経済実態からすれば、当該特定親会社に対し合算課税をすることが相当であるにもかかわらず、合算課税をなし得ない事態(過少課税)が発生し得る一方、②直近年度末においては受取株主は特定親会社と資本関係のない者であるとすれば、経済実態からすれば、当該特定親会社に対し合算課税をすることは相当でないにもかかわらず、合算課税がされる事態(過剰課税)が発生し得るとしている。
そして、この問題に対しては、政令を定めるに当たり、特定外国子会社等が会計期間の末日以外の日を基準日として配当を行った場合には、当該会計期間の始期から当該配当の基準日までの期間を一つの事業年度とみなした上で、その翌日から当該会計期間の末日までの期間をもって次の事業年度とみなすことにすれば、過少課税も過剰課税も回避することができると指摘している。
しかしながら、①本件規定の在り方は、特定外国子会社等がその会計期間の末日を基準日として配当を支払うという典型的な配当支払実務を前提とすれば、十分に合理的であり、かつ、本件委任規定の趣旨を実現するための税制を簡便なものにするという目的にも合致していること、②配当をいつ支払うかあるいは事業年度終了時をいつとするかは、実質的には当該特定外国子会社等の配当支払決定時における支配株主の判断によって決め得るから、過剰課税の発生はほとんど常に回避し得るとして、「本件規定の内容は、一般に本件委任規定の趣旨に適合するという法廷意見の判断を覆すことはできない」と結論づけている。
予期せざる税務上の不利益に注意払い得る
また、本件各子SPC事業年度における本件各子SPCの利益に関し、現に過剰課税が発生していることは否定し難い事実であり、しかもこの事態は本件各子SPCの設立、本件優先出資証券の発行及び本件劣後ローンによる貸付けの実施という一連の手続(本件資金調達手続)がなされた平成20年当時においては起こり得ないものであった(当時の租税特別措置法施行令39条の16第1項の下では、特定外国子会社等が株主に配当として支払った金額は、同項にいう適用対象留保金額に含まれず、合算課税の基礎となる余地がなかった)とも指摘している。
しかし、補足意見はこの点に対しても、みずほ銀行は「利払の損金算入効果を享受しつつ国際金融市場から自己資本を調達しようという意図の下に本件資金調達手続を立案しこれを実行したもの」であるとうかがわれ、みずほ銀行のような我が国を代表する金融機関が本件資金調達手続を立案するに当たっては、関係各国の税制や我が国のタックス・ヘイブン対策税制についても十分な調査を行い、予期せざる税務上の不利益が発生することがないよう注意を払い続けることを期待され得る立場にあったと指摘。
さらに、本件において過剰課税が発生する余地が生ずることとなったのは、いわゆる外国子会社受取配当益金不算入の制度の導入に伴う平成21年の関係規定の改正によって、合算課税の基礎となる金額(適用対象金額)から、特定外国子会社等がその株主に支払った配当を控除することができなくなったためであるところ、その改正に係る改正法の施行の時から本件優先出資証券の償還がなされるまでの間には6年余りの期間があり、本件各子SPCの事業年度を本件優先出資証券の償還日の前日までとするなどの方法を採ることによって合算課税を回避することは容易にできたはずであるとした。
結論として、補足意見も法廷意見の結論及び理由付けに全面的に賛成するものであるとして、本件は納税者側の完敗に終わった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















