解説記事2023年11月20日 税務マエストロ 申請書・届出書と国税通則法10条2項の関係(2023年11月20日号・№1004)
税務マエストロ
申請書・届出書と国税通則法10条2項の関係
#293
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
インボイス制度の開始に伴い、登録申請書や登録取消届出書、取下書の申請・提出期限についての疑問が多いようだ。
令和5年度改正で登録制度の見直しと手続の柔軟化が行われ、申請(届出)期限が大幅に短縮された。その一方で、申請(提出)期限が土日祝日などに該当した場合の国税通則法10条2項(期限の特例)の適用関係が複雑で、判断に迷うケースがあるようだ。
申請(提出)期限と国税通則法10条2項(期限の特例)の関係については、国税庁のインボイスQ&A問13(登録の取りやめ)の(注)のほか、令和5年7月31日に国税庁から公表され、同年10月1日に改訂された「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」(以下「事例集」という。)に解説がされている。これらの情報を基に、本稿では申請書・届出書と国税通則法10条2項の関係について整理してみたい。
※令和5年7月31日に公表された事例集については、本誌No.993(2023年(令和5年)9月4日号)で詳しく解説している。
Ⅰ 登録申請期限
インボイスの登録申請期限は、課税事業者の登録申請と免税事業者の登録申請で取扱いが異なっている。また、免税事業者が登録申請する場合には、課税期間の初日から登録する場合と課税期間の中途から登録する場合で微妙に違いがあることに注意する必要がある。
1 免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録する場合
(1)申請期限
免税事業者が、課税事業者となる課税期間の初日からインボイスの登録をする場合には、「適格請求書発行事業者」になろうとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない(消法57の2②、消令70の2①)。
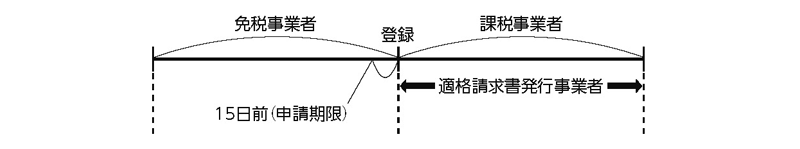
(2)みなし登録
期限までに申請書を提出した場合において、実際の登録日がその課税期間の初日後にずれこんだ場合には、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされるので、登録通知を受け取った後に登録番号を取引先に通知すれば、通知前に交付した請求書等はインボイスとしての効力を有することになる(消令70の2②)。
(3)申請期限の数え方
申請期限の数え方は下記のようになる。「……初日から起算して……」とあるので、免税の個人事業者が年初の1月1日から登録する場合には、1月1日を算入して数えると、15日目は12月18日になる。ただし、申請期限は「……15日前の日……」となっており、「15日以前」ではないのでさらに一日繰り上がり、結果として申請期限は12月17日になるのである。
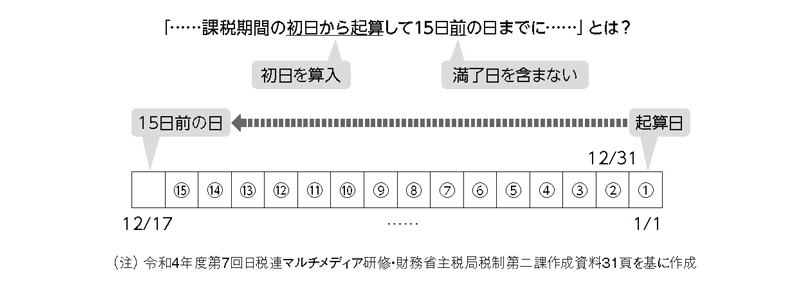
結果、個人事業者や3月(9月)決算法人の登録申請期限は次のようになる。
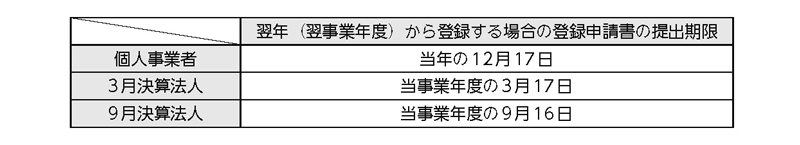
(4)国税通則法による期限の延長
個人事業者が令和6年1月1日に登録する場合には、申請期限は令和5年12月17日となり、令和5年12月17日は日曜日なので、国税通則法10条2項(期限の特例)が適用され、その翌日の18日が申請期限となる(国通10②)。
2 免税事業者が課税期間の中途から登録する場合
(1)経過措置による登録
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録する場合には、「課税事業者選択届出書」の提出は不要とされている。
例えば、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日より「適格請求書発行事業者」となる場合には、令和5年9月30日までに登録申請書を提出することにより適格請求書発行事業者としてインボイスを発行することができる。
この場合において、令和5年1月1日〜令和5年9月30日の間は免税事業者として納税義務はないので、登録開始日である令和5年10月1日以後の期間についてのみ、課税事業者として申告義務が発生することになる(平成28年改正法附則44④、消基通21−1−1)。
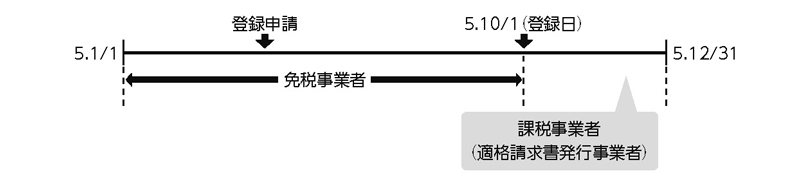
(2)申請期限とみなし登録
免税事業者が令和5年10月2日以後に登録する場合には、登録申請書の「登録希望日」の欄に、登録申請書の提出日から15日を経過する日以後の日を記載しなければならない(令和5年10月1日に登録する場合には記載不要)。
この場合において、実際の登録日が登録希望日後にずれこんだ場合には、その登録希望日に登録を受けたものとみなすこととされているので、登録通知を受け取った後に登録番号を取引先に通知すれば、通知前に交付した請求書等はインボイスとしての効力を有することになる(平成30年改正令附則15②③)。
(3)申請期限の数え方
申請期限の数え方は下記のようになる。「……起算して……」とはなっていないので、個人事業者が1月17日に登録申請書を提出した場合、提出日である1月17日は算入せずに数えることになる(国通10①一)。提出日の翌日の1月18日から起算して15日目が2月1日となり、「……15日を経過する日以後の日……」となっているので満了日の2月1日が計算期間に算入されることとなり、結果、2月1日以後の日が「登録希望日」となる。
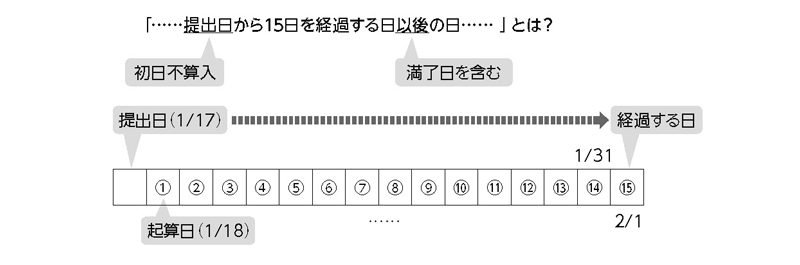
(4)国税通則法による期限の延長
免税事業者が課税期間の中途から登録する場合の登録希望日に関する取扱いは、登録申請書の申請期限を定めたものではない。よって、申請書の提出日が土日祝日などであったとしても、申請期限は延長されないことになる。
ただし、課税期間の初日を登録希望日とする場合には、1で解説したように、その課税期間の初日から起算して15日前の日が申請期限となるので、課税期間の初日から期間を数えることになる。結果、個人事業者が令和6年1月1日を登録希望日とする場合には、申請期限は令和5年12月17日となり、令和5年12月17日は日曜日なので、その翌日の18日が申請期限となるのである(登録申請書の「登録希望日」の欄には令和6年1月1日と記載する)。
※登録希望日と登録申請書の提出期限の関係について
免税事業者は、「課税事業者選択届出書」の提出を不要とする経過措置の適用期間中に限り、課税期間の中途からの登録が認められている。よって、経過措置の適用期間が終了した後は、免税事業者であっても課税期間の初日からでなければ登録することはできないことになる。
したがって、経過措置の適用期間中であっても、課税期間の初日から登録する場合には、本法の規定に沿って取扱うべきであり、その結果、国税通則法10条2項(期限の特例)が適用されるケースもあることになる。
平成30年改正令附則15条2項は、登録申請書に登録希望日を書くことを義務付けたものであり、登録希望日を書いたからといって、本法と施行令に規定された登録申請書の提出期限まで否定されるものではない。
このことは、事例集の3頁に加筆された文章(次頁参照)からも読み取ることができる(下線が加筆された文章である)。
3 課税事業者が登録申請する場合
(1)登録申請期限の定めはない?
インボイスQ&A問6(課税期間の中途での登録)には、課税事業者の登録申請について、課税事業者は課税期間の中途であってもインボイスの登録を受けることができ、この場合の登録の効力は、登録日から生ずることが書かれている。
よって、顧客がインボイスを必要としないことから、あえて登録をしてこなかった学習塾や美容業などを経営する課税事業者は、翌課税期間を待たずとも、課税期間の中途から登録することができることになる。
この場合において、法令には課税事業者が登録申請する場合の申請期限に関する定めがないことから、実際には登録センターで登録審査が終わり、登録がされた日(登録日)から登録の効力が生ずることになるものと思われる。
(2)登録希望日の記載は不可!
事例集の2頁に、既に課税事業者である者が登録を受ける場合、登録日からインボイス発行事業者となるので登録希望日の記載は不可となる(できない)ことが追記されている。
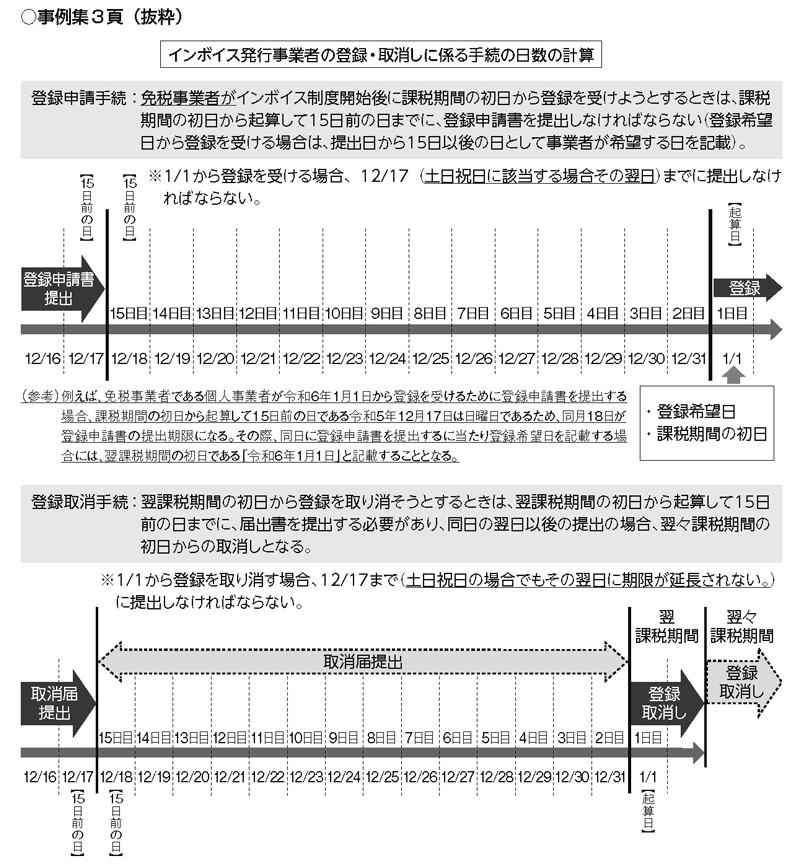
4 免税事業者の登録手続に関する経過措置の延長(令和4年度改正)
(1)登録手続に関する経過措置の延長と課税期間の中途からの登録
令和4年度改正では、免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、令和5年10月1日の属する課税期間だけでなく、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても、「課税事業者選択届出書」を提出することなく、登録申請書を提出することにより、適格請求書発行事業者となることを認めることとした。また、登録申請書を提出することにより、年又は事業年度の中途から登録をすることもできることとなった(平成28年改正法附則44④)。
<具体例>
個人事業者であれば、登録申請書を提出することにより、令和5年から令和11年分までの任意の年(課税期間)について適格請求書発行事業者になることができる。また、令和6年10月1日といったように、年の中途からの登録も認められる。
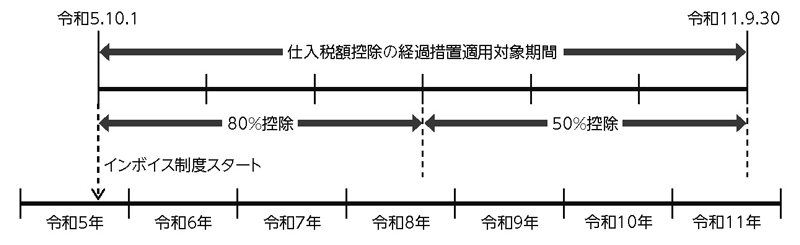
(2)免税事業者が登録した場合の課税事業者としての拘束期間
令和4年度改正では、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者とのバランスに配慮し、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において登録する免税事業者は、令和5年10月2日以後に開始する課税期間について、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は課税事業者として申告義務を課することとしている(平成28年改正法附則44⑤)。
注意したいのは、令和5年10月1日の属する課税期間において登録する免税事業者は、いわゆる2年縛りの規定がないということである。
したがって、個人事業者(免税事業者)が令和5年10月1日に登録した場合には、令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者となることができるのに対し、令和6年1月1日に登録した個人事業者(免税事業者)は、登録開始日(令和6年1月1日)から2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間(令和7年)までの間は課税事業者として申告義務があるので、結果、令和6年と令和7年の2年間は課税事業者として拘束されることとなるのである。
<具体例1>
個人事業者が令和5年12月17日までに登録申請書を提出し、令和6年1月1日から適格請求書発行事業者となった場合には、令和6年12月17日までに登録取消届出書を提出し、令和7年1月1日からインボイスの効力を失効させたとしても、令和7年12月31日までは課税事業者として申告義務がある。
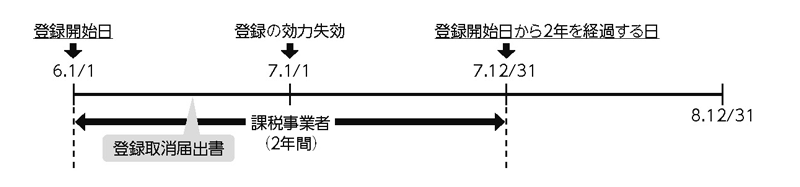
<具体例2>
個人事業者が令和6年1月17日までに登録申請書を提出し、令和6年2月1日から適格請求書発行事業者となった場合には、令和6年12月17日までに登録取消届出書を提出し、令和7年1月1日からインボイスの効力を失効させたとしても、令和8年12月31日までは課税事業者として申告義務がある。
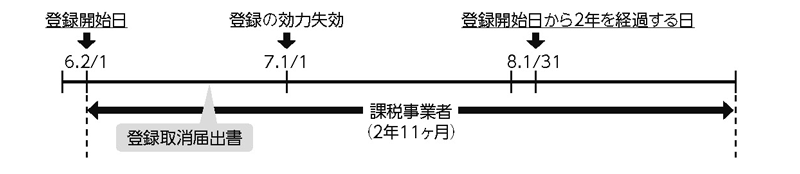
5 新規開業の個人事業者・新設された法人の登録
新規に開業した個人事業者や新設された法人は、開業した年又は事業年度中に登録申請書を提出することにより、その年又はその事業年度の初日から適格請求書発行事業者となることができる(消令70の4、消規26の4一)。
よって、開業(設立)当初は登録の予定がなかったものの、後から消費税の還付目的で登録をするような場合には、初日に遡って登録するのではなく、いわゆる「15日ルール」を使って年又は事業年度の中途から登録するのが現実的な対応方法だと思われる。
Ⅱ 登録の取消しと取下げ
1 登録の取消し
(1)届出書の提出期限
インボイスの登録を受けた適格請求書発行事業者は、登録取消届出書(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書)を提出しない限り、課税事業者として申告義務が発生する。
登録取消届出書を税務署長に提出した場合には、インボイスの登録が取り消され、インボイスの効力が失効する(消法57の2⑩一)。
適格請求書発行事業者が翌年又は翌事業年度から登録を取り止めようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録取消届出書を提出しなければならない(消法57の2⑩一、消令70の5③)。
結果、個人事業者や3月(9月)決算法人の登録取消届出書の提出期限は次のようになる。
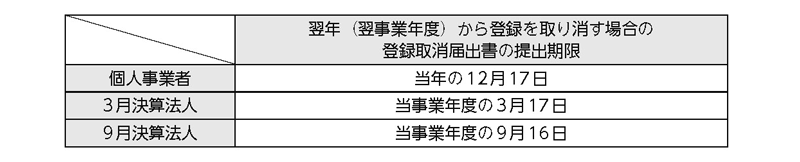
この場合において、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、「登録取消届出書」だけでなく、「課税事業者選択不適用届出書」も提出しないと免税事業者になることはできない(消基通1−4−1の2)。
「ダブルロック」により課税事業者として拘束されているということに注意する必要がある。
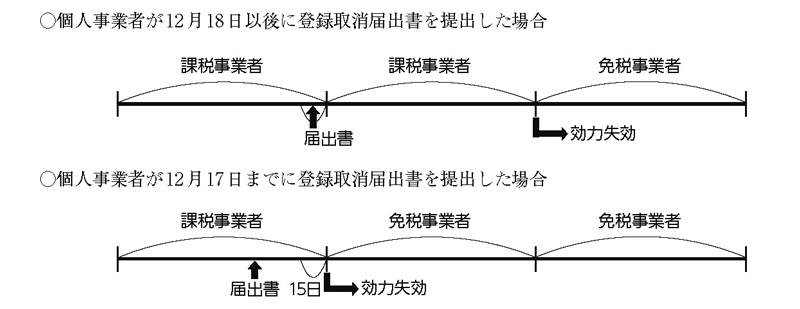
(2)国税通則法による期限の延長
登録取消届出書については提出期限を定めたものではないため、国税通則法10条2項(期限の特例)の規定は適用されない。よって、課税期間の初日から起算して15日前の日が土日祝日などであったとしても、届出書の提出期限はその翌日に延長されないことに注意する必要がある(インボイスQ&A問13)。
※登録取消届出書と国税通則法の関係
消費税法では、登録取消届出書を提出した場合、いつから登録の効力が失効するかということを定めているのであり、登録取消届出書の提出期限を定めたものではない。よって、国税通則法10条2項の期限の特例は適用されないことになる。
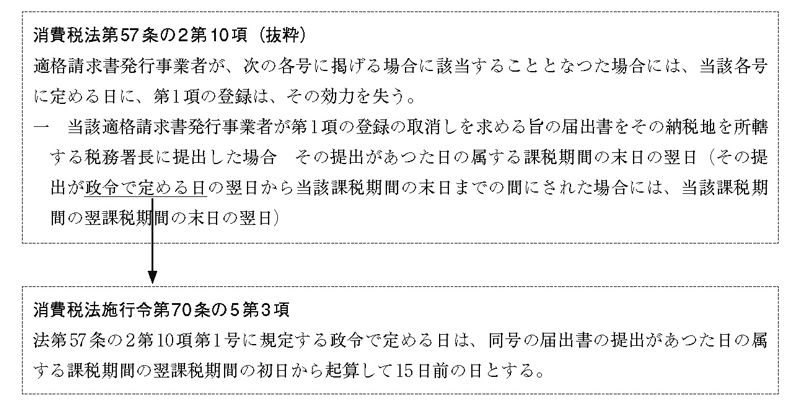
2 登録の取下げ
(1)登録取消届出書と取下書
インボイスの登録通知後に登録を取り消す場合には、1で確認したように、登録取消届出書を提出しなければならない。ただ、インボイスの効力は登録により発生するものであるから、登録通知までに登録を取り消す場合には、登録取消届出書ではなく、取下書を提出することとされている(事例集4頁)。
(2)取下書の提出期限
事例集4頁に次のような一文が追加されている(下線が加筆された文章である)。
(注)制度開始後であっても登録通知日※までに、適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げる場合は、取下書を提出する。
※登録申請書に登録希望日を記載し、登録希望日より前に登録通知を受けた場合には、登録希望日の前日(到達主義)
登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)から生ずるものとされている(インボイスQ&A問5)。
よって、登録日以後の取りやめは「取下書」ではなく、「登録取消届出書」で対応すべきところである。
しかし、電子申請ならいざ知らず、書面による申請だと登録日と登録通知日にタイムラグが生ずることがあるので、登録から登録通知までの間に取下書が提出されることも想定されるところである。そこで、10月1日の事例集の改訂で、取下書の期限を「登録日」から「登録通知日」に修正し、※で登録希望日を記載した場合の取扱いを追加したものと思われる。
免税事業者が登録申請書に登録希望日を記載して申請した場合には、登録希望日より前に登録通知を受けたとしても、登録希望日の前日までは取下げが可能とされている。ただし、取下書については国税通則法22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は適用されないため、期限は発信主義ではなく、到達主義によることとなる。
(3)取下書のフォーマット
取下書の書式は定められていないようである。よって、提出日、申請書の様式名(表題)、提出方法(書面又はe-Tax)、届出者の氏名・名称、納税地、申請書を取り下げる旨の記載をし、署名をしてインボイス登録センターに提出すればよいものと思われる(インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答:財務省(令和5年3月31日時点)問7を参考に記述)。
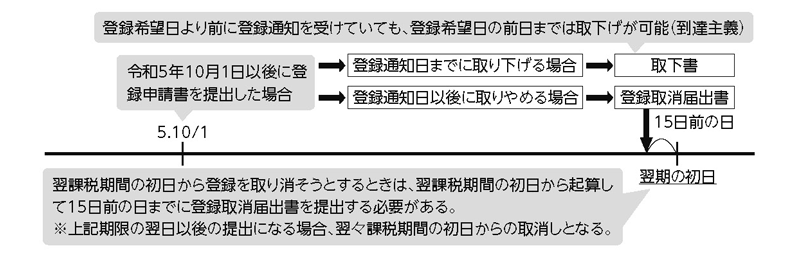
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























