解説記事2023年11月20日 SCOPE 債務免除相手が有する債権を代位行使で回収可能(2023年11月20日号・№1004)
地裁、貸倒損失の損金算入認めず
債務免除相手が有する債権を代位行使で回収可能
債務免除を行った金銭債権の額が貸倒損失として損金算入できるかどうかが争われた事案で、東京地裁民事38部(鎌野真敬裁判長)は令和5年10月31日、債務免除を受けた法人が、不法行為を行った代表取締役及び監視業務を怠った取締役に対して有する損害賠償請求権等は明らかに回収不能とはいえず、これらの損害賠償請求権等を代位行使することによって回収を図り得る原告の金銭債権についても、その全額が回収不能であることが客観的に明らかとは言えないから、当該金銭債権の額を損金算入することはできないとの判断を下した。
実体のない取引で金銭を領得した代表取締役に対する損害賠償請求権認定
原告であるE社は、原告代表者の子であるY氏の提案により、S社から建物解体業務を受注し、これを外注するという事業を行い、その後、Y氏が代表取締役を務めるI社が本件解体事業を引き継ぐことになったが、原告及びI社において行っていた本件解体事業は、実体のない取引であることが判明した。I社は、これを契機として解散し、原告からの貸付金約6億円の債務免除を受けるなどした上で、清算を結了した(図参照)。
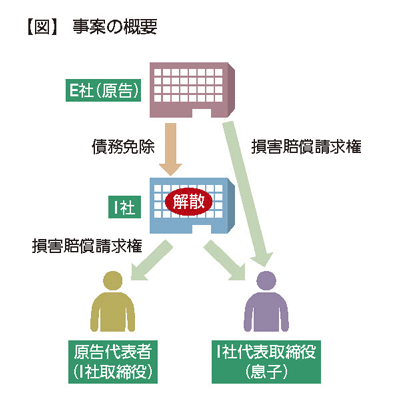
本件は、原告が、本件債務免除を行った本件金銭債権の額を貸倒損失として損金の額に算入して法人税等の申告をしたところ、本件金銭債権の額は貸倒損失として損金の額に算入することはできず、また、実体のない本件解体事業により原告が被った損害に係る損害賠償請求権を益金の額に算入すべきであるなどとして更正処分等を受けたことから、原告がその取消しを求めて提訴した事案である。
監視業務を怠った取締役も損害賠償責任あり
東京地裁はまず、「本件金銭債権の額を貸倒損失として損金算入できるかどうか」(争点1)について検討した。東京地裁は、平成16年12月24日最高裁判決を引用し、「損金の額に算入するためには、当該金銭債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならず、そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものであると解される」との解釈を示した。
その上で東京地裁は、Y氏は、I社に実体のない本件解体事業に係る取引を行わせるとともに、I社から外注先の口座に振り込まれた外注費を、当該口座から出金して領得していたから、I社はY氏に対して当該外注費相当額の不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していたと認定。Y氏には一定程度の資力があり、資産状況等について具体的な確認がされていないことから、I社のY氏に対する損害賠償請求権等が回収不能であることは、単なる見込み以上のものとして客観的に認識できる状況にはなかったとした。
また、I社の取締役も務めていた原告代表者についても、本件解体事業に係るY氏の業務執行についての監視業務を怠ったとして、I社に対して損害賠償責任を有するとした。そして、I社の原告代表者に対する損害賠償請求権についても、その全額が回収不能であることが客観的に明らかであったとは認められないとした。
その上で、これらの債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかではないと認められる以上、これらの損害賠償請求権等を代位行使することによって回収を図り得る原告のI社に対する本件金銭債権についても、その全額が回収不能であることが客観的に明らかでないと結論づけた。
債務免除益は寄附金認定、損害賠償請求権も益金算入必要
続いて東京地裁は、E社のI社に対する債務免除益の寄附金該当性及びその額(争点2)について検討したが、「何らの給付等の対価や代償を受けることなく行われた本件債務免除は、客観的にみて法人の収益を生み出すのに必要な費用又は法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性質が明白であり明確に区別し得るものであるとは認められず、本件債務免除益は寄附金に該当する」との判断を下し、寄附金の額は、当該債務免除に係る債務相当額になるとした。
また、東京地裁は、原告のY氏に対する損害賠償請求権等の損金算入時期(争点3)についても検討したところ、原告は、平成27年6月30日までに約100万円の処理費を外注先の口座に振り込んでいるが、本件処理費は、Y氏が、実際には建物解体業務を外注した事実などないのに、当該事実があるかのように装うなどして本件振込先口座に振り込ませたものと認められるから、原告は平成27年6月30日時点においてY氏に対して損害賠償請求権等を有すると認定した。その上で、原告は、遅くとも平成27年7月30日には税理士からの報告を受け、本件解体事業が実体のない取引であると認識したことが認められるとした。そして、これらの点から、原告は、Y氏に対する損害賠償請求権等が存在していることを容易に認識できる状況にあり、その権利行使が期待できないといえるような客観的な状況にはなかったと認められるから、平成28年3月期において、本件損害賠償請求権等を益金の額に算入すべきと結論づけた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















