解説記事2023年12月18日 ニュース特集 簡易課税や住宅取得等資金贈与を巡る税理士損害賠償請求事件(2023年12月18日号・№1007)
ニュース特集
簡易課税制度の説明行わず税理士に530万円
簡易課税や住宅取得等資金贈与を巡る税理士損害賠償請求事件
納税者が顧問の税理士や税理士法人に対して税務処理の誤りなどを理由に損害賠償請求を行う事例が後を絶たない。本特集では、①簡易課税制度と本則課税制度の税額の違いを説明することなく本則課税制度を選択したことなどにより、顧問税理士が原告との準委任契約に基づく善管注意義務に違反したとし、約530万円の損害賠償責任が認められた事件、②税理士法人が、住宅取得等資金の贈与について相続税の課税対象とならない要件の確認等を行わなかったものの、要件の確認等の黙示の合意が存在したと認めることはできないとし、納税者の請求が棄却された2つの税理士損害賠償請求事件を紹介する。
いずれの制度を選択することが原告の利益に叶うか判断する義務あり
1件目に紹介する事件は、よくトラブルになる案件である簡易課税制度によるものだ。原告の納税者は、被告の顧問税理士が本則課税制度を選択したことにより損害を被ったとして、530万円余りの損害賠償を求めたもの。東京地方裁判所(平城恭子裁判官)は令和5年1月24日、原告の請求を認め、被告に対し530万円余りの損害賠償責任を認める判決を下している(令和3年(ワ)第8745号)。裁判所は、簡易課税制度と本則課税制度の税額の違いを説明することなく本則課税制度を選択したことなどにより、被告は原告との準委任契約に基づく善管注意義務に違反したと認められると判断した。
本則課税選択により310万円の損害
具体的な事件の概要は以下のとおりだ。本件は、調理業務の請負等を営む原告が、顧問税理士であった被告に対し、被告は原告の消費税の確定申告において課税仕入れを過大に計上した上、簡易課税制度と本則課税制度の税額の違いを説明することなく本則課税制度を選択したことにより、修正申告のために支払った税理士費用220万円及び簡易課税制度を選択した場合の税額との差額310万1,444円の損害を被ったとして、準委任契約に基づく善管注意義務違反による損害賠償を求めたものである。
原告は、原告のように従業員の少ない調理請負事業においては、課税仕入れの対象となる支出が少なく、過去の原告の経費の内容からみても、簡易課税制度を選択した方が得になることは明らかであるなどと主張した(表1参照)。
【表1】当事者の主な主張
| 原告 | 被告(税理士) |
| 被告は、原告の平成26年分から平成30年分の消費税の確定申告において、簡易課税制度と本則課税制度の税額の違いを原告に説明することなく本則課税制度を選択して、原告との準委任契約に基づく善管注意義務に違反した。原告のように従業員の少ない調理請負事業においては、課税仕入れの対象となる支出が少なく、過去の原告の経費の内容からみても、簡易課税制度を選択した方が得になることは明らかである。 | 原告は利益の少ない会社であり、毎年赤字を計上する可能性もあるところ、赤字を計上した場合、本則課税制度によれば消費税の還付を受けられる一方で、簡易課税制度を選択した場合には少なくとも2年間は消費税の還付を受けることができなくなることからしても、本則課税制度を選択したことが債務不履行となることはあり得ない。 |
原告は簡易課税を選択する余地すら認識せず
裁判所は、被告の税理士は原告代表者の自宅について、事業として他の者から資産を借り受けたものではないにもかかわらず、自宅の家賃を課税仕入れの対象としたり、調理業務者は原告の指揮命令により労務を提供していたことから給与等を対価とする役務の提供に該当したが、課税仕入れの対象としていたなど、被告は消費税の確定申告において課税仕入れを過大に計上し、原告との準委任契約に基づく善管注意義務に違反したものと認められると判断した。
また、被告は、原告の消費税の確定申告を行うに当たり、原告との準委任契約に基づき、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限までに原告代表者から事情を聴取するなどして原告の来期以降の課税仕入れ額が大幅に変動する見込みがあるか否かを把握した上、簡易課税制度と本則課税制度のいずれを選択するのが原告の利益に叶うかを判断する義務を負っていたと認めるのが相当であるとした。本件については、原告の業務内容は調理業務の請負及び調理場の運営等であり、多額の課税仕入れが具体的に予定されている場合でない限り、簡易課税制度を選択する方が税額を軽減することができるものと認められるところ、被告の税理士は、簡易課税制度と本則課税制度の違いや各制度を適用した場合の税額の違いを原告代表者に説明しておらず、原告代表者は簡易課税制度を選択する余地があることすら認識していなかったことが認められるとした。
したがって、裁判所は、被告は原告との準委任契約に基づく善管注意義務に違反したと認められるとし、530万1,444円の損害賠償責任を負うとの判断を示した。
住宅取得等資金贈与が相続税の対象になるかの確認までは求めず
2件目に紹介するのは、被告の税理士法人が、住宅取得等資金の贈与が相続税の課税対象とならない要件の確認等を行わなかったことから、贈与税が課されたとして、原告の納税者が委任契約の債務不履行として合計で950万円余りの損害賠償を求めた事件だ。東京地方裁判所(野口晶寛裁判官)は令和5年5月16日、税理士法人が原告らに対し、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件の確認等をする旨の黙示の合意が存在したと認めることはできないとの判断を示し、原告の請求を棄却している(令和3年(ワ)第10593号)。
特例の対象か否かの確認義務は?
本件は、原告らが、原告Aの母を被相続人とする相続税の申告に係る委任契約を税理士法人と締結したところ、被相続人から原告Aへの住宅の取得のためにされた住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件の確認、説明及び助言をすべき義務に違反した結果、贈与税が課されたとして、委任契約の債務不履行として合計で950万円余りの損害賠償を求めたものである。
原告らは、被告の税理士法人は、委任契約に基づき、申告書の作成のみならず、相続税の申告に関係のある事実ないし特例の要件の確認として、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件等について、税理士自らが確認し、説明し、及び助言する義務を負っていたなどと主張した(表2参照)。
【表2】被告の債務不履行の有無に関する当事者の主な主張
| 原告ら | 被告(税理士法人) |
| 本件委任契約においては、委任業務の範囲として、被相続人の相続に係る税務相談とされていること、贈与された資産が相続税の課税対象に含まれるか否かは、相続税の申告において、住宅取得等資金の贈与がされた時期にかかわらず、必ず確認されるべき事項であること、原告は、税理士との面談の際、税理士らに対し、本件贈与が相続税の課税対象とならないか念押しするとともに、土地を令和2年5月又は同年6月に売却する予定である旨告げたところ、税理士らは確定申告をするのであれば相続税の課税対象とならない旨回答したことからすれば、被告は、委任契約に基づき、原告らに対し、申告書の作成のみならず、相続税の申告に関係のある事実ないし特例の要件の確認として、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件等について、税理士自らが確認し、説明し、及び助言する義務を負っていた。 | 被告は、委任契約において、相続税の申告に係る事務を受任したものであり、住宅取得等資金の贈与に関して何らかの事務を受任したものではないから、適正な相続税の申告に必要な限度で本件贈与が相続税の課税対象とならないための要件を確認する義務を負うにすぎない。そして、住宅取得等資金の贈与がされた場合には、贈与が行われた年において贈与税の課税対象とならないための要件を具備できているか否かの事実が既に定まっており、相続税の申告を受任した税理士は、贈与税の課税対象とならないための要件を贈与税申告書の写しを確認すれば足り、贈与が贈与税の課税対象とならないための要件を満たしていることを独自に確認する義務を負わない。 |
なお、被相続人は、令和2年中に住宅取得のための資金として、およそ2,500万円を原告Aに贈与。その後、原告らは被相続人の死亡後に報酬を87万3,500円とする委任契約を被告である税理士法人と締結した(表3参照)。委任業務の範囲は、被相続人の相続に係る相続税の税務代理、税務相談、税務書類の作成とされている。
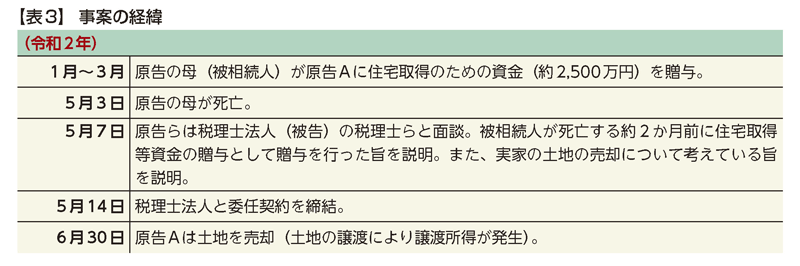
裁判所、受け取った資料で特例の要件を満たすかの確認は求められず
裁判所は、被告の税理士法人が原告らから贈与申告書等の資料を受け取ったとしても、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件を満たすか否かを確認するためには、収集された住宅取得等資金の贈与に関する資料を分析、検討した上で、資料を収集したり、不明点等を確認したりする必要があり、受け取った資料に基づき、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件を満たすか否かを直ちに確認することができるということはできないと指摘。また、資料収集を依頼する段階で、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件を満たすことを確認すべきであったということもできないとした。
したがって、税理士法人が原告らに対し、本件贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件の確認、説明又は助言をする旨の黙示の合意が存在したと認めることはできないとの判断を示し、原告らの請求を棄却した。
なお、裁判所は、住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならないことになる要件の中には、当該年度の合計所得金額が2,000万円以下であることなど、贈与の時点から見て将来に問題となる要件が存在したとしても、そのことから直ちに特定の時期に要件の確認、説明又は助言をするとの黙示の合意が存在するということはできないとの見解も示している。
委任契約の範囲に贈与税の税務代理は含まれず
本件の委任契約における業務について裁判所は、贈与が住宅取得等資金の贈与として相続税の課税対象とならない要件の確認、説明及び相談があった場合の助言をすることが含まれていると解することができるとしている。
しかし、住宅取得等資金の贈与は、所定の要件を満たして贈与税の課税対象とならない場合に、相続税の課税対象とならないという構造となっているところ、本件委任契約の対象は相続税の税務代理、税務相談、税務書類にすぎず、贈与税の税務代理等は含まれていないことが認められると判断している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























