解説記事2024年01月15日 巻頭特集 対談 消費税争訟事案の現状と展望(2024年1月15日号・№1010)
巻頭特集
対談
消費税争訟事案の現状と展望
北海道大学大学院法学研究科教授 佐藤修二
弁護士法人北浜法律事務所 弁護士・税理士 安田雄飛
従来、「国税」と言えば所得税、法人税がメインの税目だったが、令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことにより、現在は消費税が税収の最も多い国税となっている。これに伴い今後予想されるのが、消費税を巡る紛争の増加だ。既に消費税に関する審査請求、訴訟は毎年少なからず発生しており、審査請求においては取消事例も多い。
本対談では、ともに東京国税不服審判所で国税審判官を務めた経験を持つ北海道大学大学院法学研究科の佐藤修二 教授と弁護士法人北浜法律事務所の安田雄飛 弁護士・税理士に「消費税争訟事案の現状と展望」とのテーマで語っていただいた。消費税が主な争点となった訴訟における主な納税者勝訴事例、取消裁決における判断のポイントや特徴、消費税法の規定の解釈が問題となる場合の論点、さらにインボイス制度の施行に伴う消費税争訟事案の今後の展望など、話題は多岐に及んだ。消費税を巡る紛争では私法上の法律関係の認定が中心的な争点となることが多いだけに、税理士等には新たな気付きを与えるであろう貴重な対談となった。
はじめに
佐藤:今回は、北浜法律事務所の安田雄飛先生に、消費税に関する争訟事案の最近の動向について伺いたいと思います。安田先生は、国税不服審判所の任期付職員の経験を有しておられ、現在は、租税争訟(訴訟・審査請求)に精力的に取り組んでおられます。まずは、安田先生に自己紹介をお願いいたします。
安田:今回は対談の機会をいただきありがとうございます。私は、弁護士として会社関係訴訟、M&Aなど企業法務を経験した後、平成28年7月から3年間、東京国税不服審判所に国税審判官として勤務し、退官後は、税務調査対応や審査請求、訴訟といった租税争訟を主に取り扱っております。審判所では、法人税や国際課税のほか、消費税に関する審査請求事案に多く携わりました。たまたま携わる機会が多かったということに加えて、消費税事案は、国税職員や税理士・公認会計士の方々でもよく難しいとおっしゃる一方、私法上の法律関係の認定が中心的な争点となることが多く、弁護士としては、むしろ他の税目よりもお役に立てる部分が大きいと感じるようになりました。退官後も、消費税の税務調査対応や審査請求に関するご依頼が比較的多いこともあって、日頃から消費税に関する審査請求や訴訟の動向を強い関心を持って見ております。
消費税に関する争訟の全体像
最近の消費税争訟の動向
佐藤:早速ですが、最近の消費税争訟事案の動向について、聞いてまいりたいと思います。まずは、課税当局における調査体制や、国税不服審判所の動向についてお聞きしたいと思います。
安田:最近の動きとしては、消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられたことで、消費税が国の税収で最も収入額が大きい税目となっています(図表1参照)。
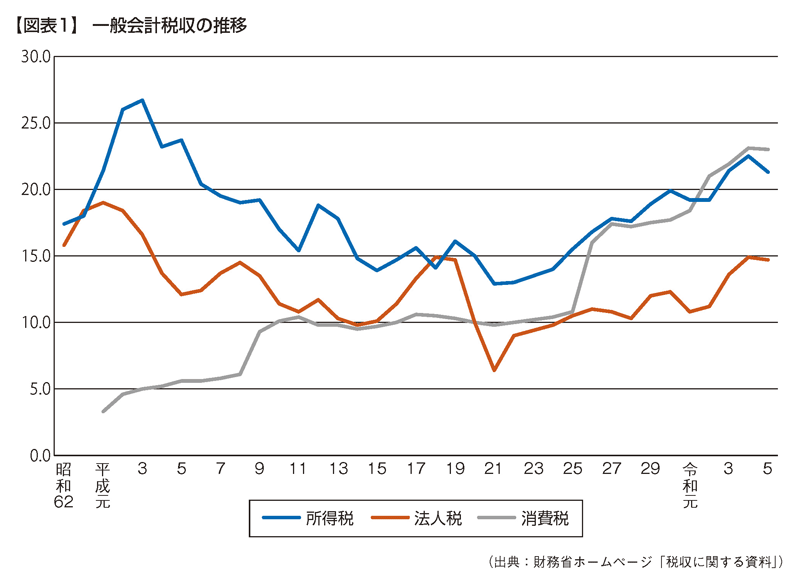
それに伴って、消費税還付申告の件数・金額も増加傾向にあります。このような流れを受けて、課税当局においては、「消費税不正還付事案」への対応として、令和3年度(脚注1)に各税務署に「消費税専門官」を、令和4年度には東京国税局に「消費税不正還付対策本部」をそれぞれ設置するなど、消費税調査を専門に担当する部署の体制が強化されています。
このような消費税の調査体制の強化を背景として、直近の令和4年度における消費税に関する審査請求事例の処理件数及び取消裁決の件数がともに増加しています。図表2は、国税不服審判所ホームページの「裁決要旨検索システム」から、各年度毎に、消費税に関する審査請求事例の裁決書の数と、そのうち取消裁決となった裁決書の数をまとめたものです。毎年度、消費税に関する裁決書数は20件から多い年でも50件程度であったものが、今年度は、令和5年3月末時点で既に55件に達しています。消費税に関する裁決書は、例年4月から6月までの期間に10~15件程度出されていますので、今年度(令和4年7月1日から令和5年6月30日まで)は65~70件程度にはなると見込まれます。また、そのうち取消裁決、つまり納税者の請求を認容して課税処分を取り消した裁決の数は、例年は0~5件であったのが、今年度は10件と2倍以上に増加していることが分かります。
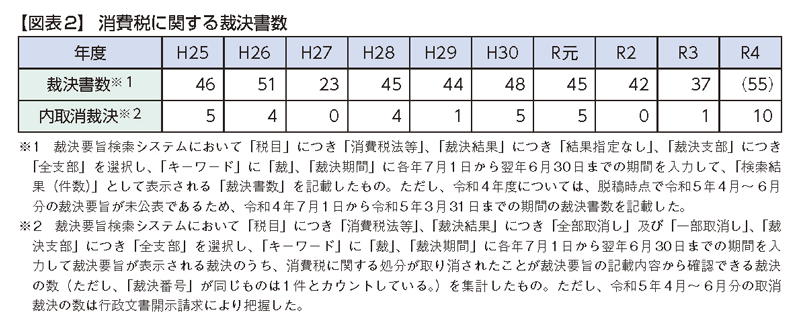
佐藤:たしかに今年度は消費税に関する裁決全体の数も、取消裁決の数も増えていますね。次に、訴訟はどのような状況ですか。
安田:国税庁のホームページで公表されている税目別の訴訟の発生状況に関する資料によれば、直近の消費税に関する訴訟の発生件数は図表3のとおりです。
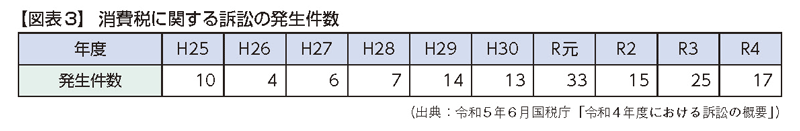
審査請求と訴訟における取消事例の比較
佐藤:訴訟でも、消費税に関する事例は毎年それなりに発生しているのですね。他方、私は、訴訟における消費税に関する納税者勝訴事例が少ないと思っていたので、それとの対比でみると、審査請求における取消裁決の数が多い印象を受けます。
安田:そうですね。訴訟において既に判決が確定した事例で、消費税に関する主な納税者勝訴事例としては、次の5件があります。
① 東京地判平成18年10月27日判タ1264号195頁〔入湯税事件〕
② 大阪地判平成25年6月18日裁判所ウェブサイト〔食肉問屋事件〕
③ 東京地判平成26年2月18日裁判所ウェブサイト〔岡本倶楽部事件〕
④ 大阪高判令和3年9月29日税資271号順号13609〔PiTaPaポイント交換事件〕
⑤ 東京地判令和4年6月7日裁判所ウェブサイト〔鑑定評価額按分事件〕
他にも、法人税に関する課税処分と併せて消費税に関する課税処分が取り消されたものなどはありますが、消費税が主な争点となったもので、納税者が勝訴した事案は、過去に遡っても、この5件ぐらいではないかと思います。これらの消費税の納税者勝訴判決は、いずれも上訴されることなく確定している点も、租税訴訟では比較的珍しく、一つの特徴と言えるかもしれません。
他方、審査請求においては、今年度に限らず、従前から、消費税事案で取消裁決が毎年のように出ており、直近10年間だけで計35件の取消裁決が出ています。
これらを全体として見ると、消費税に関する事例では、必ずしも納税者の請求が認容されにくいというわけではなく、むしろ、審査請求や下級審の段階で早期に課税処分の誤りが是正されているという見方も可能であると考えています。
消費税に関する訴訟における取消事例
佐藤:訴訟に比べて、審査請求での取消事例が多いというのは、なかなか興味深い傾向ですね。具体的な事案について伺っていきたいと思います。まずは訴訟における取消事例の特徴について教えていただけますか。
安田:訴訟における主な取消事例としては、先ほどご紹介した5件があり、そのうち3件が対価性が問題となった事例です。消費税の課税対象は(国内において)「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(消費税法2条1項8号、4条)で、課税標準は「課税資産の譲渡等の対価の額」である(同法28条1項)ところ、このうち、当事者間で支払われた金銭が役務提供などの「対価」として消費税の課税対象となるのかどうか、課税標準に含まれるのかどうか、というのが対価性の問題です。
入湯税事件では、鉱泉浴場(温泉)の経営者が納税義務者である入湯客から特別徴収すべき入湯税相当額が、消費税の課税標準である「課税資産の譲渡等の対価の額」に含まれるか否かが争われました。裁判所は、「少なくとも当事者の合理的意思解釈等により課税資産の譲渡等に係る当事者間で授受することとした取引価額と入湯税とを区別していたものと認められるときには」入湯税相当額については、「課税資産の譲渡等の対価の額」に含まない旨述べた上、結論としても、その区別がされていたと認めて「課税資産の譲渡等の対価の額」に該当しないとしました。入湯税相当額については、租税の特別徴収として授受されるものである限り、その性質上、「課税資産の譲渡等の対価の額」には含まれないと判断するのが自然だと思いますが、当事者の意思解釈次第で、取引価額と入湯税相当額とが全く区別されていないと判断される場合には、入湯税相当額も「課税資産の譲渡等の対価の額」に含まれると判断する余地をあえて残した判示になっている点が興味深いところです。
また、岡本倶楽部事件では、国内各所のホテルにおいて宿泊サービス等の提供を受けることができる会員制リゾートクラブである「岡本倶楽部」を主宰していた破産会社が会員から入会時に収受した金員の一部(本件金員)が何の対価であるのかが争われました。本件金員について、課税当局は、会員資格の付与という役務提供の対価であり、「課税資産の譲渡等の対価の額」に含まれると主張したのに対し、破産管財人は、会員に付与していた「宿泊ポイント」の対価であり、非課税である物品切手等に該当すると主張しました。裁判所は、結論として、本件金員は会員資格の付与ではなく、宿泊ポイントの対価であると認定し、非課税となると判断しました。裁判所は、その判断の過程で、「課税は、租税法律主義の目的である法的安定性を確保するという観点から、原則として私法上の法律関係に即して行われるべきである」とした上、「本件金員が何に対する対価であるかについては、本件各会員及び本件破産会社の両者を規律している本件入会契約の解釈によって定まるというべき」と判示しています。この判示は、対価性が私法上の法律関係の認定の問題であり、契約解釈によって判断されるべきことを明確に示したものと捉えています。そして、裁判所は、本件金員について、契約書の記載内容や契約締結時に会員が受けた説明の内容を踏まえ、契約解釈により、本件金員が宿泊ポイントの対価であると認定しています。
佐藤:私も、岡本倶楽部事件の判決は、課税が私法上の法律関係を基礎としてなされることを、はっきりと示した点に意義があると考えています。他方、大阪高判平成24年3月16日訟月58巻12号4163頁〔京都弁護士会事件〕は、消費税法上の「対価」に該当するためには、「当該具体的な役務提供があることを条件として、当該経済的利益が収受されるといい得ることを必要とするものの、それ以外の要件は法には要求されていない」として、いわゆる条件関係が必要であるという考え方を述べていますね。この判決では、なぜ条件関係という考え方が出てきたのでしょうか。
安田:京都弁護士会事件では、法律相談センターで法律相談を担当した弁護士がその事件を受任した場合に弁護士会に支払う「受任事件負担金」、司法修習生の実務指導に要する経費として司法研修所長が弁護士会に支払う「司法修習生研修委託費」など、弁護士会の各種収入の対価性が争われました。いずれも個別の契約に基づいて支払われる金銭ではなく、契約解釈によって対価性を判断しにくいことから、裁判所は、「当該具体的な役務提供があることを条件として、当該経済的利益が収受される」という判断基準を持ち出したのであろうと考えています。もっとも、この件では、国が条件関係により対価性を判断すべきと主張したのに対し、裁判所は、あえて「対応関係」が必要だと言い換えており、具体的な判断の過程を見ても、法律相談センターの規程の解釈や、司法修習委託金に関する当事者間のやり取りの内容も考慮していますので、私としては、そもそも、本件で裁判所が条件関係により対価性を判断したと見るべきかどうか、疑問があると考えています。
ただ、その後の課税実務や訴訟では、特に課税当局が対価性を条件関係により判断すべきだと主張するケースが目立つようになりました。
PiTaPaポイント交換事件でも、課税当局はそのような主張をしています。この件では、交通系ICカード「PiTaPa」を利用して決済を行った際に付与されるポイントを、提携企業が発行するポイントと交換できる仕組みになっており、その交換時に「PiTaPa」を発行する法人が、提携企業から、交換により付与されるポイントの数に応じた金員の支払を受けていました(図表4参照)。
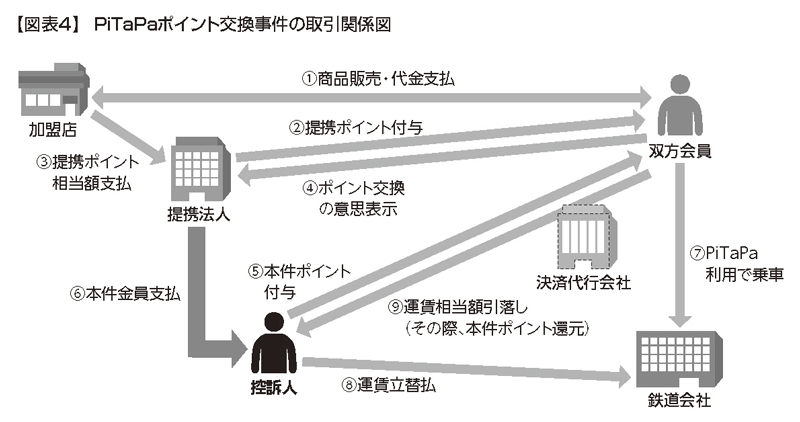
ここでは、ポイント交換に係る役務の提供がされない限り、当該金員が交付されないという条件関係があります。そこで、課税当局は、当該金員について、ポイントの交換に係る役務の提供を条件として収受するものであるから「対価」に該当すると主張し、第一審も対価性を肯定しました。しかし、控訴審は、消費税法2条1項8号にいう「対価を得て」とは「資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に対して反対給付を受けること」をいい、課税当局の主張するような条件関係が存するとしても、反対給付としての性質を有さず、無償取引に該当する場合には、「対価」には該当しないとの解釈を示して、結論としても、対価性を否定しました。私は、この判決には、「対価」該当性を条件関係により判断することを明確に否定した点に意義があると考えています。
佐藤:「対価」であるかどうかは、条件関係ではなく、反対給付としての性質を有するかどうかにより判断され、それは契約解釈によって判断されるということですね。その考え方のほうが、契約関係に着目するという点で、法曹から見ると違和感がないと思います。
安田:対価性は契約解釈によって判断するという考え方は、取消事例だけでなく、棄却事例でも同様に示されており、例えば、熊本地判平成21年2月19日税資259号順号11146があります。この事例では、納税者が、ワクチンの売買契約における契約金額の一部(本件差額金)が、実質的には厚労省からの補助金であり、「課税資産の譲渡等の対価の額」に当たらないと主張しました。しかし、裁判所は、「本件売買契約において売買代金として支払われたか否か、すなわち、原告と厚労省との間で、本件差額金を本件ワクチンの対価として支払う旨の合意があったと評価できるか」によって対価性を判断すべきであり、契約書の記載からそのように評価できる場合には「実質的な補助金として交付する旨の合意があったこと……を認めるに足りる特段の事情がない限りは」対価性を肯定すべきとの判断を示しています。本件の契約金額は約15億5千万円で、その算定根拠は、ワクチンの「単価」に数量を乗じた金額約6億8千万円に製造施設の建設費等約8億7千万円(本件差額金)を加算したというものでした。この譲渡したワクチンの客観的価値のみに着目すれば、契約金額から本件差額金を除いた部分がワクチンの売買の「対価」であるとの原告の主張にもそれなりの理由があったように思います。しかし、裁判所は、それよりも、契約書において支払額の全額が「契約金額」と記載され、特にその内訳の記載がなかったこと等を重視して、契約金額全額について対価性を認めました。
佐藤:裁判所が当事者間の合意・契約を重視して対価性を判断していることがよく分かる事例ですね。次に、食肉問屋事件はどのような事例ですか。
安田:食肉問屋事件では、出荷者から販売の委託等を受け、商法上の問屋(商法上の問屋は、「自己の名をもって」すなわち問屋自身が権利義務の主体となって、「他人のために」すなわち他人の「計算」で取引をすることを業とする者です(商法551条))の立場で食肉(牛枝肉)の卸売りを行っていた事業者(原告)が、買受人に対して有していた債権の貸倒れに係る消費税額について、消費税法39条1項による控除を受けられるかどうかが争われました。消費税法39条1項は、「課税資産の譲渡等……を行った」者が同項による控除を受ける旨を規定しています。この点に関し、課税当局は、「課税資産の譲渡等……を行った」者とは、「資産の譲渡等に係る対価を享受……する者」(消費税法13条1項)をいい、本件においてそれは出荷者であると主張しました。しかし、裁判所は、「資産の譲渡等を行った者の実質判定は、その法的実質によるべきものと解される」とした上、「原告が問屋として行う牛枝肉取引による牛枝肉の譲渡に係る対価を享受するのは原告ではなく委託者(出荷者)であるといえそうであるが、……牛枝肉取引の法的実質として、法律上資産(牛枝肉)の譲渡等を行ったとみられる者すなわち問屋である原告が、単なる名義人にすぎず、当該資産(牛枝肉)の譲渡等を行ったものではないということはできない」としました。さらに、売買代金回収のリスクも委託者(出荷者)ではなく原告が負っていること、買受人に対して瑕疵担保責任を負っているのも原告であることから、原告が消費税法39条1項による控除を受けることができると判断しました。
本件では、「課税資産の譲渡等」の主体が誰であるのかが問題となり、課税当局は、対価に係る経済的利益を享受する委託者が主体であると主張したのですが、裁判所は、資産の譲渡等を行った者が誰かは法的実質により判断すべきであり、それは本件では問屋である原告だと判断したわけです。課税当局が引用する消費税法13条1項は、資産の譲渡等を行った者の実質判定について定めた規定ですが、ここで問題にすべき実質が経済的実質ではなく法的実質である以上、結局は、資産の譲渡等を行った者が誰かの判定は、契約当事者が誰であるかの判断と基本的に重なることになると思います。
佐藤:商法上の「問屋」の場合、契約当事者の立場に立つのは、あくまで問屋(本件では原告の卸売事業者)であるという、商法における法的性質を踏まえた判断ということで、興味深いです。私が司法試験を受けたのは四半世紀も前ですが、口述試験で(あまり出題例は多くない)問屋が出題されたことを思い出しました。本件は、私法の検討を踏まえた、裁判所らしい判断であると感じました。
安田:以上の事例は、いずれも私法上の法律関係に即して判断したという点で共通した特徴があると考えています。他方、残る取消事例である鑑定評価額按分事件は、消費税の非課税資産である土地と課税資産である建物が、その対価の額を区分しないで一括譲渡された場合の対価の額の按分計算の方法が問題となった事案です。消費税法施行令45条3項によれば、この場合、対価の額を各資産の「価額」すなわち時価により按分して建物の譲渡に係る消費税の課税標準を計算することになります。裁判所は、当該資産の個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、価額費においても実質的な差異が生じた場合には、適正な鑑定に基づく評価額による価額費を用いて按分すべきとして、固定資産税評価額により按分してなされた課税処分を取り消しました。租税法上の時価評価の在り方に関わる判断事例であり、実務上は重要な裁判例ですが、資産の「価額」(時価)ではなく「対価の額」を課税標準とする消費税事案では、時価評価の在り方が問題になる場面は比較的少ないと言えます。
消費税に関する審査請求における取消事例
佐藤:次に、審査請求についてはいかがでしょうか。
安田:審査請求における最近の取消事例にも、やはり対価性や資産の譲渡等の当事者の認定が問題となったものが多く見られます。
対価性
安田:まず、対価性に関する取消事例として、令和元年6月13日裁決(東裁(法・諸)平30第161号)があります。この事例では、請求人が建造し、取引先による積荷の保証により運行していた船舶の使用を終了することに伴い、請求人が取引先から受領する金員について、課税当局が、取引先に対する役務の提供を完了したことによる対価であるから課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると主張しました。それに対し、審判所は、当該金員は、期間前に船舶の使用を中止したことにより、将来の輸送役務の対価として得られるはずであった逸失利益の補填をしたものであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないと判断しました。
同様に損害賠償金の対価性を否定した取消裁決が、最近他にも複数出ています。例えば、令和2年4月21日裁決(大裁(所・諸)令元第48号)(脚注2)では、請求人が、その所有する土地を父親が無断で第三者に駐車場として貸し付けたという不法行為を原因として父親から支払を受けた賃料相当損害金について、課税当局が、実質は駐車場としての貸付けに係る対価であると主張しました。これに対し、審判所は、請求人が駐車場として貸し付けることを承諾したわけではないことを理由に、課税資産の譲渡等の対価の額には当たらないと判断しました。
これらの事例では、支払われた金銭は、経済的に見れば、船舶の使用が中止された後の期間や土地が不法占有された期間の資産の貸付け等の対価に相当するのかもしれません。しかし、法的に見れば、請求人は、貸付け等の対価として受け取ったわけではなく、むしろ、貸付け等を行えなかったことより被った損害金として受け取ったわけですから、対価性がないという判断になったものと理解しています。
佐藤:ここでも、課税当局の、経済的実質を重視する、いわゆる「実質課税」のスタンスと、審判所の私法上の法律関係を重視するスタンスの違いが表れていますね。
資産の譲渡等の当事者
安田:次に、資産の譲渡等の当事者に関する取消事例として、令和2年5月19日裁決(札幌(諸)令元第6号)(脚注3)があります。この事例では、個人馬主である請求人が、農協のオークションで落札した軽種馬を、知人が代表者を務める法人(本件法人)を介して売主から購入しました。売買契約書も、請求人と本件法人との間、本件法人と売主との間にそれぞれ締結され、売買代金も、請求人は、落札額に一定の金額(本件差額)を上乗せした額を本件法人に支払い、本件法人が、落札額を売主に支払っています(図表5参照)。
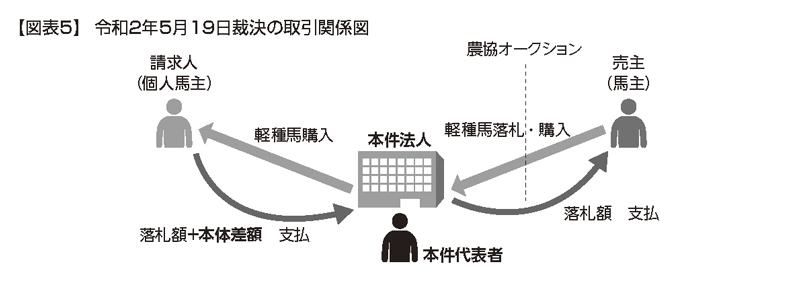
そこで、落札額だけでなく、本件差額も仕入税額控除の計算の基礎となる課税仕入れの対価の額に含めてよいかが問題となり、課税当局は、請求人と本件法人との軽種馬の売買契約は通謀虚偽表示・仮装取引であり、本件差額は課税仕入れの対価の額に当たらないと主張しました。たしかに、本件法人を売買の当事者として介在させる必然性があったかどうかは疑問がないわけではないかもしれませんが、審判所は、請求人と本件法人との間で売買契約書が存在し、その成立の真正に争いがないことを重視し、通謀虚偽表示であるなどの特別の事情がない以上、実体を伴わない取引であると認めることはできないと判断しました。
佐藤:審判所の判断は、法律行為を内容とする書面が真正に成立していれば、特段の事情がない限りその記載どおりの法律行為の存在を認定するという、「処分証書の法理」とも重なりますね。
安田:そうですね。ご承知のように、審判所では、法曹以外の職員も含め、「処分証書の法理」も含めた事実認定のルールについて教育を受けています。特に最近の裁決を見ていると、そのような法的な視点がより審判所に浸透してきているのではないかと感じています。
資産の譲渡等の時期
安田:資産の譲渡等の時期(課税仕入れの時期)に関する取消事例として、令和元年6月10日裁決(東裁(諸)平30第158号)があります。この事例では、新たに製造される変圧器を購入し、据付け及び検査が完了した後に古い変圧器が搬出されたという事実関係(図表6参照)の下で、課税当局が、古い変圧器の搬出までが代金の支払と対価関係にあり、その撤去・搬出の完了時が課税仕入れの時期であると主張しました。
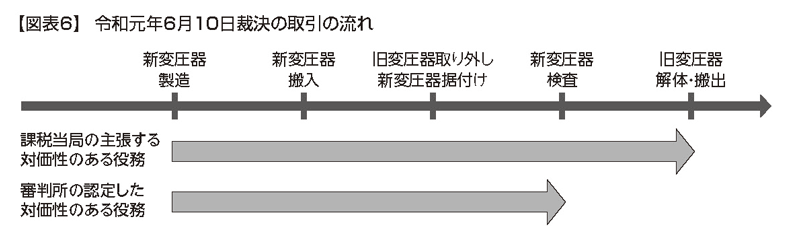
しかし、審判所は、契約書の記載、契約の目的、履行状況を考慮し、古い変圧器は無償で引き取ったもので対価性がなく、新しい変圧器の据付け後の検査が完了した時が課税仕入れの時期であると判断しました。ここでは、課税仕入れの時期との関係で、一連の役務の提供のうちどこまでが「課税仕入れ」に該当するのかが問題となっています。そして、「課税仕入れ」というためには、相手方にとって課税資産の譲渡等に該当するものであることを要し(消費税法2条1項12号)、したがって、対価性があることを要します。そうすると、一連の役務の提供のうち対価性があるのが、新しい変圧器の据付・検査までであるのか、その後の古い変圧器の搬出までであるのかを判断する必要があり、これは対価性の問題ですので、審判所は契約解釈によって前者であると判断したものです。
帳簿保存要件
佐藤:仕入税額控除を受けるためには、帳簿保存要件(消費税法30条7項)も満たす必要がありますね。帳簿保存要件については、帳簿の不提示が「帳簿を保存しない」場合に該当するかどうかに関する最高裁判例(脚注4)がありますが、審査請求においても、帳簿を作成・保存していたかどうか、税務調査において提示したかどうかに関する事実認定が問題となることが多いのでしょうか。
安田:おっしゃるとおり、最近の審査請求でも、帳簿保存要件について帳簿の不保存・不提示の事実認定が争われる事例は一定数あります。ただ、この点に関する課税当局の認定が誤りであると審判所が判断した事例は、最近の取消裁決には見当たりません。
他方、帳簿保存要件に関しては、帳簿の記載が真実の記載であるかどうかも問題となります(脚注5)。消費税の税務調査に関するご相談を受けていると、最近は、「消費税不正還付」に対する調査体制の強化の影響か、帳簿自体は作成・保存されていて、所定の事項が一応記載されている場合でも、課税当局が、帳簿に記載されている課税仕入れの当事者や対価の額が真実の記載でないから帳簿保存要件を充たさないとして仕入税額控除を否認するケースが増えているようです。最近の審査請求にも、帳簿保存要件の記載が真実かどうかが争われたケースがいくつか見られ、直近で取消裁決も出ています。
令和5年1月6日裁決(東裁(法・諸)令4第66号)は、帳簿に記載されている対価の額が真実でないとの課税当局の主張に理由がないと判断した事例です。この事例で、請求人は、高価な健康食品(ニコチンアミドモノヌクレオチド、NMN)を国内の関連会社から仕入れた(本件各商品仕入れ)上、輸出販売したとして、本件各商品仕入れの対価の額を、仕入税額控除の計算の基礎となる「課税仕入れの対価の額」に含めて消費税等の申告を行いました。これに対し、課税当局は、請求人が販売していた商品の原料が、NMNではなく、もっと安価な健康食品の原料(サジーエキス末)であったから、本件各商品仕入れについては、帳簿に記載した「課税仕入れに係る支払対価の額」が、実際にはもっと安価な商品であるはずであるのに、高価なNMNであることを前提とした著しく過大な金額が記載されている点で真実の記載でないため、帳簿保存要件を満たさないと主張しました。審判所は、商品の原料がNMNではなく安価なサジーエキス末であったことを前提としつつ、本件各商品仕入れについて、製造原価に比して著しく高額な金額を課税仕入れに係る支払対価の額として記載していたとしても、その対価の額において実際に取引が行われたのであれば、製造原価に比して著しく高額であることのみをもって真実の記載がされていないということはできないとして、帳簿保存要件を満たすと判断しました(脚注6)。製造原価に比して著しく高額であることに加えて、本件各商品仕入れに係る売買契約における対価の合意が通謀虚偽表示(仮装)であると認定できるような事情があれば、結論は異なり得たであろうと思います。しかし、そこまでの事情がないにもかかわらず、合意された対価の額が高すぎるという理由で真実ではないとは言えないというのが審判所の考え方だと理解しています。つまり、帳簿の記載が真実でないかどうかは、あくまで当事者の合意内容や効力に照らして、私法上の法律関係の認定を通じて判断されるべきということで、それを超えて、本来あるべき課税仕入れの相手方、支払対価の額に照らして真実かどうか、という議論をすることは正しくないということです。
非課税取引
佐藤:課税対象該当性や仕入税額控除の可否が争われる場面では、「資産の譲渡等」に係る私法上の法律関係の認定が重要になるということはよく分かりました。他方で、非課税取引や免税取引については、消費税法に固有の観点からの判断が必要になるということはないでしょうか。
安田:まず、非課税取引については、消費税の性質や社会政策的配慮から特に非課税と規定されているものですので、おっしゃるとおり、消費税法の規定の趣旨を踏まえて、規定の要件を解釈・適用して判断する必要が生ずる場面も少なくないと思います。例えば、最近の事例ではなく、また、棄却裁決ではありますが、介護付有料老人ホームの貸付けについて、非課税の対象となる「住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分)」(消費税法別表第一(第6条関係)第13号)の解釈が問題となった事例として、平成22年6月25日裁決・裁事79集591頁があります。この事例では、納税者は、入居者の個室だけが「住宅」に該当すると主張しました。しかし、審判所は、入居者自身が使用する居間・食堂や、さらにホームの職員が使用する事務室、宿直室、厨房、スタッフステーションといった部分も「住宅」に当たると判断しました。ここでは、誰が何のために使用しているかという生の事実自体には争いがなく、「住宅」の解釈と当てはめが問題となっています。審判所は、「住宅」の範囲について、住宅の貸付けが非課税とされた趣旨を踏まえ、「住宅賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分は、すべて住宅に含まれる」と広く解したことが、いずれの部分も非課税との判断につながったと言えます。
ただ、これは消費税の非課税取引の判断に限った話ではないのですが、事実自体に争いがなく、法令の解釈・適用が問題となる場面で、審判所が、課税当局の解釈・適用に誤りがあったと判断するケースは非常に稀です。そのためか、非課税取引該当性が問題となった事例において取消裁決はほとんど見当たりません(脚注7)。
輸出免税
安田:他方、輸出免税(消費税法7条1項)や輸出物品販売場(免税店)における輸出物品の譲渡に係る免税(消費税法8条1項)の規定の適用に関しては、やはり、資産の譲渡等に係る私法上の法律関係の認定が問題となることが多く、課税当局がその認定を誤ったとして課税処分を取り消す裁決も出てきています。
まず、輸出免税(消費税法7条1項)に関しては、課税資産の譲渡等が「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」等に該当することが要件です。「輸出」の事実やその証明(同条2項)の有無が問題となる場合があるほか、譲渡した資産が輸出されていても、「輸出として」行われる資産の譲渡かどうかが問題となる場合があります。この「輸出として」という要件に関しては、国外の輸出先に対する引渡しが国内で完了していないか、という形で譲渡の時期の認定が問題となったり、輸出先との間に国内の事業者が譲渡の当事者として関与していないか、という形で譲渡の当事者の認定が問題となったりします。後者の問題に関する取消事例として、令和4年10月25日裁決(福裁(法・諸)令4第8号)(脚注8)があります。この事例では、請求人が国内で仕入れた紙おむつパックが中国の事業者に輸出販売されていたのですが、中国の事業者からの受注や代金の受領が国内の他の法人(Q社ら)を介して行われ、輸出先に対してQ社らを荷送人とするインボイス、パッキングリスト及び船荷証券が発行されていました(図表7参照)。
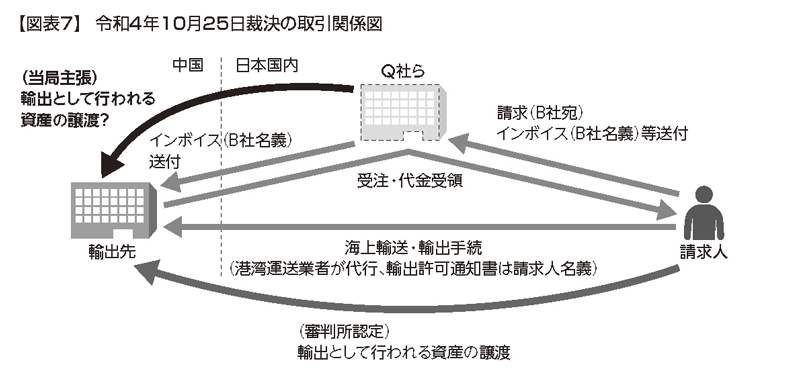
そこで、課税当局は、紙おむつパックは、請求人がQ社らに国内で譲渡した後、Q社らが中国の事業者に譲渡したものだと主張しました。これによると、請求人が行っていた資産の譲渡等は、「輸出として」行われる資産の譲渡に当たらないということになります。しかし、審判所は、請求人が国内で紙おむつパックを積載し、その海上輸送・輸出手続を港湾運送業者に委託し、輸出許可の名義人にもなっていたことを重視して、中国の事業者に対する輸出販売取引は、請求人による「輸出として」行われる資産の譲渡であると認定しました。Q社らについては、審判所は、契約当事者として関与したのではなく、あくまで窓口として業務を代行したに過ぎないと見たのだと思われます。
次に、輸出物品販売場における免税(消費税法8条1項)に関しては、「輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、政令で定める物品で、輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡」に該当することが要件です。
このうち、「政令で定める物品」に該当するためには、「通常生活の用に供しない」ものでないことを要し(消費税法施行令18条2項)、事業用として購入することが明らかなものは含まれないと解されています(脚注9)。事業用かどうかは、物品それ自体の性質のみならず、購入量や頻度なども考慮して判断されますので、例えば、一般の旅行客が購入する場合は免税対象になる物品でも、同じ者が反復継続的に大量に購入していれば免税の適用が否認される場合があります。また、「非居住者」については、入国後6月以上経過するに至った者はこれに該当しないと解されています(脚注10)が、免税店でこの点のチェックが漏れていたことで購入者が「非居住者」に当たらないとして否認される事例が少なくありません。これらの事例では、各要件に該当する事実の認定が主に問題となります。
他方、最近の審査請求事例によく見られるのが、免税店で提示された旅券の名義人である非居住者が実際の購入者ではなく、「政令で定める方法により購入」したとの要件を満たさないとして免税の適用が否認された事例です。ここでは、免税店で提示された旅券の名義人が真実の購入者であるかどうか、つまり、売買の当事者の認定が問題となります。この種の審査請求事例については、旅券の名義貸しがあり、旅券の名義人が真実の購入者でなかったと認定して審査請求を棄却する判断が続いています(脚注11)。もっとも、この点に関連して、購入者側でも、免税店で購入した物品を購入者が国内で譲渡した場合に免税額を徴収される規定(消費税法8条5項)があるところ、この規定を旅券の名義人に適用してなされた課税を一部取り消した裁決として、令和5年5月25日裁決(熊裁(諸)令4第7号)があります。この事例では、LINEで旅券の貸与に関するやり取りが行われていたことなどから、審判所は、一部の購入について旅券の名義貸しがあり、旅券の名義人が購入者ではなかったと認定しました。旅券は他人には貸与しないのが通常ですが、旅券の名義貸しがあったという判断が、それによって課税を取り消すことになる場面でもきちんとなされているという点は、第三者的な救済機関としての役割を果たしていると言えるかもしれません。
佐藤:国税不服審判所においても、私法上の観点も踏まえつつ、綿密な事実認定によって、課税処分の適否を判断しているようで、素晴らしいことだと思います。私もかつて、国税不服審判所に勤務し、国税職員の方々と一緒に仕事をしたことがあります。国税職員の皆さんは、事実認定について、高い観察眼とプライドを持っておられると感じました。その能力がいかんなく発揮されているのは、喜ばしいことだと思います。
安田:そうですね。私も、審判所で働いていた頃、国税職員の方々も、証拠が弱く、事実認定が甘い課税処分に対しては厳しい目でチェックされていると感じていました。審判所に来られる国税職員の方々は、皆さん課税の現場や審理でのご経験が豊富な方ばかりですので、おっしゃるようにプライドを持ってお仕事をされているのだと思います。
消費税法と法令解釈
佐藤:消費税に関する審査請求や訴訟では、法律関係や事実の認定が重要になるということはよく分かったのですが、消費税法の規定の解釈が問題となることはないのでしょうか。
安田:もちろん消費税法の規定の適用に当たっても、法令解釈は重要です。ただ、本日お話しさせていただいたとおり、「所得」という租税法固有の概念により課税対象を定める所得税法や法人税法と異なり、消費税法は、資産の譲渡等すなわち「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」という概念をベースに課税や仕入税額控除、免税の要件を規定しているため、争訟の場面では、やはり、資産の譲渡等の有無、当事者、時期や対価性に関し、私法上の法律関係の認定が問題となりやすいと言えます。
消費税法上の「対価」の意義
安田:消費税法の解釈に関して最も議論されてきた論点の一つは、消費税法の「対価」の意義の解釈だと思います。京都弁護士会事件で、裁判所が、「消費税は広く薄く課税対象を設定し、最終的に消費者への転嫁が予定」されているという消費税の性格から、対価性について「当該具体的な役務提供があることを条件として、当該経済的利益が収受される」という解釈を示したことをきっかけとして、学説でも、対価性の意義について様々な議論がなされてきました。しかし、裁判実務では、京都弁護士会事件のような特殊な事例を除いて、むしろ、対価性は条件関係ではなく契約解釈によって判断されてきたこと、最近のPiTaPaポイント交換事件では条件関係という判断基準が否定されたことは先に申し上げたとおりです。
転売目的でなされた居住用賃貸建物の取得の用途区分
安田:また、近年紛争が相次いで話題になった、転売目的でなされた居住用賃貸建物の取得の仕入税額控除に関する事例では、税負担の累積を排除するという仕入税額控除の趣旨に照らした法令解釈のあり方が問題となりました。この種のビジネスでは、建物の譲渡だけでなく敷地の譲渡も併せて行われることから、事業者の課税売上割合が低くなっているのが通常であるところ、建物取得の最終的な目的、主たる目的が転売という課税取引にあるのに、転売までの間、住宅の貸付けという非課税取引も行われるという理由で建物取得に係る課税仕入れを共通対応に区分すると、低い課税売上割合に応じた控除しか認められません。そこで、納税者側は、それでは税負担の累積が適正に排除されないから、用途区分に当たって、住宅の貸付けは考慮せず、課税対応に区分すべきであると主張しました。しかし、最判令和5年3月6日民集77巻3号440頁は、消費税法は、課税の明確性の確保や適正な徴税の実現といった他の目的との調和を図るため、税負担の累積が生じても仕入税額が控除されない場合があることを予定していると述べた上、建物が転売までの間、住宅として賃貸されており、その賃料を収受したことからすると、その事業における位置付けや事業者の意図等にかかわらず、共通対応に該当すると判断しました。ここでは、取得した建物は現に課税取引にも非課税取引にも用いられており、その意味で非課税取引にも事実上は対応しているので、消費税法の規定の適用上も、共通対応に区分されると解釈するのが素直な読み方だと言えます。それでも、税負担の累積の排除という仕入税額控除制度の趣旨から、非課税取引との対応を無視すべきかということが問題となったわけですが、その点は、最高裁は、課税の明確性の確保等の他の目的との関係で、税負担の累積の完全な排除がされないことは法も予定しているという考え方で、結論を変えるには至りませんでした。
その他
安田:ほかにも、帳簿保存要件における「保存」の意義、非課税規定の適用、輸出物品販売場に係る免税規定の「政令で定める物品」の意義など、個々の規定の趣旨目的に照らした法令解釈が問題となった場面は少なからずありますが、やはり、消費税に関する争訟の中心となっているのは、課税対象や仕入税額控除の基礎になる「資産の譲渡等」という要件であり、その判断は私法上の法律関係の認定と重なりやすいということだと思っています。
消費税争訟事案の今後の展望−インボイス制度施行の影響等
佐藤:最後に、消費税に関する争訟事案の今後の展望についてお考えを伺えればと思います。
安田:消費税の税収面での重要性の高まりと還付申告等に対する調査の強化の影響で、今後、消費税に関する争訟事案は増々増えるであろうと予想しています。
さらに、令和5年10月のインボイス制度の施行により、適格請求書(インボイス)の記載事項(消費税法57条の4第1項、図表8参照)が真実でない(課税仕入れに係る真実の法律関係と合致しない)として仕入税額控除を否認される(脚注12)など、新たな紛争類型が生じることも予想されます。消費税争訟事案が増加する中で、納税者にとっては、課税当局による私法上の法律関係の認定を争うことの重要性がますます高まっていくものと考えています。
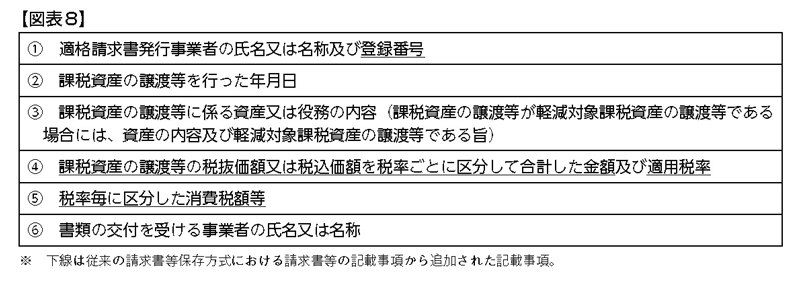
佐藤:ご指摘のような、インボイスの記載に誤記や意図的な記載事項の省略があった場合に、仕入税額控除が認められるのかという点は、実務的にも重要ですね。より詳しくご説明いただけますか。
安田:まず、適格請求書の記載事項が記載されていても、適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類(いわゆる偽インボイス)は、そもそも「適格請求書」に該当しない書類であると整理されています(消費税法57条の5第1号参照)。この場合、その課税仕入れについて控除の対象となる「適格請求書……の記載事項を基礎として計算した金額」(同法30条1項括弧書)がないことになるため、基本的に仕入税額控除を受けられないこととなると解されます。
他方、適格請求書発行事業者が適格請求書の記載事項を記載して作成した請求書等の書類は、その内容に誤りがあっても、基本的には「適格請求書」に該当するものと解されます(同法57条の4第1項、57条の5第2号)。この場合、その課税仕入れについて控除の対象となる「適格請求書……の記載事項を基礎として計算した金額」もあるということになりそうです(脚注13)。しかし帳簿保存要件(同法30条7項)に関する従前の裁判例(脚注14)を踏まえると、請求書等の記載事項(同条9項)の記載が真実でない場合は、同条7項の「帳簿及び請求書等〔引用注:同条9項で適格請求書等に限定されている。〕……を保存しない場合」に該当するとして、仕入税額控除の適用が否認されるケースが生じることが懸念されます。この点、帳簿や適格請求書の記載が真実でない場合でも、それが真実であると信ずる相当の理由がある場合には、「帳簿及び請求書等……を保存しない」場合には該当しないと解し(脚注15)、あるいは、「帳簿及び請求書等……を保存しない」場合に該当するとしても「やむを得ない事情」(同項但書)があるため仕入税額控除が認められると解する(脚注16)余地があります。また、国税庁の説明によれば、これまでも、軽微な記載事項の不備に関しては、軽微な記載不備を目的とした調査は実施しておらず、インボイス制度施行後、仮に調査等の過程で、適格請求書の記載事項の軽微なミスを把握しても、適格請求書に必要な記載事項を他の書類等で確認し、あるいは修正された適格請求書を交付させる等、柔軟に対応する方針とのことです(脚注17)ので、適格請求書の記載事項に軽微な誤りがあっただけで直ちに仕入税額控除の否認による消費税の追徴がなされるということにはならないかもしれません。もっとも、例えば、課税仕入れの相手方の氏名等の記載について言えば、従前は相手方が誰であっても消費税法30条1項の要件を満たしたような取引でも、今後は、相手方が適格請求書発行事業者であるか等、相手方の属性によって同項の要件を満たすか否かが異なり得ることになります。その意味で、帳簿や適格請求書における相手方の氏名等の記載の税務調査における重要性も高まると思われ、その分、記載の真実性やその確認についての事業者の責任が問題とされる場面が増えることが予想されます。また、適格請求書においては、従前の請求書等で記載が要求されていなかった適用税率及び消費税額等が新たに事項として追加され、これらに関する認識を次の事業者に伝達するというのが適格請求書の機能である(脚注18)ところ、これらの記載事項に(重大な)誤りがある場合に仕入税額控除が否認されるか、ということは今後の新たな問題であると言えます。
佐藤:ありがとうございました。帳簿保存要件に関する最高裁平成16年判決(脚注19)も、条文上は「保存」が要求されているだけなのに、「不提示」の場合も「保存」していなかったことになる、という点には批判が多いようです。仕入税額控除は、付加価値税としての消費税にとって要となるものであり、紛争になった場合はもちろん、それ以前の課税当局の対応としても、現実的にバランスの取れた対応が望まれるように思います。
私は今、北海道大学で租税法を教えていますが、消費税は、学生さんにとっても身近で関心も高いようです。その一方で、実際の争訟事案がどのように動いているのかを、法律家の立場から検討した文献は、目立たない印象がありました。今回は、安田先生に実情を教えていただき、大変勉強になりました。
消費税法30条
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ……については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)……の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(……)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(……)の合計額を控除する。
2−6 (省略)
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
8 (省略)
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録(……)をいう。
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次号及び第三号において同じ。)を行う他の事業者(適格請求書発行事業者に限る。次号及び第三号において同じ。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書
二~五 (省略)
消費税法57条の4
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
一~六 (省略)
2・3 (省略)
4 適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
5~7 (省略)
消費税法57条の5
適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
三 (省略)
脚注
1 「年度」は事務年度(7月1日から翌年6月30日まで)を指す。以下同じ。
2 裁事119集25頁。
3 裁事119集113頁。
4 最判平成16年12月16日民集58巻9号2458頁、最判平成16年12月20日判時1889号42頁、最判平成17年3月10日民集59巻2号379頁。
5 医薬品の現金卸売業において、帳簿に真実と異なる課税仕入れの相手方の氏名等を記載(仮名で記載)し、この種の事業において仕入取引の相手方の氏名等を明らかにすると取引先が離れてしまうので氏名等を確認することは困難であると主張した事案で、消費税法30条7項の帳簿の記載は真実の記載であることが要求される旨判示した下級審裁判例として東京高判平成10年9月30日税資238号450頁。
6 ただし、本件では、請求人がまずNMNの原料を仕入れ、関連会社に商品の製造を委託し、関連会社から商品を仕入れて(本件各商品仕入れ)輸出販売するという商流が申告の前提となっていたところ、このうち、原料の仕入れについては、実際に仕入れていたのがサジーエキス末であり、NMNの仕入れの事実がないとして仕入税額控除が否認されている。また、本件各商品仕入れについては、請求人において仕入税額控除が認められた一方で、関連会社においては、課税売上げとして消費税が課税されていると思われる。
7 裁決要旨検索システムの「争点番号検索」で「1.争点番号」につき「2課税範囲/3非課税取引」の全ての項目を選択し、「2.裁決結果」につき「全部取消し」及び「一部取消し」、「3.裁決期間」につき「全期間」、「4.裁決支部」につき「全支部」を選択して検索すると、検索結果として表示される裁決要旨から取消裁決であることが確認できるのは、非課税取引から除かれる消費税法施行令8条「駐車場施設の利用に伴って土地が使用された場合」該当性に関する平成20年3月28日裁決(関裁(諸)平19第37号)のみ。
8 裁事129集117頁。
9 広島高判平成25年10月17日税資263号順号12309等。
10 消費税法8条1項、外国為替及び外国貿易法6条1項6号、昭和55年11月29日付蔵国第4672号「外国為替法令の解釈及び運用について」
11 平成30年7月2日裁決(東裁(諸)平30第1号)、令和4年10月19日裁決(東裁(諸)令4第32号)、令和4年12月1日(関裁(諸)令4第22号)等。
12 佐藤英明=西山由美『スタンダード消費税法』(弘文堂・2022)234頁。
13 適格請求書の記載事項の誤りがあった場合、適格請求書発行事業者は修正した適格請求書を交付する義務(消費税法57条の4第4項)を負うところ、本誌950号11頁「調査時も売手に適格請求書再交付義務」によれば、売手が税務調査において過去の課税期間における適格請求書の記載事項の誤りが判明し、修正された適格請求書が再交付された場合、それによって再交付を受けた買手側が消費税額を過大に納めすぎていることになれば、更正の請求が可能であることが当局に対する取材において確認されている。
14 前掲注(5)。
15 広島地判平成11年2月18日税資240号716頁、平成14年4月3日裁決(大裁(諸)平13第71号)裁事63集653頁、平成21年1月28日裁決(仙裁(法・諸)平20第8号)裁事77集518頁等。結論はいずれも帳簿の保存がないとして仕入税額控除を否定。
16 消基通11-2-22及び8-1-3(2)によれば、消費税法30条7項の「やむを得ない事情」には、災害に準ずるような状況以外に「当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態」が含まれる。課税仕入れの相手方の真実の氏名等を記載した帳簿の保存をすることができなかったことにつき「やむを得ない事情」の有無を検討したものとして、前掲注(6)東京地判平成9年8月28日、平成15年6月13日裁決(名裁(諸)平14第15号)等。
17 令和5年8月25日付け国税庁「インボイス制度の周知広報等の取組み方針について」(内閣官房「適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議」第3回資料)。
18 国税庁「平成28年度税制改正の解説」808、809頁。
19 前掲注(4)。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年 東京大学法学部卒業、2000年 弁護士登録。2005年 ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.,Tax Concentration)。2011年~14年 東京国税不服審判所(国税審判官)。2019年~22年 東京大学法科大学院客員教授。2022年~現在 北海道大学大学院法学研究科教授。
著書に、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)、『夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話』(共著、中央経済社、2020)など。
安田雄飛 (やすだ ゆうと)
2008年 京都大学法学部卒業、2010年 京都大学法科大学院修了、2011年 弁護士登録。2012年~16年 三宅坂総合法律事務所、2016年~19年 東京国税不服審判所(国税審判官)を経て、2019年 北浜法律事務所に入所し、現在、同事務所パートナー弁護士。
論文として「デット・エクイティ・スワップにおける債権の「時価」」(月刊税理62巻15号149頁)、「ヤフー事件最高裁判決後初の法人税法132条の2に関する判断事例 “TPR事件判決”の問題点」(税務通信3584号18頁)、「転売目的でなされた居住用賃貸建物取得の仕入税額控除を巡って」(税経通信78巻7号83頁)など。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















