解説記事2024年02月26日 ニュース特集 金融商品取引法の改正も視野にサステナビリティ情報の保証制度導入へ(2024年2月26日号・№1016)
ニュース特集
気候変動などを有価証券報告書に開示
金融商品取引法の改正も視野にサステナビリティ情報の保証制度導入へ
金融審議会(会長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)は2月19日、鈴木俊一金融担当大臣の諮問を受け、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方」について検討することを決めた。現在、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が開発中のサステナビリティ開示基準で規定された開示項目を有価証券報告書に取り込むとともに、第三者保証のあり方について検討する。適用対象や適用時期は、新たに設置した「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(仮称)」で詳細を詰めるが、グローバル投資家との建設的な対話を行うとの観点から、当初はプライム市場上場会社又はその一部とする方向。また、SSBJのサステナビリティ開示基準の最終化が2025年3月を予定しているため、早くても2026年3月期からの適用となりそうだ。
なお、有価証券報告書における開示については、内閣府令等を改正することで実現するが、第三者保証に関しては、仮に監査証明と同様の仕組みを導入する場合には、金融商品取引法の改正が必要となる。
国際的な水準であれば日本版S1・S2基準の項目を法定開示対象に
2月19日開催の金融審議会総会では、鈴木俊一金融担当大臣により「サステナビリティ情報に係る昨今の国際的な動向や要請を踏まえ、我が国資本市場の一層の機能発揮に向け、投資家が中長期的な企業価値を評価し、建設的な対話を行うに当たって必要となる情報を、信頼性を確保しながら提供できるよう、同情報の開示やこれに対する保証のあり方について検討を行うこと。」との諮問が行われた。
これを受け、金融審議会では、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(仮称)」(以下、「サステナビリティWG」という)を設置し、およそ1年程度かけて検討を行うこととしている。
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は昨年6月にサステナビリティ関連財務情報の開示基準であるS1基準、S2基準を最終化している。日本のSSBJも今年3月には日本版S1基準及びS2基準の公開草案を公表する予定。その後、7月末頃まで意見募集を行い、2025年3月末までに最終化を行うとしている(今号7頁参照)。
日本では、2023年3月期から有価証券報告書においてサステナビリティ情報の一部が開示されているが(次頁参照)、個別具体的な基準はない。今回、サステナビリティWGでは、SSBJが開発する日本版S1基準及びS2基準の開示項目を有価証券報告書において開示する方向で検討を行うことになる。国際的なサステナビリティ情報の開示基準と同じ水準であればそのまま法定開示に取り入れられる可能性が高い。
2023年3月期から有報にサステナビリティ情報を一部開示
2023年3月期より、有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、「ガバナンス」及び「リスク管理」が必須記載事項となり、「戦略」及び「指標及び目標」は重要性に応じて記載を求めることとされた。
また、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載を求めることになったほか、提出会社やその連結子会社が女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表する場合には、公表するこれらの指標について、有価証券報告書等においても記載を求めることとなっている。
なお、有価証券報告書への法定開示については、内閣府令による改正が予定されている。
対象はプライム上場会社又はその一部
適用対象については、プライム上場会社又はその一部の会社となる模様だ。すでにお伝えしているとおり、2月6日開催のSSBJでは、金融庁より、「我が国のサステナビリティ関連財務情報に関する開示制度について、IFRSサステナビリティ開示基準との国際的な比較可能性の確保の必要性等も踏まえ、SSBJの公表するサステナビリティ開示基準の適用が要請される企業の範囲は、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(東京証券取引所のプライム上場会社又はその一部)と想定することが考えられる」との説明が行われ、SSBJも金融庁の方針を受け入れ、サステナビリティ開示基準案にプライム市場上場会社又はその一部の上場会社に適用することを前提とした基準である旨を明記する方針を明らかにしている(本誌1015号16頁参照)。
有価証券報告書での法定開示についてもプライム上場会社又はその一部の会社となり、今後、サステナビリティWGで決められることになる。
早くても2026年3月期からの適用
適用についても、今後、サステナビリティWGで決められることになるが、SSBJの日本版S1基準及びS2基準の最終化が2025年3月の予定となっているため、強制適用時期は、最短でも2026年3月期からとなる。
なお、日本版S1基準及びS2基準では強制適用時期は明記しないこととなっているが、3本の基準を同時に適用することを条件に、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができるとしているため、そのまま基準が確定すれば、2025年3月期からの早期適用は認められることになる。
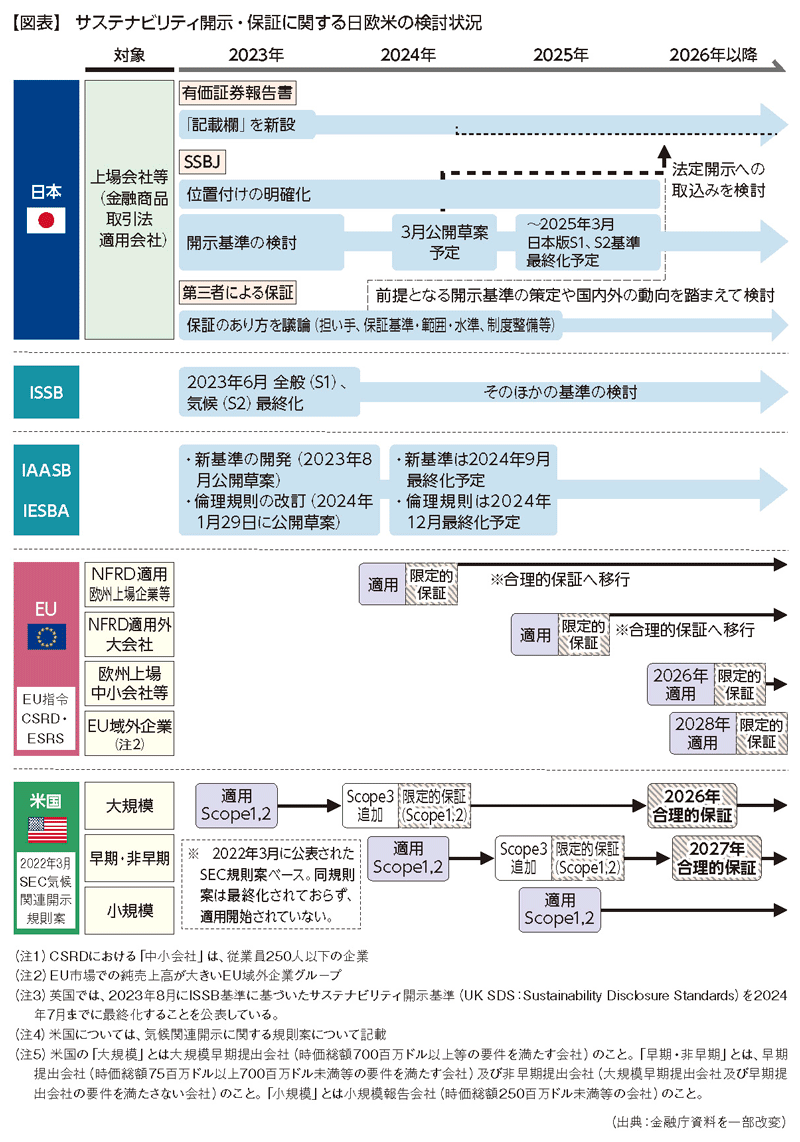
諸外国では保証の担い手は監査人に限定せず
気候変動等のサステナビリティ情報を開示するに当たって、一番の課題は第三者保証のあり方だ。担い手、保証基準・範囲・水準、制度整備等が論点となる。
海外の状況をみると、国際監査・保証基準審議会(IAASB)は昨年8月にサステナビリティ保証に関する新基準の公開草案を公表し、今年9月を目途に最終決定する予定。併せて国際会計士倫理基準審議会(IESBA)が倫理規則の改正を今年12月頃までに最終化するとしている。保証業務の提供者は監査人に限定しない方向となっており、保証の水準については、欧州は2024会計年度より順次限定的保証とし、その後合理的保証へ移行する予定。米国についてもスコープ1・2について、2024会計年度より順次限定的保証とし、2026会計年度より合理的保証を要求する予定となっている。
現在、日本では、任意でサステナビリティ情報に対する保証を行っている企業も多いが、金融庁によると、日経225企業において保証が付けられているのは65%で、このうち監査法人や監査法人系会社以外のISO認証機関等が54%にのぼっているという。
諸外国の例にならえば、日本においても保証業務の提供者は監査人に限定しないことが有力視される。
なお、合理的保証とは、結論を表明する基礎として、業務実施者が保証業務リスクを個々の業務の状況において受入可能な低い水準に抑えた保証業務であり、限定的保証よりも保証水準が高いとされる。イメージ的に合理的保証は監査と同様のものであり、仮に保証水準を合理的保証とするのであれば、金融商品取引法の改正が必要となってくる。サステナビリティ情報の開示と保証を同じタイミングで導入するかどうかも含め、サステナビリティWGの今後の検討課題となる。
SSBJが3本のサステナビリティ開示基準案を公表へ
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、3月中にも「サステナビリティ開示基準の適用(案)」のほか、「一般開示基準(案)」及び「気候関連開示基準(案)」を公表する予定だ。4か月程度意見募集を行い、来年3月までに決定する。強制時期については定められておらず、「適用基準」「一般基準」及び「気候基準」を同時に適用することを条件に、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができる旨が提案されている。
注目の温室効果ガス排出については、気候関連開示基準案では、スコープ1、スコープ2及びスコープ3の温室効果ガス排出の絶対総量の合計値を開示しなければならないこととしている。ただし、基準を適用する最初の年次報告期間については、スコープ3の温室効果ガス排出を開示しないことができる経過措置も設けられている。
なお、サステナビリティ開示基準案は、国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとするため、原則としてグローバル・ベースラインとされるIFRSサステナビリティ開示基準を取り入れているが、企業に過度の負担をかけることが明らかであると判断される場合など、すべての定めを無条件で取り入れることはしないこととしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























