解説記事2024年03月11日 SCOPE 相続後に実現した債務免除益、高裁は所得税課税を認めず(2024年3月11日号・№1018)
課税処分全部取消しで納税者逆転勝訴
相続後に実現した債務免除益、高裁は所得税課税を認めず
相続により承継した債務の債務免除益に対する所得税の課税の是非が争われていた事案の一審では、弁護士費用の控除が認められた以外は原告が敗訴していたが、控訴審では一転、原告の全面勝訴となった。
東京地裁は、免除が予定されていた当該債務は、「確実と認められるもの」として相続税の計算上負債として考慮することはできず、一方、相続後に現に実現した債務免除益に対して所得税が課されることはやむを得ないとして課税処分を適法としていたが(本誌972号参照)、東京高裁第16民事部(土田昭彦裁判長)は、「当該債務免除に係る相続人の利益は、形式的には債務免除を受けた時点で発生したものといえるとしても、所得税課税との関係では、潜在的には相続により取得していたものとみることが可能」として、所得税等の更正処分等を取り消した(令和6年1月25日判決)。
控除されなかった相続債務、相続後の免除益に所得税は課せず
亡M夫の相続人である原告らは、亡M夫の本件銀行に対する債務を相続し、その後、同債務について亡M夫と本件銀行との間で成立していた一定額の分割金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき、上記債務の分割金支払後の残部について本件銀行から免除を受けた。本件は、当該債務免除益が一時所得に係る総収入金額にあたるとして、原告らが所得税等の更正処分を受けたことから訴訟に至った事案である。
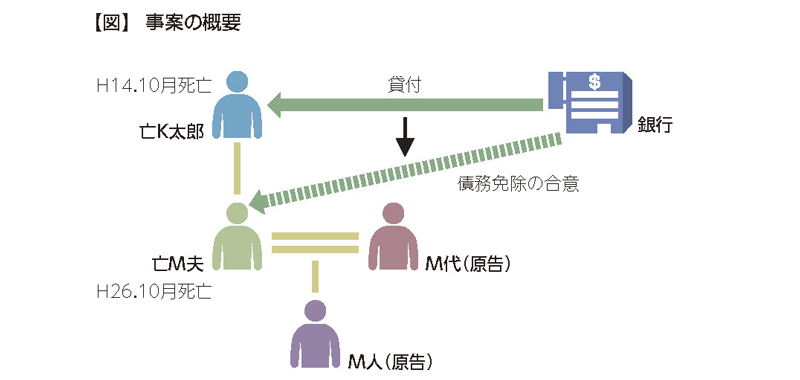
原告らは、亡M夫の相続財産から本件債務を控除せずに課税価格を算定して相続税を課しておきながら、本件債務の免除がなされた時には本件債務の存在を前提にその免除益が発生したとしてこれに所得税を課すのは、所得税法9条1項16号に反する二重課税として許されないと主張していた。
一審の東京地裁は、本件債務は原告らが分割金の支払いを行えば免除されるものであったことからすれば、「確実と認められるもの」とはいえず、相続税の算定において考慮されなかったのは当然のこととした。一方、所得税法9条1項16号の規定は、「相続時に『確実と認められ』なかったために控除が認められなかった債務を対象として想定した規定とは解されず、殊に、相続発生時の後に停止条件が成就した結果発生すべき債務免除益に適用されるものとは解されない」との考えを示し、原告らの訴えを斥けていた。
債務免除で相続人に新たな担税力生じず
これに対し東京高裁は、まず所得税法9条1項16号の趣旨について、最高裁平成22年7月6日判決を引用し、「相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税の二重課税を排除したものであると解される」と述べた。続いて、相続税法の規定について、「相続財産の取得者が被相続人の債務を承継して負担する場合にはその負担分については担税力が減殺されることになるから、相続財産からの当該債務の控除を認めるとするのが相続税法13条1項1号の趣旨であり、被相続人から承継する債務が『確実と認められるもの』でない場合には担税力が減殺されることにはならないから、当該債務については相続財産からの控除を認めないとするのが同法14条1項の趣旨であると解される」とし、これらの規定の趣旨を踏まえれば、「担税力を減殺させるものではないとして相続財産から控除されなかった相続債務が相続開始後に免除を受けたからといって、これにより債務者に新たな担税力が生じるものと解することは相当ではない」との考えを示した。
控除されなかった債務と経済的価値は同一
さらに、「被相続人から承継した現に存する債務であって、近い将来に免除を受ける可能性が極めて高いこと等を理由に相続税法14条1項の『確実と認められるもの』にあたらないとして相続財産から控除されなかった債務が、その後に債権者により免除された場合における当該債務免除に係る相続人の利益については、形式的には債務免除を受けた時点で発生したものといえるとしても、所得税課税との関係では、潜在的には相続により取得していたものとみることが可能」と指摘。当該債務免除益は、「その具体的な内容をみても、相続財産から控除されなかった上記債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができるから、特段の事情のない限り、これに所得税の課税をすることは、所得税法9条1項16号に反する」とした。
その上で、本件債務免除益は、上記のような相続人の利益にあたり、本件債務を相続財産から控除した場合としない場合の相続税の増加額(約2億円)と、本件債務免除益を一時所得として所得税の課税をした場合とした場合の所得税等の本税額の増加額(約2億円)に結果的に著しい差がないことなどの状況に照らしても上記特段の事情は見当たらないとして、原処分を取り消す判決を下した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























