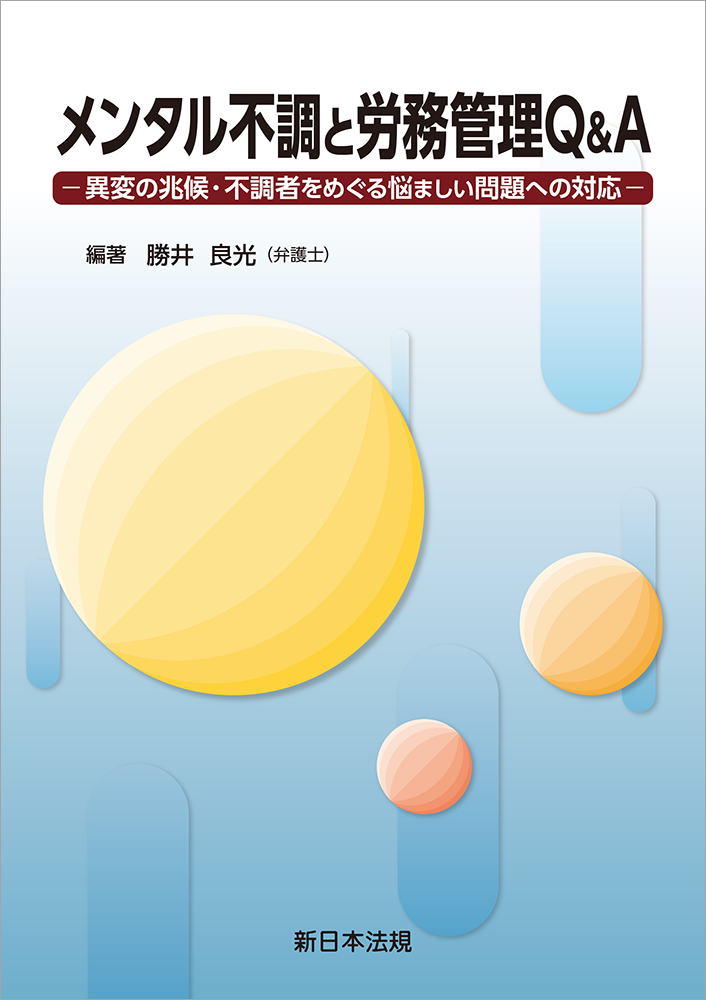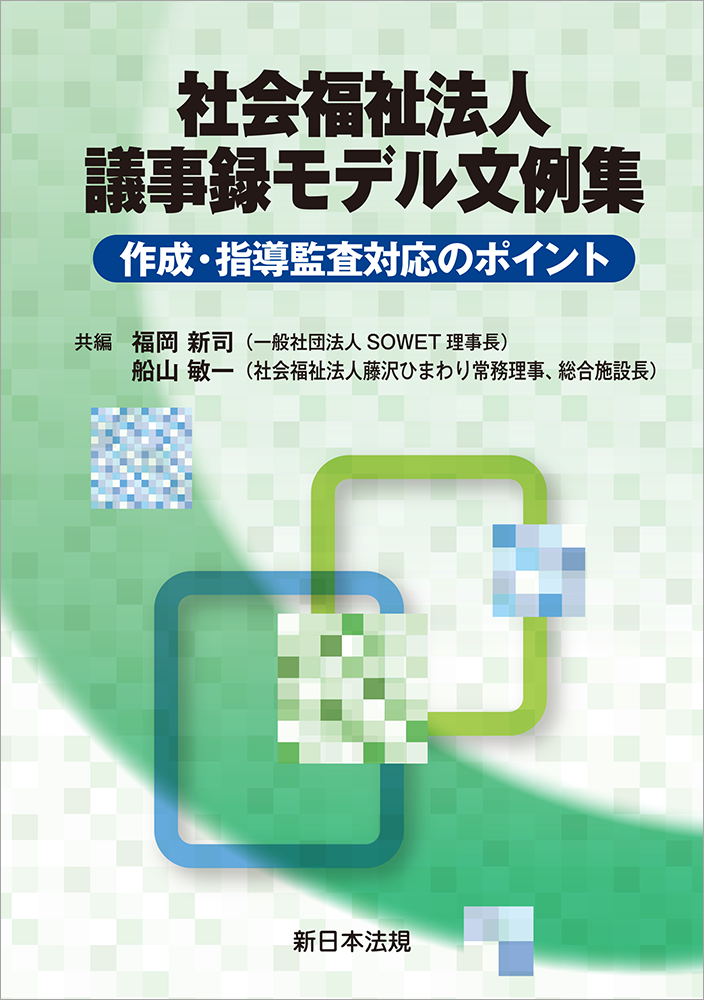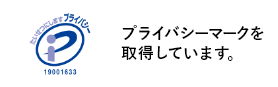解説記事2024年03月25日 未公開判決事例紹介 価額弁償金は和解の成立により確定(2024年3月25日号・№1020)
未公開判決事例紹介
価額弁償金は和解の成立により確定
東京地裁、更正の請求期限を満たさず原告敗訴
本誌988号8頁で紹介した相続税更正処分取消請求事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する。
〇裁判での和解の成立により支払った価額弁償金がいつの時点で確定したかが争われた事件。東京地方裁判所(品田幸男裁判長)は令和5年6月29日、原告が弁償すべき価額弁償金の額は、和解の成立によって「確定」したものというべきであるとした上で、遺留分減殺請求(現「遺留分侵害額請求」)を受けて価額弁償金を支払ったことによる相続税の更正の請求は、弁償すべき額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内になされていないとして原告の請求を棄却した(令和4年(行ウ)第485号)。
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
S税務署長が令和3年6月29日付けで原告に対してした被相続人Mの平成22年4月13日相続開始に係る相続税の更正処分のうち課税価格4402万4000円及び納付すべき税額189万8200円を超える部分を取り消す。
第2 事案の概要
原告は、被相続人Mの相続について、相続税の申告をした後、裁判上の和解により定められた価額弁償金を遺留分権利者に支払ったことから、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったなどとして、更正の請求をした。これに対し、S税務署長は、上記価額弁償金は上記裁判上の和解の成立によって「弁償すべき額が確定」したものであり、原告は当該事由を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をしていないから更正をすべき理由がないとして、これを前提とする更正処分をした。
本件は、原告が、上記価額弁償金は現実にこれを支払うことによって「弁償すべき額が確定」すると主張して、上記更正処分のうち、上記価額弁償金に係る更正の請求を認めなかった部分の取消しを求める事案である。
1 関係法令の定め
相続税法32条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)が定める相続税に係る更正の請求の特則の概要は、次のとおりである。
相続税について申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき国税通則法23条1項の規定による更正の請求をすることができる。
1及び2号 略
3号 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
4ないし9号 略
2 前提事実
当事者間に争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実は、次のとおりである。
(1)相続の開始等
ア 被相続人M(以下「亡M」という。)は、平成22年4月13日に死亡し、その相続が開始した。亡Mの法定相続人は、長男A(以下「A」という。)、三男原告、四男D(以下「D」という。)並びに二男B(平成3年死亡)の代襲相続人であるB1(以下「B1」という。)、B2(以下「B2」という。)及びB3(以下「B3」という。)の6名(以下「本件共同相続人」という。)であった(別紙1相続関係図参照)。
亡Mは、平成9年7月10日付け公正証書遺言により、原告及び原告の長男であるC1(以下「C1」という。)に対し、遺産の一部を相続させ、又は遺贈した。
イ A、原告、D、B2及びC1は、平成23年2月14日、S税務署長に対し、亡Mの相続に係る相続税に係る申告書を提出した。この申告に係る原告の課税価格及び納付すべき税額は、別紙2課税処分等の経緯の順号1欄記載のとおりである。
(2)遺留分減殺請求と裁判上の和解の成立等
ア A及びB1は、平成23年2月28日、原告及びC1に対し、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの。以下同じ)1031条に基づく遺留分減殺請求権を行使し、平成23年10月12日、同人らを被告として、相続財産である不動産につき所有権の一部移転登記手続などを求める訴訟を東京地方裁判所に提起した(同裁判所同年(ワ)第33231号)。
上記訴訟においては、その後、A及びB1と原告及びC1との間で、平成28年4月13日、要旨以下のとおり裁判上の和解が成立した(以下、この裁判上の和解を「本件和解」という。また、原告及びC1が本件和解により遺留分に係る価額弁償金として支払義務を負った金員を「本件価額弁償金」という。)。
(ア)原告及びC1は、Aに対し、連帯して、遺留分として2625万4102円及び和解金500万円の支払義務があることを認める。
(イ)原告及びC1は、B1に対し、連帯して、遺留分として1117万3455円及び和解金500万円の支払義務があることを認める。
イ Dは、遺留分減殺請求権を行使し、Dの死亡後、その子であるD1(以下「D1」という。)と原告及びC1との間で、令和2年8月31日、要旨、原告及びC1は、D1に対し、連帯して解決金1700万円(以下「本件解決金」という。)の支払義務があることを認める旨の合意が成立した。
(3)価額弁償金の支払と更正の請求及びこれに対する更正処分等
ア 原告及びC1は、令和2年5月13日までに、A及びB1に対し、本件和解により定められた金員を支払い、同年8月31日までに、D1に対し、本件解決金を支払った(乙1)。
イ 原告は、令和2年9月7日、S税務署長に対し、本件和解により定められた金員については合計1800万円が、本件解決金についてはその全額である1700万円が遺留分侵害額に相当する価額であり、これらに原告の負担割合27%を乗じた486万円及び459万円の合計945万円を相続税の課税価格から減算すべきであるとして、相続税法32条3号に基づく更正の請求をした(以下「本件更正請求」という。乙1)。本件更正請求に係る原告の課税価格及び納付すべき税額は、別紙2課税処分等の経緯の順号2欄記載のとおり、それぞれ4402万4000円及び189万8200円であった。
ウ S税務署長は、令和3年6月29日、本件価額弁償金に関して、遺留分による減殺の請求に基づき弁償すべき額が確定したのは本件和解が成立した日であり、本件更正請求は原告がそれを知った日から4か月を経過した後にされていることから、本件価額弁償金に係る部分(486万円)については更正をすべき理由がなく、本件解決金に係る部分(459万円)については更正をすべき理由がある旨の更正処分をした(以下「本件更正処分」という。)。本件更正処分に係る原告の課税価格及び納付すべき税額は、別紙2課税処分等の経緯の順号3欄記載のとおり、それぞれ4888万4000円及び210万8000円であった。
エ 原告は、令和3年8月20日、S税務署長に対し、本件更正処分の一部取消しを求めて再調査の請求をしたが、同署長は、同年11月5日、再調査の請求を棄却する旨の決定をした。
オ 原告は、令和3年12月3日、国税不服審判所長に対し、本件更正処分の一部取消しを求めて審査請求をしたが、同所長は、令和4年7月8日、審査請求を棄却する旨の裁決をした。
カ 原告は、令和4年10月25日、本件更正処分のうち、本件価額弁償金に係る更正の請求を認めなかった部分の取消しを求めて、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
第3 本件更正処分の根拠についての被告の主張
本件更正処分の根拠に関する被告の主張は、後記第4の2のほか、別紙3のとおりである。原告は、争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額及び計算方法を争わない。
第4 争点及び争点に関する当事者の主張
1 争点
本件価額弁償金は、本件和解の成立により、弁償すべき額として「確定」したか
2 被告の主張
(1)民法1031条に基づく遺留分減殺請求を受けた受遺者と遺留分権利者との間において、受遺者が財産の全部又は一部について遺言のとおり取得する代わりに、その弁償として遺留分権利者に対し具体的な金額を支払う旨の和解が成立した場合、和解の効力により、受遺者は遺言のとおり当該財産を取得する一方、遺留分権利者は当該財産について有していた権利等を喪失する代償として金銭支払請求権を取得することとなる。そして、その和解が裁判上の和解である場合、当該裁判上の和解の成立をもって弁償すべき額が確定したことになる。
したがって、受遺者と遺留分権利者との間において具体的な金額の弁償金を支払う旨の裁判上の和解が成立した場合には、当該裁判上の和解の成立をもって、相続税法32条3号に規定する「弁償すべき額が確定した」に該当するとするのが文理に即する。
(2)以上によれば、本件価額弁償金は、本件和解の成立により、弁償すべき額として「確定」したものである。
3 原告の主張
(1)価額弁償は代物弁済の一種であるところ、所得税法上は、代物弁済により財産の移転があったときにその資産が譲渡されたことになる。したがって、遺留分減殺請求事件の訴訟上の和解によって価額弁償金の支払が認められた場合の相続税法上の法的効果は、所得税法上のそれと同じく、価額弁償金の支払が現実になされたときに生じ、弁償すべき額が確定することになる。
(2)相続税法32条3号は「遺留分による減殺の請求があったこと」とされていたが、平成15年法律第8号により「遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと」と改正された。遺留分減殺請求の意思表示後に判決等によって紛争が解決した場合、期限内に更正の請求を行うことがほとんど不可能であったから、現実の財産の移転に着目して改正がされたものである。
(3)受遺者が遺贈の目的物の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行し、又はその履行の提供をしなければならないから、相続税法32条3号の「弁償すべき額が確定」の意義も、同様に解すべきである。
(4)遺留分権利者は、受遺者による更正の請求に対応して、価額弁償金の取得によって増加した相続税を納税しなければならないところ、価額弁償金を現実に受領しなければ納税が困難である。担税力を考慮すれば、価額弁償金の現実の受領をもって、相続税法32条3号の「弁償すべき額が確定」したと解すべきである。
(5)以上によれば、本件価額弁償金は、現実にこれを支払うことにより、弁償すべき額として「確定」したものである。
第5 当裁判所の判断
1 相続税法32条3号は、相続税について申告書を提出した者は、遺留分減殺請求に基づき「弁償すべき額が確定した」ことにより当初申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、申告書の提出者がこれを知った日の翌日から4か月以内であれば、更正の請求をすることができる旨規定する。
2 本件においては、A及びB1が、原告及びC1に対して遺留分減殺請求権を行使し、相続財産である不動産につき所有権の一部移転登記手続などを求めて提起した訴訟において、A及びB1と原告及びC1との間で、原告及びC1が、①Aに対し、連帯して遺留分として2625万4102円の支払義務があることを認め、②B1に対し、連帯して遺留分として1117万3455円の支払義務があることを認めるという裁判上の和解(本件和解)が成立することで(前提事実(2)ア)、原告とA及びB1との間で、亡Mの相続について、原告が支払うべき価額弁償の額が定まったものである。
そうすると、本件和解の成立によって、遺留分権利者であるA及びB1からの遺留分減殺請求に基づき、原告が弁償すべき本件価額弁償金が確定したと解するのが、相続税法32条3号の文言に沿う。
3 また、平成30年法律第71号による改正前の民法における遺留分制度は、遺留分権利者による遺留分減殺請求権の行使により当然に物権的効果が生じ、受遺者が価額弁償を選択した場合に遺留分権利者の現物返還請求権が金銭支払請求権になるという構造であったものである(民法1036条、1041条1項参照)。そうすると、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使し、受遺者との間で遺贈の目的物の共有関係をめぐる紛争が生じ、遺留分権利者と受遺者との間で、受遺者が支払うべき遺留分の額を定める裁判上の和解が成立した場合には、当該裁判上の和解は、受遺者が遺贈の目的物の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の額を確定させるものと解するのが相当である。
本件和解は、A及びB1が、原告及びC1に対して遺留分減殺請求権を行使し、相続財産である不動産につき所有権の一部移転登記手続などを求めて提起した訴訟において、A及びB1と原告及びC1との間で、原告及びC1が支払うべき遺留分の額を定めた裁判上の和解である(前提事実(2)ア)。そうすると、遺留分制度の上記構造からみても、本件和解の成立により、原告及びC1が遺贈の目的物の返還義務を免れるためにすべき本件価額弁償金の額が確定されたものと解される。
4 以上によれば、原告が弁償すべき本件価額弁償金の額は、本件和解の成立によって「確定」したものというべきである。
5 (1)原告は、価格弁償金の支払が現実になされたときに、所得税法上の資産譲渡が生じるから、相続税法上もその時に弁償すべき額が確定すると主張する。
しかし、相続税法32条3号は、遺留分による減殺の請求に基づき「弁償すべき額が確定」したことを受けて、当初申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったか否かを判断しようとするものであり、価格弁償金という資産の譲渡の有無や時期とは無関係な規定である。
したがって、所得税法上の資産譲渡が生じる時期から相続税法32条3号を解釈しようとする原告の主張は、採用することができない。
(2)原告は、平成15年法律第8号による相続税法32条3号の改正の趣旨は、現実の財産の移転に着目したものであると主張する。
しかし、上記改正は、遺留分減殺請求の時点から具体的な金額が確定するまで長期間を要することが多く、更正の請求の起算日を「遺留分による減殺の請求があったこと」を知った日の翌日とする旧規定では、4か月の請求期限では対応できないことがあるから、「遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと」としたものであって(乙12)、現実の財産の移転に着目してされたものということはできない。
したがって、上記改正の趣旨に依拠する原告の主張は、採用することができない。
(3)原告は、受遺者が遺贈の目的物の返還義務を免れるためには、価額弁償を現実に履行し、又はその履行の提供をしなければならないとされており、相続税法32条3号の「弁償すべき額が確定」の意義も同様に解すべきであると主張する。
しかし、相続税法32条3号は、遺留分による減殺の請求に基づき「弁償すべき額が確定」したことを受けて、当初申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったか否かを判断しようとするものであり、受遺者が遺贈の目的物の返還義務を実際に免れるか否かとは無関係な規定である。
したがって、受遺者が遺贈の目的物の返還義務を免れる時期から相続税法32条3号を解釈しようとする原告の主張は、採用することができない。
(4)原告は、価額弁償金を取得する遺留分権利者の担税力を考慮すれば、価額弁償金の現実の受領をもって相続税法32条3号の「弁償すべき額が確定」したと解すべきであると主張する。
確かに、遺留分による減殺の請求に基づき「弁償すべき額が確定」し、受遺者について更正処分がされた場合には、価額弁償を受けた遺留分権利者に課税することが予定されている(相続税法35条3項)。しかし、「弁償すべき額が確定」する時期の解釈に当たり、遺留分権利者の資力を考慮すべきことを根拠付ける規定は見当たらない。
したがって、遺留分権利者の担税力を考慮すべきであるという原告の主張は、上記4の判断を左右するものにはならない。
6 以上のとおり、本件和解の成立により、原告が弁償すべき本件価額弁償金の額が「確定」したものである。そして、原告は、本件和解の当事者であるから、本件和解の成立日である平成28年4月13日に、「弁償すべき額が確定した」ことを知ったものと認められる。本件更正請求は令和2年9月7日にされたものであって、原告が「弁償すべき額が確定した」ことを知った日の翌日から4か月以内にされたものではないから、本件更正請求のうち本件価額弁償金に係る部分について更正をすべき理由がないとした本件更正処分に誤りはない。そうすると、原告の納付すべき金額は、別紙3本件更正処分の根拠に関する被告の主張2(5)記載のとおり210万8000円であり、本件更正処分における原告の納付すべき金額と同額であるから、本件更正処分は適法である。
よって、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 品田幸男
裁判官 片瀬 亮
裁判官 横井靖世
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -