解説記事2024年04月08日 特別解説 ESMAが公表したIFRS執行決定事例集第28巻(その1)(2024年4月8日号・№1022)
特別解説
ESMAが公表したIFRS執行決定事例集第28巻(その1)
はじめに
欧州証券市場監督機構(European Securities and Markets Authority。以下「ESMA」という。)は、欧州金融市場の機能を改善するために証券法規と規制の分野で活動し、欧州各国の金融規制当局間で投資家保護及び協力を強化することを目的とした欧州連合の専門機関である。その活動の一環としてESMAは、国際財務報告基準(IFRS)の適切な適用に関する情報を財務諸表の発行者及び利用者に提供する目的で、欧州各国の執行者(規制当局等)による財務諸表に関する執行決定の機密データベースを開発・運用しており、そこからの抜粋をホームページに公表している。後述の表に記したように、執行決定事例集はこれまでに第28巻まで公表されており、このうち、2015年11月に公表された第18巻までは、日本公認会計士協会が和訳を行っている。事例集の原文と和訳ファイルは、日本公認会計士協会のホームページから入手できる。
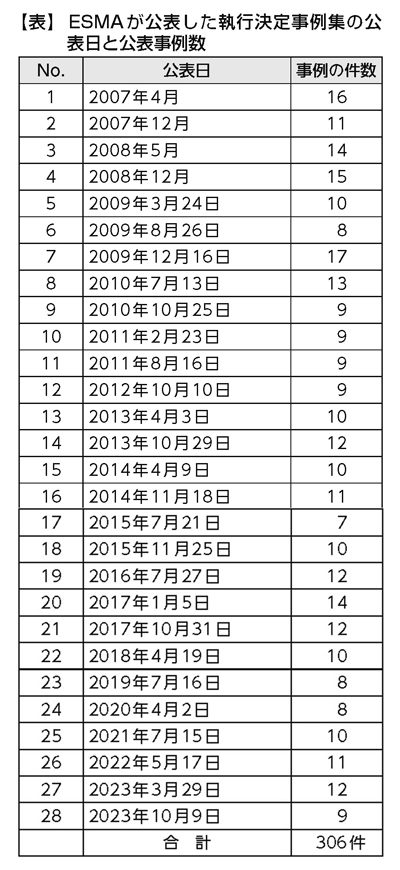
ESMAによる執行決定事例集の全体的な説明や第27巻までで公表された事例の紹介は、本誌No.817(2020年1月6日号)、No.849(2020年9月14日号)、No.901(2021年10月11日号)No.950(2022年10月17日号)、No.1005(2023年12月4日号)及びNo.1009(2024年1月1日号)を参照いただくとして、本稿では、2023年10月9日に公表された直近の事例集(第28巻)の概要と、掲載されている事例を2回に分けて紹介したい。
なお、本稿で紹介する事例はいずれもESMAのホームページに公表されている英文を筆者が仮訳したものである。
これまでにESMAが公表した執行決定事例集
これまでにESMAが公表した28巻の執行決定事例集について、公表日と含まれる事例の件数とを一覧にすると次の表のとおりである。
ここのところ、事例集は1年に1巻のペースで公表されてきていたが、2023年は半年の間隔で2回公表された。その結果、これまでの累積公表事例数は、300件を突破した。
事例集第28巻に収録されている事例
直近に公表された事例集第28巻に収録されている9件の事例の表題と、関連するIFRSの基準書を一覧にして示すと次のとおりである。
① 企業結合に関連するアーンアウトの支払(IFRS第3号「企業結合」
② 企業結合に関連するプットオプション負債の分類(IAS第32号「金融商品:表示」、IFRS第3号「企業結合」)
③ 配給権の認識と測定(IAS第38号「無形資産」)
④ 支配の喪失(IFRS第10号「連結財務諸表」)
⑤ 支配の評価(IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」)
⑥ 本人対代理人(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」)
⑦ 自己使用による免除(IFRS第9号「金融商品」、IFRS第16号「リース」)
⑧ ヘッジ会計の開示(IFRS第7号「金融商品:開示」)
⑨ リースに関連する開示(IFRS第16号「リース」)
具体的な執行決定事例
具体的な執行決定事例は、冒頭に表題と対象となる決算期末日、論点の領域及び関連する基準書が明示された後、本文は「発行者(財務諸表の作成者)の会計処理に関する説明」、「執行決定(the enforcement decision)」及び「執行決定の根拠」の3部構成となっている。本稿では、主に連結財務諸表と支配に関連する以下の2件の事例を紹介することとしたい。
・支配の喪失
・支配の評価
① 支配の喪失
対象となる決算期末日:2017年12月31日
論点の領域:支配
関連する基準書:IFRS第10号「連結財務諸表」
(発行者(財務諸表の作成者)の会計処理に関する説明)
グローバルな事業会社である発行者は、政府機関への建物の建設・賃貸を目的とした100%出資の連結子会社(A社)を設立した。2017年11月、発行者はA社の株式の約60%を外部当事者(取得者)に売却する契約を締結した(発効日は2018年4月)。A社のリスクと便益は、建物の建設完了後(建設フェーズ)に買収者に移転し、その時点でリースが開始された(リースフェーズ)。
A社と発行者の間には、建設段階に関連する複数の契約が締結され、特に、発行者が建物建設の最終的な責任を負うことが規定されていた。工事代金は固定されていたが、工事が予定通りに完了しなかった場合、発行者は金銭的な違約金を支払うことになっていた。さらに別の契約では、建設段階におけるA社の利益とすべての債務は発行者に帰属し、発行者が引き受けることが定められていた。建物の建設は、発行者が買収者と契約を締結してから約1年後の2018年末までに完了した。
報告日現在、発行者はA社の唯一の株主であったが、2017年12月31日付でA社を連結財務諸表から除外し、重要な利益を認識した。発行者は、2017年11月付の売買契約及び取得者の承認要件を考慮すると、A社の関連する活動に対する実質的な議決権及びパワーをもはや有していないため、2017年にA社に対する支配を喪失したと判断した。発行者の見解では、関連する活動とは、建物の建設とその後のリース、建設活動の資金調達であった。
売買契約によると、買収者には、将来の重要な事業取引や事業活動(例えば、総支配人の任命、株主総会の決議の設定)を承認する権利が認められていた。発行者は、買収者と協議の上、重要な投資、資金調達、人事を決定することができた。しかし、買収者は新たな戦略やビジネスモデルを確立することはできなかった。本件売買契約は、発行者とA社との間で締結された工事請負契約に大きな影響を与えるものではなかった。
買収者の同意なしに一定の意思決定を行うことができなくなったため、関連する活動を指揮する権限は制限されたと発行者は考えた。
(執行決定)
執行者は、発行者が売買契約を締結した時点でA社に対する支配を喪失していないという見解を示した。したがって、発行者はA社を連結除外すべきではなく、2017年に連結除外による利益を認識すべきではなかった。A社の連結除外により、発行者はIFRS第10号の第6項以降を遵守していなかった。
(執行決定の根拠)
発行者は、政府機関に建物を建設し、賃貸することを唯一の事業目的としてA社を設立し、法人化した。発行者は、売買契約の効力発生日まで、プロジェクト会社の唯一の株主であり、経営者であった。A社は、複数の契約上の合意(キャッシュ・プール契約など)に基づく取引関係を通じて、法的にも経済的にも発行者のグループに組み込まれていた。
契約締結から売買契約の効力発生日までの間、A社は発行者の主要な事業利益に貢献していた。建設段階におけるA社の関連活動は、建物の建設に関するものであった。発行者は建設段階における関連活動を指揮したため、IFRS第10号B13項に従い、建設が完了するまでA社を連結しなければならなかった。A社の事業目的の範囲が限定的であることから、発行者が一方的に他の企業結合を行ったり、大規模な投資を行ったりすることができないことは重要ではない。
買収者に付与された権利は、実質的にはIFRS第10号の第14項、B9項、B26〜B28項に概説されている防御的な権利であった。その権利は、契約締結から工事完了までの間に発行者が履行しなければならない工事契約が変更されないことを保証するものである。
当事者間で締結された複数の契約上の合意は、発行者がそのパワーを行使してA社の収益に影響を与える能力を有していたことを保証した。したがって執行者は、建設段階において、IFRS第10号の第6項に規定されているように、発行者がA社を支配していたと結論した。
発行者はA社との関与により変動収益にさらされ、その権利を有していた。特に建物が完成するまで、発行者はA社から生じた利益を引き受ける権利と、A社から生じた損失を引き受ける義務を有していた。さらに建物の販売価格は固定されていたが、引渡し日を超えて遅延した場合、発行者は毎月違約金を支払う必要があった。したがって、発行者は変動収益の対象となった。
② 支配の評価
対象となる決算期末日:2017年12月31日
論点の領域:支配
関連する基準書:(IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」)
(発行者(財務諸表の作成者)の会計処理に関する説明)
グローバルな事業会社である発行者は、有限責任会社(LLC)の法的形態で、中東のある国に所在する建設会社(A社)の45%の持分を保有していた。2016年以前、A社の経営委員会はA社の株主(発行者、株主B、株主C)を代表する3名の委員で構成されていた。
2016年、株主Cは撤退し、A社の持分をA社が所在する国の国民である株主Bに売却した。同日、発行者は株主CのA社に対する貸付金を引き継ぎ、A社の債権者(銀行)および顧客(保証人)に対する保証および同様の債務を引き受けた。したがって、発行者はA社に関するすべての実質的なリスクを引き継いだ。
これらの取引の後、
a)株主BはA社の株式の55%を保有した(現地の法律では、会社が所在する国の国民が本土のLLCの株式の少なくとも51%を保有しなければならない)、
b)発行者が株主Bの全株式に対する購入オプションを受領した、
c)発行者が保有する経営委員会の委員数が1名から2名に増加した(取締役は合計で3名)。
また、A社の定款によれば、(i)経営会議の決議は現取締役の過半数の賛成を必要とし、(ii)「取締役会留保事項」(特に、年間事業計画の採択、事業計画外の取引の承認、日常的な経営を担当するマネージング・ディレクターの選任・解任など)の決議は、両株主の指名する取締役の賛成を必要とし、(iii)取締役会が選任するマネージング・ディレクターは発行者が提案することになっていた。また、「取締役会留保事項」の決議が手詰まり状態に陥った場合は、独立仲裁委員会に付託されることになっていた。
購入オプションの価格は、EBITDAの倍率を用いた契約で定められた計算に基づいていた。購入オプションはいつでも行使できた。行使された場合、株式は45日以内に発行者に譲渡されなければならない。
上記の変更を踏まえ、発行者はA社を支配していないと判断した:
a)IFRS第10号B12項に列挙されている関連性のある活動を対象とする「取締役会留保事項」については、株主Bの取締役の承認が必要であった、
b)購入オプションが行使された場合、売却株主は45日以内に株式を譲渡しなければならないため、購入オプションは実質的な権利をもたらすものではなかった、
c)現地の法律による既存の株式譲渡制限を考慮すると、発行者は議決権の49%以上を保有することはできない。
その代わりに、発行者は株主BとともにA社を共同支配していると考え、A社に対する持分をIFRS第11号「共同支配の取決め」に基づき、持分法を用いてジョイント・ベンチャーとして会計処理した。
(執行決定)
執行者は、発行者の会計処理がIFRS第10号の第6項、第8項、B13項、B19項、B24項、B47項及びB65項に準拠していないと判断した。発行者は2016年以降、A社を支配していたため、財務諸表においてA社を完全に連結しなければならなかった。
(執行決定の根拠)
執行者は、年次事業計画の承認が、IFRS第10号のB12項に規定されているように、A社の最も関連性の高い活動、ひいてはその変動リターンを指示する決定であったことについて発行者と合意した。
しかし執行者は、年次事業計画の承認に関する決定には両株主(すなわち、それぞれの経営委員会メンバー)の同意が必要であることに同意する一方で、A社に対する支配を評価する際には、その他の権利やリスクも考慮すべきであるとの見解を示した。執行者は特に、株主B社の株式に対する有利な買取オプションと、株主ローンや保証から生じる非対称なリスクポジションを考慮した。特に、買取オプションを行使することにより、発行者は「取締役会留保事項」に関する手詰まり状態を解決する能力を有していた。したがって、共同支配は存在しなかった。
さらにIFRS第10号の適用に関して、株式の譲渡に45日間を要したにもかかわらず、株主Bは株式が発行者に譲渡される前に、A社の既存の関連する方針を変更することはできなかった。執行者は、IFRS第10号B24項の設例3Bと3Dに言及した。
執行者は、購入オプションは実質的なものであるという見解を示した。IFRS第10号のB47項によれば、潜在的な議決権はその権利が実質的である場合にのみ考慮される。買取オプションの条件に基づけば、(i)買取オプションは必要に応じて行使でき、(ii)行使制限が存在せず、(iii)オプションの行使は手詰まり状態を解消するために発行者にとって有益であることから、当該オプションは実質的なものであった。
さらに、執行者は、現地法における譲渡制限は、発行者が株主Bに代わる能力を継続的に有しているため、買取オプションが経済的実体を欠くことを意味するものではないと指摘した。発行者と新たな株主(国民又は会社が所在する国の他の会社)との間で、防御的な権利(例えば、会社の清算)を除き、すべての重要な経営上の意思決定は発行者が行うと合意することは可能であろう。この点では、IFRS第10号B65項も関連しており、これは、解任権が一方の当事者のみによって保有される場合、その当事者が本人として支配権を有することを示しているためである。
最後に執行者は、その見解を補強するために、発行者が投資先に対して受動的な持分以上のものを有していることを示す以下の指標にも注目した:
a)発行者は、A社のマネージング・ディレクターを含む3人の取締役のうち2人を指名する権利を持っており、事業計画の実行と日々の運営に責任を持つマネージング・ディレクターは、常に発行者によって選ばれ、提案されていた、
b)A社の事業は発行者の資金調達に大きく依存しており、発行者はA社の債務の大部分を保証していた(IFRS第10号B19項(b)(i)(ii))。
c)発行者が保証や融資を通じて実質的にすべてのリスクを負担しているため、発行者のリスク・エクスポージャーが議決権よりも不相応に大きかった(IFRS第10号B19項(d))。
IFRS第10号のB19項とB20項によれば、リスク・エクスポージャーが一人の投資家に対して大きければ大きいほど、その投資家にパワーがあることを示している。
本稿で取り上げた2件の支配に関する事例は、いずれも2017年12月期に生じたものであり、外部公表までに6年近くを要している。どのような事情で公表が遅れたのかは知る由もないが、最終的な執行決定が下されるまでに、関係者の間で相当な議論が交わされたためなのかもしれない。
支配/被支配という目に見えない関係を評価するためには、IFRS第10号をはじめとする会計基準上も多くの指標や判断基準、設例等が明示されてはいるものの、これらはあくまでも分かりやすい例示の一つに過ぎない。我が国の企業においてもある企業を連結すべきか否かはよく問題となり、会社側と会計監査人、さらには規制当局等の間で見解の相違が生じやすい論点であると言えよう。
本稿で紹介したような事例に対する執行決定やその根拠は、我が国の企業や会計監査人、規制当局等にとっても参考になるものと思われる。
次回(第2回)では、合計4件の事例を新たに取り上げることとしたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























