解説記事2020年02月24日 解説 OECDデジタル課税に関する大枠に関する声明(Statement)のポイント(2020年2月24日号・№824)
解説
OECDデジタル課税に関する大枠に関する声明(Statement)のポイント
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 南 繁樹
第1 本稿の目的(脚注1)
2020年1月31日、OECDはデジタル課税に関し、「BEPS包摂的枠組みに関する声明(Statement by the Inclusive Framework on BEPS)」を公表した(以下「IF声明」という。)(脚注2)。本稿は、IF声明の概要を説明し、今後の見通しについての観測を述べるものである。
IF声明は、2019年10月・11月に公表されたOECD事務局案を包摂的枠組み(Inclusive Framework。以下「IF」という。)の参加国(137国・地域)が承認した点において、デジタル課税を一歩前進させたといえる。他方で、IF声明は「合意することへの確約」にすぎず、現段階では何ら合意は成立していない。特に、2019年12月3日に米国ムニューシン財務長官のOECD事務総長宛て書簡(以下「米国財務長官書簡」という。)によるPillar 1を「セーフハーバー」とする旨の提案(以下「セーフハーバー提案」という。)に関する意見の対立は解消されておらず、この点が、最終的に合意が成立するか否かの視界を不透明にしている。
本稿では、上記の点について留意しつつも、IF声明の附属文書(Annex)に記載された内容について、2019年5月デジタル課税行動計画(Programme of Work)、同年10月Pillar 1公開協議文書(Public Consultation Document)、同年11月Pillar 2 公開協議文書(これらを「旧提案」という。)からの変更点に重点を置きつつ、その内容を紹介する。注目すべきポイントとして、デジタル企業のみを対象とする規定が新設されていること、セグメンテーションの細分化(事業部門の下のレベル、地域)が志向されていること、他方で適用除外の範囲を拡張していること、業種別での取扱いを異にすることが示唆されていることなどがある。なお、2019年10月のPillar 1に関するOECD事務局案に関しては、本誌810号4頁以下「デジタル課税『Pillar 1:多国籍企業の利益の配分』のポイントと理論・実務上の問題点」を、同年11月のPillar 2に関する事務局案に関しては、本誌813号19頁以下「デジタル課税『Pillar2:税源浸食対抗税制-グローバル・ミニマム・タックスと税源浸食支払否認規定』のポイントと理論・実務上の問題点」を参照されたい。
第2 交渉の現状と今後の見通し
1 IF声明の意味
IF声明は、IFの参加国(137国・地域)において、OECD事務局が2019年10月に公表したデジタル課税に関する統合提案(Pillar 1)と同年11月に公表した税源浸食対抗税制に関する提案(Pillar 2)を前提とし、修正を加えたうえ、2020年末までに合意に基づく解決案に合意するとの確約を確認したもの(“affirm their commitment to reach an agreement on a consensus-based solution”)である(IF声明パラ1)。つまり、「合意することへの確約」にすぎない。
今後、本年7月初旬のIFの次回会合で政治的合意の基礎となる主要なポイントについて合意し、2020年末までの合意を目指す。次の焦点は、7月までに、Pillar 1の重要論点について合意が形成されるか(セーフハーバーについては無理であろう)、Pillar 2についての論点(特に、能動的事業による適用除外)が整理されるかである。
2 米国財務長官の「セーフハーバー」アプローチ
2019年12月3日にOECD事務総長宛てに送付された米国財務長官書簡は、「私たちは、……米国納税者が依拠している独立企業原則に基づく移転価格税制とネクサスを基準とする課税を放棄することが義務付けられる可能性について、深刻な懸念を有しています。しかし、Pillar 1をセーフハーバーの制度とすることで、このような納税者の懸念に手当てがされるとともに、Pillar 1の目的は実質的に達成されることになると信じます。」(脚注3)と述べた。米国が賛成しなければデジタル課税のプロジェクト自体の意味が失われるといっても過言ではないが、その米国ではいずれにせよ議会の賛成がなければ制度改正はできないのであるから、米国財務長官書簡は、デジタル課税によって最も大きな影響を受ける米国企業の意向を代弁したにすぎないのかもしれない。
しかしながら、そもそもPillar 1は、物理的存在(physical presence)をネクサス(課税対象とのつながり)の中心とする国際課税の伝統的なルールを変更し、独立企業原則によらずに公式的に利益を配分することを目的としていたものであるから、米国財務長官書簡は、Pillar 1の根本を覆すものである。また、「セーフハーバー」の意味は必ずしも明らかではないが、それが納税者(企業)が自らに有利な場合だけ当該制度を選択することができる(optional)ことを意味するとすれば、結果として市場国へ配分される税収は少なくなる。
したがって、IF声明は、セーフハーバー提案に対し、「多くのIFメンバーは、『セーフハーバー』の制度としてPillar 1を実施することは、大きな困難を引き起こし、不確実性を増大させ、全体的なプロセスの政策目標のすべてを満たさない可能性があるとの懸念を表明している。」(脚注4)と否定的に述べている。この問題は、他の要素について合意に達した後に最終決定されるものとされたが、IF声明は「この問題を解決することがコンセンサスを形成するために決定的に重要(“crucial”)である」と述べている(パラ3)。
3 単独立法措置の阻止
そうすると振り出しに戻って、デジタル課税の国際的合意は成立しないのではないかとの懸念が生じる。既に、単独立法措置を検討する国は増加している(脚注5)。これに対し、米国は、フランスのデジタル課税(Digital Services Tax, DST)への報復措置を示唆していた。米仏両政府は2020年1月20日、2020年末まで報復関税の応酬を避けることで合意したが(脚注6)、あくまでも「休戦」に過ぎない。
附属文書1は、単独措置に関し、「コンセンサスに基づくあらゆる合意には、この合意を実施すると同時に関連する単独措置を撤回した上、将来そのような単独措置を採用しない旨のIFのメンバーによる確約(“commitment”)が含まれなければならないことが期待される。」(パラ89)(脚注7)と述べている。
以上のような緊張をはらむ状況に対し、OECDは、「合意に至らない場合には、各国が単独で行動し(“act unilaterally”)、すでに脆弱な世界経済に更なる悪影響を及ぼすリスクが大幅に高まる」と警告している(IF声明に関する2020年1月31日付プレス・リリース)。
もはや、デジタル課税は通商問題の一部である(脚注8)。このように、政治的・戦略的な側面を否定することはできないが、以下ではIF声明の附属文書に記載された制度概要を客観的に説明する。
第3 Pillar 1に関する論点
1 Pillar 1の全体像
Pillar 1の基本的構造は、旧提案と変わらない。すなわち、Pillar 1は、多国籍企業グループに対し、そのグローバルでの利益のうち、下記のAmount A、Amount B及びAmount Cの3種類の金額を、市場国に配分することを提案する。中核はAmount Aであり、企業がその国に物理的拠点を有するか否かを問わず、「みなし残余利益」の一定部分に対し、市場国に新たな課税権を付与し、その市場国へ一定の公式によって利益を配分する。このAmount Aが今回のプロジェクトの最も革新的な部分である。これに対しAmount Bは、企業がその国に物理的拠点のある場合において、その国に一定の固定比率によって利益を与えるもので、既存の移転価格税制の簡素化にすぎない。Amount Cは、課税ルールそのものというより、Amount A及びAmount Bと既存の制度との関係を調整し、実効性を高めるものである。それぞれの概要は、次頁の表1のとおりである。以下では、従然の提案から変更があった点を中心に、ポイントを述べる。
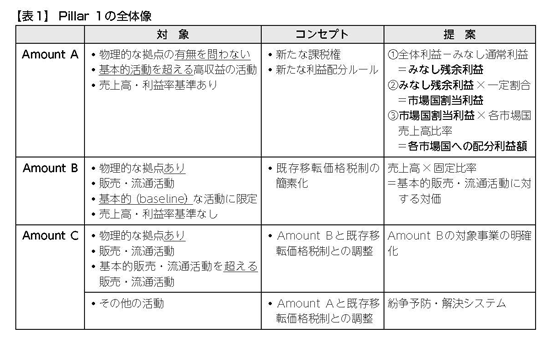
2 Amount A
(1)対象事業(課税物件・課税標準):Scope of Amount A
(a)理論的根拠
Amount Aは、多国籍企業が、国境を越えてある国で経済活動を行っているにもかかわらず、その国に物理的存在(子会社又は恒久的施設)を有していないためにその国の課税権が及ばないという問題を克服するために提唱されたものであり(公開協議文書パラ51)、従来のネクサスが物理的存在(physical presence)を中核としていたことからすると大きな飛躍を示したものである。
(b)「自動化されたデジタルサービス」事業
旧提案は、Amount Aにつき、消費者向け事業(“consumer-facing businesses”)のみを対象としていたが(公開協議文書パラ19)、新提案では「自動化されたデジタルサービス」(“automated digital services”)が加えられた(附属文書1パラ18)。旧提案では、典型的なデジタル企業を出発点としつつ、課税対象を「マーケティング無形資産」案を基礎に組み立てたため、対象となる企業の範囲が曖昧になってしまっていた。これに対し、新提案は、市場国に拠点を有することなく遠隔地からデジタルサービスを提供する企業に関し、「強力な顧客や利用者のネットワーク効果を活用することで利益を得て、利用者や顧客との相互交流(“interaction”)から実質的な価値を生」み、「利用者が提供するデータやコンテンツそのものや、利用者の活動を強度にモニターして対応するデータを活用することでも利益を得ている」(附属文書1パラ18)と述べ、「ユーザー参加」による価値創造にデジタル課税の根拠を求めた英国案に近接する記載がなされており、“ring fencing”(狙い撃ち)ではないのかとの疑問が生じないではない。そして、「自動化されたデジタルサービス」とは、「複数の国(管轄区域)にわたる多数の顧客又は利用者に標準化された形態で自動化されたデジタルサービスを提供する事業」(“businesses that generate revenue from the provision of automated digital services that are provided on a standardised basis to a large population of customers or users across multiple jurisdictions”)と定義され、以下の事業が課税対象として例示されている(附属文書1パラ22)。
・オンライン検索エンジン
・ソーシャルメディアプラットフォーム
・オンライン市場運営等のオンライン仲介プラットフォーム(使用者が事業者であるか、消費者であるかを問わない)
・デジタル・コンテンツ配信
・オンラインゲーム
・クラウドコンピューティングサービス
・オンライン広告
特に、事業者向けクラウドコンピューティングの提供は、旧提案の「消費者向け事業」には含まれないと思われたところだが、新提案では含まれることになる。
但し、オンラインで役務を影響するとしても、高度な人的介入・判断を要する役務は「自動化されたデジタルサービス」には含まれない。これに該当するのは、法律、会計、建築、技術及びコンサルティング業務である(附属文書1パラ23)。
(c)「消費者向け」事業
「消費者向け事業」は、旧提案を踏襲するものであり、「通常、消費者に販売される種類の商品・役務の販売から収益を生み出す事業」と定義されている(附属文書1パラ24)。このため、直接に消費者に販売を行う事業者だけではなく、第三者である再販売事業者や仲介業者を通じて販売を行っている者も、商品の性格として消費者向けである限り、「消費者向け」事業としてAmount Aの課税対象になる(附属文書1パラ25)。
これに対し、消費者向け商品に組み込まれる中間製品(“intermediate products”)や部品(“components”)は課税対象にならないことが明確化された。但し、それがブランドを付され、消費者の個人的用途のために購入される場合は課税対象となりうる(附属文書1パラ26)。
さらに、商標が付された消費者製品に対するライセンス事業や、フランチャイズのように消費者ブランド及び商業的ノウハウのライセンスを提供する事業に関しては、ライセンシーが事業者であったとしても、ライセンサーは「消費者向け」事業に該当し、課税対象とする(附属文書1パラ27)。これは「マーケティング無形資産」案に基づいたものであろう。
以上に基づき、「消費者向け」事業に該当するものとして、以下の事業が例示されている(附属文書1パラ28)。
・パーソナルコンピュータ製品(ソフトウエア、家電製品、携帯電話)
・衣服、衛生用品、化粧品、奢侈品
・ブランドが付された食品・飲料
・フランチャイズ事業(レストランやホテルを含む)
・自動車
(d)Amount Aの課税対象に含まれない事業
採掘事業、原材料(“raw materials”)・一次産品(“commodities”)の生産・販売事業は、それらが下流で消費者製品に組み込まれるとしても、Amount Aの課税対象に含まれない(附属文書1パラ30)。金融・保険事業は原則として課税対象に含まれないが、デジタルによるソーシャルレンディングは別途検討される(附属文書1パラ31)。船舶・航空機は、課税対象にならない(附属文書1パラ32)。
(e)対象企業の金額基準
Amount Aは、大規模な多国籍企業のみを対象とするが、企業グループ全体としては大規模であっても、上記の課税対象となる事業は小規模であるかもしれない。そのような企業を対象から除外するため、以下のような複数の金額基準が検討される(附属文書1パラ35、附属文書B)。
① グループの総売上高が7億5000万ユーロを超えること
② 課税対象事業の売上高の総合計が基準値を超えること
③ 課税対象事業の利益(みなし残余利益のうち市場国に配分される額)の絶対額が基準値を超えること
④ 事業部門単位での利益率が基準率を超えること
(2)ネクサス(課税国):New nexus rules and related treaty considerations
(a)概要
上記(1)のscopeは納税者側(事業)の要件であるが、本(2)のネクサスは国家側の要件である。従前は、国家の課税管轄権(執行管轄権)が認められる要件として恒久的施設(permanent establishment)が求められていた(OECDモデル租税条約7条1項参照)。それに代わる国家と企業との関わり合いとして、企業が市場国に対し「重要かつ持続的な関与」(“a significant and sustained engagement”)を有していることが求められる。すなわち、ある企業の、当該国における対象事業の複数年度にわたる売上高が基準値を超えることが、当該国が当該企業に対してAmount Aの課税権を有する要件となる。当該売上高は、市場規模に応じて異なり、最低基準額が設けられる(附属文書1パラ37)。
(b)「自動化されたデジタルサービス」事業
「自動化されたデジタルサービス」事業については、そもそも遠隔地からのアクセスが問題とされているので、当該国における売上高のみが課税権を有するか否かの基準になる。
(c)「消費者向け」事業における商品販売
これに対し、「消費者向け」事業で商品販売を行う場合、市場(国)との持続的な相互交流(“a sustained interaction with the market”)がなく、単に商品を販売しているにすぎない場合には、その市場国が新たなネクサスに基づく課税権を有することはない(附属文書1パラ39)。この部分は分かりにくいが、たとえば、多国籍企業Xの消費者向けブランド商品が、独立の再販売業者Yによって市場国Aで販売される場合であろう。この場合、たとえA国における売上高が基準値を超えたとしても、それだけでは当該企業のA国との「重要かつ持続的な関与」はないとされる。しかし、「プラス」ファクターとして、企業XがA国に物理的拠点を有する場合や、A国をターゲットとした広告を行っている場合には、上記関与が認められうる。
(3)Amount Aの課税標準(課税対象金額):Tax base determinations
(a)基本となる数値
課税標準(課税ベース)は、連結グループの財務会計上の利益を出発点とすることは、旧提案と変わらないが、新提案においては、基準となる利益が「税引前利益」(profit before tax,“PBT”)であることが明示された(附属文書1パラ44)。移転価格税制が営業利益を基準とすることが多いのと異なる。異なる会計基準が採用可能であることは前提とされているが(脚注9)、それらを整合的に取り扱うための調整について、会計基準間の相違の大半はタイミングに関するものにすぎないから、相違が金額及び持続年数において重要なものに限り調整を行うとして、割り切った整理をしている(同パラ43)。また、損失の繰越を認めるべきことが明記されている(同パラ44)。
(b)事業単位・地域単位でのセグメンテーション
旧提案において示唆されていた事業部門(“business line”)でのセグメンテーション(区分)は、より明確に記載された(附属文書1パラ45)。さらに、地域や事業部門によって利益率が大きく異なる場合には、地域や対象事業をさらに細分化する区分も示唆されている。区分により結果が異なる可能性があるが、事業区分は業種やビジネスモデルにより千差万別であり、客観的で合理的な基準の設定ができるかが実務上、重要な課題となる。
(c)「みなし通常利益率」と「市場配分比率」
Amount Aは、マーケティング無形資産による貢献を把握するものであるから、通常の利益とみなされる部分(みなし通常利益)を超え、残余利益とみなされる部分(みなし残余利益)を対象とする。このため、この二者を区分する利益率が問題となる。また、みなし残余利益のうち、どれだけが市場国に配分されるべきかも問題になる。いずれについても具体的な数値は記載されていない。たとえば、売上高の10%までをみなし通常利益とし、それを超えたみなし残余利益のうちの10%が市場国に配分される案(“10-over-10”)(図1参照)が採用された場合、グローバルでの売上高営業利益率が30%の企業は、売上高の20%(=30%-10%)がみなし残余利益とされ、その10%である売上高の2%が市場国に配分されることになる(上記(1)の基準を充足することが前提である。)。いずれの比率についても旧提案と同様に、新提案においても具体的な数値は記載されていない。
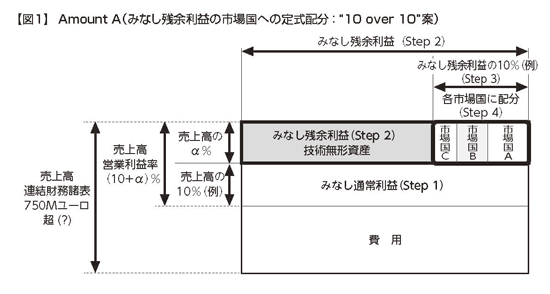
新提案において、対象事業の中でも、デジタル化の程度(「デジタル化水準」(“digital differentiation”))によってAmount Aの金額に差を設ける可能性が示唆されている(附属文書1パラ46)。典型的なデジタル企業である「自動化されたデジタルサービス」事業については、Amount Aに配分される割合を大きくするということであろうか。これも、「自動化されたデジタルサービス」事業の定義の追加(上述2(1)(b))と並び、デジタル企業に照準を合わせた提案である。
事業ごとに比率が異なる可能性も示唆されている(同)。
(d)Amount Aの課税標準に関するまとめ
以上をまとめると、企業(納税者)の側では、対象事業(自動化されたデジタルサービス事業又は消費者向け事業)で、グローバル売上高・対象事業売上高・対象事業利益市場国配分額の基準を充足した企業に対し、みなし通常利益率を超えた部分がみなし残余利益となり、そのうちの一定比率が市場国に配分される。但し、全グループ単位ではなく、事業部門・地域によってより小さいセグメントに区分された場
合には、その単位ごとにAmount Aを適用することになる。
(4)市場国間でのAmount Aの配分:Revenue sourcing under Amount A
市場国がAmount Aに関する課税権を有するためには、まず、当該企業との間で上記(2)のネクサスを有することが要件とされており、それを充足した複数国の間では売上高に応じて配分される(附属文書1パラ47)。
所得源泉のルールが必要になることが指摘されている。たとえば、A国所在の多国籍企業Xが消費者向け商品を、B国の独立販売業者Yに販売し、YがC国で販売した場合に、XについてC国での対象事業の売上高が計上されるかというような問題である。物理的拠点がない場合に、どのように源泉を特定するのかが問題となる。
(5)課税所得減少法人の特定(外国税額控除・課税免除)
Amount Aは多国籍企業のグローバルの課税所得の一部を、既存ルールでは課税所得が計上されない市場国に配分するものである。そうすると、二重課税を防止するためには、既存ルールで所得を計上していたいずれかの法人の所在地国で二重課税防止の措置(外国税額控除又は課税免除)を取らなければならない。既存移転価格税制における対応的調整と同様である。しかし、Amount Aに関しては、①配分される所得は全世界グループ全体の所得であることに加え、②グループ内の法人が各市場国に物理的拠点を有していない場合には、各市場国とグループ内の特定の法人との結び付きも必ずしも明らかではない。このため、市場国に配分された所得について、それに対応するものとしていずれの国が二重課税防止措置を取る(税収を失う)のかを明らかにするルールを定める必要がある(附属文書1パラ51)。利益率を参照して(対象となる)納税者を特定すべきとされている(“identify the taxpayer entities by reference to measures of profitability”)のは、利益率が高い法人はみなし残余利益を稼得しており、それが市場国に配分されたと考えて、そのような法人の所在地国に二重課税防止措置を義務付けるとの趣旨であろうか。ただ、税収を失う複数国間で税率は異なるから、企業側においては、どの国の法人で二重課税防止措置を受けるかで、グローバル実効税率に変化が生じうる。
3 Amount B
(1)対象となる事業・活動
Amount Bは、旧提案から大きな変更はなく、市場国において行われる基本的な販売および流通活動(“baseline marketing and distribution activities”)に対し、一定比率での固定報酬(“a fixed remuneration”)を与えるものである(図2参照)。旧提案と比較し、あくまでも移転価格税制に基づくものであること(それが簡素化されたに過ぎない)が強調されていることに加え、Amount Aのセーフハーバー提案を反映し、Amount Bは選択制でもセーフハーバーでもない旨をわざわざ明記している(附属文書1パラ58)。
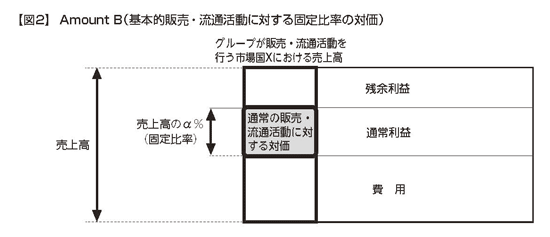
また、固定比率での報酬とする以上、「基本的」以上の機能を有する場合と区別されなければならない。なぜならば、後者の場合には、既存の移転価格税制に基づいて、機能が高い分だけ、固定比率で配分されるAmount B以上の利益が配分されなければならないからである。そこで、Amount BであるかAmount Cであるかの紛争を避けるためには、対象となる「基本的な販売及び流通活動」を明確に定義することが必要となる(附属文書1パラ60)。その要素としては、以下の点が上げられている(同パラ61)。
・ルーティン(日常)水準の機能しか有しないこと
・無形資産を有しないこと
・リスクがないか限定されていること
なお、Amount Bは、既存の国際課税ルールに変更を加えるものではない。したがって、Amount Aと異なり、総売上高などによる適用基準や、「自動化されたデジタルサービス」事業又は「消費者向け」事業などによる対象の限定はない。原則として、業種を問わず、販売・流通活動を行う限り、Amount Bの対象となる。
(2)Amount B=みなし課税所得金額
基本的な販売及び流通活動を行う企業の課税所得とされる金額は、一定の利益水準として固定比率で定められる(附属文書1パラ58)。適切な利益水準指標を規定することは検討課題とされている(同64)。売上高営業利益率が候補として考えられるが、それ以外にもベリー比もありうるのかもしれない。具体的な利益水準指標とその水準は、最終段階で合意されるのであろう。
なお、多機能な法人(“multifunctional entities”)や非常に低いシステム利益の法人(“entities with very low system profits”)の取扱いが検討課題とされている(附属文書A,VIII)。後者は、必ずしも明確ではないが、利益率が恒常的に非常に低い法人のことであろうか。たとえば、グループ全体の売上高営業利益率が恒常的に低い場合(例えば、3%)に、それを上回る固定比率(例えば、5%)で基本的な販売・流通活動から利益を先取りすると、本国で損失が生じることが生じうる。このため、Amount Bの固定比率をグループ全体の利益率の一定割合を上限とすることなども考えられよう。たとえば、Johnson & Johnson は、地域販売・流通業者(Local Market Distributor)に対する利益は、グループ全体の売上高営業利益率の40%を上限とすべきとしていた(脚注10)。
(3)事業・地域による区別
新提案は、ベンチマーク検証(同業種の公開企業のデータから基準となる利益水準を算定すること)を検討すると同時に、業種や地域ごとに取扱いを異にする必要があるかを検討するとしている(附属文書1パラ64)。既存移転価格税制の取引単位営業利益法(TNMM)に近いイメージであろうか。
4 二重課税の排除
新提案では、公聴会における意見を反映してか、二重課税が生じるおそれとそれに対する対応について、踏み込んだ検討を行っている。
(1)Amount Aに関する二重課税排除
上述(2(5))のとおり、Amount Aに関しては、市場国に配分する利益について、市場国でない国のうち、いずれの国において二重課税防止の措置(外国税額控除又は課税免除)を義務付けられるかという問題がある。
(2)Amount AとAmount Bの関係
Amount Aはみなし残余利益であり、これは重要な無形資産から生じているとの前提がある。これに対し、Amount Bは、基本的な販売・流通活動から生じるものであるから、両者はコンセプト上利益の源泉となる活動が異なり、重なり合いは生じないはずである(附属文書1パラ55)。
(3)Amount AとAmount Cの関係
多国籍企業グループが市場国に課税上の存在(子会社・支店)を有している場合、既に既存国際課税制度に基づきAmount Cが計上されているにもかかわらず、さらに市場国への配分としてAmount Aが計上され、二重計上が生じる可能性がある。たとえば、A国に本社を有する多国籍企業Xが市場国Bの子会社Yによって著名ブランドの商品を販売した場合、Yが既存の移転価格税制に基づき計上した利益(Amount C)と、グループ全体の利益から算定されるAmount Aの間には重複が生じうる。いずれも無形資産によって生じた残余利益であるからである。新提案は、そのような場合として、①市場国においてマーケティング無形固定資産を使用する場合、②独立企業原則に基づいて比較可能性調整を行う場合、③独立企業原則に関して(いずれかの国が)異例な解釈を採用する場合を挙げている(附属文書1パラ56)。
(4)Amount BとAmount Cとの関係
Amount BとAmount Cの間には重複が生じうるが、上述のとおり、Amount Bの対象となる「基本的な販売及び流通活動」を明確に定義することで、Amount Bとそれ以外の活動であるAmount Cを分けることが可能になるとされている(附属文書1パラ60)。
5 執 行
(1)申告・納付
上述のとおり、Amount Aに関しては、多国籍企業グループの利益を、複数市場国に配分し、それ以外の複数国がそれに対応して二重課税回避の措置(外国税額控除又は課税免除)を義務付けられることになる。新提案は、「ワン・ストップ・ショップ」(“one stop shop”)として、申告は最終親会社が行う旨を検討するものとしている(附属文書1パラ36)。
(2)紛争予防・解決
以上のように、Amount Aにおいては、特定の企業に関して多くの国が潜在的な利害関係を有するため、既存制度では複数の相互協議手続が必要となり、整合性を欠き、非効率で長期間を要する結果となる可能性がある(附属文書1パラ68)。このため、新提案は、「革新的なアプローチ」(“an innovative approach”)が必要であるとして、IFのメンバーを適切に代表し、効果的、透明かつ包括的なプロセスによる「代表者によるパネル」(“representative panels”)の設置を提唱している(同パラ71)。その詳細は明らかではないが、紛争発生後の仲裁のようなものではなく、事前に、より一般的な形で各国当局の専門家による審査プロセスを用意することを意図しているように感じられる。もっとも、紛争予防・解決システムは、最終的には強制的で拘束力を有する必要があるが(同パラ75)、各国の主権の問題もあり、この点に合意が成立するか否かの見通しは難しい。
第4 Pillar 2に関する論点
ミニマム・タックスに関するPillar 2については、IF声明・附属文書Bが現在の作業状況を報告し、今後の検討課題を提示するにとどまる。Pillar 2については基本的に2019年5月作業計画の内容が踏襲されている(表2参照)。
【表2】全世界で統一的に設定された最低税率での課税(ミニマム・タックス)
但し、具体的な最低税率は未定(12.5%を予想する見解あり)
| 課税主体 | 提 案 | 内 容 |
| 親会社・本社で の課税 |
所得合算ルール (Income inclusion rule) |
軽課税国子会社所得の親会社での合算 (Top up to a minimum rate) 最低税率での課税を受けていない子会社の所得を親会社に合算し、最低税率までで課税を行うルール |
| 外国支店所得の本社での合算 (Switch-over rule) 外国PE 帰属所得が最低税率での課税を受けていない場合に、本社での課税(外国税額控除を前提とする全世界所得課税)に転換する制度 |
||
| 支払国での課税 | 税源浸食支払に対する否認 (Tax on base eroding payments) |
税源浸食支払の損金算入否認・源泉課税 (Undertaxed payments rule) 税源を浸食する支払に対して、支払国において損金算入を否認し又は源泉税を課すことにより、支払国において課税を行う制度 |
| 税源浸食支払への租税条約恩典の否認 (Subject to tax rule) 特定の所得が最低税率の課税を受けている場合にのみ一定の条約恩典を付与する旨の租税条約の規定(その結果、源泉税が課されうる) |
Pillar 2に対しては低税率国や中税率国の反発が予想されるところである。附属文書2も、残るBEPSの課題に集中すべきであり、「全ての国際的事業が最低限度の税金を支払うことを確保するシステマティックな解決案は、Pillar 2の政策目的を超える」との反対意見(パラ4)を記載しており、抵抗が強いことを窺わせる。
Pillar 2の個別論点として重要なのはブレンディング(“blending”)の問題である(公開協議文書パラ53~72)。ミニマム・タックスを課す前提として、既存税制において課される税金の課税所得に対する割合(実効税率)を計算する必要がある(税金/課税所得)。その計算の際に、同一の事業体内または同一グループ内の異なる事業体間において、高税率で課税される所得(重課税所得)と低税率で課税される所得(軽課税所得)を通算するのがブレンディングである。どの範囲でブレンディングを認めるかについて、公開協議文書においては、以下の3つを挙げていたが(パラ55)、附属文書2は、議論の状況を具体的には明らかにしていない(パラ11)。
① 全世界グループの合算(“A worldwide blending approach”) (脚注11)
② 国・地域単位での合算(“A jurisdictional blending approach”)
③ 法人単位での合算(“An entity blending approach”)
また、Pillar 2について、タックスヘイブン税制において採用されているように、能動的事業活動を行っていることによる除外を認め、ミニマム・タックスの対象としないのか否かが重大な問題となる。この点について、作業計画は否定的なコメントをしていたが(2.1.3a)、今回は、一部の国が、実体的基準に基づく適用除外を重要性を強調した旨が記載されており、この点も予断を許さない(附属文書2パラ12)。
第5 今後の留意点
Pillar 1の動向は米国のセーフハーバー提案により不透明であり、その米国はPillar 2には積極的であるものの、Pillar 1とPillar 2はパッケージであるので、Pillar 1が成立しなければ全体が成立しないとみるべきであろう。そのような状況であるが、このように経済のデジタル化に対して既存の国際課税制度に限界がある旨を世界各国で確認してしまったのであるから、もはや元には戻れない。
米国(企業)の抵抗からすると、Pillar 1のAmount Aについては、制度として、あるいは基準の設定において、インパクトを小さくするように進められると思われ、日本企業への影響は(事務負担を除き)比較的小さいかもしれない。これに対し、Amount Bは新興国の執行強化に直結するおそれがある。Pillar 2は、低中税率国にとって死活問題であり、抵抗が予想されるが、米国がミニマム・タックスを導入した以上、その影響は避けられないのではないか。
企業としては、長期的には、新興国のインセンティブ税制は廃止ないし弱体化する趨勢にあることを念頭に置きつつ、OECDの動向を注視する必要があろう。
さらに国際課税制度全体を俯瞰すれば、各国の租税制度が連結され、全体として標準化・均一化が進んでいくと思われるが、他方で、相互作用によるチェーンリアクションが生じうる。その結果、「ゲーム化」が一層進展すると同時に、予期しない結果も生じうる。税務担当者の力量が一層問われることになるであろう。
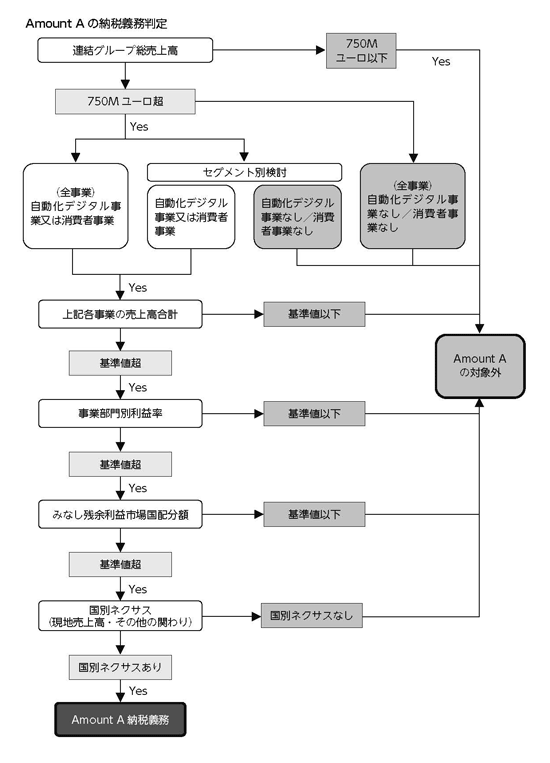
脚注
1 本稿の執筆に際し、キヤノン株式会社理事・経理本部税務担当上席菖蒲静夫氏および東レ株式会社税務室長栗原正明氏から貴重な示唆をいただいた。記して感謝する。もちろん、本稿にありうべき誤りはすべて筆者のみの責任に属する。
2 http://www.oecd.org/internet/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
3 “we have serious concerns regarding potential mandatory departures from arm's-length transfer pricing and taxable nexus standards- longstanding pillars of the international tax system upon which U.S. taxpayers rely. Nevertheless, we believe that taxpayer concerns could be addressed and the goals of Pillar 1 could be substantially achieved by making Pillar 1 a safe-harbor regime.”
4 “Many IF Members express concerns that implementing Pillar One on a ‘safe harbour' basis could raise major difficulties, increase uncertainty and fail to meet all of the policy objectives of the overall process.”
5 既に導入している国として仏、伊、オーストリア、トルコ等、検討中の国として英、カナダ、ベルギー、スペイン、イスラエル等(2019年12月5日Financial Times)。
6 2020年1月22日日本経済新聞
7 “It is also expected that any consensus-based agreement must include a commitment by members of the Inclusive Framework to implement this agreement and at the same time to withdraw relevant unilateral actions, and not adopt such unilateral actions in the future.”
8 ウィルバー=ロス米国商務長官は、ヨーロッパの炭素税(carbon tax)に対して、「デジタル課税と同様に」報復措置を行う旨を述べた (2020年1月26日Financial Times)。
9 Pillar 2公開協議文書は、国際会計基準(IFRS)、米国GAAP及び日本GAAPを使用可能な会計基準として例示していた(パラ22)。
10 Josh White, “Johnson & Johnson hatches plan for marketing intangibles” , International Tax Review, March 25, 2019.
11 全世界グループでの合算の場合も、最終親会社分は含まないとみられる点に注意が必要である(公開協議文書パラ55)。
南 繁樹 (みなみ しげき)
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士、東京弁護士会:1997年登録(49期)
E-mail:shigeki_minami@noandt.com
1994年東京大学法学部卒業。1997年東京弁護士会登録。2003年New York University School of Law卒業(会社法・租税法LL.M)。東京大学法学部非常勤講師(法と経済学)、神戸大学法科大学院客員教授、上智大学法科大学院非常勤講師、LEC会計大学院客員教授(いずれも租税法)。2017年~2018年IFA(国際租税協会)Asia-Pacific Chair。経済産業研究所「これからの法人に対する課税の方向性」プロジェクトメンバー。専門はM&A及び税務。税務の経験分野は、移転価格税制、国際的組織再編、租税条約、源泉所得税、法人税全般、金融商品、相続税等の全般に及ぶ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















