解説記事2024年05月27日 税務マエストロ 令和6年度消費税改正(上)(2024年5月27日号・№1028)
税務マエストロ
令和6年度消費税改正(上)
#300
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
令和6年3月28日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立したことを受け、関係政省令が3月30日(土)に官報にて公布された。政省令の官報による公布は、例年であれば年度末の3月31日であるが、令和6年は3月31日が日曜日ということもあり、一日前倒しでの公布となったようだ。
また、例年通り4月1日に改正基本通達が公表されたことにより、令和6年度の消費税改正の全容が確認できることとなったので、今回は、この令和6年度消費税改正の実務ポイントについて解説する。
Ⅰ 令和6年度改正消費税法の概要と適用期日
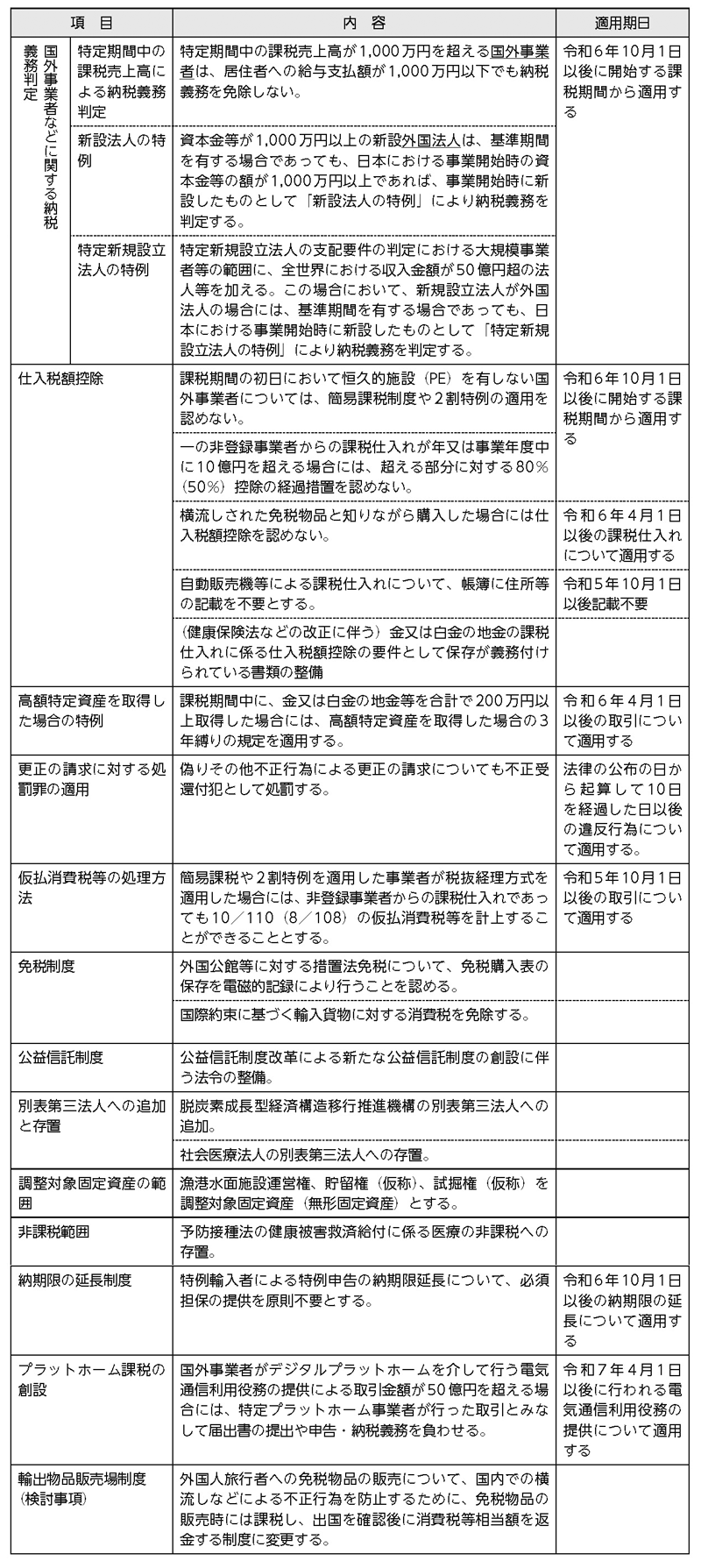
Ⅱ 国外事業者などに関する納税義務判定の改正
1 国外事業者に対する給与支払額による納税義務判定(特定期間中の課税売上高による判定)の見直し
(1)改正内容
特定期間中の課税売上高による納税義務判定は、特定期間中の課税売上高と給与等の支払額を天秤にかけ、いずれかが1,000万円以下の場合には免税事業者となることを認めている。納税義務判定に用いる給与等の金額は、消費税法第9条の2第3項において、「……所得税法第231条第1項に規定する給与等の金額……」と規定されており、所得税法第231条第1項は、「居住者に対し……」という書き出しで始まっている。
よって、非居住者に支払う給与は納税義務判定に関係させないこととなる。
国外事業者は、国外の事務所を拠点にして活動することが多いため、日本国内で居住者に支払う給与が少なくなる傾向にある。結果、国内での売上規模に比較して、国外事業者は居住者分の給与が少額となるため、特定期間中の課税売上高がどんなに多額でも納税義務が免除されることになってしまう。
そこで、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超える国外事業者は、居住者への給与支払額が1,000万円以下でも納税義務を免除しないこととしたものである(消法9の2③)。
(2)特定期間中の課税売上高と給与支払額との関係
特定期間中の課税売上高は、売掛金を認識したところの、いわゆる発生主義により計算することになる。そこで、特定期間中の課税売上高の計算が困難な小規模事業者に配慮して、給与支払額による納税義務の判定を認めたものと思われる。
ただし、特定期間中の給与支払額による納税義務判定は、特定期間中の課税売上高の計算が困難な事業者に限り認めるものではない。結果、特定期間中の課税売上高と給与支払額を比較して、次頁表のパターン②又は③に該当する場合には、免税事業者になることができる一方で、課税事業者となって還付申告をすることもできることになる。
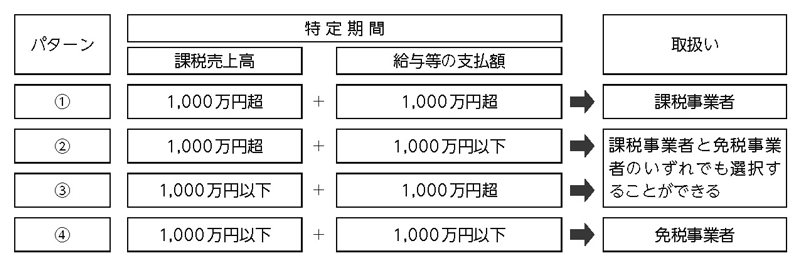
パターン①で課税事業者となる場合とパターン②~③のケースで課税事業者を選択する場合には、第3−(2)号様式(消費税課税事業者届出書 )を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(消法57①一)。
)を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(消法57①一)。
ただし、「課税事業者選択届出書」のように提出期限が定められたものではない。
2 外国法人が国内で事業を開始した場合の納税義務判定(新設法人の特例)の見直し
(1)改正内容
期首の資本金が1,000万円以上の新設法人は、基準期間のない事業年度については無条件に課税事業者となる(消法12の2①)。
「新設法人の特例」は、基準期間がない事業年度について適用されるのであるから、基準期間ができた以後の課税期間については、原則として基準期間における課税売上高により納税義務を判定する(消基通1−5−18)。
国外事業者は、日本で法人を設立しても、実際に事業が軌道に乗るまでには一定期間を要するのが一般的である。結果、法人を設立して数年間は売上高がゼロあるいは少額となるため、基準期間が発生して「新設法人の特例」が適用されない課税期間になった際、基準期間や特定期間中の課税売上高が1,000万円以下であることから免税事業者になれてしまうということがある。
国外事業者は、日本において事業を開始した時が事実上の会社設立日であることから、たとえ基準期間がある課税期間(事業年度)であっても、事業開始時に法人を設立したものとして「新設法人の特例」により納税義務を判定することとしたものである(消法12の2③)。
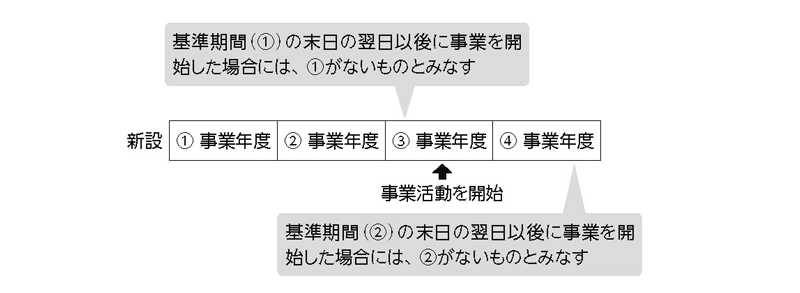
(2)日本における事業を開始した時とは?
外国法人が日本における事業を開始した時とは、開業準備行為を行った日を意味するのだろうか……。
新規開業の場合には、「課税事業者選択届出書」の提出日の属する課税期間から課税事業者になることができるわけであるが、この「新規開業」については、消費税法施行令20条一号で「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」と規定している。
注意したいのは、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」というのは、「課税資産の譲渡等を開始した日」つまり課税売上げが発生した日を意味するものではないということである。DHCコンメンタール(第一法規出版)によれば、「事業に必要な事務所、店舗等の賃貸借契約の締結や資材、商品の仕入などの開業準備行為を行った日もこれに該当する」とされているので、その翌課税期間から課税事業者になろうとする場合には、これらの開業準備行為を行った日の属する課税期間中に届出書を提出しなければならない。
外国法人が日本における事業を開始した時とは、この消費税法施行令20条一号に規定する「新規開業」の定義と同意義と解釈すべきなのであろうか……。
一方で、「法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲」については、消費税法基本通達1−4−7において、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうこととしつつ、なお書で、「設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う」と定めている。
「実質的に事業活動を開始した場合」とは「開業準備行為を行った日」と解釈していいのだろうか……?
3 「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者(金額基準)の見直し
(1)特定新規設立法人の特例とは?
大規模事業者等(国内の課税売上高が5億円を超える規模の事業者が属するグループ)が、一定要件の下、50%超の持分や議決権などを有する法人を設立した場合には、その新規設立法人の資本金が1,000万円未満であっても、基準期間がない事業年度については納税義務は免除しないこととされている。また、これらの事業年度開始日前1年以内に大規模事業者等に属する特殊関係法人が解散した場合であっても、新規設立法人は免税事業者となることはできない(消法12の3、消令25の2~25の4)。
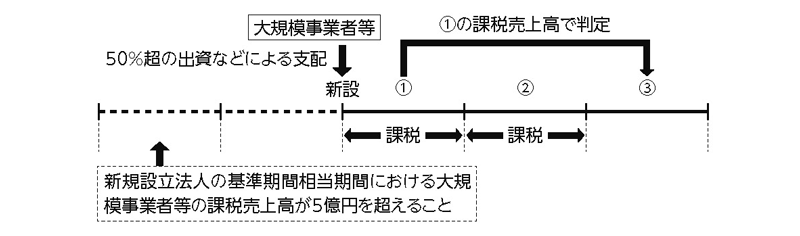
(2)改正内容
事務処理能力を有する事実上の大企業が法人を設立した場合であっても、その大企業の日本国内における課税売上高が5億円以下であれば、「特定新規設立法人」の特例を適用することができない。そこで、特定新規設立法人の支配要件の判定における大規模事業者等の範囲に、全世界における総収入金額が50億円超の法人等を加えることとしたものである(消法12の3①、消令25の4②)。
この場合において、新規設立法人が外国法人の場合には、基準期間を有する場合であっても、日本における事業開始時に新設したものとして、「特定新規設立法人の特例」により納税義務を判定することとされている(消法12の3⑤)。
(注)詳細については上記2を参照されたい。
(3)総収入金額の範囲
日本国内における課税売上高が5億円を超える大規模事業者等に支配されている新規設立法人は、特定新規設立法人として基準期間のない事業年度の納税義務は免除されないことになる。この場合の5億円判定には、非課税売上高や配当金収入などの課税対象外収入は含まれない。
これに対し、全世界における総収入金額による50億円判定をする場合には、国内外を問わず、課税売上高は無論のこと、非課税売上高や配当金収入などの課税対象外収入も含まれることになる(消令25の4②、消基通1−5−21の3)。
消費税法基本通達1−5−21の3(総収入金額の範囲)では、有価証券売却益や為替差益、貸倒引当金戻入益、固定資産売却益なども判定金額に含めることとしているが、消費税における対価の額は売却損益ではなく、売却収入である。
よって、有価証券や固定資産を売却した場合には、売却益ではなく売却収入が課税(非課税)売上高となる。また、貸倒引当金は企業会計において計上が要請されるものであり、貸倒引当金戻入益はそもそもが収入ではない。
全世界における総収入金額は、消費税の売上げ、仕入れの概念とは切り離して計算するということなのであろうか?
また、内国法人であっても、全世界における収入金額が50億円を超える場合には、その内国法人は大規模事業者に取り込まれることになる。
そうすると、専ら非課税事業を行う規模の大きな社会福祉法人や国内での配当金収入が50億円を超える持株会社などの場合には、国内での課税売上高が5億円以下であるにもかかわらず、傘下にある新規設立法人が課税事業者となるケースもありそうだ。
Ⅲ 仕入税額控除
1 国外事業者に対する簡易課税・2割特例の適用制限
(1)改正内容
インターネットを利用してオンラインゲームの配信(デジタルサービス)などを提供している国外事業者は、日本国内で課税仕入れが発生することはほぼないものと予想される。そこで、その課税期間の初日において日本国内に恒久的施設を有しない国外事業者は、簡易課税及び2割特例による仕入税額控除を認めないこととした(消法37①、平成28年改正法附則51の2①)。
(2)恒久的施設を有しないこととなった場合
恒久的施設の有無については、その課税期間の初日の現況で判断することとなるため、「簡易課税制度選択届出書」を提出している国外事業者が、その恒久的施設を有しないこととなった場合には、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができないことになる(消基通13−1−3の5)。
ここで注意したいのが法人税におけるみなし事業年度の取扱いである。
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途で恒久的施設を有しないこととなった場合には、「事業年度の開始日~恒久的施設を有しないこととなった日」と「恒久的施設を有しないこととなった日の翌日~事業年度終了日」を一事業年度とみなすこととされている(法法14①八)。結果、恒久的施設を有しないこととなった日の翌日(翌課税期間の初日)から簡易課税制度の適用を受けることができないことになる。
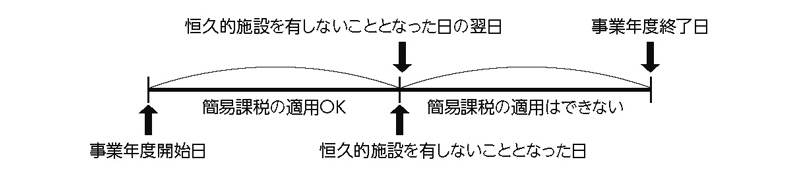
(3)恒久的施設を有することとなった場合
国内に恒久的施設を有しない国外事業者が「簡易課税制度選択届出書」を提出することはできるのであるが、たとえ基準期間における課税売上高が5,000万円以下であったとしても、当然に簡易課税制度の適用を受けることはできない(消基通13−1−4)。
この国外事業者が、国内に恒久的施設を有することとなった場合には、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
ここで注意したいのが法人税におけるみなし事業年度の取扱いである。
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途で恒久的施設を有することとなった場合には、「事業年度の開始日~恒久的施設を有することとなった日の前日」と「恒久的施設を有することとなった日~事業年度終了日」を一事業年度とみなすこととされている(法法14①七)。結果、恒久的施設を有することとなった日(翌課税期間の初日)から簡易課税制度の適用を受けることができることになる。
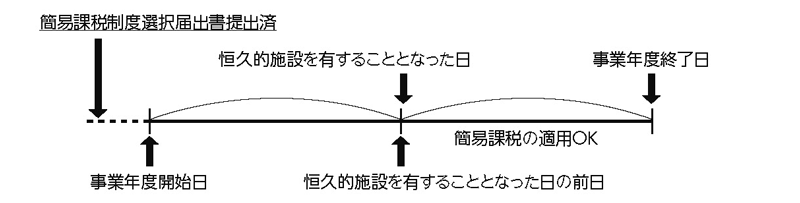
2 経過措置による80%(50%)控除の適用制限
(1)改正内容
一の非登録事業者からの課税仕入高(税込)が年又は事業年度中に10億円を超える場合には、その超える部分に対する80%(50%)控除の経過措置を認めないこととされた(平成28年改正法附則52①、53①)。
(2)改正の理由
平成22年11月16日付で税制調査会より公表された下記の資料(資料2補足資料−要望にない項目等・27頁~編集部でイラストをアレンジ)では、「免税点制度を悪用した消費税の脱税事例」として、ペーパーカンパニーを利用した脱税の手口を紹介している。
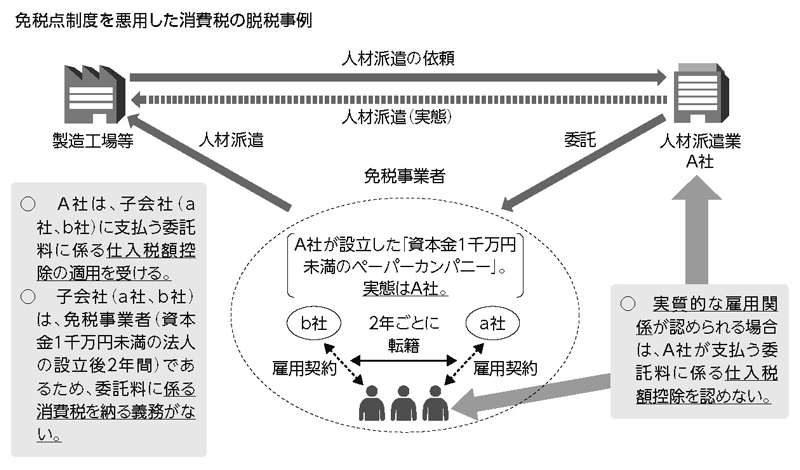
こういった資料から、23年度改正により創設された「特定期間中の課税売上高による納税義務判定」、社会保障・税一体改革法により創設された「特定新規設立法人の特例」は、いずれも新設された法人の基準期間がない事業年度を利用した節税スキームを封じ込めることを目的としたものであると推測することができる。
資本金1,000万円未満で法人を設立した場合、新設された法人は基準期間がない設立事業年度とその翌事業年度の納税義務が免除されることになる。この免税事業者である新設の法人に支払った外注費や人材派遣料を仕入税額控除の対象とすることを防ぐため、「特定期間中の課税売上高による納税義務判定」や「特定新規設立法人の特例」を創設したということである。
インボイス制度の導入により、上記のような制度上の欠陥は解消されることとなったものの、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、非登録事業者からの課税仕入れであっても税額の80%(50%)は経過措置により控除することが認められている。そこで、節税目的で法人を設立し、意図的に多額の課税仕入れを発生させて80%(50%)の経過措置を適用することを防止するために、10億円を超える部分についての仕入税額控除を認めないこととしたものと思われる。
私見としては、10億円ではなく、もっと低い金額でもよかったのではないかと感じている。また、経過措置を利用した節税スキームは十分に予想できたはずであるから、令和6年度改正ではなく、令和5年度改正に織り込んで、インボイス制度の導入とともに実施することができなかったのであろうか?
(3)年換算は必要ないか?
改正された平成28年改正法附則52条1項では、「……個人事業者にあってはその年、法人にあっては……事業年度において一の事業者から行う当該課税仕入れに係る支払対価の額……」と規定しており、事業年度が1年未満の場合における年換算については何も書かれていない。そうすると、仮に1か月決算法人を設立した場合には、1事業年度(1か月)で10億円まで仕入税額控除ができることとなり、年間で120億円まで節税? が可能となってしまうのだろうか……?
3 帳簿の記載事項の見直し
改訂前のインボイスQ&A問110では、自動販売機で課税仕入れを行った場合の「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載例として「〇〇市 自販機」と書くことを指導していた。この取扱いは、旧消費税法基本通達11−6−4(課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲)に規定されていたものが、令和5年10月1日の消費税法基本通達の改正により削除となり、令和5年8月10日に国税庁告示第26号に格下げされ、同年10月1日から適用されていたものである。
令和6年度の改正により、国税庁告示第26号が改正されたことに伴い、国税庁のインボイスQ&Aも令和6年4月に改訂となった。問110に例示されていた「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」といった記載は自販機やATMの所在場所を省略して単に「自販機」、「ATM」と記載すればよいこととなり、この取扱いは令和5年10月1日以後の帳簿の記載についても遡って適用してよいことになっている。日々帳簿を付けずにまとめ記帳をしている事業者は、法律の成立前の期間分であっても記帳は必要ないという課税側の忖度なのだと思われる。
実務の現場を考えれば、「〇〇市 自販機」という帳簿の記載に何の意味もないことは一目瞭然である。横浜市に自販機はいったい何台あるのだろう……。インボイスが導入されたことによる実務の煩雑さを考えると、あまりにも遅すぎた改正であると言わざるを得ない。
なお、令和6年3月30日付で国税庁告示第10号(消費税法施行令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件)が告示され、新たに入場券特例が適用される3万円未満の課税仕入れについても住所又は所在地の記載が不要となった。
結果、帳簿に住所又は所在地の記載が必要となるのは入場券特例が適用される3万円以上の課税仕入れだけという、何とも奇妙な結末となった次第である。
【帳簿の記載イメージ】
会議の際に提供する飲み物として、自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入した場合

従業員の福利厚生目的で〇〇施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用した場合
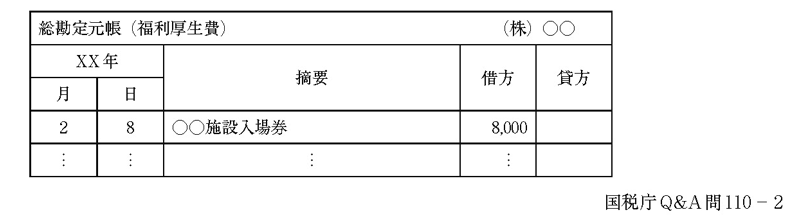
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















