解説記事2024年06月03日 新会計基準解説 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要(2024年6月3日号・№1029)
新会計基準解説
企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の概要
企業会計基準委員会専門研究員 山田正顕
1 はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日に、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。また、以下合わせて「本会計基準等」という。)を公表(脚注1)した。本稿では、本会計基準等の概要を紹介する。
なお、本会計基準等は日本公認会計士協会から公表されている会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(以下「資本連結実務指針」という。)にも影響するため、ASBJで検討の上、同協会に改正を依頼している。これを受けて、2024年5月27日に同協会より資本連結実務指針の改正(脚注2)が公表されているため、併せてご確認いただきたい。
また、文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、ASBJの見解を示すものではないことをあらかじめ申し添える。
2 本会計基準等の公表の経緯
2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「ディスクロージャーWG報告」という。)(脚注3)において、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」すること及び開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することが示された。当該ディスクロージャーWG報告に沿って2023年3月に金融商品取引法等の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)が国会に提出され、2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)(以下「法律」という。)として成立し、これにより金融商品取引法(昭和23年法律第25号)が改正された(以下「改正後の金融商品取引法」という。)。ASBJは、法律案において施行日が2024年4月1日とされていたことから、法律案の成立を前提に四半期報告書制度の見直しへの対応について検討を行った。
本会計基準等は、2023年12月に公表した企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至ったものである。
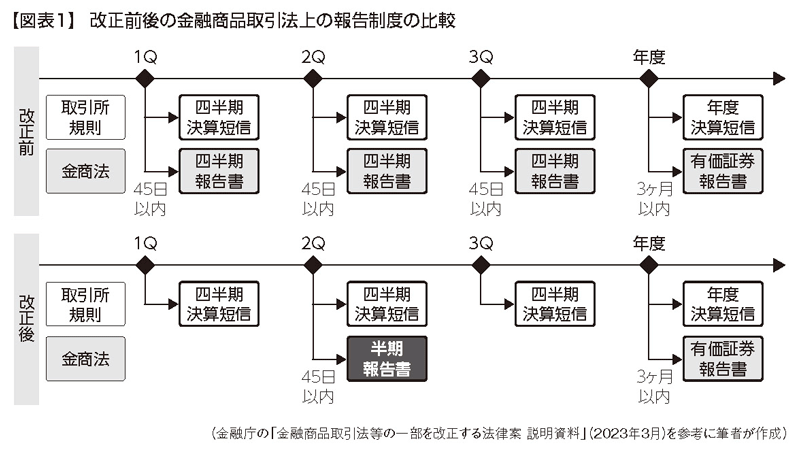
3 本会計基準等の概要
(1)本会計基準等の適用範囲
本会計基準等は、改正後の金融商品取引法に従い、新たに中間財務諸表を作成する企業に適用するため、次の会社が半期報告書制度に基づき作成する中間財務諸表に適用することとした(本会計基準第4項及びBC9項並びに本適用指針第2項)。
① 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号に掲げる上場会社等
② 金融商品取引法第24条の5第1項ただし書きにより、同項の表の第1号に掲げる上場会社等と同様の半期報告書を提出する第3号に掲げる非上場会社
なお、特定事業会社(銀行法、保険業法及び信用金庫法の特定の条項で定める業務に係る事業を行う会社)(脚注4)及び改正後の金融商品取引法第24条の5第1項ただし書きを適用しない非上場会社が作成する中間財務諸表については、中間連結財務諸表作成基準、中間連結財務諸表作成基準注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表作成基準注解(以下合わせて「中間作成基準等」という。)が適用される(本会計基準BC10項)。
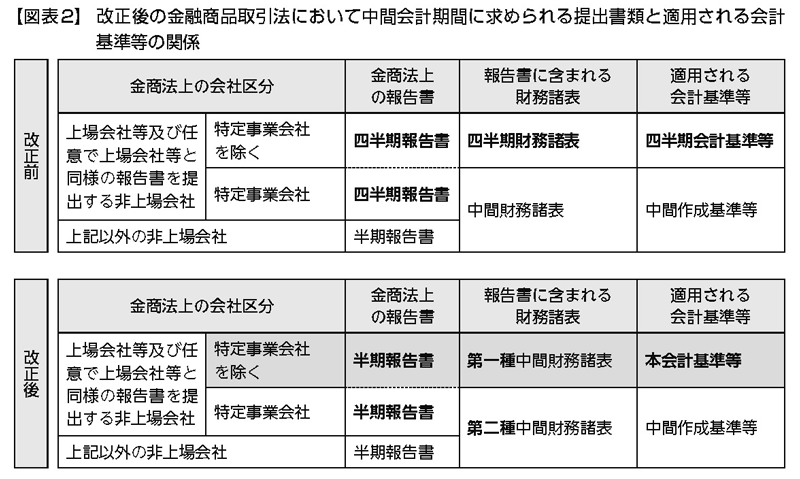
(2)開発にあたっての基本的な方針
本会計基準が適用される中間財務諸表を含む半期報告書制度の概要は、次のとおりである(本会計基準BC3項)。
① 半期報告書では中間会計期間(6か月間)を1つの会計期間とした中間財務諸表を作成する。
② 従前の四半期報告書と同様に、中間会計期間終了後、45日以内の政令で定める期間内での提出が求められる。
③ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の改正案(以下「財務諸表等規則等の改正案」という。)は、ディスクロージャーWG報告(「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」)に基づき作成されている(脚注5)。
本会計基準は上記①の半期報告書制度の概要を前提として、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定めることとしている(本会計基準BC4項)。この場合の開発にあたっての基本的な方針として、上記③の半期報告書制度の概要を前提として、中間財務諸表の記載内容が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容となるように、基本的に企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「四半期適用指針」という。また、以下合わせて「四半期会計基準等」という。)の会計処理及び開示を引き継ぐこととした(本会計基準BC5項)。
この方針により多くの取扱いは四半期会計基準等の定めをそのまま引き継ぐことができるが、四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合と、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とした場合とで差異が生じる可能性がある項目については、改正後の金融商品取引法の成立日から施行日までの期間が短期間であることから、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めることとした(本会計基準BC8項)。
(3)中間財務諸表の範囲等
本会計基準の適用対象となる中間財務諸表の範囲及び開示対象期間については、当該中間財務諸表が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容を基本とするとされたことを踏まえ、四半期会計基準の考え方を踏襲することとした(本会計基準BC11項)。
なお、四半期財務諸表では四半期ごとに開示が行われることから、四半期会計基準においては、期首からの累計期間(累計期間)の開示を基本としつつ、四半期会計期間(3か月間)を任意で開示する場合の取扱いも定められていた。一方、中間財務諸表では中間会計期間(6か月間)が1つの会計期間となるため、本会計基準においては、中間会計期間の取扱いのみを定めている。
(4)中間財務諸表の取扱い
① 本会計基準等で個別に検討したもの
本会計基準等は、(2)開発にあたっての基本的な方針に記載のとおり、中間財務諸表の作成にあたり必要となる会計処理について基本的に四半期会計基準等の会計処理に関する定めを引き継いでいるが、中間財務諸表において期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とすることに伴い差異が生じる可能性がある次の項目について個別に取扱いを検討した。
(ア)原価差異の繰延処理
(イ)子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日
(ウ)有価証券の減損処理に係る中間切放し法
(エ)棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法
(オ)一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理
(カ)未実現損益の消去における簡便的な会計処理
② 原価差異の繰延処理
中間財務諸表作成基準では、相対的にみて恣意的な判断の介入の余地が大きい等の理由により原価差異の繰延処理は認められていない。一方、四半期会計基準では、年度決算や中間決算よりも短い会計期間の中で企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する情報を適切に提供しなければならないという点を踏まえ、一定の条件を満たした場合に継続適用を条件に四半期特有の会計処理として認められていた。
本会計基準の適用対象となる中間財務諸表は、中間財務諸表作成基準と同様に会計期間が期首から6か月間であることから、年度決算や中間決算よりも短い会計期間(3か月間)である四半期決算について定めた四半期会計基準とは前提が異なると考えられる。
しかしながら、中間財務諸表作成基準と同様に原価差異の繰延処理を廃止することとした場合には、現在適用している企業に一定の影響があり、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めるという本会計基準の開発にあたっての基本的な方針と整合しないこととなるため、四半期会計基準の取扱いを踏襲することとした(本会計基準第17項及びBC14項)。
③ 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日
企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)(注5)において、支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができるとしている。四半期会計基準では、この決算日には四半期決算日を含むこととしていた(四半期会計基準第52項)が、改正後の金融商品取引法では四半期報告書制度が廃止されることから四半期決算日も廃止されることとなる(本会計基準BC16項)。
改正後の金融商品取引法に従い四半期決算日をみなし取得日として認めないこととした場合には、四半期会計基準に基づいた会計処理と異なる結果となることがあり、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めるという本会計基準の開発にあたっての基本的な方針と整合しないこととなる。
ここで、子会社の資産及び負債は、支配獲得日に時価評価して連結することとしており(連結会計基準第20項及び資本連結実務指針第2項)、みなし取得日の取扱いは容認規定とされている(連結会計基準(注5)及び資本連結実務指針第7項)ことから、改正後の金融商品取引法において四半期決算が廃止されても、年度又は中間会計期間より支配獲得日に近い特定の期日に決算が行われる場合には、当該決算日をみなし取得日とすることが否定されるものではないと考えられる。
これらを踏まえ、みなし取得日の決算日等には、期首、中間会計期間の末日のほか、その他の適切に決算が行われた日を含むこととした(本会計基準第20項及びBC17項)。
なお、本会計基準では四半期会計基準における四半期決算日をその他の適切に決算が行われた日に変更しているが、当該用語の変更は、四半期会計基準において認められていた四半期決算日を引き続きみなし取得日として適用可能とすることを意図したものであり、従来の四半期の実務を見直すことを意図したものではない。また、その他の適切に決算が行われたとは、子会社において本会計基準に準じた決算が行われたことを想定している(本会計基準BC18項)。
④ 有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法
四半期適用指針においては、関連諸制度との整合性を考慮し、有価証券の減損処理に係る方法として、継続適用を条件に四半期切放し法と四半期洗替え法の選択適用を認めていた(四半期適用指針第4項)。同様の理由により、四半期適用指針においては、棚卸資産の簿価切下げに係る方法として年度決算において切放し法を採用している場合について、継続適用を条件に切放し法(以下、有価証券の減損処理に係る四半期切放し法と合わせて「四半期切放し法」という。)と洗替え法(以下、有価証券の減損処理に係る四半期洗替え法と合わせて「四半期洗替え法」という。)の選択適用を認めていた(四半期適用指針第7項)。
本会計基準等は、(2)開発にあたっての基本的な方針に記載のとおり、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定めることを原則としたため、四半期切放し法及び四半期洗替え法に代えて、中間切放し法及び中間洗替え法の適用を認めることとした(本適用指針第4項、第7項及びBC2項)。
ここで、現行の四半期適用指針に基づき有価証券の減損処理又は棚卸資産の簿価切下げに係る方法として四半期切放し法を適用している会社においては、第1四半期決算で減損又は評価損を計上する場合に、現行の四半期切放し法による第2四半期決算の会計処理と中間切放し法とで、会計処理の結果が異なると考えられるため、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる経過措置を設けることとした(本適用指針第62項、第63項及びBC2項)。
なお、現行の四半期切放し法による第2四半期決算の会計処理と中間切放し法とで、会計処理の結果が異なる場合の例は次頁参考のとおりである。
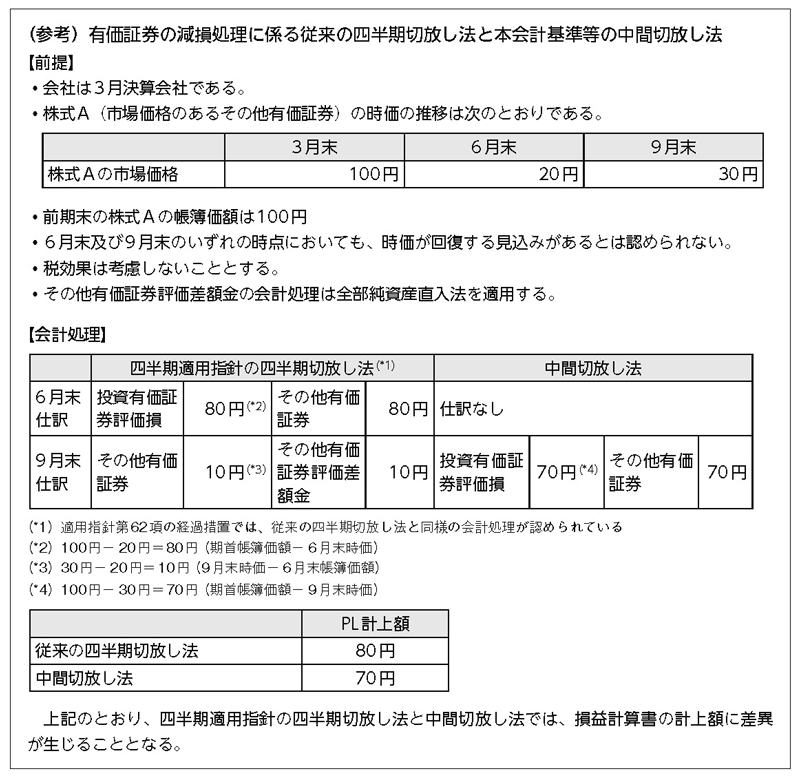
⑤ 一般債権の貸倒見積高の算定及び未実現損益の消去における簡便的な会計処理
四半期適用指針においては、四半期財務諸表に求められる開示の迅速性の観点から、一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理として、前年度又は前四半期会計期間から著しく変動していないと考えられる場合に、前年度又は前四半期会計期間の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を四半期決算で使用することを認めていた(四半期適用指針第3項)。同様の理由により四半期適用指針においては、未実現損益の消去における簡便的な会計処理として取引状況に大きな変化がないと認められる場合に、前年度又は前四半期会計期間の損益率を四半期決算で使用することを認めていた(四半期適用指針第30項)。
本会計基準等の適用対象となる中間財務諸表は、中間作成基準等の適用対象となる中間財務諸表より開示の迅速性が求められることから、前年度からの著しい変動がない場合に前年度末の決算において算定した実績率等を中間決算で使用することができるとする取扱いを、本適用指針でも簡便的な会計処理として引き継ぐこととした(本適用指針第3項、第28項及びBC3項)。
一方で、改正後の金融商品取引法では四半期報告書制度が廃止されるため、前四半期の決算において算定した基準等を中間会計期間において使用することは、決算日以外の期中の特定の日において算定した実績率等を使用することとなり、使用する実績率として適切ではないと考えられる。しかしながら、簡便的な会計処理は、財務諸表利用者の判断を誤らせないことを条件として認められた(四半期会計基準第9項及び第20項)ものであることから、引き続き当該簡便的な会計処理を認めたとしても財務諸表利用者の判断を誤らせるものではないと考えられるため、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる経過措置を設けることとした(本適用指針第61項、第64項及びBC3項)。
⑥ 四半期会計基準等の定め及び考え方を引き継いだもの
本会計基準等は、個別に検討したものを除き、中間財務諸表の作成にあたって必要な会計処理及び開示について、基本的に四半期会計基準等の定め及び考え方を引き継ぎ、四半期会計期間等の用語を中間会計期間等に置き換えることとした(本会計基準BC19項及びBC20項並びに本適用指針BC4項及びBC5項)。
なお、四半期会計基準第10-3項ただし書き(脚注6)のように、四半期会計基準には同一年度に複数の四半期決算が存在し得るため設けられたと考えられる定めについては、同一年度に中間決算は1度しか存在しないため、本会計基準等では引き継いでいない。
(5)適用時期等
① 適用時期
本会計基準等は、改正後の金融商品取引法に基づく中間財務諸表に適用されるため、本会計基準の適用時期は改正後の金融商品取引法の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用することとした(本会計基準第37項及びBC21項並びに本適用指針第60項)。
法律の施行日の前後において各企業が四半期報告書、改正前の金融商品取引法に基づく半期報告書又は改正後の金融商品取引法に基づく半期報告書のどの報告書の提出が求められるかどうかは、法律の附則第3条に定められており、2024年3月27日に金融庁が公表した「各決算期における適用時期(四半期報告書提出会社)」(脚注7)も参考になると考えられる。
図表3に記載のとおり、本会計基準等が最初に適用されるのは、改正前の金融商品取引法に基づき2024年4月1日以後に第1四半期に係る四半期報告書の提出が求められる12月決算会社になると考えられる。この場合には、第1四半期(2024年1月1日から2024年3月31日)に係る四半期報告書に含まれる四半期財務諸表については四半期会計基準等が適用され、中間会計期間(2024年1月1日から2024年6月30日)に係る半期報告書に含まれる中間財務諸表については本会計基準等が適用されることになると考えられる。
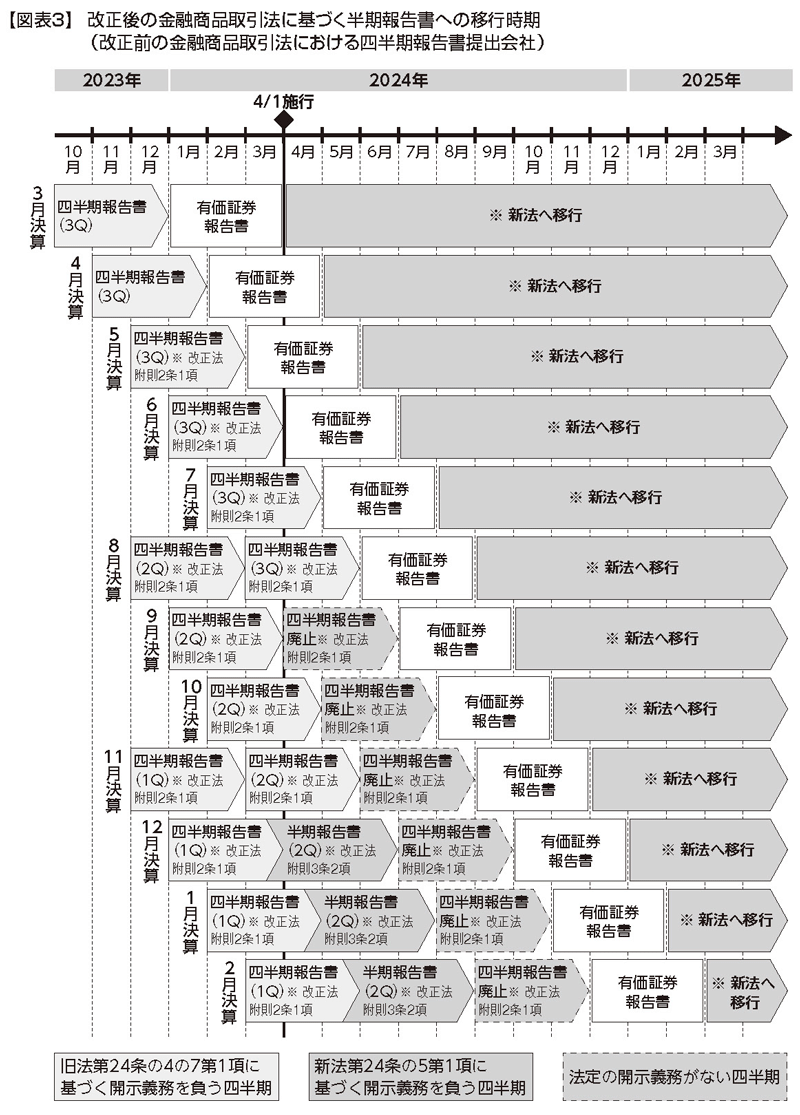
② 適用初年度の取扱い
本会計基準の適用初年度においては、遡及適用によってもたらされる過去の期間に関する情報に有用性があると考えられ、企業が自主的に前年度の四半期において適用していた会計方針と異なる会計方針を採用しない限り前年度の第2四半期財務諸表と同様の会計処理により適用初年度においても開示対象期間の中間財務諸表を作成することが可能となると考えられることから、開示対象期間の中間財務諸表等について本会計基準を遡及適用することとした(本会計基準第38項、BC22項及びBC23項)。
また、本会計基準の適用初年度においては、従来作成していた財務諸表(四半期財務諸表)と異なる種類の財務諸表(中間財務諸表)を新たに作成することになると考えられるため、適用初年度において従前の四半期財務諸表において採用していた会計方針(年度の会計方針との首尾一貫性が求められる会計方針を除く。)と異なる会計方針を採用する場合には、会計方針の変更に該当せず新たに会計方針を採用することになると考えられる(本会計基準BC24項)。
③ 他の会計基準等における四半期財務諸表に関する取扱い
本会計基準は、基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を引き継ぐこととしており、本会計基準が適用される中間財務諸表においては、これまでに公表された会計基準等における四半期財務諸表に関する会計処理及び開示の定め(本会計基準等が定めている会計処理及び開示は除く。)も引き継ぐことが考えられる。
このため、他の会計基準等における四半期財務諸表に関する定めを従前の四半期での実務が継続して適用可能となるように、「四半期会計期間」、「四半期決算」、「四半期財務諸表」、「四半期連結財務諸表」又は「四半期個別財務諸表」という用語(会計基準等の名称を除く。)を「中間会計期間」、「中間決算」、「中間財務諸表」、「中間連結財務諸表」又は「中間個別財務諸表」という用語に読み替えることとした(本会計基準第39項及びBC25項)。
また、他の会計基準等の読替えにあたっては、従前の四半期の実務を変更することを意図していないことに留意する必要がある。なお、これまでに公表された会計基準等には、日本公認会計士協会が公表した企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。)のうち会計処理の原則及び手続を定めたものが含まれる。
4 財務諸表等規則等の改正
本会計基準等の公表に合わせて、2024年3月27日付で、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令が公布されている。本会計基準等は、金融商品取引法の改正を受けて公表に至ったものであり、改正後の金融商品取引法並びに「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の関連する開示規則等についても併せてご確認いただきたい。
5 おわりに
本稿が本会計基準等の概要やその趣旨をご理解いただくための一助となれば幸いである。
脚注
1 本会計基準等の全文については、ASBJのウェブサイト(https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0322.html)を参照のこと。
2 資本連結実務指針の改正については、日本公認会計士協会のウェブサイト(https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240527ruy.html)を参照のこと。
3 ディスクロージャーWG報告の全文については、金融庁のウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20221227.html)を参照のこと。
4 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令に基づき改正された企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)(以下「企業内容等の開示に関する内閣府令」という。)第4号の3様式の記載上の注意(5)aにおいて、改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に定める事業を行う会社を特定事業会社と定義している。上記改正については、金融庁のウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html)を参照のこと。
5 金融庁のウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231208/20231208.html)を参照のこと。
6 四半期会計基準第10-3項では、「(略)ただし、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なとき(企業会計基準第24号第9項(2))は、当年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。」とされている。
7 金融庁のウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327/20240327.html)を参照のこと。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















