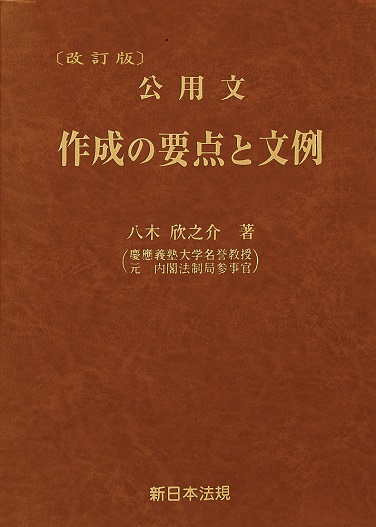解説記事2020年03月16日 税理士のための相続法講座 相続法改正(11)―配偶者居住権(2)(2020年3月16日号・№827)
税理士のための相続法講座
第56回 相続法改正(11)―配偶者居住権(2)
弁護士 間瀬まゆ子
1 はじめに
前回(本誌823号20頁)に引き続き、配偶者居住権について解説します。
2 配偶者居住権とは
まず、配偶者居住権がどのような権利かを確認しましょう。
(1)法的性質
配偶者居住権は、賃借権類似の法定の債権とされます。その際の債権者は配偶者であり、債務者は居住建物の所有者(共有の場合は共有者全員)です。
(2)基本的な権利の内容
配偶者居住権の債権者たる配偶者は、「無償」で居住建物の「全部」を「使用収益」することができます。
① まず、「無償」という点についてですが、配偶者が一切の金銭的負担を負わなくてよいという意味ではありません。民法上の使用貸借における借主と同様、通常の必要費は負担しなければならず(民法1034条1項)、具体的には、居住建物の保存に必要な修繕費のほか、居住建物および敷地の固定資産税相当額を負担すべきことになります。
② 次に、配偶者居住権は居住建物「全部」に及ぶ権利とされます。相続開始時に配偶者が居住に使用していたのが居住建物の一部であったとしても、配偶者居住権の効力は居住建物全てに及ぶのです。この点、筆者の私見ですが、配偶者と居住建物所有者の特約によっても、効力の及ぶ範囲を一部に限定することはできないと考えます。居住建物の一部についてのみ対抗要件を具備するということができないためです。
また、配偶者は、居住建物のほか、その敷地についても、居住建物の使用収益に必要な限度で利用することができます。
※上記のとおり配偶者居住権は建物全部に効力が及ぶことを前提とする権利ですが、相続開始時にその一部が賃貸に供されている居住建物についても、配偶者居住権を設定することは可能です。その場合に問題となるのが、賃貸部分について得られる賃料が、配偶者と所有者のどちらに帰属するかという点です。
まず、賃貸人たる地位は、居住建物の所有者が承継すると思われます(いわゆる「賃貸人たる地位の移転」の話です。)。したがって、貸主は所有者ということになります。ただ、そうであるからと言って、賃料を当然に所有者が収受してよいということにはなりません。所有者が取得したのは配偶者居住権の制限が付された所有権であり、前述のとおり、配偶者居住権の効力は居住建物全部に及ぶからです。
となると、法律論からすると、所有者は配偶者に対し、借主から受領した賃料を交付すべき債務を負うとの結論が導かれそうです。
しかし、仮に上記のような解釈が正しいとしても、賃料は所有者が受領すべきものと当事者が当初から想定していたケースも多々あり得(賃貸部分を除いて配偶者居住権を評価して遺産分割を行ったようなケース)、そのような場合、いちいち賃料を所有者から配偶者に交付しなければならないというのは実態に反します。ただ、そのような場合には、所有者と配偶者との間で、所有者が上記の債務を負わないとの黙示の同意があったと解する余地があるように思います。
いずれにしても、この辺りについては解釈が未だはっきりせず、今後の実務の集積が待たれるところです。
なお、上記のような賃料の帰属の問題との関係で、相続開始時の一部賃貸部分を配偶者居住権の評価対象から外している相続税法施行令5条の8第1項の問題を指摘したものとして、坂田真吾「配偶者居住権のすべてがわかる! 民法(相続法)改正のファイナルチェック」税務弘報2020年2月号80頁があります。
③ 最後に、「使用収益」とは、文字通り、配偶者自身が使用するほか、居住建物の一部で店舗を経営したり、居住建物を賃貸して賃料を得たりすることができるという意味です。ただし、相続開始前に居住の用に供されていた部分を、後から配偶者が営業の用に供することは、用法遵守義務違反(民法1032条1項)にあたり許されませんし(逆の用法変更は可能です。)、居住建物を第三者に賃貸するためには、居住建物所有者の同意が必要ですので(同条3項)、配偶者が実際に居住建物から収益を得られる場面は限定されそうです。
(3)存続期間
配偶者居住権の存続期間についての定めがないとき、その存続期間は配偶者の終身の間とされます(民法1030条本文)。
ただし、実務上あまりないかもしれませんが、遺産分割や遺言の中で終身ではない一定の期間を定めることも可能です(同条但書)。
存続期間の長さ(終身の場合は配偶者の平均余命までの年数)は、次回述べる配偶者居住権の評価額に大きな影響を及ぼします。配偶者の年齢が若く、存続期間が長期にわたる場合、配偶者居住権の評価額が思いのほか高額になってしまい、わざわざ所有権ではなく配偶者居住権を選択する意味がなくなってしまうことも考えられます。そのため、設定時に、存続期間を何年とするかというのは、大きな問題となるはずです。
なお、終身以外の期間を定めた場合、終了時に未だ配偶者が居住建物を必要としている可能性もあるわけですが、その場合でも期間の延長や更新は認められないと解されています(堂薗幹一郎ほか編著「概説改正相続法-平成30年民法等改正、遺言書保管法制定-」15頁で、配偶者居住権の財産評価を適切に行うことが困難になるためと説明されています。)。ただ、存続期間が終了した時点で、新たに所有者と配偶者との間で使用貸借契約や賃貸借契約を締結すれば、配偶者は居住建物に住み続けることは可能です。
(4)対抗要件
配偶者居住権は登記することができます。登記したときは、その後に居住建物の所有権を取得した第三者や居住建物を差し押さえた債権者等に対抗できることになります(民法1031条2項)。
※この場合の「第三者」は、居住建物の所有権を取得した者等です。例えば、居住建物と敷地の所有権を取得した相続人が他者に敷地だけを売却し、その際に居住建物の利用権が設定されなかった場合、敷地の譲受人は上記の「第三者」にあたりませんので、配偶者は当該譲受人に配偶者居住権を対抗することができないと解されています(居住建物の所有者すなわち敷地を売却してしまった相続人が、配偶者に対して責任を負うかはまた別の問題です。)。
この登記は、配偶者と所有者が共同して申請する必要があり(不動産登記法60条)、所有者は配偶者に登記を備えさせる義務を負っています(民法1031条1項)。所有者がこの義務を履行しないときは裁判手続が必要です。
3 配偶者居住権の成立
配偶者居住権の成立要件は以下のとおりです(民法1028条1項)。
① 配偶者が、相続開始の時に、遺産である居住建物に居住していたこと
② その居住建物が、被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有にかかるものであること
③ その居住建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の遺産分割または遺贈(死因贈与を含む)がされたこと
①について
「配偶者」は、法律婚の場合に限定され、内縁の配偶者が配偶者居住権を取得することはできません。
また、「居住していた」とは、配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを意味します。相続開始時に配偶者が一時的に施設に入っていたとしても、生活の本拠としての実態を失っていなければ「居住していた」と認められます。また、面白いのが、生活の本拠が複数あった場合には複数の建物について、また、2棟の建物を一体として居住の用に供していた場合には2棟の建物について、それぞれ配偶者居住権が成立し得ると解されているところです(堂薗ほか前掲書12頁)。このあたりの発想は、税理士にはないところではないでしょうか。
②について
被相続人と配偶者以外の者が建物を共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項但書)。
筆者が実際に見聞きした問題になりそうな事例として、以下のようなものがありました(事実関係を変えています。)。
Aが亡くなった。相続人は、Aと先妻Bの子であるCと、Bが亡くなった後に再婚したD。AとDが住んでいた自宅の建物は、AとBの共有名義のままとなっている。自宅以外にめぼしい資産はなく、Dに代償金の支払能力もないため、Dは配偶者居住権の取得を希望している。しかし、Cは早く自宅を売ってお金にしたいと言っている。
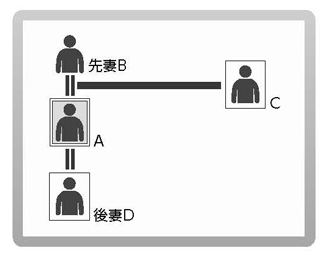
この事案で、Dが配偶者居住権を取得するためには、Bの相続に関する遺産分割協議で、Bの持分全部をAが取得するする必要があります。仮にCが持分を取得すると、AとCの共有であったことになり、②の要件を欠くことになってしまうからです。そのためには、Cの協力が不可欠です。しかし、そもそも配偶者居住権の設定に反対しているCが協力するわけがありません。
したがって、この事案で、Dが配偶者居住権を取得することは非常に困難です。
※Aの相続とBの相続に関して遺産分割協議が整わず家裁の審判に移行した場合に、Dが代償金の支払能力を証明するか、不動産以外にBの財産があれば、Bの遺産分割でBの建物持分をAが承継し、Aの遺産分割でDの配偶者居住権が認められるという余地もないわけではありません。ただ、そのハードルは高そうです。
③について
配偶者居住権は、あらかじめ被相続人が遺言で定めておいた場合のほか、遺産分割により設定することも可能です(民 法554条により死因贈与にも準用されます。)。遺産分割調停で協議がまとまらず、審判に移行した場合に、裁判官の判断により配偶者居住権の取得が認められることもあり得ます(民法1029条)。
※ただ、反対する相続人がいる場合に審判で配偶者居住権の取得を認めるには法律上厳しい要件が課されており、裁判官も配偶者居住権を認めるのにはかなり慎重になると思われます。
注意が必要なのは遺言で設定する場合です。「遺贈」はよいのですが、いわゆる「相続させる」遺言により取得させることが法律上認められていないからです。
なぜ相続させる遺言が認められなかったのでしょう。これについては、仮に配偶者が配偶者居住権はいらないと考えたときに、遺贈であればそれを放棄した上で配偶者において遺産分割協議に参加することが可能なのに対し、相続させる遺言の場合、配偶者居住権の取得を免れるためには相続自体を放棄するほかなく、事実上配偶者居住権を取得しないという選択肢がなくなるためと説明されています。
しかし、公証実務も含め、相続人に取得させる場合「遺贈する」ではなく「相続させる」と記載する実務が広く定着しています。上記の点について知識がないと、書式集等のとおりに「相続させる」と記載してしまいかねないので、注意が必要です(実務的には、「相続させる」と書かれていても、遺贈の趣旨と解して救済することが多くなるとは言われています。ただ、確実とは言えませんし、手続きの手間もありますので、やはり初めから「遺贈する」としておくべきです。)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.