解説記事2024年07月22日 ニュース特集 訴訟にまで発展した税理士業務を巡るトラブルⅢ(2024年7月22日号・№1036)
ニュース特集
退職の際に顧問先を勧誘、誓約事項に違反するか
訴訟にまで発展した税理士業務を巡るトラブルⅢ
本特集では、前回(本誌946号)に引き続き税理士業務を巡って訴訟にまで発展した事件を3件紹介する。税理士が多く所属するコンサルティング会社の社員が独立する際に、顧問先を勧誘したかどうかが問題となった事件では、社員と交わした誓約事項の「自己の退職を当該事務所の顧問先等に予告し、自己の顧問先とする勧誘行為を致しません。」との部分が裁判所の判断のポイントの1つとなっている。また、税理士が顧問先へ税務書類の一部を返還しなかった事件では、税務顧問契約の債務不履行に該当するとの判断が下され、損害賠償金の支払いが命じられている。そのほか、顧問先が銀行に対して税理士の不満を相談したことが不法行為に該当するか争われた事件では、銀行から税理士を紹介されて顧問契約の締結に至ったという経緯があったということを踏まえ、銀行も相談内容を他の顧客等に漏洩するとはおよそ考え難いとして税理士の主張を斥けている。当然の話ではあるが、いずれの事件も税理士と顧問先(又は社員)の信頼関係は大きく損なわれた上で訴訟に至ったもの。仮に一部勝訴しても裁判にかける労力に比べればその賠償金額はわずかなものにとどまっている。留意しておきたい点であろう。
雇用契約には顧問先に退職を予告し、勧誘しないとの誓約事項あるが
1件目に紹介するのは、原告である税理士が多く所属するコンサルティング会社(経営診断、経営指導及び経営意思決定援助業務等を目的とする株式会社)の社員(被告)が独立するに際し、被告が担当する顧問先を自分の顧問先に勧誘したかどうかが問題となった事件(令和5年4月14日、令和4年(ワ)第4302号)だ。
社員は顧問先に退職の挨拶
被告は、会社(原告)との間で雇用契約を締結し、原告の顧問先に対する巡回監査・会計ソフト入力業務を担当(なお、被告は税理士資格を有していない)。雇用契約の締結の際には、「法人を退職する者は、……自己の退職を当該事務所の顧問先等に予告し、自己の顧問先とする勧誘行為を致しません。」とする誓約事項が付されており、これに違反して原告に損害を与えたときは、その損害額を弁済することとされていた。その後、被告は原告の会社を退職し、独立することになるが、退職する前に、顧問先に対し、会社を退職する予定である旨を告げていた。
会社側は、被告が会社を辞めた時期に前後して被告の担当していた顧問先34件中14件(約41%)が顧問解約を申し入れており、社員が顧問先に退職を予告し、自分の顧問先とする勧誘行為を行ったとしたほか、被告は退職後、X税理士事務所に所長として勤務しており、顧問先を勧誘する動機があったなどと主張した(表1参照)。

勧誘行為を行ったように思えるが……
裁判所は、本件では①顧問先による顧問契約の解約の申入れが、被告が担当する顧問先34件中14件(約41%)と高い割合を示しており、かつ、被告の退職に近接する時期に行われていること、②解約の申入れが、被告がその案文を作成し、標題・本文ともほぼ同一の内容である顧問契約解除通知書により行われていたこと、さらに、③被告が原告を退職した後、原告と同業関係にあるX税理士事務所において、所長として勤務していたことが認められ、これらの事実は、原告が顧問先を自己の顧問先とする勧誘行為を行ったことに一定程度沿うものであるとした。
しかし裁判所は、顧問先の1つは顧問契約を解約した理由として、被告から勧誘行為を受けたことを挙げておらず、かえって、原告に対する不満があった旨を述べており、また、別の顧問先は、原告との顧問契約の解約に当たり、被告による「勧め」や「積極的な関与」があったことを否定しており、顧問先で、原告との間の顧問契約の解約に当たり、被告から勧誘行為を受けた旨を述べる者がいるとは認められないとした。
礼儀として退職を伝えたにすぎず
これに加え、被告が退職に当たり、顧問先にビジネス上の礼儀として退職を伝えたところ、被告に対し、他の税理士事務所で勤務する予定があるかを聞いてくる者もおり、そうした者に対しては、他の税理士事務所で勤務する予定がある旨を回答していたこと、これらの顧問先の中には、今後も被告に担当してもらいたいから、原告との間の顧問契約を解約したいと述べる者もいたこと、また、これらの者からは、解約に必要な書面を作成してほしいと要望を受けたため、顧問契約解除通知書の案文を作成し、交付していたことを供述等するところ、これらの供述等に係る事実関係が不自然なものであるとは断じ難いとした。
退職予告の禁止は社会通念上相当性を欠く
誓約事項の「自己の退職を当該事務所の顧問先等に予告し、」との部分については、既定の通常の読み方に照らせば、「を致しません。」に直接かかるものではなく、「勧誘行為」を修飾するものというべきであり、退職予定者が勧誘行為を行う場合、その前提として退職の予告をすることが通常の態様であることから、注意的に規定されたものと解されるとした。実質的にみても、退職予定者が自己の退職を顧問先に予告することは、顧問先に対する適切な業務遂行や担当者の引継ぎのために、これを行わざるを得ない場面があると解され、退職の予告自体を禁止し、違反した場合に損害賠償責任を課すことは、社会通念上相当性を欠くといわざるを得ないと指摘。誓約事項は、原告の退職予定者が原告の顧問先に対してこれを自己の顧問先とする勧誘行為を禁止するものと解するのが相当であり、被告が顧問先に対し、自己の顧問先とする勧誘行為を行ったことが認められないことを踏まえると、被告に誓約事項の違反(債務不履行)は認められないと判断し、原告の請求を棄却した。
税務書類の一部を返還せず、債務不履行となるか
2件目に紹介する事件は、税理士(被告)が顧問先(原告)から税務書類の未返還及び税務顧問契約の債務不履行に基づき、損害賠償請求が行われたもの(令和6年2月6日、令和4年(ワ)第2541号)。具体的には、被告の税理士と税務顧問契約を締結していた原告が、被告に対し、①被告は原告が記帳代行業務のために交付した各証憑書類を返還せず占有していると主張して、所有権に基づき、各証憑書類の引渡しを求めるとともに、②被告は令和元年9月以降の同契約に基づく原告の第11期分の業務を行わなかったと主張して、同契約の債務不履行に基づき、およそ188万円の損害賠償金の支払いを求めたものである。
裁判所は、被告が原告の10期分及び11期分の書類を返還していないと認めた上で、被告が11期分の業務を行わず、11期分の損益計算書の交付や税務報告をせず、また、原告に対して11期分の証憑書類を返還しなかったことから、これが債務不履行に当たるか否かについて検討を行っている。
裁判所は、本件契約は税務顧問契約(表2参照)であり、本件業務①(会計処理の指導、相談及び記帳代行業務)の月額報酬(5万円)の対象となる業務は当該月又は年度のものに限定されないから、10期分の会計処理に係る相談や記帳代行業務であっても対象期間の本件業務①に含まれると解され、また、各支払いのうち、令和2年5月分の本件業務②(法人税、住民税及び事業税の申告書類の作成並びにその税務代理業務)の報酬(16万円)は10期分の税務申告についてのものであるから、単に11期分の業務を行っていないというだけで債務不履行となるわけではないとした。
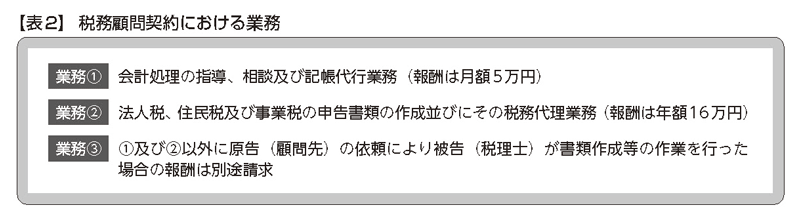
ただし、被告が、原告からの求めにもかかわらず、原告から預かった11期分書類を返還しておらず、また、記帳代行業務によって作成した総勘定元帳も交付しなかったことからすると、被告は、契約に基づいて預かった書類の返還義務を怠ったものであるし、契約に定められた本件業務①には記帳代行業務の成果を原告の求めに応じて原告に利用させる義務も含まれていると解されるところ、被告は当該成果を原告が利用することを妨げたというべきであるから、これらの点で、被告には本件契約に基づく債務の不履行があるとの判断を示した。
これに対し、被告は、①本件契約の途中からやり取りができない状況を作ったのは原告の責任である、②原告が難癖をつけていたため、総勘定元帳等はすべて後任の税理士に引き継ぐ予定で、原告には交付しなかったと主張したが、裁判所は、原告代表者は被告と面談し、10期の決算報告書の数値に誤りがあると指摘し、面談を録画しつつ、約1時間半にわたり説明を求めたことは、被告が相当な負担を感じたことは推測できるが、決算報告書の数値に誤りがあったことからすれば原告がその原因を確認しようとすることが直ちに不当とはいえず、その後、解約解除時まで被告が原告のメールの質問等にも回答をしていないのであるから、その責任が原告にあるとは認められないとした。
8か月分の報酬の半分が記帳代行業務の報酬
なお、被告の債務不履行による損害賠償金は裁判所に30万円と判断とされている。裁判所は、原告は対価を支払った11期分の記帳代行業務の成果を利用することができず、また、11期分書類の返還も受けられなかったため、解除の1か月後には決算期が迫っていた11期の決算報告及び確定申告のため、その基礎となる証憑書類の再発行を受け、一から決算報告書を作成するなど、余分な時間や労力をかけることを余儀なくされたものであると指摘。8か月分の本件業務①の報酬について原告が支払った合計40万円のうち、少なくとも20万円は記帳代行業務の報酬とみるのが相当であるとした。また、2か月分の本件業務①に係る役務の提供を受けられなかったという不利益に係る損害を金銭的に評価すると、各月分の報酬として支払った額に相当する10万円と認めるのが相当であるとし、本件契約の債務不履行による原告の損害を30万円と認定した。
顧問先が税理士の取引先の銀行に不満を吐露、不法行為は成立するか
最後に紹介する事件は、顧問先及び税理士法人がお互いに信頼関係を失い、税理士法人(原告)が税理士報酬等の請求とともに、被告である顧問先が第三者であるY銀行に対して虚偽事実を告知したことから不法行為に基づく損害賠償を求めたもの(令和5年6月29日、令和4年(ワ)第5632号)。そもそも税理士法人側の請求は60万円弱と高額なものではなかったが、結果的に認められたのは決算書類等作成報酬等の17万円余りにすぎず、顧問先の不法行為については成立しなかった。では、本件の概要についてみてみることにしよう。
被告である顧問先会社及び同社の代表者は、原告である税理士法人が申告書の作成及び提出したことは認めつつも、担当税理士から被告を愚弄する言動をしたり、担当替えの際に十分な引き継ぎをしなかったり、不必要な保険への加入を勧めたりするなど、原告の作成業務は杜撰であって行うべき仕事を行っていないなどと主張。一方、税理士法人側は、Y銀行は原告にとって業務上の付合いのある重要な顧客であるところ、被告がY銀行に対し、①原告の担当税理士からセクハラ行為を受けた、②不必要な共済・保険に加入させられた、③顧問契約を締結する前に契約をしていた不動産管理会社を変更させられた、④担当税理士が交代した際の引き継ぎがされなかった、⑤被告個人についての総勘定元帳が作成されていなかった、⑥クレジットカードのポイントやiDeCoについて経費算入の説明がされなかったなど、虚偽事実を告知したことにより原告の名誉又は信用を毀損されたなどと主張した。
紹介を受けた銀行に相談したにすぎず
裁判所は、事実認定の上、被告会社の決算書類等作成報酬及び被告代表者の確定申告書作成報酬について、被告に対し税理士法人に支払うよう命じたが、被告の不法行為に関しては、被告がY銀行に対してセクハラ行為を受けたなどと告げた理由は、Y銀行の行員から被告の税理士法人を紹介されて顧問契約の締結に至ったという経緯があったことから、原告の業務に不満を有し、紹介先であるY銀行に相談したというものであると指摘。Y銀行としては、顧客である被告代表者から顧問先の税理士法人についての相談を受ける中で不満を聞いたのであるから、その相談内容を他の顧客等に漏洩するとはおよそ考え難く、被告代表者がY銀行に相談したことをもって、原告の名誉権を侵害したとはいえず、原告に対する不法行為が成立すると認められないと判断している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























