解説記事2025年01月13日 巻頭特集 令和7年度税制改正大綱−国際課税に関する改正(2025年1月13日号・№1058)
巻頭特集
令和7年度税制改正大綱−国際課税に関する改正
移転価格税制(利益B)、CFC税制(合算タイミング)、グローバル・ミニマム課税、外国人旅行者向け免税店
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 南 繁樹
国際課税に関する改正点
昨2024(令和6)年12月20日、自民党と公明党は令和7年度与党税制改正大綱(以下「大綱」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、国際課税に関する重要な改正点として、下記の項目を取り上げる。
・移転価格税制に関する「利益B」(販売会社の利益率に関する、コンパラを使用しない簡素な算定方法)の取扱い(下記第1)
・CFC税制の合算タイミング変更と書類簡素化(下記第2)
・グローバル・ミニマム課税に関するUTPRとQDMTTの法制化(下記第3)
・外国人旅行者向け免税店の見直し(下記第4)
・「物品販売」に対する消費税のプラットフォーム課税(下記第5)
本稿は、大綱に基づいて速報性を重視して要旨を紹介するものであり、筆者の推測や私見も含む。詳細は2025(令和7)年1月以降の通常国会に上程される税制改正法案や最終的に成立した法律を参照する必要があることに留意されたい。なお、本稿のうち意見にわたる部分は筆者個人のものであり、筆者が過去又は現在において所属する組織に属するものではない。
第1 移転価格税制:販売活動に関する利益Bは、売上高にかかわらず、実務に影響
「BEPS (Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクト」に関し、大綱では第1の柱に言及があるほか、第2の柱に関して軽課税所得ルール(UTPR)と国内ミニマム課税(QDMTT)の新設が行われる(下記第3)。特に、移転価格税制に関する利益Bについては、適用対象が限定されておらず(後述)、本年(2025年)からの適用の可能性もあり、早急な確認と検討が必要である。
1 第1の柱、利益B(コンパラなしの利益率算定)
(1)中小企業も適用対象となりうる
グローバル・ミニマム課税の適用範囲は、総収入金額(売上高)7億5,000万ユーロ以上(約1,200億円以上)の多国籍企業グループに限られているが、利益Bについては収入金額(売上高)にも利益率にも限定はない。したがって、いわゆる中小企業であっても外国に関連会社(国外関連者)を有する限り利益B(簡素な算定方法)の適用の可能性がある。したがって、利益Bの適用がありうるのか、適用がある場合には利益Bによる独立企業間価格の算定がこれまでの自社の移転価格ポリシーやベンチマーク分析と整合するか否か、早急な確認が必要である。
(2)利益Bとは何か?
利益Bとは、基礎的マーケティング及び販売活動(Baseline marketing and distribution activities)に対する独立企業間価格について、「簡素化・合理化アプローチ」(SSA:Simplified and streamlined approach)と呼ばれる簡易な方法で算定された利益率を意味する。比較対象法人(コンパラ)を使用しない。簡素な方法で自動的に独立企業間価格を算出し、それを国際的に承認することで、執行能力が必ずしも十分ではない新興国に対して一定の利益を保証する効果を有している。
デジタル課税を扱う第1の柱でなぜ移転価格税制が出てくるのか疑問に思う読者もいるかもしれないが、いずれも市場国の不満に対応する点において共通するのである。多国籍企業が全世界の市場国で事業活動を行っているにもかかわらず、市場国に十分な税収がもたらされていないという点に市場国の不満があった。そのうち、物理的拠点(恒久的施設)なしにオンラインで行う販売活動を対象としたのが(もともとの)利益A(いわゆるデジタル課税)で、物理的な拠点(子会社、支店)を有して行う販売活動を対象としたのが利益Bと考えるとよい。
(3)日本は利益Bを導入しない
利益Bは、当初は利益Aとのパッケージで導入されることとされていたが、利益Aの成立が困難となったため、利益Bのみでも延命させようとOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」における「政治的コミットメント」の下に導入されることとなった。参加国間の法的な合意は要求せずに、利益Bを導入するか否かは各国に委ねるが、参加国は一定の条件の下にそれを「尊重(respect)」することを政治的にコミットする、ということとなったのである(条約としての効力は存在しないのであろう)。そのコミットメントの内容が記載されているのが、2024(令和6)年2月に公表された利益Bに関するガイダンス(以下「利益Bガイダンス」という。)であり、すでに国税庁のウェブサイトに仮訳が掲載されている(脚注2)。同ガイダンスによれば、利益Bについて、それ(簡素な算定方法)を導入するか否かは各国が選択するものとし、導入した場合も、①納税者が選択適用する(セーフ・ハーバー)か、②納税者に義務付けるのか(強制適用)のいずれかを、各国が選択できるものとされた(利益Bガイダンス・パラ5~8)。
この点に関し、大綱は、「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化については、今後、国際的な議論及び各国の動向を踏まえて対応を検討することとし、当面は実施しない。」(大綱15頁)と記載している。すなわち、我が国当局に関しては、当面は、移転価格税制の執行に関して従前からの変更はなく、原則として、独立企業原則に従い、機能・リスクの類似する比較対象法人を選定して独立企業間価格を算定するなど、独立企業原則に従った取引価格の設定が必要である(措法66条の4)。
(4) 相手国が利益Bを採用する場合、日本はそれを「尊重」
他方で、大綱は、「他国が本簡素化・合理化を実施する場合については、現行法令及び租税条約の下、国際合意に沿って対応する。」(大綱15頁)とも記載している。この「国際合意」とは利益Bガイダンス及びこれに関連する文書であると思われる(脚注3)。これらの文書において、利益Bの導入を選択しない国においては利益Bに基づく算定方法は拘束力を有しないことを原則としつつも、相手国が新興国を主とする利益B対象国(covered jurisdiction・後述)である場合には、導入しない国も相手国の適用する利益Bを尊重(respect)するということを各国は政治的に約束(コミット)しており(脚注4)、我が国当局もそのような約束に従うということであると思われる。このため、我が国企業が利益B対象国に所在する関連会社との取引に関して二国間相互協議を行う場合において、相手国(利益B対象国)の当局が利益Bを主張したときは、現行法令及び租税条約に反しない限り、我が国当局はそれを「尊重」せざるをえないため、相互協議においても利益Bによって定められた売上高営業利益率が事実上の基準となることが想定される(私見)。
(5)利益Bはどのようにして算定するのか?
利益Bは本質的には従来の取引単位営業利益法(TNMM)と変わらない。しかし、本来の取引単位営業利益法においては、機能・リスクを個別具体的な分析に基づいて比較対象法人と検証対象法人の間で機能・リスクが類似することを求めるので、類似性(比較可能性)があるか否かが問題になることが多い。そのプロセスを簡素化し、標準化された算定により手間と紛争を解消しようというのが「簡素化・合理化アプローチ」の眼目である。特に、比較対象法人の選定(コンパラ・サーチ)が不要となる点は従来との大きな違いであろう。以下、利益Bガイダンスを略説する。
ア 「適格取引」
個別具体的な機能・リスク分析に代えて、「基礎的マーケティング及び販売活動」を定義し、入口において、この「基礎的マーティング及び販売活動」に該当する取引を「適格取引」と呼び、適格取引を行う当事者のみが「簡素化・合理化アプローチ」(利益B)の対象となる。購入・再販売(バイ・セル)と、代理店・コミッショネアが対象となるが(パラ10)、売上高に対する営業費用(Operating Expense)の比率が3%の下限、20%~30%で定められる上限(導入国が決定)の範囲内でなければならない(パラ13)。無形資産、サービス、一次産品(コモディティー)の取引は適格取引に含まれず、利益Bの対象とならない。
イ 利益率の適用表(Pricing Matrix)を用いた売上高営業利益率の算定
「適格取引」に該当する取引については、以下の3ステップで売上高営業利益率を求める(パラ45~48)。
ステップ1:3区分の産業分類(図表1参照)のいずれに該当するかを決定する。
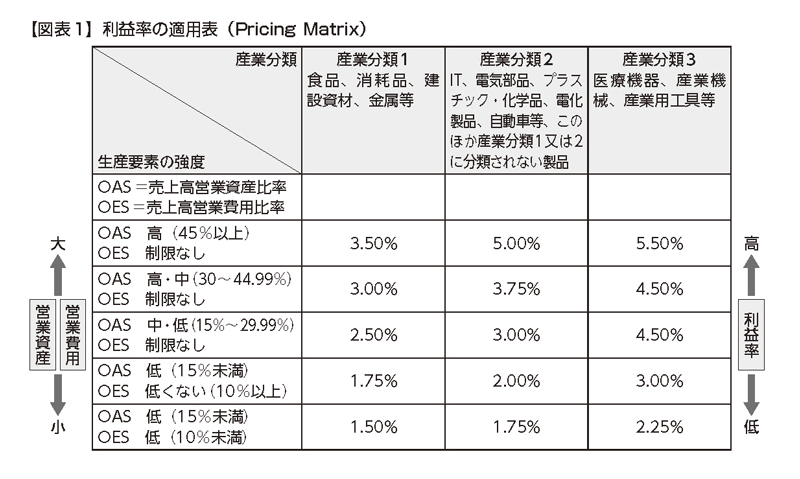
ステップ2:当該当事者による販売活動に投入される生産要素の強度の指標として、売上高に対する営業資産の比率(OAS:net Operating Asset intensity)と、売上高に対する営業費用の比率(OES:Operating Expense intensity)を求める。
ステップ3:図表1の適用表(Pricing Matrix)に当てはめて、営業利益率を求める。なお、±0.5%を加えた幅になる。
すなわち、業種によって収益性が異なることを前提に、より多額の営業資産、より多額の営業費用を使用するほど、利益率が高まる、ということである。
ウ 営業費用に対する営業利益の比率による検証
営業費用(Operating Expense)に対する営業利益の数値が10%から上限値(売上高に対する営業資産・営業費用の比率により40%、60%又は70%)の範囲に入るように調整する。上限値を超える場合には上限値まで営業利益率を減少させ、10%未満の場合には10%になるように営業利益率を増加させる(パラ51~52)。ベリー比によるチェックに代わるものである。
10% ≦ 営業利益/営業費用 ≦ [40/60/70]%
エ 国債格付けによる調整
国債格付け(sovereign credit rating)が低い国については、そのリスクに応じて利益率を増加させる(パラ53~54)。
(6)実務上の対応
上記のとおり、我が国政府は利益Bを導入しないが、相手国が利益B対象国である場合には、我が国政府は利益Bを「尊重」せざるをえず、上記適用表に基づく売上高営業利益率が事実上の基準として働く可能性がある。利益B対象国との間では、利益Bは2025(令和7)年1月1日から発効する可能性がある(脚注5)。利益B対象国には、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、メキシコ、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムなども含まれており、注意が必要である。たとえば、電気部品や電化製品に関し、新興国での単純な販売活動について、売上高営業利益率3.00%が標準的な値とされることについては、国や製品によってはやや高いと感じられる場合もあるかもしれない。その場合、機能・リスク分析に基く比較対象法人の平均の営業利益率が1%であると主張しても、反論として認められない、ということになる。
利益B対象国(2024(令和6)年6月時点)
(注目すべき国に下線を付した)
アルバニア、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベリーズ、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、ケイボ・ベルデ、カメルーン、コンゴ、コスタリカ、コート・ジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エジプト、エスワティニ王国、 フィジー、ガボン、ジョージア、グレナダ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、リベリア、マレーシア、モルジブ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、ナミビア、ナイジェリア、北マケドニア、パキスタン、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、サモア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、南アフリカ、スリ・ランカ、タイ、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナム、ザンビア
(7)米国は利益Bを納税者の任意選択として採用
なお、2024(令和6)年12月18日、米国税務当局(内国歳入庁及び財務省)は、利益Bを納税者の任意選択とする旨の規則案(Notice 2025-04)を公表した(脚注6)。米国は利益B対象国(covered jurisdiction)には含まれていないが、米国法人が利益Bに基づいて取引価格を算定した場合、米国当局としてはそれを承認することになる。以上は米国国内法の問題である。日米の相互協議において、日本当局は米国企業が算定した利益Bを「尊重」する政治的コミットメントを負っておらず、それに拘束されないのが建前であるが、利益Bはいわば国際的な標準として示され、移転価格ガイドラインにも組み込まれている(第4章附属書)。それを前提として、我が国政府が「国際合意に沿って対応する」と記載している以上、利益B対象国ではない国との間においても利益Bを無視することは難しいのではないだろうか(私見)。この点はさらなる検討を要する。
2 第1の柱、利益A(デジタル課税)
利益Aは、デジタル化した経済に対応し、市場国へ新たな課税権を配分することを目的とする。具体的には、利益Aは、売上高200億ユーロ超(約3兆2,000億円超)、利益率10%超の大規模・高利益水準のグローバル企業を対象として、その利益率10%を超える超過利益のうち25%を市場国に配分する(脚注7)。これを実現するためには多国間条約が必要であり、2023(令和5)年10月に条約文案が公表されたが、その後最終化されておらず、当初2024(令和6)年6月末を目標の期限としていた署名式も目処は立っていない。米国で国際協調に消極的なトランプ政権が成立した現在、多国間条約が発効する見通しは乏しい(脚注8)。大綱には、「市場国への新たな課税権の配分等に関する多数国間条約の早期署名に向けて、引き続き国際的な議論に積極的に貢献することが重要である。」(大綱15頁)との記載があるが、現実的には困難であろう。
3 (参考)非居住者の給与課税のあり方
大綱は「経済活動のグローバル化やデジタル化による国境を越えたビジネスや人の往来の一層の拡大等も踏まえて、非居住者の給与課税のあり方について、今後とも検討を行っていく。」(大綱15頁)と述べている。日本にとっての非居住者が外国からリモートで日本企業のために役務を提供した場合、居住地である外国で課税されるのが現行法の原則であるが、日本で課税しなくてもよいのか、という問題意識であろうと思われる(脚注9)。この点は今後の課題であり、中長期的には注意しておく必要があると思われる。
第2 CFC税制:親会社と子会社の事業年度が異なる場合、合算年度に変更
1 日本親会社の合算年度が、外国子会社の年度終了日から「4月」を経過する日を含む年度に改正
外国子会社合算税制(以下「CFC税制」という。)に関し、子会社(以下「外国関係会社」という。)の課税対象金額等(合算される金額)が合算される日本親会社の事業年度について、従前は、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から「2月」を経過する日を含む(日本親会社の)事業年度とされていた(脚注10)。この「2月」が改正され、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から「4月」を経過する日を含む(日本親会社の)事業年度に改正される(大綱94頁)。下記のとおり、日本親会社3月決算、外国関係会社12月決算の場合などに影響が生じる。
(1)日本親会社3月決算、外国関係会社12月決算(図表2参照):1年後ろ倒し
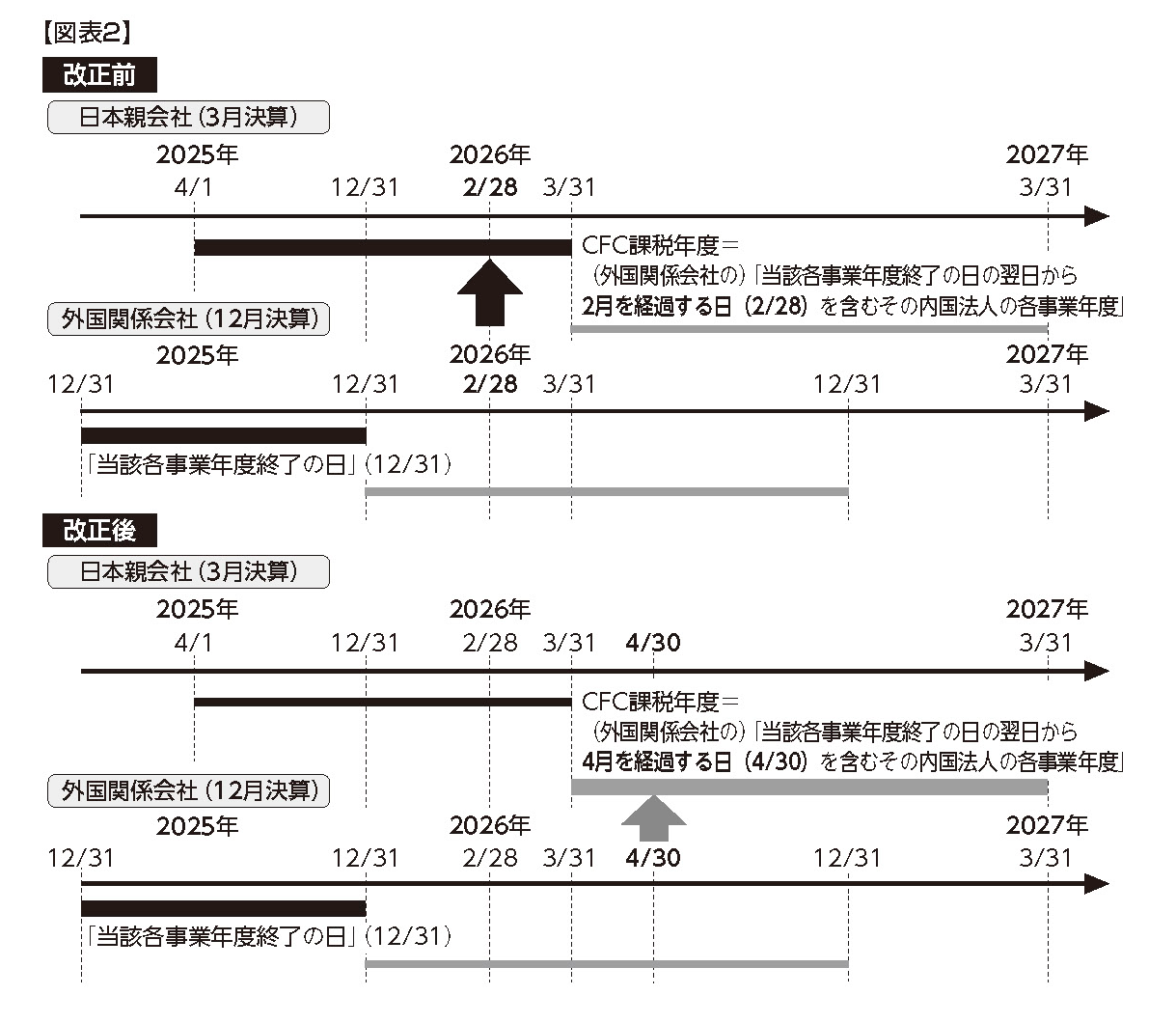
(改正前)
改正前は、たとえば、外国関係会社の2025年12月期については、「当該各事業年度終了の日の翌日から『2月』を経過する日(=2026年2月28日)を含むその内国法人の各事業年度」、すなわち、直後の日本親会社の2026年3月期において合算がなされてた。
(改正後)
これに対し、改正後は、たとえば、外国関係会社の2025年12月期については、「当該各事業年度終了の日の翌日から『4月』を経過する日(=2026年4月30日)を含むその内国法人の各事業年度」、すなわち、日本親会社の2027年3月期(2026年4月1日~2027年3月31日事業年度)において合算がなされる。このように、合算年度が1年度ほど後にずれることになる。
(2)日本親会社12月決算、外国関係会社12月決算(図表3参照):変更なし
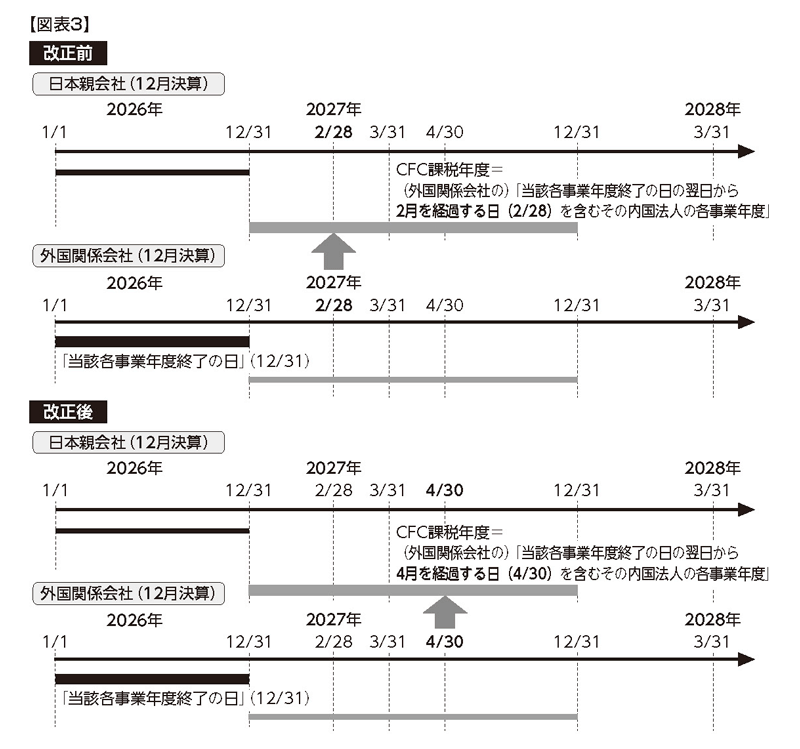
(改正前)
改正前は、たとえば、外国関係会社の2026年12月期については、「当該各事業年度終了の日の翌日から『2月』を経過する日(=2027年2月28日)を含むその内国法人の各事業年度」、すなわち、直後の日本親会社の2027年12月期(翌事業年度)において合算がなされていた。
(改正後)
日本親会社と外国関係会社が同一の事業年度を採用している場合、従前から、日本親会社の翌事業年度において合算されていたことから、改正によっても影響を受けない。すなわち、改正後は、たとえば、外国関係会社の2026年12月期については、「当該各事業年度終了の日の翌日から『4月』を経過する日(=2027年4月30日)を含むその内国法人の各事業年度」、すなわち、日本親会社の2027年12月期において合算がなされる。このように、合算年度は「翌事業年度」であって、従前と変わらない。
2 外国関係会社に関する書類の簡素化
申告書に添付又は保存を要する外国関係会社の書類から、次の書類が除外される(脚注11)。
① 株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書
② 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書
なお、貸借対照表・損益計算書、本店所在地国の法人所得税申告書、株主名簿等は従前どおり添付又は保存が必要である。
3 適用時期−前倒し適用も
上記1及び2は、日本親会社の2025(令和7)年4月1日以後に開始する事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の同年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用される(大綱94頁)。つまり、日本親会社が3月決算で、外国関係会社が12月決算会社の場合、日本親会社の2025年4月1日~2026年3月31日事業年度において、(旧法であれば合算されていた)外国関係会社の2025年1月1日~2025年12月31日事業年度の所得を合算せず、外国会社のその年度の所得は日本親会社の翌事業年度(2026年4月1日~2027年3月31日事業年度)に合算する(1年遅れる)、ということになる。
そうすると、たとえば、外国関係会社の2024年1月1日~2024年12月31日事業年度については、旧法によって日本親会社の2024年4月1日~2025年3月31日事業年度に合算されることになるが、これを日本親会社の2025年4月1日~2026年3月31日事業年度に合算する(旧法よりも1年後ろにずらす)ことができる経過措置が講じられるようである。経過措置の対象となるのは、外国関係会社の2024年1月1日~2024年12月31日事業年度、2024年2月1日~2025年1月31日事業年度等である。合算年度に変更が生じる場合について、進行年度についても早期適用を認める(日本親会社における合算年度を後ろにずらすことの早期適用を認める)ということのように思われる(私見)。大綱では「できる」との表現になっており、詳細について注意が必要である(図表4参照)。
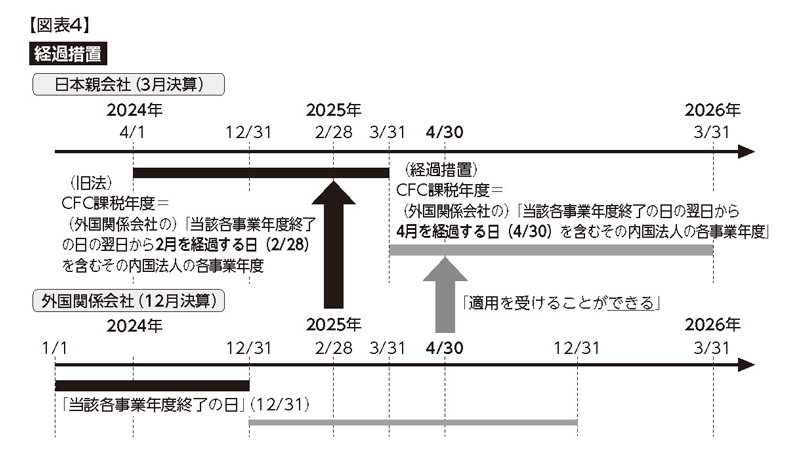
第3 グローバル・ミニマム課税:UTPRとQDMTTの実施は2026年4月から
1 グローバル・ミニマム課税の全体像
大綱において、第2の柱であるグローバル・ミニマム課税の実施に向けた取組みを進めるとされている(大綱14頁)。第2の柱に関しては、すでに、所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)が2024(令和6)年4月以降に実施され、総収入金額7.5億ユーロ以上(約1,200億円以上)の「特定多国籍企業グループ等」(脚注12)に対して適用されている(脚注13)。令和7年度税制改正では、軽課税所得ルール(UTPR: Undertaxed Profits Rule)と国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)の法制化が行われる。前者は「国際最低課税残余額に対する法人税」(大綱83~86頁)、後者は「国内最低課税額に対する法人税」という名称が与えられている(大綱86~93頁)。
日本に最終親会社を有する企業グループに対しては、基本的に所得合算ルールでミニマム課税が実現されるため、これらの規定が適用される場面は限定的であると思われる。これに対し、外国に最終親会社を有する企業グループにおいては、最終親会社所在地国においてグローバル・ミニマム課税を導入しない場合には、日本子会社において軽課税所得ルールの適用の可能性が生じるので、検討が必要である。
なお、UTPRもQDMTTも適用時期は対象企業の準備期間を確保する観点から法人の2026(令和8)年4月1日以後に開始する対象会計年度からとされており、時間的余裕はある。その申告・納付は、対象会計年度終了の日の1年3月(一定の場合1年6月)後であり、2026(令和8)年4月1日~2027(令和9)年3月31日会計年度については申告・納付は2028(令和10)年6月以降となる。3年半後である。
2 国際最低課税「残余額」に対する法人税=軽課税所得ルール(UTPR: Undertaxed Profits Rule)
(1)国際最低課税「残余額」に対する法人税(UTPR)の仕組み
グローバル・ミニマム課税は、国単位でみて実効税率15%(基準税率)を下回る国(以下「軽課税国」という。)がある場合、その国の実効税率を15%に引き上げる制度である。そのために、15%に満たない部分の「上乗せ税率」によって、軽課税国に所在するグループ会社(構成会社等)について「上乗せ税額」を算出し、その「上乗せ税額」を親会社(最終親会社又は中間親会社)にて課税する。これが所得合算ルール(IIR)である。
しかし、所得合算ルールだけではこの仕組みが機能しない場合がある。たとえば、軽課税国に所在するグループ会社の親会社の所在する国が所得合算ルールを実施していない場合である。この場合、親会社には課税できないことから、兄弟会社や子会社に対して代替的に課税を行う。これが、国際最低課税「残余額」に対する法人税=軽課税所得ルール(UTPR)である。所得合算ルールで課税されずに残っているので「残余額」という。軽課税所得ルールは本来的な制度である所得合算ルールを補完する「バックストップ」と位置付けられている。典型的には下記の図表5のような場合が考えられる。
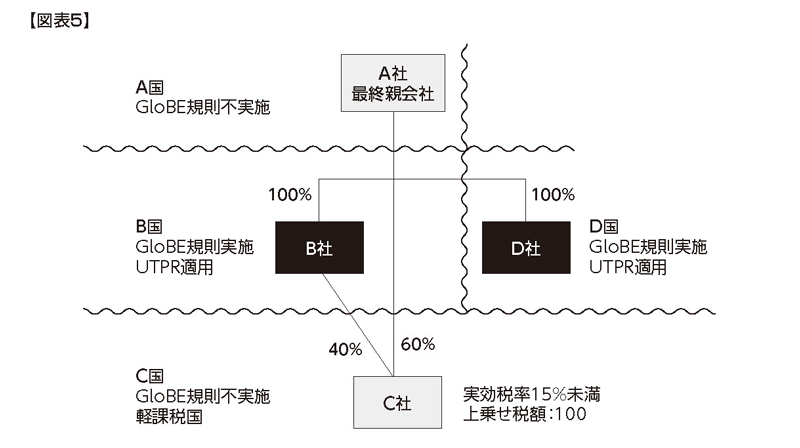
図表5において、C国にはC社のみが所在し、その実効税率は15%未満で、15%までの不足分の租税額(上乗せ税額)が100である。所得合算ルールでは親会社(最終親会社)A社がこの上乗せ税額100の課税を受けるが(脚注14)、A社が所在するA国がグローバル・ミニマム課税を実施する規則(以下「GloBE規則」という。)を実施していない場合、A国では課税できない。そこで、グループ(特定多国籍企業グループ等)に属する兄弟会社又は子会社で、その所在国のうち軽課税所得ルールを実施している国で課税を行う。図表5では、B国とD国が軽課税所得ルールを実施していることから、B社とD社に対して、軽課税所得ルールが適用される。
C社に対する上乗せ税額100について、B国とD国では、それぞれの従業員等の数(重み付け50%)と有形資産の額(重み付け50%)の割合によって按分して配分し、課税を行う。
(2)日本企業(最終親会社が日本に所在する企業)に軽課税所得ルール(UTPR)の適用の余地はあるか?
日本は所得合算ルール(IIR)を実施しているため、最終親会社が日本に所在する企業には所得合算ルールが適用され、軽課税所得ルールが適用される場面はあまりないのではないかと思われる。
軽課税所得ルールについては改正法案が公表された段階で、その詳細を検討する必要があることにご留意いただきたい(脚注15)。
(3)青色申告の対象外
軽課税所得ルール(下記の国内ミニマム課税も同じ)について「青色申告制度の対象外とする。ただし、更正の理由付記の対象とし、推計課税の対象外とする。」とされている(大綱85、91頁)。青色申告は法人税法上の欠損金の繰越控除・繰戻還付や少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却などの利益を受ける条件となっている(脚注16)。軽課税所得ルールや国内ミニマム課税が青色申告制度の対象外ということになると、たとえば、軽課税所得ルールに関する帳簿の記録不備や申告書の提出期限内不提出により、青色申告の承認が取り消されて上記のような利益が失われるということがなくなるのではないかと思われる(私見)(脚注17)。この点は安心材料である。
(4)米国企業(最終親会社が米国に所在する企業)に軽課税所得ルールの適用の余地はあるか?
米国では連邦法人税の原則的な税率が低く(21%)、非課税所得や(一定の)税額控除によっては、多国籍企業グループの米国における実効税率が15%を下回る可能性は相応にある。最終親会社が米国に所在する企業(米国企業)において、米国での実効税率が15%を下回った場合に子会社に対して他国が軽課税所得ルール(UTPR)に基づいて課税を行うことについて、米国共和党は強く反発していた。このため2023(令和5)年7月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において経過措置が合意され、最終親会社の所在地国における名目的な法人税率が20%以上である場合、当該最終親会社における上乗せ税額はゼロとすることとされ、当面米国企業が軽課税所得ルールに基づいて課税を受けることはなくなった(経過的UTPRセーフ・ハーバー)。
経過的UTPRセーフ・ハーバーは、2025(令和7)年12月31日以前に開始し、2026(令和8)年12月31日より前に終了する対象会計年度に適用される。上記セーフ・ハーバーが失効する前にOECDと米国政府との間で一定の合意がなされることが期待されるところだが、見通しは不透明である。
(5)軽課税所得ルール(UTPR)は発動されるか?
軽課税所得ルールは、課税対象となる所得が生じた法人(構成会社等)が所在しない国で課税が行われ、課税対象(所得)と国との結び付き(ネクサス)が希薄であることから、国際法上違法でないかとの指摘がある(脚注18)。また、トランプ政権は、米国企業に対して他国が軽課税所得ルールを適用することに強く反発する可能性があり、そのリスクを冒して他国が軽課税所得ルールを適用するのか、疑問を呈する見解もある(脚注19)。
我が国の軽課税所得ルールの適用は2026(令和8)年4月以降であり、1年の猶予があるが、その間のトランプ政権の動向と世界各国の対応を注視する必要がある。
3 国内最低課税額に対する法人税=国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)
(1)国内最低課税額=国内ミニマム課税(QDMTT)の仕組み
日本においても国内ミニマム課税が導入される。これにより、特定多国籍グループ等に関し、その日本におけるグループ会社(構成会社等)の合算した実効税率が15%(基準税率)を下回る場合、15%に満たない部分について日本国内で課税が行われる。この結果、当該グループの日本における実効税率は15%に到達することになり、グローバル・ミニマム課税の目的が達成される。GloBE規則を導入する国の多くが同様の国内ミニマム課税(QDMTT)を導入する方針であり、法人税率引下げへの「底辺への競争」が底上げされる(少なくとも15%は課税される)ことから、外国からの投資誘致を図る国(いわゆる新興国、投資ハブ国)においても一定の税収が確保されることになる。
(2)国内ミニマム課税(QDMTT)の計算方法(図表6参照)
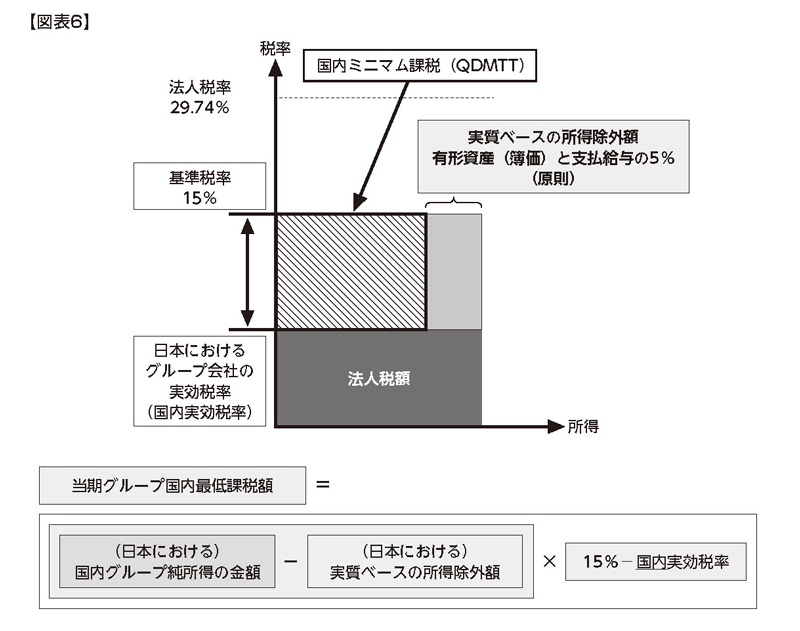
上記の「当期グループ国内最低課税額」は、日本国内におけるグループ会社(構成会社等)に対して課されるミニマム課税の総額であり、これを日本における構成会社等に配分する。その配分は「内国法人の寄与の程度」を勘案して計算される割合に応じてなされる(大綱88頁)。「寄与の程度」は、構成会社等の純所得の金額に比例するものではないかと思われるが(私見)、大綱には記載がない。
(3)日本企業への影響
我が国の法人税率の標準が約30%であることを考えると、実効税率が15%を下回るのは、政策減税による税額控除を多額に得た場合などかなり限定的ではないかと思われる。また、仮にそのような場合であっても、国内ミニマム課税によって日本で課税されることになり、他国での課税を避けられるという意味では、日本に所在する企業にとって安心できるといえる。
第4 外国人旅行者向け消費税免税制度(免税店)の見直し
外国からの旅行者が、輸出物品販売場(以下「免税店」という。)で行う日用品などの買い物については消費税が免除されている(脚注20)。しかし、近年、外国人が免税店で消費税を課されずに「爆買い」を行い、それを転売していたことが問題となった。
そもそも消費税は、仕向地主義を採用しており、消費地のみで課税する。このため、国境を越える貨物取引については輸出国では課税せず、輸出時に消費税を排除することとされており(輸出免税(脚注21)。前段階で受領した消費税の還付を認める。)、免税店もこれと同様の考えに基づく。とはいえ、旅行者は最終消費者であり、外国で消費税(付加価値税)が課されることはないから、外国で輸入されるときにその外国で消費税(付加価値税)が課される輸出貨物とは異なり、無限定に免税を認めるのは適当ではない。また、国内での転売がなされると、転売者は消費税抜きで購入した商品を消費税込みで販売して消費税分だけ利ざやを稼ぐことができる。たとえば、免税店で購入した者が税抜き価格の5%を上乗せして転売したとすれば、転売者は税抜き価格の5%分を国庫から得たのと同じであり、制度の趣旨に反する。このため、現行法でも免税店で販売された商品について、購入者は国内での転売が禁止されている。実務上は、購入者が免税店において転売目的で購入し、「輸出するため」の譲渡でないにもかかわらず免税店が免税取引として取り扱った場合には、免税の条件を満たしていないとして、免税店が追徴課税を受ける場合もある。しかし、購入者が転売目的であるかを免税店に判断させるのは負担が大きい。
そこで、令和7年度税制改正では、不正対策のための改正がなされる。これと同時に、旅行者・免税店双方にとって利用しやすい制度とするために免税店の負担を軽減しており、訪日外国人によるインバウンド消費を拡大することも意図されている(大綱77~79頁)。
1.免税「方式」の見直し:返金(リファンド)方式の導入
従来は、免税店では販売時に消費税抜きの価格で販売していた。改正後は、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に国外への持出しが確認された場合に免税店から購入者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる。
購入者は、購入した免税対象物品について、出国時にパスポート等を提示して税関での確認を受け、その確認を受けた免税対象物品を国外に持ち出さなければならない。
2.免税「対象物品」の範囲の見直し:免税か否かの判断を容易に
対象物品について、消耗品について購入者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装(封印付き半透明袋等)を廃止し、かつ一般物品と消耗品の区分を廃止する。これにより免税店の事務負担が緩和され、免税手続が円滑になる。
免税の対象として日用品(通常生活の用に供する物品)の要件を廃止する。これにより、免税店は日用品か否かの判断が不要となり、税務リスクを免れる。なお、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品については、免税販売の対象外として個別に定める。
3.免税「販売手続」の見直し:手続の円滑化と情報提供の仕組み
① 免税販売手続においては、上陸許可書及びパスポートの提示を求め、免税店はパスポート番号に基づき購入記録情報(免税販売データ)を国税庁(免税販売管理システム)に提供する。
② 日本国籍を有する購入者は国内に2年以上住所等を有しないことの要件が必要であるが、その証明書類に個人番号カードを追加する。免税店は、証明書類の種類及び出国日を購入記録情報として国税庁に送信する。
③ 100万円(税抜き)以上の商品については、購入記録情報の送信事項にその商品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加える。
④ 購入者が免税店で運送契約を締結し、かつ、その場で物品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式については、輸出免税制度により消費税を免除することができることとする。
⑤ 購入者が免税店で購入した免税対象物品について、その購入者が別途、免税店以外の場所から国外へ配送する、いわゆる「別送」をした場合、配送等に係る書類により輸出したことを確認する取扱いを廃止する。つまり、「別送」による免税を認めない。
4.免税店の「許可」要件の見直し:購入記録の確保
免税店(輸出物品販売場)の許可については、適切に購入記録情報及び税関確認情報を授受できることを要件とする。
5.適用時期
2026(令和8)年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。但し、上記3.⑤の「別送」に関する取扱いは、2025(令和7)年3月31日をもって廃止する。
第5 (参考)「物品販売」に対する消費税のプラットフォーム課税
「物品販売」に係る国境を越えた電子商取引について、「国外事業者による消費税の無申告」や「少額輸入貨物に対する免税」について、今後検討を行うとされている(大綱16頁)。つまり、今年度の改正はなく、来年度以降の改正が検討される。
プラットフォームに関しては、既に「電気通信利用役務の提供」について令和6年度税制改正においてプラットフォーム課税が導入されており、本2025(令和7)年4月1日から施行される(脚注22)。そのプラットフォーム課税は、デジタルプラットフォーム(アプリストアやオンラインモールなど)を介して行われる個々の(国外)サプライヤーによる消費者への「デジタルコンテンツ提供」(オンラインゲーム等)であり、「物品販売」は含まれていない。また、当該プラットフォーム課税の対象となり、国外サプライヤーに代わって納税義務を負うプラットフォーム事業者は、取引高50億円を超える大規模プラットフォーム事業者に限られている。
今後導入が検討されるのは以上と異なり、「物品販売」に関するプラットフォーム事業者(いわゆるマーケットプレイスの運営者)に対する課税である。立法に際しては、対象とするプラットフォームの線引きをどうするか(取引高の大小)、少額輸入免税制度(脚注23)を見直すか(免税点を引き下げるか)が論点になると思われる(脚注24)。これらの点は、電気通信利用役務の提供に関するプラットフォーム課税と同じとは限らないので、今後の動向に注意する必要がある。
第6 最後に
喫緊の検討課題としては、以下の点が重要である。
まず、移転価格税制に関する利益Bは、相手国が利益B対象国である場合には、本年における取引(国外関連取引)から適用がありうる。相手国が利益B対象国であるか否かを確認し、さらにそれ以外の国でも利益Bを導入していないかの確認が必要である。
次に、CFC税制については、日本親会社と外国関係会社の事業年度が異なる場合には、合算年度について経過措置を含めてよく確認する必要がある。
このほかの改正は、比較的時間があるので、情報を収集しつつ、落ち着いた対応をすることが可能であろう。
脚注
1 https://www.jimin.jp/news/policy/209630.html
2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/oecd/tp/2024.htm
3 2024年6月公表「利益B追加ガイダンス」、2024年9月公表「簡素化・合理化アプローチの適用に関する権限ある当局間のモデル協定」参照。
https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/transfer-pricing/pillar-one-amount-b.html
4 原文は"members of the IF commit to respect the outcome determined under the simplified and streamlined approach to in-scope transactions where such approach is applied by a covered jurisdiction"とされている。この"simplified and streamlined approach"(「簡素化・合理化アプローチ」)が利益Bで定められる独立企業間価格の簡易な算定方法である。
5 2024年6月17日公表「包摂的枠組みの利益Bに関する政治的コミットメントにおける、対象国の定義に関する声明」パラ4参照。https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/transfer-pricing/pillar-one-amount-b.html
6 https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-25-04.pdf
7 南繁樹「デジタル課税.主権国家間の『協調の体系』形成への試み」(ジュリスト2022年2月号21頁)参照。
8 多国間条約は各国に割り当てられたポイント(合計999ポイント)のうち、合計600に相当する締約国の批准が発効条件とされているが、米国が486ポイント、それ以外の国が513ポイントが割り当てられているので、米国が批准しない限り発効しない。多国間条約案48条参照。
9 非居住者による人的役務の提供は「国内において行う勤務その他の人的役務の提供」に限り、我が国で課税される(所法161条1項12号イ、164条2項2号、169条、170条、172条1項、212条1項、213条1項)。
10 措法66条の6第1項。
11 措法66条の6第11項、措規22条の11第48項。
12 グローバル・ミニマム課税の対象となるのは、全世界での総収入金額(売上高)が7.5億ユーロ以上(直前の4対象会計年度中の2年度以上)である多国籍企業グループであり、これを「特定多国籍企業グループ等」という(法法82四)。
13 法法82条以下。
14 所得合算ルールでは、親会社A社に対して課税される額は、C社のA社に対する帰属割合(合算比率)100%に相当する100となる。法法82条の2第1項1号イ等、GloBE規則2.1.1条、2.2.1条。
15 所得合算ルールの適用範囲と軽課税所得ルールの適用範囲の整合性については、南繁樹「『第2の柱 グローバル・ミニマム課税』コメンタリーの重要ポイント(上)」月刊国際税務2022年6月号26頁以下、同「軽課税所得ルール(UTPR)の仕組みと議論の動向について(3)」月刊国際税務2024年6月号92頁以下参照。
16 法法57条1項、58条1項、80条、措法67条の5参照。
17 法法127条1項参照。
18 この点の詳細については、南繁樹「軽課税所得ルール(UTPR)の仕組みと議論の動向について」月刊国際税務2024年3月号44頁、4月号44頁、5月号90頁参照。
19 2024年11月10日Financial Times
20 消法8条1項、消令18条。
21 消法7条1項。
22 消法15条の2、令6改正法附則13。
23 課税価格の合計額が1万円以下(個人的使用の場合は海外小売価格16,666円以下)の物品の輸入については、関税及び消費税が免税されている(関税定率法14条18号、4条の6第2項、輸入品徴収法13条1項1号、関税定率法基本通達4の6−2(3))。
24 2024(令和6)年11月13日税制調査会・経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合「資料1−1」参照。
南 繁樹 (みなみ しげき)
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士、東京弁護士会:1997年登録(49期)
E-mail: shigeki_minami@noandt.com
1994年東京大学法学部卒業。1997年弁護士登録(東京弁護士会)。2002年 New York University School of Law卒業(LL.M in Corporate Law)、2003年 New York University School of Law卒業(LL.M. in Tax Law)。主な業務分野は、M&A取引と税務。特に、移転価格、組織再編税制、個人資産家の資産運用、法人税一般に関する税務調査・審査請求・訴訟経験多数。東京大学非常勤講師、経済産業研究所「これからの法人に対する課税の方向性」プロジェクトメンバー、経済産業省 最低税率課税制度の国内法化に向けた論点勉強会委員、2016−2018年International Fiscal Association(国際租税協会)Asia Pacific, Chair。日本経済新聞社「企業法務税務・弁護士調査」の2024年に活躍した弁護士ランキングにおいて選定される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























