解説記事2025年01月27日 巻頭特集 令和7年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント−成長型経済への移行に向けて(2025年1月27日号・№1060)
巻頭特集
令和7年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント
−成長型経済への移行に向けて
一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦/長基公則/瀧沢 颯
令和7年度税制改正の議論については、先の衆議院選挙により自由民主党・公明党が少数与党となったことを受け、与党の税制調査会と並行して、国民民主党を含めた3党で税制協議を行うという異例のプロセスで進められた。しかし、いわゆる「103万円の壁」の引上げ幅等について合意には至らず、結果としては、3党での合意を経ないまま、例年より1週間程度遅れる形で、昨年12月20日に与党税制改正大綱が取りまとめられることとなった。
令和7年度税制改正では、デフレからの脱却が見えてきた中で、物価に負けない賃上げの定着を図るとともに、少子高齢化・人口減少への対応、安全保障の強化など、わが国が直面する諸課題に取り組む必要があるという認識の下、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行に向けた措置が講じられた。
本稿では、主要な改正事項等を概観するとともに、令和8年度税制改正についても展望していく。なお、本稿の記載事項は、令和7年1月16日時点の情報に基づいており、今後法令等により変更が生じうる。全ては筆者個人の見解であり、所属組織を代表したものではないことを予めお断りしておく。
Ⅰ.主要改正事項の解説
1 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、令和5年度税制改正大綱において枠組みが決定されたが、施行時期や法人税の付加税率の水準などの決定はその後の政治プロセスに委ねられることとなった。
令和6年度税制改正では、所得税等の定額減税との整合性などを踏まえ、施行時期等の決定は見送られた。税制改正法の附則において「令和5年度税制改正の大綱及び(中略)令和6年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和9年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずる」と記載され、検討事項とされた。
こうした中で迎えた令和7年度改正では、決定をこれ以上先送りすると、「令和9年度において、1兆円強を確保する」という令和5年度大綱での方針が実現困難になる可能性があるという問題意識の下、議論が行われた。その結果、法人税、たばこ税に係る措置については令和8年度から実施することが決定されたが、一方で、所得税に係る措置は、開始時期の決定が来年以降に先送りされることとなった。
(1)法人税
法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として「防衛特別法人税」(仮称)が課され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、当面の間、適用されることとなった。中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額は、基準法人税額(所得税額控除、外国税額控除等を適用する前の法人税額)から基礎控除額(500万円)を控除した金額となる。
付加税率の水準については、令和5年度大綱の枠組みでは「4~4.5%」と幅を持って示されていたが、企業による国内投資の拡大、賃金引上げの取組みへの配慮から、最小限の4%に抑えられたものと考えられる。法人実効税率は、現行の29.74%に0.9%程度上乗せされ、30.64%となる。政府税制改正大綱(令和6年12月27日閣議決定)によると、当措置により平年度ベースで約7,710億円の税収が確保される見込みである。
(2)所得税
所得税に係る措置については、当初は令和9年1月から実施する案が示されていたが、いわゆる「103万円の壁」の引上げに関する議論が行われている状況や、その動向次第では所得税収の見通しが不透明になる中で、復興財源を着実に確保していく観点を踏まえ、来年以降に決定を先送りすることとなった。与党大綱では「令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえつつ、いわゆる「103万円の壁」の引上げ等の状況も勘案しながら、引き続き検討する」と記載された。
(3)たばこ税
たばこ税については、まず、加熱式たばこの課税方式の見直しを2段階(令和8年4月、同年10月)で実施し、紙巻たばことの税負担差を解消することとなった。その上で、国のたばこ税率を1本当たり1.5円引き上げることとなった(令和9年4月、令和10年4月、令和11年4月にそれぞれ0.5円ずつ、3段階で引き上げ)。政府大綱によると、当措置により平年度ベースで約2,150億円の税収増が見込まれ、法人税の措置と合わせて、約9,860億円の税収が確保される見通しである。
2 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(1)議論の経過
昨年11月中旬から12月中旬にかけて計6回行われた自民党・公明党・国民民主党の3党の税制協議において最大の論点になったのは、所得税のいわゆる「103万円の壁」への対応である。
国民民主党は選挙公約の通り、手取りの増加や就業調整の抑制を図る観点から、平成7年からの最低賃金の上昇率(1.73倍)に基づき基礎控除等を178万円に引き上げることや、特定扶養控除に係る年収要件の引上げを要望した。他方で、同党の要望に沿って、仮に基礎控除を75万円引き上げた場合、国・地方合わせて7~8兆円程度の税収減が見込まれるという試算が政府から示され、地方自治体を中心に、地方財政への影響を懸念する声も高まった。こうした中、3党の税制協議において、具体的な引上げ幅のほか、地方税の取扱いなどについて議論が行われた。
12月11日には、令和6年度補正予算の衆議院での採決にあたり、3党の幹事長間において、「103万円の壁」については「国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる」ことが、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止とともに合意された。12月13日の5回目の税制協議においては、与党側から基礎控除と給与所得控除の最低保障額をそれぞれ10万円引き上げ、両者の合計を123万円にする案が示されたが、国民民主党側はそれでは不十分であるとし、改めて178万円への引上げを求めた。その後、12月17日の6回目の協議において、与党側からさらなる提案がなかったことを受け、国民民主党側から協議が打ち切られる形となり、最終的には、123万円に引き上げる案で与党大綱が取りまとめられることとなった。
ただ、与党大綱においても、12月11日の幹事長合意を引用した上で、「引き続き、真摯に協議を行っていく」としている。このため、今後、税制改正法案の国会審議の過程で、3党協議が再開され、法案の内容が修正される可能性もあると考えられる。
(2)改正の概要
① 所得税
(i)基礎控除・給与所得控除の引上げ
生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は、前回、基礎控除の引上げが行われた平成7年から直近の令和5年にかけ、20%程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、基礎控除について、現行の最高48万円から10万円(20%程度)引き上げ、最高58万円とすることとなった(図表1参照)。あわせて、控除額が逓減し始める合計所得金額は、現行の2,400万円から2,350万円に引き下げられる。
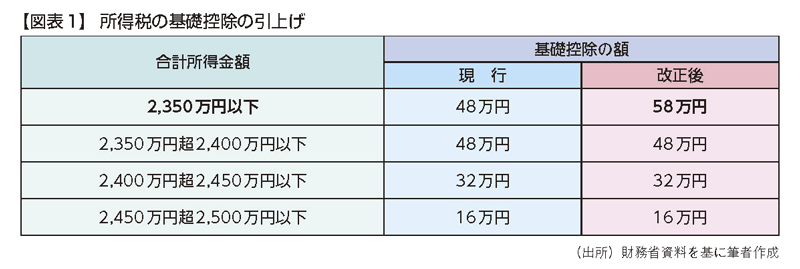
さらに、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除について、最低保障額を現行の55万円から10万円引き上げ、65万円とすることとなった(図表2参照)。これに伴い、給与収入190万円未満の個人については、給与所得控除額が増加することとなる。
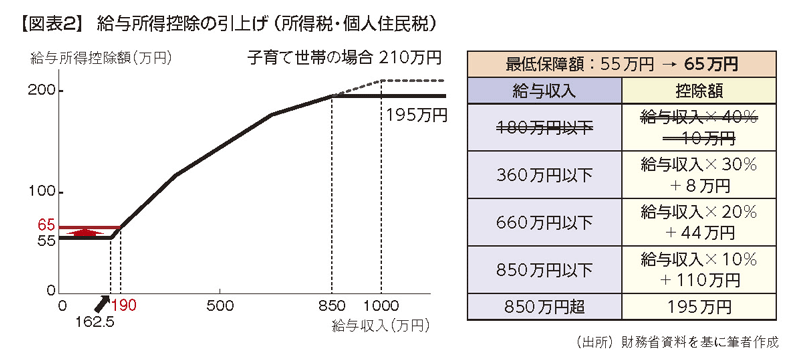
これらの見直しにより、所得税の課税最低限(社会保険料がない場合)は、現行の103万円(48万円+55万円)から123万円(58万円+65万円)に引き上げられることとなった。
(ii)扶養親族・同一生計配偶者に係る要件の見直し
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件(扶養者が扶養控除、配偶者控除を受けられるための被扶養者の所得の要件)についても、基礎控除の引上げに合わせ、現行の48万円(給与収入103万円)以下から、58万円(同123万円)以下に引き上げられる。
(ⅲ)特定親族特別控除の創設
現下の人手不足の状況において、大学生のアルバイトの就業調整に対応する観点から、国民民主党の要望を踏まえ、大学生年代の扶養控除についても見直しが行われた。
具体的には、19~22歳の大学生年代の子等の合計所得金額が58万円(給与収入123万円)超から85万円(同150万円)以下の場合は、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられる制度(「特定親族特別控除」(仮称))が創設される(図表3参照)。さらに、子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも、親等が受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みが導入される。
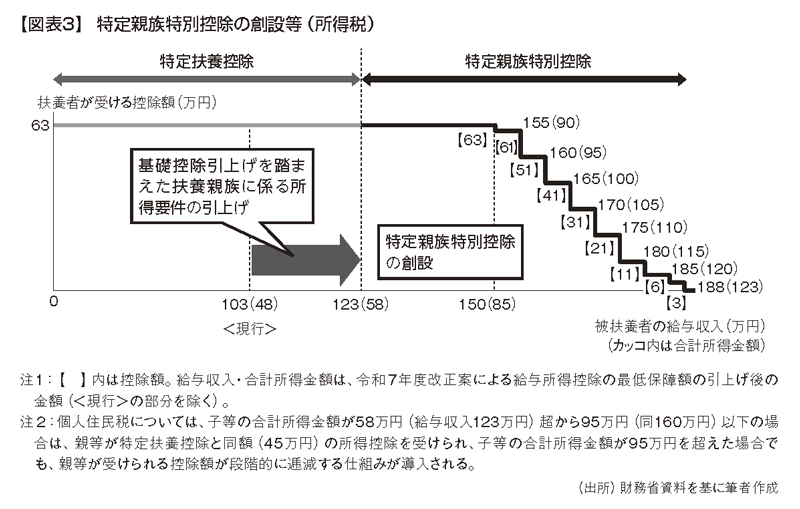
(ⅳ)施行時期
所得税に係る上記(i)~(iii)の見直しは、令和7年から適用され、同年分については年末調整での対応となる。
② 個人住民税
所得税の諸控除の見直しを踏まえ、個人住民税においても、給与所得控除の最低保障額の引上げ(55万円→65万円)、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げ(48万円以下→58万円以下)、特定親族特別控除(仮称)の創設が行われ、令和8年度分から適用される。
一方で、地方税財源への影響等を勘案し、個人住民税の基礎控除については、引上げは行わず、現行の額(最高43万円)を維持することとなった。
③ 税収への影響
政府大綱によると、これらの見直しに伴い、平年度ベースにおいて、所得税で約5,830億円、個人住民税で約750億円の税収減が見込まれる。財源については、与党大綱において、「デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が定額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないもの」と整理されている。
3 確定拠出年金の拠出限度額引上げ
勤務先の企業年金の有無等による拠出限度額の差異を解消する観点から、第2号被保険者(会社員等)について、iDeCo(個人型確定拠出年金)独自の拠出限度額(企業年金加入者の場合は月額2万円まで)を廃止し、企業年金と共通の限度額に一本化されることとなった。
その上で、公的年金を補完し老後に向けた資産形成を支援する観点から、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇を勘案し、共通の限度額について、現行の月額5.5万円から7,000円引き上げ、月額6.2万円とすることとなった(図表4参照)。また、第1号被保険者(個人事業主等)のiDeCoと国民年金基金の共通限度額についても、第2号被保険者との公平性の観点から、現行の月額6.8万円から7,000円引き上げ、月額7.5万円とされる。
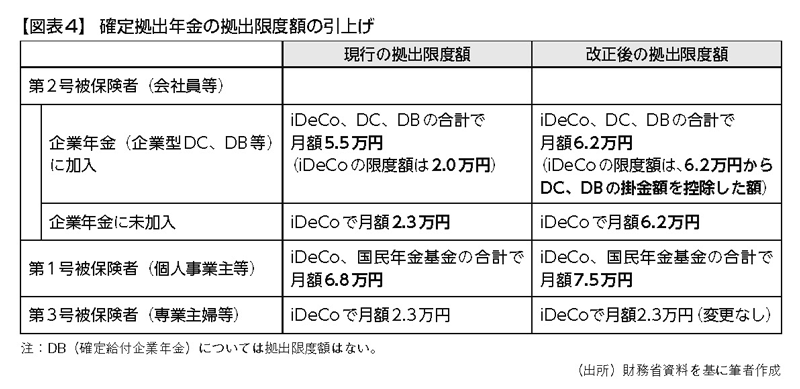
そのほか、企業型DC(企業型確定拠出年金)のマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止するなどの見直しも行われる。
4 子育て支援関連
(1)高校生年代の扶養控除
16~18歳の高校生年代の扶養控除については、児童手当の支給期間の高校生年代への延長を踏まえ、令和6年度与党大綱において、現行(所得税38万円、個人住民税33万円)から縮小し、所得税25万円、個人住民税12万円とする方向性が示され、令和7年度改正において結論を得るとされていた。
今回の議論において、公明党と国民民主党は子育て世帯の負担に配慮する観点から、現行の維持を主張した。最終的には、両党の意見を踏まえ、令和8年分の所得税及び令和9年度分の個人住民税については現行制度を維持することとし、児童手当をはじめとする子育て関連施策との関係等を踏まえつつ、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として、引き続き検討することとなった。
(2)子育て支援税制
令和6年度与党大綱において高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うとされた子育て支援税制については、「高校生年代の扶養控除の取扱いを踏まえて、あり方を検討することとなる」という前提の下、1年間の時限的な措置として対応されることとなった。
令和6年限りの措置として先行的に実施されていた子育て世帯等に対する住宅ローン減税の借入限度額等に係る措置、住宅リフォーム税制の拡充については、1年延長され、令和7年も引き続き実施されることとなった。
また、令和6年度与党大綱において方向性が示されていた子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充についても、予定通り実施されることとなった。具体的には、令和8年分の所得税において、一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置が講じられる。
5 エンジェル税制
エンジェル税制では、保有株式の譲渡益を元手としてスタートアップに再投資した際に、株式譲渡益を非課税とする措置が講じられている。しかし、本税制の適用を受けることができるのは、株式譲渡益の発生年に投資を行った場合に限られていたことから、十分に投資先を検討する時間が確保されていなかった。令和6年度税制改正では、本税制の適用を受けられる再投資の対象期間を延長するよう議論がなされたが、所得税の原則である暦年課税と対立することもあり、令和7年度税制改正に向けて引き続き検討されることとなっていた。今般、再投資期間の延長が認められる形で決着し、「繰戻し還付制度」が創設されることとなった。譲渡益発生年の翌年にスタートアップ投資を行った場合には、譲渡益発生年に遡って、投資額に相当する金額を譲渡益から控除することが可能となる。令和8年1月1日以降の再投資について適用される。
再投資期間の延長にあたっては、譲渡益に対する課税を翌年に繰延する仕組みも考えられるが、今回は、一旦課税された後に、要件を満たすことで還付を受けられる仕組みとなった。このような措置は、政策税制では珍しいものであるが、課税逃れを未然に抑制する観点が重視されたと考えられる。
なお、所得税の暦年課税の例外となる異例な措置であることも踏まえ、制度の健全な利用促進を図る必要があることから、再投資非課税措置については、株式を取得した年の翌年末までに当該株式を売却した場合には課税を行うこととされている。
6 中小企業税制
(1)中小企業経営強化税制等
中小企業経営強化税制について、売上高100億円超を目指す中小企業に係る拡充措置等を講じた上で、適用期限が2年延長された。売上高100億円を超えるような中小企業(100億企業)が、輸出や海外展開等によって外需を取り込み、域内調達によって地域経済に新たな需要を創出する存在であるという認識に基づいて、「100億企業」を目指す中小企業に対して、大規模な設備投資を後押しすることとなった。
具体的には、既存の「収益力強化設備」の類型に要件を上乗せした「経営規模拡大設備」の類型が新設された。「投資利益率が年平均7%以上」、「売上高成長率年平均10%以上を目指す」等の経営規模の拡大に係る要件を満たす場合には、本税制の対象設備の中に建物が追加されることとなる。
他方で、「収益力強化設備」の類型において、投資収益率の要件が年平均7%以上(現行:5%以上)に引き上げられたほか、「デジタル化設備」の類型が廃止された。
なお、中小企業投資促進税制については、大きな見直しを行わずに、適用期限が2年延長された。
(2)中小企業の法人税率の特例
中小企業者等の法人税率に関して、年間800万円以下の所得金額に対する税率を19%から15%に軽減する措置については、適用期限が2年延長された。当局からは、本特例がリーマン・ショックの際に経済対策として講じられたという背景等を踏まえて、厳しく見直しを行うべきだという見方が示されていた。しかし、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、現行の特例を延長しつつ、次に期限切れを迎える2年後に改めて検討されることとなった。ただし、所得10億円超の中小法人等については、税率が17%に引き上げられるとともに、通算法人は特例措置の対象から除外された。
(3)事業承継税制における役員就任要件等の見直し
法人版事業承継税制における役員就任要件について、現行では、株式贈与日に後継者が役員に就任後3年以上経過している必要があるところ、贈与の直前に役員に就任していればよいものとされた。あわせて、個人版事業承継税制における事業従事要件についても見直しが行われる。
なお、与党税制改正大綱では、本措置は極めて異例の時限措置であることから、適用期限(令和9年12月末)は今後とも延長しないことが、令和6年度に引き続き明記された。他方で、事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討することとされた。
7 地方創生関係
(1)地域未来投資促進税制
地域未来投資促進税制について、各地方自治体が設定する重点分野への設備投資を後押しするため、「高成長投資枠」に対する新たな類型の追加等を行った上で、適用期限が3年延長されることとなった。各地方自治体が設定する重点分野としては、日本標準産業分類上の中分類ベースで3つまで指定することができる。今回の上乗せ類型の活用が想定される事例としては、熊本県の半導体関連産業や、富山県の製薬関連産業が挙げられる。
他方で、通常類型においては、設備投資総額が前年度減価償却費の25%以上(現行:20%以上)、かつ、1億円以上(現行:2,000万円以上)であることが要件とされたほか、機械装置・器具備品の特別償却率が35%(現行:40%)に引き下げられることとなった。
(2)企業版ふるさと納税
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)については、適用期限が延長されることとなった。ただし、地方自治体が寄付をした企業に便宜供与を行う不適切事案が発生したことを踏まえ、寄付活用事業の監督機能の強化や透明性の向上のために必要な見直しを行い、その効果検証を行うために、適用期限は5年間から3年間に短縮された。
経済界からは、本社所在地の自治体への寄付も対象とするよう検討すべきという意見が出されていたが、上記のような事案が生じている状況も踏まえて、今回の改正では見送られることとなった。
8 自動車関係諸税の総合的な見直し
自動車関係諸税については、「2050年カーボンニュートラル」目標の実現や、電気自動車をはじめとした多様な動力源の利用の広がり等、自動車を取り巻く大きな環境変化を踏まえて、中長期的な視点から議論・検討が進められる方向である。車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、令和8年度税制改正において結論が出される見通しとなっている。
なお、自由民主党、公明党及び国民民主党の幹事長間の合意(令和6年12月11日)では、いわゆる「ガソリンの暫定税率」を廃止することが既に明記された。具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進めることとされている。暫定税率の廃止にあたり、現行の本則税率が見直される可能性にも留意しつつ、協議の状況を注視していく必要がある。
9 納税環境整備
(1)電子帳簿等保存制度の見直し
当局においては、納税者による適正な申告を促し、事業者のコンプライアンス負担の軽減も図るためには、将来的に事業者が取引先等と相互に行うやり取りが可能な限りデジタルデータにより行われ、人の手を介さないで自動処理されることが重要であると考えられている。今般、このような「デジタルシームレス」な取引に対して、電子帳簿等保存制度を見直す形でインセンティブ措置が講じられることとなった。
電子帳簿等保存制度では、電子取引データの複製・改ざん行為が容易である等の特性に鑑みて、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税が10%加重されている。今回の見直しで、データの改ざん防止や適正な記帳のための要件を満たした電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為は、重加算税の10%加重の適用対象から除外される。当該措置の対象となる電子取引データの要件は、以下の通りである。
① データの送受信と保存を、訂正・削除の履歴が残るシステムやそもそも訂正・削除ができないシステムで行うこと。
② 電子取引データの金額を、訂正・削除を行った上で電子帳簿に記録することができないこと(又は訂正・削除の事実を確認できるようにしておくこと)。
③ 電子取引データ(請求書・納品書等の重要書類に相当するデータに限る)と電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと。
なお、これらの要件は個別の取引ごとに判定されるが、その前提として、デジタルインボイス(JP PINT)か金融機関等の決済データを、上記の①~③の要件を満たす形で保存することができるシステムを利用していることが求められている。個別の取引については、電子データ交換(EDI)等を用いて①~③の要件を充足していたとしても、本措置の対象に含まれる。
今回の見直しは、令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税に適用される。
(2)納税通知書等に係るeLTAX経由での送付
地方税のデジタル化については、総務省の「地方税における電子化の推進に関する検討会」で検討が進められてきた。その中で特に重点的に議論されてきたのが、地方税関係通知のデジタル化であった。検討会における関係者での議論の末、4税目(固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割)の納税通知書等について、その副本を電子的に送付できる仕組みが導入されることとなった。「納税通知書等」には、課税明細書、更正決定通知書、税額変更通知書も含まれている。令和7年度税制改正では、納税通知書等の電子的送付に向けた所要の法改正が行われることとなった。電子的送付の運用開始時期は、法人あての通知については令和9年4月から、個人あての通知については令和10年4月からの予定である。
なお、納税証明書についても、納税通知書等と同様にデジタル化が期待されている。納税証明書の交付は申請・納付・通知等の複数の要素から成り立っていることから、納税通知書等のデジタル化が実現したのちに、デジタル化が行われることとなる。
10 国際課税
国際課税においては、令和7年度税制改正で、グローバル・ミニマム課税への対応として、OECD・G20による包摂的枠組み(IF:Inclusive Framework)の2本の柱に関する国際合意を踏まえ、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)に対応した「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」および国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に対応した「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」が導入されるとともに、OECDの所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)に対応した「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」について、一部見直しが行われた。
また、外国子会社合算税制(CFC税制)においても第2の柱の導入等を踏まえた簡素化に資する見直しが行われた。
(1)各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(UTPR)
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税は、最終親会社の所在地国においてIIRもしくはQDMTTが法制化されていない場合に、バックストップとして課税を及ぼすための措置として位置づけられるものである。このため、日本に最終親会社がある法人は、基本的にまず所得合算ルールおよび国内ミニマム課税の適用を検討することとなり、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の課税対象とはならないと考えられる。
なお、実際の国際最低課税残余額の計算にあたっては、課税対象となる軽課税国の税額に対し、UTPRを発動する国における構成会社の従業員数や有形資産の額を考慮して計算される。
また、対象についても限定されており、スタートアップなど、特定多国籍企業グループ等に該当後5年以内の場合や、国際的な事業活動の初期段階にある場合は、課税されない。
国際最低課税残余額に対する法人税は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用される。
(2)各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税(QDMTT)
同時に導入される各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税では、日本におけるグループ会社等の合算した法人実効税率が15%を下回る場合、その15%に満たない部分について課税が行われる。もっとも、日本国内の法人実効税率が約30%という高い水準にあることを踏まえれば、実際に実効税率が15%を下回るのは極めて限定された場合になると想定される。
この制度は、令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用される。また、制度の導入にあたっては、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税と同様に、収入金額等に関する適用免除基準や一定の国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準などが設けられる予定である。
(3)各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR)
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税では、2024年6月に公表されたOECDの第2の柱に関する実施ガイダンスを踏まえ、外国子会社合算税制等の対象とされる他の構成会社等に係る調整後対象租税額に含まれる金額等の計算において、その対象に法人税等調整額を加えるなどの見直しが行われた。
(4)外国子会社合算税制(CFC税制)
外国子会社合算税制について、合算時期を「事業年度終了の日の翌日から4月(現行:2月)を経過する日」に見直すとともに、株主資本等変動計算書等や勘定科目内訳明細書について、申告書への添付・保存を不要とすることが明確化された。
合算時期の見直しについては、与党税制改正大綱94頁の注1において、CFC税制の改正は「内国法人の令和7年4月1日以後に開始する事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の同年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用する」とされる一方、注2において、「内国法人の令和7年4月1日前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の令和6年12月1日から令和7年1月31日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)について、その外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含むその内国法人の同年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社合算税制の適用を受けることができる経過措置を講ずる」との注記がつけられている。これらの注記により、外国子会社の12月期の所得について、日本法人で合算する年度に違いが生じうるため、取り扱いには注意が必要である。
また、CFC税制のさらなる見直しについては、現在、経済産業省の「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方に関する研究会」において、合理的な経済活動の実体のある外国子会社の所得が課税対象となるケースが発生していることや、グローバル・ミニマム課税とCFC税制の両制度への対応が必要となり、コンプライアンスコストが大きく増加していることを踏まえ、CFC税制の適用対象となる租税回避行為の範囲やCFC税制の具体的な見直し案について検討が進められている。令和8年度税制改正に向けた議論の進展も引き続き注目される。
Ⅱ.今後の法人税のあり方
令和7年度与党大綱では、「第一 令和7年度税制改正の基本的考え方」の「1.成長型経済への移行」の中に、「(3)今後の法人税のあり方」という項目が設けられ、令和6年度与党大綱に引き続き、法人税のあり方に対する政府・与党の問題意識が記載され、将来的な法人税率引上げの可能性が示唆された。当項目を要約すると次の通りである。
・世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、わが国では2010年代に、設備投資や雇用・賃上げの促進、立地競争力の強化を図るため、法人税率を引き下げ。
・この間、経済界には、法人税改革の趣旨を踏まえ、国内投資の拡大や賃上げを求めてきたが、企業部門では、収益が拡大したにもかかわらず、現預金等が積み上がり続けた。
・今般、EBPM(Evidence Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)の観点からデータ分析等を行い、法人税改革の成果について議論。
・設備投資については、法人税改革以降、海外投資等が増加したのに対し、大企業を中心に国内投資は低水準で推移。賃上げについても、諸外国と比較して、長年低迷。他方、企業の利益が現預金として社内にとどまる傾向が一層強まってきた。
・こうした振り返りを踏まえれば、法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税のあり方を転換していかなければならない。
・大企業を中心に企業が国内投資や賃上げに機動的に取り組むよう、減税措置の実効性を高める観点からも、レベニュー・ニュートラルの観点からも、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、メリハリのある法人税体系を構築していく。
令和6年度与党大綱では「今後、法人税率の引上げも視野に入れた検討が必要」という記載であったが、今回は「法人税率を引き上げつつ」と、より踏み込んだ表現となっている。
また、政府税制調査会においても、令和6年6月に「税制のEBPMに関する専門家会合」が設置され、EBPMの観点から、近年の法人税改革の効果について議論が行われている。なお、同専門家会合の第2回(11月19日開催)では、経団連事務局もオブザーバー参加し、法人税改革実施後も国内投資や賃金引上げが進展し、税収も増加したことや、法人税率については国際的なイコールフッティングの観点が重要であることなどを意見表明している。
令和8年度以降の税制改正では、法人税率について具体的な議論が行われる可能性があるため、引き続き動向を注視していく必要があると考えている。
Ⅲ.令和8年度税制改正に向けた展望
次の令和8年度税制改正では、前述の通り、法人税率の引上げを含め、法人税のあり方が大きなテーマの1つになることが予想される。国内投資の拡大や賃金引上げを通じた成長と分配の好循環の実現に向け、どのような税制のあり方が望ましいのか、検討が求められる。
令和7年度末に適用期限を迎える主な租税特別措置としては、研究開発税制、オープンイノベーション促進税制などが挙げられるとともに、カーボンニュートラル投資促進税制の認定期間が令和7年度末に終了するなど、重要な項目が控えている。研究開発投資、設備投資の推進に向け、企業のニーズを十分に踏まえた対応が必要である。
住宅・土地税制については、住宅ローン減税の適用期限が令和7年末に到来するほか、長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例が令和7年度末で適用期限を迎える。住宅投資の促進や土地の利用転換の円滑化などの観点から、これらの措置について十分な検討が求められる。
このほか、自動車関係諸税については、車体課税に係る各種措置が令和8年3~4月に適用期限を迎える。こうした中、前述の通り、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しが行われる予定である。
また、私的年金税制については、企業年金等の積立金に係る特別法人税の課税停止措置が令和7年度末で適用期限を迎える。老後の資産形成に向けた私的年金制度の普及・促進を図る観点から、特別法人税については廃止を含めた検討が求められる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























