解説記事2025年03月03日 SCOPE 税制改正で社債を貸付金に、所得税の負担増加を回避と推認(2025年3月3日号・№1065)
審判所、消費貸借は経済的合理性を欠くと判断
税制改正で社債を貸付金に、所得税の負担増加を回避と推認
貸付利率が著しく低いとして同族会社の行為計算否認規定が適用されるかどうかが争われた裁決で、国税不服審判所は、貸付金は弁済期限を定めず、物的担保及び人的担保も付さずに著しく低利率で貸し付けたものであり、経済的合理性を有する取引であるとは認められないとし、請求人の請求を棄却した(大裁(所)令5第47号)。
今回の事案は、平成25年度税制改正により、同族会社が発行する社債に係る利子が分離課税から総合課税の対象となったことに端を発するもの。審判所からは、社債を貸付金に転換することで、所得税の負担増加を回避することを目的にしたものと推認されている。
多額の社債を償還し、その原資をそのまま貸付金に転換
本件は、承継前請求人らが、同族会社に対する金員の貸付けに係る利息を雑所得として所得税等の確定申告を行ったところ、原処分庁が当該貸付けにおける貸付利率が著しく低いとして同族会社の行為計算否認(所法157条1項)の規定を適用し、適正な貸付利率で受け取るべき利息を計算するなどして更正処分等を行ったことから、承継前請求人らが当該貸付けには経済的合理性があるとして、更正処分等の全部の取消しを求めたものである。
承継前請求人らは、同族会社に対して行っていた低利息貸付けについて、貸付金の原資は自己資金であり、定期預金利息相当の利息を得ていることから、貸付けは経済的合理性を有する取引であり、同族会社等の行為計算否認規定は適用されないなどと主張した。
承継前請求人らは、同族会社が発行した社債を保有し社債利息を得ていたが、平成27年11月に開催された取締役会決議に基づき、社債をすべて買入消却して合計78億円を償還した。その後、承継前請求人らは、社債の償還によって生じた償還金を原資として、金銭消費貸借契約に基づき、同社に貸し付けた。なお、同族会社は、本件金銭消費貸借について、帳簿上、承継前請求人らが社債を買入消却した際の償還金を未払金として計上すると同時に、償還に係る未払金を承継前承継人からの短期借入金に振り替える会計処理を行っており、社債の償還の際も、金銭消費貸借の貸付けの際も、承継前請求人らと同社との間において、現実の金員の移動はされていなかった。
この点について請求人らは、税制改正を契機として同族会社が自社の資産状況を確認した上で社債の全額償還を検討したものではあるものの、社債を保有する承継前請求人らの要望を踏まえ、いわば長期貸付金(社債)をいつでも引き出せる短期貸付金に変更したものであり、租税回避の意図をもって行ったことではないとしている。
平成28年1月から社債利子は総合課税に
同族会社が発行する社債から生じる利子については、平成25年度税制改正により、総合課税の対象に見直されている(平成28年1月1日以後に支払われる利子から適用)(図参照)。税制改正前は、利子所得として分離課税とされていたものだ。同族会社が役員給与に対する節税策として、発行が容易な少人数私募債を利用して役員給与に対する税率(累進課税)と社債利子に係る税率(20%)の差を利用した節税スキームが横行したことから規制がなされたものである。
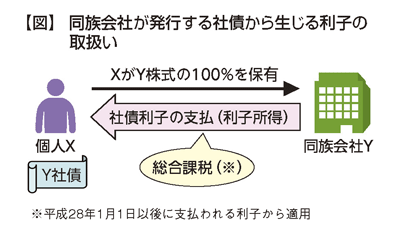
今回の事案は、この節税スキームが税制改正により社債に係る利子が分離課税から総合課税の対象となったことに伴い、承継前請求人らの所得税負担の増加が想定されたため、社債を貸付金に転換することで、承継前請求人らの所得税負担の増加を回避することを目的としたものといえ、審判所もこの点について推認している。
審判所、貸付利率は社債の年利率の比較でも著しく低いと指摘
審判所は、貸付けは承継前請求人らの自己資金を貸し付けたものではあるものの、承継前請求人らと同族会社との間の特殊な関係に基づき、社債の償還金及び未払金の合計額81億6,000万円もの多額の金員について弁済期限を定めず、物的担保及び人的担保も付さずに著しく低利率(貸出約定金利の約100分の1又は約500分の1)で貸し付けたものであり、経済的合理性を有する取引であるとは認められないとした。
また、金銭消費貸借における貸付利率は、貸出約定平均金利(新規貸出しかつ長期貸出しに係るもの)との比較においても、社債の年利率との比較においても、著しく低いものとなっていることからすると、金銭消費貸借に係る各契約は、承継前請求人らが同族会社から収受する利息の額を、同社から収受できたであろう利息相当額よりも減少させ、その結果、所得税の負担も減少させる結果となっていることは明らかであるとした。
貸出約定平均金利が相当
その上で審判所は、事業者が金員を借り入れる場合においては、取引のある銀行から借り入れるのが一般的と考えられることからすれば、独立当事者間で行われる標準的な金銭消費貸借において付されるべき利率は、事業者が銀行から金員を借り入れる際の利率を採用するのが合理的かつ相当であることからすると、本件金銭消費貸借について適用されるべき年利率は、国内銀行における貸出約定平均金利とするのが相当であるとし、原処分は適法であるとの判断を示した。
なお、審判所は、金銭消費貸借は税制改正によって承継前請求人らに新たに生ずることが予定されていた所得税の負担を回避することを主たる目的として行われたものであると推認し、所得税の負担増加を回避する以外に、正当で合理的な理由や目的があったとは認められないとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























